副業による残業の割増賃金はどこが支払う?【計算例あり】労働時間の通算ルールや計算方法を解説
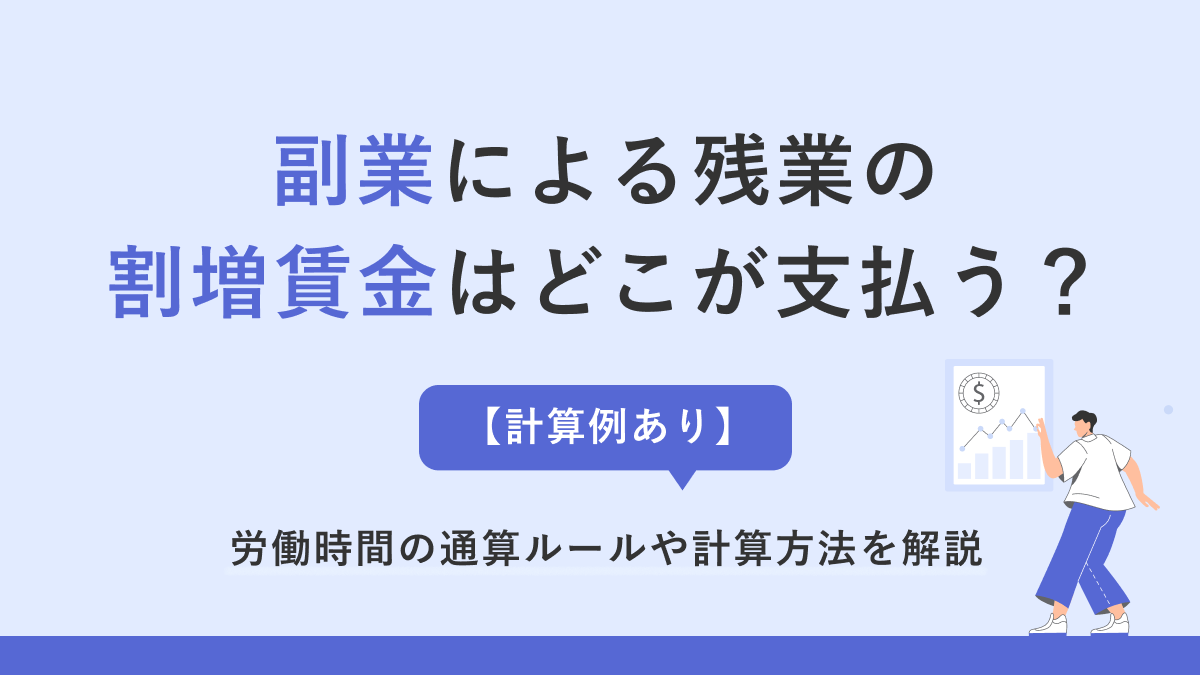
副業を認める企業が増えるなか、「法定労働時間を超えたら、割増賃金はどこが支払うのか」と疑問に思う方もいるでしょう。
副業が絡んだ割増賃金の支給ルールは少し複雑で、対応を誤ると未払い残業代の請求や労基署の是正勧告といったリスクにつながります。
本記事では、副業・ダブルワークにおける労働時間の通算ルールと割増賃金の支払い義務を、計算例を交えながらわかりやすく解説します。
→給与計算をミスなく速く|「One人事」の資料を無料ダウンロード
 目次[表示]
目次[表示]
副業(ダブルワーク)における割増賃金のルール
副業やダブルワークが一般的になった今、労働時間の通算と割増賃金の扱いを正しく理解することは、人事労務担当者にとって重要です。労働基準法第38条では、異なる事業場で働いていても、労働時間は合計(通算)して扱うと規定されています。
副業をする従業員の健康維持のためにも、通算ルールの適切な運用が欠かせません。通算という考え方について、詳しく解説していきます。
労働時間は本業と副業を通算する
本業と副業で働く場合、雇用契約に基づく勤務時間は合計して管理する必要があります。異なる事業場であっても労働時間を通算する労働基準法の条文があるためです。
たとえば、本業で1日6時間、副業で2時間勤務すれば、合計8時間です。さらに副業で1時間残業すれば、通算9時間となり、1時間に割増賃金が発生します。
副業者の労働時間は、たとえ他社であっても「まとめて見る」ことが、人事労務担当者に求められる対応です。
なお、労働時間の通算は雇用契約による勤務に限られます(管理監督者は除く)。フリーランスや経営・顧問など労基法が適用されない働き方には適用されません。
参照:『労働時間法制の具体的課題について③(副業・兼業)』厚生労働省
参考:『副業・兼業』厚生労働省

残業時間や割増賃金は通算結果で考える
本業と副業それぞれの労働時間が法定内であっても、通算した結果が法定労働時間を超えれば、割増賃金を支払う必要があります。法定労働時間は、1日8時間・週40時間以内です。
副業における割増率の判断や残業時間のカウントも、「通算後の労働時間」が基準となります。
たとえば時給1,500円の労働者が、本業で1日6時間、副業で3時間働いた場合、合計9時間となります。法定労働時間を1時間超えているため、 1,500円 × 1.25 × 1時間 = 1,875円 が残業代として支払われる計算です。
本業・副業どちらか一方の勤務時間だけ見ても、正しい判断はできません。必ず通算結果で残業代を算定しましょう。
副業・本業の労働時間を通算するルールは見直しが検討されている
現在、副業・兼業における労働時間通算ルールについて大きな見直しが議論されています。
厚生労働省の研究会は2024年12月、副業や兼業をする人の割増賃金について、通算管理による支給を廃止する案を示しました。企業の負担を減らし、副業・兼業に取り組みやすい環境を整備することが目的です。
現行制度では、企業側が本業と副業・兼業先の労働時間を何かしらの方法で管理しなければなりません。企業にとって重い事務負担となり、以前から副業・兼業の許可や受け入れを難しくしているという指摘がありました。
そのため、割増賃金支払いに関する通算ルールの廃止を含め、見直しの検討が進んでいます。
ただし、法改正が施行されるまでは時間がかかるため、本記事では現行の通算ルールを前提に副業における割増賃金の考え方を解説しています。
参照:『副業の割増賃金、労働時間通算ルール見直し 厚労省検討』日本経済新聞
参考:『令和6年度規制改革実施計画への対応状況等について(副業・兼業関係)』厚生労働省
参考:『労働基準関係法制研究会報告書(案)』(P47-49)厚生労働省
参考:『厚労省の労基法改正研究会、報告書案取りまとめへ議論 副業やテレワーク関連など』産経新聞(2024/12/24)

副業で残業が発生したら割増賃金はどこが支払う?
副業やダブルワークで労働時間が法定を超えた場合、どの企業が割増賃金を支払うのでしょうか。労働時間を通算したうえでの割増賃金の支払い責任には、明確な基準があります。原則と例外を正しく理解し、適切な労務管理につなげましょう。
(原則)あとから雇用契約を結んだ企業が支払う
副業による割増賃金は、「あとから労働契約を締結した会社」が支払うのが原則です。
労働契約を締結する際、使用者には労働者の副業・兼業の実態を確認する義務があります。
たとえば、先にA社(本業)と「1日8時間」の契約を結んだ従業員が、その後B社(副業)と「1日3時間」の契約を結んだ場合、B社での3時間はすべて時間外労働です。本業ですでに法定労働時間に達しているためです。
つまり、自社が先に契約していて、あとから従業員が副業を始めた場合は、通算結果後の時間外労働について、原則として自社に支払い義務はありません。
(例外)先に雇用契約を結んだ企業が割増賃金を支払うケースもある
先に労働契約を締結した会社(本業)でも、例外として割増賃金の支払い義務が発生することがあります。主な例は以下のとおりです。
| 通算で法定労働時間を超えると認識していながら勤務を延長したとき |
|---|
| A社と4時間契約→B社と4時間契約(通算8時間)。A社が1時間延長して5時間働かせた場合、通算9時間となり、A社に支払い義務が発生します。 |
| 副業を把握したうえで残業や休日出勤をさせたとき |
|---|
| 本業側が従業員の副業状況を把握していながら時間外労働をさせた場合、時間外労働によって法定労働時間を超過するなら、本業側に割増賃金の支払い義務が生じます。 |
| 副業先との雇用契約が先にあったとき |
|---|
| 副業先と先に短時間労働を契約し、その後本業と契約した場合は、本業側が「あとから契約した会社」になるため、本業側に割増賃金の支払い義務が生じます。 |
副業の割増賃金を「どちらが支払うべきか」で迷わないよう、契約順と勤務実態を把握し、未払いを防ぎましょう。
【計算例】副業(ダブルワーク)における割増賃金の計算方法
副業やダブルワークにおける割増賃金の計算は、通算した労働時間をもとに行います。次の2つのパターンについて具体的な計算例を紹介します。
- あとから雇用契約を結んだ企業が支払うケース
- 先に契約した企業が支払うケース
A社(あとから雇用契約を締結)が割増賃金を支払う場合
A社があとから雇用契約を締結した場合、本業であるB社の労働時間と通算して法定労働時間を超えると、A社は割増賃金を支払う義務を負います。
太郎さんは、先にB社(本業)と「時給1,200円/平日週5日/9:00〜18:00の1日8時間勤務」で契約しています。
その後、副業先のA社は、B社との契約について申告を受けたうえで、「時給1,200円/平日週5日/19:00〜22:00の1日3時間勤務」で契約し、勤務を開始しました。
本業B社での1日あたりの労働時間が法定労働時間の8時間に達しているため、副業A社での労働はすべて法定時間外労働です。
太郎さんに支払われる、1日あたりの賃金は以下のとおりです。
- 本業B社(法定労働時間に達している)時給1,200円×8時間=9,600円
- 副業A社(すべて時間外労働)時給1,200円×1.25×3時間=4,500円
A社での勤務が22時を超え23時まで働くと、深夜労働として、さらに25%加算する必要があります。
- 1,200円 × 1.5 × 1時間 + 1,200円 × 1.25 × 3時間 = 6,300円
B社(先に雇用契約を締結)が割増賃金を支払う場合
B社が通算労働時間が法定を超えることを認識しながら、労働時間を延長した場合はB社にも割増賃金の支払い義務が生じます。
花子さんは、先にB社と「時給1,200円、平日週5日、9:00〜13:00の1日4時間勤務」で契約しています。その後、A社と「時給1,200円、平日週5日、15:00〜19:00の1日4時間勤務」で契約しました。
B社とA社の労働時間を通算しても週40時間で法定内です。
しかしB社が繁忙期のため、1日1時間の残業を命じ、花子さんは毎日B社で5時間、A社で4時間勤務することになりました。
B社とA社の1日あたりの労働時間を通算すると9時間となり、1日の法定労働時間の8時間を超えています。
B社が1時間残業させたことにより法定時間外労働が発生したため、B社が1時間の割増賃金の支払い義務を負います。
花子さんに支払われる、1日あたりの賃金は以下のとおりです。
- 本業B社(通算で法定労働時間を超えると認識):時給1,200円×4時間+時給1,200円×1.25×1時間=6,300円
- 副業A社:時給1,200円×4時間=4,800円
従業員が副業(ダブルワーク)をしている場合の注意点
副業やダブルワークを行う従業員が増える中、企業には労働時間管理や健康確保の観点から適切な対応が求められます。
法律で定められている異なる職場の労働時間通算ルールを怠ると、法令違反とみなされるため注意しなければなりません。しかし実際は、管理が煩雑で対応に苦慮されている方もいるでしょう。
労務トラブルを防ぐためにも、副業社員を抱える企業の管理者として、4つのポイントを紹介します。
- ほかの勤務先の労働時間を把握しておく
- 時間外労働の上限規制について理解する
- 従業員の健康にも配慮する
ほかの勤務先の労働時間を把握しておく
副業者の労働時間を正確に通算するには、ほかの勤務先での労働時間を把握する仕組みを構築しなければなりません。
厚生労働省が公表するガイドラインでは、管理の頻度は指定されていないため、必ずしも日単位で把握する必要はないとされています。
現実的には、次のような方法を組みあわせて運用する対応が考えられます。
- 副業届出制度を設ける
- 定期的な報告フォームを用意する
- 面談などで口頭確認する
- 報告は一定期間をまとめて申告する
- 所定労働時間内に収まった場合は申告不要とする
- 所定外労働があった場合のみ申告してもらう
- 時間外労働の上限規制に近づいた場合に申告する
副業の有無・内容を確認する社内制度を整えることはもちろん、報告の頻度や方法を柔軟に設定すると、現場の負担を減らせるでしょう。
また、使用者が適切に労務管理ができるよう、労働者側も各勤務先の労働時間をきちんと把握し、必要に応じてすみやかに報告する配慮が必要です。
参考:『副業・兼業の促進に関するガイドラインわかりやすい解説』厚生労働省

時間外労働の上限規制について理解する
時間外労働の上限規制については、事業場単位で適用されるため「通算」という考えがなくなります。本業と副業で「労働時間」は通算されても、「時間外労働時間」は通算されないのです。
ただし、健康管理の観点から、本業と副業の時間外労働間の合計が、以下の基準を超えてはいけないとされています。
- 単月で時間外労働と休日労働の合計が100時間未満である
- 複数月平均で時間外労働と休日労働の合計が80時間以内である
つまり「36協定の上限規制は通算しないが、健康基準は通算する」という違いを理解しておく必要があります。
36協定の上限時間を守っているつもりでも、健康基準を超えてしまう危険があるため注意して管理体制を整えましょう。
従業員の健康にも配慮する
副業やダブルワークをしていると、気づかないうちに長時間労働になってしまうこともあるでしょう。
割増賃金の計算と同じくらい、副業をしている従業員の健康管理も重要な課題です。
企業側の対応としては、以下のような取り組みが考えられます。
- 定期的な健康状態の確認
- 過重労働にならないよう労働時間の上限設定
- 健康管理に関する相談窓口の設置
副業・兼業を認めている場合は、従業員に自己管理を促すことも必要です。心身の不調を感じたら、ためらわず相談してほしいと伝え、一人ひとりの健康維持に努めましょう。
まとめ
副業やダブルワークでは、雇用契約に基づく勤務時間は本業と通算して管理します。
通算の結果、法定労働時間を超えた場合は、原則「あとから契約した会社」が割増賃金を支払いますが、状況によっては先に契約した会社にも義務が生じます。
労務管理の精度を保つには、勤怠管理システムの活用がおすすめです。正確な記録と集計、超過アラートにより、法令遵守と健康管理を両立できるでしょう。
適切な労働時間の管理に|One人事[勤怠]
One人事[勤怠]は、労働時間の管理効率化にお役立ていただける、クラウド型勤怠管理システムです。
One人事[給与]との連携により、実労働時間の集計から残業代の計算までをシームレスに運用できます。
One人事[勤怠]の初期費用や操作性については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門のスタッフが貴社の課題をていねいにお聞きしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、勤怠管理の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードしていただけます。勤怠管理をラクにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |
