入社式はいつ何する?【人事向け】式次第やユニーク事例、オンライン入社式の実施状況まで紹介

入社式は新入社員の門出となるイベントです。多くの企業が入社式の日に新しい仲間を迎え入れ、会社の理念や文化を伝える機会としての役割を果たします。
本記事では、人事担当者向けに入社式の具体的な内容や開催時期、式次第の構成、他社のユニークな事例、さらには近年増えているオンライン入社式の実施状況について紹介します。初めて入社式を準備する方や、より新入社員にとって魅力的な入社式を目指す方はお役立てください。

 目次
目次
入社式とは
入社式とは、新入社員が企業に正式に加入する際の式典です。新入社員は会社の一員として歓迎され、会社の規則や文化、ビジョンなどについて紹介されます。
入社式の主な目的
入社式には以下のような目的があります。
- 歓迎の意を示す
- 会社の文化と価値の紹介
- チームビルディング
- オリエンテーション
入社式は企業が新入社員を迎え、歓迎の意を示す場です。新入社員に「組織の一員」としての実感を持たせると同時に、入社2〜4年目の若手社員に「指導役」としての自覚を持たせる目的もあります。
また、入社式は新入社員にあらためて会社のミッションやビジョン、理念を強調して伝える機会でもあります。これにより、会社の存在意義や役割を理解し、新たな決意や社会人としての意識を高めてもらえるでしょう。
なかには、入社式当日に懇親会を設け、入社後のチームワークの形成につなげている企業もあります。
入社式はオリエンテーションとして機能し、就業規則などの確認したり、自社製品をあらためて説明したりするなど、今後自社の一員として働くうえで必要な情報を提供する目的もあります。

内定式との違い
一般的に入社日に実施する入社式と、内定が確定した段階で実施する内定式にはどのような違いがあるのでしょうか。
内定式とは、企業が採用選考を通過した学生や求職者に対して、正式に内定を通知するための式典やイベントです。
入社式と内定式には以下の違いがあります。
| 入社式 | 内定式 | |
|---|---|---|
| タイミング | 入社日 | 入社前、主に卒業前 |
| 主な開催日程 | 4月1日前後 | 10月1日以降 |
| 目的 | 新入社員の歓迎とオリエンテーション | 会社の紹介と内定者との関係強化 |
| 雇用契約 | 正式な雇用契約が成立 | 正式な雇用契約はまだ成立していない |
入社式と異なり内定式の目的は、企業のビジョンやミッションなどを紹介し、内定者との関係を深めることです。10月以降に実施されるのは、政府が定める就活のルールで、内定通知日を10月1日としているためです。この時点では、正式に雇用契約が成立していないため、学生は内定式後であっても辞退が可能です。
入社式はいつやる?
入社式は新年度の初日、4月1日前後に実施されるのが通例です。日本は4月が年度の区切りであるため、新年度の初日に実施されています。暦上4月1日が土日など休日の場合は、2日または3日に実施するのが一般的です。
なかには3月下旬に入社式を実施する企業もあり、通年採用で入社式を実施する企業の場合は、この限りではありません。
入社式では何をする? 一般的な式次第
初めて入社式の準備を担当する場合「入社式は何をするのか?」と悩まれている方もいるでしょう。企業・団体によって異なりますが、一般的に入社式は以下の式次第に沿って執り行われます。
| 1.開会の宣言 | 入社式の開始を宣言する 主催者や人事部の責任者が、式の目的と流れについて説明する |
|---|---|
| 2.役員の挨拶 | 会社の役員(社長や取締役など)が、新入社員へ挨拶する 例:歓迎の言葉や会社のMVVについて など |
| 3.入社辞令の交付 | 入社したことを証明する入社辞令を受領する 多くの場合は、取締役などから直接手渡しされる |
| 4.新入社員の決意表明 | 新入社員が一堂に会して、代表者が決意表明を行う 例:企業の規範を尊重し、最善を尽くすこと など |
| 5.部署紹介 | 新入社員が配属される部署の紹介をし、部長が挨拶をする |
| 6.記念撮影 | 新卒社員全員と社長で記念写真を撮影する |
| 7.閉会の宣言 | 入社式の終了を宣言する |
| 8.懇親会 | 入社式後、先輩や上司、同期の仲間と交流する |
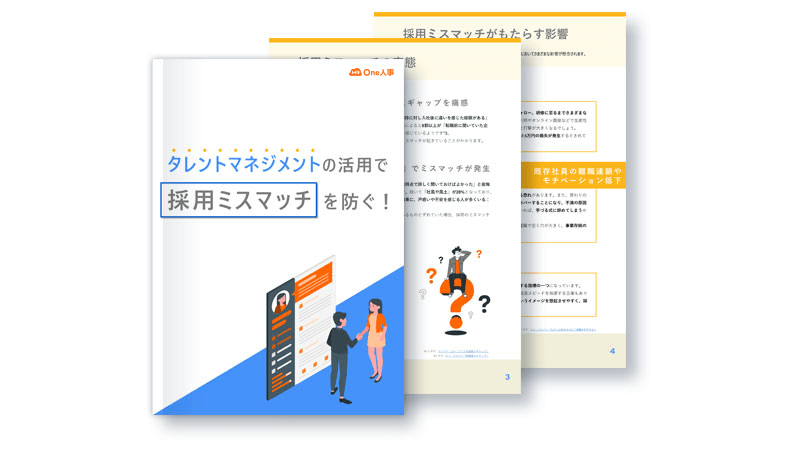
入社式までに担当者が準備しておくこと
入社式の準備を担当する方が、当日までに用意しておく実務や対応を紹介します。
- 日程の設定と通知
- 場所の予約
- 案内状の準備
- アジェンダの作成
- スピーチや挨拶の準備
- 部署やチームの紹介
- 講話やセミナーの調整
- 受付の準備
- 懇親会の準備
- リハーサル
日程の設定と通知
入社式の日程を早めに決定し、関連するすべての人(新入社員、管理職、人事担当者など)に通知します。新入社員には入社式の日程、場所、時間、持ち物、服装などの詳細情報を通知します。
管理職や人事担当者、そして参加するほかの部署のメンバーにも、日程や役割、必要な準備物などの情報を伝えます。入社式の数日前や前日には、出席者にリマインドを通知することで、当日のスムーズな進行につながるでしょう。
場所の予約
入社式の式次第や参加人数を考慮し、十分な広さを持った適切な会場を選定し、開催日程の日時を確定しますします。
会場のマイクやプロジェクターの動作テストも忘れてはなりません。入社式の当日の椅子の配置など、レイアウトも事前に計画し、スムーズに進行できるように準備します。
案内状の準備
新入社員に向けて入社式の案内状を送付します。
案内は「入社式のご案内」と明確にしてもよいですが、「招待状」記載してもよいかもしれません。
入社式は新入社員の初仕事であり、不安や緊張を感じている人も少なくないでしょう。学生の不安や緊張を緩和させてあげることも担当者の役割といえます。
アジェンダの作成
入社式で行う主要なイベントやセッションの内容をリストアップし、時間配分を踏まえてスケジューリングします。具体的には以下のとおりです。
- 社長や人事部長の挨拶
- 新入社員の自己紹介
- 企業文化やビジョンの紹介
- 誓約の宣誓
各セッションの所要時間や順番を検討し、詳細なタイムスケジュールを組み立てます。必要に応じて休憩や質疑応答の時間も設け、全体の流れがスムーズに進行するように努めましょう。
アジェンダも関係者全員に事前に共有し、担当者には事前に心構えをしてもらい、新入社員には安心して参加できるように促します。
スピーチや挨拶の準備
入社式での挨拶や談話を役員や部長クラスなどに依頼します。
社長には経営理念や新入社員への期待について、人事部長には企業文化や人事方針について触れてもらうとよいでしょう。入社式のアジェンダ作成の際に設定した所要時間も伝えます。内容が重複しないよう、発言者との調整や連携も必要です。
部署やチームの紹介
入社式で部署やチームの紹介を行う場合は、各配属部署と連携して、紹介の準備を依頼します。紹介内容や進行を確認し、スムーズな進行に向けて準備しましょう。
新入社員の所属意識やモチベーションを高められるよう、チームの雰囲気を感じ取ってもらえるような資料を補足してもよいかもしれません。
受付の準備
入社式の受付の準備では、まず入口付近の適切な位置に受付テーブルを設置します。新入社員や関係者がスムーズに受付を済ませられるよう、通路や待機スペースも確保します。
テーブルには、新入社員の名前が記載された名札をアルファベット順や部署別など、取り扱いやすい順序で配置します。名札は、新入社員がほかの社員や役員と交流しやすくなるよう、見やすくデザインされたものを選びましょう。さらに、受付時に新入社員に配布する資料や企業のパンフレット、入社手続きに関する書類なども用意します。
受付業務を担当するスタッフには、事前に役割や業務の流れを明確に伝え、質問に対する回答や対応方法を研修します。あらかじめ研修することにより、迅速でていねいな対応ができるでしょう。
また、受付終了後の名札や資料の整理方法も検討しておきます。
懇親会の準備
入社式のあとに懇親会を計画している場合、事前に場所の予約や飲食の手配をしましょう。
懇親会の目的は、新入社員が仕事に対する疑問点の解消と、親睦を深めることにあります。そのため、先輩社員の話を聞いて自由に質問してもらったり、新入社員同士で選考時の心境を話してもらったりといった場を設けることが大切です。
先輩が会社で歩んだキャリアを聞けば、実務をイメージしやすくなり、就職活動についてお互いに話せば「みんな同じことを経験していたんだ」と親近感を感じられるでしょう。
リハーサル
入社式の当日に備えて何度かリハーサルを行いましょう。プログラムを通してみると、スムーズな別の方法や適切な時間の割り振りなど、課題が出てくるはずです。検討事項を一つずつ解消していきます。
入社式は年に1回の特別なイベントで、通常業務とは異なるため、多くの人員を割くことを避けたいと感じる担当者もいるかもしれません。しかし、適切な人員配置を怠ると、入社式の運営に問題が生じる可能性があります。
新入社員が業務に対して鮮明なイメージを持てるよう、プログラムを考え、考えられるトラブルを想定しながら準備します。新入社員にとって満足度の高い式典にできるよう、複数名で、役割分担しながら準備を進めるとよいでしょう。
オンライン入社式について
2020年から2023年にかけて続いた新型コロナウイルスの流行により、オンライン形式で入社式を実施した企業もあったでしょう。
入社式のオンライン開催には以下の特徴があります。
メリット
| どこからでも参加できる | 遠隔地にいる新入社員も自宅から参加できる |
|---|---|
| コストを削減できる | 会場のレンタルや移動、宿泊、飲食などのコストを削減できる |
| 効率化できる | 録画やリプレイ機能を活用することで、複数回開催できる |
デメリット
一方で、以下のデメリットもあります。
| コミュニケーションが難しい | オンラインではほかのメンバーと交流するのが難しい |
|---|---|
| ラグが生じることがある | インターネットの接続問題やシステムの不具合など、 技術的な障害が発生するおそれがある |
| 集中力を保ちづらい | 環境によっては、集中力が散漫になるおそれがある |
| 現場の雰囲気を感じづらい | オフラインで参加している新入社員に比べ、 入社後にモチベーションを見出しにくい |
オンライン形式で開催する場合の準備
入社式は、可能であればオンラインよりオフラインで開催したいと考える企業は多いのではないでしょうか。しかし、当日の悪天候や参加者がウイルス感染した場合には、オンラインでの開催を検討する必要があります。
オンライン入社式の開催に際して、以下の3点を意識して準備を進めるとよいでしょう。
通信環境の確認
オンライン入社式の開催は通信環境が参加者の満足度に大きく影響します。式の間頻繁に映像と音声が乱れてしまっては十分な意思疎通をとれず、雰囲気をつかめません。事前に人事担当者がオンラインで話してみて通信環境を確認しましょう。
対面の参加者と同じものを食べる
オンライン入社式で食事をしながら交流の機会を設ける場合、食べるものに差があると、メンバーそれぞれが自分だけ孤立しているように感じるものです。準備の段階でオンラインの出席者がいると分かっているときは、日持ちのするお菓子などを準備し、全員で同じものを食べるとよいでしょう。ささいな配慮が、新入社員の不安の解消や満足度にの向上につながります。
交流の時間を長く取る
オンライン入社式の参加者はリアル会場の空気感をつかめません。新入社員は、自分の同僚や上司がどのような人なのかが気になります。出社したときに、違和感なくなじめるように、オンラインの参加者が1人でも多くの人と話せるようにしましょう。
ユニークな入社式の事例
入社式は式次第に沿って開催されるのが一般的です。しかし、なかには会社独自のイベント要素を取り入れている企業もあります。ユニークな入社式を開催している企業の事例を紹介します。
アウトドア入社式
新入社員を自然の中に連れて行き、キャンプやハイキングを行うことで、チームワークを育む入社式を実施している企業もあります。自然の中での体験を通じて、新入社員同士の絆を深めることが狙いです。
テーマパーク入社式
テーマパークを貸し切って入社式を行う企業もあります。新入社員が一緒にアトラクションを楽しむことで、リラックスした雰囲気での交流を促進します。
伝統文化体験入社式
日本の伝統文化や芸能を体験する入社式を行う企業もあります。茶道や華道、和太鼓などの体験を通じて、日本の伝統や文化を学びながらの交流が行われます。
スポーツ入社式
新入社員をスポーツ施設に連れて行き、スポーツを通じて交流をはかる入社式です。サッカーやバスケットボールなどのチームスポーツで、チームワークを育むことを目的としています。
VR・AR入社式
最新の技術を取り入れた入社式の事例もあります。VRやARを使用して仮想空間での入社式を実施し、新入社員に未来のビジョンや企業の技術力をアピールします。
旅行入社式
新入社員を国内外の旅行先に連れて行き、旅行を通じて交流をする入社式の事例もあるようです。新しい場所での体験を通じて、新入社員同士の絆を深めることが狙いです。
まとめ
入社式は新入社員にとって人生で一度限りのイベントであり、入社後の働き方やモチベーションにも影響します。
式次第は、社長や幹部からのあいさつ、辞令の交付、先輩社員のスピーチなどが執り行われるのが一般的です。
ただし形式にとらわれず、招待状を送る演出や先輩社員の体験談を共有する場なども、新しい仲間を迎え入れるためには大切でしょう。
コロナ禍を経て、一時はオンライン入社式の実施も増えました。オンラインツールを利用した入社式でも、対話型のセッションを設け、選考時の振り返りを共有することで、入社後の目的意識を高めることも可能です。
入社式は正式に新入社員と企業が接点を持つ場です。 本記事で紹介したユニークな事例や流れなども参考にしつつ、自社の入社式プランを検討してみてはいかがでしょうか。
新入社員の情報管理ならOne人事[タレントマネジメント]
One人事[タレントマネジメント]は、従業員の個人情報やスキル、経験値などを一元管理するタレントマネジメントシステムです。スキルや経歴を見える化して、特徴ごとに区分けしたり、適性を見極めたりすることで、配置の検討や育成計画の立案に役立ちます。
日頃から情報をシステムに集約しておくと、組織の全体像や過去から将来にわたる課題が見えてきます。人材戦略や従業員一人ひとりの育成プランの策定と実行を助ける蓄積されたデータは、組織力の強化を助けるでしょう。担当者が分散された書類をあちこちから探してくる手間も必要ありません。
One人事[タレントマネジメント]の初期費用や気になる使い心地については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門のスタッフが自社の課題をていねいにお聞きしたうえでご案内いたします。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 従業員の「入社から退社まで」をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失などのリスクを軽減することで、経営者や担当者が「本当にやるべき業務」に集中できるようにサポートいたします。 |
