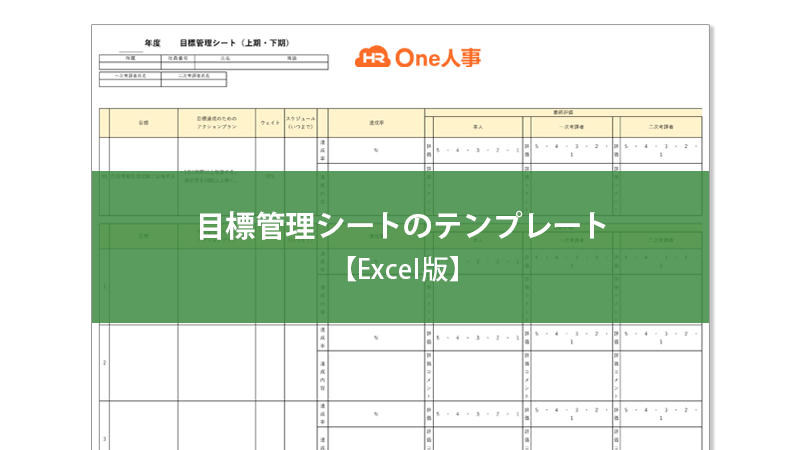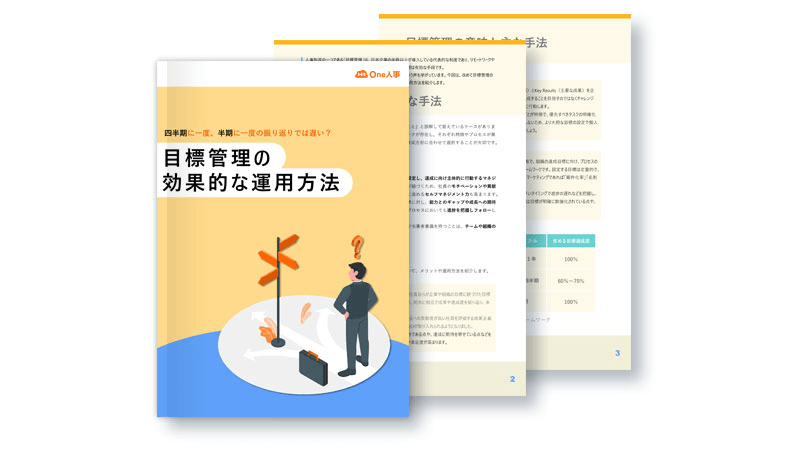マネジメント目標とは何かを例文で解説|重要な3つの視点と部下を支援する管理手法
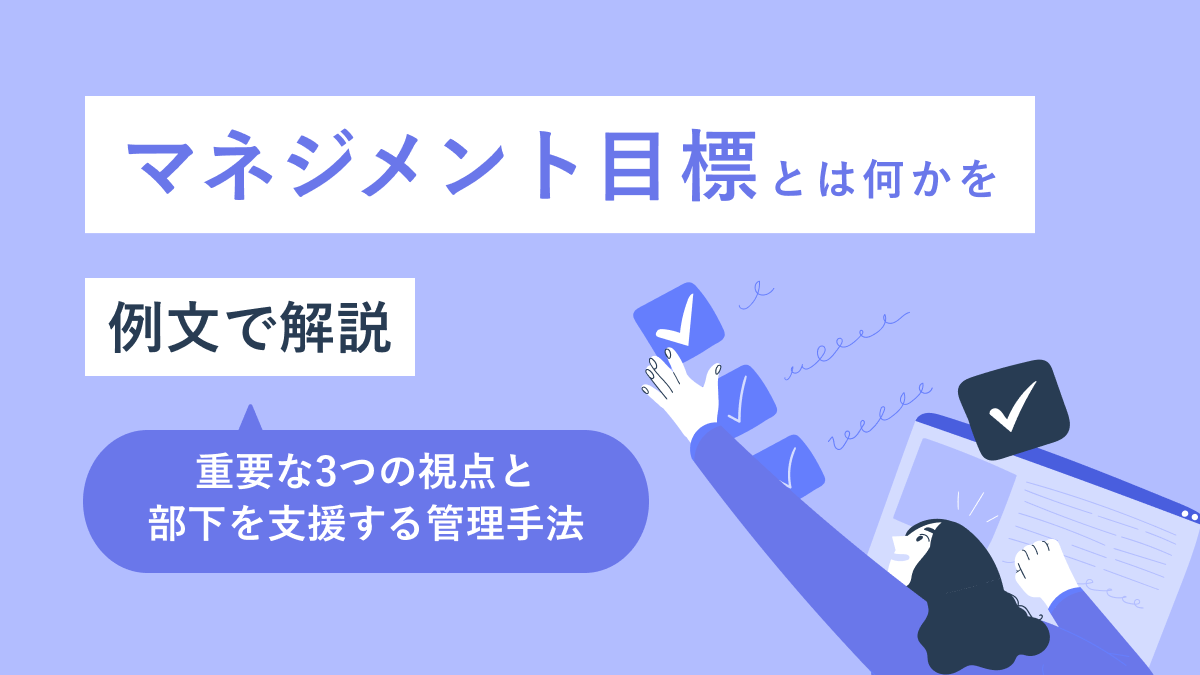
「チームの目標設定がうまくいかない」「部下のモチベーションが続かない」こんな悩みを抱える管理職の方は少なくないでしょう。
マネジメントにおける目標設定は、チームの方向性を示す重要な指標です。適切に設定すれば、部下は主体的に行動でき、あいまいであれば生産性を落としてしまうでしょう。
本記事では、マネジメント目標の基本と設定のコツ、部下の達成を支える方法を知識を解説します。
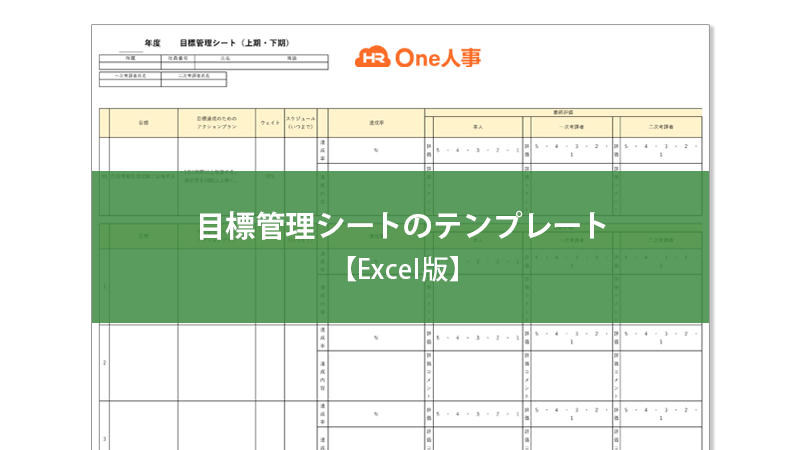
 目次[表示]
目次[表示]
マネジメント目標とは? 管理職が意識したい3つの指標
マネジメント目標とは、組織のビジョンや経営方針を実現するために、管理職が定める目標のことです。組織の方向性と、メンバー一人ひとりの行動をつなぐ役割を持っています。
明確な目標があると、メンバーは「自分が何を目指し、どう動けばいいのか」がはっきりします。結果として、チームの成長や成果も生まれるでしょう。
では、マネジメントにおいて目標を考えるときは何を意識すべきなのでしょうか。大切なのは、組織全体・部下・管理職自身の3つの視点から目標を設定することです。
1.組織(会社・部署・チーム全体)の目標
組織の目標は、部署やチーム全体で共有し、達成を目指す具体的なゴールです。チームが同じ方向に進むために必要不可欠なものといえます。
たとえば営業部では「部門売上高を前年比110%に増やす」「原価率を2%下げる」といった数値目標が一般的です。プロダクト開発では「製品を〇月までにリリースする」などが該当します。
組織全体の目標を明文化し、全員が理解・共有することが達成のポイントです。
2.チームメンバーの個人目標
メンバーの個人目標は、組織目標を現実にするために一人ひとりが担う具体的な役割です。組織の目標と整合し、個々の役割や能力に即した内容である必要があります。
たとえば「売上30%増」を組織目標に掲げるなら、個人には「月間商談10件」「新規顧客5社獲得」といった目標を割り当てます。
個人目標は「達成型(成果重視)」「ストック型(価値の蓄積)」「スキルアップ型(能力向上)」の3つを組み合わせると、成長と成果を両立できます。
3.管理職自身の目標
管理職は組織の目標や部下の成長だけでなく、自分自身のマネジメント目標もあります。リーダーとしての成果と自己成長の両方を示す指標を設定します。
「どの行動で目標達成に貢献するのか」「部下をどう支援するか」を具体的に考え、行動計画に落とし込まなければなりません。
短期的な課題解決だけでなく、既存業務の改善、新しい挑戦、部下の育成を同時に進める視点が求められます。
管理職はチームの経営者です。チーム全体の収益や価値を高めることに責任を持ち、自分と組織の目標をつなげる意識が欠かせません。
チームマネジメントでも目標設定は重要
そもそもマネジメントをするうえで、目標設定がなぜ重要なのでしょうか。主な理由は以下の4つが挙げられます。
- メンバーの成長・成果を最大化するため
- 部下のモチベーションを維持・向上するため
- 上司と部下の期待値をすり合わせるため
- 評価に反映させて納得度を高めるため
メンバーの成長・成果を最大化するため
マネジメントで目標を設定する理由は、メンバーの成長と成果を最大化できる点にあります。
目標があいまいだと、チームは方向性を見失い、全員が別々の方向に進んでしまいます。
たとえるなら、同じボートに乗っていながら、皆がバラバラにオールを漕いでいる状態です。
組織の目標と個人の目標を結びつけることで、行動に統一感が生まれ、全員が同じゴールを目指す力が強くなります。
部下のモチベーションを維持・向上するため
マネジメントにおいて目標は部下のモチベーションを保つための重要な仕組みです。目標が明確だと、日々の業務に意味が生まれ、ただの作業が価値ある成果に変わります。
たとえば小さな目標を設定し、それを達成するごとに成功体験を積むことで自信が育ちます。その積み重ねが「次も頑張ろう」という前向きな気持ちを支えます。
さらに、目標設定に本人がかかわると、内発的動機づけが促され、キャリアへの主体性も高まります。進捗を可視化し、達成を祝う文化をつくることが大切です。
上司と部下の期待値をすり合わせるため
マネジメントにおいて目標設定は、上司と部下の期待を一致させる場でもあります。
目標が共有されていないと、部下は何を求められているのかを自分で解釈するしかありません。結果として、意図と違う方向に努力が向き、パフォーマンスが落ちることもあります。
たとえば意思決定の主体をめぐる価値観のズレが、信頼関係を損なう原因になる場合もあります。
定期的な1on1ミーティングで目標を話し合えば、誤解を減らし期待をそろえることができます。目標に関する対話は、チームの結束にもつながります。
▼1on1ミーティングの実施に課題がある方は、以下の資料もぜひご活用ください。
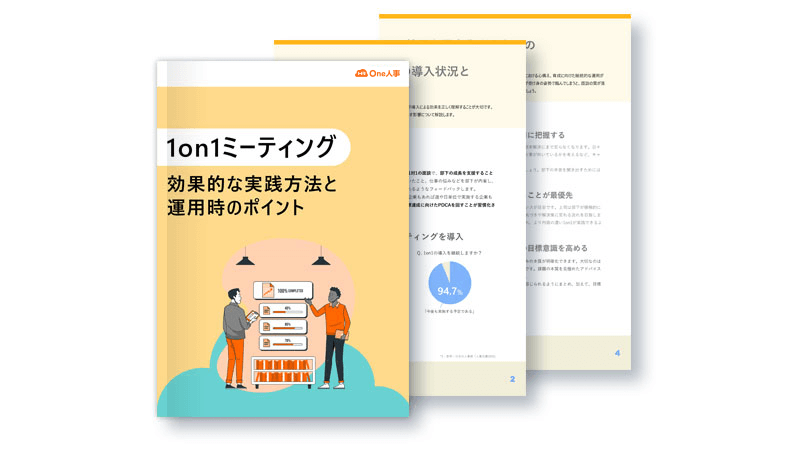
評価に反映させて納得度を高めるため
マネジメントにおける目標は公正な評価の軸です。目標と評価基準があいまいだと、評価が主観的になり不公平感が生まれます。
明確な基準を先に決めておけば、評価に納得感が出ますし、あとから基準を変えてしまうリスクも避けられます。
たとえば、達成度を客観的な数値や行動で示すことで、評価の透明性が上がります。目標設定は単なる管理ではなく、信頼関係を築くコミュニケーションの機会です。
成果を正当に評価し、部下とともに振り返ることで、組織全体の成長を支えられるでしょう。
マネジメント目標の設定例
ここまでは、マネジメントにおける目標設定の重要性を紹介してきました。
マネージャーにはもう1つ欠かせない視点があります。それは、自分自身が取り組むべき目標を定めることです。組織やチームを導くだけでなく、自分の行動や成長に責任を持つことが求められます。
たとえば、組織目標と連動する目標や、チームマネジメントに関する目標、プロジェクト推進に関する目標、組織文化を変える目標などです。
ここでは、それぞれの観点から具体的な目標設定の例を紹介します。自分の状況にあった目標のヒントを探してみてください。
組織目標とリンクしたマネジメント目標の例文
組織目標とリンクしたマネジメント目標は、会社全体の方向性と部門の活動を結びつける役割を果たします。
| 組織目標とリンクしたマネジメント目標の例 |
|---|
| 部下に営業プロセスの標準化を徹底させることにより、部門売上高を前年比15%以上の○○円にする |
| 四半期ごとに事業計画の進捗確認会議を実施し、年度末までに部門の売上目標達成率を95%以上にする |
| 顧客満足度調査を四半期ごとに実施・分析し、年度末までに顧客満足度スコアを現在の4.2から4.5に向上させる |
| 今期中に部門の業務プロセスを見直し、コスト削減策を3つ以上実施することで、部門コストを前年比10%削減する |
| 月次で市場動向分析会議を開催し、9月末までに新規市場向け商品・サービスを2つ以上開発する |
| 部門横断プロジェクトを四半期に1回以上主導し、年度末までに全社的な業務効率化を実現する |
部門の活動が会社の成長にどのように貢献しているかを明確にできるとよいでしょう。
チームマネジメントの目標の例文
チームマネジメントの目標は、チームメンバーの成長と生産性向上に焦点をあてたものです。
| チームマネジメントの目標の例 |
|---|
| 毎月1回のスキル向上研修を実施し、チームメンバー全員が年度内に1人あたり2つ以上の新しいスキルを習得できるようにする |
| 週次の1on1ミーティングを全メンバーと実施し、年度末の従業員満足度調査でチーム平均スコアを前年比15%向上させる |
| 四半期ごとにキャリア開発計画を見直し、年度末までにチームメンバー5名以上をプロジェクトリーダーとして独り立ちさせる |
| 月次のチームビルディング活動を実施し、年度末までにチーム内のコミュニケーション満足度を30%向上させる |
| 部下の強みを活かした業務分担の最適化を四半期ごとに見直し、チーム全体の生産性を20%向上させる |
| メンバー間の知識共有会を月2回開催し、年度末までにチーム内のナレッジベースを構築する |
よいチームマネジメント目標は、メンバーの能力開発やモチベーション向上、チームワークの強化を促進できるでしょう。
プロジェクトマネジメントの目標の例文
プロジェクトのマネジメントの目標は、特定のプロジェクトを成功に導くための具体的な指標を設定するものです。
| プロジェクトマネジメントの目標の例 |
|---|
| 新システム導入プロジェクトを9月末までに予算内で完了させ、業務処理時間を30%削減する |
| 製品開発プロジェクトを四半期ごとのマイルストーン管理により、年度末までに計画どおりリリースし、市場シェアを5%拡大する |
| クロスファンクショナルチームを編成し、6か月以内に顧客対応プロセスを再構築することで、顧客対応時間を平均15%短縮する |
| プロジェクト管理ツールを活用し、全プロジェクトの進捗状況を週次で可視化することで、プロジェクト完了率を85%から95%に向上させる |
| リスク管理プロセスを強化し、四半期ごとにリスク評価を実施することで、プロジェクトの遅延発生率を前年比50%削減する |
| ステークホルダーとの定期的なコミュニケーション計画を策定・実行し、プロジェクト満足度評価を4.0から4.5に向上させる |
プロジェクトの期限や予算、品質などの要素をバランスよく考慮した目標設定が重要です。
組織文化・働き方改革に関する目標の例文
組織文化・働き方改革に関するマネジメント目標は、職場全体をよりよい方向に変えていくことを目指すものです。
| 組織文化・働き方改革に関するマネジメント目標の例 |
|---|
| フレックスタイム制度を導入し、年度末までにチームメンバーの残業時間を月平均30%削減する |
| 四半期ごとに業務効率化ワークショップを開催し、年度末までに部門の業務プロセスを20%効率化する |
| 月1回のチーム内コミュニケーション活性化イベントを実施し、年度末の従業員エンゲージメント調査スコアを25%向上させる |
| リモートワークとオフィスワークのハイブリッド体制を確立し、年度末までにワークライフバランス満足度を40%向上させる |
| 多様性と包括性を促進するための研修を四半期ごとに実施し、年度末までに女性管理職比率を15%から25%に向上させる |
| 健康経営の取り組みとして、月次の健康促進イベントを実施し、年度末までに従業員の健康診断受診率を100%達成する |
マネージャーだけでなく、人事などのバックオフィスとも連携しながら、具体的な目標を計画に落とし込みましょう。
マネジメント目標の設定ポイント・注意点
マネジメントにおいて目標は、立てるだけでは十分とはいえません。設定した目標を実際に機能させ、チームの成果や自身の成長につなげるためには、いくつか大切なポイントがあります。
ここでは、おさえておきたい5つの注意点を解説します。
- 組織の課題と目指すべき理想を定義する
- 組織とメンバーに対する理解を深める
- 組織目標と個人目標をリンクさせる
- メンバーが納得できる目標を設定する
- 数字と期限を明確にする
ぜひ自分のマネジメントに置き換えて考えてみてください。
組織の課題と目指すべき理想を定義する
マネジメントにおいて目標を正しく設定するには、まず組織の課題と理想の姿を具体的に定めることが重要です。
課題が不明確だと、行動がばらつき改善効果も出にくくなります。
たとえば「顧客対応の遅延」が課題なら、「平均対応時間を15%短縮する」と目標を明示しましょう。
現状分析に基づいて課題の原因を特定し、根拠ある目標を立てることが欠かせません。「What(何)When(いつ)Why(なぜ)」の視点で理想を整理すると、マネジメント目標に説得力が生まれます。
組織とメンバーに対する理解を深める
マネジメントにおいて目標を設定する際は、組織の方針やチームの状況、メンバーの強みを理解する必要があります。
会社の戦略とずれた目標は、現場の負担や混乱を招きます。
たとえばチームで方針を共有し、共通認識をつくる会議を開くのも一つの方法です。
メンバーの適性を把握するために1on1面談を行い、キャリア志向や課題を整理しましょう。
理解を深めることで、個々の力を最大限に活かせる目標設定が可能になります。
組織目標と個人目標をリンクさせる
マネジメントにおいて目標は、組織全体の方針と個人の目標をつなげることが重要です。
整合性がないと努力が分散し、成果が上がりません。
たとえば「顧客満足度向上」が会社の目標なら、営業では「定期フォローアップ」、個人では「月1回の訪問」を目標にします。
組織から個人まで一貫した目標を設定すると、行動の方向性がそろい、達成感も共有しやすくなります。全員が同じゴールを目指せる体制を築くことが重要です。
メンバーが納得できる目標を設定する
マネジメントにおいて目標は一方的に与えるのではなく、部下が納得できる内容であることが大切です。
自分で達成できると感じられる目標は、やる気を引き出し行動を促します。
たとえば「まずは小さな成果を積み上げ、徐々に難易度を上げる」など段階的に設定すると効果的です。
目標を決める際は、トップダウンだけでなくボトムアップの意見も取り入れましょう。定期的に振り返り、必要に応じて修正する柔軟さも欠かせません。
数字と期限を明確にする
マネジメントにおいて目標には必ず数字と期限を設定しましょう。あいまいな目標では進捗が測れず、達成感も薄れます。
「月末までに新規契約を5件獲得する」と具体化すれば行動計画が立てやすくなります。
期限がないと優先順位が下がり、行動が遅れがちです。
さらに評価基準も事前に共有し、達成度を客観的に判断できるようにしましょう。
たとえば「達成率100%以上をA評価」と明示すると、目標に対する納得感が高まります。
▼目標を数値化するコツは、以下の記事でご確認ください。
【参考】マネジメント目標の設定に役立つフレームワーク3選
実際にマネジメント目標を決めるときは「どう整理したらいいのか」「何から考えればいいのか」と迷うことも多いでしょう。そんなときは、フレームワークを活用すると視点が整理され、行動に移しやすくなります。
ここでは、マネジメントにおいて目標の設定に役立つ代表的な3つのフレームワークを紹介します。
- SMARTの法則
- MBO
- OKR
それぞれの特徴を知り、チームや組織にあった方法を選んでみてください。
SMARTの法則
SMARTの法則は、目標を具体的かつ測定可能に設定する基本フレームワークです。
Specific(具体的)、Measurable(測定可能)、Achievable(達成可能)、Relevant(関連性)、Time-bound(期限)の頭文字をとっています。
たとえば「売上を増やす」というあいまいな表現は、フレームワークに沿って「6か月以内に新規顧客を20%増やし、売上を15%伸ばす」と言い換えるとよいでしょう。
マネジメントにおける目標設定では、チームや個人の達成基準を明確にするのに役立ちます。
MBO
MBOは、経営目標を現場の目標に落とし込むための仕組みです。組織全体のゴールを部門や個人の目標に分解し、進捗を管理します。
たとえば、年間の売り上げ目標を部門の四半期目標に分け、さらに個人の月次目標に具体化するなどします。
マネジメントにおける目標設定では、組織の大きな目標を分解し、チームや個人の目標と一貫性を持たせるのに役立ちます。また、定期的に進捗を確認しながら目標を見直す仕組みとしても有効です。
OKR
OKRは、組織のビジョンを具体的な目標に落とし込むためのフレームワークです。
Objectives(目標)を定性的に設定したうえで、測定可能なKey Results(主要な結果)で進捗を測ります。
たとえば「顧客満足度を業界トップにする」というObjectivesに対し、「NPSを40から70に引き上げる」と具体的なKey Resultsを設定します。
マネジメントにおける目標設定では、挑戦的な目標を掲げつつ、全員の方向性をそろえるのに有用です。
▼ほかにもフレームワークを参考にしたいなら、以下の記事もご確認ください。
マネジメントにおける目標管理のコツ
どんなによい目標でも、マネジメント次第で結果は変わります。実際に行動を引き出し、成果につなげるためには、目標管理も工夫しなければなりません。
ここからは、チームの力を最大限に引き出し、目標を達成へ導くためのコツを3つ紹介します。
- チーム・組織で共有しあう
- 目標を細分化してみる
- 定期的に振り返り、ブラッシュアップする
チーム・組織で共有しあう
マネジメントにおける目標は、チームや組織で共有することが大切です。全員が同じゴールを理解することで、行動がそろい、一体感が生まれるためです。
たとえば、開発チームが「新製品を期日内に完成させる」と目標を共有すれば、開発者やテスターが同じ方向を向いて進めます。
共有された目標は、責任感や主体性を引き出す効果もあります。定期的なミーティングや進捗の見える化を通じて、チームで共通認識を育てましょう。
▼目標をチームで共有し、進捗を見える化するなら、目標管理機能が充実したシステムの活用がおすすめです。
→目標管理を効率化するシステム「One人事」の資料を無料でダウンロード

→目標管理のシステム化によって社員の働く姿勢に変化があった事例はこちら
目標を細分化してみる
目標設定が高いほど、メンバーの心理的な負担も増えてしまいます。だからこそ、目標を小さく分解することが大切です。
目標を細分化すると、短期間で達成感を積み重ねやすくなり、前向きな行動を引き出せます。
たとえば「月末までにキャンペーンを完成させる」という目標を、「準備会議の実施」「資料作成」「顧客確認」といった具体的なタスクに分けると、進捗がはっきり見えるようになります。
細分化により目標達成までの道筋をマネジメントして、メンバーが自信を持って行動できるようになるでしょう。
定期的に振り返り、ブラッシュアップする
目標をマネジメント運用するうえで、定期的な振り返りが欠かせません。状況は常に変化し、目標も柔軟に見直す必要があるためです。
たとえば、週次の1on1で進捗や課題を確認すれば、遅れや不安を早期に発見できます。振り返りは、達成度を評価するだけでなく、改善策を考える機会にもなります。
月次や四半期単位でブラッシュアップしながら進めることで、チームの成長と成果を継続的に引き出せます。
▼目標の振り返りの頻度はどれくらいが適切なのでしょうか。目標管理の運用の参考に、以下の資料もぜひご活用ください。
部下・メンバーの目標達成を支援するマネジメント
マネジメントにおいて、もっとも大切なのは、部下やチームが目標を達成できるように支援することです。
どんなに優秀なメンバーでも、適切なサポートがなければ力を発揮しきれないことがあります。マネージャーの支援次第で、チームの可能性は何倍にも広がるでしょう。
最後に、メンバーが安心して挑戦し、成果を出すために欠かせない姿勢を4つ紹介します。
- ティーチングではなくコーチングをする
- Iメッセージを利用する
- 目標達成のプロセスも重視する
- 外向き思考を促す
ティーチングではなくコーチングをする
部下の目標達成を支援するには、ティーチングとコーチングを適切に使い分けることが重要です。部下が自分で考え行動する力を育てられるためです。
たとえば「この課題をどう解決できそう?」と質問すると、部下は答えを探し主体的に動きます。
上司が正解を教えるだけでは、成長の機会を奪ってしまいます。コーチングを通じて、目標に向けた主体性と自己解決力を伸ばすかかわりを意識しましょう。
Iメッセージを利用する
マネジメントにおける目標達成には、Iメッセージ(アイメッセージ)が有効です。
自分を主語にする表現は、相手を責めずに気持ちや要望を伝えられるためです。
たとえば「私は進捗がわからず困っています」と伝えると、相手は防御的にならず話を聞きやすくなります。
一方で「あなたは報告が遅い」と言うと批判に聞こえます。
Iメッセージは信頼関係を守り、目標に向けた建設的な対話を促すでしょう。
目標達成のプロセスも重視する
マネジメント目標を達成するには、結果だけでなくプロセスを大切にする必要があります。どんなに素晴らしい成果が出ても、進め方が正しくなければ再現性がなく、一時的な成功で終わるおそれがあるためです。
過程を重視すると、メンバーは日々の行動や判断の質を意識し、結果に至るまでの努力を積み上げられます。
また、プロセスを振り返る文化があれば、うまくいかなかったときも「方法を見直そう」と前向きに改善を考えられます。
結果至上主義に偏らず、健全な成長を続けるチームをつくるためにも、過程を見守り評価する視点が欠かせません。
外向き思考を促す
マネジメントにおける目標支援では、部下に外向き思考を持たせることが大切です。他者の期待やニーズを理解する姿勢が成果につながるためです。
たとえば「お客様は何を望んでいるのか」を考える習慣があれば、より実践的な改善ができます。
上司は「相手の立場からも考えられている?」と問いかけてみましょう。外向き思考が定着すると、チームの協力意識と達成力を引き出せるでしょう。
まとめ|マネジメント目標を活かし、組織と個人の成長へ
マネジメントにおいて目標は、組織のビジョンと現場の行動をつなぐ重要な指標です。明確な目標があることでチームの方向性が定まり、部下が自分の役割を理解し主体的に動けるようになるためです。
たとえば、SMARTの法則を使えばあいまいな目標を具体的に落とし込みやすくなりますMBOやOKRを組みあわせることで、組織の戦略と個人の目標を一貫させることも可能です。
適切な目標設定と部下への支援は、結果としてチームの力を引き出します。本記事で紹介した方法やフレームワークを参考に、組織と個人の成長を実感するためにも、マネジメント目標を見直してみましょう。