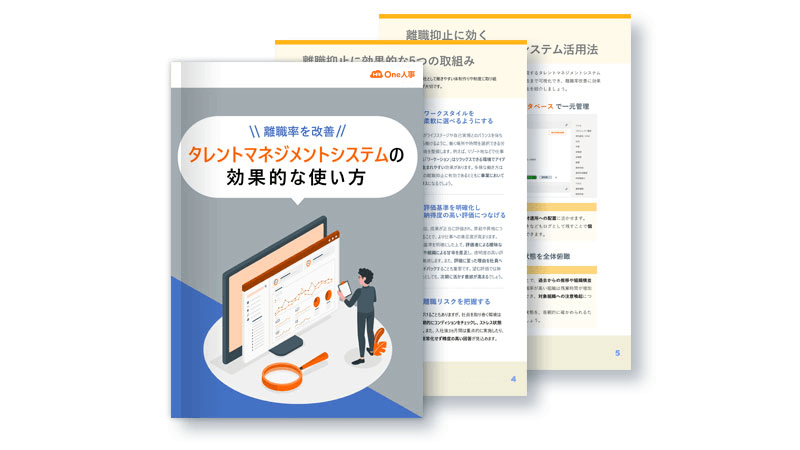人事考課システムとは? 人事評価システムとの違いと活用事例、選び方のコツ

「評価が属人的で公平性に欠ける」「人事考課の作業に膨大な時間がかかる」「評価結果の集計や分析が追いつかない」という悩みを抱えていませんか。
課題を根本から見直すには、業務を見直すだけでなく、人事考課を支える仕組みから整える必要があります。そこで注目したいのが、人事考課システムの導入です。
本記事では、人事考課システムと人事評価システムの違いを明確にしながら、導入のメリットや選び方のポイントを解説します。
→人事考課システムOne人事[タレントマネジメント]の資料をダウンロード
 目次[表示]
目次[表示]
人事考課システムとは?
人事考課システムとは、従業員の業務態度や成果、行動目標の達成度などを評価し、給与・昇進・配置転換といった人事上の意思決定を支援するツールです。
従来の紙やエクセルに頼った評価方法を見直し、評価基準の設定から結果の集計・分析までを一元的に管理できるシステムとして、多くの企業で導入されています。
人事考課システムの目的は、評価プロセスの効率化と標準化にあります。目標設定や評価シートの作成、評価フローの管理、結果の分析や可視化といった人事評価業務をデジタル化することで、人事部門の負担を大きく軽減できます。結果として、公平性と透明性の高い評価運用が実現できるでしょう。
人事評価システムとの違い・関連
人事考課システムと人事評価システムは、基本的に同じ意味で使われることが多いですが、厳密には少し違いがあります。
人事考課は「成績の査定」というニュアンスが強く、主に昇進・給与などの判断材料として使用されます。
一方で、人事評価はより広義の意味を持ちます。360度評価のように、成績の優劣だけでなく、プロジェクトへのアサインや部署異動、育成の判断にも活用が可能です。
言葉の意味に沿って整理すると、人事考課システムは、従業員の業績やスキルを評価し、昇給や昇進といった短期的な意思決定を支援することが主な目的です。
一方、人事評価システムは人事考課を含む広義の評価を支える仕組みといえます。長期的な人材育成やキャリア開発、タレントマネジメントまでを視野に入れて設計されている場合が多くあります。
人事考課システムの基本機能
人事考課システムは、従業員の評価プロセスを効率化し、公平な評価を実現するためのさまざまな機能を備えています。以下では4つの基本機能について、詳しく紹介します。
- 考課基準の設定・管理
- 考課結果の集計・分析
- フィードバックの記録
- 昇進・昇格への判断サポート
考課基準の設定・管理
人事考課システムでは、評価基準を柔軟に設定できる機能が提供されています。業績評価や行動評価などの基準を明確に定義し、組織の目標や価値観に合わせたカスタマイズが可能です。システムによる評価基準の管理は、評価の透明性と一貫性を大幅に向上させます。
評価基準を明確に定義し、全従業員に共有することは、公平な評価を実現するための第一歩です。評価基準は具体的で測定可能なものである必要があります。
たとえば、営業部門であれば「月間売上目標の達成率」や「新規顧客獲得数」などが評価基準となります。評価基準を文書化し、説明会を開催することで、従業員の理解を深められるでしょう。

考課結果の集計・分析
人事考課システムは、評価データを自動集計し、手動での計算ミスを防ぐ機能を備えています。考課者が入力した評定値を、ウエイトの係数をもとに相対評価・絶対評価それぞれの指定の集計方法に基づき、最終評定結果を自動計算します。集計作業の負担が大幅に削減され、迅速なフィードバックが可能です。
各従業員のパフォーマンスはスコアやグラフで視覚的に表示され、直感的な理解が促進されます。考課者は自身が評価した対象者の考課結果を一覧で照会し、考課傾向を見ながら、極端に偏った結果にならないよう訂正することも可能です。
フィードバックの記録
面談記録やフィードバック支援は、人事考課システムにおいて活用できる機能の1つです。
多くのシステムでは、考課面談の内容を記録でき、過去のフィードバックをいつでも確認可能です。一時的な評価にとどまらず、長期的な育成やキャリア形成の支援につなげられます。
また、「何をどう書けばいいかわからない」と悩む評価者に向けて、コメント入力の補助ガイドが表示される製品もあります。評価者の負担を軽減し、より建設的なフィードバックの手助けになるでしょう。
昇進・昇格への判断サポート
人事考課システムは、集計した評価結果をもとに、昇給や昇格の判断に役立つ情報を提示できます。データに基づいた意思決定を支援することで、公平性を保ち、従業員の納得感を高められます。
昇進や昇格の判断には、人が実施する以上、どうしても上司の推薦や面接などの主観的な評価が含まれます。そのため、評価結果を同じ基準で比べるのは難しくなりがちです。判断のブレを補う手段として、人事考課システムで蓄積された評価データが活用されています。
さらに、昇格アセスメントを取り入れると、日常業務では見えにくい従業員の特性や能力を客観的に把握できるでしょう。結果を昇格判断に加えれば、公正で透明性のある評価が可能です。
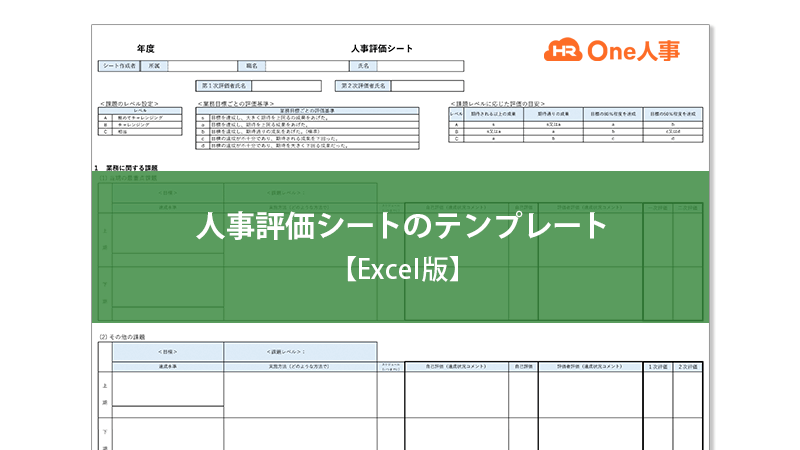
人事考課の課題とシステム導入の必要性
人事考課は従業員の育成と企業の成長に欠かせませんが、実際の運用では評価の属人化や手作業による非効率性など、さまざまな課題があります。評価者によって基準がぶれたり、個々の業務内容がブラックボックス化していると、公平性や納得感が損なわれがちです。
公平性に欠けた評価は、モチベーション低下につながります。とくに、評価結果が昇給や昇進と結びついていない場合、従業員は「頑張っても報われない」と感じやすくなります。優秀な人材ほど早期に見切りをつけ、退職の連鎖が起こることも少なくありません。
こうした背景から、統一した基準による公平な評価を支える人事考課システムの導入をおすすめします。システムを上手に活用すれば、評価の透明性が高まり、評価に納得しやすい仕組みをつくれるでしょう。蓄積されたデータに基づく昇格・昇給の判断も可能となり、組織全体にとって信頼性の高い評価運用の実現につながります。
人事考課システムの活用メリット
人事考課システムの導入は、紙やエクセルに依存した運用を見直し、公平性と効率性、そして評価の質の向上を実現する手段です。
人事考課システムが企業にもたらす具体的なメリットについて見ていきましょう。
- 考課業務の効率化
- 考課の公平性の向上
- 考課データの活用
- マネジメントの参考
考課業務の効率化
人事考課システムの最大のメリットは、評価業務の大幅な効率化です。評価シートの作成・配布・回収・集計・レポート作成といった一連の作業が自動化され、手作業の負担が大きく軽減された事例も多くあります。
たとえば、ある新車・中古車販売会社では、システム導入前は評価シートの運用に多くの時間を要していましたが、導入後は評価工数が4分の1に削減されました。
このように、システムの活用は業務負担を大幅に減らし、全体の業務効率化とDX推進につながっています。
考課の公平性の向上
人事考課システムを活用することで、評価基準を全社で統一し、評価者が変わっても同じ基準で判断される仕組みが整います。「評価者によって結果が変わる」といった不公平感をなくしたいと考える企業は少なくありませんよね。
評価者によって判断に差が出る、いわゆる「甘辛」評価の偏りも、システム上で調整が可能です。
属人的な判断を排除し、公平かつ透明性のある運用が実現すれば、従業員の不満や不信感も生まれにくくなるでしょう。結果として、評価に対する納得感が高まり、一人ひとりのモチベーションの向上にもつながります。
考課データの活用
人事考課システムで自動集計された業績スコアや目標達成度は、昇進・昇格の判断や給与改定、ボーナス支給に活用できるデータとなります。データに基づく公平な判断は、従業員の納得感や信頼を高めるうえで重要です。
評価データを分析することで、部署ごとのスキル不足や人材の強み・弱みの偏りを可視化できます。分析をもとに、必要な研修を選定したり、適材適所の人事異動を検討したりすることで戦略的な人材マネジメントを推進できます。
マネジメントの参考
人事考課システムに記録された中間考課や最終結果は、日々のマネジメントにも役立ちます。管理者は部下の強みや課題を客観的に把握し、的確な指導に活かせます。
目標の進捗状況をリアルタイムで確認できるため、期末評価を待たずにタイムリーな声かけが可能です。上司と部下の継続的なコミュニケーションは、チーム全体のパフォーマンス向上にもつながっていくでしょう。
離職防止への効果
人事考課システムを導入することで、公平で透明性のある評価制度を構築しやすくなります。「正当に評価されている」という実感は、従業員のエンゲージメントを高め、帰属意識と定着率を高めます。
また、人事考課システムに蓄積された評価データを活用して、不満や変化の兆しを早期に察知し、適切な対応をとることが可能です。とくに優秀な人材の離職を防ぐには、先手の対策が欠かせません。
最適な人事考課システムを選ぶには? 確認したい比較ポイント
人事考課システムは、評価業務の効率化や公平性の向上などメリットをもたらしますが、自社に適したものでないと、期待した効果を得られません。
そこで人事考課システムを比較・検討するときに、おさえておきたい8つのポイントを紹介します。
- 企業規模や業務特性に対する相性
- 初期費用・運用費用
- 自社の考課プロセスに必要な機能
- 権限設定の柔軟さ・セキュリティ要件
- 操作性と使いやすさ
- サポート体制
- 拡張性・連携性
- クラウド型・オンプレミス型・パッケージ型
企業規模や業務特性に対する相性を比較
人事考課システムは、企業の規模や業務特性に合ったものを選ぶことが重要です。たとえば中小企業が大企業向けのシステムを導入すると、使わない機能が多く、費用対効果が下がる可能性があります。
業種によって評価基準も異なります。営業職中心の企業では成果重視、製造業では品質や安全性重視など、業種に合った評価項目が設計できるかを確認しましょう。
初期費用・運用費用で比較
人事考課システムには、初期費用や月額利用料がかかります。クラウド型は月額数万円程度で導入しやすく、初期費用が無料のサービスもあります。一方でオンプレミス型は初期費用が高めで、サーバー費などの別途コストが必要です。
多機能なほど費用がかさむ傾向があり、機能に過不足がないように選定するのがポイントです。従業員数によって料金が変動する場合もあるため、将来の組織拡大も見据えてコストを検討しましょう。
自社の考課プロセスに必要な機能で比較
人事考課システムに搭載されているすべての機能が自社に必要とは限りません。MBOやOKR、360度評価など、自社で導入している評価手法に対応しているかが重要です。
評価項目の編集やワークフローの設定が柔軟にできるかもチェックポイントといえます。多機能すぎると使いづらくなる場合もあるため、「自社に必要な機能が過不足なくそろっているか」を基準に判断しましょう。
権限設定の柔軟さ・セキュリティ要件で比較
人事考課システムでは、評価情報や個人情報といった機密性の高いデータを扱います。
役職ごとに閲覧範囲を制限できる「権限設定」の柔軟さは欠かせません。
また、SSL暗号化や二段階認証、定期バックアップなどクラウド型ならではのセキュリティ対策が十分かどうかも確認しておきましょう。
操作性と使いやすさで比較
人事考課システムは、評価者・被評価者の双方が使いやすくなければ定着しません。直感的な操作が可能か、スマートフォンやタブレットでの利用に対応しているかも見ておきたいポイントです。
可能であれば、デモや無料トライアルで実際の操作性を確認し、自社の従業員にも負担なく使えるかどうか判断しましょう。
サポート体制で比較
人事考課システム導入後にトラブルが発生した場合や操作に不安がある場合、手厚いサポート体制があるかどうかは安心材料になります。
電話・チャット・メールなどのサポート手段や、対応時間、追加費用の有無などを確認しましょう。導入支援やマニュアルの充実度も比較ポイントになります。
拡張性・連携性で比較
人事考課システムは、給与計算システムや労務管理システムなどと連携することで、活用の幅があります。とくに最近では人的資本情報の開示が求められており、評価に関する指標や労務関連の指標をあわせて見える化しておくことが大切です。 API連携ができるか、データの入出力がしやすいかも確認が必要です。
また、評価制度の見直しや組織の拡大にも柔軟に対応できる「拡張性」も見逃せません。将来的な変化に耐えうるシステムかを考慮して見極めましょう。
クラウド型・オンプレミス型・パッケージ型で比較
人事考課システムには、主に以下3つのタイプがあります。それぞれ特徴があり、自社の状況や予算に応じて最適なタイプを選びましょう。
| クラウド型 | 低コストで導入しやすく、アップデートも自動。テレワーク環境にも適しています。 |
| オンプレミス型 | 自社サーバーに設置。高いカスタマイズ性とセキュリティを求める企業に向いています。 |
| パッケージ型 | 買い切り型で月額費用なし。ただし、機能追加やカスタマイズには限界があります。 |
現在は導入のしやすさからクラウド型が主流ですが、自社の方針や予算に応じて適したタイプを選ぶことが大切です。
→人事考課のクラウド化なら「One人事」資料を無料ダウンロード

人事考課システム(クラウド型)の活用事例
人事考課システムの導入は、考課業務の効率化だけでなく、従業員のモチベーション向上や人材データ活用の高度化にもつながります。
ここでは、クラウド型の人事考課システムを導入し、具体的な成果を上げている企業や自治体の導入事例を紹介します。導入前に抱えていた課題と、システムの導入によってどのような効果が生まれたのかを見ていきましょう。
茨城トヨペット株式会社
茨城県内に40拠点を展開する正規ディーラー・茨城トヨペット株式会社では、人材情報の分散と評価業務の属人化が課題でした。とくに評価集計やフィードバックの作業に年間800時間を要しており、アナログな運用の限界を感じていました。
【導入の効果】
- 年間800時間の業務工数が約200時間まで削減見込み
- 人材情報の一元化により、「一人ひとりの魅力が輝く会社」の実現に
▼同社の導入効果は以下より詳しくご覧いただけます。
株式会社ハイテックシステムズ
岡山県で自治体ソリューションを提供する株式会社ハイテックシステムズでは、従来エクセルで人事評価と目標管理を実施しており、作業に3営業日を要していました。加えて、個人の目標が達成されるまでの過程が見えないという課題もありました。
【導入の効果】
- 作業時間が3日から1日に短縮
- 目標進捗の可視化により、社員のモチベーションが向上
- 管理職による適切なフィードバックが可能に
▼同社の導入効果は以下より詳しくご覧いただけます。
上尾市役所
地方公務員法の改正を受け、上尾市では人事評価制度の刷新。当初はエクセル運用するつもりでしたが、複雑な計算式がエラーになってしまい、シート回収のリマインド業務も担当者の負担となっていました。また、過去の評価結果を整理して管理できていないないことも課題でした。
【導入の効果】
- 評価シートの再現性があり、システムでも問題なく運用が安定化
- 過去の評価データを容易に閲覧が可能に
- 処遇だけでなくキャリア形成に活かす人事異動を視野に
▼同市役所の導入効果は以下より詳しくご覧いただけます。
→人事考課の効果を高める「One人事」資料を無料ダウンロード

人事考課システムの導入時の注意点
人事考課システムの導入にあたっては、いくつかの注意点があります。
まず、トライアル期間には人事部門だけでなく一般社員にも使ってもらい、自己評価の入力やフィードバックが直感的に操作できるかを確認しましょう。
システム移行にともない評価プロセスに変更があるなら、変更点を関係者に周知し、混乱を防ぎます。操作に戸惑うこともあるため、マニュアルを整備し、社内問い合わせ窓口を周知しておくと安心です。社員の不安を和らげるためには、導入目的や効果をていねいに説明し、理解を得ることが重要です。
また、既存の人事・給与システムと連携できるかも確認しましょう。1つのデータベースで多岐にわたる情報を統合管理できると、二重入力の手間が省け効率化がはかれます。大規模組織では限定的な部署から段階的に導入するのもおすすめです。
人事考課システムの活用で公平性・透明性を向上(まとめ)
人事考課システムは、属人化しやすい評価業務を効率化し、公平で納得感ある制度運用を支えるツールです。
自社に合ったシステムを選べば、評価の質はもちろん、育成や配置といった人材活用の幅も広がります。
評価の属人化や不透明さ、業務の煩雑さに悩んでいるなら、人事考課システムの導入を前向きに検討してみてはいかがでしょうか。
評価制度の課題を解決し、人材を活かす仕組みに変えるには、自社に合った人事考課システムの導入が有用です。まずは比較・検討から始めてみましょう。
人事考課にも役立つタレントマネジメントシステム
One人事[タレントマネジメント]は、従業員一人ひとりの能力や評価データをクラウドで一元管理し、戦略的な人材マネジメントを支援するタレントマネジメントシステムです。
人事考課と目標管理を連動させて管理する機能が搭載されており、期初の目標設定から期中の進捗管理、期末の評価実施までを一貫して運用できます。評価結果は、育成や配置の検討材料として活用でき、組織全体のパフォーマンス強化にもつながるでしょう。
One人事[タレントマネジメント]は、自社の課題や目的に応じて欲しい機能だけを選べる、柔軟な料金プランでご利用いただけます。多機能過ぎて使いこなせないといった無駄はありません。
当サイトでは、サービス紹介資料はもちろん、人事労務のノウハウに関する資料を無料でダウンロードいただけます。また、無料トライアルも提供していますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |