業務委託で起こりうるトラブルの事例7選|契約の注意点や具体的な対策を解説
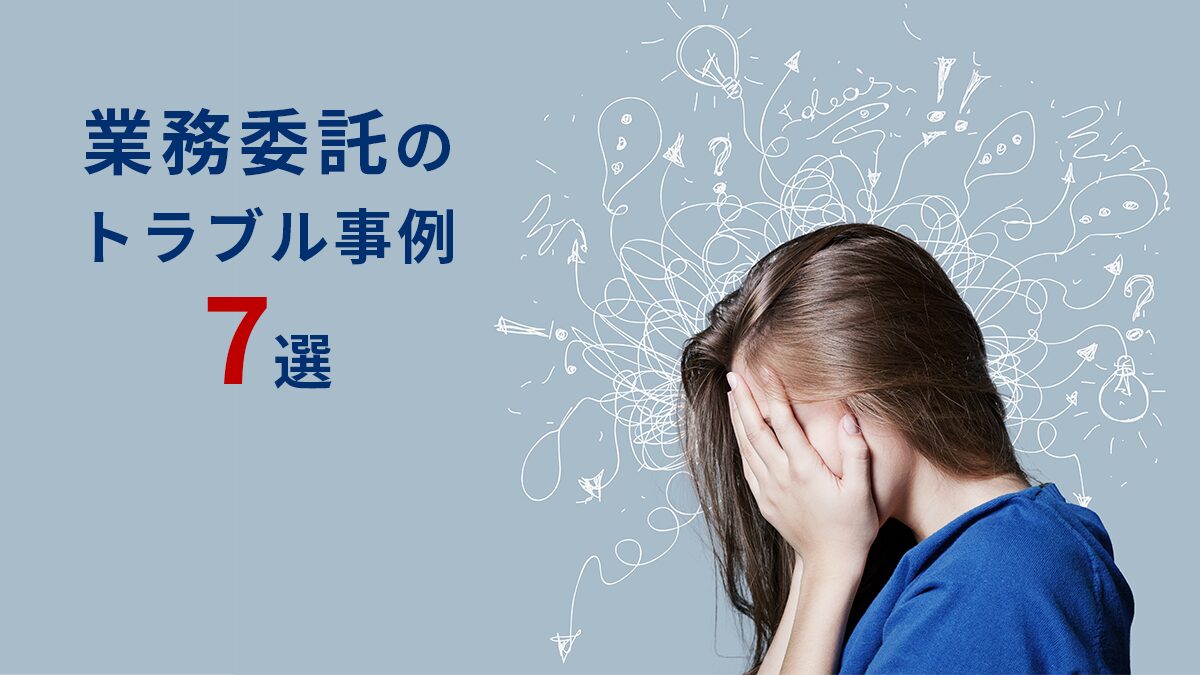
人件費の削減や生産性向上を目的として、業務委託を考えている方も多いのではないでしょうか。業務委託にはメリットがある一方、契約によるトラブルが起こる可能性も高いため、あらかじめどのようなトラブルが想定されるのか把握しておくことが重要です。
そこで本記事では、業務委託の概要やメリット・デメリットを解説し、業務委託のトラブル事例と対処法についてご紹介します。業務委託を検討している企業の担当者は、ぜひ参考にしてください。

業務委託契約とは
「業務委託契約」とは、自社の業務を外部の人材、あるいは企業に任せる契約のことです。委託された側は、契約に則って成果物の作成・提出を行う必要があり、できなかった場合はペナルティが科せられる恐れがあります。
業務委託契約について定められた法律はありませんが、「請負」や「委任」といった契約が記述されている民法632条・643条に法的根拠を持ちます。ただし、業務委託契約の内容は多岐にわたるため、契約書によって個別に細かく決めておくことが重要です。
業務委託契約書の記載項目の一覧
業務委託契約書に記載する主な項目は、下記の通りです。
| 委託料(報酬) | 業務を委託するときの報酬金額を記載する。特に、委任契約で報酬が発生する場合は記載が必要。 |
|---|---|
| 契約期間 | 業務の契約期間を記載する。委任契約だけでなく、請負契約の場合も目安として期間を記載しておく。 |
| 支払条件・支払時期 | 支払条件(検収後・着手時・毎月、請求方法など)と支払時期(翌月末日など)を記載する。 |
| 成果物の権利 | 成果物そのもの、または委託された業務の過程で発生した著作権や知的財産権といった権利がどちらに帰属するかを記載する。 |
| 再委託 | 受託者が委託された業務の全部、または一部を第三者に再委託することを認めるか、またその場合の条件を記載する。 |
| 秘密保持 | 共有する情報の秘密保持が必要な場合、業務委託の過程で開示された情報の秘密保持について記載する。 |
| 反社会的勢力の排除 | 委託者あるいは受託者が反社会的勢力に属している場合や反社会的勢力であることを騙った場合、他方は契約の解約ができるとする項目。 |
| 禁止事項 | 業務を委託するにあたって、受託者に対して禁止すべき事柄を記載する。 |
| 契約解除 | 委託者または受託者に契約違反や契約を履行できないといった問題が発生した際の契約解除について記載する。条件についても記載しておく。 |
| 損害賠償 | 委託者または受託者に契約違反があった場合の損害賠償責任や額について記載する。 |
上記の内容を漏れなく記載することで、業務委託に関するトラブルの発生リスクが低減されます。
業務委託のメリット
業務委託をすることでどのようなメリットが得られるのでしょうか。代表的な3つのメリットをご紹介します。
生産性が向上する
生産性の向上は、業務委託の大きなメリットです。ノンコア業務を業務委託すれば、重要度の高いコア業務に人的リソースを集中させられ、業務の効率化が図れます。また、従業員を定型業務からそれぞれの得意とする作業やスキルを活かせる業務に振り分けることで、生産性向上につながります。
人件費を削減できる
業務委託のメリットの一つとして、人件費を削減できる点も挙げられるでしょう。業務委託を利用すると、人材採用・育成にかかわるコストや、社会保険料、設備費なども削減できます。
専門知識やスキルが必要な業務を任せられる
業務委託のメリットは、専門知識やスキルが必要な業務を任せられることです。業務委託を活用することで、人材の採用や育成にかかる時間や費用を節約できます。自社だけでは対応できない専門業務や新規業務を社外の人材に任せられるため、さまざまな手間のかかる心配がありません。
業務委託のデメリット
業務委託にはメリットがある一方、デメリットも存在します。業務委託の主な2つのデメリットについてご紹介します。
社内ナレッジが蓄積されない
業務委託は社外の人材を利用するため、ナレッジが社内に蓄積されない点がデメリットの一つです。結果的に、委託先への依存度が高まってしまうおそれもあります。ナレッジが必要となる分野の業務は、自社の従業員に任せる方がよいでしょう。
業務品質の均一化が難しい
業務委託では、委託元と受託者の間に使用関係はないため、業務の進め方や時間配分を指示することができません。そのため、作業ペースや品質を把握・維持しにくく、業務品質の均一化が難しいといったデメリットがあります。
業務委託で起こりうるトラブルの事例7選
業務委託で起こる可能性が高いトラブルの事例を8つご紹介します。
コンプライアンス違反や不正
業務委託の場合、綿密にコミュニケーションを取らないと、委託者と受託者の間で信頼関係を構築しにくいものです。また、そもそも雇用契約ではなく、会社への帰属意識も低いため、コンプライアンス違反や不正を引き起こす可能性があります。
成果物の納品遅れや契約不履行
業務を委託する相手に問題があった場合、途中で音信不通になったり期日通りに納品されなかったりするリスクがあります。さらに、納品物の修正に対応してもらえない可能性についても考えておく必要があるでしょう。
再委託による業務品質の低下
再委託とは、受託者が委託業務を第三者に依頼することです。再委託を行うと、委託者と受託者、あるいはその下請けとのコミュニケーションが取りにくくなるおそれがあります。委託者の意図や望む成果が共有できず、業務品質の低下につながるため注意が必要です。再委託は、原則として禁止している場合が多いですが、なかには無断で行う受託者もいます。再受託禁止の旨と違反したときの対応について、あらかじめ決めておくことが重要です。
報酬に関する認識の相違
報酬に関連する問題は、金銭的な要素が絡むため、トラブルが生じやすくなっています。特に、報酬の支払いスケジュールや成果物の合格基準については、認識の相違が発生することも多くあります。また、支払い方法や税金関係でトラブルになるケースも多いため、注意する必要があるでしょう。
契約解除による損害賠償
契約解除による損害賠償もトラブル発生事例の一つです。業務委託契約を締結したあと、「より有利な条件の委託先が見つかった」「成果が出ない」といった理由で契約期間中に解約しようとすると、違約金や損害賠償を請求される場合があります。ただし、やむを得ない場合は損害賠償の必要はないため、相手からの合意のもとに契約解除するとよいでしょう。
契約内容の把握不足による偽装請負
業務委託でありながら、契約内容の把握不足で「偽装請負」になっていることも少なくありません。偽装請負とは、契約上は業務委託契約を締結しているにもかかわらず、委託者が受託者に指揮命令を行っている状態を指します。
業務委託契約にもかかわらず、指揮命令を行った場合、違法となる恐れがあるため注意が必要です。知らないうちに偽装請負をしてしまうことのないよう、契約内容を把握し、常に注意しておく必要があります。
情報セキュリティ不足による情報漏えい
情報セキュリティ不足による情報漏えいも、業務委託でトラブルが発生する原因です。業務を社外に委託する場合、受託者が情報を窃取したり、過失によって漏えいしたりする可能性があるでしょう。受託者が情報漏えいすると委託側の社会的信用が損なわれるため、注意しなくてはいけません。
業務委託に関するトラブルの予防方法12選
業務委託のトラブルを予防するには、次の12の方法を実践するのがおすすめです。
優良な委託先を選ぶ
トラブルの大半は、委託先の質が低いことに起因するものが多く、人柄や実績を確認しないまま契約してしまうと、トラブルが起きやすくなります。そのため、信頼できる知り合いや仲介サービスから委託先を紹介してもらい、契約前にしっかり面接することが重要です。優良な委託先を見極めて、契約を結びましょう。
委託業務の範囲を明確にする
委託業務の範囲を明確にしないと、追加料金を請求されたり業務を拒否されたりするトラブルが起こりがちです。こうしたトラブルを回避するには、できる限り具体的に業務内容を決めておくとよいでしょう。
委託業務の契約期間を決める
トラブルを防ぐには、業務委託の契約や修正、検収の対応期間、自動更新について詳細に定めておくことも大切です。特に、契約の継続については、期間満了時の更新や解約手続きを契約書に明記しておくことをおすすめします。
契約不適合責任を規定する
売買契約においては商品の品質、内容の違い、数量の不足などが生じた場合に、売主が買主に対して負う責任存在します。この責任を「契約不適合責任」といいます。
請負契約においても同様に、仕事の内容に不備があった場合は、請け負った側が契約不適合責任を負うことになるでしょう。契約不適合責任について詳細に決めておけば、契約の履行を求めて成果物や業務の修正を依頼したり、損害の補填を要求したりできます。
権利の帰属について明記する
委託業務で発生した知的財産権が委託者と受託者どちらに帰属するのかを決め、契約書に記載しておくことも重要です。また、著作者人格権の行使についても明記しておくとよいでしょう。
報酬や経費について詳細に決める
お金に関するトラブルを防ぐためには、報酬額と支払い時期を契約書に明記しておくことが重要です。また、源泉徴収税や復興税の有無に関しても詳細に決めておきましょう。加えて、業務で発生する機材購入や交通費などの請求について、費用として認められる範囲も規定しておくとよいです。
再委託を制限する
原則として、再委託は禁止することをおすすめします。再委託を許可する場合は、再委託先に求める専門性や損害が生じた際の賠償などを決めておく必要があるでしょう。
反社条項について決める
「反社条項(反社会的勢力の排除に関する条項)」とは、契約を締結する際、反社会的勢力ではない、暴力的な要求行為などをしないといったことを、相互に示して保証する条項を指します。コンプライアンスの強化や社会的責任を果たすためにも、契約書には必ず反社条項を記載しておきましょう。
情報セキュリティ対策を万全にする
情報セキュリティ対策を万全にすることも、トラブル防止に役立ちます。秘密保持契約について規定し、契約書に記載しておくとよいでしょう。また、組織における情報管理の基本原則の一つである「Need-to-know(ニードトゥノウ)の原則」を徹底することも大切です。情報を必要とする人にのみ、情報に接する権限を与えるよう心がけましょう。
準拠法を記載する
業務委託契約における準拠法とは、契約上の権利義務に適用される法律を指します。特に、国際的な取引で紛争が生じた場合、どの国の法律を適用すべきかを明確にするために重要です。そのため、準拠法を記載しておけば、国境を越えて契約を結ぶ場合に無用なリスクを回避できるでしょう。
口頭で契約しない
口頭で契約しないこともトラブル防止につながるでしょう。本来、契約は口頭でも成立しますが、裁判になった際は不利になるケースが多くあります。また、委託者と受託者間で認識の相違が生じる可能性もあります。契約する際は、きちんと書面で行っておきましょう。
契約書の法務チェックを法律家に依頼する
業務委託契約を締結する際は、弁護士や行政書士に依頼して、契約書の内容に問題がないか確認しておきます。専門家に依頼することで、法律違反をしたり、不利な条件で契約したりするリスクが軽減されます。
業務委託に関する注意点
業務委託をするときは、次の2つの点に注意が必要です。
条件を途中で変更する場合は変更契約書をつくる必要がある
契約内容を変更したり修正したりする際は、変更契約書をつくることが重要です。また、契約書の記載量が膨大な場合は、変更内容を記載した覚書や念書をつくっておきましょう。なお、覚書や念書をつくった場合は、契約書をつくり直す必要はありません。
条件によっては業務委託ではなく雇用契約として扱われる
専属性がある、勤務時間を指定するなど、業務委託契約に使用従属性がある場合、「雇用契約」と見なされる可能性があります。雇用契約と見なされてしまうと、社会保険の適用や残業代を請求されるケースがあるため、契約条件には注意が必要です。
まとめ
業務委託には、生産性向上や人件費削減などのメリットがある一方、社内ナレッジが蓄積されない、業務品質の均一化が難しいといったデメリットもあります。また、さまざまなトラブルが発生するリスクもあります。そのため、あらかじめ事例について把握しておき、対策を講じておくとよいでしょう。本記事の内容を参考にして、業務委託の検討を進めてみてください。
多様な働き方を管理する「One人事」
「One人事」は、人事労務をワンストップで支えるクラウドサービスです。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失などの労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。
労務をはじめ人材情報が分散し、業務ごとにツールを使い分けている企業は、運用の見直しとともに、クラウド化を検討してみてはいかがでしょうか。
| データ・ツールが分散している例 |
|---|
| 入退社手続き(エクセル)勤怠(タイムカード)給与計算(専用ソフト)給与明細(紙で印刷)年末調整(紙で印刷) |
情報を集約できると、勤怠管理や年末調整など幅広い業務の効率化が実現し、担当者の負担が軽減します。
「One人事」の初期費用や気になる使い心地については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門スタッフが、貴社の課題をていねいにヒアリングしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、年末調整の電子手続きをはじめ労務管理の効率化のヒントが詰まったお役立ち資料を、無料でダウンロードいただけます。労務管理をシンプルにして「本来やりたい業務」に集中したい企業は、お気軽にお申し込みください。
