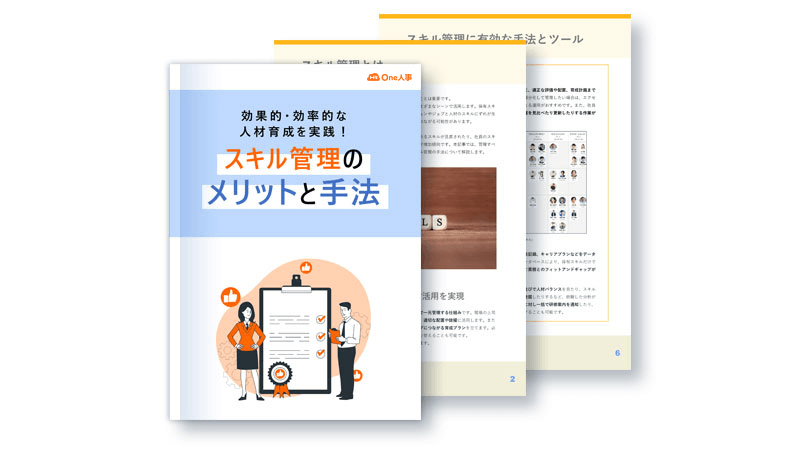偽装フリーランスとは? 問題点や見分け方、発注時の注意点を解説
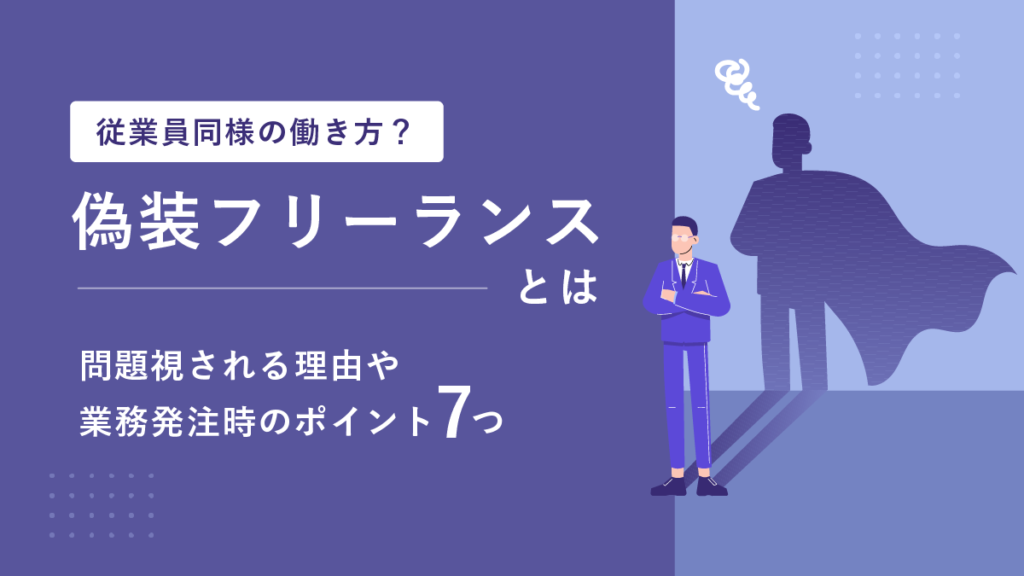
偽装フリーランスとは、表面上はフリーランスとの業務委託契約を締結しているにもかかわらず、実態は労働者同様の雇用契約になっている状態のことです。
近年は、働き方改革によりフリーランスに外注する企業も増えており、偽装フリーランスが問題視されています。偽装フリーランスの状況をつくってしまうと法律違反となる恐れもあるため、十分な注意が必要です。
本記事では、偽装フリーランスの概要や問題となる理由、フリーランスに業務を発注するときの注意点などを詳しく解説します。
 目次[表示]
目次[表示]
偽装フリーランスとは
偽装フリーランスとは、独立して自立的な立場であるはずのフリーランスが、企業に勤める労働者と同じような働き方をしている状態を指す言葉です。実態は労働者にもかかわらず、フリーランスのように偽っていることから名づけられました。
フリーランスとして働く人の中には、業務委託で発注を受けているにもかかわらず、労働者と同様に企業の指示で働いているケースも少なくありません。実質的に労働者と同様の働き方を偽装フリーランスと呼び、近年大きな問題として取り上げられています。
フリーランスとは
そもそもフリーランスとは、特定の企業に所属せず、案件ごとに契約を交わして業務を請け負う働き方のことです。
フリーランスは、企業からの業務委託を受ける「事業者」であり、「労働者」ではありません。就労場所や就業時間、請け負う業務量はフリーランスの裁量で決められるため、自由度の高い働き方を実現できます。
また、一つの企業に限定せずに、複数の企業と双方で合意したうえで仕事を受けられるため、経済的に自立しているのも大きな特徴です。
しかし、企業に所属する労働者と比較して収入が安定しづらく、労働基準法による保護が適用されません。業務に関連する知識やスキルはもちろん、スケジュール管理やコミュニケーション能力なども求められるでしょう。
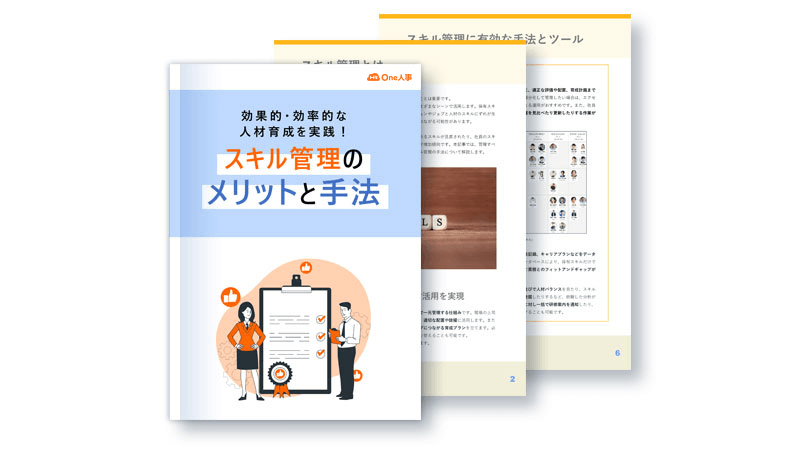
個人事業主とは
個人事業主とは、法人を設立せずに税務署へ開業届を提出し、個人で事業を営む人のことです。事業主のみで事業を行う場合だけでなく、家族や雇用した従業員などと複数の人で事業を行う場合も、法人でなければ個人事業主とみなされます。
フリーランスは開業届を提出しているか否かに関係なく、企業に所属せずに業務を請け負う人を指すため、個人事業主でありながらフリーランスとして活躍する人も存在します。
従業員とは
従業員とは、企業と雇用契約を締結して働く人のことです。企業に雇用され、就業規則にしたがって働きます。正社員に限らず、契約社員や派遣社員、パート、アルバイトも従業員です。
フリーランスとの大きな違いは、企業と雇用契約を締結しているため、指揮命令を受ける立場にあることです。
また、従業員には労働法が適用されるので、業務上の病気やケガをした際には労災補償が受けられ、最低賃金や時間外労働に対する割増賃金、休日、有給休暇なども保障されます。
偽装フリーランスが問題となる理由
本来、企業がフリーランスと仕事をする場合、両者は同じ事業者として対等な関係にあります。そのため、発注者である企業側が、フリーランスに対して指揮監督を行うことはできません。
しかし、近年では、雇用契約を締結する従業員と実態がほぼ変わらないにもかかわらず、表面上はフリーランスとして業務委託契約を結んでしまうケースが散見されます。企業が社会保険料を負担せずに、安価で融通のきく労働力として扱う事例も少なくありません。
偽装フリーランスとして働くと、フリーランスのメリットである自由な働き方を実現しづらくなるだけでなく、雇用契約を締結していれば受けられるはずの各種保障を受けられなくなるおそれもあるのです。
偽装フリーランスとして働かせた場合の罰則
企業が業務委託契約を締結した相手を偽装フリーランスとして働かせた場合は、実質的に雇用契約を締結していることになります。適用されるべき労働基準法上のルールを適用していないため、違法とみなされる恐れがあります。
万が一、契約相手を法定労働時間よりも長く働かせてしまうと、労働基準法違反となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金を科されるケースがあるため注意が必要です。
偽装フリーランスとみなされるケースとは
どのような状況が偽装フリーランスとみなされるのか、4つの観点から見分け方を詳しく紹介します。
- 発注側の指揮監督下で業務を行っている
- 発注者の指揮監督下における労務の対価として報酬を得ている
- 事業者性を持ち合わせていない
- 受注制限や時間の制約でほかの仕事が事実上難しい
発注側の指揮監督下で業務を行っている
フリーランスが発注者側である企業の指揮監督下で業務を行う場合は、偽装フリーランスとみなされます。
指揮監督下の労働であるかを見分けるポイントは、以下のとおりです。
- フリーランス側に業務依頼や指示を許諾する自由があるか
- フリーランス側が業務内容や業務の進め方について具体的な指示を受けているか
- フリーランス側が勤務場所や勤務時間などを拘束されているか
従業員と同じようにタイムカードの打刻を求めたり、マニュアルどおりの業務遂行を指導したりする行為は、偽装フリーランスとみなされる可能性が高いでしょう。
発注者の指揮監督下における労務の対価として報酬を得ている
フリーランスが受け取る報酬に、労務対償性があるかも偽装フリーランスを見分けるポイントです。労務対償性とは、取引先企業の指揮監督下における労務の対価として報酬が支払われることを意味します。
作業時間によって報酬が決まったり、仕事をしない時間の分の報酬が減額されたりする場合は、報酬の労務対償性があるとみなされるおそれがあります。日給や時給制など、時間を基準とした報酬体制には十分に注意が必要です。
事業者性を持ち合わせていない
フリーランスは事業主であるという点も重要なポイントなので、事業者性を持ち合わせていないと、偽装フリーランスとみなされる可能性があります。
たとえば、業務に必要な機器や器具などをフリーランス側が負担する場合は、事業者性が高いと判断されやすくなります。
また、フリーランスの報酬が、同じような業務に携わる従業員と比較して高額である場合は、事業者性が高いとみなされるでしょう。
受注制限や時間の制約でほかの仕事が事実上難しい
ほかの企業からの受注制限や時間的な制約を受ける場合は、企業に対する専属性が高いとみなされます。フリーランスは、依頼された仕事をすべて請け負う必要はなく、苦手な仕事は断ったり、条件を提示したりして自由に選べる働き方です。
仕事を請け負うことでほかの業務の時間を捻出できなくなる場合は、偽装フリーランスとみなされるおそれがあるため注意しましょう。
偽装フリーランスと偽装請負との違い
偽装フリーランスと似た言葉に、偽装請負があります。両者の違いについて詳しく解説しましょう。
偽装請負とは
偽装請負には2つの意味合いがあります。
1つは業務委託契約を締結しているにもかかわらず、実態が雇用契約である場合で、偽装フリーランスと同じ意味を持ちます。
もう1つの偽装請負とは、書類上や形式上は請負契約であるにもかかわらず、実態は労働者派遣が行われている状況を指します。本記事では、実態が労働者派遣の意味における偽装請負を解説します。
偽装請負には以下の4つのパターンがあります。
| 偽装請負のパターン | 内容 |
|---|---|
| 代表的型 | 請負としながらも、発注者による細かな指示や勤務管理が行われている |
| 形式だけ責任者型 | 現場には形式上の責任者を置いているものの、発注者の指示を個々の労働者に伝えているだけで、実態は発注者が指示をしているのと同じ状況である |
| 使用者不明型 | 委託先や受託先の関係が複雑に絡み合っており、どの企業と請負契約をしているのかわからない |
| 一人請負型 | 斡旋された企業が労働者ではなく、個人事業主として請負契約を締結し、業務の指示や命令をして働かせている |
偽装請負の場合の法律違反
偽装請負とみなされた場合、企業は以下の法律に違反していると判断されます。
- 労働者派遣法
- 職業安定法
違反した条項によって、指導や勧告、公表の対象となり得るため注意が必要です。
偽装請負に該当しないかを判断する基準として、『労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準』があります。詳しい内容は、厚生労働省の『労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド』を確認しましょう。
参照:『労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド』厚生労働省
参照:『労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準』厚生労働省
フリーランスに業務を発注するときの注意点7つ
フリーランスに業務を発注する際に注意すべきポイントを紹介します。
- 偽装フリーランスの疑いを持たれる状況をつくらない
- フリーランス新法(フリーランス保護新法)が定める義務を果たす
- 依頼目的を明確にする
- 業務委託料を定める
- 知的財産権に関連するルールを定める
- 業務に必要な機材の所有者がフリーランスであるかを確認する
- 他業務を受けることを妨げていないかをチェックする
偽装フリーランスの疑いを持たれる状況をつくらない
偽装フリーランスを疑われるような状況をつくってしまうと、労働基準法をはじめとする関連法令に違反するおそれがあります。
内閣官房や厚生労働省が2021年に公表した『フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン』や、フリーランス協会が2024年2月に公表した『偽装フリーランス防止のための手引き』などを参考にしながら、業務の発注方法を検討しましょう。
参照:『フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン』厚生労働省
参照:『「偽装フリーランス防止のための手引き」を公開します』フリーランス協会
フリーランス新法(フリーランス保護新法)が定める義務を果たす
フリーランス新法とは、業務委託を受けるフリーランスを保護するために制定された法律です。フリーランスに業務を委託するすべての事業者を対象としています。2023年5月に公布され、2024年11月1日施行予定です。
「書面などによる取引条件の明示」「報酬支払期日の設定・期日内の支払い」「禁止行為」などの義務が定められており、発注事業者は要件ごとに義務を果たすよう求められています。
参照:『フリーランスの取引に関する 新しい法律が11月にスタート!』中小企業庁
依頼目的を明確にする
フリーランスに業務を依頼する目的を明確にしたうえで、目的に合わせた契約を締結しましょう。
たとえば、成果物を完成させることが目的であれば「請負契約」、成果物のない事務処理が目的であれば「準委任契約」を選択します。
業務委託料を定める
フリーランスに業務を委託する場合は、業務委託料の金額をはじめ、支払期日や支払方法を明確に定めることが大切です。
業務委託は、契約形態によって報酬の対象が異なります。請負契約の場合は成果物に対して報酬が支払われるため、完成させるために必要とされるスキルや経験をもとに報酬を定めます。
一方で、準委任契約は、スキルや経験に応じた業務遂行そのものに対して報酬を支払います。
作業時間によって割増報酬を支払ったり、余った契約時間に委託した業務以外のタスクを課したりする行為は、偽装フリーランスとみなされるおそれがあるため注意します。
交通費や旅費、通信費など業務を遂行するためにかかった費用については、別途支給するか否かルールを定めておきましょう。
知的財産権に関連するルールを定める
委託した業務で発生した楽曲やイラスト、デザインなどの知的財産権は、契約書に規定がない限り発注先に移転しません。知的財産権を確保したい場合は、契約書で定めておきましょう。
業務に必要な機材の所有者がフリーランスであるかを確認する
業務を遂行するにあたって必要な機材がある場合は、機材の所有者がフリーランスになっているかを確認しましょう。万が一、企業側が提供している場合は、事業者性がないと判断されやすくなってしまいます。
ただし、機密情報の漏えいを防止する目的でセキュリティソフトを支給するなど、合理的な理由が認められる場合は、支給しても偽装フリーランスとは判断されないでしょう。
他業務を受けることを妨げていないかをチェックする
フリーランスは、自分の裁量で複数の企業から業務を請け負えます。業務を発注することでほかの業務を妨げてしまう行為は、独占契約を締結しているとし、偽装フリーランスとみなされるため注意が必要です。
専属契約が認められるのは、特別な事情がある場合のみです。発注側である企業が専属契約を強要することは、独占禁止法違反とみなされる可能性があるため気をつけましょう。
参照:『フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン』内閣官房|公正取引委員会|中小企業庁|厚生労働省
フリーランスを活用して業務効率化や生産性向上へ
偽装フリーランスとは、フリーランスとして契約を結んでいるにもかかわらず、実際は労働者と変わりない働き方を促している状態です。
働き方が多様化する中で、フリーランスを活用する動きが年々盛んになっています。しかし、安易にフリーランスと業務委託契約を締結して労働者と同様に取り扱う行為は、法律違反となるため注意します。
本記事で紹介した内容を参考にしながら、フリーランスに委託する具体的な業務内容に問題はないか、雇用契約とみなされる点がないかを確認する必要があります。フリーランスを適切に活用して、業務効率化や生産性向上を目指しましょう。