会社の熱中症対策は何をする?【2025年6月義務化】内容と罰則、対応を解説
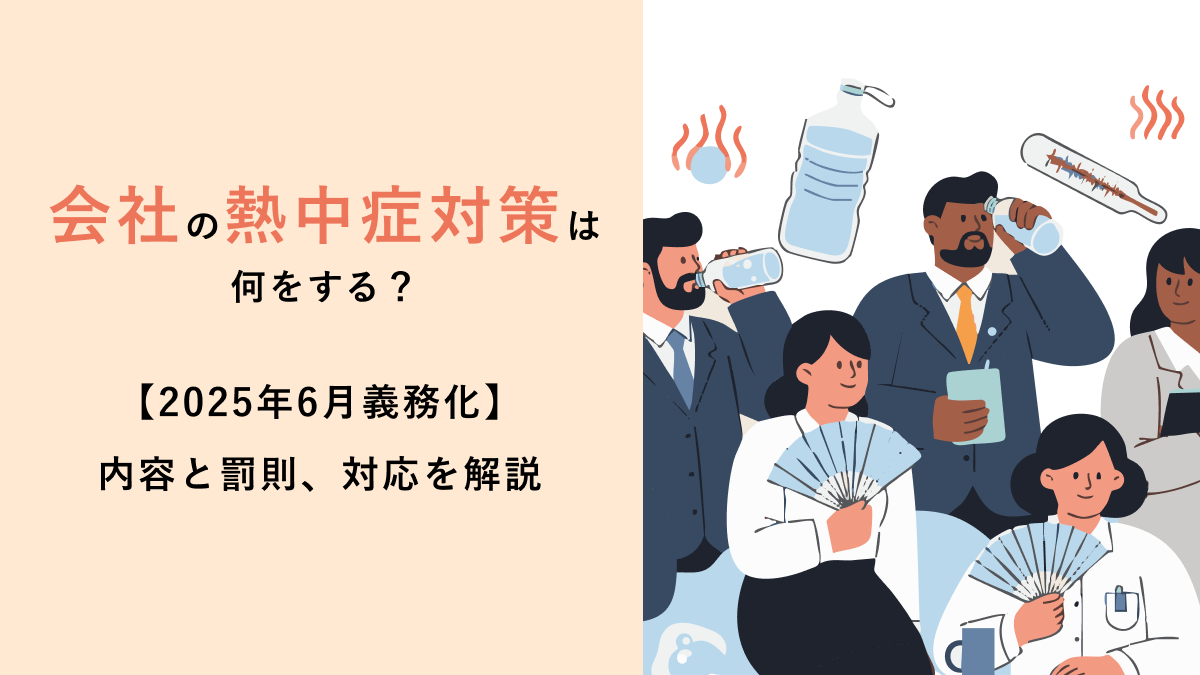
2025年6月、企業における熱中症対策が義務化されました。「努力義務」とされてきた熱中症対策が、法改正によって明確に会社の責任となり、対応を怠れば罰則の対象となりました。
会社がやるべき熱中症対策について「どこまで何をすればよいのか」「具体的な対応手順や罰則は?」と不安を感じている労務管理担当者も多いはずです。
本記事では、2025年6月施行の労働安全衛生法規則改正による熱中症対策義務化の内容や背景、会社が講じるべき具体的な対策、違反時の罰則までを詳しく解説します。

 目次[表示]
目次[表示]
会社の熱中症対策が2025年6月から義務に|内容と罰則
2025年6月1日から、企業には職場での熱中症対策が法律で義務づけられました。
背景には、近年の猛暑による熱中症リスクが増大し、死亡災害が増えている状況にあります。従来の努力義務だけでは十分な対策が徹底されず、建設業や製造業を中心に、毎年多くの労働災害が発生していたのです。
新しい規則では、WBGT値(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間以上作業を行う場合、事業者は以下の対応が求められます。
- 熱中症の早期発見や重篤化防止のための体制整備
- 従業員への周知徹底
- 緊急時の対応手順の明確化
- 作業環境のWBGT値測定と管理
- 適切な休憩や水分補給の確保
違反した場合、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金、法人には、50万円以下の罰金が科される可能性もあります。
会社による熱中症対策の義務化により、企業は従業員の健康管理に対する責任がいっそう重くなりました。労務管理担当者は、法改正の内容を正確に把握し、自社の現場に必要な実践的対策を進めていきましょう。

勤務時間中の熱中症は会社の安全配慮義務違反?
勤務時間中に熱中症が発生した場合、企業が従業員の健康と安全に十分な配慮をしていなければ、安全配慮義務違反と判断されることがあります。
労働契約法第5条では、企業に対し、「従業員が安全かつ健康に働けるよう必要な措置を講じる義務」が定められています。
熱中症は命にかかわるリスクがあるため、企業が適切な対策を怠ると、損害賠償請求や社会的信用の低下といった重大な問題につながります。
リスクを回避するためにも、企業は熱中症対策を徹底し、従業員の命と健康が守られる体制を整えましょう。
安全配慮義務とは
安全配慮義務とは、企業が従業員の生命や健康を守るために必要な配慮をする法的責任のことです。労働契約法第5条に定められています。
たとえば、職場の温度や湿度の管理、十分な休憩時間の確保、定期的な健康診断の実施が具体例です。
熱中症対策も安全配慮義務の一部です。近年の猛暑を背景に、職場での熱中症リスクは高まっています。
従業員が安心して働ける環境を維持することが企業に強く求められています。適切な対策を怠れば、従業員が熱中症で倒れた場合に安全配慮義務違反となる可能性も大きくなるため注意が必要です。
熱中症が安全配慮義務違反とみなされるケース
熱中症が安全配慮義務違反と認定されるかどうかは、主に3つの基準で判断されます。
- 企業が熱中症の発生を予見できたか(予見可能性)
- 適切な対策を講じていれば防げたかどうか(結果回避性)
- 労働者側に過失がなかったかどうか(労働者の過失の有無)
気温や湿度が高い日であれば、企業は熱中症のリスクを予測し、事前に対策をとらなければなりません。
空調設備を使わなかったり、休憩や水分補給の指示を怠ったりした場合は、企業の配慮不足が熱中症発生の原因とみなされるでしょう。結果として、熱中症と企業の行為との間に因果関係が認められる可能性が高くなります。
一方で、企業が十分な対策や指導を行っていたにもかかわらず、労働者が指示に従わなかった場合は、企業の責任が軽減されることもあります。

熱中症対策・予防の基本をおさらい!
熱中症は、正しい予防策を知り、日常生活で意識すれば防げる災害です。
それでも毎年、気温が高くなる季節になると、職場や学校、家庭などさまざまな場所で熱中症の事故があとを絶ちません。
高温多湿な環境では、誰でも熱中症になるリスクがあります。熱中症予防の基本をおさえて、日々の生活や業務のなかで実践していきましょう。
- 高温環境下での活動を避ける
- こまめに水分を補給する
- 涼しい衣服を身につける
- 冷房器具を活用する
高温環境下での活動を避ける
熱中症を防ぐには、高温多湿な環境での無理な作業を避けることが基本です。気温が高い日中は、屋外や工場内での長時間作業はできるだけ控えましょう。
やむを得ず作業を行う場合は、日陰や風通しのよい場所を確保します。
また、天気予報や暑さ指数(WBGT)を確認し、作業時間や作業内容を柔軟に調整することが重要です。
気温が上がる前の朝や夕方に重点的に作業を進める、暑さが厳しい時間帯は休憩を増やすなど、計画的に運用しましょう。
小さな工夫を積み重ねることで、熱中症のリスクは、大きく減らせます。
こまめに水分を補給する
熱中症を防ぐうえで、水分補給はもっとも基本的な対策です。のどが渇く前から、少量ずつこまめに水分をとる習慣を徹底しましょう。
高温環境や汗を多くかく作業では、適度な塩分補給も必要です。大量に汗をかいた場合は、水分だけでなく、スポーツドリンクや経口補水液、塩分を含む飴やタブレットなどを利用します。
水だけを大量に摂取すると、体内の電解質バランスが崩れ、体調不良を招くこともあります。作業前に飲料を準備し、作業中も声がけをして補給を促すなど、職場全体で意識を高めていきましょう。
涼しい衣服を身につける
熱中症を防ぐためには、衣服の選び方も重要なポイントです。通気性や吸湿性、速乾性に優れた素材の作業服やユニフォームを着用しましょう。綿や麻などの天然素材や、汗を素早く乾かす機能性素材の服装がおすすめです。
色は白や淡い色を選ぶと、熱を反射して体温の上昇を抑えられます。 直射日光下では、ヘルメットや帽子に取りつけられる日よけカバーを活用すると効果的です。
また、冷感素材のインナーやファンが付属された作業服なども人気です。 職場の環境や作業内容に合わせて、必要な装備を準備しましょう。
冷房器具を活用する
熱中症を防ぐためには、作業場や休憩所における冷房器具の使用が欠かせません。高温多湿の環境で、光熱費を気にして冷房を控えると、室内でも熱中症のリスクが高まります。
エアコンの設定は、室温28度以下、湿度50~60%程度を目安に管理するのが適切といわれています。扇風機も併用すると、空気の流れが生まれ、体感温度を下げやすくなります。
工場や倉庫などでは、換気扇を稼働させる、カーテンやシェードで直射日光を遮るなどの工夫も、室内温度の上昇を防ぐには効果的です。
職場で使う冷房器具は、安全に配慮しながら積極的に活用しましょう。

熱中症対策で会社は具体的に何をする?
企業が従業員の健康と安全を守るためには、熱中症対策を計画的、具体的に実施することが重要です。
2025年6月により、会社には作業環境や従業員の健康状態を常に把握し、適切な対応をとる責任が求められるようになりました。
厚生労働省の指針では、熱中症対策を「5つの柱」に沿って進めることが推奨されています。
- 作業環境管理
- 作業管理
- 健康管理
- 健康管理
- 労働衛生教育
- 応急処置
実務で役立つ具体策を確認し、 自社の取り組みを見直していきましょう。
作業環境管理
作業環境の管理は、職場での熱中症予防の基本です。屋外では日差しを遮る屋根やテントを設置し、直射日光や地面からの照り返しを防ぎましょう。作業者の体温上昇を抑えられます。
屋内では、エアコンや扇風機を併用し、室温と湿度を適切に管理することが大切です。休憩場所は日陰や冷房の効いたスペースに設け、冷たい飲み物やおしぼりを常備しましょう。
冷房つきの休憩車両を導入した建設現場では、熱中症による救急搬送がゼロになった事例も報告されています。
作業管理
作業管理も、熱中症予防のために欠かせない取り組みです。暑さがもっとも厳しい昼間の作業を避け、朝や夕方など比較的涼しい時間帯に作業を進めることで、従業員の負担を大きく減らせます。
作業時間そのものを短縮したり、休憩時間を延長したりすることも大切です。作業工程を見直し、無理のないスケジュールを組むだけで、体調不良や事故のリスクを抑えられます。
また、現場ごとに暑さ指数(WBGT)や気象情報をこまめに確認し、作業計画に反映させることも重要です。
熱中症リスクを最小限に抑えるため、日々の作業管理を見直しましょう。
健康管理
健康管理は、従業員一人ひとりの体調を守るうえで欠かせない取り組みです。作業前や作業中に体調をチェックし、自覚症状がなくても、少しの異常があればすぐに休ませましょう。熱中症の重症化を防げます。
従業員が体調不良を訴えやすい雰囲気づくりも大切です。上司や同僚が声をかけ合い、無理をしないよう促すことで、早期発見につながります。バディ制(2人1組でお互いの体調を確認し合う制度)を導入すれば、見落としを防ぐことが可能です。
熱中症の初期症状は、軽いめまいやだるさなど見逃しやすいものが多いようです。日々の健康観察を徹底して、全員で安全意識を高め、職場全体の安心につなげましょう。
労働衛生教育
労働衛生教育は、熱中症の予防と早期対応のために欠かせない取り組みです。熱中症の症状や予防方法、応急処置の流れを周知し、必要な場面で適切に行動できるようにしましょう。
たとえば、研修や朝礼時の注意喚起、ポスターの掲示に加え、eラーニングを活用すると、
日常的に安全意識を高められます。
現場リーダーや管理職が率先して熱中症対策に取り組む姿勢を示すことで、職場全体の安全意識が高まります。教育と周知を徹底し、熱中症ゼロを目指しましょう。
応急処置
会社における熱中症対策では、応急処置の準備と社内での流れの共有も不可欠です。
万が一に備え、受診可能な病院をリストアップしておきましょう。いざというときに、迅速な対応が可能となります。日頃から応急処置の流れを確認し、医療機関に連絡して搬送する手順を、全従業員に周知徹底しておくことが重要です。
症状が出た場合はすぐに作業を中止し、涼しい場所で体を冷やしながら休ませます。冷却用のタオルや氷、経口補水液といった応急処置グッズの常備も欠かせません。
緊急時の体制を整えることで、万が一の際にも落ち着いて適切な対応ができ、従業員の安全と健康を守ることにつながります。
熱中症対策は「WBGT値(暑さ指数)」の活用も有効
熱中症対策を強化するうえで、WBGT値(暑さ指数)の活用はとても有効です。気温だけでなく、湿度や輻射熱(放射熱)を総合的に評価できるため、現場のリスクを正確に把握しやすくなります。
2025年6月の法改正で、WBGT値の測定と管理も企業の義務として明確化されました。
会社はWBGT値を日常的に測り、数値に応じた対策を計画的に実施しましょう。従業員の安全を守るためにも、WBGT値を活用した熱中症対策をおすすめします。
WBGT値とは
WBGT値(Wet-Bulb Globe Temperature)は、熱中症リスクを評価する国際的な指標です。気温や湿度、輻射熱など複数の要素を組みあわせて、人体が受ける熱ストレスを総合的に示しています。
WBGT値は、通常の温度計では測れない「体感的な暑さ」を数値で表現できるのが特徴です。同じ気温でも湿度や日差しで値が変わり、熱中症対策の現場では、活動の可否を判断する基準となります。
WBGT値が高いほど熱中症のリスクも上昇するため、こまめに測定し、管理を徹底しましょう。
作業強度に応じた指数
WBGT値は、作業の強度によって基準値が異なります。安静時や軽作業では33℃前後、中程度の作業では30℃前後、重作業では28℃前後が目安です。熱に慣れていない人の場合は、1℃程度低い値で判断します。作業強度別の基準値は以下のとおりです。
| 作業強度 | 例 | WBGT基準値(熱順化あり/なし) |
|---|---|---|
| 安静 | 座って休む、軽い事務作業 | 33℃ / 32℃ |
| 低代謝率 | 軽い手作業、点検、組立、歩行 | 30℃ / 29℃ |
| 中程度代謝率 | くぎ打ち、草むしり | 28℃ / 26℃ |
| 高代謝率 | ショベル作業、草刈り、土堀り、重量物を運ぶ | 26℃ / 23℃ |
| 極高代謝率 | 階段昇降、走る、激しく動く | 25℃ / 20℃ |
WBGT値の基準値を超える場合は作業を中止したり、休憩時間を延長したりする対応が必要です。
参考:『暑さ指数(WBGT値)』職場のあんぜんサイト (厚生労働省)
WBGT値を低減させる方法
WBGT値(暑さ指数)を下げるには、作業環境の工夫が不可欠です。
屋外作業では、テントやシェードで直射日光や地面からの照り返しを防ぎ、散水やミストシャワーを活用しましょう。
屋内作業では、エアコンやスポットクーラーを設置し、室温と湿度を適切に管理します。
作業服を通気性や吸湿性に優れた素材に変更したり、冷却ベストを着用するなど、個人での対策も有効です。
WBGT値の基準値を超えた際は、作業を調整し、必要な休憩や水分補給を徹底しましょう。従業員の安全を守る取り組みを継続することで、職場全体の熱中症リスクを減らせます。
勤務時間中の熱中症は労災認定される?
勤務時間中に発症した熱中症は、一定の条件を満たすと労災として認定されます。労働基準法施行規則でも「暑熱な場所における業務による熱中症」は、業務上の疾病として明記されています。
なぜ労災にあたるのでしょうか。
会社には従業員の健康と安全を守る法的責任があります。業務に起因して熱中症を発症した場合、労災保険の給付対象となります。屋外作業や高温多湿な環境での業務中の発症は、業務との関連性が認められやすいでしょう。
一方で、持病の悪化や業務と関係のない私的な行動が原因の場合は、業務起因性が認められず、労災認定の対象外となることがあります。
労災認定の基準や過去の事例を理解し、従業員が安心して働ける環境を整えることが重要です。会社としては、熱中症発症時の対応手順や申請方法を周知し、適切なサポート体制を整えましょう。
従業員が熱中症になったときの対処法
どれだけ予防を徹底していても、会社で熱中症が突然発症することも考えられます。万一のときに備えて、症状の見分け方や応急処置の流れを紹介しましょう。
熱中症の症状には、以下のようなものがあります。
- めまい、立ちくらみ
- 頭痛、吐き気、倦怠感
- 異常な発汗、筋肉のけいれん
- 意識がもうろうとする、呼びかけに反応しない
- 「ボーッとしている」「イライラしている」「フラフラしている」など、様子がおかしい場合
症状が見られたら、すぐに対応を始めましょう。一般的な熱中症の応急処置の手順は以下のとおりです。
| 涼しい場所への移動 | 直射日光を避け、冷房の効いた室内や日陰に移動させます。 |
| 衣服をゆるめて体温を下げる | 衣服をゆるめ、首・脇の下・太ももの付け根など太い血管の部分を氷や冷たいタオルで冷やします。 |
| 体をあおぐ | うちわや扇風機で体をあおぎ、熱を逃がしましょう。 |
| 水分・塩分の補給 | 意識がはっきりしていれば、スポーツドリンクや、経口補水液で水分と塩分を補給します。 |
次の場合は、すぐに作業を中止し、119番で救急車を呼びます。
- 呼びかけに反応しない
- 意識がもうろうとしている
- けいれんや嘔吐がある
意識障害がある場合は、無理に水分を飲ませると誤嚥の危険があるため、口から水分を与えてはいけません。救急車を待つ間も、涼しい場所に移動させ、衣服をゆるめ、体を冷やす応急処置を続けましょう。
参照:『熱中症について学ぼう:応急処置のポイント』株式会社ヒロモリ/一般財団法人日本気象協会
まとめ
2025年6月1日から労働安全衛生規則の改正により、企業には熱中症対策が法的に義務づけられました。従業員が安全に働ける環境を整える責任は、すべての事業者に課されています。今回の改正では、患者の報告体制や重症化を防ぐ対応手順の整備、関係者への周知が求められています。
適切な熱中症対策を怠れば、罰則が科されます。企業はWBGT値の測定・管理をはじめ、作業環境や気象条件に応じた予防措置を徹底し、健康被害を未然に防がなければなりません。
会社での熱中症対策の徹底は従業員の命を守るだけでなく、企業への信頼にもつながります。新しい法令を正しく理解し、確実に実践しましょう。
