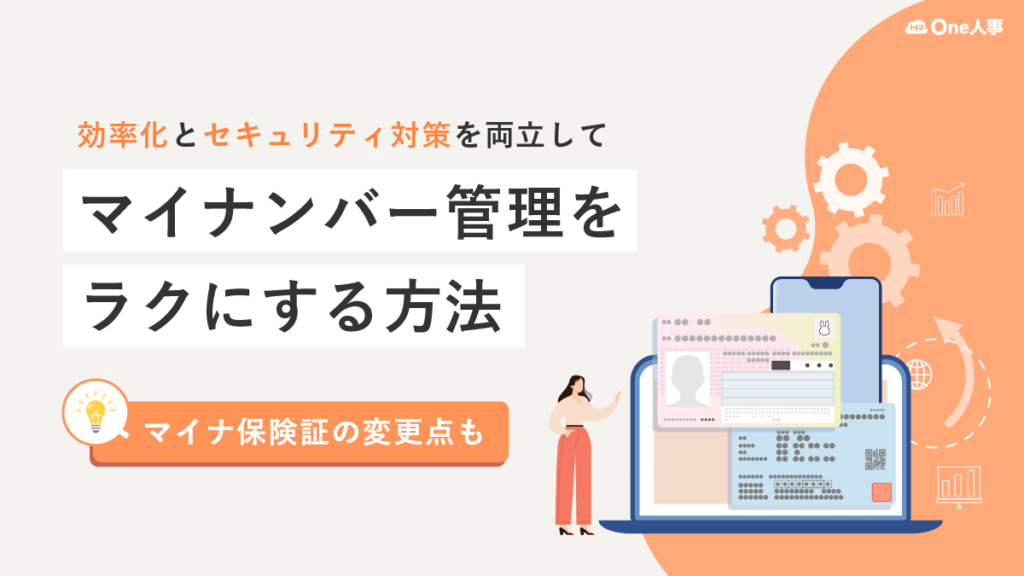入社手続きに必要な書類【一覧表】そろわない場合の対応も会社側向けに解説

「入社手続きの書類はこれで全部そろっているか」「期限までにそろわなかったらどうすればいいか」と不安を感じたことはありませんか。入社手続きは、新しい従業員が1日でも早く活躍できる環境を整えるための業務です。社会保険や税務関連の手続きなど、期限が決まっている書類も多く、不備や提出遅れは双方に影響を与えます。とくに中途採用は、時期が不定期なので、毎回確認に時間がかかり、手間がかかることもあるでしょう。
本記事では、入社手続きに必要な書類を「企業側」と「従業員側」に分けて一覧で解説します。書類がそろわない場合の対処法や、書類管理を効率化する方法まで紹介しているので、日々の負担を減らすために、ぜひ活用してみてください。
入社手続きの不安は、これ1冊|完全ガイドは以下より無料ダウンロードできます。

 目次[表示]
目次[表示]
入社手続きで会社が用意する書類【一覧表】
入社手続きでは、会社が従業員に対して用意する書類が多数あります。提出が法的に義務づけられている書類もあり、抜け漏れがないよう整理しておきましょう。
入社手続きに必要な書類の一覧表は以下のとおりです。「用途・目的」「必須か/任意か」「新卒と途中どちらに必要か」という観点でまとめています。
| 書類名 | 用途・目的 | 必須/任意 | 新卒/中途 |
|---|---|---|---|
| 労働条件通知書 | 労働条件の明示(法定義務) | 必須 | 両方 |
| 雇用契約書 | 労働契約の取り交わし | 任意 | |
| 扶養控除等申告書 | 所得税の扶養状況申告(年末調整) | 必須 | |
| 健康保険被扶養者異動届 | 扶養家族の保険加入手続き | 扶養家族がいる場合必須 | |
| 採用通知書(内定通知書) | 採用の正式通知 | 任意 | |
| 入社誓約書 | 就業規則遵守の誓約 | ||
| 身元保証書 | 損害賠償の保証契約 |
以上の入社書類は、新卒・中途いずれも回収が必須です。回収にあたって、書類の役割や注意点を具体的に見ていきましょう。

労働条件通知書(雇用契約書)【必須】
労働条件通知書は労働基準法第15条によって義務づけられた書類です。賃金や就業時間、勤務地、契約期間など契約内容を明示し、企業と従業員双方の認識違いを防ぐ役割があります。作成では会社名を記入したうえで、押印することが一般的です。
また雇用契約書は、双方が合意した労働条件を証明する書類です。「労働条件通知書兼雇用契約書」として労働条件通知書と一体化することもできます。
必ず用意する労働条件通知書とは異なり、雇用契約書単体の作成は任意です。作成するのであれば、双方が署名と捺印をすることが望ましいでしょう。
扶養控除等申告書【必須】
扶養控除等申告書は税金の手続きに必要で、給与から控除される所得税の計算に影響する入社書類です。
提出がないと、年末調整で従業員が扶養控除や配偶者控除を受けられなくなってしまいます。
また、扶養控除等申告書は扶養家族がいなくても提出してもらうのがポイントです。担当者は、入社手続きを行う際、新入社員全員ぶんを回収しなければなりません。
会社が用意した書類に必要事項を記入してもらったうえで回収しましょう。
健康保険被扶養者異動届・国民年金第3号被保険者届
入社手続きのなかでも、社会保険の加入手続きに必要な書類です。扶養家族を健康保険や年金に加入させるときに提出してもらいます。
家族の収入状況によって加入が決まるため、要件を満たしているかもあわせて確認しましょう。
扶養控除等申告書と同様に、会社が書類を用意し、従業員が記入したうえで提出してもらいます。ただし、健康保険被扶養者異動届は、条件を満たす扶養家族がいるときだけ回収する点が違います。
また、国民年金第3号被保険者関係届は、年収130万円未満の配偶者がいる場合に提出してもらう書類です。
採用通知書(内定通知書)
正式な採用を通知するための入社書類で、法律では発行する義務はないため、作成は任意です。採用通知書にも会社側の署名・捺印を入れることが一般的です。
会社側の都合で身勝手に採用通知を取り消すと、違法となる可能性があるため、入社手続きの一環で書類を準備する場合は慎重に手配しましょう。
採用通知書に「内定承諾書」を添えて対応する企業もあります。
入社誓約書(入社承諾書)
入社誓約書は、入社手続きのなかで、会社のルールを守ることを誓約してもらうための任意作成書類です。就業規則や服務規律、秘密保持(NDA)、競業避止義務、個人情報の保護などに関する内容を記載します。
入社の意思を確認するために「入社承諾書」を兼ねる場合もあり、新入社員に署名と捺印を求めることが一般的です。
身元保証書
新しく入社する社員が問題を起こした場合、将来の賠償責任を明確にする書類です。
労働基準法第16条により、損害賠償予定の契約は禁止されていますが、「身元保証契約」については認められているため、任意で作成できます。
身元保証人には親族(両親・配偶者など)を指定することが一般的です。
書類には保証人の署名・捺印を求める場合が多く、印鑑証明書の提出を求める会社もあります。
企業によっては、身元保証人を必須としないケースもあるため、自社の状況と照らし合わせ、入社手続きで提出を求めるか判断しましょう。
▼入退社手続きでやることチェックリストは以下よりご確認ください。
入社手続きで内定者から必ず回収する書類など【一覧表】
入社手続きでは会社が用意するだけでなく、内定者から提出してもらう書類や情報もあります。
必ず回収しなければならない書類も多く、とくに社会保険や税金の手続き関連は、公的期限があるため、入社時に確実にそろえなければなりません。
入社手続きで、内定者から必ず回収する書類などの一覧表は、以下のとおりです。
| 書類・情報名 | 概要 | 必須/任意 | 新卒/中途 |
|---|---|---|---|
| マイナンバー | 社会保険・税金手続きに使用 | 必須 | 両方 |
| 基礎年金番号 | 社会保険手続きで使用 | 必須(マイナンバーで手続き可能な場合は不要) | 両方 |
| 雇用保険被保険者証番号 | 雇用保険手続きで使用 | 必須 | 中途のみ |
| 源泉徴収票 | 年末調整で使用 | 必須 | 中途のみ |
| 給与振込先の情報 | 給与支払いで使用 | 任意 | 両方 |
以上の入社書類は、新卒・中途で少し異なる点があるため、各書類の役割や注意点を詳しく解説していきます。

マイナンバー
マイナンバーは社会保険や雇用保険、税金関係の手続きで使用する12桁の番号です。提出方法は以下の2とおりです。
| 取得・未取得 | 提出内容 |
|---|---|
| マイナンバーカードを取得している | カードの表面と裏面のコピー |
| マイナンバーカードを取得していない | ・通知カードまたはマイナンバー記載の住民票の写し ・本人確認書類(例:運転免許証やパスポート) |
入社手続きの際に、従業員のマイナンバーを収集するには「利用目的」を説明する必要があります。厳重に取り扱わないとならないため、目的以外の用途では使用できません。
万一、新入社員が本人確認書類を準備できない場合、健康保険証と年金手帳を提示することで認められます。
マイナンバーは個人が特定される重要な情報であり、企業が回収する場合も、法律に沿った管理が求められます。マイナンバーを適切に管理するには以下の資料をお役立てください。
基礎年金番号
基礎年金番号は社会保険の各種手続きで使用する10桁の番号です。2022年4月以前に発行されている年金手帳や基礎年金番号通知書で確認できます。
2022年4月以降は、年金手帳の新規発行が廃止され、新たに「基礎年金番号通知書」が交付されるようになりました。
年金手帳を持っていない新入社員は、基礎年金番号通知書を確認、または発行してもらうようにしましょう。再発行手続きは、管轄の年金事務所で行います。
本人が年金手帳を保管している場合、コピーを会社側に提出してもらいます。
ただしマイナンバーの提出をもって、入社手続きを行う場合は、基礎年金番号の提出は不要です。
雇用保険被保険者証番号
雇用保険被保険者証番号は「4桁-6桁-1桁」で構成される11桁の番号です。過去に雇用保険に加入したことがある人に付与され、アルバイトやパートでも、条件を満たしていれば被保険者番号を持っています。
新卒社員の場合、新しく発行(加入)手続きが必要です。
番号が記載されている雇用保険被保険者証は、基本的に勤務先が保管し、退職時に従業員へ返却されます。
万一、新しい中途社員が紛失した場合は、ハローワークで前職の会社名から照会が可能なことを案内しましょう。再発行の際は、「雇用保険被保険者証再交付申請書」に記入し、一緒に本人確認書類の届け出が必要です。
源泉徴収票
源泉徴収票は、前職での給与収入額と源泉徴収額を確認する書類で、年末調整に使用します。前職を退職した年と自社に入社した年が同じ中途入社者からは、回収しなければなりません。ただし、入社のタイミングによっては提出が不要になります。
年末に退職し、前の会社で年末調整を終えたあと、年明け(1月以降)に入社する場合、提出されなくても問題ありません。ただし、翌月払いなど支払いスケジュールの関係上、1月に前職の給与の支給がある場合には提出が必要です。
また、新卒でもアルバイト収入があると提出が必要なこともあります。
転職者が源泉徴収票を紛失していたら、前職の会社に再発行を依頼するよう案内しましょう。
給与振込先の情報
給与振込先の情報は、従業員の給与を正しく振り込むために重要です。金融機関名・支店名・口座種別(普通・当座など)・口座番号を把握しなければなりません。
提出方法は企業ごとに指定しても問題ありません。一般的に以下の方法が採用されています。
- 給与振込届出書/口座振込依頼書(企業によって名称が異なる)
- 通帳のコピー
- オンライン(人事労務システムのアカウントを発行し、本人に入力してもらう)
給与支払いの口座指定をはじめ、入社書類はシステムを利用すると手早く簡単に回収できます。書
類のやり取りが増えるとミスも発生しやすくなるため、煩雑さを感じているなら入社手続きに対応した労務管理システムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
→One人事[労務]に関する製品資料の無料ダウンロードは【こちら】
入社手続きで任意で回収する書類など【一覧表】
入社手続きでは法的に必須ではないものの、用意してもらうと入社後の人材管理に役立つ資料があります。
たとえば、保有スキルを把握するための免許・資格証明書や、現在のコンディションを確認するための健康診断書です。
| 書類名 | 概要 | 必須/任意 | 新卒/中途 |
|---|---|---|---|
| 人事管理用の書類 | 個人情報や緊急連絡先の記録 | 任意 | 両方 |
| 住民票記載事項証明書 | 本人確認や住所確認 | 任意 | 両方 |
| 免許・資格証明書 | 業務に必要な資格の確認 | 任意(職種により必須の場合あり) | 両方 |
| 卒業証明書・成績証明書 | 学歴・成績の確認 | 任意 | 新卒のみの場合が多い |
| 退職証明書 | 前職での在籍確認 | 任意 | 中途のみ |
| 健康診断の結果 | 健康状態の確認 | 任意 | 両方 |
会社のルールや用途に応じて、回収を検討しましょう。それぞれ以下で詳しく紹介します。
人事管理用の書類
従業員調書とも呼ばれる書類で、人事管理の基本情報として回収します。緊急連絡先、家族構成、通勤経路などの情報を記入してもらいましょう。
履歴書で代用する場合もありますが、入社手続きの際に、本人が人事管理システムへ直接入力し、デジタルで管理する企業も増えてきました。
家族手当や通勤手当の申請条件となるため、常に最新の情報に更新しておくことが大切です。
住民票記載事項証明書
本人確認や住所確認のために使用する入社手続きの書類です。住民税の支払い手続きや労働者名簿の作成にも利用します。
個人情報保護の観点から一般の住民票とは異なり、必要な情報のみ記載されているため、企業が採用するケースもあります。
発行場所は従業員が住む区町村の役所、有効期限は発行から3か月以内が一般的です。
免許・資格を証明する書類
業務に必要な資格の証明書を提出してもらいます。資格証明が必要な職種や職場の例は以下のとおりです。
- 運転免許証(営業車の運転、配送業務など)
- 宅地建物取引士証(不動産業務)
- フォークリフト運転技能講習修了証(倉庫作業・物流業務)
- 電気工事士免許(電気設備工事・メンテナンス業務)
- 危険物取扱者資格(ガソリンスタンド・工場の管理業務)
- TOEICスコア証明書(通訳・翻訳・海外営業)
資格手当制度を設ける場合は、証明書の提出を必須とするケースが多くあります。どの資格証明書を提出してもらうかは、職種や業務内容に応じて企業ごとにルールを決めましょう。
卒業証明書・成績証明書
卒業証明書や成績証明書は任意ですが、新卒採用の場合、最終学歴の証明として提出してもらうのが一般的です。
企業によっては、内定承諾後に「卒業見込証明書」の提出を求め、卒業後に正式な卒業証明書を提出する流れを取る場合があります。
成績証明書は、学業成績の評価を確認する目的で回収するケースがあります。
とくに技術系や研究職では、専門知識の確認や配属先の判断材料として活用されることがあるため、必要に応じて回収を検討しましょう。
中途採用では、卒業証明書や成績証明書の提出を求めることはほとんどありません。
ただし、特定の資格要件を満たしているかを確認する必要がある場合は、職種や企業のルールに応じて回収の要否を決めるとよいでしょう。
退職証明書
中途採用者の前職での在籍確認に使用します。在職期間や職務内容、退職理由などが記載されています。
中途採用者の前職での在籍確認に使用される入社手続きに関連する書類です。公文書ではないため、記載項目に決まりはありません。代表的な項目は以下のとおりです。
- 在職期間
- 職務内容
- 退職理由
通常は退職時に前職の会社に希望を出すと発行してもらえます。自社で提出を求める場合は、内定者へ早めに案内し、申請手続きを進めてもらいましょう。
健康診断の結果
労働安全衛生法に基づき、常時使用する労働者は、雇用時に健康診断を受ける必要があります。ただし、直近3か月以内に受診した際の結果があれば、入社手続きでの健診を省略できます。「健康診断書を提出してもらうのか」「入社後に健診を受診させるのか」、企業のルールにしたがって案内しましょう。
入社手続き書類をやり取りする方法|受け渡しを効率化するには?
入社手続きに必要な書類は、郵送・手渡し・メールの3つの方法でやり取りが可能です。
| 提出方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 郵送 | ・書類の正確な送付ができる ・手書き書類が扱いやすい | ・送付・受領に時間がかかる ・郵送費が発生する |
| 手渡し | ・その場で書類の説明ができる ・直接受け取れるため確実 | ・受け取りに行く手間がかかる ・対面できる機会がないと受け渡しが難しい |
| メール | ・迅速なやり取りが可能 ・ペーパーレス化 | ・セキュリティ対策が必要 ・誤送信リスクがある |
近年では労務管理システムを活用したオンラインで新入社員の情報を回収する企業も増えており、入社手続きの効率化が進んでいます。以下で、各提出方法のポイントとあわせて、オンライン化の可能性についても解説します。
郵送
入社手続き書類を郵送で回収する場合は、書類の紛失や破損を防ぐために、以下の点に注意し、郵便事故や紛失の防止に努めましょう。
- A4サイズの白い封筒を使用
- 入社書類はクリアファイルに入れて保護
- 封筒の表面に「入社書類在中」と赤字で記載
- 簡易書留や特定記録郵便を利用
- 返信用封筒を同封
- 添え状を同封し、書類の種類や部数を明記
内定者の返送の手間を減らす配慮も大切です。
手渡し
内定者に来社する機会をつくってもらい、入社手続き書類を直接手渡しすることも可能です。
手渡しは、その場で不備を確認できるため、自宅とオフィスが近い場合や、内定者懇親会など対面の機会がある場合は指定するとよいでしょう。
メール
入社手続き書類をメールでやり取りする際は、わかりやすい件名を設定し、不明点の問い合わせ先を案内することが大切です。添付する入社書類はPDF形式で添付します。
メールでの受け渡しは手軽ですが、誤送信のリスクもあるため、セキュリティ対策も忘れずに行います。個人情報を含むファイルには必ずパスワードを設定しましょう。
入社手続きの案内メールの書き方については、以下の記事をご確認ください。
労務管理システムを活用したオンライン回収
入社手続きでは、紙の書類をやり取りするのではなく、クラウド上で情報を管理する方法を採用する企業も増えています。
たとえば、労務管理システムを活用すれば、入社手続き書類をデジタルフォームで簡単に収集が可能です。
書類紛失のリスクを防げるとともに、企業と従業員双方にとって、やり取りの手間が省けるのはメリットといえます。
入社手続きの効率化を考えている企業は、労務管理システムの導入も検討してみるとよいでしょう。
→One人事[労務]に関する製品資料の無料ダウンロードは【こちら】
入社手続きに必要な書類に関する注意点
入社手続きでは、多くの書類を短期間でそろえる必要があります。とくに公的書類には期限があり、遅れると会社側・従業員側の双方に影響を与える可能性があります。
不要な労務トラブルを防ぐためにも、入社手続きの書類に関する注意点を詳しく解説しますので、提出遅れを防ぐポイントとあわせて確認していきましょう。
行政手続きに紐づく書類の対応
入社手続きに必要な書類のなかには、社会保険や雇用保険のように法定期限が決められているものがあります。
健康保険・厚生年金保険の加入手続きは入社日から5日以内、雇用保険は入社の翌月10日までに届出が必要です。期限を過ぎると、従業員が本来受けられるべき社会保険の適用が遅れ、企業側に指導が入る可能性があります。
また、マイナンバーは各種行政手続きの基礎情報となるため、入社手続き書類の一環として必ず回収し、適切に管理する体制を整えましょう。
扶養控除等申告書は給与計算に直結する入社手続き書類の一つです。提出が遅れると、従業員の源泉徴収税額が変わってしまいます。入社月の給与計算に間に合うよう、入社日までに提出を依頼しましょう。
書類が遅れた場合の対応
入社手続き書類の提出が遅れると、社会保険や雇用保険などの行政手続きに影響し、企業側の事務負担が増えるだけでなく、保険適用が遅れる可能性もあります。
遅延を防ぐには、期限の設定と管理、準備と事前案内が重要です。
入社日の2週間前までに必要書類のリストを送付し、準備期間を十分に確保することで、提出遅れを防ぎやすくなります。
とくに紛失により再発行が必要な書類(源泉徴収票や雇用保険被保険者証など)は時間がかかるため、人事労務担当者として早めに案内しておくと安心です。
それでも提出が遅れる内定者には、個別に電話やメールで状況を確認し、事情があれば担当者として可能な範囲でサポートしましょう。
入社手続きを電子化すると、書類の提出状況をリアルタイムで管理できます。未提出の書類は期限が過ぎると、自動でリマインドを出せるため管理の手間を減らせます。
入社手続き後に作成する書類|法定三帳簿について
入社手続きが完了したら「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」の3つの帳簿(法定三帳簿)を作成しなければなりません。
法定三帳簿も入社手続きにかかわる重要書類の一種といえます。労働基準法に基づき、各事業所で作成後、5年間の保存(当面3年でも可)が義務づけられています。
| 帳簿 | 記載される内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 労働者名簿 | 氏名、生年月日、履歴、性別、住所、業務の種類、雇入れ・退職(死亡)日 | 採用時に作成し、異動・退職時に更新 |
| 賃金台帳 | 氏名、性別、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、基本給、各種手当、控除額、時間外労働実績 | 毎月の給与支払い時に更新 |
| 出勤簿 | 氏名、出勤日、出勤日ごとの始終業時刻、休憩時間、時間外労働の記録 | 日々の勤務実態を記録 |
近年は、労務管理システムを活用し、デジタルでの管理も可能です。労働基準監督署の指導に応じてすぐ提出できるよう、正確に記録し、適切な保存体制を整えておきましょう。
まとめ
入社手続きに必要な書類は、会社が用意するものと従業員から提出を受けるものに大別されます。必要な書類を漏れなく準備し、適切な方法で受け渡すことが重要です。
とくに、社会保険や雇用保険などの行政手続きにかかわる書類は法定期限があるため、十分な準備期間を確保しなければなりません。
近年は入社手続きのデジタル化も進んでいます。利用することで、書類管理が効率化し、提出状況の把握が簡単になります。
入社手続きを円滑に進めることは、新入社員との良好な関係構築の第一歩です。書類の準備から保管まで、計画的な対応を心がけましょう。
入社情報の回収はOne人事[労務]の活用でスムーズに
入社手続きの書類作成や収集に時間がかかっていませんか?
One人事[労務]は、入社手続きのペーパーレス化を実現し、手続きの効率化を支援する労務管理システムです。
専用フォームから従業員が直接情報を入力することで、書類作成の手間を大幅に削減できます。
収集した情報は自動でデータベースに保存され、「e-GOV」連携により、社会保険や雇用保険の電子化にも対応が可能です。
One人事[労務]の活用方法は、無料のオンライン相談にてお尋ねください。専門のスタッフが貴社の課題をていねいにお聞きしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、入社手続きの電子化に役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。お気軽にお申し込みください。