【企業向け】退職における就業規則と法的ルール| 退職届を受理しない場合についても解説
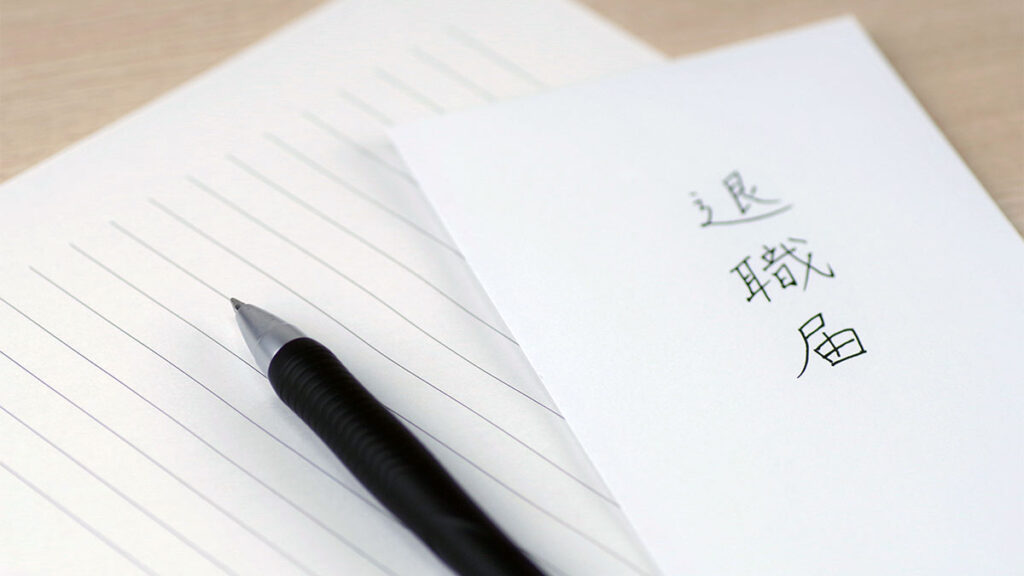
労働法を遵守し、雇用契約条件を守るために設けられる就業規則。退職について、どのようなルールを設ければよいのか分からずに困ってしまうケースもあるでしょう。また、就業規則に退職に関するルールを設けていても、従業員は必ずしも守らないといけないわけではありません。
そこで本記事では就業規則における退職の取り扱いについて解説します。法的なルールとの違いも解説するので役立ててください。
 目次
目次
まずは法的な退職の申し出期間のルールを確認
前提として、退職とは「従業員から申し出て労働契約を終了すること」を指します。そして、雇用形態ごとの退職の申し出の期間は、民法や労働基準法で規定されています。
次のケースごとに、退職の申し出期間のルールを解説します。
- 無期雇用の従業員が退職する場合
- 有期雇用の従業員が退職する場合
- 有期雇用で雇用契約期間が1年以上の従業員が退職する場合
無期雇用の従業員が退職する場合
雇用期間が定められていない従業員は、退職の申し出の2週間後に雇用契約が終了すると民法第627条第1項で定められています。
民法第627条第1項は、雇用期間が定められていない従業員に適用され、正社員であるかパートであるかは問われません。ただし、多くのパートは有期雇用であり、主に正社員がこの規定の対象となるでしょう。
なお、会社側が従業員を解雇する場合は、少なくとも30日前に解雇の旨を告げる必要があります。これは、労働基準法第20条により決められています。もし事前告知なく解雇すると、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。
参考:『労働政策審議会労働条件分科会 第49回資料』厚生労働省
参考:『労働基準法』e-Gov法令検索
有期雇用の従業員が退職する場合
民法第628条により、有期雇用契約の従業員は、原則としてやむ得ない理由があるのでなければ、契約期間中は退職できません。これは、会社側も同様であり、契約期間中は原則として契約解除できません。
有期雇用で雇用契約期間が1年以上の従業員が退職する場合
原則として有期雇用契約は、労使双方とも契約期間中の解除ができません。しかし、雇用契約期間が1年以上であり、契約日から1年が経過している従業員であれば、1年経過後は理由を問わず退職できます。
就業規則でルールを定めた場合はどうなるのか
前提として、就業規則には退職に関するルールを記載できます。たとえば「退職の旨は1か月前に告げる」などです。しかし、退職ルールを従業員に強制はできません。たとえ従業員が1か月前に退職の旨を告げなかった場合でも、退職を拒んだり、退職を拒否して働かせたりするのはNGです。
労働基準法上の退職におけるトラブルをチェック
労働基準法上の退職におけるトラブルについて、次の3つのケースを例にご紹介します。
- 有期雇用者が一方的に退職してしまった場合
- 引き継ぎなしで無期雇用者が退職して知った場合
- 労働条件に相違があった場合
それぞれ解説します。
有期雇用者が一方的に退職してしまった場合
原則、有期雇用者は契約期間中であれば、やむを得ない理由がない限り退職できません。もし会社の合意なく有期雇用者が退職した場合、民法上、企業は従業員に損害賠償請求ができます。
ただし、企業側にセクハラやパワハラなどの過失があった場合は、損害賠償を請求される可能性があります。
引き継ぎなしで無期雇用者が退職してしまった場合
法的なルール上、無期雇用者は2週間前の申し出で退職できます。
ただし、引き継ぎせずに退職した場合、会社は従業員に損害賠償を請求できます。引き継ぎがないとほかの従業員に負担がかかることもあるため、トラブルを避ける工夫が必要です。
労働条件に相違があった場合
もし会社が提示した労働条件と、実際の就業状況が大きく異なる場合、従業員は直ちに労働契約を解除できます。たとえば「無期雇用での募集であったのに実際は有期雇用だった」「求人票に記載された給料と採用時の給料が明らかに異なる」などです。
また就業にともない引っ越したにもかかわらず、労働条件の相違を理由に退職した従業員が、退職日から14日以内に以前の住居に戻る場合には、その旅費を支払わなければなりません。
従業員は2週間前の申し出で自由に退職できる
雇用期間による違いはありますが、基本的に従業員は2週間前に申し出ることで退職できます。
ただし、退職によって企業に大きな損失を与えた場合は損害賠償が請求される可能性があります。退職時のトラブルを防止するためにも、日ごろから就業規則の遵守を促すなどの工夫が必要です。
従業員の退職届を受理しないとどうなるのか
従業員が退職届を提出したにもかかわらず、会社が受理しない場合、次の3つの問題が起こる可能性があります。
- 慰謝料を請求される
- 弁護士・退職代行会社が介入してくる
- 労働基準監督署に通報される
それぞれ解説します。
慰謝料を請求される
従業員が退職の2週間前に退職届を提出してきたにもかかわらず、拒否すると従業員から慰謝料を請求される可能性があります。退職の意思を拒むことは、従業員の権利を侵害することです。従業員の意思を尊重した対応が求められるでしょう。
弁護士・退職代行会社が介入してくる
退職届を受理しない場合、従業員が弁護士や退職代行会社などに、退職の手続きを依頼する可能性があります。弁護士や退職代行会社への退職手続きの依頼が完了すれば、従業員と直接やりとりできなくなってしまうでしょう。結果、退職の引き継ぎに支障をきたすことが考えられます。
また、弁護士や退職代行会社などの第三者が介入すれば、通常の退職手続きよりも手間がかかります。円満に退職してもらうためにも、事前に退職届を受理することが好ましいです。
労働基準監督署に通報される
退職届を受理してもらえない場合、従業員が労働基準監督署に通報して、企業に調査および指導が入るかもしれません。労働基準監督署への相談は無料であるため、従業員からすると利用のハードルが低く、通報の手段を取ることは十分考えられます。
また、従業員が退職の意思を持っているにもかかわらず働かせ続けた場合は、強制労働と見なされて労働基準法第5条に違反するおそれがあります。
指導に従わない場合は刑事罰を受ける可能性がある
労働基準監督署からの指導に従わない場合は、強制的な捜査や刑事罰を受ける可能性があります。最悪、企業名が公表されて、社会的信用を失うことも考えられるでしょう。企業イメージの低下を防ぐためにも、労働基準監督署からの指導には早急に対応することが大切です。
退職を希望する従業員に対してやってはいけないこと
次のことは、退職を希望する従業員にやってはいけません。
- 就業規則に従った退職をしないなら損害賠償を請求する
- 退職金を支払わない
- 離職票を発行しない
上記のような行動をすると労働問題に発展する恐れもあるので注意が必要です。
まとめ
無期雇用の従業員は、退職の旨を申し出た2週間後に退職できます。有期雇用の従業員は、契約日から1年が経過していればいつでも理由を問わず退職可能です。
これらの退職に関する期間は、民法や労働基準法により定められています。民法や労働基準法の範囲内で退職手続きをした従業員の退職を拒んだ場合は、慰謝料を請求されたり弁護士が介入してきたりするため注意しましょう。
「One人事」は、人事労務をワンストップで支えるクラウドサービスです。従業員の入退社手続きや年末調整の効率化を実現し、担当者の負担を軽減することで、人材活用の基盤をつくります。気になる費用や操作性は、お気軽にご相談いただけますので、まずは当サイトよりお問い合わせください。
当サイトでは、サービス紹介資料はもちろん、無料のお役立ち資料をダウンロードいただけます。業務効率化のヒントに、こちらもお気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |
