労災保険に加入していないとどんなリスクや罰則があるか違法性や未加入時の対応を解説
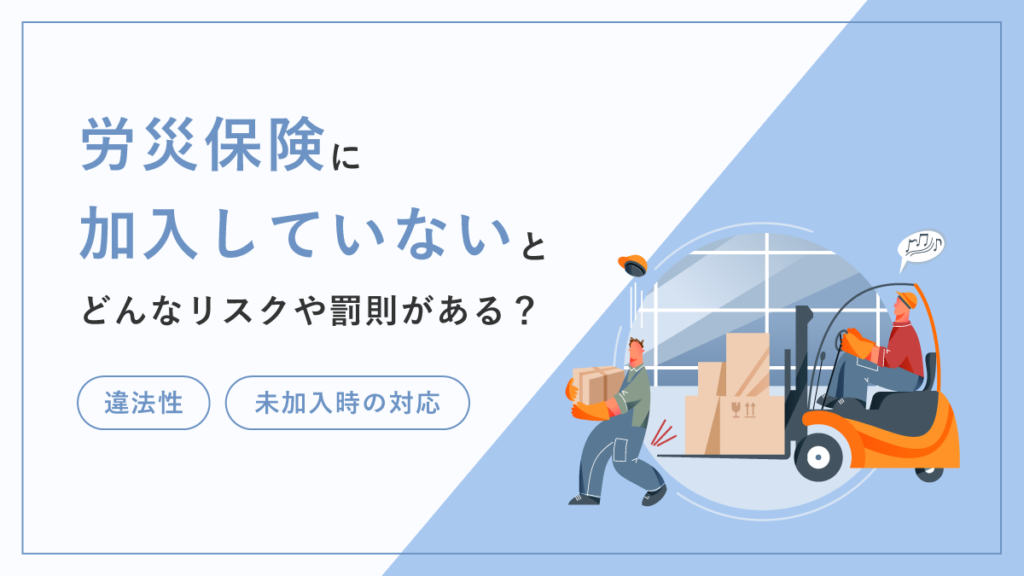
労災保険に加入していないと、主に以下の2つのリスクが考えられます。
- 従業員のケガや病気に対する補償を最大限負担する
- 労働基準監督署からの指導や罰則を受ける
労災保険とは、業務中や通勤中に発生したケガや病気に対して必要な給付を行う公的保険制度です。
本記事では、労災保険に未加入だった場合のリスクと、企業が取るべき適切な対応方法について詳しく解説します。
労災保険を含め、社会保険関係の手続きは順調にお済みですか。社会保険の提出書類や方法が整理できていない方は、以下の資料もぜひご活用ください。
 目次[表示]
目次[表示]
労災保険とは
労災保険とは、従業員が業務中や通勤中のできごとが原因で傷病を負ったり、死亡したりした際に必要な補償をする社会保険制度です。
正式名称を『労働者災害補償保険』といい、被災した労働者やその遺族は一定の給付を受けられる仕組みです。労災保険は「労災」という略称が広く使われています。
労災保険の対象になると、8種類の中から内容に応じた給付が支給されます。
労災保険は、原則として1人でも従業員を雇用する事業所であれば、規模や業種を問わず適用されるのが特徴です。正社員だけではなく、条件を満たしたパートやアルバイト、日雇い労働者などすべての労働者が対象となります。
参照:『労災補償』厚生労働省
参照:『労働基準情報:労災補償』厚生労働省
労災保険と雇用保険の違いからおさらいしたい方は、以下の記事もご確認ください。
労災対象の3つの種類
労災保険の対象となる事案には3つの種類があります。労災対象の基本を理解しておきましょう。
| 種類 | 対象 |
|---|---|
| 業務災害 | 業務上でのケガや病気、障害または死亡。業務遂行性と業務起因性により判断 |
| 複数業務要因災害 | 「複数事業労働者」が、労働時間やストレスが要因で発症した傷病(脳・心臓疾患、精神障害など) |
| 通勤災害 | 通勤中に労働者が被った負傷や疾病、障害または死亡 |
業務災害の労災認定は、過去に争われた事例があるほど、判断が難しいとされています。
「事業主の管理下にあるか」「業務に関係があるか」という基準で判断され、業務時間内であっても、業務に関係のない私的な行為が原因や故意によるケガは、業務災害には該当しません。
複数業務要因災害の注意点は、傷病が1つの事業所のみの負担によるものとみなされると、「業務災害」と認定されることです。
また通勤災害は、寄り道をして通勤経路から大幅に外れると対象外ですが、公衆トイレや経路上にある店での日用品の買い物などは認められています。
参照:『業務災害・通勤災害について』厚生労働省
参照:『複数業務要因災害』厚生労働省
参照:『業務災害・通勤災害について』厚生労働省
参照:『通勤災害について』厚生労働省東京労働局
労災保険に加入していないとどうなる? 未加入のリスクと罰則
本来であれば、従業員を雇用してから10日以内に管轄の労働基準監督署に届け出て、労災保険の加入手続きをしなければなりません。
たとえ企業側が労災保険に未加入の状態であったとしても、本来加入する義務がある場合には、労災事故に見舞われた従業員は労災保険の補償を受けられます。
従業員みずから労働基準監督署に対して申請し、労災認定が下りれば通常どおりの給付が行われる仕組みです。
また、労災保険に未加入の状態で従業員が傷病を負った場合、企業は故意や過失による未加入と判断され、未払い保険料のほか給付に要した費用の一定割合を徴収されるおそれがあります。
未払い保険料を徴収される
労災保険の未加入は労働基準法違反に該当するため、発覚した場合には過去2年間にわたる保険料と追徴金(10%)を支払わなければなりません。
労災保険料は「全従業員の賃金総額×労災保険料率」です。労災保険料率は業種によって異なり、「2.5/1,000~88/1,000」の範囲内で定められています。
労災保険料率について詳しく知るには以下の記事もご確認ください。
保険料を支払いたくないからと労災保険に未加入のままでいると、いざ事故が発生した際、想像以上の多額な費用負担がのしかかります。
未加入によるリスクは、目先の保険料の節約よりもはるかに大きな代償を生むのです。
今一度、労災保険への加入状況を見直し、安全対策の一環として対応を進めましょう。
参照:『成立手続を怠っていた場合は』厚生労働省
参照:『令和6年度の労災保険率について(令和6年度から変更されます)』厚生労働省
故意・重過失の場合は一定額も徴収されるおそれがある
労災保険に未加入のまま放置していると、従業員への給付に要した金額の一部もしくは全額を企業側が負担しなければならなくなるため、注意が必要です。
徴収される保険給付に要した額の割合は、事業主の過失度合いによって以下のように異なります。
| 過失度合い | 負担割合 |
|---|---|
| 重大な過失により加入手続きをしていなかった場合 | 40% |
| 故意に労災保険への加入手続きをしていなかった場合 | 100% |
労働局や労働基準監督署からの指導は受けていないものの、加入対象であるにもかかわらず1年以上手続きをしていなかった場合は、重大な過失とみなされかねません。
指導を無視した状態で労働災害が発生してしまうと、給付に要した額の40%を追加徴収される可能性があります。
また、労働局や労働基準監督署から指導を受けていたにもかかわらず、労災保険の加入手続きを怠っていた場合は、さらに深刻な問題につながります。
故意に未加入とみなされ、給付に要した額の全額を負担しなければならないケースも考えられるでしょう。
労災保険の未加入が大ごとになる前に、手続き内容や流れを確認したい方は以下の資料もご確認ください。

法律違反となるおそれもある
労災保険に未加入だった場合は、労働者災害補償保険法に違反し、罰則を科されるおそれがあります。
同法法第51条により、行政からの命令に反して報告や文書の提出をしなかったり、虚偽の申告をしたりした事業所には厳しい処分が適用されます。具体的には「6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金」が科される規定です。
また、悪質性が高いと判断されると、厚生労働省によって企業名が公表されることもあります。ハローワークでの求人掲載も停止され、採用活動にも支障が出るため、軽視できない事態といえるでしょう。
労災保険の加入条件
労災保険は、常勤やパート・アルバイト、派遣社員などの名称や雇用形態に関係なく、労働者を1人でも雇用する事業場は原則として加入しなければなりません。
厚生労働省では、労災保険と雇用保険の総称である「労働保険」に加入すべき事業所を「強制適用事業所」と呼んでいます。
ただし、以下に当てはまる事業所や労働者は異なる法律で保障されるため、労災保険の加入対象ではありません。
- 官公署の事業のうち非現業のもの(例:役所の窓口職員)
- 国の直営事業(例:造幣局の職員)
また、個人事業主や家族従事者など労働者に該当しない人は、本来加入対象ではないものの、特別加入制度を利用すれば労災保険に加入できます。
2024年9月現在、特別加入制度の対象者は次のとおりです。
- 中小事業主やその家族従事者
- 一人親方やその他の自営業者
- 海外派遣者
- 特定作業従事者
2024年11月より、以上の対象者に加えてフリーランスも特別加入の対象となりました。詳しくは、厚生労働省のホームページを確認してみましょう。
参照:『労働保険への加入について』厚生労働省
参照:『令和6年11月から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となります』厚生労働省
労災保険の適用対象者について詳しくは以下の記事もご確認ください。
労災保険の未加入が起こる理由
労災保険は、原則としてすべての労働者が加入すべき保険制度です。しかし、さまざまな理由から労災保険の未加入が起こってしまうケースも少なくありません。
まずは、事業所が意図的に未加入にしている場合が考えられるでしょう。労働局や労働基準監督署から指導を受けたにもかかわらず、加入せずに放置している会社もあるようです。
労働局や労働基準監督署から指導はされていなくても、従業員を雇用してから1年以上が経過しているにもかかわらず、故意に加入していないケースも挙げられます。
そのほかにも、次のような理由で未加入のままとなっている事例があります。
- 労災保険の必要性を理解していなかった
- 労災保険料の負担を避けたかった
- 日常業務に追われて手続きを後回しにしてしまっていた
未加入を続けると、労働災害時に負担を強いられ、従業員からの信頼喪失にもつながります。事業所の 現状を見直し、早急に労災保険への加入手続きを完了させ、安全で信頼される職場づくりを目指しましょう。
労災保険に加入して安心して働ける環境を整備
労災保険とは、業務中や通勤中に発生したケガや病気の治療費、生活費などを補償するための保険制度です。
労働災害は、すべての業種において起こり得るものです。工場や作業場などの現場仕事ではない事務系の仕事であったとしても、労災保険の対象となるケースがあります。どのような事業所でも、突発的な事故やアクシデントは避けられないと心得ておきましょう。
労災保険が未加入のままでは、労働基準法違反として法的リスクを抱えるだけでなく、従業員や社会からの信頼を失い、企業イメージの低下にもつながります。
企業は労災保険制度の概要や加入条件を正しく理解し、従業員たちが安心して勤務できる環境を整備していきましょう。
クラウド労務管理システムOne人事[労務]は、社会保険の申請手続きをオンラインで完結させる効率化ツールです。e-Gov電子申請にAPI連携し、窓口に出向かなくても、簡単に申請ができます。
2025年からは「労働者死傷病報告」など一部手続きの電子申請が義務化されました。社会保険申請のペーパーレス化が進んでいない企業は、検討してみてはいかがでしょうか。
One人事[労務]で実現できること・機能は、当サイトよりお気軽にお問い合わせください。専門スタッフが、課題の整理からお手伝いします。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします |
