年末調整で記載する住所とは? 住民票と違うとどうなる? 変更や間違えた場合の対応も解説
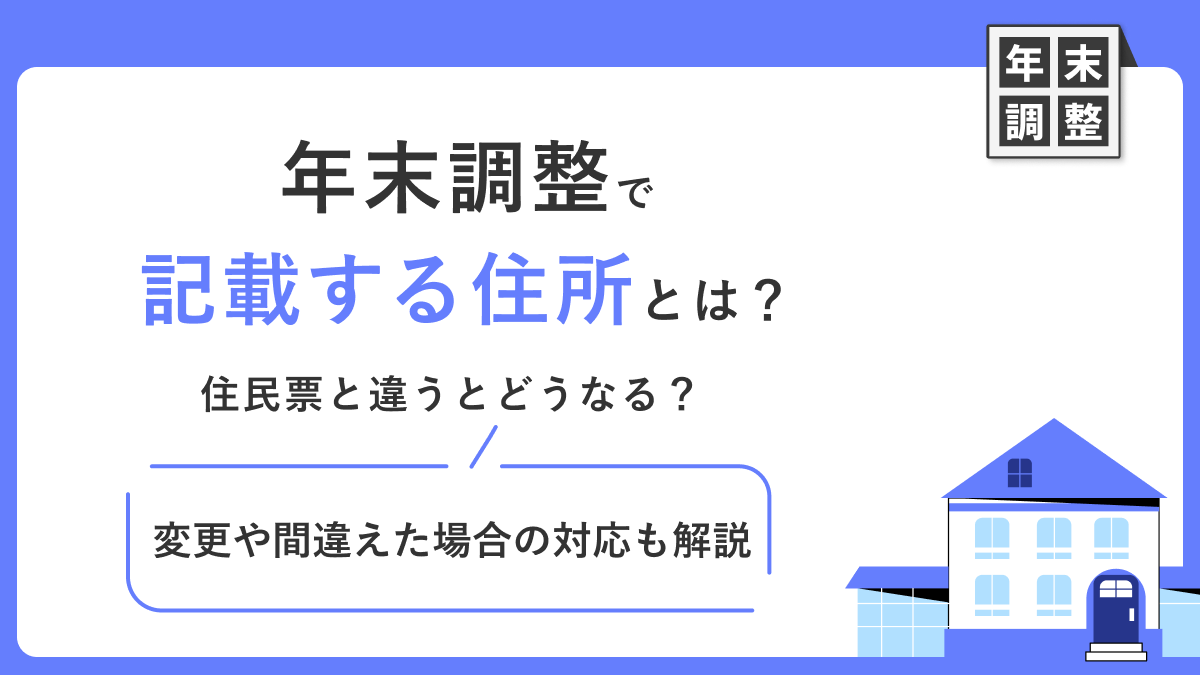
年末調整の書類には、住所を記載する欄が設けられており、従業員から以下のような問い合わせを受けることがあります。
「住民票の住所と今現在住んでいる住所が違う」
「年末に引っ越しを予定している」
年末調整で記載する住所は「年末調整をした翌年1月1日時点で住民票を置いている住所」が原則です。住所は翌年の住民税を納める自治体を決める基準となります。
本記事では、年末調整で記載する住所の基本ルールから、住所変更時の対応、記載ミスがあった場合の訂正方法までを解説します。

 目次[表示]
目次[表示]
年末調整で記載する住所はどこ? いつ時点? 重要性も解説
年末調整は、1年間の所得税を精算し、翌年の住民税額を決定する重要な手続きです。年末調整で記載する住所欄には、ほかの公的書類とは異なる特殊なルールがあります。
多くの方が「現在住んでいる住所をそのまま書けばいい」と考えがちですが、じつはそうではありません。
原則「翌1月1日時点で住民票がある住所」を書く
では年末調整の書類には、いつの時点での住所を書けばよいのでしょうか。
原則として「翌年1月1日時点で住民票を置いている住所」を書きます。
たとえば、2024年の年末調整であれば、2025年1月1日時点での住所を記載します。
現時点ではなく翌年1月1日時点の住所を記載する理由は、住民税の課税ルールが関係しています。
住民税はその年の1月1日時点に住まいのある自治体に対して、前年1年間の所得を基に計算された税額を納付する仕組みです。そのため年末調整の書類には翌年1月1日時点の住所を記載しなければなりません。
住所とは法的には「生活の本拠地」を指します。民法第22条では以下のとおり定められています。
(住所)第二十二条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。
引用:『民法第22条』e-Gov法令検索
生活の中心となっている場所が法律上の「住所」です。
年末調整における住所記載の重要性
年末調整における住所記載は、住民税の課税地(どの自治体に税金を納めるか)を決める基礎情報となるため重要です。
書く住所を間違えると以下のようなトラブルが起こる可能性があります。
- 住民税が別の自治体に納付される
- 従業員に納税通知書が届かない
- 自治体から送付される書類が現住所に届かない
住所は納税義務を正確に果たすため、ルールに沿って記載しなければなりません。
実際の住所と住民票の住所が異なる場合どうする?
住んでいる住所と住民票の住所が異なる場合、基本的には「生活の本拠地」となっている実際の住所を記載します。住民税は「生活の本拠」がある場所で課税されるルールとなっているためです。
単身赴任の場合
単身赴任で家族と離れて生活している場合、住民票を変更しているかどうかで対応が分かれます。住民票を変更している場合は変更後の住所を記載します。住民票を変更していない場合でも、生活の本拠地である単身赴任先の住所を記載するのが原則です。
学生の場合
学生の場合も同様で、実家に住民票があっても、生活しているのが大学の寮や下宿先であれば、その住所を記載します。住民税が「その市町村に住所を有する個人」を納税義務者としており、住所とは生活の本拠地のことだからです。
実務上は、従業員が住民票の住所を記載していても大きな問題に発展するケースは多くありません。ただし、法的には「生活の本拠地(実際に居住している場所)」を記載するのが適切です。人事担当者としては、従業員の居住実態を踏まえたうえで、会社としてどの住所を記載すべきかを明確に案内することが望ましいでしょう。

年末調整書類における住所記載の基本ルールを解説
年末調整の書類には、基礎控除等申告書・扶養控除等申告書・社会保険料控除申告書それぞれに住所を記載する欄があります。
住所を記載する際は、以下の基本ルールをおさえておきましょう。
- 都道府県名から正式名称で記載する(郵便番号も忘れずに書く)
- マンション・アパート名、部屋番号まで省略せずに書く
- 扶養親族の住所は同上と記載してもよい
どれもあたり前のように感じるものですが、ほんの一文字の違いが、あとで手間を増やしてしまうことも考えられます。一つずつ確認していきます。
郵便番号、都道府県から記載する
年末調整書類の住所欄には、原則として「都道府県」から記載します。郵便番号も忘れずに記入しましょう。都道府県名から始まり、市区町村、町名、番地の順に正確に書きます。
住所は自治体による住民税の課税に直接かかわる重要な情報です。とくに従業員が引っ越しをした場合など、住所が変わったときは注意が必要です。
都道府県名を省略したり、市区町村名を略したりすると、正確な住所として認識されない場合があります。たとえば「東京都」を「東京」、「神奈川県」を「神奈川」と省略せず、正式名称で記載しましょう。
マンション名・アパート名、部屋番号まで記載する
集合住宅に住む場合、年末調整の書類へ住所欄は必ずマンション名やアパート名、部屋番号まで正確に記入しましょう。「○○マンション101号室」と具体的に明記するのが基本です。
省略してしまうと、住民税の納税通知書や源泉徴収票など、大切な書類が届かない可能性があります。
同じマンションに同姓同名の入居者がいるなど特殊ケースでは、部屋番号の記載がないことで書類の誤配につながるリスクもあります。少しの手間でトラブルを回避できますので、慎重に記入しましょう。
扶養親族の住所は同上と記載してもよい
年末調整の書類には、扶養親族の情報を記入する欄があります。家族が同居している場合、一人ひとりの住所欄に同じ住所を記入するのは手間がかかります。扶養親族の住所欄には「同上」と記載しても問題ありません。「同上」という記載により、会社側の確認作業も軽減できます。
別居している扶養親族
当然ながら、扶養親族が別居している場合は、正確な住所を記載しなければなりません。別居の住所は、主に控除対象かどうかを判断するために用いられます。従業員によって提出された各種控除申告書は、勤務先での精算手続きが終わったら、会社で保管するものです。
年末調整は従業員情報を更新するタイミング
多くの企業では、人事労務システムに入社時点の従業員情報(住所や扶養家族など)がすでに登録されています。
年末調整の書類は新たに情報を収集するというより、登録内容に変更がないかを確認・更新する役割も果たしています。
従業員の住所や扶養関係に変更があったら、年末調整のタイミングで正しい情報に更新してもらうとよいでしょう。
年末調整における住所の書き方【ケース別】
引っ越しや単身赴任、海外赴任など、さまざまな状況によって、年末調整の書類に記載すべき住所が異なるケース、状況によって判断が難しいケースもあります。
| ケース | 記載すべき住所 |
|---|---|
| 年末直前に引っ越しした場合 | 引っ越し後の新住所 |
| 年末調整提出後に引っ越しが決まった場合 | 新住所(報告後に修正) |
| 扶養控除対象者の住所が異なる場合 | 扶養親族の現住所 |
| 海外赴任から帰国後の年末調整 | 翌年1月1日時点で住民票を置く予定の住所 |
| 住民票が実家で一人暮らししている場合 | 実際に生活している住所 |
具体的なケース別に、正しい住所の記載方法を解説します。
年末直前に引っ越しをした場合
年末直前に引っ越しをした場合、年末調整の書類には引っ越し後の新住所を記載します。年末調整の書類に記載する住所が「翌年1月1日時点の住所」であるためです。
たとえば、12月25日に引っ越しをした場合、たとえ、1年のほとんどを引っ越し前の住所で過ごしていたとしても年末調整の書類には新住所を記載します。
年末調整の書類提出後に引っ越しが決まった場合は、会社にすみやかに報告することが重要です。会社は翌年1月末までに「給与支払報告書」を自治体に提出するため、それまでに新住所を報告すれば修正が可能です。
もし1月末までに報告できなかった場合、従業員自身で確定申告をして修正しなければなりません。
年末調整の時点で引っ越し先の住所がまだ決まっていない場合は、現在の住所を記載し、新しい住所が決まり次第、会社に報告してもらうようにしましょう。
扶養控除対象者の住所が異なる場合
扶養親族が従業員と別居している場合は、居住地の住所を個別に年末調整の書類に記載する必要があります。
地方の実家に住む親を扶養しているなら、実家の住所を記載します。
扶養控除対象者が本人と同じ住所に住んでいる場合は、「同上」と記載しても問題ありません。誤解を招かないよう明確に記載しましょう。
海外赴任からの帰国後に年末調整をする場合
海外赴任から帰国したあとに年末調整をする場合、翌年1月1日時点で住民票を置く予定の住所を記載します。
帰国後、住民票の移動手続きが完了していない場合は、生活の本拠地となっている住所を記載しましょう。
海外赴任者の場合、帰国のタイミングによって住民税の課税状況が変わることがあります。年をまたぐ時期の帰国の場合は、1月1日時点での居住地が重要です。
単身赴任の場合
単身赴任中の従業員の場合、住民票を変更しているかどうかで対応が分かれます。住民票を変更していれば、赴任先の住所を記載します。
住民票を変更していなくても、生活の本拠地である単身赴任先の住所を記載するのが原則です。住民税が「生活の本拠」がある場所で課税されるルールとなっているためです。
たとえば、東京に住む家族がいて従業員が大阪で単身赴任している場合、住民票が東京のままでも、実際の生活の本拠地である大阪の住所を年末調整の書類に記載します。
ただし企業によって、経理担当者や顧問税理士のやり方で統一されているケースもあるため、まずは自社のルールを確認しましょう。
住民票が実家で1人暮らしの場合
学生や新社会人が住民票は実家にあるものの、別の場所で一人暮らししている場合、年末調整の書類には生活している住所を記載します。
実家の住民票は大阪でも、東京で社会人生活を送っているなら、東京の住所が正しいです。住民税は翌年1月1日時点の住所地で課税されるため、生活の本拠地を明示します。

年末調整の提出後に住所変更・引越し予定があったらどうする?
年末調整の書類を提出したあとに引っ越しが決まった場合、すみやかに担当部署へ報告してもらうことが重要です。
年末調整の書類に記載する住所は「翌年1月1日時点の住所」が原則です。年末調整の書類提出後に12月中に引っ越しをする場合は、新住所を勤務先に報告する必要があります。
会社は翌年1月末までに「給与支払報告書」を自治体に提出しなければなりません。提出に間に合うように新住所を報告すれば修正が可能です。
報告が遅れると、住民税が誤った自治体に納付されたり、自治体からの書類が届かなかったりするトラブルが発生する可能性があります。住民税の特別徴収(給与天引き)は、正確な住所情報が不可欠です。
新住所を勤務先に報告する際の注意点
従業員が引っ越しを予定している場合は、住所変更の報告をできるだけ早めに受ける体制を整えておくことが重要です。
報告が遅れると、年末調整や住民税の課税地、通勤手当の切り替えなど、複数の手続きに影響がおよびます。
報告方法は企業によって異なりますが、主に以下の3つの手段で受け付けるケースが一般的です。
- 人事労務システム
- 書面による届け出
- メールによる報告
- 上司や人事担当者への口頭連絡
人事担当者は、報告のタイミングと提出方法を社内で明確に周知しておきましょう。 報告を受けた際は「引っ越し日」と「新住所」を必ず確認し、必要に応じて住民票の写しなどの添付書類を求めるようにします。
人事労務システムに、従業員みずから身上変更ができる機能があると、担当者の手間が省け便利です。
年末調整で住所記載を間違えた場合の影響と対処法
年末調整の書類に記載する住所を間違えて記載すると、住民税が誤った自治体に納付されてしまうおそれがあります。
住民税は翌年1月1日時点の住所地の自治体に納付するものです。
間違った住所を記載すると、本来納税すべき自治体とは異なる自治体に住民税が納付されることになります。
また自治体から送付される重要な書類が現住所に届かないという問題も発生します。事態が発覚したら、できるだけ早く修正手続きを行うことが重要です。
会社経由で修正する場合
従業員が年末調整の書類に誤った住所を記載していた場合は、まずは会社経由で修正手続きを行うのが基本です。
修正は、年末調整の期限である翌年1月31日までであれば、比較的スムーズに対応できます。
人事担当者は、以下の手順で対応しましょう。
- 従業員から住所記載ミスの申し出を受ける
- 必要に応じて、該当の年末調整書類(例:扶養控除等申告書など)を再提出してもらう
- 修正箇所は二重線で訂正し、空欄に正しい住所を記載してもらう(修正液・修正テープは不可)
社内ルールで規定がなければ、年末調整の書類修正に、原則して訂正印は不要です。
修正後は、給与支払報告書や住民税データに反映されているか確認し、自治体への提出内容にズレがないよう注意が必要です。
従業員が直接自治体へ修正する場合
もし1月31日以降に誤りが発覚した場合は、会社経由での修正が間に合わないため、従業員自身が自治体へ修正申告を行う必要があります。
人事担当者は、次のように案内します。
- 誤りが判明した従業員から報告を受ける
- 修正が必要な自治体(住民税の課税地)を確認し、該当自治体の担当窓口(市区町村民税担当)へ手続き方法を問い合わせるよう伝える
- 必要に応じて、「修正申告書」や「本人確認書類」「住民票」などの提出が必要になる場合があることを説明する
- 確定申告による修正が必要なケースもあるため、税務署への相談も案内する
また、住民票の住所と実際の居住地が異なる場合は、自治体間で照会が入ることがあります。必要な手続きは、自治体により異なるため、人事担当者としては、従業員に納税地の自治体へ直接確認を行うよう案内するのが基本です。
まとめ
年末調整の住所記載は、翌年1月1日時点の生活の本拠地をもとに記入します。住所記載は翌年度の住民税の課税地を決定する重要情報です。誤りがあると納税トラブルにつながります。
従業員の住民票と実際の居住地が異なる場合は、実際に生活している場所(生活の本拠地)を記載するよう案内しましょう。単身赴任や学生の一人暮らしなども同じ扱いです。
書類提出後に住所変更や記載ミスが判明した場合は、すみやかに従業員から報告を受け、社内で修正対応を行います。翌年1月末までは会社経由で修正が可能ですが、以降に発覚した場合は、従業員に自治体への修正申告を案内しなければなりません。
人事担当者は、提出書類の住所情報が最新かどうかを確認し、正確な人事データ管理をすることで税務トラブルを未然に防ぐことが求められます。

