年末調整は住民税に影響する? 控除は対象外? 住民税申告が必要な場合も解説
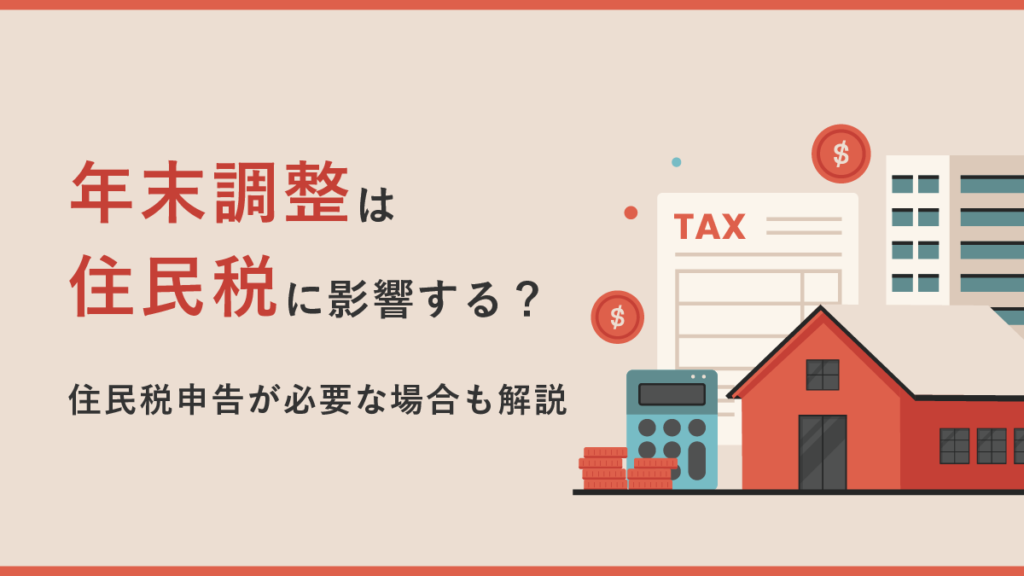
年末調整は個人の所得税の支払い額を調整する仕組みですが、その結果が住民税にどのように影響するのかと疑問に思ったことはありませんか。
年末調整は住民税に直接的には影響しません。しかし調整額によっては翌年の住民税額が変わることがあります。
また「住民税は年末調整で控除対象になるのか」「住民税申告が必要な場合はどんなケースか」など、関連性を整理できていない人もいるかもしれません。
本記事では、年末調整と住民税の関係についてわかりやすく解説していきます。

 目次[表示]
目次[表示]
年末調整と住民税、それぞれの仕組みとは?
年末調整と住民税それぞれを理解していないと、2つの制度は一見関連していると思われがちです。しかし実際は目的や仕組みが異なります。
| 年末調整(所得税) | 住民税 |
|---|---|
| 源泉徴収額と本来納めるべき所得税の差分の精算 | 居住する自治体に納めるべき地方税 |
基本的な仕組みを順番におさらいし、それぞれの違いや関係性について整理していきましょう。
年末調整とは
年末調整とは、毎月の給与や賞与から差し引かれた源泉徴収税額と、本来納めるべき所得税額の差分を清算する手続きです。1月1日から12月31日までの1年間で支払われた給与が対象となります。
年末調整では、実際に支払う所得税額を上回る源泉徴収税額が給与から天引きされているケースが多く見られます。払い過ぎた所得税額は「還付金」として、12月や1月の給与支給時に払い戻しをされるのが一般的です。
所得税は、所得によって負担すべき所得税額が多くなるよう、超過累進税率が採用されています。つまり、所得が多いほど税率が高くなるのがポイントです。
年末調整の対象は、勤め先において源泉徴収がされていて、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人です。
自営業やフリーランスのような個人事業主のほか、給与所得が2,000万円を超える人、兼業などで2か所以上から給与が支払われている人などは対象外である点もおさえておきましょう。
年末調整を初心者向けに解説している以下の記事もぜひご確認ください。
住民税とは
住民税とは、一定の所得を得ている人が、居住する地域に納める地方税です。教育や福祉、消防・救急、ごみ処理など身近な行政サービスを支える目的で使用されます。当年の1月1日時点で生活している自治体に納付する税金です。
住民税は、大きく次の2つに分類されます。
| 法人住民税 | 企業が負担する税金 |
| 個人住民税 | 市区町村や都道府県に住所がある個人が負担する税金 |
年末調整がかかわる所得税が当年の収入に対して課税されるのに対し、住民税は前年の所得に対して課税されるのが大きな違いです。
また所得や控除の状況によっても異なりますが、住民税の税率は、地方税によって全国一律で10%と定められています。
住民税の基礎をおさらいしたい方は以下の記事もご確認ください。
年末調整の控除対象に住民税は含まれない
年末調整では、所得税のみが精算対象であり、住民税は対象外です。あくまでも「当年の収入」に対して、課される所得税を計算して過不足を調整するのが年末調整です。
一方で住民税は、「前年の所得」をもとに金額が決まり、年末調整で取り扱われることはありません。所得が確定されてから翌年度に課税されるため、所得税のように月ごとの差分が生じないのです。そのため、年末調整では住民税を計算したり、過不足を調整したりする作業は行われません。
| 住民税 | 所得税(年末調整が必要) | |
|---|---|---|
| 課税対象 | 前年の収入 | 本年の収入 |
| 税額決定のタイミング | 翌年度に金額が確定 | 年末調整や確定申告で精算 |
| 納付先 | 市区町村(自治体) | 国(税務署) |
住民税は年末調整がなく、通常は還付金は発生しません。しかし非常にめずらしいケースではあるものの、以下の条件に該当すると住民税が還付される場合があります。
- 住宅ローン控除や医療費控除の漏れがあった
- 年末調整をしていない
- 株の売却損がある
- 確定申告に誤記載があった
住民税が還付される場合は、それぞれの市区町村から「過誤納通知書」が本人に送付されます。
還付金を受け取るための申告期間は、請求できる日(過誤納通知書の発行日や通知日)から5年間です。期限を過ぎてしまうと、還付金を受けられません。還付金の対象であると気づいたら、可能な限り早いタイミングで対応する必要があります。

自分で納付(普通徴収)であっても基本的に還付金はない
住民税の納付方法には「特別徴収」「普通徴収」の2種類があります。
| 種類 | 対象者 | 方法 | 時期 |
|---|---|---|---|
| 特別徴収 | 会社勤め | 給与からの天引き | 毎月 |
| 普通徴収 | 個人事業主、無職 | 市区町村から送付される納付書 | 一括、もしくは4期分割 |
特別徴収でも普通徴収でも支払う住民税額に違いはなく、いずれも基本的に還付金は発生しません。
参照:『個人住民税』総務省
年末調整の結果は翌年の住民税納付に影響する
住民税は年末調整の対象ではありませんが、2つの制度はまったく関係ないとはいえません。
年末調整で確定した所得税額が、翌年の住民税を計算するうえでの基礎となります。年末調整における所得が増えれば翌年の住民税が増え、所得が減れば、その分住民税が減ります。
つまり年末調整の結果は、翌年の住民税に影響を与えるものであると覚えておきましょう。

源泉徴収票と給与支払報告書の関係
源泉徴収票と給与支払報告書は、年末調整の手続きのあとに作成する報告書です。どちらの書類も、年間で支払った給与の総額を記載する書類ですが、書類の提出先や作成する目的が大きく異なります。
| 源泉徴収票 | 給与支払報告書 | |
|---|---|---|
| 概要 | 個人の年間収入と納税額を証明する重要な文書 | 市区町村が住民税を計算するための文書 |
| 記載内容 | 企業が従業員に対して支払った「給与の支払総額」「源泉徴収した税額」「各種控除額」 ※記載内容ほぼ同じ | |
| 利用者 | 税務署に提出、従業員本人に交付 | 従業員の居住地である市区町村に提出 |
源泉徴収票と給与支払報告書を詳しく整理したい方は以下の記事もご確認ください。
年末調整や確定申告をしないと住民税の申告が必要
企業に勤める従業員で特別徴収を受けている人や、個人事業主やフリーランスでみずから所得税の確定申告をする人は、住民税の申告が必要ありません。
しかし、年末調整や確定申告をしていないのであれば、自治体が住民税を正しく算出するために、個人で申告する責任があります。
住民税申告が必要になる詳しい条件や手続きについて詳しく確認していきましょう。
申告が必要な場合・不要な場合
住民税申告とは、地方税である住民税の納税額を申告することです。
住民税は、1月1日から12月31日までの所得に対して課税され、翌年の3月15日までに申告をしなければなりません。申告先は、1月1日時点で居住する市区町村の自治体です。
住民税申告の要・不要の条件は、次のとおりです。
| 住民税の申告が必要 | 住民税の申告が不要 |
|---|---|
| ・確定申告が不要な人 ・会社を退職して年末調整を受けていない人 ・年末調整を受けていない分の収入が20万円以下である人 ・医療費控除のように特別な控除制度を利用する人 ・生活保護や災害などを理由に住民税の減免制度を利用する人 | ・確定申告をしている人 ・年末調整の手続きを受けている人 ・公的年金収入を得ていて、医療費控除などを利用しない人 |
住民税の申告が必要な場合は居住エリアによって多少異なりますが、条件はほとんどの地域で共通しています。申告が必要かどうかを確認するには、各市区町村のホームページを確認するか、直接役所にお問い合わせください。
年末調整と住民税の関係に関する質問
最後に、年末調整と住民税の関連性について、よくある質問と回答を紹介します。
| 住民税を払い過ぎたら年末調整で還付してもらえる? | × |
| 住民税は年末調整の控除の対象? | × |
| 年末調整で住民税の領収書は必要? | × |
| 年末調整をしたら住民税の申告は必要? | × |
| 年末調整を忘れたら住民税はどうなる? | 所得に応じて翌年の住民税が上がる可能性も |
住民税を払い過ぎたら年末調整で還付してもらえる?
年末調整の対象は所得税のみで、住民税は対象外です。所得税の過払い分は年末調整の際に還付してもらえますが、住民税の過払い分は還付を受けられません。
年末調整で確定した所得額をもとに翌年の住民税を算出するため、住民税は所得税のように差分が生じにくいです。ただし次の条件に該当する場合は、住民税が還付される可能性があります。
- 扶養控除の変更をした
- 住宅ローン控除や医療費控除の漏れがあった
- 年末調整をしていない
- 株の売却損がある
- 確定申告に誤記載があった
住民税の還付を受けるためには、住民税申告が必要です。市区町村から送付される「過誤納通知書」をもとに、必要な手続きを進めます。還付されるタイミングは、自治体によって違いはありますが、申告してから2〜3か月で還付されるケースが多いようです。
還付される時効は、発行日や通知日など、請求できる日から5年間です。申告できる期間内に、必要な手続きを行ってください。
住民税は年末調整の控除の対象?
住民税は、年末調整の控除の対象ではありません。
年末調整は、その年の収入に対して課税される所得税の計算を行うための手続きです。前年の所得をもとに課税額が算出される住民税は控除の対象外なので、注意しましょう。
年末調整で住民税の領収書は必要?
年末調整では、所得控除を受けるために保険料などの領収書が必要になります。しかし、年末調整の手続きに住民税の領収書は必要ありません。住民税は年末調整の控除対象ではなく、年末調整の手続きに関係しないためです。
年末調整をしたら住民税の申告は必要?
勤務先で年末調整を受けている人や確定申告をしている人は、住民税を申告する必要はありません。年末調整や確定申告のデータをもとに、それぞれの自治体が住民税を計算してくれるためです。
年末調整を忘れたら住民税はどうなる?
従業員が納税する住民税の額は、年末調整で決定された所得から算出されるものです。
年末調整では、社会保険料控除や扶養控除など、さまざまな所得控除が適用されます。
万が一、年末調整の手続きが遅れてしまったり、忘れてしまったりした場合は、所得控除が適用されずに、控除前の所得に対してそのまま課税されてしまうため、本来よりも高額な住民税となるおそれがあります。
所得控除を適切に受けるためにも、年末調整の手続きは忘れずに進めましょう。
まとめ
企業に勤めていて源泉徴収をされている人は、勤務先が年末調整の手続きをしてくれるため、原則として住民税を申告する必要はありません。ただし年末調整で受けられる控除には限りがあり、確定申告で住宅ローンや医療費控除などの申請をすると住民税の減額や還付されるケースもあります。
本記事で紹介した内容を参考にしながら、年末調整と住民税の関係について正しく理解しましょう。
年末調整の電子化に|One人事[労務]
年末調整に関わる業務は非常に煩雑であり、工数のかかるものです。限られた時間の中でミスなく円滑に進めるには、業務の電子化をおすすめします。
One人事[労務]は、書類の回収から申請までを半自動化することで、効率的な年末調整業務を支援するツールです。修正の差し戻しや進捗状況の把握も簡単な操作で実施できます。
One人事[労務]の機能や操作性は、こちらの資料よりご確認いただけます。さらに詳細を知りたい方は、当サイトよりお気軽にご相談ください。専門スタッフが課題をお聞きしたうえでご案内いたします。
また、当サイトでは労務管理の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードしていただけます。労務管理をシンプルにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |
