11月退職者の年末調整は必要? 基本のルールや必要なケースを紹介
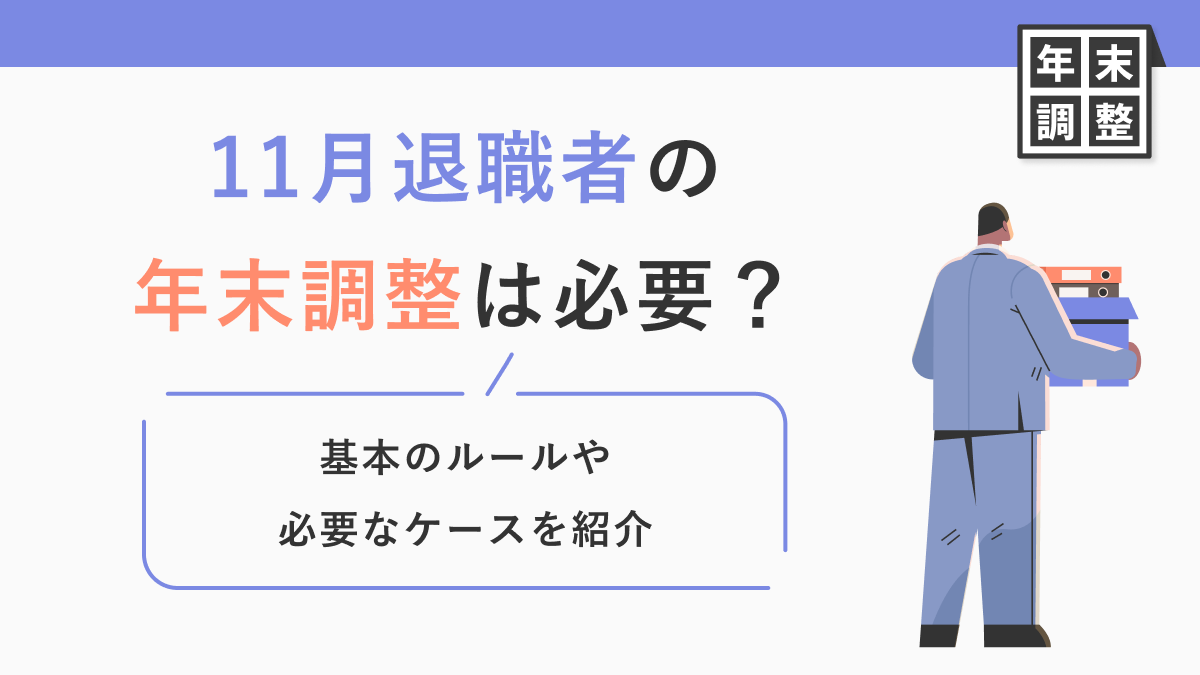
「11月に退職した従業員の年末調整は、会社でやるべきなのか」と不安になる担当者もいるのではないでしょうか。
年末調整の対象は原則として、12月末時点で在籍している従業員です。11月退職者については、基本的に会社で年末調整を行う必要はありません。
ただし、退職者の事情や給与の支給時期によって、会社で年末調整を行う必要があるケースもあるため注意が必要です。
本記事では、11月に退職した従業員の年末調整について、原則不要な理由と例外的に必要なケース、源泉徴収票の取り扱いや実務上の注意点などを解説します。

 目次[表示]
目次[表示]
年末調整の一般的なスケジュール
まずは、年末調整の一般的なスケジュールを確認しておきましょう。
年末調整は、原則12月31日時点で在籍している従業員を対象として、1年間に納めた所得税の過不足を精算する手続きです。
多くの企業では11月初めから書類回収を開始し、12月中に計算処理を終えるスケジュールで進められています。ただでさえ忙しい年末は、ほかの業務とも重なり、毎年バタバタしてしまうという担当者も少なくありません。
では、11月に従業員が退職した場合、年末調整の対応はどうなるのでしょうか。
11月に退職した人の年末調整はどうなる? 正社員の場合
11月に退職した従業員の年末調整は、通常会社で行う必要はありません。
ただし、その後すぐ年内に転職したかどうかによって、対応方法が少し変わります。
11月に退職した従業員の状況に応じてどのような対応が必要なのか、2つのケースを解説します。
年内に転職する場合
11月に退職した従業員が同じ年のうちに新しい会社へ就職した場合、年末調整は転職先の会社で行うことになります。「12月31日時点で在籍している会社が年末調整を行う」という原則に基づくためです。
転職先での年末調整の流れは、とてもシンプルです。 前の会社が配付した源泉徴収票を、退職者が新しい勤務先に提出することで、1年間の所得が正しく合算され、年末調整は完了します。
年末調整によって税金の過不足が調整されるため、確定申告は原則として不要です。
ただし注意したいのは、源泉徴収票の提出が遅れると、転職先での年末調整に間に合わない可能性があります。12月末が締め切りのため、退職後はなるべく早く源泉徴収票を受け取り、新しい会社へ提出しなければなりません。
退職者が転職先で困らないよう、源泉徴収票の発行時期や、転職先での提出の必要性をあらかじめ伝えておくと親切です。
年内に転職しない場合
11月に退職したあと、年内に再就職しない場合は、会社で年末調整を受けられません。
一般的には退職者自身が、翌年の2月16日~3月15日の間に確定申告をします。ただし、還付申告の場合は翌年1月1日から5年間であればいつでも可能です。必ずその期間にする必要はありません。
確定申告と聞くと「難しそう」と感じる方も多いかもしれませんが、実際にはそれほど複雑ではありません。前職から受け取った源泉徴収票をもとに1年間の所得や控除を自分で計算し、税務署に申告するだけです。
期間内(還付申告の場合は翌年1月から5年間)に申告しないと、払いすぎた税金の還付が受けられないこともあるため、忘れずに対応しましょう。
確定申告にも源泉徴収票が必要です。退職時に必ず交付し、確定申告の必要性もあわせて伝えることをおすすめします。

パートが11月で退職した場合は年末調整の要否に注意
パート・アルバイトが11月に退職した場合も、年末調整が必要かどうかは「年収」や「退職後の就労予定」によって判断されます。
とくに、パートタイム労働者は正社員と比べて、年間の給与総額が103万円以下となるケースが多く、判断に迷いやすい点です。
年末調整が必要となるのは、次の両方にあてはまるケースです。
- 年内に他社で働く予定がない
- 年間の給与収入が123万円以下に収まる見込みである
以上の場合、会社側で退職時に年末調整を行う必要があります。「年内に給与の支払いを受ける見込みがない従業員」に対しては、会社側で年末調整を完結させることが原則とされているためです。
一方で、以下に該当する場合は、パート従業員は年末調整の対象外となり、本人が翌年に確定申告を行う必要があります。
- 退職後に新たな勤務先から給与を受ける
- 年間の給与が123万円を超える
退職時点での支給済み給与額や、他社での就業予定の有無をもとに、年末調整の要否を判断しましょう。
11月退職でも年末調整が前倒しで必要なケース
年末調整は、12月31日時点で在籍している従業員を対象とするのが原則であり、11月に退職した場合は通常、会社で年末調整を行う必要はありません。
しかし実務では、以下のいずれかに該当する場合、退職時に前倒しで年末調整が必要になります。
- 海外転勤などにより非居住者となった人
- 死亡によって退職した人
- 著しい心身の障害のために退職した人
- 12月に支給されるべき給与を受け取ってから退職した人
以上のような例外ケースでは、12月末の在籍を待たずに、年末調整を前倒しで行う必要があるため、注意が必要です。
海外転勤などにより非居住者となった人
従業員が海外支店に転勤し、非居住者扱いとなる場合は、11月時点でも会社で年末調整を行う必要があります。
非居住者となると、国内での給与の支払いが終了し、税務上は日本での課税関係が終了したとみなされます。そこで在職中でも退職者と同様の扱いで、1年分の所得を確定させ、その時点で年末調整を完了させなければなりません。
このケースでは、事前の準備が重要です。海外赴任が決まり次第、年末調整に必要な書類を早めに回収し、赴任日までに処理を完了させるようにしましょう。海外に行ってしまうと、あとから書類の提出を依頼するのが困難になるため、計画的な対応が求められます。
死亡によって退職した人
従業員が在職中に亡くなった場合も、退職時点で年末調整を行う必要があります。たとえ年末を迎えていなくても、支払われた給与・賞与などの所得について、会社が年末調整を実施する必要があるのです。
この取り扱いは、税法上の特例であり、遺族の負担を軽減することが主な目的です。もし年末調整を行わなければ、遺族が確定申告をしなければならず、負担が大きくなってしまいます。
死亡退職者の年末調整にあたっては、次の点を確認します。
- 死亡日までに支払われた給与・賞与の金額
- 控除申告書に記載された内容(生命保険料控除や扶養控除など)
- 源泉徴収票の交付
遺族への説明や必要書類の案内は、心情に配慮しながら、落ち着いた対応を心がけましょう。
著しい心身の障害のために退職した人
従業員が著しい心身の障害により退職した場合も、会社で年末調整を行います。ただし、退職後に再就職して給与を受け取る見込みがある場合は、対象にはなりません。
障害による退職は、本人や家族にとって大きな負担となります。医療費や生活環境の変化など、さまざまな課題に直面することが少なくありません。
年末調整を実施することで、確定申告の負担を軽減できるため、会社の対応が重要です。手続きにあたっては、次の点を確認します。
- 医師の診断書
- 本人の申告書
- 障害の程度
- 再就職の見込みの有無
- 障害者控除の適用可否
- 特別な控除の有無(寝たきりなど)
適切な判断のもと、年末調整を行い、本人やご家族へのサポートにつなげましょう。
12月に支給されるべき給与を受け取ってから退職した人
11月に退職する場合でも、12月に支給予定の給与を受け取ってから退職した場合は、会社で年末調整を行う必要があります。1年間の給与がすべて、その会社で確定するためです。
会社が年末調整を実施することで、退職者本人による確定申告は不要です。ただし、給与支給のタイミングと退職日に注意しなければなりません。
- 12月給与の支給前に退職した場合:年末調整は不要(退職者が確定申告)
- 12月給与の支給後に退職した場合:年末調整が必要(確定申告は原則不要)
年末は業務が立て込みやすい時期だからこそ、判断ミスがないように注意深く対応することが大切です。退職者本人にも「年末調整は完了したこと」「確定申告は不要であること」を伝えると、安心してもらえるでしょう。
そもそも年末調整が不要なケース
年末調整は多くの従業員に必要な手続きですが、そもそも対象外となるケースもあります。対象外の代表的な例として以下があります。
ここまで、11月に退職した従業員は原則として年末調整の対象外であることを解説してきました。
11月退職以外にも、年末調整の対象とならないケースがいくつかあります。代表的な例をおさらいしておきましょう。
- 年収が2,000万円を超える人
- 年の途中で退職し、特例(例:海外転勤による非居住者、死亡退職、著しい心身障害による退職など)に該当しない人
- 2か所以上の勤務先から給与を受け取っている人
- 給与所得者の扶養控除等申告書を提出していない人
以上に該当する場合は、会社では年末調整を行わず、本人が確定申告を行うことになります。
年末調整を怠った場合の罰則
年末調整は企業に課された法的な義務です。必要な年末調整を怠った場合、罰則や追加の税負担が発生する可能性があります。
年末調整を怠った場合には直ちに刑罰になるわけではありませんが、指導を無視したり悪質な場合は罰則の対象となる場合があります。 虚偽の記載をした場合や税務署へ法定調書を提出しなかった場合には、所得税法に基づき「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」が科されることがあります。「知らなかった」「忙しくて時間がなかった」という理由は通用しません。
源泉徴収した所得税を意図的に納税しなかったなど悪質と判断された場合は、「10年以下の懲役または200万円以下の罰金」といった重い刑罰が科される可能性もあります。
また、納税が遅れると、延滞税や不納付加算税が自動的に課されます。納付期限は翌年1月10日、書類の提出期限は1月31日です。
期限に遅れることで、税務署から督促が届くほか、最悪の場合は資産の差し押さえや企業の信用低下といった深刻な事態につながるおそれもあります。
11月退職者は早めに源泉徴収票を発行
11月に退職した従業員が自社で年末調整の対象外となる場合でも、源泉徴収票の発行は必須の手続きです。
源泉徴収票は、転職先での年末調整や本人による確定申告に必ず必要な書類だからです。企業は退職日から1か月以内に源泉徴収票を作成し、本人に交付しなければなりません。
源泉徴収票には支払った給与や、源泉徴収税額などが記載されており、所得証明や税務手続きの基礎資料として使われます。
源泉徴収票の活用場面は主に2つあります。
- 年内に転職した場合:新しい勤務先に提出することで、前職と合算した年末調整が可能
- 年内に転職しない場合:翌年の確定申告で必要。紛失しないように大切に保管してもらいましょう。
まとめ
11月に退職した従業員の年末調整は、基本的に自社で行う必要はありません。ただし、12月の給与受給後の退職や、死亡退職などの特定の条件に該当するケースは注意が必要です。
年末調整が不要な場合でも、源泉徴収票の発行は必須です。 退職者が転職先で年末調整を受ける場合や、自分で確定申告を行う際に必要となります。発行が遅れると、退職者が次の手続きで困ることもあるため、ミスなくすみやかに交付しましょう。
年末調整や源泉徴収票の発行を効率化するには?
年末調整業務や源泉徴収票の発行をスムーズに進めたい場合は、年末調整システムの導入も有効です。システムを活用すれば、人的ミスや手間を減らし、書類作成や従業員とのやり取りも効率化できます。
11月退職者の対応は、例外や手続きの違いをしっかり理解し、迅速かつ正確に進めることが重要です。担当者は、年末調整のルールと実務ポイントを押さえ、退職者が安心して次のステップに進めるようサポートしましょう。
One人事[労務]は、書類の回収から申請までの過程を半自動化し、効率的な年末調整を支援する労務管理システムです。修正の差し戻しや進捗状況の把握も簡単な操作で実施できます。
One人事[給与]との連携により還付金の計算もスムーズに進められます。
One人事[労務]の機能や操作性は、こちらの資料でもご確認いただけます。さらに詳細を知りたい場合は、当サイトよりお気軽にご相談ください。専門スタッフが課題をお聞きしたうえでご案内いたします。
また、当サイトでは労務管理の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードしていただけます。労務管理をシンプルにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |
