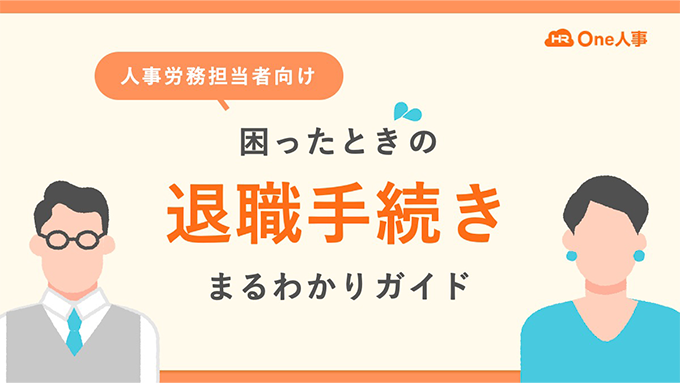退職金に年末調整が不要な理由【わかりやすく】税金の計算方法や確定申告が必要な場合も解説
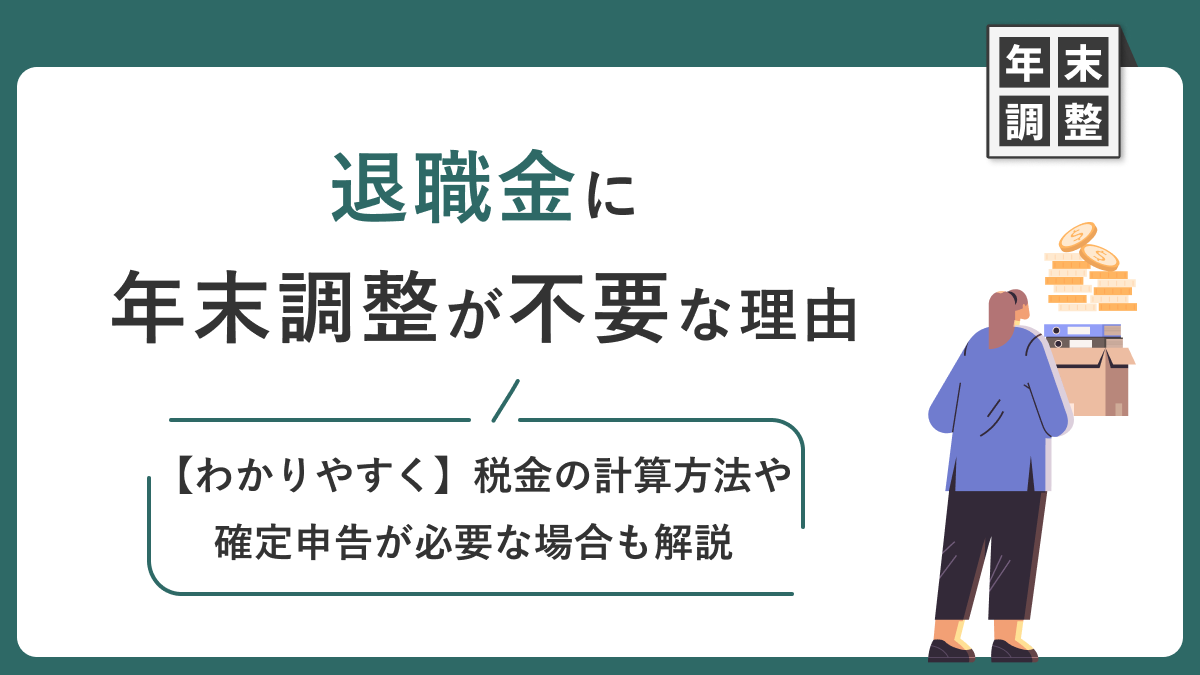
退職金は年末調整の対象外です。「給与所得」ではなく「退職所得」という区分で、支給時に会社が源泉徴収を行うため、年末調整で再計算する必要はありません。
ただし、退職金は非課税というわけではありません。退職所得として所得税と住民税がかかります。計算方法は通常の給与とは異なり、特別に優遇される税務処理が必要です。
本記事では、退職金に年末調整が不要な理由を詳しく解説し、税金の計算方法や確定申告が必要となる場合について、人事実務の観点から紹介します。

 目次[表示]
目次[表示]
退職金が年末調整の対象にならない理由
退職金が年末調整の対象外となる理由は、所得税法上の分類と課税方式の違いにあります。
年末調整は「給与所得」に対する税額調整の手続きです。退職金は「退職所得」として別の所得区分に分類されます。退職金は分離課税の対象となり、給与所得とは異なる計算方法で税額が算出されます。
退職金は老後の生活資金としての性質を持つため、特別に税務上優遇されているのです。ほかの所得と合算して課税すると、税負担が大きくなってしまうため、分離課税方式が採用されています。
退職金は支給時に一括して税額計算と源泉徴収が行われるため、年末調整による調整は必要ありません。
そもそも年末調整とは
年末調整とは、1年間に支払われた給与に対して、最終的な所得税額を確定させる手続きです。毎月の給与からは、あくまでも「源泉徴収税額表」をもとに税金が源泉徴収されています。
しかし実際の年収は、賞与の有無や給与の変動によって、概算金額と異なることがほとんどです。そのため、年末に1年間の収入を正確に計算し直し、払いすぎた金額は還付、不足していれば追徴という方法で調整します。
生命保険料控除や住宅ローン控除など、年の途中では反映されない控除も、年末調整でまとめて精算されます。
退職金は確定申告も原則不要
退職金は、年末調整だけでなく、確定申告の対象にもなりません。
従業員が退職時に会社へ提出する「退職所得の受給に関する申告書」によって税務処理が完結するためです。
会社は申告書をもとに税額を算出し、所得税・復興特別所得税・住民税を退職金支給時にまとめて源泉徴収します。
そのため、基本的に退職者が自分で確定申告を行う必要はありません。
ただし、申告書を提出していない場合や、医療費控除など追加の控除を受けたい場合は、確定申告が必要となります。
退職金にも3つの税金がかかる
退職金は年末調整の対象外であるものの、課税対象所得として税金が課されます。
退職金に課される税金は所得税、復興特別所得税、住民税の3種類です。それぞれ異なる目的と計算方法を適用する必要があるため、退職金にかかわる点をおさえておきましょう。
所得税:退職金は「退職所得」として分離課税
所得税は、個人が1年間に得た所得に対して課される国税です。所得は10種の区分に分かれ、それぞれ異なる課税方式が採用されています。
退職金にかかる所得税は、ほかの所得と切り離して「分離課税方式」で計算します。
通常の給与は「総合課税方式」なのに対し、退職金は老後資金としての性質を考慮されて優遇されているためです。
さらに「2分の1課税」という特例もあり、課税負担を軽減するために制度が設計されているといえるでしょう。
なお、退職金に対する所得税の税率は、退職所得の金額に応じて、5%から45%まで段階的税率が適用されます。
復興特別所得税:所得税に上乗せされる臨時税
復興特別所得税は、東日本大震災からの復興財源を確保するために設けられた時限的な税金です。 2013年から2037年までの25年間、所得税額の2.1%が上乗せされる仕組みとなっています。
退職金も所得税の課税対象であるため、同様に復興特別所得税が適用されます。所得税が発生しない場合は復興特別所得税が課されません。
復興特別所得税は、退職金の源泉徴収時に、所得税と一緒に自動で計算・納付される点をおさえておきましょう。
住民税:退職時の住所地で一律10%が課税
退職金には住民税もかかります。 税率は、退職時点で前年1月1日に住所があった市区町村に対して、一律10%(市民税6%+県民税4%)です。
通常の給与のように翌年度へ繰り越して課税されるわけではなく、退職金支給時に源泉徴収で完結します。
また、住民税も所得税と同様に、退職所得のみで計算され、ほかの所得と合算することはありません。 退職金を受け取った時点で課税処理が完結すると理解しておきましょう。
退職金にかかる税金の計算方法
退職金にかかる税金は、次の5つの手順で計算します。まずは全体の流れをつかみましょう。
- 退職所得控除額を計算する
- 退職所得額を求める(2分の1課税)
- 所得税額を算出する
- 復興特別所得税を加算する
- 住民税を計算する
手順を理解しておくと、退職金の源泉徴収額の仕組みが見えてきます。ステップごとに確認していきましょう。
1.退職所得控除額を計算する
退職所得控除額は、何年働いたかによって計算方法が異なります。
| 勤続年数 | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(最低80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 × (勤続年数 – 20年) |
勤続年数が20年以下なら「40万円×勤続年数」で計算しますが、80万円を下回る場合は最低保証額は80万円です。勤続年数が20年を超えると「800万円+70万円×(勤続年数−20年)」で求めます。
たとえば勤続25年なら、控除額の計算例は以下のとおりです。
| 退職所得の控除額=800万円+350万円=1,150万円 |
長く勤務するほど控除額も増えるため、負担が軽く感じられる方も少なくないでしょう。
なお、障害が理由での退職なら、100万円加算される点もおさえておく必要があります。
2.退職所得額を計算する
退職所得額は、退職金から1で算出した控除金額を引いて、2分の1を乗じます。
ただし、「2分の1課税」はすべての退職金に適用されるわけではないため、注意が必要です。
| 退職所得 =(退職金 – 退職所得控除額)× 1/2 |
2分の1を掛け算するのは、退職金の性質を考慮した優遇措置です。
退職金2,000万円、控除額1,500万円の場合、計算例は以下のとおりです。
| 退職所得 =(2,000万円−1,500万円)×1/2=250万円 |
退職所得額の出し方は、退職という人生の転機に、税負担が和らぐように設計されています。計算式だけを見ると難しそうですが、引いて半分にするだけと覚えれば簡単です。
3.退職所得の所得税額を計算する
所得税額は、退職所得に税率を乗じ、控除額を差し引いて求めます。
| 所得税=退職所得×税率−控除額 |
税率は所得金額に応じて段階的に上がり、5%から45%の範囲です。
| 課税退職所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
出典:『退職金と税』国税庁
課税退職所得が250万円で、税率10%、控除額97,500円の場合、計算例は以下のとおりです。
| 所得税額 = 250万円×10%−97,500円=152,500円 |
「多くもらうと税金も増える」という仕組みです。給与とは違う点に注意しましょう。「今の自分だと何%?」と調べてみると、意外な発見があるかもしれません。
退職金に対する所得税は、課税退職所得金額に応じて段階的に税率が上がる仕組みとなっています。 退職金額や勤続年数によって税負担が大きく変わります。退職金シミュレーションが必要なケースがあれば、この点を踏まえて概算を試算するとよいでしょう。
4.復興所得税額を計算する
復興特別所得税は、東日本大震災からの復興財源として設けられた税金です。算出された所得税額に2.1%を乗じて計算します。
| 復興特別所得税 =所得税額 × 2.1% |
所得税が152,500円なら、計算例は以下のとおりです。
| 復興特別所得税 =152,500円×0.021=3,202円 |
端数は切り捨てが必要です。
5.住民税を計算する
住民税は退職所得に一律10%の税率を乗じて計算します。市民税が6%、都道府県民税が4%の内訳となります。
| 住民税=退職所得×10%(市民税6%・都道府県民税4%) |
退職所得250万円なら、計算例は以下のとおりです。
| 住民税=250万円×10%=25万円 |
【例外】退職金にかかる税金を計算する際の注意点
退職金の税金は基本的に「退職所得控除」や「1/2課税」が適用されますが、すべての退職者が同じ扱いになるわけではありません。
次のような場合は、通常の計算方法が使えない例外的なケースです。
- 勤続5年以下の短期退職(2分の1課税が適用されない)
- 退職金が非課税となるケース(控除超過・死亡退職など)
- 「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合
それぞれのケースについて、順に見ていきましょう。
退職所得に2分の1を適用しない場合
勤続年数が5年以下の従業員や役員が受け取る退職金には、通常の「2分の1課税」が適用されません。
短期間で高額な退職金を受け取るケースが課税回避に利用されるのを防ぐためです。具体的には以下のように区分されます。
- 短期退職手当:勤続5年以下の一般従業員に支払われる退職金
- 特定役員退職手当:勤続5年以下の役員に支払われる退職金
短期退職手当等は、退職金の額から退職所得控除額を差し引いた額のうち300万円を超える部分については2分の1課税が適用されません。
特定役員退職手当は退職所得控除額を差し引いた残額がすべて課税対象となります。 2分の1課税が適用されないため、通常より税負担が大きくなる点に注意が必要です。
退職金規程を見直す際は、役員の在任期間と支給額のバランスを確認しておきましょう。
退職金が非課税になる場合
退職金が非課税になるのは、次の2つのケースです。
- 退職所得控除額が退職金額を上回る場合
- 従業員が死亡した場合
退職所得控除額が退職金額を超えると課税所得がゼロになり、税金はかかりません。小額の退職金や、勤続年数が長く控除額が大きい場合に該当します。
また、死亡退職金は所得税の対象ではなく、相続税の対象です。死亡退職の場合も一定額まで非課税枠が設けられています。
人事労務担当者は、退職事由(生前退職か死亡退職か)によって課税区分が変わる点を把握し、遺族への説明や書類準備に誤りがないよう注意しましょう。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合
退職金の正確な税額計算には、「退職所得の受給に関する申告書」の提出が欠かせません。
申告書が提出されていないと、退職金に対して一律 20.42%(所得税+復興特別所得税) の高い税率で源泉徴収されます。
未提出の場合は、従業員が過大に源泉徴収される可能性があるため、担当者は退職時に確実に提出を促すことが重要です。
もし未提出のまま支給してしまった場合、退職者本人が確定申告を行うことで払いすぎた税金を還付できます。ただし、退職後に本人が自力で対応する必要があるため、トラブル防止のためにも社内体制を整備しておくほうが望ましいでしょう。

退職金の受領後に確定申告が必要な場合
退職金は原則として確定申告が不要ですが、退職後の状況によっては申告が必要になります。退職金や退職後の所得に関して、確定申告が必要となるのは以下の6つのケースです。
- 公的年金などの収入合計額が400万円を超える
- 退職金や給与以外の所得がある
- 退職後に個人事業主やフリーランスになった
- 「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない
- 年の途中で退職して再就職していない
- 年末調整で適用できなかった所得控除がある
従業員から、退職金に関連して確定申告について尋ねられることもあるかもしれません。同様のケースか具体的に確認していきましょう。
公的年金などの収入合計額が400万円を超える
公的年金の年間受給額が400万円を超える場合は、確定申告が必要です。対象となるのは、厚生年金・国民年金・共済年金など、すべての公的年金の合計額です。
退職金は「分離課税方式」を適用するため年金とは合算しませんが、公的年金は「総合課税方式」です。
年金額は「ねんきん定期便」などで確認できます。申告期限を過ぎないよう、早めの準備を促すと安心です。
退職金や給与以外の所得がある
不動産収入・事業所得・副業収入などがある場合は確定申告が必要です。
退職金とは別に、不動産収入・事業所得・副業収入などがある場合は、確定申告が必要です。
家賃収入や株式の譲渡益など、ほかの所得と合算して「総合課税」の対象になります。
どの所得が申告対象か迷うときは、税務署や税理士への相談を案内しましょう。会社としても、再就職前後の副収入がある従業員には注意喚起しておくと親切です。
退職後に個人事業主やフリーランスになった
退職後に従業員が開業した場合は、事業所得として確定申告が必要です。売上規模によっては消費税の申告義務が発生するケースもあります。
開業初年度は手続きが煩雑になりやすいため、必要に応じて国税庁の「確定申告書等作成コーナー」などの公的情報源を案内するとよいでしょう。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない
申告書を提出せずに、従業員が退職金を受け取ると、一律20.42%の税率で源泉徴収されます。通常よりも高い税金が引かれ、従業員が損をしてしまうため、未提出の場合は、確定申告をすすめましょう。
確定申告をすれば払いすぎた税金を取り戻せます。
退職所得の受給に関する申告書は、退職手続き時に会社が従業員へ案内する重要書類です。提出漏れを防ぐため、退職時チェックリストに含めておくと安心です。
年の途中で退職して再就職していない
年の途中で退職し、年末調整を受けていない従業員は、確定申告によって納めすぎた税金が還付されることがあります。
毎月の給与からは、1年間勤務する前提で源泉所得税が計算されているため、途中退職では税金を多く納めすぎている可能性があります。
退職時には源泉徴収票を必ず交付し、従業員が申告に利用できるよう案内しておくと安心です。
年末調整で適用できなかった所得控除がある
退職後に再就職しておらず、年末調整を受けていない従業員は、控除を受けるために確定申告が必要です。
医療費控除や住宅ローン控除(初年度)、寄附金控除(ふるさと納税)、雑損控除などは年末調整では対応できません。
たとえば、医療費が年間10万円を超えた場合やふるさと納税をした場合は、確定申告によって税金が還付される可能性があります。
退職者に向けた案内では、控除証明書や領収書の保管を呼びかけ、申告漏れ防止をサポートするとよいでしょう。

まとめ|退職金に年末調整は原則不要だが、正しく税務手続きを
退職金は「給与所得」ではなく「退職所得」として扱われ、支給時に分離課税方式で源泉徴収が行われるため、年末調整の対象にはなりません。
税金は「退職所得控除」「2分の1課税」「段階的税率」などの優遇措置を踏まえて計算されるため、金額や勤続年数によって負担が大きく変わります。
一方で、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合や、退職後にほかの所得や控除がある場合は、確定申告が必要です。
人事労務担当者は、退職金支給時の源泉徴収処理だけでなく、退職者が確定申告を行う必要があるかどうかも含めて適切に案内できる体制を整えておくとよいでしょう。