36協定の届出に関する疑問|提出方法や期限、届出前に知っておきたいことをわかりやすく解説
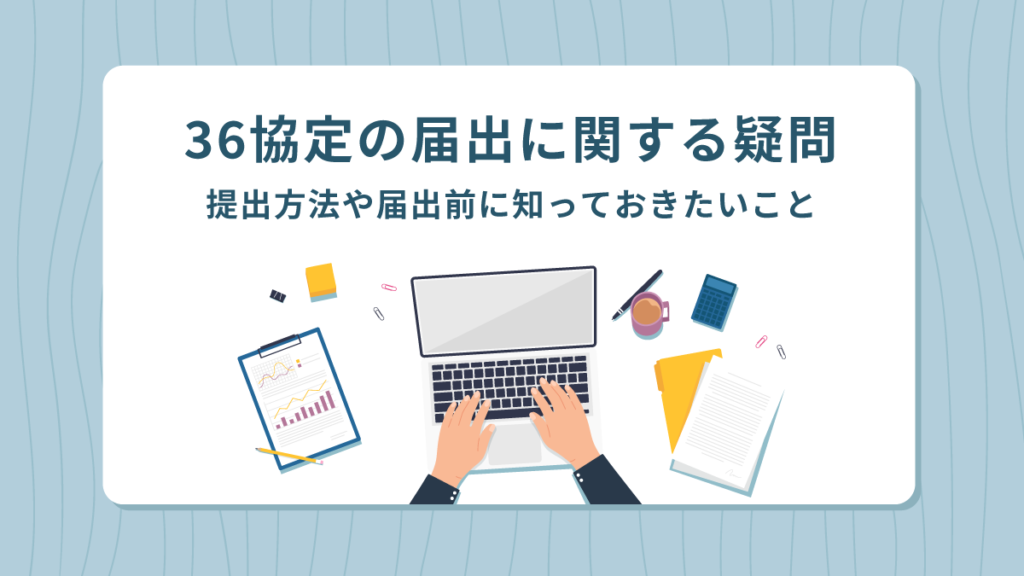
36協定の届出とは、36協定届を労働基準監督長に提出することです。時間外労働や休日出勤をする場合は必ず提出が必要であり、未提出のままでいると効力がありません。
本記事では、36協定の概要や届出方法、罰則などを解説します。勤怠管理を担当している方は、参考にしてください。
→36協定の管理にも「One人事」資料を無料ダウンロードする

 目次[表示]
目次[表示]
36協定の届出の意味と必要性
36協定の届出は、時間外労働や休日労働に関する労使協定(36協定)を労働基準監督長に届け出ることです。
企業が従業員に法定の「1日8時間/週40時間」を超える残業や休日勤務をさせる際は、労働基準監督署長へ36協定の届出が義務とされています。
36協定を締結しただけでは、効力はない点を理解しておきましょう。
36協定とは
36協定とは、労働基準法36条に基づいた「時間外・休日労働に関する労使協定」です。正式名称は「時間外・休日労働に関する労使協定」といいます。
1日8時間・週40時間以内の「法定労働時間」を超えて、従業員に時間外労働をさせる場合は締結と届出が必要です。
36協定の上限規制
36協定の上限は、原則として⽉45時間・年360時間です。以前までは、36協定による労働時間の上限はとくに決められていませんでした。
しかし、2018年に働き方改革関連法が公布され、時間外労働の上限規制に関する改正が実施されました。
大企業は2019年4月から、中小企業は2020年4月から適用されています。、さらに2024年4月からは、建設業やトラック・バス・タクシーなどのドライバー、医師といった適用猶予となっていた業種も対象となりました。
36協定の届出期限
36協定の届出にはとくに期限はありません。しかし、従業員に残業や休日出勤をさせる前に、36協定を締結して届出を行う必要があります。
また、36協定には1年から3年の有効期間があり、更新は通常1年ごとに行われることが推奨されています。
そのため、たとえば有効期間を1年間で設定している場合、前回の届出から1年以内に次の協定を締結・届出しなくてはなりません。「前回の届出から1年が更新期限」である点を心得て忘れないようにしましょう。

36協定を締結しなければならないのはいつ?
36協定を締結しなければならないのは、どのようなタイミングなのでしょうか。
- 締結が必要になるのは、以下の2つのケースです。法定労働時間を超えて時間外労働をさせる場合
- 法定休日に出勤させる場合
それぞれについて解説します。
法定労働時間を超えて時間外労働をさせる場合
事前に36協定を締結していないと、従業員に法定労働時間を超えて働かせることができません。36協定で労使間に合意がされている場合に限り、企業は従業員に対して、月に最大45時間、年間で最大360時間の残業を命じることが可能です。
日常的に1日8時間、週に40時間の法定労働時間が守られているなら、36協定の必要はありません。ただし、予期せぬ残業が発生した場合、36協定が締結されていなければ法律違反とみなされます。
企業規模や従業員の数に関係なく、事前に36協定を結んでおくことが望ましいといえるでしょう。
法定休日に出勤させる場合
従業員が「週に1回、または4週間に合計4回の休み」を取ることは、法律で義務づけられており、これを「法定休日」と呼びます。
たとえば、週休2日制(土日休み)の企業では、土日のうち、どちらかが法定休日で、もう片方が所定休日です。法定休日に従業員が出勤する場合は、あらかじめ36協定の締結が必要です。
ただし、法定休日に休日出勤を行わず、労働時間が法定労働時間の枠内に納まっていれば、36協定の締結は必要ありません。
36協定の届出前に知っておきたいこと
36協定の届出に関連して、届出の前に担当者が知っておきたいポイントを解説します。
- 36協定の項目を協議する
- 事業場単位で締結する
- 36協定届は押印と捺印を省略できる
- 36協定の有効期限は最長3年まで設定できる
- 事業場単位で締結する
36協定の項目を協議する
36協定では、従業員に時間外労働をさせる際の条件を詳細に定める必要があります。
36協定を締結するにあたって、労使で協議すべき主な項目は以下のとおりです。
- 対象となる従業員の範囲
- 対象期間
- 時間外労働や休日出勤をさせることができる場合
- 対象期間における1日、1か月、1年のそれぞれの期間における時間外労働の時間および休日出勤させることのできる休日の日数
- 有効期間および起算日
なかでも、時間外労働の理由や具体的な業務内容、従業員の人数を明確にすることは非常に重要といえます。内容が不明瞭だと企業が36協定を都合よく解釈し、従業員が不利益を受ける恐れがあるためです。労使間での問題を防ぐため、具体性と明確性を持った協議が必要です 。
また、時間外労働の上限は「月45時間・年360時間」と定められています。しかし、特別条項を締結する場合は、上限を超過することも可能です。
事業場単位で締結する
36協定は、それぞれの「事業場」ごとに締結する必要があります。事業場とは、実際に従業員が働いている場所のことです。
支社や支店、営業所など複数の事業場がある大きな企業では、個別に36協定を結び、それぞれの事業場を管轄する労働基準監督署長に届け出ることが基本です。
36協定届は押印と捺印を省略できる
2021年3月までの36協定届には、社印の押印と労働者代表の署名または記名・押印が必要でした。しかし、2021年4月からは、36協定届に対する押印や署名が不要となっています。
ただし、押印や署名の省略は36協定届に限定されています。36協定届が労使間の合意の証として「36協定書」の役割も果たす場合は、引き続き必要であるため、混同しないようにしましょう。
36協定の有効期限は最長3年まで設定できる
36協定の有効期間は最長3年まで設定が可能です。有効期限は1年以上3年以内で自由に決められ、一般的には1年ごとの更新が推奨されています。
定期的に36協定の内容を見直せることから、多くの企業が1年ごとに更新しているようです。
ただし、特定のプロジェクトや業務が1年以内に完了する場合は、業務期間に合わせて有効期限を設定することもできます。
電子申請以外の提出は書類を2部用意する
36協定届は電子申請で行うのが便利です。しかし、電子申請以外の方法でも提出できます。
36協定届を紙で窓口持参や郵送によって提出するときは、2部の書類が必要です。1部は提出用として労働基準監督署長に提出し、もう1部は保管用の控えとします。
保管用の控えは従業員に知らせるために使うとよいでしょう。控えはコピーで構いませんが、手続きに手間がかからないように、事前に2部準備しておくことをおすすめします。

36協定の届出までの流れ・手順
36協定の届出の流れを順を追ってご紹介します。
1.36協定の内容検討など事前準備をする
2.労働者代表を選出する
3.36協定届(36協定書)を提出する
4.従業員への周知とシステムへの反映をする
1.36協定の内容検討など事前準備をする
36協定の届出は、約1か月前から余裕を持って事前準備を進めましょう。まずは前年度の36協定届の内容を見直し、過去1年間の時間外や休日労働の状況を確認して、今年度の計画を立てます。
次に、最新のフォーマットや36協定作成ツールを使用して、36協定書の草案を作成します。その後、過半数代表者の選出方法を「推薦」や「挙手」「労働者の話し合い」などから決め、立候補の方法・期限・選出日や期間を含めた公示の内容を検討します。
2.労働者代表を選出する
36協定の届出では、事業場ごとに労働者代表を選出します。全従業員に情報を伝える必要があるため、スケジュールは早めに調整しましょう。
過半数代表者の立候補者を募集するための公告を、メールや掲示板などを活用し、前もって知らせます。その後、定めた方法に従って労働者代表の選出を行います。
3.36協定届(36協定書)を提出する
前年度の期限が切れる前に、今年度の36協定の届出を行うことが重要です。たとえば、起算日が10月1日であれば、その年の9月中に届出を完了させる必要があります。
手続きには、労働者代表と合意形成を行い、最終的に36協定書の内容を決める作業が含まれます。36協定届が完成したら、電子申請や郵送、窓口持参のいずれかの方法で提出します。
4.従業員への周知とシステムへの反映をする
提出した36協定は、従業員に周知する義務があります。周知を怠ると労働基準法第106条違反として30万円以下の罰金が科される可能性があるため、注意が必要です。
また、今年度の36協定に基づいた設定を勤怠管理システムに反映させましょう。
36協定の届出・手続き方法
続いて、36協定の届出・手続き方法は、電子申請や郵送、窓口持参の3種類あります。それぞれの手続きについて解説します。
労働基準監督署の窓口で手続きをする
36協定の届出は、管轄の労働基準監督署で行うことができます。労働基準監督署を直接訪問するメリットは、書類作成に関する疑問をその場で質問して解決できる点です。
ただし、労働基準監督署での手続きは平日の日中に限られており、勤務時間中に訪れる必要があります。とくに3月から4月は混雑が予想されるため、時期を調整することも検討するとよいでしょう。
郵送で提出する
36協定の届出書類は、管轄の労働基準監督署に郵送することも可能です。郵送の場合、36協定届の原本とコピーを合わせた2部を封筒に入れ、返送用の封筒(返送先の住所と名前を記載済み)と必要な切手、同封する書類と枚数を明記した送付状を同梱します。
郵送での提出は、労働基準監督署の開庁時間を気にせず手続きできて便利です。しかし、郵送には数日から1週間程度かかることがあるため、余裕を持って行う必要があります。

電子申請をする
厚生労働省や労働基準監督署では、電子申請による36協定の届出を推奨しています。
電子申請を利用するには、国の行政サービスを一元管理している『e-Gov』のアカウントが必要です。
e-Govアカウントをすでに持っていればすぐに使用できますが、初めて利用する場合は、新たにアカウントを作成しなければなりません。アカウントを取得したら、使用するオペレーティングシステムに適した電子申請アプリケーションをインストールします。
e-Govのアプリケーションにアクセスし、利用可能な手続きの中から36協定届を選択してフォームに必要な情報を記入しましょう。作成した書類をシステムを通じて提出することで、届出の手続きが完了します。
36協定の届出に違反したときの罰則
36協定の届出に違反した場合、最大で6か月の懲役刑や30万円以下の罰金に処される可能性があります。悪質な場合には、厚生労働省や都道府県の労働局のWebサイトに企業の情報が公開されることもあります。
具体的な違反内容は、労使協定なしでの時間外労働や、36協定で定めた時間を超えて労働させる行為などです。
罰せられるのは企業だけでなく、従業員の労務管理を担当する責任者も対象となるため、36協定の届出が正しく実施できているか都度確認しながら業務を遂行しましょう。
まとめ
36協定の届出とは、労使で締結した36協定を労働基準監督長に届け出ることです。時間外労働や休日出勤をさせる場合は必ず届出が必要となり、違反すると罰則もあるため注意する必要があります。
電子申請や36協定の徹底をしたい企業は、自社に適した勤怠管理システムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
勤怠管理を徹底するなら|One人事[勤怠]
One人事[勤怠]は、煩雑な勤怠管理をクラウド上で完結させる勤怠管理システムです。
- 勤怠の入力・打刻漏れが多い
- 月末の集計をラクにしたい
- 労働時間や残業時間を正確に把握できていない
というお悩みを持つ企業をご支援しております。
One人事[給与]と連携すれば、給与計算に自動で紐づけられるため、より速くより正確に業務を進められるでしょう。また、有給の付与・失効アラート機能や、労働基準法などの改正にも対応しております。
One人事[勤怠]の初期費用や気になる操作性については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門のスタッフが貴社の課題をていねいにヒアリングしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、勤怠管理の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードしていただけます。勤怠管理をラクにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |
