残業の多い・少ないはどう評価すべき?残業によらない人事評価制度の作り方も解説
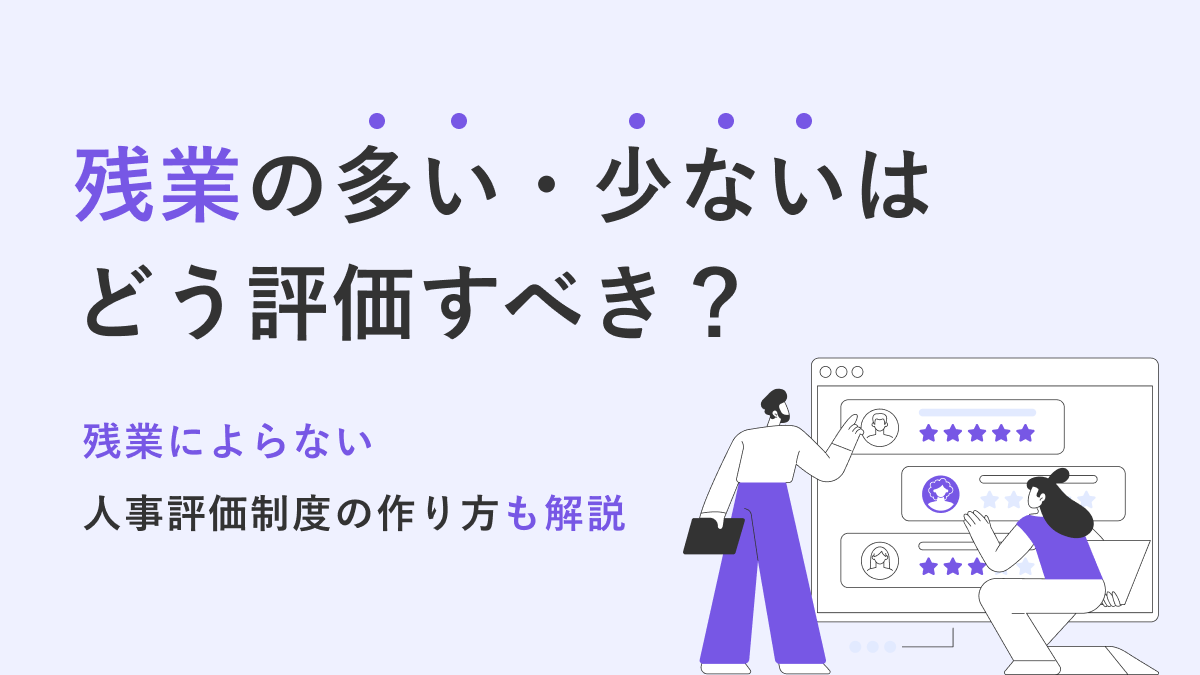
「残業が多い社員は頑張っている」「残業が少ない社員はやる気がない」という基準で人事評価を行っていませんか。残業時間を評価基準にするのは、本当に適切な評価方法なのでしょうか。
残業の多い・少ないを評価基準にすると、生産性の高い社員を正当に評価できず、ダラダラ残業を助長する危険性があります。
本記事では、残業時間と人事評価の関係性を見直し、真に公平な評価制度の作り方を解説していきます。

 目次[表示]
目次[表示]
残業時間の長さは人事評価でどう評価すべき?
残業時間そのものを評価基準に入れるのは適切とはいえません。労働時間の長さは、成果や貢献度を直接示すものではないからです。
人事評価で重視すべきは、残業時間ではなく成果と質です。
「何をどれだけの時間で達成したか」ではなく「何を達成したか」「それがどのくらいの価値を生んだか」を評価軸に置くことで、公平な評価制度に近づきます。
しかし現場では、「長い=高評価」「短い=低評価」という単純な見方は確かに存在するのが実状です。
日本は残業が多い人が評価される風潮がある
日本の企業文化では、長時間労働が美徳とされる傾向が長く続いてきました。
残業が多い社員は「頑張っている」「責任感が強い」と高く評価される一方、定時で帰る社員は「仕事に対する意欲が低い」とみなされることも少なくありません。
たとえば、毎日2時間残業しているAさんと、ほとんど残業せず業務をこなすBさんがいた場合、多くの上司はAさんを「頑張っている」と評価しがちです。
しかし実際には、Bさんのほうが効率的に仕事を進め、より高い成果を出している可能性もあります。
働き方改革が進む現在でも、残業の長さを評価する考えが残っている職場もあるのではないでしょうか。
残業の多い・少ないだけで評価はできない
単純に残業時間の長さだけで、社員を評価することは難しいです。
残業時間が長いからといって、必ずしも仕事の成果や貢献度が高いとは限らず、反対に短いからといって、結果がともなっているわけでもありません。
残業が多いから評価が高い、少ないから評価が低いとしてしまうと、生産性の高い社員が不当に低く評価され、時間をかけるほど有利になってしまいます。
長時間労働の常態化や生活残業の温床にもなりかねません。
もちろん難易度の高い案件や業務量の多さが理由で遅くまで残っているケースもあります。人事評価は、こうした背景や理由を踏まえて判断する必要があります。
▼従業員の評価基準に悩んでいるなら、エクセルで加工できる評価シートを活用してみてください。
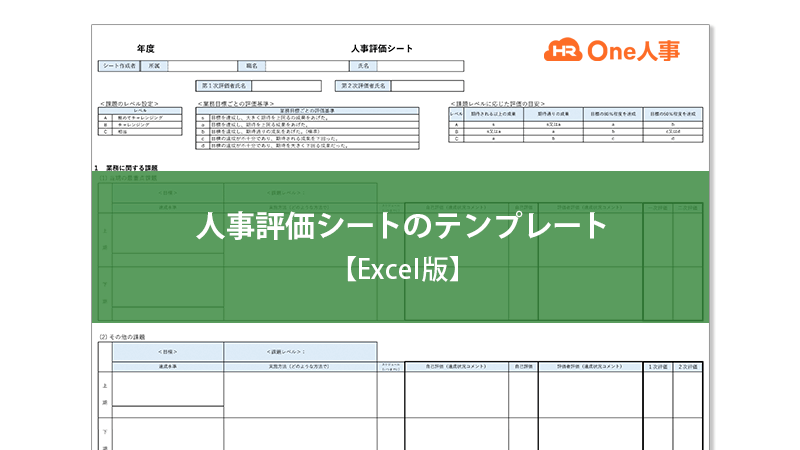
そもそもなぜ従業員は残業をするのか?
従業員が残業する理由は一つではありません。企業文化や人員体制、そして個人の事情が複雑に絡みあい、主に4つの理由が挙げられます。
- 業務量が多すぎて時間内で終わらないから
- 上司や同僚が残業をしていて帰りづらいから
- 残業代で生活費の足しにしたいから
- 残業が多いと評価される雰囲気を感じているから
まずは、背景を正しく把握することが大切です。原因を理解すれば、ムダな残業を減らし、働き方改革や生産性向上のきっかけになるため、一つずつ確認していきましょう。
業務量が多すぎて時間内で終わらないから
もっともよくある残業理由は、単純に業務量が多すぎることです。人員不足や業務の偏りにより、就業時間内に仕事を終わらせることが物理的に不可能な状況が生まれています。
一部の企業では「少数精鋭」と称して人員を最小限に抑え、そのしわ寄せで、1人あたりの業務負担が増加しています。業務の属人化が進み、特定の社員に難易度の高い仕事が集中することも少なくありません。
本来3人で担当すべき業務を2人で行っているケースや、部署内で成果を出しやすい人に案件が集中してしまうケースが該当します。
忙しすぎる職場環境では、どれだけ効率よく働いても定時内で業務を終えることは難しいでしょう。
上司や同僚が残業をしていて帰りづらいから
職場の雰囲気も残業を促す大きな要因です。上司や同僚が残業しているなか、自分だけ定時で帰ることに罪悪感を覚える社員は少なくありません。
日本の企業文化では「チームワーク」や「協調性」が重視される傾向があり、周囲と足並みを揃えることが暗黙の了解となっています。
上司が残っている状況で部下が先に帰ることは「仕事に対する熱意が足りない」と思われることすらあります。
効率よく業務を終わらせられる人にとって、このような空気は大きなストレスです。
残業代で生活費の足しにしたいから
経済的な理由であえて残業する、いわゆる「生活残業」も無視できない問題です。基本給だけでは生活が厳しく、残業代を含めた収入で家計を維持しているのです。
生活残業では、本来なら効率化できる業務をあえて時間をかけて行ったり、必要以上に細部にこだわったりすることで残業時間を確保しています。
業務とは関係のないネットサーフィンや雑談で時間を潰す「ダラダラ残業」に発展するケースもあります。
住宅ローンや教育費など固定費が重い場合、残業代が減ると生活設計がくずれるため、社内の残業削減施策にも抵抗を示すかもしれません。
生活残業は個人の問題というよりも、基本給の水準や評価制度の問題として捉える必要があります。
残業が多いと評価される雰囲気を感じているから
一部の日本企業では、残業の多さを「頑張り」や「責任感」のあらわれとして評価する風潮があります。認識が社員の間に浸透していると、昇進や評価を意識して、あえて残業を増やす人も出てくるものです。
残業時間が人事評価に影響する職場では、あえて仕事を非効率に進めるという、逆インセンティブが働きます。結果として生まれるのは、意図的な非効率や不要な長時間労働です。
もっとも最近では、「残業が多い=高評価」とは限りません。むしろ生産性が低いとみなされ、マイナス評価につながる企業もあります。
▼従業員の評価基準に悩んでいるなら、エクセルで加工できる評価シートを活用してみてください。
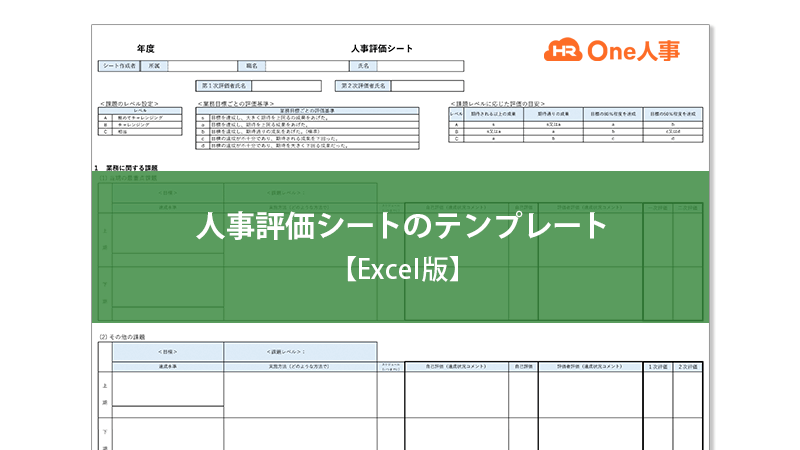
残業時間が長い人を高評価するリスク
一見すると、長時間残業している社員は「責任感が強く、頑張っている」ように見えるかもしれません。
しかし、残業時間の長さを評価基準にしてしまうことには、多くの問題が潜んでいます。
- 生産性や効率性を見落とす
- 無駄な残業を誘発する
- 長時間労働が常態化する
労働時間の多さは、必ずしも高い成果や価値を意味しません。むしろ、同じ成果を短時間で出せる人材こそ、組織にとって貴重な存在です。
残業時間を評価に組み込むと、「頑張っても意味がない」というあきらめが生まれてモチベーションが低下し、優秀な人材の離職につながるおそれがあります。
また「長く働くほど有利」というメッセージが社内に広がると、評価や昇進を狙って必要以上に残業する社員が増えます。ダラダラ残業や生活残業の温床になりかねません。
さらに長く働くことが評価される文化が根づくと、長期的に見て、組織の健全な発展を阻害します。従業員の健康リスクや法令違反といった問題も生じやすくなるためです。
たとえば、毎日2時間残業して納期をなんとか守っているAさんと、定時で業務を終え余裕を持って納品できるBさんがいたとします。多くの職場ではAさんが「頑張っている」とみなされがちですが、実際にはBさんのほうが効率的に働き、会社の経費削減や生産性向上に貢献しているかもしれません。

残業時間によらない人事評価制度をつくるポイント
残業時間を評価基準から切り離すことは、企業の生産性向上と従業員のワークライフバランスを両立させるために不可欠です。
「長く働く=頑張っている」という古い図式を捨て、成果や効率性を正しく評価する制度へ移行しましょう。
残業時間に依存しない、評価制度をつくる4つのポイントを紹介します。
- 業務効率を高める取り組みを評価する
- 労働時間とスキルや成果をセットで評価する
- 仕事の成果を重視することを周知する
- 業務内容や職種に応じて残業時間の目安を設ける
業務効率を高める取り組みを評価する
効率的に仕事を進める工夫や業務改善は、組織への大きな貢献の一つです。残業に依存しない評価制度に組み込むと、組織全体の生産性向上にもつながります。
たとえば、以下のような取り組みを評価項目に加えると、社員の行動が変わるでしょう。
- 業務プロセスの改善提案と実施
- 新しいツールやテクノロジーの導入による効率化
- ナレッジの共有や標準化による組織全体の効率向上
- 会議時間の短縮や資料作成の効率化
定性的な評価だけでなく、業務開始から完了までの時間や品質スコアといった指標も設定すると、評価の説得力が増します。
労働時間とスキルや成果をセットで評価する
労働時間だけでなく、スキルや成果を組みあわせて評価する「労働生産性」の視点が重要です。
労働生産性とは、投入した労働量に対してどれだけの成果が得られたかを示す指標です。評価の中心に据えることで、単なる労働時間の長さではなく、効率性や成果を重視した評価が可能になります。
▼労働生産性について詳しく知るには、以下の記事をご確認ください。
たとえば、同じ業務を行うAさんとBさんを労働生産性で比較してみます。
- Aさん:8時間で10件の処理を完了(生産性:1.25件/時間)
- Bさん:10時間で11件の処理を完了(生産性:1.1件/時間)
時間だけ見ればBさんが「頑張っている」ように見えますが、労働生産性はAさんのほうが高いとわかります。Aさんのほうが効率的に業務をこなしているのです。
労働生産性で評価する場合は、個人のスキルレベルや経験値も考慮しましょう。経験が浅い社員が効率化に取り組み、生産性を前月比20%向上させた場合、成長度合いを加点要素にすると納得感があります。
仕事の成果を重視することを周知する
残業時間ではなく仕事の成果を重視する評価方針を、組織全体に明確に周知することが重要です。制度を変えても、現場が理解していなければ意味がありません。
経営層からのメッセージや評価制度の説明会で、「残業の多さ=評価が高い」という誤った認識を払拭する必要があります。
具体的な周知方法としては、以下の3つが挙げられます。
- 評価基準や評価シートに「残業時間の多寡は評価に影響しない」と明記する
- 定期的な1on1ミーティングで成果ベースの評価について説明する
- 効率的に成果をあげて働く社員を社内で表彰し、ロールモデルとして紹介する
短時間で成果をあげた社員に報酬を与えると、意識は大きく変わり、限られた時間で結果を出す工夫を促進できるでしょう。
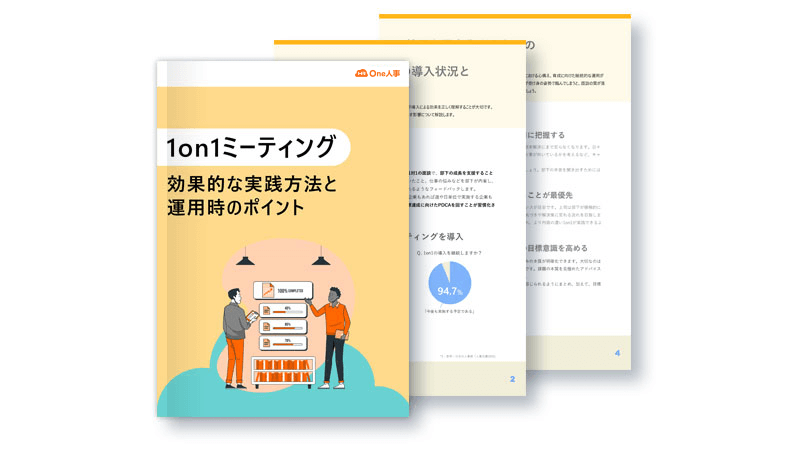
業務内容や職種に応じて残業時間の目安を設ける
すべての職種や部署に一律の基準を適用するのではなく、業務内容や職種の特性に応じた残業時間の目安を設定することも重要です。職種間の差を考慮せず、一律に残業の少なさを評価すると、不公平感が生まれます。
業務特性や繁閑期の違いにあわせ、残業時間の目安や評価の期待値を調整しましょう。
- 営業職は業界平均残業時間を参考にしつつ、成約率や売上貢献度を評価軸にする
- 繁忙期と閑散期で評価基準を切り替える
- プロジェクトの難易度や規模に応じて基準を変える
柔軟な基準設定が、納得感のある評価制度につながります。制度変更は時間がかかりますが、取り組みを始めると一人ひとりの行動と意識は変わり始めるでしょう。

従業員のダラダラ残業をなくす取り組み
残業時間の削減は、企業の生産性向上と従業員のワークライフバランス実現のために欠かせません。
目的のない残業は、企業にとっては人件費のムダ、社員にとっては時間と健康の損失です。
「評価のため」「生活費のため」といった理由で長く残る文化は、効率重視の働き方を阻害します。
「短時間で成果を出して評価されたい」と考える社員が、力を発揮できる環境をつくるため、企業ができる取り組みを4つ紹介します。
- ノー残業デーを設定する
- 残業を事前承認制とする
- 業務改善に取り組む
- 従業員の残業時間を正確に把握する
ノー残業デーを設定する
ノー残業デーは、特定の曜日や日を指定して、全社員が定時で退社することを推奨する制度です。残業削減の第一歩として多くの企業で導入されています。
ただし「今日は残業禁止」と言うだけでは形骸化しやすいものです。確実に定時で退社させるには、同時に次のような取り組みも実施する必要があります。
- ノー残業デー当日の会議設定を禁止する
- 定時30分前に退社アラートを流す
- 事前に業務を整理しておく時間を設ける
また全社一律ではなく、業務内容や進捗状況に応じて、部署やチームごとに独自のノー残業デーを設ける方法も効果的です。
残業を事前承認制とする
残業を行う前に、理由と必要時間を上長に申請し承認を得る取り組みです。承認プロセスを入れるだけで、残業の必要性を個人が考えるきっかけになるでしょう。
残業への手間を増やすことで、無駄な残業を抑制し、労働時間の適正管理が可能になります。
事前承認制のメリットは以下のとおりです。
- 管理者が部下の残業状況を事前に把握・管理できる
- 人件費や36協定の超過リスクを予測・回避できる
- タイムマネジメントの意識が向上する
- 不要な残業を抑制し、業務優先度の見直しが可能になる
申請時は、業務内容や期限を具体的に記載するようにすると、上司が判断しやすくなります。
業務改善に取り組む
残業を減らすには、個人の意識改革だけでなく、そもそも時間内で終えられる業務構造に変えることが不可欠です。
業務改善の具体的な方法としては、以下のようなアプローチがあります。
- ITツールやシステムの導入
- RPAによる定型業務の自動化
- コミュニケーションツールや情報共有ツールの活用
- 業務プロセスの見直しと業務標準化
- 役割分担の見直し・マニュアル化
- 会議時間の短縮
- ペーパーレス化の推進
- 仕事の多い部署への応援体制の構築
- アウトソーシングの活用
業務改善を成功させるためには、経営層のコミットメントと、従業員の積極的な参加が欠かせません。トップダウンとボトムアップの両方からのアプローチが重要です。
従業員の残業時間を正確に把握する
残業削減には、まず現状を正確に把握することから始めるのもポイントです。 一人ひとりの残業時間を正しく管理できれば、問題のある部署や業務の偏りを見つけやすくなり、適切な対策につなげられます。
残業時間の管理には、勤怠管理システムの活用をおすすめします。集計した残業時間を使って、部署ごとの傾向や個人別の残業推移を分析し、残業の発生原因を特定しましょう。原因が予想できれば、効果的な改善策を打ちやすくなります。
また多くの勤怠管理システムには、残業時間が一定の基準を超えた時にアラートを出す機能もあります。上限に近づいた社員に注意を促し、法令違反や過重労働を未然に防ぐことも可能です。
→使いやすい・分析もできるシステム「One人事」の特長はこちら

まとめ
残業時間の長さで従業員を評価する時代は終わりました。 大切なのは、労働時間ではなく成果や生産性を評価の基準にすることです。
ノー残業デーや事前承認制、業務改善、勤怠管理システムの活用で残業を減らし、効率よく働く社員を正しく評価できる環境をつくりましょう。
「長く働く」ではなく「成果を出す」を評価する文化こそ、企業と社員の双方を成長させるはずです。
適切な残業管理に|One人事[勤怠]
One人事[勤怠]は、残業時間の管理効率化にお役立ていただけるクラウド型の勤怠管理システムです。
One人事[給与]との連携により、実労働時間の集計から割増賃金の計算までをシームレスに運用できます。
One人事[勤怠]の初期費用や操作性については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門のスタッフが貴社の課題をていねいにお聞きしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、勤怠管理の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードしていただけます。勤怠管理をラクにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |
