有給休暇の付与タイミング(基準日)とは|月途中入社はいつ? 前倒しや統一の方法
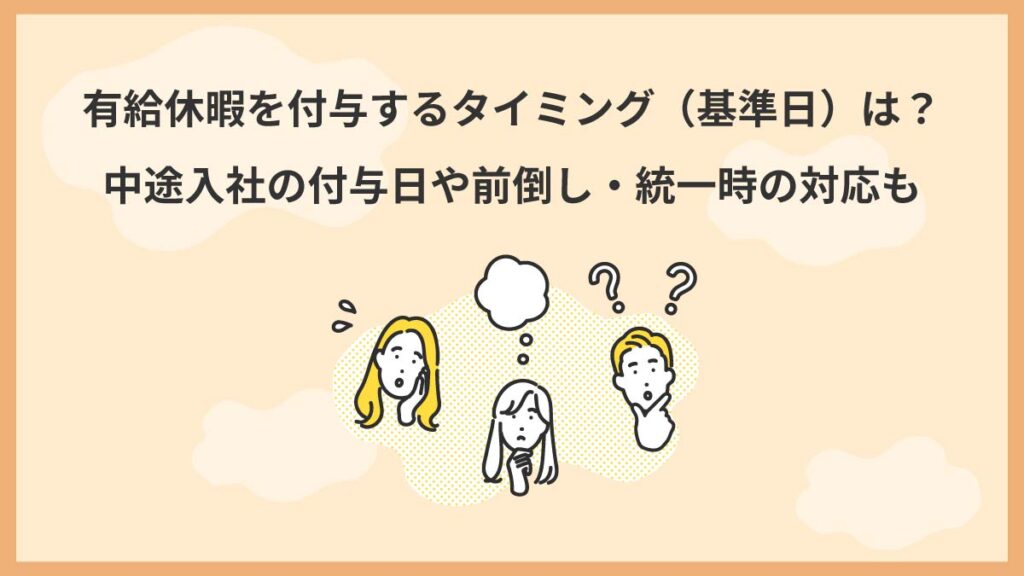
有給休暇は、従業員の権利であるとともに、雇用主にとっては義務です。しかし、いつどのように有給休暇を付与すればよいのか混乱してしまうこともあるでしょう。
とくに、月の途中に中途入社した従業員は、その付与タイミングや日数の計算は複雑になりがちです。企業によっては、前倒しや統一基準の運用の対応も必要でしょう。
そこで本記事では、有給休暇の付与タイミング(基準日)について解説し、中途入社の取り扱いと前倒しや統一時の対応方法を紹介します。
▼有休管理のコツを確認したい方は、以下の資料もぜひご活用ください。

 目次[表示]
目次[表示]
有給休暇を付与するタイミング(基準日)とは
従業員に有給休暇を付与するタイミングを「基準日」といいます。基準日の定め方は、最低限満たすべき条件が労働基準法に規定されています。まずは基本ルールを理解しましょう。
最初の付与日は雇い入れから半年後が基本
有給休暇の付与については労働基準法第39条で定められており、初めて付与される日は雇い入れから半年後が原則です。たとえば9月1日に入社した従業員は、6か月後の3月1日に付与されます。
ただし、この付与タイミングは最低基準であり、前倒しにして付与を早めることも可能です。
同様に中途入社で月の途中から勤務を開始する従業員の場合、原則のとおりにすると、ほかの従業員との違いにより管理が煩雑になるため、前倒しで付与して、全従業員で基準日を統一することも可能です。
自社の現行ルールは就業規則を確認する必要があるでしょう。
パート・アルバイトも付与するタイミングは同じ
正社員だけでなく、パートやアルバイトも有給休暇を取得できます。6か月以上連続して勤務し、かつ出勤率が80%以上の従業員は、週や年間の所定労働日数に比例して年次有給休暇が付与されます。
週所定労働時間が30時間未満かつ週の所定労働日数が4日以下の人、あるいは年間所定労働日数が216日以下の人が対象です。

有給休暇の付与条件と日数
有給休暇の付与条件と付与日数は、労働基準法39条によって定められています。
付与される条件
有給休暇が付与される条件として、下記の2つを満たしている必要があります。
- 雇い入れ日から継続して6か月以上勤務していること
- 全労働日の8割以上出勤していること
付与日数
有給休暇の付与日数は、雇い入れの日から勤続6か月後の基準日に10日、その後、年数に応じて増えていきます。
| 勤続年数 | 付与日数 |
|---|---|
| 0.5年 | 10日 |
| 1.5年 | 11日 |
| 2.5年 | 12日 |
| 3.5年 | 14日 |
| 4.5年 | 16日 |
| 5.5年 | 18日 |
| 6.5年〜 | 20日 |
フルタイム
週5日、フルタイムで勤務している従業員は、上記と同様の条件で付与されます。週5日勤務なら、週の労働時間が30時間未満であっても同じ日数です。
パートタイム・アルバイト
パートタイム・アルバイト従業員は、所定労働日数と継続勤務年数に応じて付与される有給休暇日数が異なります。
ただし、週4日以下の所定労働日数であっても、1週間の所定労働時間が30時間以上となる場合にはフルタイムと同様の日数が付与されます。
| 所定労働日数 | 勤務年数と付与日数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1週間 | 1年間 | 0.5年 | 1.5年 | 2.5年 | 3.5年 | 4.5年 | 5.5年 | 6.5年~ |
| 4日 | 169〜 216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 121〜 168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 73〜 120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 48〜 72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
参照:『次年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています 』厚生労働省(【リーフレットシリーズ労基法39条】)
参照:『年次有給休暇とはどのような制度ですか。パートタイム労働者でも有給があると聞きましたが、本当ですか。』厚生労働省
有給休暇を付与するタイミングは前倒しもできる
有給休暇を付与するタイミング(基準日)は、労働者の不利益にならないのであれば、前倒しができます。たとえば6月1日入社の場合、半年後の12月1日が基準日となり、毎年12月1日に新しく有給が付与されます。ほかの従業員にそろえるために、次回の付与を10月1日にすることも可能なのです。
どのようなケースが考えられるかをご紹介します。
ケース1.入社日に付与する前倒しの場合
入社日に10日の有給休暇を付与する場合、基準日は入社当日です。たとえば9月1日が入社日なら、基準日は9月1日で、次回は1年後の9月1日に11日付与されます。
ケース2.分割で一部日数を前倒しする場合
有給休暇の最初の付与日数10日を分割して、入社日と半年後に分け、それぞれの日に付与することもできます。これを「分割付与」といいます。たとえば入社日を4月1日とする場合、入社当日に5日、6か月後の10月1日に5日を付与します。
有給休暇を付与するタイミングの前倒しに関する注意点
有給休暇を付与するタイミングは前倒しできますが、運用には注意が必要です。主な注意点を3つ紹介します。
合計付与日数が10日に達すると取得義務が発生する
有給休暇の基準日を前倒しし、有給休暇の合計付与日数が10日に達すると年5日の取得義務が発生します。そのため、基準日から1年以内に付与日数のうち5日分、基本的に時季を指定して取得させなければなりません。
前倒しで付与した従業員が退職しても有休は返納されない
前倒しで付与した従業員が途中で退職したとき、有給休暇はどのような扱いになるのでしょうか。
たとえば4月1日に有休を10日付与し、8月30日に辞めた場合を考えます。この場合、有給休暇の付与条件である「雇い入れから6か月の勤続」「全労働日の8割以上の出勤」を満たしていなくても付与が認められます。
つまり、有給休暇を付与した段階で、要件が有効となり、企業は有休の返納などを請求できません。
タイミングをあとから変更した場合は付与日数に注意
有給休暇の付与タイミングをあとから変更する場合、短縮された期間分は、すべて出勤したとして次の付与を前倒しする必要があります。
たとえば、4月1日に入社した従業員の最初の付与タイミングは法律上10月1日で、2回目はその翌年の10月1日です。しかし、全従業員で統一するために2回目を翌年の4月1日に前倒すと、その時点で2回目の付与日数が発生します。
有給休暇の付与日数が前倒しした時点で変わる可能性があるため、タイミングを変更するときは注意しなくてはなりません。
有給休暇を付与するタイミングは統一してもよい
人事管理の効率化のため、有給休暇を付与するタイミングは全体で統一できます。これを「年次有給休暇の斉一的取扱い」といい、厚生労働省からの通達内容に含まれています。
ただし、斉一的取扱いによって労働者が不利になる場合は違法とみなされるため、注意が必要です。
有給休暇を付与するタイミングの統一に関する注意点
有給休暇を付与するタイミングを統一する場合は、次の3つの点に注意しましょう。
就業規則に明記
有給休暇を付与するタイミングについては、必ず労使間で合意をし、そのうえで就業規則に明記、あるいは変更を行います。加えて、所轄の労働基準監督署長への届け出も必要です。
社内周知
有給休暇の付与についての規則は、社内に周知することも大切です。従業員からの問い合わせに明確に回答するのはもちろん、申請の対応もスムーズに行えるようにしておきましょう。
有給休暇の管理体制の見直し
計算ミスや付与日数のミスを起こさぬように、また管理工数の煩雑さに備えておくことが重要です。場合によっては、有給休暇の管理体制を見直す必要があります。
有給休暇の付与日数・タイミングに関するポイント
有給休暇の付与日数やタイミングに関する3つのポイントを紹介します。
タイミングを統一するなら前倒しに
有給休暇付与のタイミングを統一するなら、前倒しにしなくてはなりません。あくまでも従業員にとって不利益とならないようにすることが重要です。
繰越と期限に注意
繰越と期限にも注意が必要です。労働基準法第115条により、年次有給休暇の権利は、付与されてから2年間有効です。つまり、有給休暇を使わなければ、付与日から2年後にはその権利は失われます。
もし前年度に使い切れなかった有給休暇があれば、1年間だけ繰り越すことができます。
出勤率が8割に達しない年も勤続年数に換算
有給休暇の付与には、出勤率が8割以上が必要です。8割に達しない場合、その年は有給休暇がもらえませんが、勤続年数にはカウントされます。
たとえば、勤続年数が1. 5年であれば通常11日の有給休暇が付与されますが、もし出勤率が8割に達していなければ、その年は付与されません。
ただし、前年において条件を満たしていなくても勤続年数2. 5年となった時点で条件を満たしていれば、11日(勤続年数1. 5年)ではなく12日(勤続年数2. 5年)が付与されます。あくまで勤続年数に応じて付与されることに注意してください。
まとめ
有給休暇の最初の付与日は、雇い入れから半年後が基本です。正社員だけでなく、パートやアルバイトも付与するタイミングは同じですが、要件によって付与日数などが細かく異なるため、把握しておく必要があります。
また、有給休暇を付与するタイミングは前倒しが可能です。合計付与日数が10日に達すると取得義務が発生するため、従業員の不利益にならないような設定を行うことが重要です。
有給休暇を付与するタイミングは統一できますが、その際は就業規則に明記したり、社内周知を行ったりすることが重要です。管理が煩雑になりがちなので、効率化のため、場合によっては有給休暇の管理体制を見直しましょう。
有給休暇の管理に|One人事[勤怠]
One人事[勤怠]は、有休管理を自動化する勤怠管理システムです。簡単な設定により、有給休暇の付与日や取得日数、残日数などを自動で計算でき、従業員へのリマインド機能もあるため、担当者の負担を軽減します。
有休管理を怠ると、罰金・罰則の適用の恐れや信用低下につながります。有給休暇の取得率が低い企業さまは、ぜひご検討してみてはいかがでしょうか。
One人事[勤怠]の初期費用や気になる使い心地については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門のスタッフが貴社の課題をていねいにヒアリングしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、勤怠管理の効率化のヒントが詰まったお役立ち資料を無料でダウンロードしていただけます。勤怠管理をラクにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |
