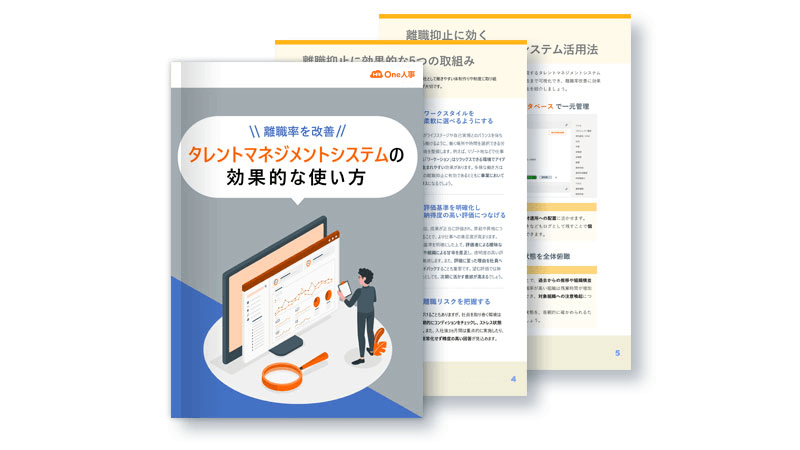労働時間の短縮は必要? メリット・デメリットと国内外の事例、助成金、課題への対策
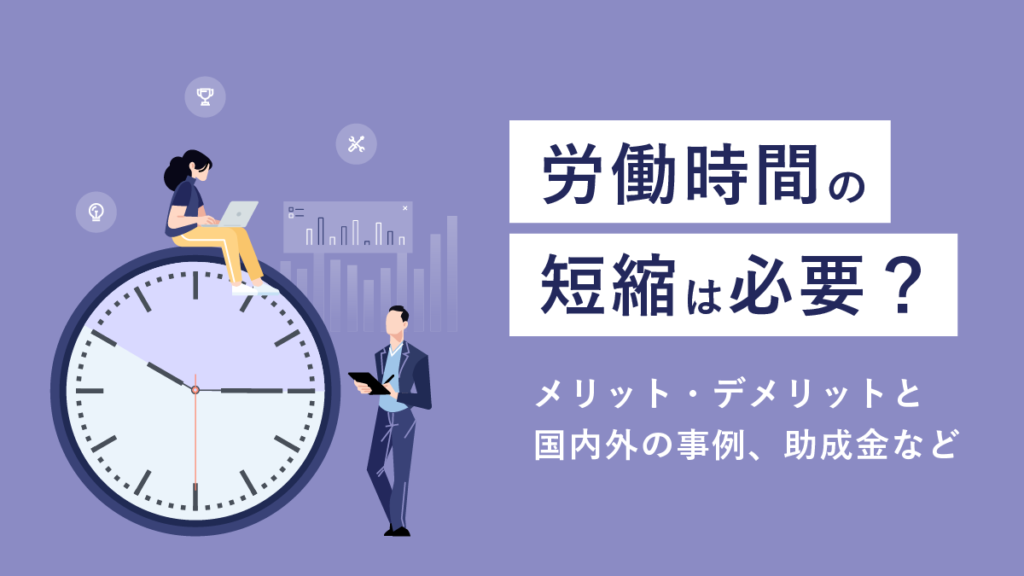
労働時間の短縮は、単に勤務時間を減らすだけでなく、生産性向上やワークライフバランスの改善、企業の競争力を高める重要な施策です。働き方改革やリモートワークの普及により、労働時間を見直す流れが加速しています。
しかし、労働時間の短縮を実現しようとすると、「生産性が落ちるのではないか」「コストが増えるのでは」といった不安を感じる企業も多いのではないでしょうか。
本記事では、労働時間を短縮するメリット・デメリットに加え、具体的な国内外の成功事例や利用可能な助成金制度を紹介しています。また、労働時間の短縮にともなう課題への対応策も解説しているので、自社の働き方を見直す際のヒントとしてお役立てください。
労働時間の見直す前に現状の勤怠実績を可視化することも必要です。
→従業員一人ひとりの働き方を可視化するOne人事[勤怠]の特長はこちら

 目次[表示]
目次[表示]
労働時間の短縮とは
労働時間の短縮とは、法定労働時間(1日8時間、週40時間)を踏まえ、企業が自主的に定める勤務時間を短縮する施策です。たとえば、所定労働時間を一律で「8時~17時」から「8時~16時」に変更するといった改革を指します。7時間労働や6時間労働が採用されている事例もあります。
ただし、ただ拘束時間を短くするだけでは不十分です。企業は、従業員一人ひとりが効率的に働ける環境を整え、無駄を省いて生産性を高めるまで、全社的に支援しなければなりません。
労働時間を短縮することで、個人が余裕をもって働けてワークライフバランスが改善されるため、心身の健康が守られます。また、競争力を強化して優秀な人材の確保にもつながるため、日本企業が取り組みたい課題の一つです。
労働時間を短縮する取り組みの例
労働時間の短縮は、所定労働時間の改定にとどまりません。代表的な3つの取り組みの例は以下のとおりです。
| 取り組みの例 | |
|---|---|
| 残業時間の削減 | 残業時間を制限。従業員が長時間労働をしなくても業務を遂行できる体制の整備 |
| フレックスタイム制の導入 | 労働時間の一定の枠内で、従業員が自分のスケジュールに合わせて働ける制度 |
| ノー残業デーの導入 | 特定の曜日や時間帯に残業を禁止。強制的に定時退社を促す制度 |
以上の取り組みを実施すると、従業員はリフレッシュできるので、業務効率の向上が期待できます。プライベートの予定や家族と過ごす時間を確保できるでしょう。
しかし、残業時間を制限したり、ノー残業デーを設けたりしても、こっそり仕事を持ち帰る人がいてもおかしくありません。労働時間を制限する場合は同時に、効率化を支援することが重要です。

なぜ労働時間は8時間が標準?
フルタイム正社員の労働時間を8時間とする企業は多いでしょう。しかし、なぜ「8時間」が一般的になったのでしょうか。
じつは、労働時間が1日8時間と定められている背景には、19世紀の産業革命時代における長時間労働に対する反発が関係しています。
19世紀のイギリスでは当時、労働者が1日12~16時間の長時間労働を強いられていました。過酷な労働環境に徐々に反発が広がるなか、社会活動家ロバート・オーウェン氏が、とある理念を提唱し注目を集めます。「8時間労働、8時間休息、8時間自由時間」という考えが世界中に広まり、1日8時間の労働時間が一般化したのです。
日本でも、1919年に川崎造船所が国内で初めて1日8時間労働を導入しました。そして1947年に施行された労働基準法によって法定化されています。
しかし現代では、1日8時間の労働時間が必ずしも効率的であるとは限りません。とくに先進国では、1日6時間など労働時間短縮を目指す取り組みが進んでいます。
労働時間の短縮が進められる背景
労働時間の短縮が推進される背景には、社会的課題や労働環境の見直しが強く関連しています。以下の3つのポイントから、なぜ労働時間の短縮が必要なのか、由を具体的に解説します。
- 政府による推進
- 人手不足の解消
- 労働時間が長い文化の是正
背景を知ることで、企業として取り組むべき課題が明確になり、労働環境の改善に向けた具体的な施策を検討するのに役立つでしょう。
政府による推進
日本政府は、少子高齢化による労働力不足に対応するため、労働時間の短縮を積極的に推進しています。とくに2019年に施行された「改正労働基準法」では、時間外労働の上限規制や勤務間インターバル制度の導入など、長時間労働を是正するための施策が打ち出されました。企業には労働時間を適正に管理し、従業員の健康を守ることが求められています。
人手不足の解消
日本では生産年齢人口の減少が進み、多くの企業で人材確保が困難な状況です。人手不足の解決策として、労働時間の短縮が注目されています。
とくに、育児や介護で働く意欲があるものの、フルタイム勤務が難しい人材を取り込むために、短時間勤務という選択肢を増やす手段が取られています。
労働時間が長い文化の是正
日本の企業には、「長時間働くことが美徳」という文化が根強く残っています。しかし、実際には、長時間労働が疲労やストレスを招き、生産性を低下させる原因となっています。
労働時間を短縮し、効率的な働き方を実現することは、悪しき慣習を見直すきっかけとなるでしょう。

労働時間を短縮するメリット・効果
労働時間の短縮は、従業員や企業にとってさまざまなメリットや効果をもたらします。以下では、ワークライフバランスの実現、定着率の向上、企業イメージの向上といった3つの効果を中心に解説します。
以上のメリットを知ることで、労働時間短縮の取り組み、経営や従業員満足度に与える影響を具体的に確認していきましょう。
ワークライフバランスの実現
労働時間の短縮は、従業員が私生活を充実させるための時間を確保する助けとなります。
たとえば、1日の労働時間が「8時~18時」から「8時~17時」に短縮されると、1時間を家族・友人との食事やスキルアップ、趣味や休養に充てることが可能です。
プライベートな時間が増えることで、従業員は心身の健康を維持しやすくなり、ストレスも軽減されるでしょう。
環境が整えば、従業員のモチベーションが向上し、業務に対する集中力が高まります。労働時間の短縮で、「生産性が下がるのでは?」と感じられるかもしれませんが、むしろ結果的に企業全体の生産性向上が期待できるのです。
定着率の向上
とくに育児や介護を担う従業員にとって、フルタイム勤務は大きな負担となることがあります。労働時間の短縮により、従業員が仕事と家庭のバランスを保ちやすくなり、企業への定着率が向上する可能性があります。
従業員一人ひとりのライフステージに配慮して、柔軟な働き方を提供することは人材定着において重要です。定着率が向上して離職率が低下すれば、新たな採用・教育コストを抑えられ、長期的に人材を育てられるため、競争力の向上も期待できるでしょう。
企業イメージの向上
労働時間を短縮する取り組みは、従業員に配慮する企業としてアピール材料となります。とくに現在の労働市場では、福利厚生や柔軟な働き方を求める求職者が増えています。「労働者に優しい企業イメージ」により、優秀な人材を集めやすくなるでしょう。
また、働き方改革の実現は、取引先や顧客からの信頼を高める要因にもなります。従業員の健康や働きやすさを重視する姿勢が、社会的責任を果たす企業として評価され、ビジネスチャンスの拡大にもつながるかもしれません。
労働時間を短縮すると受けられる助成金
労働時間を短縮するにも「賃金コストが心配」「人件費の負担が重くなるのでは?」と悩みを抱える企業の担当者は少なくありません。そこで活用したいのが、国や自治体が提供する助成金制度です。
厚生労働省が提供する「働き方改革推進支援助成金」は、労働時間短縮や年次有給休暇の促進を目的とする中小企業向けの支援制度です。
本制度では従業員の就労環境を整え、働きやすさを改善する取り組みを実施する企業に対して、達成した成果目標や賃金引上げに応じ、最大730万円が支給されます。
対象となる取り組みには、時間外労働の削減や年次有給休暇の計画的付与、特別休暇の導入などが含まれます。
| 助成額 | 最大730万円(コースや取り組み内容によって変動) |
| 条件 | ・労働時間削減目標を設定 ・達成に向けた計画を策定して達成 |
| 申請手続き | ・36協定の届出 ・専用フォーマットでの申請書提出 |
参照:『働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)』厚生労働省
助成金制度の活用により、導入にかかるコストを抑えられます。取り組みの実現可能性を高め、企業の負担を軽減できるでしょう。
ただし制度は毎年度見直される可能性があるため、最新の情報を確認することが重要です。厚生労働省の公式ウェブサイトを通じて、最新の条件や申請手続きを随時チェックしてください。また、申請には提出期限があるため、早めの手配を心がけましょう。
労働時間の短縮を実現した国内・海外事例
実際に労働時間を短縮し、成功を収めた国内外の企業事例は、今後の取り組みの参考となります。以下では具体的な事例を紹介します。
味の素株式会社の事例
味の素株式会社は、2017年に所定労働時間を1日あたり20分短縮しつつも、基本給を維持しながら1日7時間15分の労働時間を実現する制度を導入しました。同社の取り組みには、「働き方計画表」を利用した労働時間の見える化や、最終退館時刻を24時から20時に早めるなどの施策が含まれ、従業員の効率的な働き方を促進しています。
同社は、単に労働時間を短縮するだけでなく、従業員一人ひとりの働き方に対する意識改革を重視し、全社的な効率化をはかることで、生産性を維持しています。企業全体の競争力も強化されており、参考になる労働時間短縮の事例の一つです。
参考:『味の素株式会社』働き方・休み方改善ポータルサイト
参考:『テレワークをいち早く実施!味の素グループの働き方改革』味の素株式会社
参考:『味の素流「働き方改革」と「健康経営」』味の素株式会社人事部
株式会社友和物流の事例
株式会社友和物流(千葉県浦安市)は、運輸業界の「2024年問題」に対応するため、労働時間の短縮に向けて多様な取り組みを行っています。
具体的には、まず荷待ち時間を是正するために実際の待機時間をデータ化し、荷主と共有することで無駄削減に成功しました。
ほかにも、最新のデジタルツールで労働時間や休憩時間を正確に管理する体制を整えています。
取り組みを通じて、労働時間短縮と業務効率化を同時に実現し、従業員の意識改革にも成功しています。同社の事例は、同業種にとって参考となる労働時間短縮の成功モデルといえるでしょう。
参照:『最新デジタル機器等による働き方の見える化でさらなる業務効率化を目指す』厚生労働省
スウェーデンの事例
スウェーデンでは、2015年にヨーテボリ市の養護老人ホームで試験的に1日6時間労働が導入されました。試験期間中、従業員の欠勤率が大幅に減少し、健康状態や生産性の改善が報告されています。とくに、看護師のストレスが軽減されたことで、患者へのケアの質が向上し、労働者と入居者の両方に良好な影響が見られました。
ただし、労働時間の短縮にともなう追加人員の雇用が必要となったため、財政的な負担が増加したという課題も浮上しています。税金による社会福祉が充実しているスウェーデンは、短時間労働の普及に対して慎重な姿勢を示していますが、試験的な導入は続けられています。
アメリカの事例
アメリカのサンディエゴに拠点を置く小規模企業「Tower Paddle Boards」は、1日5時間労働を導入しながら、売り上げを大幅に伸ばしています。
同社では、9時から13時の短い時間に集中して仕事をすることで、従業員の仕事に対する意欲が高まり、生産性が向上しました。労働時間の短縮で従業員の幸福度も高まり、プライベートと仕事の両立が実現されています。
同社の取り組みから、従業員が幸福を感じ、集中して働くことで、短時間でも十分な成果を出せるという見解が示されています。
幸福感と生産性向上が相関関係にあるという考えは、多くの企業にとって新たな働き方改革の指針となるでしょう。
労働時間を短縮するデメリット・課題
労働時間を短縮しても業績を上げられた企業がある一方で、実現にはいくつかの課題もあります。
「業務量を調整できるか」「今までどおり円滑に社内コミュニケーションができるか」と懸念する企業も少なくありません。従業員のなかには賃金への影響を心配する人もいるでしょう。
ここでは労働時間を短縮する施策を実施した際に、企業や従業員が直面しやすい具体的な課題・デメリットを取り上げ、解決策についても解説します。
課題を事前に理解し対策を講じることで、スムーズに労働時間短縮に取り組めるでしょう。
個人の給与が減る可能性がある
労働時間の短縮にともない、とくに残業代をあてにしている従業員にとっては、総収入が減るリスクがあります。たとえば、月に30時間の残業をしていた従業員が、残業時間削減により月収が数万円減少する場合、生活への影響は避けられません。
味の素株式会社のように基本給を維持できればよいですが、必ずしも資金力がある企業ばかりではないでしょう。
給与の減少は従業員のモチベーション低下を招きます。企業は給与体系の見直しや助成金の活用など、収入を維持できる仕組みを検討する必要があります。

今までの納期を守れなく可能性がある
労働時間を短縮しても、業務量が減らなければ、従来の納期を守るのが難しくなります。たとえば、1日8時間働いて対応していた業務を7時間で行う場合、業務効率が向上しない限り、遅延が発生するでしょう。
解決策として、業務プロセスの見直しや優先順位の明確化が必要です。具体的には、各業務において効率化ツールを導入する方法があります。
とくに人事領域では、定型化している書類業務や公的手続きは、専用システムの活用により効率化するのがおすすめです。社内で分散する人材情報を集約することで、労務や勤怠・給与、評価業務を体系的に運用するのが理想でしょう。
人事労務をワンストップで支えるサービスとして、人事労務管理システム「One人事」があります。
「One人事」は人事労務の一元化を実現し、担当者が「本来やるべき業務」に集中できるように支援しております。詳しくは当サイトよりお気軽にお問い合わせください。
→人事領域で30年の実績「One人事」サービス資料はこちら
コミュニケーションの行き違いが生じる
労働時間を短縮すると、勤務時間のズレによって社員間のコミュニケーションが不足するリスクがあります。とくにチームで動く業務では、行き違いが発生し、非効率やミスにつながるため工夫が必要です。
タスク管理・共有ツールやチャットツールを活用し、タイムリーな情報共有を促進する取り組みを検討しましょう。
時短ハラスメント・残業させないハラスメントが発生する
労働時間短縮の取り組みが進むなかで、一切の残業を無理に禁止すると、かえって従業員に過剰な負担をかけてしまいます。「時短ハラスメント」「残業させないハラスメント」と呼ばれる問題につながりかねません。
たとえば、残業を禁止した結果、従業員が業務を終わらせるために自宅へ仕事を持ち帰ったり、サービス残業を余儀なくされたりすることがあります。事態を防ぐためには、適材適所の人材配置により、業務量の調整や人員の追加など、企業としてのサポートが重要です。
「時短勤務」について詳しく知るには次の記事もご確認ください。
隠れ・持ち帰り・サービス残業が発生する
労働時間を短縮しても、業務量が変わらない場合、従業員が隠れ残業や持ち帰りの仕事を余儀なくされることがあります。これにより、表面的には労働時間が短縮されていても、実際の負担は変わらず、従業員の健康に悪影響をおよぼします。
業務量の適正化のほかに、労働時間の管理方法の見直しも必要となるでしょう。
「サービス残業」を放置するリスクについて詳しく知るには次の記事もご確認ください。
労働時間の短縮による課題への対策
労働時間を短縮する取り組みには、収入の変動や納期、業務効率や社内コミュニケーションの維持に関する不安がともないます。
課題を解決しないまま取り組みを進めると、労働環境がかえって悪化したりするリスクも否定できません。
一方で、適切な対策を講じれば、課題を克服しながら労働時間を短縮するメリットを最大限に得られるでしょう。
ここでは課題を具体的に解消するための対策を解説します。
労働時間の短縮を成功させる実践的な方法が分かり、自社の取り組みに役立てられるでしょう。
業務の可視化・見直し
労働時間短縮の第一歩は、従業員一人ひとりの業務を可視化することです。たとえば、1日のタスクを記録し、どの業務にどれだけの時間を費やしているかを明確にすることで、無駄や効率の悪さを特定します。
具体的には、以下のような方法です。
| タスクの優先順位づけ | 重要度と緊急度を基準にタスクを整理する |
| ボトルネックの特定 | 進捗が遅れている業務やリソース不足の箇所を見つけ、改善策を実施する |
従業員が効率的に働ける環境を整え、限られた労働時間内での生産性を向上できるようにしましょう。
外注・アウトソーシング
社内リソースだけで業務を抱えると、従業員の負担が増え、労働時間短縮の実現が難しくなります。一部の業務を外部に委託することで、従業員の負担を軽減し、コア業務に集中できる環境を構築しましょう。
専門性の高い業務はアウトソーシングにより、内部リソースを重要な業務に集中させることが可能です。
効率化ツール・システムの導入
デジタルツールを活用した効率化は、労働時間短縮を実現するうえで欠かせません。たとえば、以下のようなツールやシステムの導入が考えられます。
| 勤怠管理システム | 労働時間を正確に記録し、データをもとに改善策を実施する |
| プロジェクト管理ツール | タスクの進捗状況を可視化し、チーム間の連携をスムーズにする |
ITツールは、作業効率を高めるだけでなく、従業員の負担軽減やミスの削減も期待できます。
労働時間管理の徹底
労働時間短縮を成功させるためには、正確な労働時間の管理が必要です。従業員が過剰な残業をしないよう、労働時間を可視化し、必要に応じて調整しましょう。管理の徹底には勤怠管理のシステム化が便利です。
勤怠管理システムの活用により、従業員ごとの勤務状況を把握し、過労が発生しないよう管理するとよいでしょう。基準に達した従業員に個別にアラートを出すことも可能です。
労働時間の管理効率化におすすめなのが、クラウド勤怠管理システムOne人事[勤怠]です。企業独自の勤務ルールに合わせた柔軟な設定が可能で、自社に適した管理と運用が実現します。One人事[勤怠]で実現できることなど詳しくは、当サイトよりお気軽にお問い合わせください。
→人事領域で30年の実績「One人事」サービス資料はこちら
労働時間管理の徹底により、労働時間の短縮にともなう課題だけでなく、従業員が無理なく働ける環境を整えられるため、健康被害を未然に防ぐこともできるでしょう。

労働時間を短縮しつつ、生産性を高めるには?(まとめ)
労働時間の短縮といった働き方改革と生産性向上の両立には、全社的な取り組みが必要です。業務の無駄を排除して効率化を進めるとともに、従業員の意識をあらため、チーム内のコミュニケーションを強化しましょう。
本記事で紹介した取り組みや助成金制度、勤怠管理システムの活用を参考にして、課題を解決しながら労働時間短縮が実現できます。
適切な対策を講じることで、従業員のモチベーションを維持しつつ、生産性も向上させることが可能です。労働時間短縮の取り組みが、企業の成長と従業員の満足度向上につながるように取り組んでいきましょう。
労働時間の見える化で残業削減へ|One人事[勤怠]
One人事[勤怠]は、煩雑な勤怠管理をシンプルにする勤怠管理システムです。労働時間の管理・運用の効率化により、勤怠管理に課題がある企業をご支援しております。
One人事[給与]と連携すれば、給与計算に自動で紐づけられるため、より速くより正確に業務を進められるでしょう。One人事[勤怠]の初期費用や気になる操作性については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門のスタッフが貴社の課題をていねいにヒアリングしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、勤怠管理の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。勤怠管理をラクにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |