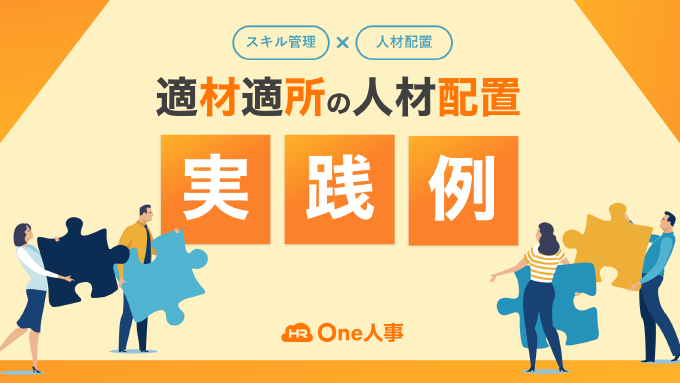シニア人材の活用推進【事例あり】メリットと課題、人手不足解消のポイントとは
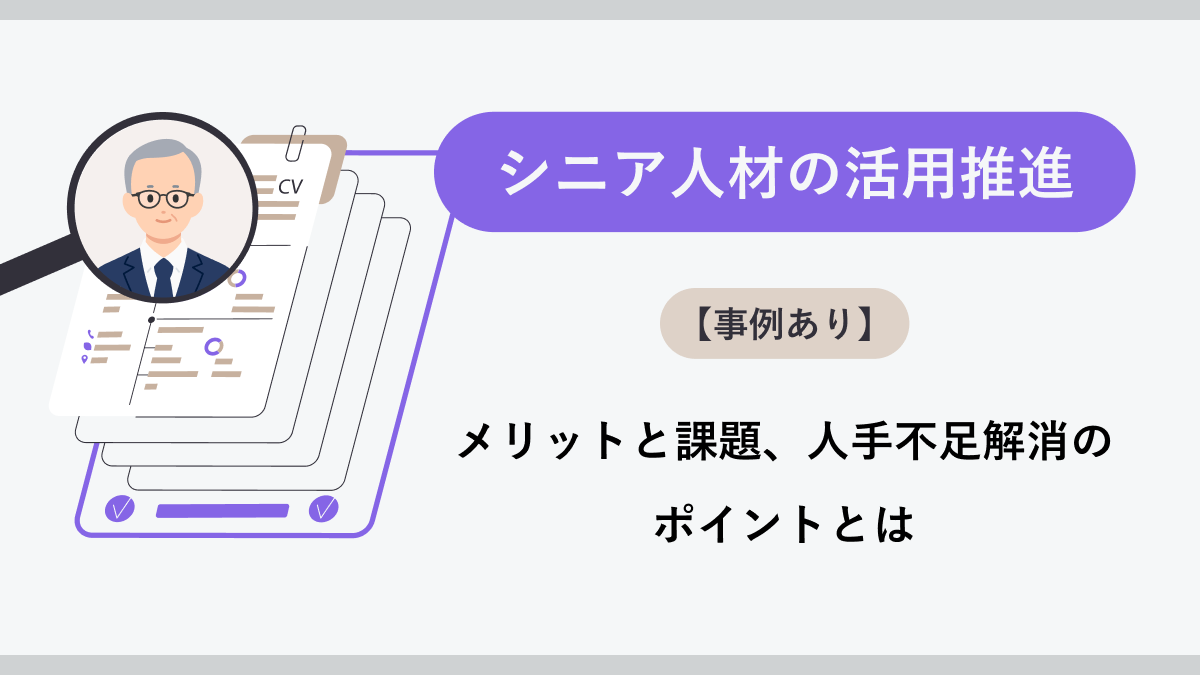
人手不足に悩む企業は、今やめずらしくありません。とくに現場を預かる人事マネージャーは、採用が思うように進まず、即戦力の確保に頭を抱えているのではないでしょうか。
そんななか、注目されている「シニア活用」は、人手不足対策にとどまらず、組織の競争力を高める戦略として、多くの企業が取り入れ始めています。
しかし「シニア人材は戦力になるのか」「若手との摩擦やモチベーション低下は起きないか」と、不安を感じている方も少なくないでしょう。
本記事では、シニア人材活用のメリットと課題、現場で役立つ成功事例、適材適所を実現するタレントマネジメントのポイントまで解説します。
→シニアも若手も適材適所の人材配置を実現するなら「One人事」の資料を無料ダウンロード
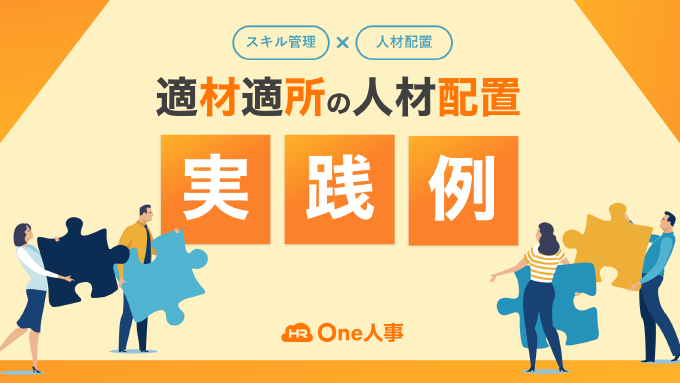
 目次[表示]
目次[表示]
シニア人材の活用が推進される背景
日本社会では、シニア人材の活用が急速に推進されています。背景には、いくつかの大きな変化があります。ここでは、とくに影響の大きい3つの背景を整理しておきましょう。
- 定年の引き上げ
- 働く意欲があるシニア人材の増加
- 少子高齢化、生産年齢人口の減少
定年の引き上げ
シニア人材の活用を支える制度の変化として、定年年齢の引き上げが加速しています。2021年の高年齢者雇用安定法改正により、70歳までの就業機会確保が企業の努力義務となりました。
定年の引き上げや定年制の廃止、継続雇用制度の導入など、企業にはシニア層の雇用を維持しながら、多様な働き方への対応が求められています。
今後も65歳以降のシニア人材が働ける雇用環境の整備や、高年齢雇用継続給付の縮小への対応も必要です。
働く意欲があるシニア人材の増加
シニア人材活用を支えるもう一つの要因として、働く意欲を持つシニア層の増加が挙げられます。「定年後も働き続けたい」「これまでの知識や経験を活かしたい」と考える方が年々増えています。
年金受給開始年齢の引き上げや、生涯現役志向の広がりも、この動きを後押ししています。企業も、安定した業務遂行や若手への指導など、シニア人材ならではの強みを期待して、積極的な採用に取り組むケースが増えました。
少子高齢化、生産年齢人口の減少
シニア人材の活用が避けられない背景として、少子高齢化の進行と生産年齢人口の急減があります。 日本は世界でも例を見ないスピードで高齢化が進んでおり、若手の採用だけでは人手不足を補えない状況です。
産業活動を維持し、経済成長を持続させるためには、シニア人材を戦略的に配置し、モチベーションを高める評価制度や育成支援が必要です。
政府や企業も、労働課題に対応するため、就業環境の整備や制度変更に力を入れています。
シニア人材は何歳から何歳までを指す?
シニア人材とは、企業や業界によって定義に幅がありますが、一般的には55歳以上、あるいは60歳以上の従業員を指すことが多いです。雇用の現場では、55歳を境にシニア人材とみなすケースが増えています。
たとえば高齢者雇用安定法では、55歳以上を「高年齢労働者」と定義し、雇用安定措置の対象としています。同様に、求人サイトや転職エージェントでは、54歳までを「ミドル」、55歳以上を「シニア」とする表現が一般的です。
シニア人材の年齢定義は一律ではありません。企業の方針や雇用制度にあわせて柔軟に設定されています。
シニア人材を活用するメリット・目的
少子高齢化が進むなか、若手人材の採用は年々厳しさを増していますよね。
そんな状況でも、組織をさらに成長させていくためには、今まで以上に「シニア人材」の力を活かす視点が欠かせません。長いキャリアで培った知見や経験は、何よりの財産です。
シニア人材を活用するメリットと目的を、より具体的に見ていきましょう。
- 人材不足の解消
- 企業の競争力強化
- DEIの実現
人材不足の解消
シニア人材の活用は、深刻な人材不足を補う有効な手段です。定年退職後も働く意欲を持つシニア層は多く、即戦力として現場に貢献できる点が強みです。
長年の経験や専門知識を持つシニアは、若手のOJTや技能伝承の担い手としても重宝されます。
勤務時間や業務内容を柔軟に調整することで、体力面での負担を軽減しつつ、労働力として最大限に活用できます。
企業の競争力強化
シニア人材は、豊富な経験と高い専門性を持ちあわせています。長年にわたり培った知識や人脈は、企業にとって大きな財産です。
新しい技術や価値観と融合させることで、組織の生産性や競争力が向上します。たとえば、シニアが現場で積み上げてきたノウハウや暗黙知は、若手にはない、独自の強みです。
シニアの洞察力や問題解決力は、日々の業務推進や新規事業の立ち上げなど、さまざまな場面で企業の成長を支えるでしょう。
DEIの実現
シニア人材の活用は、DEI(ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョンI)の実現にも貢献します。年齢や世代を超えた多様な人材が活躍することで、組織全体の活性化や新たな発想の創出が期待できます。
シニアは若手のロールモデルや相談役としても重要な役割を果たし、職場の人間関係やチームワークの向上にもつながるでしょう。多様な価値観や経験が交わることで、イノベーションが生まれやすい環境が整います。
▼多様なスキル・経験を活かした人材配置を検討しているなら、以下の資料をぜひご活用ください。
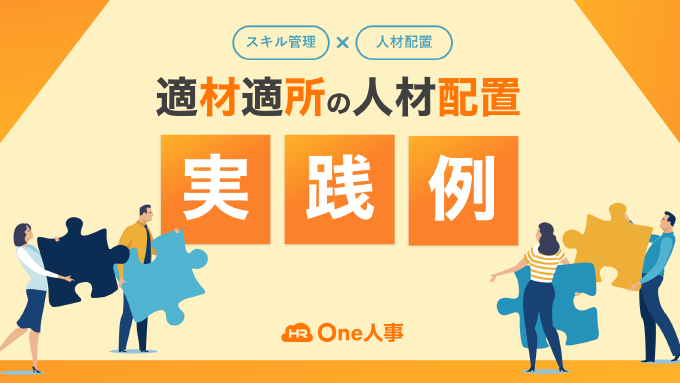
シニア人材活用の課題|いらない?
シニア人材の活用には多くのメリットがありますが、現場ではさまざまな課題も浮き彫りになっています。「シニアに頼って大丈夫だろうか」「若手の育成は遅れないか」と心配になる方もいるでしょう。
シニア活用における5つの課題について紹介します。
- 若手社員とのバランス
- 健康管理
- 適切な待遇の検討
- モチベーション維持
- リスキリング・キャリア自律支援
若手社員とのバランス
シニア人材と若手社員のバランスを取ることは、組織運営上の大きな課題です。業務の進め方や価値観が異なるため、コミュニケーションのすれ違いや役割分担の不明確さが摩擦を生むことがあります。
若手の成長機会を奪わないよう、シニアにはメンターや指導役など経験を活かせるポジションを与えるとよいでしょう。役割や期待値を明確にし、双方が納得できる人材配置を目指すことが重要です。
▼Z世代・ゆとり世代の価値観にあわせたマネジメントのコツを知るには以下の記事もご確認ください。
健康管理
シニア人材は体力や健康面での不安がつきまといます。長時間労働や過度な負担は、健康リスクを高める要因です。
短時間勤務やフレックスタイム制、在宅勤務など多様な働き方を導入し、シニア層が無理なく力を発揮できる環境を整える必要があります。健康診断や産業医との連携も欠かせません。
▼健康経営の観点から、最近では従業員の健康管理も企業に求められています。ポイントを知るには以下の記事をご確認ください。
適切な待遇の検討
給与や配属、労働条件の見直しもシニア活用における大きな課題です。
定年後の給与水準が、大幅に下がると、高年齢労働者のモチベーション低下を招きかねません。
シニア人材の役割や貢献度に応じた適正な報酬制度の導入が求められます。ジョブ型雇用や業務内容にあわせた給与体系を検討し、納得感のある待遇を検討しましょう。
モチベーション維持
シニア人材のやる気を引き出すには、納得感のある仕事や役割を与えることが不可欠です。存在意義を感じられない業務や、期待値が伝わっていない状況では、意欲の低下や不満が生じやすくなります。
上司とのコミュニケーションを密にし、期待される役割や目標を明確に伝えることが大切です。組織としてシニア人材を尊重し、承認する風土づくりが理想です。
リスキリング・キャリア自律支援
DX(デジタルトランスフォーメーション)の進展により、シニア人材のデジタル適応力が問われています。新しいシステムやツールの導入が進むなか、戸惑いや抵抗を感じる人も少なくありません。
企業としてデジタル研修など、リスキリングの機会を提供し、シニア人材が自信を持って業務に取り組めるよう支援することが重要です。キャリア自律を促すためのカウンセリングも有用です。
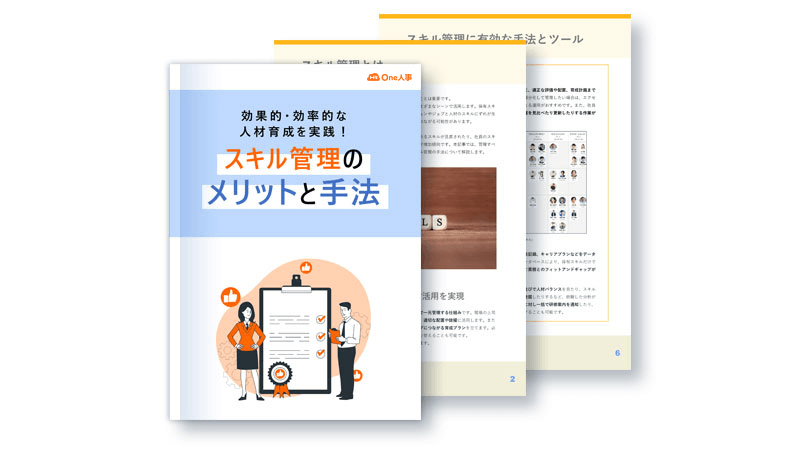
活躍するシニア人材の特徴に関する調査
シニア人材が現場で活躍するためには、どのような特徴や資質が求められるのでしょうか。
ここでは、2つの調査結果をもとに、活躍するシニア人材の特徴を紹介します。
日本人材紹介事業協会の調査によると、活躍しているシニア人材にはいくつかの共通点が見られます。人材紹介業界に限定される調査ですが、主な傾向は以下のとおりです。
- 培ってきた知識やノウハウを業務に活かしている
- 責任感や勤勉さを持っている
- 肩書や環境の変化を柔軟に受け入れ意識の切り替えができる
- 行動力や実践力が高い
シニア人材がいる企業では、本人の活躍が企業全体のメリットにつながっていると認識されています。
さらにパーソル総合研究所と大学の共同調査では、活躍するシニア人材に共通する5つの特性が明らかになっています。
- 仕事を意味づける
- まずやってみる
- 学びを活かす
- 自ら人とかかわる
- 年下とうまくやる
参照:『躍進するミドル・シニアに共通する5つの行動特性』パーソル総合研究所
調査結果から、経験や知識だけでなく、変化への適応力や自律性、周囲との協調性が不可欠であることがわかります。
企業は、シニア人材を見極め、適切な配置や役割を与えることが重要です。
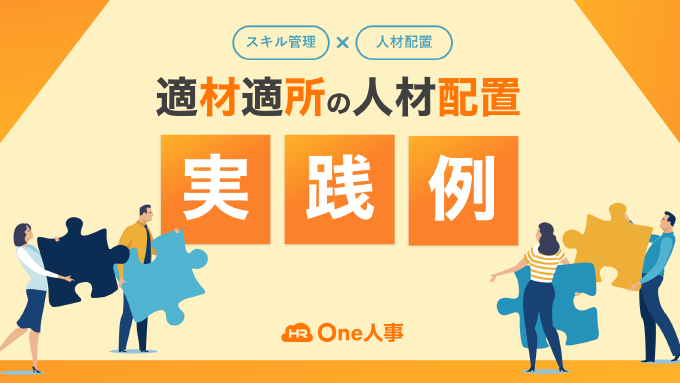
シニア人材の活用事例
「シニアを活用する」といっても、実際にどのように取り入れているのか気になりますよね。
ここでは、年齢や経験にかかわらず、多様な人材が戦力として活躍している企業の事例を紹介します。自社の配置や待遇の検討に、お役立てください。
80歳が活躍する株式会社ノジマ
株式会社ノジマでは、80歳を超えても働き続ける従業員が複数在籍しています。
定年を65歳に引き上げたあと、再雇用制度の上限も80歳まで拡大。
本人の希望と健康状態を踏まえ、80歳を超えても雇用を継続する柔軟な体制を整えています。
年齢に関係なく意欲と能力があれば活躍できる環境を整備し、実際に店舗で複数の80歳を超えた従業員が接客の第一線で活躍しています。
参考:『80歳を超えての雇用延長事例4例目誕生 ~年齢に関係なく活躍の場を提供~』株式会社ノジマ
シニア活用を支援するオムロン エキスパートリンク株式会社
オムロン エキスパートリンク株式会社は、『GOOD AGENT AWARD 2018』で「柔軟なシニア活用成功賞」を受賞しました。
シニア人材の専門性や経験を活かし、プロジェクト単位でのマッチングや多様な働き方を推進。
本人の希望や適性に合わせた業務設計を行い、企業とシニア双方にとって最適な就業機会を提供しています。
参考:『「GOOD AGENT AWARD 2018」(リクルートキャリア主催)特別賞 受賞』オムロン エキスパートリンク株式会社
豊富な経験値を活かした島屋株式会社
島屋株式会社では、スーパーセンター店舗でシニア人材が長年の経験と知識を活かして活躍しています。
売場運営や後進育成など、シニアの強みを最大限に発揮できる業務を担わせることで、組織全体の安定運営やサービス品質向上に貢献しています。
参照:『シニア活用企業事例集』公益社団法人 岐阜県シルバー人材センター連合会 岐阜県生涯現役促進地域連携協議会
技術継承に成功した神鋼造機株式会社
神鋼造機株式会社は、ベテラン従業員の高齢化・定年退職による技術・技能の継承を課題としていました。
定年を65歳に引きあげながら、シニア従業員には技術伝承を主な業務目標として明確化。
業績評価にも反映させることで、ベテラン層のモチベーション向上と若手への技術継承の両立に成功しています。
参照:『シニア活用企業事例集』公益社団法人 岐阜県シルバー人材センター連合会 岐阜県生涯現役促進地域連携協議会
シニア人材の活用推進ポイント
シニア活用の事例や活用パターンを知ると、次は実際に進める方法が気になりますよね。
シニア人材を戦力として迎えるには、企業が制度や環境を整え、一人ひとりの適性や想いを引き出す仕組みづくりが欠かせません。
現役世代と同じルールのままでは、シニア層の強みやモチベーションを活かしきれないこともあります。
ここでは、シニア活用を進めるために、おさえておきたい5つのポイントを紹介していきます。
- 賃金・雇用制度を見直す
- 就業規則を見直す
- 働きやすい環境を整備する
- 納得される評価制度を構築する
- 適性と想いを知り、最適な配置を検討する
賃金・雇用制度を見直す
シニア人材の活用を進めるには、年齢や雇用形態に応じた柔軟な賃金制度の導入が求められます。再雇用後に賃金が大きく下がると、モチベーション低下や離職リスクが高まります。
現役時代の処遇を一部引き継ぐ、貢献度や専門性に応じて個別に賃金を設定するなど、納得感のある制度設計が重要です。物価上昇や生活費の変動も考慮し、定期的な見直しを行う企業も増えています。
就業規則を見直す
シニア人材の活用に向けて、再雇用制度や定年延長を導入する場合、就業規則の改定が不可欠です。定年や雇用形態、勤務条件などの記載を現状にあわせて修正し、労働基準監督署への届け出も必要となります。
従業員への説明や個別面談を通じて、制度内容や働き方の選択肢をていねいに周知することが、トラブル防止や納得感の向上につながります。
働きやすい環境を整備する
シニア人材が快適に働ける環境づくりも大切です。身体的負担を軽減するため、適切な照明や椅子、デスクの配置を工夫します。
フレックスタイム制やリモートワークなど、柔軟な働き方を導入することで、健康状態やライフスタイルに合わせた就業が可能となります。
定期的な意見交換やアンケートを実施し、現場の声を反映させることで、職場への帰属意識やモチベーションも高まるでしょう。
▼アンケートの実施方法は、以下の記事をご確認ください。
納得される評価制度を構築する
年齢や在籍年数ではなく、シニア人材の貢献度・専門知識・成果などを正当に評価できる仕組みを整えましょう。
人事評価制度の見直しや360度評価の導入、業務内容に応じた目標設定など、制度の改善と運用を一体で進めることが重要です。
さらに、評価基準を明確にしたうえで定期的にフィードバックをすれば、シニア人材の意欲や自己成長を引き出しやすくなります。
適性と想いを知り、最適な配置を検討する
シニア人材の能力や希望、健康状態を把握し、適材適所で活躍できる配置を検討します。
単純作業に限定せず、経験や知識を活かせるポジションや後進育成、プロジェクト支援など多様な役割を用意します。
個別面談やキャリアカウンセリングを通じて、本人の想いをくみ取り、長期的な活躍につなげることが重要です。
まとめ|シニア人材の適正に応じて活用を進めるには?
シニア人材の活用は、人手不足対策にとどまらず、組織の競争力や活性化にもつながります。
健康や希望に配慮し、柔軟な働き方や納得感のある評価制度を整える工夫が必要です。
タレントマネジメントを活用すれば、シニアのスキルや経験を正確に把握し、適材適所の配置が可能になります。
年齢ではなく能力と適性で評価し、シニアの力を組織の成長に活かしていきましょう。
シニア人材の最適配置にも|One人事[タレントマネジメント]
シニア人材の最適な配置や育成を進めるには、感覚や経験則に頼らず、客観的なデータを活用した人材マネジメントが不可欠です。
One人事[タレントマネジメント]は、従業員のスキルやキャリア志向、評価結果などを一元管理し、最適な人材配置や育成施策を支援するタレントマネジメントシステムです。
個々の適性やキャリア志向をもとに配置シミュレーションが可能です。顔写真やスキル分布を確認しながら、バランスの取れたチーム編成や、リーダー・管理職候補の選出なども画面上で簡単に行えます。
スキル管理機能を活用すれば、シニア人材の強みや弱みを可視化し、リスキリングや育成プランの立案にも役立てられます。
One人事[タレントマネジメント]は、無料トライアルを実施しています。お気軽にどうぞご利用ください。