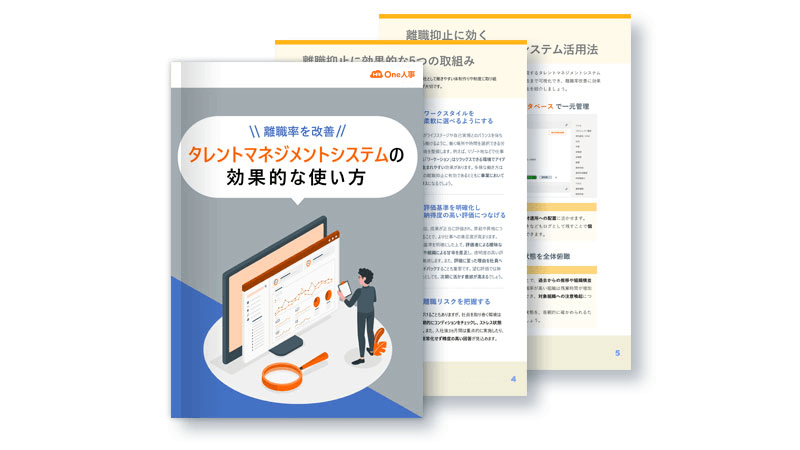育児介護休業法とは【簡単に】制度の基本と2025年の改正ポイントをわかりやすく解説
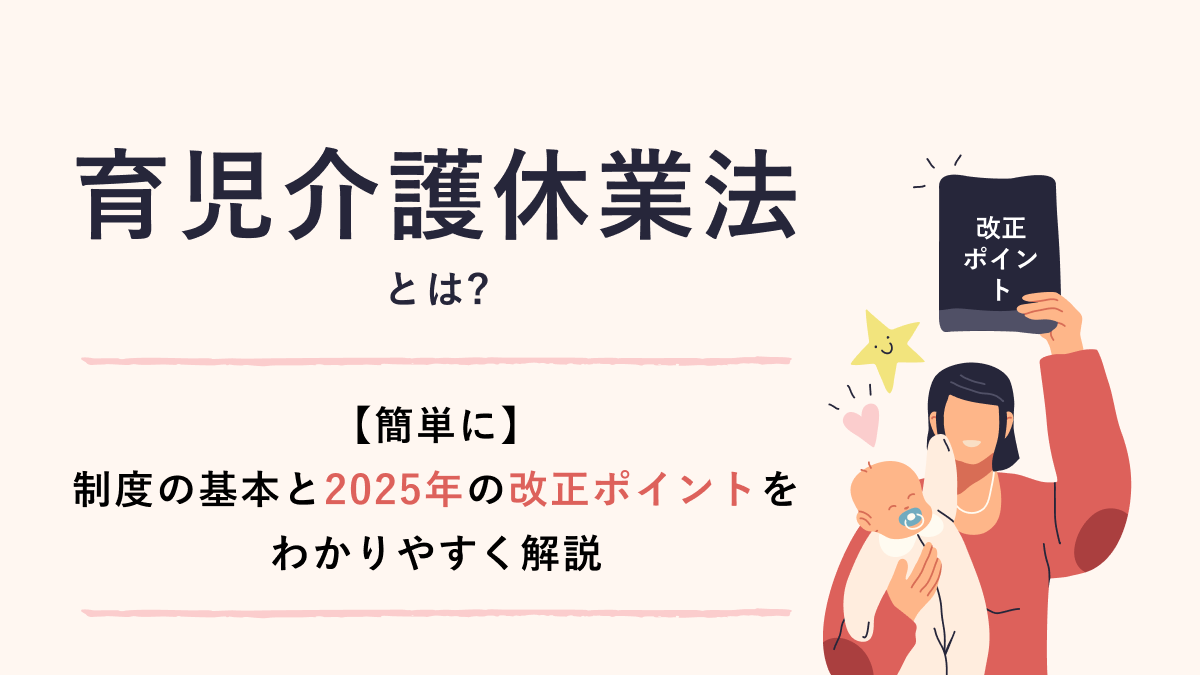
「育児介護休業法の内容や改正点がよくわからない」「自社でどのような対応が必要なのか知りたい」という方も多いはずです。2025年の改正は、企業の制度運用にも従業員の働き方にも影響する変更が含まれています。
人事労務担当者にとっては、就業規則や社内規定の見直し、従業員への周知が必要です。
本記事では、育児介護休業法の基本と2025年改正のポイントを、企業と従業員の両方の視点で、わかりやすく解説しています。制度の全体像と改正による影響、そして次に何をすべきかを知るために、お役立てください。
→従業員の育児休業にともなう労務管理も効率化「One人事」資料をダウンロード
 目次[表示]
目次[表示]
育児介護休業法とは? わかりやすく解説
育児介護休業法とは、仕事と家庭の両立を実現するために制定された法律です。少子高齢化が進む日本では、労働力人口の減少や介護離職、出産・育児によるキャリア中断が深刻な社会課題となっています。
たとえば、優秀な社員が出産や介護をきっかけに離職してしまえば、企業にとって大きな損失です。従業員が安心して子育てや介護に専念しつつ、働き続けられる環境を整えることは、企業の成長だけでなく、地域経済や労働市場の活性化にもつながります。
育児・介護休業法は1991年の制定以来、時代の変化や働き方の多様化にあわせて繰り返し改正されてきました。現在では、男女問わず誰もがライフイベントと仕事を両立できるよう、多様な制度が用意されています。

育児介護休業法で定められている制度
育児介護休業法には、男女問わず誰もがライフイベントと仕事を両立できるよう、多様な制度が用意されています。
ここでは制度の概要とポイントを整理し、実際の利用シーンも交えて解説します。
育児休業制度
育児休業制度は、1歳未満の子どもを養育するために取得できる休業です。保育所に入所できないなど特別な事情がある場合は、最長で子が2歳になるまで延長が可能です。父母のどちらも取得でき、両親が協力して育児に参加できるよう設計されています。
| 条件・対象者 | 1歳未満の子どもを養育する労働者(父母) |
| 1歳到達後の延長 | 2歳まで延長可能(条件あり) |
| 関連制度 | ・産後パパ育休(出生時育児休業) ・パパママ育休プラス |
2022年からは「産後パパ育休(出生時育児休業)」が開始され、子の出生後8週間以内に父親が最大4週間(28日)まで、2回に分けて取得できるようになりました。出産直後のサポート体制が整い、男性の育児参加が促進されています。
さらに「パパママ育休プラス」は、両親がともに育児休業を取得することで、休業期間の延長が可能となり、家庭ごとの多様なニーズに対応できるようになっています。

介護休業制度
介護休業制度は、従業員の家族が要介護状態になったときに利用できる休業制度です。対象家族1人につき通算93日まで、最大3回に分けて取得できます。
短期間の集中介護が必要なときや、状態の変化に応じて柔軟に休業を使い分けられるのも特徴です。離職せずに仕事と介護を両立したい従業員にとって大きな支えとなるでしょう。
| 条件・対象者 | 要介護状態の家族を介護する労働者 |
| 取得日数 | 対象要介護者1人に対して通算93日。 |
| 取得単位 | 分割取得が可能(最大3回まで) |
介護休業の会社への申請期限は原則として2週間前です。その間に企業は、業務調整や代替要員の確保など、引き継ぎのための準備を進めます。
復帰後も基本的に、これまでの経験やスキルが活かせる職場環境が維持されるため、従業員はキャリアをあきらめずに介護に専念できます。
子の看護等休暇制度
子の看護等休暇制度は、小学校3年生修了までの子どもを持つ従業員が特定の事情で取得できるものです。
例として病気やケガをしたとき、予防接種や健康診断を受けるとき、または感染症による学級閉鎖や入園・卒園・入学式などの学校行事に参加するときが該当します。
年間の取得日数は、子どもが1人の場合で5日、2人以上の場合で10日まで認められているため、複数の子どもをもつ家庭にも配慮されています。
| 条件・対象者 | 小学校3年生修了までの子どもがいる労働者※取得理由に制限あり |
| 取得日数 | 子1人:年間5日 子2人以上:年間10日 |
| 取得単位 | 1日・半日・時間単位 |
子の看護等休暇制度の特徴は、1日単位だけでなく時間単位でも取得できる点にあります。たとえば、午前だけ通院に付き添う、数時間だけ学校行事に参加するといった柔軟な使い方が可能です。
手続きも一定の手順を踏めば比較的容易で、保護者の多様なニーズに応えやすい制度といえるでしょう。
介護休暇制度
介護休暇制度は、要介護状態にある家族の通院や急な体調不良など、短期的な介護や世話のために取得できる休暇制度です。
対象家族が1人の場合は年間5日、2人以上の場合は年間10日まで利用でき、取得単位は1日または半日です。
長期の介護休業と組みあわせれば、計画的なケアから突発的な対応まで幅広くカバーできます。
| 条件・対象者 | 要介護状態の家族を介護する労働者 |
| 取得日数 | 要介護者1人:年間5日 要介護者2人以上:年間10日 |
| 取得単位 | 1日・半日 |
従業員が制度を有効に活用するためには、企業が内容や申請フローをわかりやすく示し、取得しやすい雰囲気を職場に根づかせることが欠かせません。制度利用への不利益な取り扱いは禁止されています。企業として公平な運用を徹底することが重要なポイントです。

育児介護休業法で定められている制限
育児介護休業法では、育児や介護を担う従業員が無理なく働き続けられるよう、労働時間に関して特別な制限が設けられています。主な制限は以下の3つです。
| 制限の種類 | 対象 | 主な対象外 | |
|---|---|---|---|
| 育児 | 介護 | ||
| 所定外労働(法定内残業)免除 | 3歳未満の子を養育している | 要介護家族を介護している | 日雇、継続雇用1年未満の者 など |
| 時間外労働(法定外残業)制限 | 小学校就学前の子を養育している | 所定労働日が週2日以下の者 など | |
| 深夜業免除 | 小学校就学前の子を養育している | 所定労働日が週2日以下の者 など | |
いずれも、従業員からの申し出があった場合、企業は条件に応じて業務を免除しなければなりません。
所定外労働(法定内残業)の免除
3歳未満の子を養育している従業員や、要介護家族を介護している従業員が申し出た場合、会社は所定外の勤務を命じることはできません。
所定外労働とは、会社が定めた所定勤務時間(定時)を超えて働くことです。
残業免除は正社員だけでなく、パートや契約社員にも適用されます。ただし、日々雇用されている方や継続雇用期間が1年未満の方など、一部は対象外です。制度運用者は、自社の雇用形態ごとの適用可否を明確にしておく必要があります。
時間外労働(法定外残業)の制限
小学校就学前の子を養育する従業員や介護者が申し出た場合、会社は時間外労働を1か月24時間以内、年間150時間以内に制限しなければなりません。
時間外労働とは、法律で定められた1日8時間・週40時間を超える労働です。
所定労働日が週2日以下の人など、一定の条件に該当すると対象から外れます。
また、会社が就業規則などでより厳しい上限を設けている場合は、自社独自の規定が優先されます。従業員へ周知するときは「自社ルールと法定条件の違い」を明確に説明しておくと誤解を防げるでしょう。
深夜業の制限
小学校就学前の子や介護が必要な家族がいる従業員が申し出た場合、深夜時間帯での勤務は免除されます。深夜業とは、午後10時から午前5時までを指します。
夜勤や深夜シフトが含まれる業務に従事している人の免除申請を受けたあとは、スケジュールや人員配置を見直さなければなりません。利用者にとっては心身への負担軽減につながり、企業にとっては健康管理や離職防止の面でも重要な制限といえます。
| 申請から制限適用までの流れ |
|---|
| 1.従業員による申し出 2.企業側の確認 3.勤務計画・シフト調整 4.適用開始通知 5.定期的な見直し |

【〜2023年】育児介護休業法の改正履歴
育児介護休業法は、社会や働き方の変化にあわせて何度も改正されてきました。近年の改正は、ハラスメント防止や男性の育児休業取得促進、柔軟な働き方の実現など、企業にも従業員にも大きな影響を与えています。2020年から2023年までの主な改正内容は次のとおりです。
| 施行年月日 | 改正のポイント |
|---|---|
| 2020年6月1日 | ハラスメント防止対策の強化。不利益取り扱いの禁止を明確化。 |
| 2021年1月1日 | 子の看護休暇・介護休暇の時間単位取得が可能に。 |
| 2022年4月1日 | 育児休業取得しやすい雇用環境の整備、個別周知・意向確認の義務化。有期雇用労働者の取得要件緩和。 |
| 2022年10月1日 | 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設。育児休業の分割取得が可能に。 |
| 2023年4月1日 | 育児休業取得状況の公表義務(常時雇用1,000人超の事業主対象)。 |
2020年の改正では、育児や介護に関するハラスメント防止が強化され、相談を理由とする不利益な取り扱いが明確に禁止されました。企業は従業員が制度を安心して利用できる環境づくりに努めなければなりません。
2021年には、子の看護休暇や介護休暇が時間単位で取得できるようになり、午前中だけの通院や短時間の付き添いといった柔軟な対応が可能になっています。
2022年4月からは、妊娠や出産を申し出た従業員に対して個別に制度を説明し、取得意思を確認することが義務化されました。また、有期雇用労働者も一定条件を満たせば育児休業を取得できるように制度の充実がはかられています。
同年10月には「産後パパ育休」が新設され、出生直後の子育てに男性が積極的にかかわれるようになりました。家庭ごとの事情に応じた分割取得も可能となっています。
2023年4月からは、常時雇用1,000人を超える企業に対し、男女別の育児休業取得率や取得者数を公表する義務が課されました。取り組みに対する透明性の向上と、男性の育児休業取得促進が狙いです。
【2025年最新】育児介護休業法の改正ポイント
2025年の育児介護休業法改正は、仕事と育児・介護の両立をより現実的に支援し、男女問わず働きやすい職場環境を実現することが目的です。
少子高齢化や人手不足が深刻化するなか、柔軟な働き方の実現、男性の育児参加、介護離職防止が重視されています。2025年の同法改正は4月1日施行分と10月1日施行分に分かれて行われています。
2025年4月1日施行
育児・介護休業法に関して、2025年4月1日からは、次の改正が実施されています。
- 子の看護等休暇:対象を小学校3年生修了まで拡大、理由も行事参加などに拡大
- 所定外労働(残業免除):対象を就学前まで拡大
- テレワーク:育児・介護従業員への導入努力義務化
- 育児休業取得状況の公表義務:300人超企業まで拡大
- 介護離職防止措置の義務化・介護休暇の取得要件緩和
- 育休状況の数値目標設定(100人超企業)
【子の看護等休暇の対象拡大】
以前は小学校就学前の子どもが対象だった看護等休暇が、小学校3年生修了までに拡大されました。取得理由も病気やケガ、予防接種や健康診断に加え、感染症による学級閉鎖や入学式・卒園式などの行事参加も含まれるようになりました。保護者が学校行事や突発的な休みに対応しやすくなっています。
企業の対応としては就業規則の改訂と、従業員への周知資料を早めに整備しましょう。
【所定外労働(残業免除)の対象拡大】
残業免除の請求が可能な対象が、3歳未満の子を養育する労働者から、小学校就学前の子を養育する労働者まで広がりました。長期的に子育てと仕事の両立を支援する設計へ変わっています。
企業の対応としては、勤務シフトを調整し、代替要員を確保しておきましょう。勤怠管理システムの設定を変更しておく必要もあるかもしれません。
【テレワークの努力義務化】
3歳未満の子を育てる従業員や介護を行う従業員に対して、短時間勤務制度の代替措置としてテレワークを導入する努力義務が課されました。通勤負担を減らし、在宅での育児・介護が可能になります。
企業は導入可否を検討し、運用ルールを作成しなければなりません。
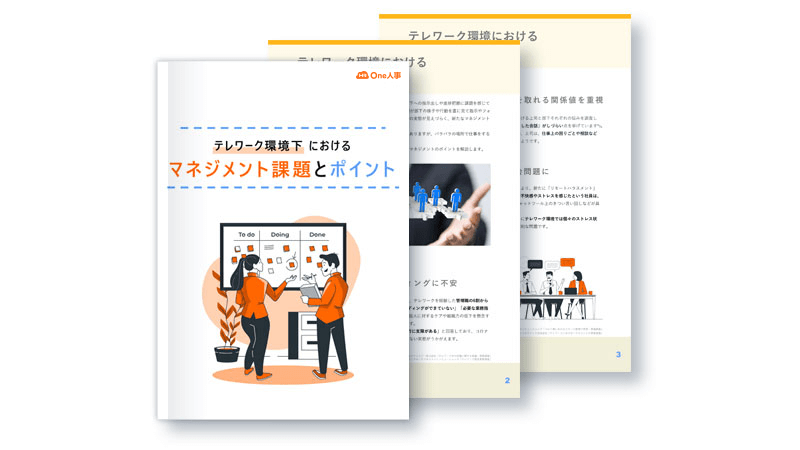
【育児休業取得状況の公表義務拡大】
従業員数300人超の企業にも、育児休業取得率や取得者数の公表が義務づけられました。中堅企業も透明性を確保しなければなりません。企業は公表方法とデータ収集体制を早めに確立しておきましょう。
【介護離職防止のための措置強化・介護休暇の取得要件緩和】
個別の周知・意向確認や雇用環境整備が義務化され、介護休暇の取得要件も緩和されました。介護をしている従業員へのテレワーク導入も努力義務です。面談や情報提供のタイミングをスケジュール化しておくと安心です。
【育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定の義務化】
従業員数100人超の企業は、育児休業取得に関する数値目標を設定し、その進捗を把握する必要があります。KPI設定や進捗の管理方法を関係部署と協議して決定しましょう。
2025年10月1日施行
育児介護休業法に関して、2025年10月1日からは、柔軟な働き方の実現に向けた新たな義務が加わっています。企業は早めの準備が必要です。
- 柔軟な働き方制度の義務化(5つの制度うち2つ以上を実施)
- 個別の意向聴取・配慮義務(3歳未満対象)
【柔軟な働き方を実現するための措置の義務化】
3歳以上小学校就学前の子どもを育てる従業員に対し、企業は以下の5つの制度のうち、2つ以上の制度を用意し、従業員が1つを選んで利用できるようにします。
- 始業時刻等の変更(フレックスタイム制や時差出勤)
- テレワーク(月10日以上、原則時間単位で利用可能)
- 保育施設の設置・運営やベビーシッターの手配・費用補助
- 養育両立支援休暇の付与(年10日以上、原則時間単位で取得可能)
- 短時間勤務制度(原則1日6時間勤務)
どの制度を導入するかを早急に選定し、導入準備に着手しましょう。
【仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮の義務化】
3歳未満の子を育てる従業員に対し、制度利用前に個別の周知と意向確認を行うことが義務づけられます。対象期間は、子どもが3歳の誕生日を迎える1か月前までの1年間です。
面談時期と記録方法を決め、継続的に実施できる体制を整えましょう。
2025年の育児介護休業法改正は、制度利用者の対象範囲拡大と企業の義務強化が目立ちます。とくに、テレワーク導入や柔軟な働き方の制度整備は、運用フローや就業規則の見直しが欠かせません。また、数値目標の設定や公表義務にともなって、データ管理や報告体制の整備が求められます。

育児介護休業法改正にともなう企業の対応策
2025年の育児介護休業法改正は、企業の持続的成長や人材確保の観点からも重要なテーマです。
従業員の多様なライフステージや働き方に対応するため、企業は制度面・運用面の両方で具体的な対応策を講じる必要があります。
【主な対応策】
- 就業環境を整備する
- 就業規則を見直す
- 従業員に制度内容を周知し、取得意思を確認する
- 育児休業者・介護休業者へのハラスメントを防止する
- 育児休業取得状況を公表する
ここでは、改正法に対応するために企業が実践すべき主な施策について、より詳しく解説します。
就業環境を整備する
まず、従業員が安心して育児や介護と仕事を両立できる環境づくりが不可欠です。
育児介護休業法の改正内容を踏まえ、フレックスタイム制、時差出勤、テレワーク、短時間勤務制度など、柔軟な働き方を可能にする制度を導入しましょう。
2025年10月からは、3歳以上小学校就学前の子を育てる従業員に対し、複数の両立支援制度を用意し、本人が選べる体制が義務化されています。既存制度の見直しや新制度の導入、運用ルールの明確化が必要です。
休業取得時の混乱を防ぐために、業務マニュアルの整備やタスク分担、情報共有の仕組みづくりも重要です。休業の取得者が出ても引き継ぎができていれば、組織全体の生産性は維持されます。
さらに、管理職や人事担当者向けの研修を実施し、制度の趣旨や現場での対応事例を共有すると効果的です。
就業規則を見直す
育児介護休業法の法改正内容を反映させるため、就業規則や労使協定の更新が必須です。
子の看護等休暇の対象拡大、残業免除の範囲拡大、テレワークの努力義務化などを反映させましょう。
就業規則の改定は、厚生労働省のモデル規程やガイドラインを参考に、自社の状況にあわせて設計するのがおすすめです。
就業規則を変更するときは、労働者代表の意見聴取と周知が義務づけられています。
▼就業規則の変更方法について詳しく知るには、以下の記事をご確認ください。
従業員に制度内容を周知し、取得意思を確認する
育児介護休業法の改正により、制度内容の周知と取得意思の確認が、これまで以上に重視されました。
とくに3歳未満の子を育てる従業員には、育児休業や短時間勤務、テレワークなどの利用可能制度を個別に説明し、取得の意思を確認することが義務化されています。
従業員が制度を知らずに利用をあきらめてしまうことを防ぐためです。
妊娠・出産の申し出があったときや、子どもが3歳の誕生日を迎える1か月前までの1年間に個別面談や書面、メールなどで説明して利用希望の有無を確認します。
説明会や社内イントラネット、FAQを作成する方法もあります。従業員が安心して制度を利用できるよう、相談窓口を設置し、取得希望者へのフォロー体制も整備しましょう。
育児休業者・介護休業者へのハラスメントを防止する
育児や介護を理由としたハラスメント(マタハラ、パタハラ、ケアハラ)は、職場環境に深刻な影響を与えます。
育児介護休業法の改正により、ハラスメント防止措置が強化されました。企業は相談窓口設置や社内研修、ハラスメント防止規程の整備など具体的な対応を講じる必要があります。
管理職や現場リーダーには、ハラスメントの定義や事例、適切な対応方法を周知徹底し、未然防止に努めましょう。
万が一発生した場合は、事実関係を迅速に調査し、再発防止策を講じることが欠かせません。
育児休業取得状況を公表する
2025年の育児介護休業法改正で、育児休業取得状況の公表義務は、従業員300人超の企業に拡大されました。以前まで対象外だった中堅企業も対応が必要です。
具体的には、男女別の育児休業取得率や取得者数を公表します。公表方法は、企業のWebサイトや社内報、事業所内掲示が一般的です。
公表の際は、厚生労働省のガイドラインに沿い、正確でわかりやすい情報発信を心がけましょう。透明性を高めることで社会的な信用が向上し、男性の育児休業取得促進や社内意識改革にもつながります。
公表データは今後の両立支援施策改善にも活用が可能です。日頃から自社の人材情報を一元的に管理し、データ化しておくと公表もスムーズです。人材情報の一元化のコツを知るには以下の記事もご確認ください。
育児介護休業法に企業が対応するメリット
2025年における育児介護休業法の改正内容を見ると、やらなければならないことが増えたと感じた方もいるはずです。
確かに、育児介護休業法は法的義務をともなうため、企業としては必ず対応しなければなりません。
しかし、適切に制度を整えて運用すれば、従業員の働きやすさ向上や社会的な信用の向上など、企業にも好影響が期待できます。主なメリットは次の4点です。
- 従業員のモチベーションや生産性の向上
- 社会的信用の向上
- 離職防止
- 属人化の解消
メリットを理解しておくことで、義務対応を単なる負担ではなく、労務環境を整える機会として活かせるでしょう。詳しく見ていきます。
従業員のモチベーションや生産性の向上
育児介護休業法に基づいた育児・介護との両立支援制度は、従業員のモチベーションを高め、生産性向上にもつながります。
業務と家庭の両立がしやすくなることで、日々の仕事への集中度や前向きな姿勢が維持されるからです。
たとえば、復帰後に短時間勤務やテレワークなど柔軟な働き方を選べる職場では、従業員は無理なく安心して業務に取り組めます。結果として主体性が増し、周囲との協力も活発化。チーム全体の効率や成果も向上します。女性のキャリア形成や多様な人材活躍の促進にもつながるでしょう。
育児介護休業法の適切な運用は、従業員一人ひとりの業務意欲と組織全体のパフォーマンスを同時に高められるといえます。
社会的信用の向上
育児介護休業法に積極的に対応する企業は、対外的なイメージが向上し、社会的な信用を高められます。
法令遵守はもちろん、従業員のライフイベントを支える姿勢がCSR(企業の社会的責任)の実践として評価されるためです。
柔軟な働き方や両立支援制度が整っている企業は、求職者や取引先からも好印象を持たれ、優秀な人材の確保や定着にもつながります。とくに若年層や多様な人材が重視する「働きやすさ」を打ち出すことで、採用や人材定着の面で他社との差別化も可能です。
育児介護休業法への積極対応は、単なる義務履行を超え、企業ブランドと競争力を向上させる可能性があります。
離職防止
育児介護休業法の制度整備は、育児や介護を理由とする離職を防ぐ手段としてメリットがあります。
家族の状況が変わっても働き続けられるという安心感が生まれ、従業員の長期的なキャリアへの不安が軽減されるためです。
たとえば、相談窓口や定期的なヒアリングを設けて小さな悩みを早期に把握できれば、問題が深刻化する前にサポートが可能です。結果として、従業員は安心してキャリアと家庭を両立でき、職場への定着率が高まります。
育児介護休業法を活かした職場づくりは、経験豊富な人材を守り、組織の安定と成長を支えるでしょう。
属人化の解消
育児介護休業法に基づく休業取得が一般化すると、間接的に業務の属人化防止にもつながります。
長期休業が想定されることで、特定の人にしかできない仕事を減らし、業務の標準化や共有が進むためです。
たとえば、マニュアル整備や日常的な情報共有が進めば、誰が担当しても一定の品質を維持しやすくなるでしょう。結果として、業務のムラやミスが減少し、改善アイデアや新たな取り組みも生まれやすくなります。
育児介護休業法を前提とした業務設計は、組織全体の柔軟性を高めます。
育児介護休業法に違反した場合の罰則
育児介護休業法に違反した企業には、厳しい行政指導や罰則が科されます。
| 育児・介護休業法に違反した場合の流れ | |
|---|---|
| 報告要求 | 厚生労働大臣または都道府県労働局長が、違反の疑いがある企業に報告を求める企業は要請に応じ、必要な情報を提出する義務あり |
| 行政指導 | 違反が認められると、助言 → 指導 → 勧告の順で是正を求められる |
| 企業名の公表 | 勧告にしたがわず是正措置を取らなかった場合は、企業名が公表される |
報告を怠ったり虚偽の報告を行ったりすると、20万円以下の過料が科されます。刑事罰ではないものの、経済的な損失は小さくないでしょう。
最終的に企業名が公開されると、社会的な信用や取引先・顧客からの信頼低下、採用活動への悪影響など、深刻なダメージの大きさは計り知れません。
また、育児休業や介護休業の取得を理由に従業員を不利益に取り扱った場合も同様に、行政指導や企業名の公表、過料の対象です。
法令遵守は企業の社会的な責任であり、違反によるリスクは非常に大きいことを念頭に置く必要があります。
まとめ
育児介護休業法は、従業員が育児や介護と仕事を両立できる環境を整えるための法律です。2025年改正では、子の看護休暇や残業免除の対象拡大、テレワークの努力義務化など、企業の実務にも影響する変更が加わりました。
育児介護休業法への対応は法的義務ですが、制度を適切に運用すれば、働きやすさの向上や離職防止、企業イメージの強化にもつながります。今後も改正動向を踏まえ、柔軟で戦略的な制度運用を進めていきましょう。