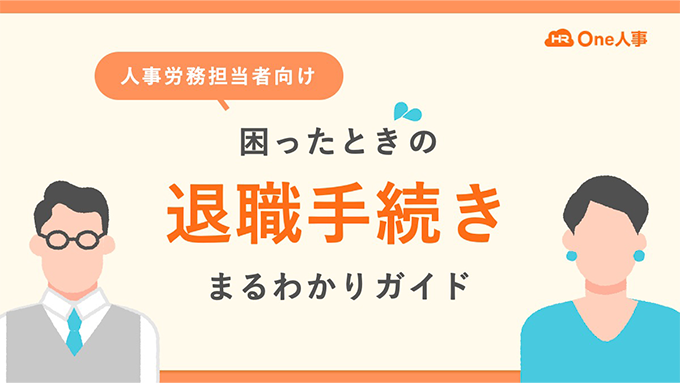解雇予告手当とは?計算方法や条件、支払い日も解説

従業員の解雇は、企業にとって慎重な判断が求められる重要な手続きです。一歩間違えると労務トラブルに発展するリスクがあるため慎重に対応しなければなりません。
本記事では、解雇予告手当の基本的な概要から、計算方法や支払いの条件、支払い日などについて詳しく解説します。実務担当者が適切に対応するためのポイントをおさえ、リスク回避や適切な労務管理にお役立てください。
そもそも解雇とは? 種類や条件を確認するには【解雇の種類|条件や違い、処分の流れも解説】の記事もご確認ください。
→労務管理を効率化「One人事」資料をダウンロード
 目次[表示]
目次[表示]
解雇予告手当とは
解雇予告手当とは、企業が事前の予告(解雇予告)なしに従業員を解雇する際に支払うお金です。
解雇を通知する日から解雇日までの長さに応じて、最大30日分の平均賃金を支払う必要があります。
解雇予告手当を理解するうえで重要な、通知日と支払い金額の関係は以下のとおりです。
| 解雇を通知した日 | 解雇予告手当の支払い額 |
|---|---|
| 解雇日当日 | 平均賃金の30日分 |
| 解雇日の29日前から1日前 | 予告期間が不足している日数分の平均賃金 |
| 解雇日の30日以上前 | 支払いなし |
解雇日までの期間が短ければ短いほど、支払う解雇予告手当の金額が大きくなると理解しておきましょう。
参照:『しっかりマスター労働基準法ー解雇編ー』厚生労働省東京労働局
まずは解雇の事前予告「解雇予告」について知るには以下の記事もご確認ください。
解雇予告とは
解雇予告とは、企業が従業員を解雇する際に、30日前までに対象者に告知することです。
会社から突然解雇された従業員は、職を失って生活に困ったり、転職活動にも支障が出たりする場合があります。
解雇予告は、従業員側が突然解雇されたときに被る不利益の大きさに配慮して設けられた制度です。
労働基準法で定める解雇予告手当の規定
解雇予告や解雇予告手当の支払いについては、労働基準法で明確に定められています。
法律に違反した場合は、6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金を科される可能性があるため、企業は慎重に対応しなければなりません。
解雇予告手当の支払い条件
解雇予告手当は、労働基準法で定められた従業員の権利です。企業は法令に基づいて正しく支払う義務があります。
支払い条件について、対象者や支払い日を理解しておかないと、重大な労務トラブルに発展しかねません。
解雇予告手当の支払い条件を整理すると以下のとおりです。
| 対象者 | 雇用形態にかかわらず全従業員 |
| 支払い日 | 最後の給与支払いと同時 |
法的責任を果たすためにも条件を整理し、適切に対応しましょう。
解雇予告手当の対象者
解雇予告手当の対象者は、企業に雇用されているすべての従業員です。正社員だけでなくアルバイトやパート、契約社員などの非正規雇用労働者も含まれる点に注意しなければなりません。
解雇予告手当の支払い日
解雇予告手当は、退職前の最終給与と一緒に支払われるのが一般的です。
しかし、解雇のタイミングによっては、支払い日が前後します。
| 解雇のタイミング | 解雇予告手当の支払い日 |
|---|---|
| 即時の解雇 | 解雇と同時に支払う |
| 予告後の解雇 | 解雇日までに支払う |
即時解雇では、解雇と同時に解雇予告手当を支払わなければならない点に注意しましょう。
解雇予告手当を支払わなくてもよい場合
解雇予告手当は、企業が事前の予告なしに従業員を解雇する際に支払う手当です。ただし、状況に応じて解雇予告手当を支払わなくてもよい場合があります。
具体的にどのような状況が該当するのか3つのケースを紹介します。
| 解雇予告手当の支払い義務が発生しない場合 | 例 | 労働基準監督署での認定 |
|---|---|---|
| 会社側のやむ得ない事情 | 天変地異(地震、火事、津波など)で事業継続が困難 | 必要 |
| 従業員側の重大責任 | 横領や重大な規律違反、無断欠勤が続いた | 必要 |
| 特定の雇用契約 | 日雇い労働者、試用期間中の14日以内の解雇 | 不要 |
企業は、以上3つに該当するかどうかを慎重に判断し、判断が難しい場合は専門家に相談しましょう。
災害などやむを得ない事情がある
災害などのやむを得ない事情によって事業が続けられなくなったら解雇予告手当の支払いが免除されます。
たとえば、震災の津波によって事業所が復旧不可能な状態になったり、火災によって事業所が焼失したりする状況が挙げられます。
災害が発生した場合、解雇予告手当を免除するには、企業を管轄する労働基準監督署長の認定が必要です。
従業員側の重大な問題がある
解雇予告手当を支払わなくてもよいのは、解雇する従業員側に大きな問題や原因がある場合です。
ただし、いわゆる「懲戒解雇」であっても、必ずしも解雇予告手当が不要になるわけではないため、個別の状況に応じて判断することが重要です。
従業員の勤務状況や職責を踏まえて、以下のチェックポイントで判断します。
- 組織に大きな迷惑をかけたか
- 重大な規律違反があったか
- 採用の可否に影響する内容についての経歴詐称などがあったか
- 遅刻や欠勤が多く、改善が見込めないか
- 法律違反行為などがあったか
以上のように従業員に問題がある場合は、社会通念上に照らして判断されます。
また、従業員側に明らかな非があっても、解雇予告手当の支払いを免除するには、管轄の労働基準監督署長の認定が必要です。
特定の雇用契約に該当する
特定の雇用契約を結んでいる従業員は、解雇予告手当の支払い対象から除外されます。
具体的には、主に以下の4つのような短期労働を指しています。
- 日雇い労働者(雇用期間が1か月未満である)
- 雇用期間が2か月以内の労働者
- 季節的業務として雇用期間を4か月以内で定められた労働者
- 試用期間中の労働者(働き始めた日から14日未満が該当)
解雇予告手当だけでなく、事前の解雇予告も不要です。
労働基準法第21条に定められているため、労働基準監督署長の認定も必要ありません。
短い雇用期間での契約では、解雇前に契約内容を正しく把握して、解雇予告手当の要否について判断しましょう。
参照:『労働基準法第19条、20条、21条』e-Gov法令検索
正当な解雇理由について詳しく知るには以下の記事でもご確認ください。
試用期間中の解雇条件は以下の記事でもご確認ください。
解雇予告手当の計算
解雇予告手当は以下の式で算出します。
| 解雇予告手当=平均賃金×支給対象日数 |
まずは、式のなかある「平均賃金」と「支給対象日数」の求め方から確認していきましょう。とくに平均賃金は2つの計算方法に注意が必要です。
平均賃金の算出
平均賃金は、解雇予告手当の計算で重要なポイントとなる指標です。
過去3か月間の総賃金をもとにし、所得税や社会保険料を控除する前の給与額を対象とします。
臨時的に支払われるものや賞与は対象外なので間違えないように注意しましょう。
平均賃金の2種類の計算方法は、以下のとおりです。
| 計算方法1 | 原則 | 直近3か月の合計賃金÷直近3か月の暦日数 |
|---|---|---|
| 計算方法2 | 最低保障額 | 直近3か月の合計賃金÷直近3か月の労働日数×0.6 |
2種類の計算方法のうち、高い金額を平均賃金として採用します。
「計算方法1」の原則的なやり方で計算すると、最低保障額を下回る場合があるためです。
なお、銭未満の端数は切り捨てても問題ありません。
日数の算出
解雇予告手当の計算では、支給対象となる日数も正しく把握する必要があります。
支給対象日数とは、解雇予告が30日前までであるのに対して不足している日数です。
解雇日までに30日前を切って予告する場合は、30日から不足した日数を差し引きます。
解雇日から25日前に解雇の予告をした場合、解雇予告に必要な5日分足りないため、支給対象日数は5日と考えます。
解雇予告手当の金額を計算
支給対象日数と平均賃金額を算出したら、解雇予告手当の計算式にあてはめて計算しましょう。
| 解雇予告手当=平均賃金×支給対象日数 |
以下の条件を例に確認してみます。
| 月給 | 40万円 |
|---|---|
| 直近3ヶ月の合計賃金 | 120万円 |
| 労働日数 | 62日(8月分21日、9月分19日、10月分22日) |
| 暦日数 | 92日(8月分31日、9月分30日、10月分31日) |
| 解雇日 | 10月31日 |
| 支給対象日数(解雇予告の不足日数) | 20日 |
平均賃金の計算は以下のとおりです。
| 計算方法1 | 原則 | 120万円÷92日=13,043円47銭(銭未満切り捨て) |
|---|---|---|
| 計算方法2 | 最低保障額 | 120万円÷62×0.6=11,612円90銭(銭未満切り捨て) |
より金額が高いほう「1.原則」の計算結果が適用されます。
最後に解雇予告手当の計算式にあてはめて計算します。
| 解雇予告手当の計算具体例 |
|---|
| 13,043円47銭×20日=260,869円(円未満は四捨五入) |
例における解雇予告手当の金額は、26万869円です。
解雇予告期間の起算日は、初日不算入の原則により、解雇を予告した日の翌日です。
解雇予告手当と所得税
解雇予告手当は、給与所得ではなく退職所得に該当します。
そのため、企業が解雇予告手当を支払う際は、退職金と同じように所得税を源泉徴収しなければなりません。
より正しく所得税を徴収するためには、従業員から「退職所得の受給に関する申告書」を提出してもらう必要があるものの、実際は提出されないケースも多くあります。
申告書が提出されなかったら、解雇予告手当の「20.42%」の金額を源泉徴収して処理する決まりです。
また、企業が解雇予告手当を支払ったあとは、本人に「退職所得の源泉徴収票」を退職後1か月以内に送付します。
以下では申告書提出の有無によって変わる計算方法を具体例とともに解説していきます。
退職所得の受給に関する申告書が提出されている場合
申告書が提出された場合は、以下のような計算式で課税額を算出します。
| 課税退職所得金額=(一般退職手当等の収入金額-退職所得控除額)÷ 2 |
| 勤続年数20年以下の場合 | 退職所得控除額=40万円×勤続年数 |
|---|---|
| 勤続年数20年超の場合 | 退職所得控除額=800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
退職所得控除額が80万円に満たない場合は、80万円を下限とします。
解雇予告手当の支給で所得税の源泉徴収が発生するのは、解雇予告手当額を含めた一般退職手当等の収入金額が退職所得控除額を上回った場合です。
求められた課税退職所得金額を「退職所得の源泉徴収税額の速算表」にあてはめて計算した額が、源泉徴収する税額になります。
退職所得の受給に関する申告書が提出されていない場合
「退職所得の受給に関する申告書」が提出されていない場合は、以下の計算式で求めた額が、源泉徴収する税額です。
| 一般退職手当等の収入金額×20.42% |
手続きが漏れると税務リスクが発生する可能性もあるため、正確な事務処理を覚えて徹底しましょう。
解雇予告手当を支払わない企業側のリスク
解雇予告手当の支払いは、労働基準法で義務づけられた重要な要件です。企業が解雇予告手当の支払い義務を怠ると、法的および経営上の重大なリスクを背負うことになります。
支払わないとどうなるのか、具体的に考えられる3つのリスクを紹介します。
- 訴訟や労働審判に発展することもある
- 付加金を支払わなければならない場合もある
- 罰則を受ける可能性がある
訴訟や労働審判に発展することもある
解雇予告手当を支払わなかった場合、従業員から不当解雇として請求があり、訴訟や労働審判を起こされるリスクがあります。
万が一敗訴すると、社会的な信用の低下は逃れられません。敗訴しなかったとしても、精神的な負担や労力、時間がかかり、体力がある企業でないと労務トラブルを乗り越えられないかもしれません。
労務トラブルの発生を防ぐためには、解雇手続きの正確性が重要です。
付加金を支払わなければならない場合もある
解雇予告手当を支払わずに従業員から訴訟を起こされると、本来の解雇予告手当とは別に「付加金」の支払いを判決で命じられることもあります。
付加金は、本来支払われる金額と同額になるため、企業側にとって大きな負担になります。
無駄な費用の計上を避けるためにも、適切な解雇手順に沿って対応しなければなりません。
参照:『労働基準法第115条』e-Gov法令検索
参照:『(3) 解雇予告手当に関する事件 』裁判所
罰則を受ける可能性がある
解雇予告手当の支払いは、労働基準法に規定された企業の義務です。法令にしたがわず解雇予告手当を支払わないと、罰則規定が適用される可能性もあります。
企業が刑事罰を受けるということは、社会的信用を失ったり、企業イメージの失墜にもつながるため、大きなリスクといえます。
企業の信頼を守るためにも、解雇予告手当を確実に、適切な手続きに沿って用意しましょう。

まとめ
解雇予告手当とは、企業が解雇予告なしで従業員を解雇する場合に支払わなければならないお金です。
労働基準法では、企業が従業員を解雇する際は、30日前までに本人へ予告することを定めています。
また、解雇予告をせずに解雇する場合は、解雇日までの期間に応じて解雇予告手当金を支払わなければなりません。
企業は、法令違反やトラブルにつながらないよう、計算方法も含めて正しく理解しましょう。