雇用契約書の記載事項とは? 必須項目はある? 各項目の記載例と作成・変更のポイントを解説
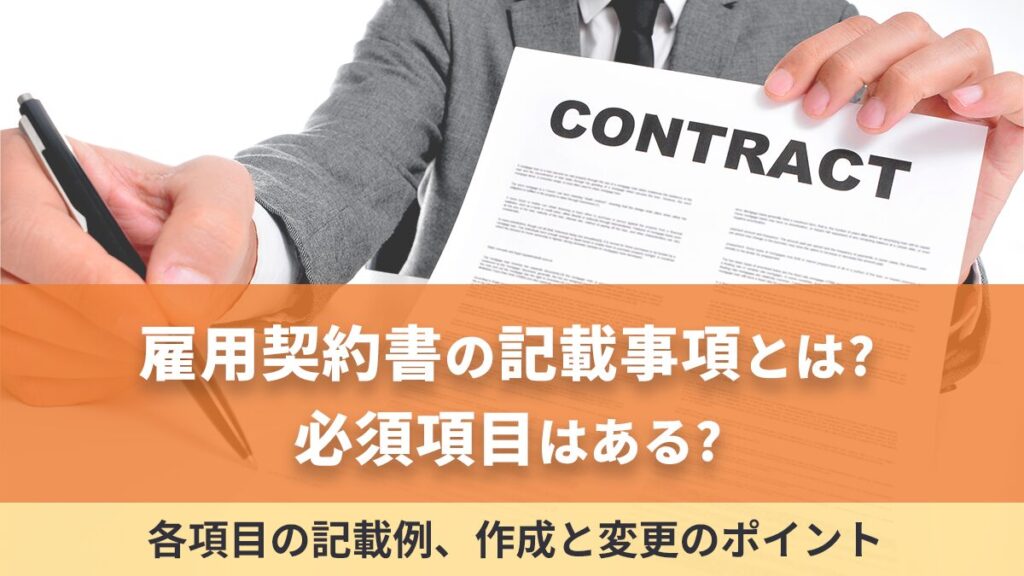
雇用契約書とは企業側と労働者が合意のうえで契約を締結したことを示す書類です。法律上は作成しなくても問題ありませんが、のちのトラブルを回避するために作成した方がよいとされています。作成する際にはどのような項目を記載すればよいか、事前に確認しておきましょう。
本記事では、雇用契約書の記載事項について解説します。雇用契約書を作成する際のポイントや注意点も紹介します。
 目次[表示]
目次[表示]
雇用契約書の記載事項に決まりはない
雇用契約書とは、企業側と労働者が合意のうえで締結したことを示す契約書です。業務内容や雇用期間、賃金など労働にかかわる事項が記載されています。
雇用契約書の記載内容は定められておらず、任意で項目を選択できます。そもそも雇用契約書の作成は法的に義務づけられていません。口頭での契約でも雇用契約は有効です。
しかし、勤務開始後に「契約時の話と違う」というトラブルが発生する可能性があるため、作成しておいた方がよいでしょう。
雇用契約書と似ている書類には「労働条件通知書」があります。
労働条件通知書とは、賃金や労働時間などについて記載し、企業が従業員に送付する書類です。雇用契約書とは異なり、労働基準法に規定があるため、従業員を雇用する際には作成しなければなりません。
雇用契約書と労働条件通知書を兼ねた契約書類の作成も可能です。その場合、労働条件通知書の書式に沿って作成します。
雇用契約書を兼ねた労働条件通知書は、労働条件を通知するだけでなく、企業と従業員の双方が署名・押印することが一般的であるため、トラブル回避に有効でしょう。
雇用契約書の一般的な記載事項
雇用契約書の一般的な記載事項は以下のとおりです。
- 労働契約期間・更新の有無
- 就業場所
- 業務内容
- 就業時間
- 交替勤務の有無
- 休憩時間
- 時間外労働の有無
- 休日休暇
- 賃金や手当および支払日
- 退職に関する事項
労働契約期間・更新の有無
雇用契約書は、労働者の契約期間や雇用契約の更新の有無について記載します。雇用形態によって記載内容が異なり、それぞれに合わせた書き方が必要です。
雇用形態別の労働契約期間・更新の有無の記載例は、以下のとおりです。
| 正社員(無期雇用) | 期間の定めなし |
| 契約社員 | 〇年〇月〇日〜〇年〇月〇日まで |
| 有期パート社員 |
正社員の多くは期間を定めず定年まで雇用されます。一方で、契約社員は期間が定められていることが多く、一定期間ごとに契約を更新するため、契約期間を明記しておきましょう。
就業場所
雇用契約書には、具体的にどこで勤務するか店舗名や住所を記載します。
| 就業場所 | ・本社・事業所名(住所)※勤務先が複数ある場合はすべて記載 |
就業場所は基本的に本社と書かれることが多いようです。
住所まで記載する必要はありませんが、本社と異なる事業所で働く場合は、記載しておくとよいでしょう。複数の事業所で勤務する可能性があるなら、該当するすべての施設名を雇用契約書に記載します。
業務内容
雇用契約書には入社後に行う業務内容を記載します。付随業務以外にも複数業務に従事する契約にするのであれば、その内容も明記しましょう。
業務内容の具体的な記載例は以下のとおりです。
| 業務内容 | 〇〇およびこれに付随する業務 |
就業時間
雇用契約書には、始業時間と終業時間を明記することが重要です。従業員が何時から何時まで勤務するのか、時間外労働の可能性や休憩時間についても記載しましょう。
就業時間の具体的な記載例は以下のとおりです。
| 就業時間 | 9時00分から18時00分まで(うち休憩時間60分) |
| 所定労働時間外労働 | 有 |
交替勤務の有無
雇用契約書には、交替勤務に関する詳細な勤務時間を記載します。たとえば、営業時間が長い事業所や夜勤のある工場・医療現場など、シフト制を採用している従業員が該当します。
雇用契約書には、交代勤務の有無について、勤務する可能性のある時間帯はすべて明記しましょう。記載例は以下のとおりです。
| 就業時間 | 1勤 8時00分〜17時00分 2勤 15時00分〜24時00分 3勤 21時00分〜6時00分 |
休憩時間
労働時間のうち、決められた休憩時間も雇用契約書に記載します。労働基準法で定められている休憩時間のルールについては、具体的に記述する必要はありません。以下の記載例のように簡潔に明記しましょう。
| 休憩時間 | 60分 |
時間外労働の有無
雇用契約書には、所定労働時間を超えて労働する可能性の有無も記載します。時間外労働について、詳細時間を記載する必要はありません。記載例は以下のとおりです。
| 所定時間外労働 | 有または無 |
休日休暇
雇用契約書には、休日や休暇に関する取り決めも記載します。法定休日や所定休日について以下のように記しましょう。
| 休日・休暇 | (定例の場合)土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始 |
| (非定例の場合)週休2日 | |
| (1年単位の変動労働時間制の場合)年間120日 |
賃金や手当および支払日
賃金の支払い方法や支給日についても雇用契約書に記載します。賃金にかかわるすべての事項を漏れなく明示する必要があり、記載例は以下のとおりです。
| 基本給 | 300,000円 |
| 通勤手当 | 全額支給 |
| 賃金締切日 | 毎月月末 |
| 賃金支払日 | 翌月20日 |
| 賃金支払い方法 | 本人名義口座へ振込 |
退職に関する事項
雇用契約書には、定年制度や再雇用制度、退職手続きに関する事項も記載します。記載例は以下のとおりです。
| 定年制 | 60歳まで |
| 定年後再雇用制度 | 有(65歳まで) |
| 自己都合退職 | 退職の1か月前までに申し出ること |
雇用契約書と労働条件通知書を兼ねる場合は必須の記載事項がある
雇用契約書は、労働条件通知書と兼用のものを作成してもよいとされています。労働条件通知書兼雇用契約書を作成する場合は、以下のポイントに注意しましょう。
- 絶対的記載事項を明記する
- 2024年4月に改正された項目を確認する
- パート・アルバイトで必須の項目を確認する
- 相対的記載事項があれば明記する
絶対的記載事項を明記する(※必須)
労働条件通知書には、必ず記載しなければならない絶対的記載事項があります。したがって、雇用契約書と労働条件通知書を兼ねる場合も、以下の項目を記載しなければなりません。
- 雇用契約期間(期間の定めがある契約は更新する基準を定める)
- 就業場所および従事すべき業務
- 始終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩・休日・休暇などに関する事項
- 賃金の計算方法や支払日
- 退職に関する事項
- 昇給に関する事項
上記のすべての事項が記載されていないと、労働条件通知書として認められません。なお、昇給に関しては書面による明示は求められていませんが、ほかの項目と一緒に記載することが一般的です。
そもそも労働条件通知書には法的に交付義務があるため、雇用契約書を作成しなかったとしても、必ず作成する必要があります。
労働条件通知書だけ用意する場合も、雇用契約書と労働条件通知書を兼ねる場合も、テンプレートを用意しておくと事務処理が円滑に進むでしょう。
2024年4月に改正された項目を確認する
労働条件通知書兼雇用契約書の作成に関連して、法改正により2024年4月から、労働条件の明示項目が追加されました。労働契約を締結するときと更新するときに、新たに明示することとなった必須項目は、以下のとおりです。
| すべての労働者 | 就業場所・業務の変更の範囲 |
| 有期労働契約締結時と更新時 | 更新上限の有無と内容 |
| 無期転換申込権が発生する契約の更新時 | 無期転換申込機会、無期転換後の労働条件 |
参考:『2024年4月から労働条件明示のルールが変わります』厚生労働省
パート・アルバイトにおいて必須の項目
労働条件通知書兼雇用契約書の作成にあたって、パート・アルバイトにおいては、上記の絶対的記載事項に加えて、以下の事項を明示しなければなりません。
- 昇給の有無
- 退職手当の有無
- 賞与の有無
- 相談窓口
相対的記載事項(※社内制度がある場合は必要)
労働条件通知書兼雇用契約書には、必要に応じて相対的記載事項も内容に含める必要があります。
相対的記載事項とは、社内で制度を運用している場合に、記載しなければならない項目です。相対的記載事項の具体的な内容は以下のとおりです。
- 退職手当について
- 賞与について
- 食費や作業用品の負担について
- 安全衛生について
- 職業訓練について
- 災害補償について
- 表彰や制裁について
- 休職について
上記の中で社内制度として設定している項目があれば、必ず明記しましょう。制度として運用しているにもかかわらず、記載されていないと将来的な労務トラブルにつながります。
雇用契約書のテンプレート・サンプル・記載例
雇用契約書は、従業員を雇用するたびに作成する必要があるため、テンプレートを用意しておくと効率的に業務を進められます。インターネット上でも多様なテンプレートが公開されており、ダウンロードして自社に適した形式へ加工して活用するとよいでしょう。
将来的な労務トラブルを避けるため、労働条件通知書兼雇用契約書を発行する企業が多いようです。基本的に労働条件通知書の内容に沿って作成し、書面の最後に当事者同士の意思が合致していることを明らかにするために、企業と従業員双方が署名と押印をします。
厚生労働省は、労働条件通知書兼雇用契約書のテンプレートを公開しています。正社員・アルバイト・パートなど雇用形態を問わず使える仕様であるため、新しく作成を検討している企業や変更を検討している企業は、活用してみるのもよいでしょう。
雇用契約書を作成するポイント
雇用契約書を作成するポイントは以下の7つです。
- 2通作成して企業と従業員で1通ずつ保管する
- 必要な項目を過不足なく記載する
- 採用条件と相違がないか確認する
- 労働時間を決める
- 転勤・出向・人事異動の有無を明確にする
- 試用期間中の条件を規定する
- 雇用形態が変わる際は条件の変更に注意する
2通作成し、企業と従業員で1通ずつ保管する
雇用契約書は、従業員と企業それぞれが保管できるように2通作成しましょう。内容はまったく同じものを用意します。お互いに契約書に署名したあと、1部ずつ控えを残しておきます。
必要な項目を過不足なく記載する
雇用契約書には、労働にあたって必要な情報を過不足なく記載しましょう。雇用契約書と労働条件通知書を兼ねる場合は、絶対的明示事項と相対的明示事項のいずれも記載する必要があります。
採用条件と相違がないか確認する
雇用契約書の内容が、企業が従業員に対して採用時に提示した条件と相違がないか確認しましょう。労働時間や賃金などが異なっていると、将来的な労務トラブルに発展する可能性があります。
労働時間を決める
勤務するうえで必要な所定労働時間を雇用契約書には記載します。始業時間と終業時間を記載して、労働時間を提示しましょう。
転勤・出向・人事異動の有無を明確にする
正社員などで転勤や出向の可能性があれば「会社の転勤(出向)命令に従う」と雇用契約書に記載しましょう。転勤が予測される地域もあわせて明記しておきます。
試用期間中の条件を規定する
雇用契約書には試用期間中の労働条件を規定しておきます。試用期間の規定は法律上、書面で記載しなければならないものではありません。しかし、雇用契約書などに記載がないと従業員は試用期間がないものと認識する可能性があります。
試用期間がいつまでなのか、本採用と比べて賃金に違いがあるのかなど、本採用と異なる点がある場合は明記するようにしましょう。
雇用形態が変わる際は条件の変更に注意する
「パートから正社員」「正社員からアルバイト」など雇用形態に変更がある場合は、雇用契約書の内容も見直さなければなりません。勤務時間や賃金などさまざまな条件が変化することが多いでしょう。変更箇所に漏れがないか注意を払って雇用契約書を作成します。
雇用契約書の記載事項を変更したい場合
雇用形態や時短勤務への変更など、雇用契約の内容を見直さなければいけないタイミングもあるかもしれません。雇用契約書の記載事項を変更するときは以下の対応が必要です。
- 法的内容の確認をする
- 企業と従業員で合意をとる
- 労働者に不利になる場合は注意する
法的内容の確認をする
変更したい雇用契約書の記載内容が法律違反していないか確認します。労使双方で合意した内容でも、法律に違反しているのであれば無効です。記載内容が法律に則しているか不安があるのであれば、弁護士や社労士などの専門家に確認を依頼しましょう。
企業と従業員で合意をとる
変更した雇用契約書の内容について、企業と従業員の間で合意をとりましょう。従業員の同意もなく、企業が一方的に労働条件を変更すると、労働問題に発展する可能性があります。
変更前に必ず話し合いの場を設けて、なぜ変更するのか、変更点はどこなのかを説明して、合意が取れたあとに変更手続きを進めます。
労働者に不利になる場合は注意する
労働者が不利になる労働条件の変更および、それにともなう雇用契約書の変更には、合理的な理由が必要です。不利な条件は、会社に対して不満を持つきっかけとなり、退職の原因になる可能性も否定できません。
賃金の減額のような明らかに従業員が不利になる変更を進めなければならない事情がある場合は、明確な理由を提示したうえで、必ず同意をとります。合意のない一方的な不利益変更は、労働基準法8条に違反し、従業員から訴訟を起こされる恐れがあります。
雇用契約書は記載事項に沿って記載を(まとめ)
雇用契約書とは、企業側と労働者が合意のうえで締結したことを示す契約書です。企業と労働者の双方を守る役割があります。
雇用契約書に作成義務はないため、企業側が任意で記載項目を選択できます。しかし、労務トラブルを避けるためには作成が推奨されています。
雇用契約書の具体的な記載内容は、労働時間や就業場所、賃金など、労働条件通知書の内容に沿っていることが多いようです。
雇用契約書と労働条件通知書を兼ねる場合は、絶対的記載事項と相対的記載事項にあたる項目を必ず明記しなければなりません。決められた項目を記載しないと、法律違反となり企業が罰則を受ける可能性もあるため、法律に沿って書類を作成しましょう。
雇用契約書を電子化|One人事[労務]
One人事[労務]は、入社にともなう雇用契約書を電子化し、手続きの簡略化を支援する労務管理システムです。
- 【入社手続き】従業員情報の収集が面倒
- 【行政手続き】転記・参照ミスが多い
- 【年末調整】記入漏れ・修正の対応に追われている
という悩みがある担当者の業務効率化を助けて手間を軽減。ペーパーレス化や工数削減、コア業務への注力を支援しております。
One人事[労務]の初期費用や気になる操作性については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門スタッフが、貴社の課題をていねいにお聞きしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、労務管理の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードしていただけます。労務管理をシンプルにして「本来やりたい業務」に集中したい企業は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |
