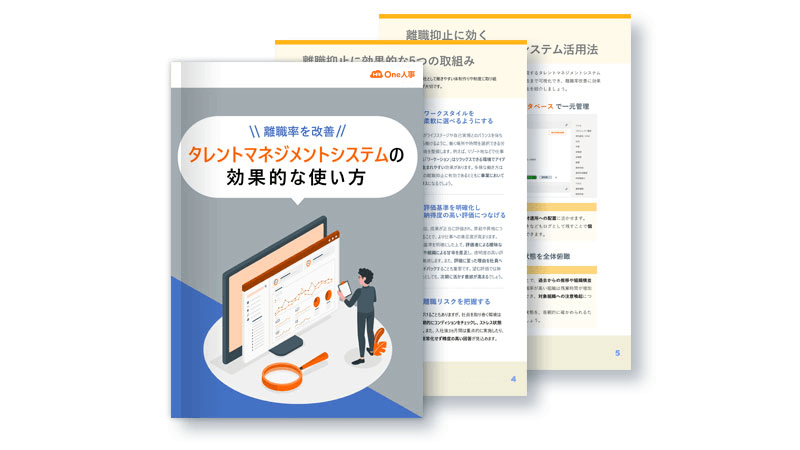休職期間のよくある疑問を徹底解説! 決め方や給与の支払い義務、満了時の対応など

休職期間とは、従業員が病気やケガなどの理由により業務を遂行できない場合に、雇用契約を維持しつつ、「休ませる」または「業務を禁止する」期間です。休職期間は法律で明確に定められていないため、運用に悩むケースも少なくありません。
本記事では、休職期間の決め方や給与の支払い義務、満了時の対応など、休職制度に関するよくある疑問について詳しく解説します。休職に関するトラブルは発生しやすいため、事前に理解を深めておきましょう。
→離職の予兆を察知するには? エンゲージメント向上もサポート「One人事」
 目次[表示]
目次[表示]
休職期間とは
休職期間とは、従業員が業務外の理由で病気やケガをして、業務を遂行できないときに、雇用契約を維持しながら、一定期間仕事を休む制度です。
休職は年次有給休暇とは異なり、会社から従業員に休暇を与えるか、または会社から命じられる方法で適用されます。休職期間中は、業務の遂行が休止または禁止されます。
休職期間の主な種類
休職制度は法律で義務づけられているものではありません。基本的には企業が任意で設ける制度です。ある調査によると、99.7%の企業が休職の規定を設けています。
参照:『私傷病欠勤・休職制度に関する実態調査』労政時報 第4077号(2024年5月10・24日発行)(P.18)
主な休職の種類は以下のとおりです。
| 休職の種類 | 適用対象 |
|---|---|
| 私傷病休職 | 業務や通勤以外の事情による従業員の病気・ケガに適用 |
| 事故欠勤休職 | 勤務外の事故により長期的に欠勤する場合に適用 |
| 自己都合休職 | 家事、ボランティア活動、自己啓発、留学など、個人的な理由に適用 |
| 組合専従休職 | 労働組合員が組合業務に専従する際に適用 |
| 公職就任休職 | 従業員が国会議員、地方議員、都道府県知事などの公職に就任し、通常業務が困難になった場合に適用 |
| 出向休職 | 従業員がグループ会社や関連会社に一時的に出向する際に適用 |
| 起訴休職 | 従業員が起訴され、会社の社会的信用や職場秩序に支障が生じる恐れがある際に適用 |
休職期間の平均は1年程度
休職期間の平均は、一般的に1年程度とされていますが、実際にはさまざまな要因によって変動します。とくに、勤続年数によって休職期間に差が見られる傾向があります。
一般疾病を理由とした、勤続年数別に見る休職期間の分布状況は以下のとおりです。(対象:290社/単位:%)
| 休職期間 | 勤続1年 | 勤続5年 | 勤続10年 | 勤続20年 |
|---|---|---|---|---|
| 3か月未満 | 5.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 3~5か月(うち、3か月) | 13.8(10.3) | 4.1(3.1) | 1.7(1.4) | 1.7(1.4) |
| 6~11か月(うち、6か月) | 30.0(24.5) | 20.7(13.4) | 15.2(12.8) | 14.1(12.8) |
| 12~17か月(うち、12か月) | 29.3(26.2) | 29.3(23.1) | 24.1(19.7) | 20.7(18.3) |
| 18~23か月(うち、18か月) | 10.7(9.3) | 23.4(21.7) | 23.1(20.0) | 23.8(21.7) |
| 24~29カ月(うち、24か月) | 5.9(5.2) | 14.5(12.8) | 23.4(21.0) | 22.1(19.0) |
| 30~35カ月(うち、30か月) | 2.4(1.7) | 3.1(2.4) | 4.5(2.8) | 6.9(5.2) |
| 36か月以上 | 2.8 | 3.8 | 6.9 | 9.7 |
| 平均(か月) | 11.3 | 15.5 | 18.1 | 19.0 |
| 最高(か月) | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 最低(か月) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
出典:『私傷病欠勤・休職制度に関する実態調査』労政時報 第4077号(2024年5月10・24日発行)(P.24)
勤続年数が長くなるほど、休職期間も長い傾向にあることがわかります。
勤続1年の従業員の平均休職期間は11.3か月であるのに対し、勤続20年の従業員は19.0か月と、その差は約7.7か月です。
勤続年数が5年から10年に増えると、休職期間は約2.6か月延び、勤続10年から20年になると、休職期間の延長幅は小さくなり、約0.9か月の増加にとどまっています。
以上から、多くの企業では、長期勤続の従業員に対してより長い回復期間を認める傾向があるようです。
ただし、実際の休職期間は個々の状況や会社の方針によって異なります。また、業種や職種によっても差異が生じるため、一概にすべての企業にあてはまるわけではありません。
休職期間の決め方・判断基準
休職期間を決定するための判断基準として、次の3つの指標があります。
- 医師の診断書
- 勤続年数
- 傷病手当金の支給期間
休職期間の決め方を以下で詳しく解説します。
医師の診断書
従業員が私的な傷病により職務遂行が困難となった場合、休職期間の決定には医療専門家の意見が重要な指針となります。医師の診断書を通じて、休職の具体的な原因や予想される療養期間を把握できます。
近年、メンタルヘルス不調による長期欠勤が増加傾向にあり、その対応には特別な配慮が必要です。このような複雑なケースでは、主治医の診断に加え、職場環境や業務内容に精通した産業医の見解を求めることも有効です。産業医は、従業員の健康状態と職務の適合性を専門的に評価し、復職のタイミングや業務の調整について実践的なアドバイスを提供できます。
勤続年数
休職期間の決定において、従業員の勤続年数を考慮する企業は少なくありません。長期にわたり会社に貢献してきた従業員に、より長い休職期間を認めて配慮をする方針といえます。
雑誌『労政時報』の調査によると、60.3%の企業が勤続年数別に期間を定めています。ただし、企業によっては勤続年数に関係なく、統一的な休職期間を設けることもあります。
休職期間の設定は、解雇回避措置としての側面もあるため、各企業の状況や方針に応じて慎重な決定が必要です。
参照:『私傷病欠勤・休職制度に関する実態調査』労政時報 第4077号(2024年5月10・24日発行)(P.19〜20)
傷病手当金の支給期間
休職期間の決定には、傷病手当金の支給期間を参考にする方法もあります。
業務外の傷病による休職の場合、健康保険から傷病手当金が支給されます。給付には最長1年6か月の期限があるため、この傷病手当金制度に合わせて休職期間を設定することも可能です。
傷病手当金は、従業員の経済的支援と会社の人事管理の整合性をはかるうえで有効な基準であり、多くの企業で採用されています。
傷病手当金を基準とした休職期間の決定方法は、制度的な裏づけがあるため、公平性と合理性を備えた基準といえるでしょう。
休職期間における給与の取り扱い
休職期間中の給与の取り扱いについても、正しく把握しておくことが大切です。休職期間における給与に関して覚えておきたい重要なポイントは次のとおりです。
- 休職期間は給与の支払い義務はない
- 病気やケガによる休職は、傷病手当金が支給される
- 休職期間でも社会保険料は免除されない
休職期間は給与の支払い義務はない
休職制度に法的義務はないため、休職期間中の給与支払いも企業の判断に委ねられます。
2012年の調査によると、18.1%の企業が病気休職中に月給を支給しており、大規模な企業ほど支給する傾向にあります。8割の企業は休職期間中の給与を支給していません。
休職中の給与支払いを、就業規則に規定している場合は、支払い義務が生じるので注意しましょう。
参照:『メンタルヘルス、私傷病などの治療と 職業生活の両立支援に関する調査(P.46)』独立行政法人労働政策研究・研修機構
病気やケガによる休職は、傷病手当金が支給される
病気やケガによる休職では、健康保険から傷病手当金が支給されます。
傷病手当金は、業務外の傷病で働けない被保険者の生活を支援する制度です。連続3日間の待機期間を経て、4日目以降の就労不能日に対して支給されます。
傷病手当金の金額は、1日につき標準報酬日額(直近12か月の標準報酬月額の平均÷30)の3分の2相当額で、期間は最長1年6カ月までです。支給には一定の条件があり、休んでいる期間の給与支払いがないことが求められます。
休職期間でも社会保険料は免除されない
休職期間中であっても、健康保険料と厚生年金保険料は免除制度がなく、支払い義務が継続します。社会保険料が直近の標準報酬月額を基準に算出されるためです。
休職により給与が支給されていなくても、以前の標準報酬月額に基づいて保険料が課されるため、従業員も企業も理解しておきましょう。
休職期間が満了したときの対応
休職期間の満了が近づいてきたら、企業は従業員に連絡します。休職期間満了時には、さまざまな対応方法が考えられ、以下の基本的な3つの方針を理解しておきましょう。
- 復職を支援する
- 休職期間を延長する
- 退職または解雇を検討する
復職を支援する
休職期間を経て従業員の健康状態が回復し、職場復帰が可能であれば、スムーズな復職を支援します。復職支援の対応として、「リハビリ出社」や「リハビリ勤務」があります。
復職支援のリハビリ制度について
「リハビリ出社」は、一般疾病による休職者には46.9%、メンタルヘルス疾患による休職者には50.7%の企業が導入しています。リハビリ出社とは、従業員が職場に来て、実際の業務は行わず、環境に慣れる機会を提供する制度です。
「リハビリ勤務」は、リハビリ出社より多くの企業で採用されています。一般疾病の休職には68.8%、メンタルヘルス疾患には71.4%の企業が認めています。リハビリ勤務制度は、従業員が軽減された業務や時短勤務で、徐々に仕事へ復帰する方法です。
参照:『私傷病欠勤・休職制度に関する実態調査』労政時報 第4077号(2024年5月10・24日発行)(P.30〜33)
試し出勤の例は以下のとおりです。
| 「試し出勤制度」等の例 | |
|---|---|
| 模擬出勤 | ・勤務時間と同様の時間帯に模擬的な軽作業を行う ・図書館などで時間を過ごす |
| 通勤訓練 | ・自宅から勤務職場の近くまで通勤経路で移動し、付近で一定時間を過ごしたあとに帰宅する |
| 試し出勤 | ・職場復帰の判断を目的として、試験的に本来の職場などに一定期間継続して出勤する |
出典:『改定 心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き』厚生労働省 中央労働災害防止協会(p.6)
休職期間後のリハビリ制度は、従業員が無理なく職場に戻れるように支援し、再度の休職リスクを軽減する効果があります。企業にとっても、従業員の状態を見極めつつ、適切な業務配分を検討できるため、スムーズな職場復帰を支援する手段といえるでしょう。
休職期間を延長する
従業員の回復にさらに時間が必要と判断された場合、就業規則の範囲内で休職期間の延長を検討することが可能です。ただし、延長の判断は慎重に実施する必要があります。
延長を認めない方がよい場合
休職期間を経ても従業員の回復の見込みが立たないのであれば、満了期日以上の休職は、双方にとって有益とはいえないでしょう。とくにメンタルヘルス不調による休職の場合、回復に有する期間を想定しにくい傾向があります。従業員から休職期間延長の申し出があった場合、慎重に検討しましょう。
延長を認めてもよい場合
病気やケガによる休職で、近い将来の復職が見込まれるなら、休職期間の延長を認めてもよいと判断できます。たとえば、医師から「あと1か月ほどの加療で復帰が可能」といった診断がある場合です。
ただし、延長を認める際は、診断書の提出などで判断基準を明確にすることが大切です。
退職または解雇を検討する
休職期間満了時に復職が困難な場合、退職または解雇の検討も必要です。退職(自己都合退職)や解雇の手続きは、就業規則の規定に沿って進められます。休職期間満了時の対応についても、あらかじめ就業規則に明確に定めておきましょう。
ただし、業務上の疾病による休職の場合、療養期間中やその後30日間に退職や解雇を促すことは、労働基準法違反です。企業は個別のケースを慎重に評価し、法的リスクを考慮して公正な判断を下す必要があるといえます。
休職期間のトラブルを避けるためには?
休職期間満了とともに退職や解雇を検討する場合、従業員と企業間でトラブルが発生する可能性も否定できません。トラブル防止のために、おさえておきたいポイントを紹介するので、リスク回避にお役立てください。
- 不当解雇にあたらないようにする
- 就業規則にしたがって退職・解雇を通知する
- 退職金を正しく支払う
- 退職後はすぐに雇用保険の手続きをする
不当解雇にあたらないようにする
休職期間満了後の解雇が不当なものにならないよう、適切な手続きを踏むことが重要です。次の例は不当解雇とみなされる可能性が高いため注意しましょう。
| 不当解雇にあたる例 |
|---|
| ・セクハラやパワハラ、長時間労働、退職の強要などによるメンタルヘルス疾患が原因の場合 ・医師が復職可能と診断したにもかかわらず、会社が認めずに解雇した場合 ・休職発令をせず、いつから休職扱いとしたのか不明なまま解雇した場合 |
不当解雇と判断されると、退職後に未払いの賃金を請求されることがあります。とくに、不当解雇の期間が長くなると、支払うべき給与の総額が高額になるリスクがあります。
トラブルを避けるためには、従業員に対して明確な形式で休職を命じることが重要です。また、休職期間中の状況や復職の可能性について定期的に確認し、記録を残すとよいでしょう。
就業規則にしたがって退職・解雇を通知する
休職期間満了後に退職または解雇を決定するときは、就業規則に基づいた適切な通知手続が必要です。従業員に送付する退職通知書または解雇通知書には、以下の内容を明記するとよいでしょう。
- 休職期間満了日
- 適用される就業規則の規定
- 退職日または解雇日
解雇には30日前までの通知が必要で、通知できない場合は、解雇予告手当の支払いが求められます。
退職通知書類の発行には法的な義務はありませんが、トラブルを防ぐために送付するとよいでしょう。確実に通知する方法として、内容証明郵便の利用が挙げられます。
退職金を正しく支払う
退職金の取り扱いは、法律による規定がないため、各企業の裁量に委ねられています。支給の有無や金額の算出方法は、会社ごとに独自の基準を設けることが可能です。
一方、就業規則に退職金に関する規定を設ける場合、労働基準法で支払い時期を明確に定めることが義務づけられています。退職金に関する就業規則には次の項目を明記しましょう。
- 休職期間が勤続年数に算入されるかどうか
- 退職金の具体的な支払い時期
- 退職金の計算方法
退職後はすぐに雇用保険の手続きをする
従業員が退職したら、すみやかに雇用保険の喪失手続きを進めます。手続きが遅れると、退職した従業員が失業給付をスムーズに受け取れなくなる可能性があります。
退職が決まったらすぐに対応できるよう、雇用保険手続きの流れを理解しておくことが大切です。
雇用保険の手続きは単なる事務作業ではなく、従業員が次のステップに進む支援をする目的もあります。迅速に対応し、退職者の将来に寄り添う姿勢を示しましょう。
まとめ
休職期間は、従業員が業務外の理由で働けないときに、雇用を維持しながら一定期間休ませる制度です。平均期間は1年程度であり、勤続年数が長いほど長期化する傾向があります。
休職期間中の給与支払い義務はありませんが、傷病手当金などの公的制度が適用される場合があります。
休職期間満了時の対応としては、復職支援、期間延長、退職・解雇の検討という3つが考えられます。延長は近い将来の復帰が見込まれる従業員に対して検討するとよいでしょう。
将来のトラブルを防ぐためには、就業規則に基づいて、休職開始から復帰までの対応を慎重に進める必要があります。休職の発令や期間の管理、復職・退職手続きなどを明確に定め、従業員と適切にコミュニケーションをとることが重要です。