特定扶養控除とは? 適用要件や控除額、令和7年度税制改正での変更点を解説
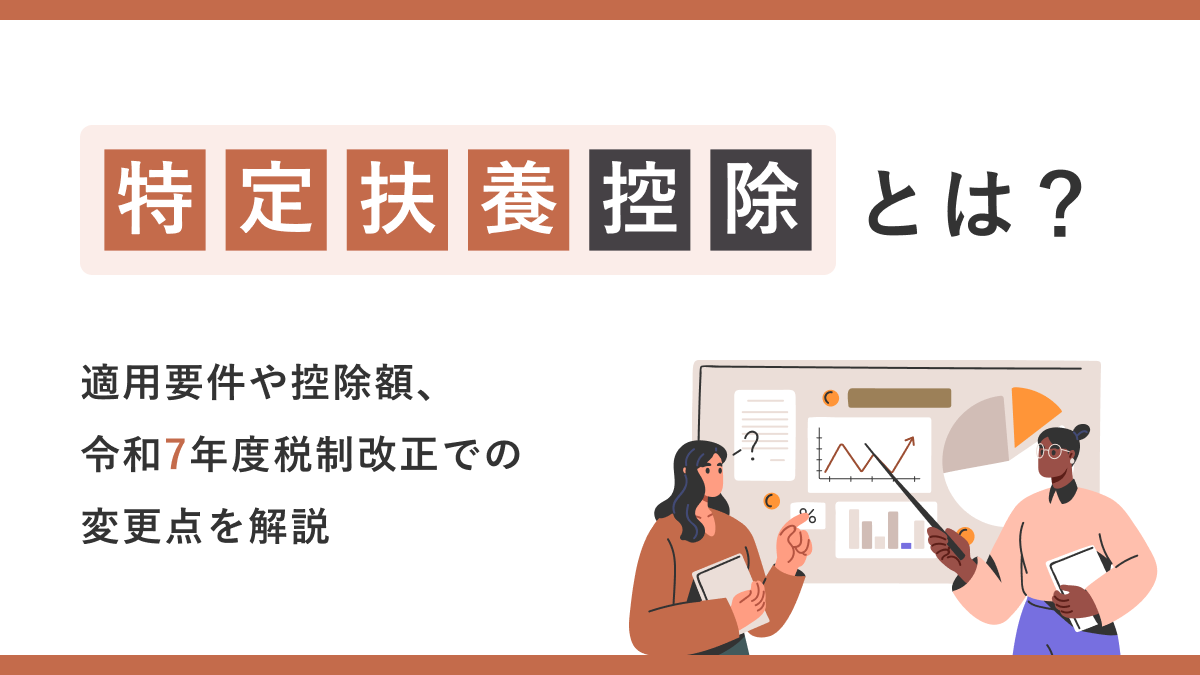
特定扶養控除は、19歳以上23歳未満の扶養親族に適用される所得控除です。制度をよく理解していないと、年末調整で従業員からの問い合わせ対応に時間をとられ、余計な手間が増えてしまうかもしれません。
また、特定扶養控除は、令和7年度税制改正で重要な変更点があるため、十分な注意が必要です。
本記事では、特定扶養控除の適用要件や控除額、節税額の計算方法などについて解説します。2025年改正後に必要となる実務対応にも触れるので、年末調整の担当者はぜひご一読ください。

 目次[表示]
目次[表示]
特定扶養控除とは?
特定扶養控除とは、年末調整で適用される所得控除の一種です。所得控除が適用されると、税金の計算において所得から一定額が差し引かれ、所得税や住民税などの税負担が軽減されます。
納税者(従業員)に所得税法上の控除対象扶養親族がいる場合、従業員は「扶養控除」という所得控除を受けられます。
扶養控除のうち、その年の12月31日時点で年齢が19歳以上23歳未満の扶養親族に関する控除が、特定扶養控除です。
扶養親族にはほかにも複数の区分があり、扶養親族の年齢、同居の有無などによってそれぞれ要件が定められています。
| 控除対象扶養親族 | 扶養親族のうち、その年の12月31日時点で年齢が16歳以上の人 | ||
| 特定扶養親族 | 控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点で年齢が19歳以上23歳未満の人 | ||
| 老人扶養親族 | 控除対象扶養親族のうち、その年の12月31日時点で年齢が70歳以上の人 | 同居老親等 | 老人扶養親族のうち、納税者や配偶者の直系尊属(父母、祖父母など)であり、納税者や配偶者との同居を常としている人 |
| 同居老親等以外の者 | 老人扶養親族のうち、同居老親等の要件を満たさない人 | ||
参照:『No.1180 扶養控除』国税庁
参照:『専門用語集』国税庁

特定扶養控除に関する年齢以外の要件
特定扶養親族となるためには年齢以外に、扶養控除の基本的な要件を満たす必要があります。
- 配偶者以外の親族
- 年間合計所得金額が58万円以下
- 納税者と生計を一としている
- 納税者が事業を行っている場合、青色申告の事業専従者として1年を通じて一度も給与の支払いを受けていない、あるいは白色申告の事業専従者でない
従来、扶養親族の所得要件は「48万円以下」でしたが、令和7年(2025年)の税制改正により「58万円以下」に変更となりました。詳しくは後述しますが、所得税の基礎控除の見直しが大きくかかわっています。
また、従来は給与所得控除の55万円と合算して「48万円+55万円=103万円」が年収の壁とされていましたが、税制改正により壁の基準となる金額も見直されます。
特定扶養控除の金額
特定扶養控除の控除額は、一律63万円です。そのほかの区分も控除額が一律で定められており、以下のような違いがあります。
| 控除対象扶養親族 | 38万円 | |
| 特定扶養親族 | 63万円 | |
| 老人扶養親族 | 同居老親等 | 58万円 |
| 同居老親等以外の人 | 48万円 | |
特定扶養控除と年少扶養控除の違い
年少扶養控除は、その年の12月31日時点で0~15歳の親族を扶養する納税者に適用される制度です。同じ扶養控除の枠組みですが、特定扶養控除とは年齢要件が異なります。
年少扶養控除はかつて存在した制度であり、現在は廃止されています。
令和7年度(2025年度)の特定扶養控除に関する改正ポイント
令和7年度(2025年度)の税制改正では、特定扶養控除について大きな見直しが入ります。今回の改正ポイントは次の2つです。
- 特定扶養親族の年収要件が引き上げられる
- 特定親族特別控除が創設される
今まで「103万円の壁」と呼ばれていた基準が変わり、従業員からの問い合わせが増えることが予想されます。とくに大学生の子どもを扶養に入れている従業員に配慮が必要でしょう。
特定扶養控除に影響する改正点を具体的に紹介していきます。
特定扶養親族の年収要件が引き上げられる
扶養親族等の所得要件の最低ラインが58万円になるのにともない、特定扶養親族の年間合計所得金額の要件も48万円から58万円に変更されます。
また、税制改正では、給与所得控除の最低保障額も55万円から65万円に引き上げられます。
つまり、19歳以上23歳未満の扶養親族の年収(給与所得のみの場合)が58万円+65万円=123万円までであれば、特定扶養控除を適用することが可能です。
参照:『令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について』国税庁
特定親族特別控除が創設される
税制改正では、新たに「特定親族特別控除」という制度が創設されます。特定親族特別控除とは、19歳以上23歳未満の扶養親族の合計所得金額が58万円超の場合でも、所得金額に応じて段階的に控除を受けられる制度です。
次の表は、合計所得金額ごとの控除額です。
| 特定扶養親族の合計所得金額 | 控除額 |
| 58万円超85万円以下 | 63万円 |
| 85万円超90万円以下 | 61万円 |
| 90万円超95万円以下 | 51万円 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 |
出典:『令和7年度税制改正(基礎控除の見直し等関係)Q&A』国税庁
特定扶養親族の合計所得金額が85万円(給与所得のみの場合は年収150万円)までであれば、特定親族特別控除の金額は特定扶養控除と同じです。
そのため、年収の壁は実質的に「123万円」ではなく「150万円」といえます。
特定扶養控除による節税額の計算例
特定扶養控除は、所得税だけでなく住民税にも影響します。実際にどれくらい税額が軽減されるのか把握したい方もいるでしょう。
特定扶養控除による節税額を、具体的な計算例を使って確認してみましょう。
所得税+復興特別所得税
所得控除が適用される場合、所得税額はおおまかに次の式で計算します。
| (合計所得金額-所得控除額)×所得税率 |
所得控除額に所得税率を掛け算すれば、所得控除による節税額を計算することが可能です。
特定扶養控除額は63万円です。たとえば納税者に課せられる所得税+復興特別所得税率が20.420%の場合、控除による節税額は以下のとおりです。
| 63万円×20.420%=12万8,646円 |
特定扶養控除を適用するだけで、年間約13万円の節税効果がある計算になります。
住民税
特定扶養控除は所得税だけでなく、住民税にも適用されます。
住民税における特定扶養控除額は、45万円です。住民税の税率は一律10%なので、計算はシンプルです。
| 45万円×10%=4万5,000円 |
所得税と住民税をあわせると、年間で約17万円超の税負担軽減につながります。
特定扶養控除の手続きにおける注意点
従業員の特定扶養控除の手続きについて、担当者は以下の5点に注意する必要があります。
- 申告年度の12月31日時点での年齢を基準とする
- 共働きの場合はどちらか一方にのみ適用される
- 生計を一にしている必要がある
- 配偶者は特定扶養親族にはなれない
- 改正内容を社内に周知する
年末調整では、控除の対象者について従業員から質問されることがあります。特定扶養控除の注意点を理解していないと、すぐに答えられず手続きが滞ってしまうかもしれません。
とくに年齢の基準日や共働き世帯での扱いは、迷いがちなポイントです。特定扶養控除の5つの注意点について、一つずつ確認していきましょう。
申告年度の12月31日時点での年齢を基準とする
特定扶養親族の年齢要件は、申告年度の12月31日時点での年齢を基準とします。
たとえば、子どもが2025年12月31日に19歳を迎える場合、特定扶養控除が適用されるのは2025年の確定申告からです。
一方、子どもが2026年1月1日に19歳を迎える場合は、2026年の確定申告から適用されます。
早生まれ(1月~3月生まれ)の子どもは、4月〜12月生まれの子どもとは適用される年度が異なるため注意が必要です。
子どもが大学生であれば、1年生のときは一般の控除対象扶養親族の控除が適用されます。
共働きの場合はどちらか一方にのみ適用される
特定扶養控除は、同じ親族について、複数の納税者が重複して控除することはできません。親族1人につき、控除が適用されるのは納税者1人だけです。
たとえば共働きの夫婦に19歳の大学生の子どもがいる場合、夫が年末調整で特定扶養控除を適用したら、妻は同じ子を対象に控除を申請できません。
もし両方で申告してしまうと、あとから税務署の指摘を受け、修正や返金が必要になります。
生計を一にしている必要がある
特定扶養控除を適用するには、対象となる親族が納税者と「生計を一にしている」必要があります。生計を一にするとは、同居しているかどうかではなく、生活費や学費などの大部分を納税者が負担している状態です。
たとえば、子どもが実家を離れて一人暮らしをしていても、親から仕送りを受けて生活しているなら同一生計とみなされます。反対に子どもが高校卒業後に就職して、自活している場合は、同居していても控除の対象外です。
配偶者は特定扶養親族にはなれない
特定扶養控除を含め、扶養控除は配偶者以外の親族を対象とした制度です。誤解してしまう人もいるため注意しましょう。
一定の要件を満たす配偶者を扶養している場合は、「配偶者控除」もしくは「配偶者特別控除」を利用します。
担当者は、扶養控除と配偶者控除の違いを正しく説明できるようにしておかなければなりません。
改正内容を社内に周知する
令和7年度(2025年度)の税制改正により特定扶養控除の要件が変わることで、新たに控除が適用される従業員もいるでしょう。
また、今後も税制改正により要件が変更される可能性も考えられます。担当者は常に最新の情報をチェックし、社内に周知することが大切です。
新制度に関する資料を配布したり、FAQを整備したりして、従業員が制度を適切に利用できるよう支援しましょう。
税制改正について企業の対応が必要なのはいつから?
令和7年度(2025年度)の税制改正は2025年12月1日に施行され、2025年分以後の所得税に対して適用されます。
税制改正について企業の対応が必要になるのは、2025年12月に行う年末調整などの源泉徴収事務からです。
2025年11月までの源泉徴収事務に変更はありませんが、施行後にスムーズに対応できるよう、早めの準備が肝心です。
参照:『令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について』国税庁
まとめ|特定扶養控除の改正内容を把握
特定扶養控除とは、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の扶養親族を有する人に適用される所得控除です。
令和7年度(2025年度)の税制改正により、扶養親族の年収要件は年間合計所得金額48万円から58万円に変更されます。新たに特定親族特別控除も創設され、58万円を超える場合でも段階的に控除を受けられるようになりました。
担当者は常に最新の情報をチェックするとともに、従業員からの問い合わせに答えられるよう、制度について理解することが大切です。
特定扶養控除をはじめとする税制度は、今後も改正される可能性があります。税制改正後の実務にもスムーズに対応できるよう、自社に適した給与計算システムへの見直しも検討してみましょう。
多くの給与計算システムは、最低限の対応で手間なく、法改正にあわせた実務への移行を助けます。度重なる改正に迅速に対応できる社内体制を整えたいなら、給与計算システムを活用してミスに備えましょう。
年末調整の控除計算をミスなく|One人事[給与]
One人事[給与]は、ミスができない年末調整の計算をはじめ、給与計算の自動化を助けるクラウド給与計算システムです。
One人事[労務]との連携により、書類の回収から一貫してシステム上で完結できます。制度改正にもスムーズに対応でき、繁忙期の担当者の負担を減らせるでしょう。
One人事[給与]の初期費用や気になる操作性については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門スタッフが、貴社の課題をていねいにお聞きしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、給与計算をはじめ労務管理の効率化のヒントになるお役立ち資料を、無料でダウンロードいただけます。ぜひお気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |
