年末調整の提出は翌年1月まで! スケジュールについてわかりやすく解説
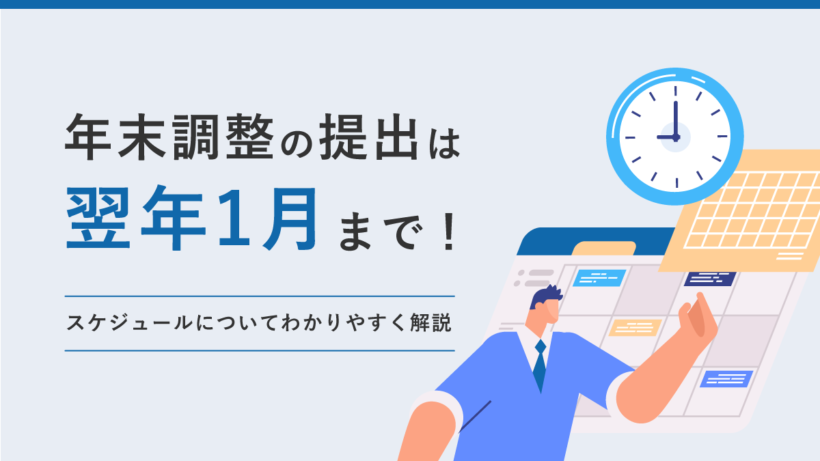
年末調整は1月になっても問題ないのでしょうか。年末調整は年内に終えるイメージを持たれている方もいますよね。給与の支払いがずれたり、書類の提出が遅れたりして1月に手続きがずれ込むと、不安に感じられるでしょう。
年末調整に関する書類の提出期限や税金の納付期限は、翌年1月末です。処理自体も1月に行って問題ないケースがあります。とはいえ、どこまでが1月でも間に合うのかを理解しておくことが大切です。
本記事では、「年末調整が1月にずれ込んだ場合の対応」「還付や追加徴収のスケジュール」「修正対応が可能な期限」など、1月に年末調整をする際におさえておきたいポイントを解説します。
→年末調整を効率化「One人事」の資料を無料ダウンロード

 目次[表示]
目次[表示]
年末調整とは
年末調整とは、給与所得者の源泉徴収された所得税と、1年間の実際の所得に基づく所得税額との差額を精算する手続きです。
企業は、従業員の給与や賞与から概算の所得税を天引きし国に納付していますが、この金額は正確な税額とは異なります。そこで、年末に各種控除を反映して正確な税額を算出し、差額があれば還付または追加徴収を行います。
年末調整は会社が行う義務を負っている
年末調整は、所得税法で給与支払い者である雇用主に義務づけられた手続きです。給与や賞与から所得税を源泉徴収する企業は、年末に税額を正しく精算する必要があります。
企業が年末調整を実施しなければ、源泉徴収した所得税と実際に支払うべき所得税に差異があったとしても還付されません。手続きを誤ると、法令違反として次のような処罰の対象となるため、注意しましょう。
| 年末調整をせずに従業員から正しい税額を徴収しなかった | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
| 年末調整をしたものの従業員から徴収した追加の徴収額を納付しなかった | 10年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、またはその両方 |
参照:『第1 源泉徴収制度の概要』国税庁
参照:『所得税法』e-Gov法令検索

11月〜1月までの年末調整の簡易スケジュール
年末調整の手続きは、多くの企業において10月下旬〜11月上旬から書類の回収作業がスタートします。そして税務署や市区町村への申告書類の申請期限である翌年1月下旬まで続きます。
具体的には、次のような流れです。
| 11月 | 12月 | 1月 | |
|---|---|---|---|
| 従業員による申告 | 年末調整の計算 | 提出書類の作成・提出 | |
| 労務担当者 | ・申告書の配布/回収/チェック | ・年末調整の計算 ・源泉徴収票の作成 ・所得税の過不足分の還付または追加徴収 | ・源泉所得税の納付 ・税務署への年末調整関係書類の作成/提出 ・自治体への住民税関係書類の作成/提出 ・年末調整関連書類の作成/保存 |
| 従業員 | ・必要書類の記入/提出 ・添付書類の提出 | ・なし | ・なし |
とくに年末は賞与の計算など、さまざまな業務が集中する時期です。並行して対応できるように、余裕を持ったスケジュールを立てなくてはなりません。
▼年末調整業務の進め方に不安がある方は、次の資料もぜひご活用ください。
11月
多くの企業では年末調整に必要な書類を11月中、遅くとも12月上旬までに提出するように呼びかけています。
企業は従業員一人ひとりに対して申告書を配布し、必要事項を記入してもらい、税額を計算するために必要な情報を収集します。控除証明書のような添付書類も準備してもらわなければなりません。
回収できたら、記載に不備や誤りがないかを確認し、必要に応じて修正・訂正を依頼しましょう。万が一、内容に誤りがあると、やり直しとなり、各機関への提出期限を守れなくなるため、早めに社内締切を設定したいところです。
▼回収書類のチェックに時間を取られていませんか。回収作業の手間を減らすなら年末調整の電子化がおすすめです。書類の一括チェック機能があるため、紙を目視で確認するよりもラクに確認を完了できます。
→年末調整の回収・確認作業をラクにする|One人事[労務]の特長

12月
必要書類がそろったら、12月は各種控除を反映した所得税の合計額を計算します。もし過不足があった場合は、12月の給与明細・賞与明細もしくは個別の明細書で過不足税額を還付または徴収します。
1月
1月は源泉徴収票を発行して従業員に配布し、法定調書に取りまとめます。翌年1月31日までに所轄の税務署へ法定調書を提出し、所得税を納付すれば、年末調整手続きはすべて完了です。
年末調整の法定調書提出は1月まで
年末調整における法定調書の提出期限は、法律で翌年の1月31日と定められています。記入漏れや訂正があっても、1月31日までに提出すれば法的な問題はありません。
企業が管轄する税務署、従業員が居住する市区町村に対して、提出しなければならない調書類は以下のとおりです。
| 税務署 | 市区町村 |
|---|---|
| ・支払調書(提出が必要な支払いがあった場合) ・源泉徴収票 ・法定調書合計表 | ・給与支払報告書(総括表・個⼈別明細書) |
正しく年末調整の手続きがされないと、企業も従業員も処罰の対象となるケースが考えられます。提出期限は厳守しなければなりません。
提出が遅れた場合の対応方法
従業員それぞれの事情により年末調整の必要書類の提出が遅れてしまうことも考えられますよね。たとえば、生命保険料や地震保険料の控除証明書を紛失してしまうケースです。そのときは、どのように対処したらよいのでしょうか。
社内締切を過ぎても、人事労務担当者が翌年1月31日までに法定調書を税務署に提出できれば問題はありません。
ただし、年末調整の時期は証明書の再発行申請が集中するため、手続きの遅れによって間に合わないリスクもあります。従業員の提出が遅れた場合、本人が確定申告で控除を申請する必要があります。
確定申告の申告期間は、例年2月16日から3月15日(土日の場合は翌月曜日)です。企業は、対象となる従業員に向けて確定申告が必要なことを周知し、適切にフォローしましょう。

翌年1月までであれば修正可能
従業員が申告書を提出したあとに記載内容の訂正や修正が必要になった場合でも、原則として翌年1月31日までは企業側で修正が可能です。
しかし、次の場合は企業では対応できず、従業員がみずから確定申告をする必要があります。
- 源泉徴収票を発行したあと
- 2月1日以降に修正が判明した場合
企業側は翌年1月10日(納期の特例適用事業者は1月20日)までに年末調整で確定した源泉徴収税額を納付する義務があるため、源泉徴収票は1月10日より前に発行されることが一般的です。つまり、企業による修正ができるのは「1月31日まで」でも、実際の運用ではもっと早い対応が必要になります。
年末調整をスムーズに完了させるためにも、修正の必要がある場合は、すみやかに担当部署へ相談するよう従業員に促しましょう。
年末調整の還付・追加徴収のスケジュール
年末調整が完了すると、還付金の支払いや追加徴収の対応が実施されます。それぞれの時期について解説していきましょう。
還付の時期
年末調整による還付金は、多くの企業で12月の給与支給日にまとめて支払われます。当年に支給した給与や賞与の精算を年内に終わらせようと考える企業が多いためです。
ただし、年末の繁忙期を避けたい場合や、共働きの配偶者の所得が確定していない場合など、事情によっては1月下旬に還付する企業もあります。
追加徴収の時期
追加徴収が発生する場合は、年末調整後の最初の給与支給時にまとめて差し引かれます。源泉徴収された所得税額が本来の税額より少なかったときに発生するのが追加徴収です。
追加徴収が発生する主なケースは、次のとおりです。
- 賞与が高額だった
- 扶養家族が減った
- 給与所得以外の副業を申告した
- 譲渡所得や一時所得などを申告した
- 年末調整で受けた控除に誤りがあった
あらかじめ追加徴収のパターンを把握しておくと、効率的に計算処理を進められるでしょう。
【ケース別】年末調整のスケジュールを確認
ここまで、年末調整の基本的なスケジュールを踏まえ、1月中であれば修正対応が可能かについて解説してきました。
年末調整の流れはある程度決まっていますが、年末の入退社や海外勤務の社員には、対応が一部異なります。以下ではケース別の年末調整の進め方や注意点を確認しておきましょう。
12月に入社した場合
12月に入社した従業員の年末調整は、12月中に給与が発生しているかどうかで対応が分かれます。
12月中に給与が支払われる場合は、年末調整の対象となるため、必要な書類を短期間で提出してもらう必要があります。前職がある場合は、前職の源泉徴収票の提出も忘れずに依頼しましょう。
12月分の給与を翌年1月に支払う場合は、12月中に給与が支払われないため、年末調整の対象にはなりません。
12月に退職した場合
12月に退職した従業員の年末調整は、転職先で給与をいつ受け取るかによって異なります。
転職先で年内に給与を受け取る場合は、転職先で年末調整の対象となります。
年内に給与を受け取らない場合、前職で年末調整は行われず、本人による確定申告が必要です。保険料控除などの手続きをする際は、退職時に発行された源泉徴収票を使用します。
退職時にすでに年末調整が済んでおり、追加の精算が不要な場合は、対応は不要です。
海外で勤務している場合
海外支店や現地法人で勤務している従業員も、日本居住者であれば所得税の課税対象となり、年末調整が必要です。
給与の計算期間中に海外に勤務していても、給与の支払時点で日本に居住していれば、給与は課税対象となります。たとえば、査定期間が海外勤務中であっても、実際の振込が日本滞在中であれば、年末調整の対象です。

年末調整の還付金の受け取り方法
年末調整が終わって、気になるのは「還付金はいつ・どうやって受け取れるのか」という点ではないでしょうか。
還付金の支払い方法については、法律によって明確な規定がありません。企業ごとの運用に任せられています。
以下では、多くの企業で採用されている代表的な還付方法を紹介します。
給与に反映
還付金が給与と一緒に支払われるのが一般的です。多くの企業では給与が口座に振り込まれ、還付金も同じタイミング・同じ口座にまとめて振り込まれます。給与と別に振り込んでしまうと、手数料がかかるため、実務ではまとめて処理するほうが効率的です。
手渡し
給与を手渡しで支給している企業では、年末調整の還付金も同様に手渡しされることがあります。また、給与支給は振込でも、還付金のみ手渡しにしたり、従業員の希望に応じて振込と手渡しを使い分けたりするケースもあるようです。
まとめ
年末調整は期限が決まっており、年末から1月にかけて多くの業務が集中するなかで、担当者にとって大きな負担となりがちです。
税務署や自治体への提出期限は翌年1月31日までとされており、年末調整の処理や修正も多くの場合1月中なら対応が可能です。
還付や追加徴収のスケジュールも見越しながら、計画的に対応すれば、1月に手続きがずれ込んでも大きく心配する必要はありません。
本記事で紹介したポイントをおさえ、1月対応でも安心して処理できる体制を整えておきましょう。
年末調整を効率化|One人事[労務]
年末調整の手続きは、とても煩雑で工数のかかる業務です。担当者の負担も大きく、人的ミスが発生しやすいのが現状ですよね。ミスなくスムーズに進めるには、業務の電子化も検討してみてはいかがでしょうか。
One人事[労務]は、書類の回収から申請までの過程を半自動化し、効率的な年末調整を支援する労務管理システムです。修正の差し戻しや進捗状況の把握も簡単な操作で実施できます。
One人事[給与]との連携により還付金の計算もスムーズに進められます。
One人事[労務]の機能や操作性は、こちらの資料でもご確認いただけます。さらに詳細を知りたい場合は、当サイトよりお気軽にご相談ください。専門スタッフが課題をお聞きしたうえでご案内いたします。
また、当サイトでは労務管理の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードしていただけます。労務管理をシンプルにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |

