年末調整の市区町村長欄とは? 正しい記入方法を解説
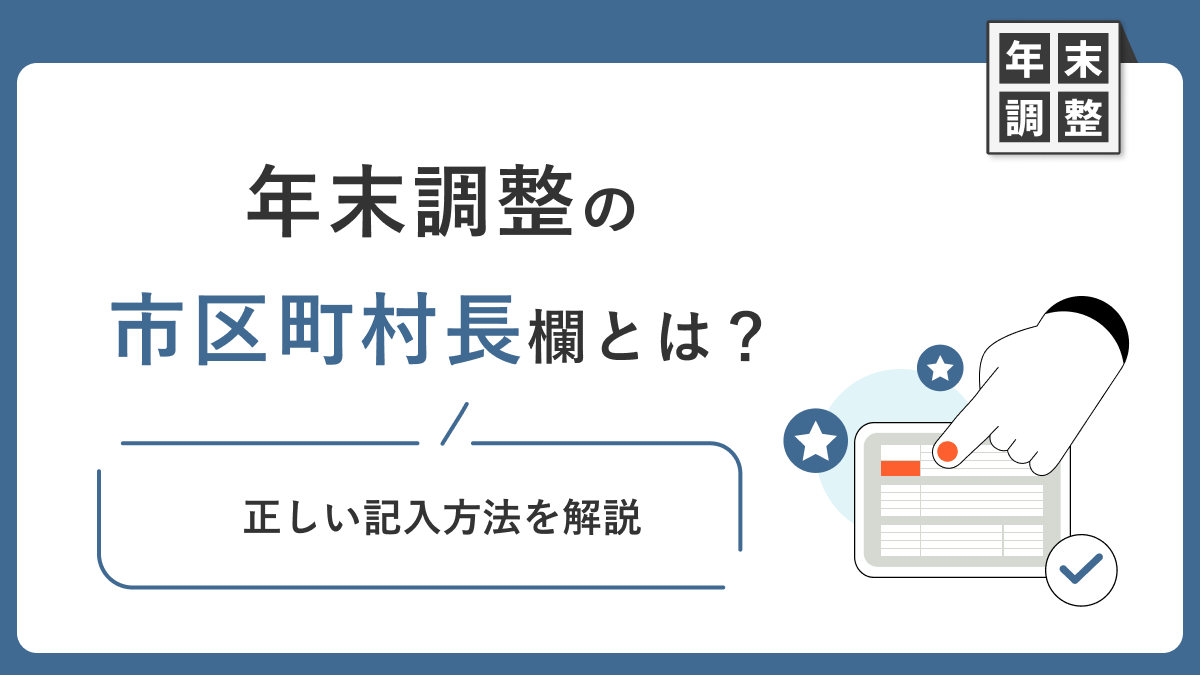
年末調整の書類にある「所轄市区町村長」の欄には、何を書けばよいのでしょうか。「税務署長」欄は会社の所在地ですが、とくに従業員が年内に転居した場合、「どこの住所か」と悩む方もいるかもしれません。
本記事では、年末調整書類における市区町村長欄の基本的な書き方から、転居・単身赴任などの特殊なケースまで、最低限おさえておきたい実務ポイントを紹介します。

 目次[表示]
目次[表示]
年末調整書類の所轄市区町村長とは?
年末調整書類に記載する「所轄市区町村長」欄には、従業員の住所地の市区町村名を記入します。たとえば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にも、「所轄税務署長等」欄の中に「所轄市区町村長」欄が設けられています。
記入内容は、個人住民税の納付先を決めるために重要です。誤って記入すると、誤った自治体へ納付されるおそれがあるため、現住所を必ず最新情報で把握しなければなりません。
市区町村長の定義と役割
「所轄市区町村長」とは、従業員が居住する自治体の長を指します。つまり、個人住民税の納税先となる市区町村を示す欄です。
注意したいのは「人名」ではなく「市区町村名」を記入する点です。たとえば住所が「東京都渋谷区」なら「渋谷」、「東京都八王子市」なら「八王子」と書きます。「市」や「区」は省略して構いません。
「所轄市区町村長」欄が設けられているのは、年末調整が所得税だけでなく、住民税の申告も兼ねているためです。 個人住民税は前年の所得をもとに課税される地方税で、「都道府県民税」と「市町村民税」で構成されています。
会社員は毎月の給与から天引きされる「特別徴収」により納税するため、正しい納付先を記載する必要があります。
税務署長との違い
年末調整の書類には「所轄税務署長」と「所轄市区町村長」の両方がありますが、目的が異なります。
| 所轄税務署長欄 | 所得税の納税地 | 企業の本店または主たる事務所を管轄する税務署名を記入 |
| 所轄市区町村長欄 | 住民税の納税地 | 従業員が1月1日時点で住民票を置いている市区町村名を記入 |
所得税は国に納める国税、住民税は自治体に納める地方税という違いです。年末調整では両方の情報を記載することで、国と地方の双方の税務処理を正確に行えるようになっています。
年末調整における市区町村長欄には翌1月1日時点の住所を書く
年末調整書類の「所轄市区町村長」欄には、翌年1月1日時点での居住地の市区町村名を記入します。
年末調整の時点での住所ではなく、1月1日時点で実際に住んでいる、または住む予定の住所をもとに記載するのがポイントです。
たとえば、2024年度12月に行う年末調整書類には、2025年1月1日時点の居住地が記載されます。
住民税は「1月1日の住所地」に基づいて課税されるため、実際にはまだ住んでいなくても1月1日の実態というのが判定基準となるのです。
11〜12月に引越しの予定がある従業員がいる場合は、転居後の予定住所を必ず確認しておきましょう。
すでに引っ越しを終えて住民票が移されている場合は、新住所を記入すれば問題ありません。 旧住所のまま記入すると、納付先の自治体が誤ってしまうため注意が必要です。
住民票と実際の居住地が異なる場合の対応
住民票の住所と実際の居住地が異なる場合は、生活の本拠地を優先して、年末調整の書類に記載します。生活の本拠地とは、実際に生活の中心を置いている場所のことです。
たとえば単身赴任や長期出張で、住民票を残したまま別の場所に暮らしている場合、実際に生活している市区町村が納税先です。実家に住民票を置いたまま一人暮らししているケースも同様で、年末調整書類には一人暮らし先の市区町村名を記入します。
なお、実際の居住地を記入すると、市区町村から企業へ確認の連絡が入る場合があります。住民票の所在地と異なるため、確認のための照会が行われることがあるというだけで、問題ではありません。

年末調整における市区町村長欄の書き方・具体例
「所轄市区町村長」欄は、従業員の住民税の納付先を特定するための重要な項目です。ここでは、記入ミスの例やケース別の書き方ポイントを解説します。
よくある間違い
市区町村長欄では、次のような間違いが見られることがあります。代表的な3つのケースを確認しておきましょう。
- 会社の所在地を記入してしまう
- 住民票の住所をそのまま書く
- 政令指定都市で行政区まで書く
| 間違い | 正しい記入例 |
| 会社の所在地を記入してしまう | 会社が東京都にあり、従業員が横浜市青葉区に住んでいる場合は「横浜」と書く |
→正しくは、従業員が1月1日時点で住んでいる市区町村名を記入します。
| 間違い | 正しい記入例 |
| 生活の拠点が別にあるのに、住民票の住所をそのまま書く | 住民票が東京都にあり、生活の拠点が横浜市青葉区にある場合は「横浜」と書く |
→ 原則は「生活の本拠地」、つまり実際に生活の中心となっている住所を記入します。住民票と現住所が異なる場合は、現住所を優先しましょう。
| 間違い | 正しい記入例 |
| 政令指定都市で行政区まで書く | 従業員が横浜市中区に住んでいる場合は「横浜」と書きます。 ※中区は不要 |
→ 「横浜市中区」ではなく「横浜」と記入します。政令指定都市は市単位で扱われるため、区名は不要です。

年の途中で引っ越した場合
年末調整前に引っ越して住民票を移している場合は、市区町村長欄に、新住所の市区町村名を記入します。たとえば、11月に東京都から神奈川県横浜市青葉区に転居した場合、「横浜」と書きます。
12月中に引っ越し予定で新住所が未定の場合は、いったん現住所を記入し、決まり次第会社へ報告しましょう。提出後に住所が変わった場合は、二重線を引いて修正すれば問題ありません。
翌年1月2日以降に引っ越す場合は、1月1日時点の住所(旧住所)を記入します。住民税はその住所地で課税され、次年度の年末調整で新住所に更新します。
単身赴任の場合
単身赴任の場合、市区町村長欄にはどの住所を記入すべきか迷う人もいるかもしれません。
単身赴任は、生活の本拠地がどこかで判断します。住民票を赴任先に移していれば、赴任先の住所の市区町村を記入します。
住民票を移していない場合でも、実際に生活の中心が赴任先であれば、赴任先の住所を記入してもらいましょう。週末に帰る頻度などが考慮されますが、一般的には赴任先の住所を記入するのが適切です。
住民税は「生活の本拠地」で課税されるため、残された家族がいる住民票の住所よりも、生活実態を優先します。
年末調整における市区町村長欄に関連する税制
年末調整書類の「所轄市区町村長」欄は、単なる形式的な記入項目ではなく、個人住民税の課税・徴収につながる重要な情報です。ここでは市区町村長欄と個人住民税制度の関連性、特別徴収制度の仕組みについて詳しく解説します。
個人住民税との関連性
住民税の納税地を示す「市区町村長欄」は、個人住民税の課税・徴収に影響する大切な情報です。
個人住民税は、都道府県民税と市町村民税から成り立ち、地域の運営を支える税金です。
課税対象は前年の所得で決まり、1月1日時点で住民票のある市区町村(住民票と生活の本拠地が異なる場合は生活の本拠地)に納付します。
誤って記入すると納付先が違い、修正手続きや遅延の原因になります。住所変更があった場合は、必ず最新情報を反映させましょう。
特別徴収制度の概要
住民税の特別徴収とは、会社(事業主)が従業員の給与から個人住民税を天引きし、まとめて納付する制度です。徴収金額は、毎年1月31日までに会社が提出する「給与支払報告書」に基づいて市区町村によって決められます。
決定後、5月末までに「特別徴収税額通知書」が会社に送付され、通知内容に沿って、6月から翌年5月までの1年間、毎月の給与から住民税が天引きされるという仕組みとなっています。
住民税の正しい徴収のためには、「給与支払報告書」の提出とあわせて、年末調整書類の「市区町村長欄」への正確な記入が欠かせません。
年末調整書類の提出と保管
年末調整書類には税務署に提出するもの、市区町村に提出するもの、会社で保管するものの3種類があります。
最後に年末調整書類の保管義務と提出先について解説します。提出・保管のルールもおさえておきましょう。
提出先
- 税務署へ提出する書類:
源泉徴収票(500万円超の給与支払者分等)、法定調書合計表、支払調書など - 市区町村へ提出する書類:
給与支払報告書(個人別明細書・総括表)
給与支払報告書は、従業員が1月1日時点で居住している市区町村に提出します。同じ自治体に複数人がいる場合は、個人別明細書に1枚の総括表を添えてまとめて提出しましょう。
提出が遅れると翌年度の住民税計算に影響するため、期限(翌年1月31日)を厳守します。
会社での保管義務
源泉徴収義務者である会社は、年末調整関連書類を7年間保管する義務が法律で定められています。 起算日は書類を提出期限の属する年の翌年1月10日の翌日からです。
たとえば、2024年に行った年末調整に関する書類なら、2025年1月10日の翌日11日から2032年1月10日までが保管期間です。税務調査の対象となる期間が最大で7年間であることが理由です。
保管が必要な主な対象書類は次のとおりです。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 給与所得者の配偶者控除等申告書
- 給与所得者の特定親族特別控除申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書
- 給与所得者の基礎控除申告書
- 住宅借入金等特別控除申告書
書類は従業員から提出を受けたあと、会社で保管します。退職した従業員の書類についても同様にすべて保管の対象です。
保存期間中に税務署長から提出を求められた場合、会社は応じる義務があります。
税務署への提出が必要な書類
年末調整後、会社は特定の書類を税務署に提出する必要があります。提出期限は原則として翌年1月31日までです。
税務署に提出が必要な主な書類は以下のとおりです。
- 給与の源泉徴収票(税務署提出用)※500万円超の給与支払者分 等(※)
- 給与の法定調書合計表
- 支払調書
- 退職所得の源泉徴収票
※一部
参照:『No.7411 「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数等』国税庁
市区町村提出が必要な主な書類は以下のとおりです。
- 給与支払報告書(総括表)
- 給与支払報告書(個人別明細書)
給与支払報告書の提出先は、従業員が1月1日時点で居住している市区町村です。同じ自治体に複数人がいる場合は、個人別明細書に1枚の総括表を添えてまとめて提出します。
提出が遅れると、翌年度の住民税計算に影響するため、期限を厳守しましょう。
まとめ
年末調整における市区町村長欄は、従業員の住民税を正しい自治体に納付するための重要な項目です。翌年1月1日時点の住所地を基準に、生活の本拠地を優先して記入しましょう。
また、会社は年末調整書類を7年間保管し、必要書類を期限内に提出することが求められます。 不明点がある場合は、税務署や市区町村の担当窓口へ早めに確認しましょう。
年末調整を効率化したいなら|One人事[労務]
年末調整の書類回収・確認作業は、担当者の負担も大きく、課題を抱える企業も少なくありません。ミスなく円滑に進めるには、業務の電子化も検討してみてはいかがでしょうか。
One人事[労務]は、書類の回収から申請までの過程を半自動化し、効率的な年末調整を支援する労務管理システムです。回収書類は画面上で一覧表示され、申告内容も書類ごとに一括でチェックが可能。書類を一枚一枚確認しなくても、対応漏れの防止に役立ちます。
One人事[給与]との連携により、還付金の計算もスムーズに進められます。
One人事[労務]の機能や操作性は、こちらの資料でもご確認いただけます。さらに詳細を知りたい場合は、当サイトよりお気軽にご相談ください。専門スタッフが課題をお聞きしたうえでご案内いたします。
また、当サイトでは労務管理の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードしていただけます。労務管理をシンプルにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |

