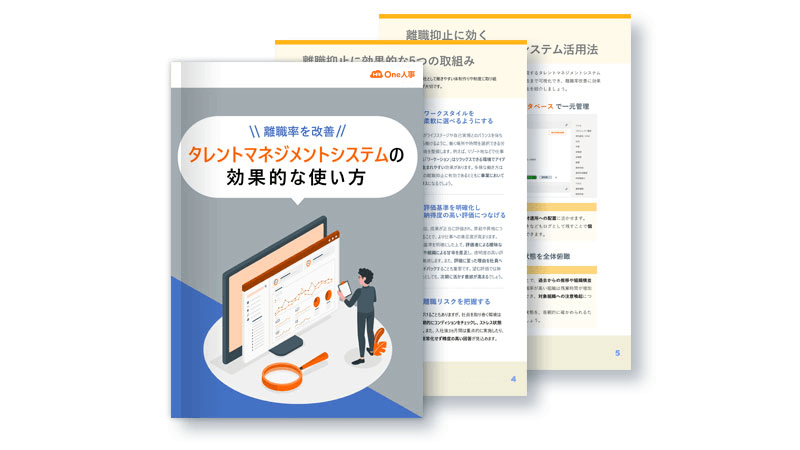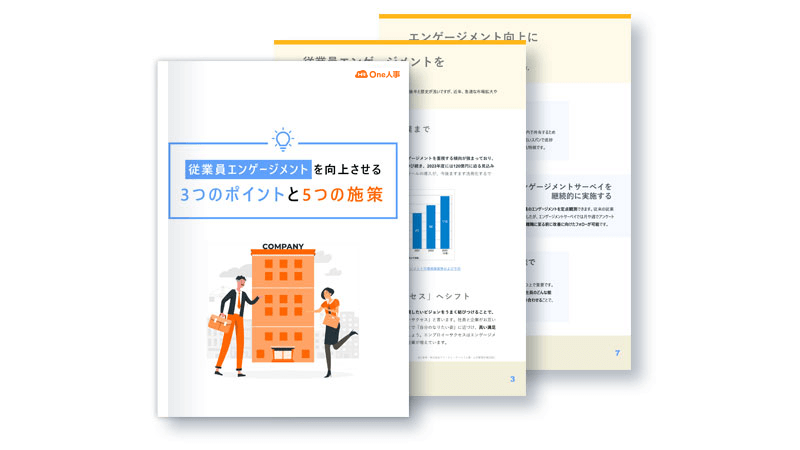皆勤手当とは? 支給条件や相場、遅刻・早退時の扱い、時代遅れなのかを解説
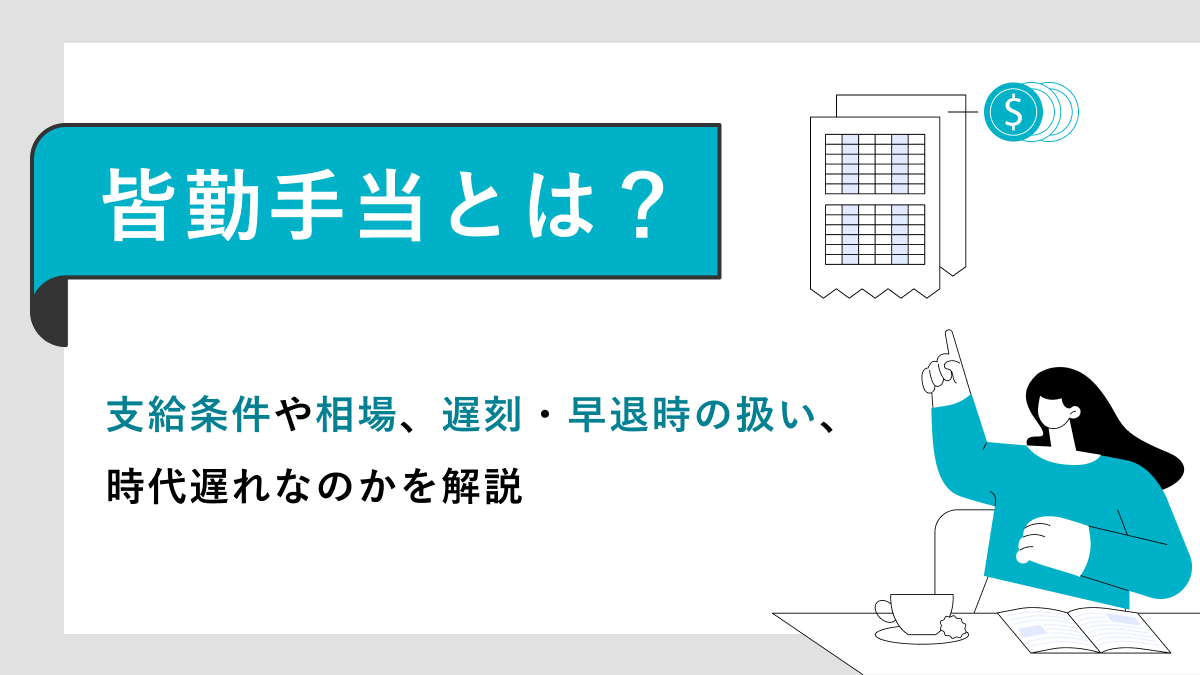
皆勤手当とは、無遅刻・無欠勤の従業員に支給される手当です。かつては勤怠意識の向上やモチベーションアップを目的に、複数の企業で導入されてきました。
しかし、働き方改革やテレワークの普及など働く環境は大きく変化し、「時代遅れでは?」「見直すべき?」という声も少なくありません。
本記事では、皆勤手当の定義や支給条件、相場、残業代や有給との関係まで、実務担当者にも従業員にも役立つポイントをわかりやすく解説します。制度の妥当性を判断するのにお役立てください。
→皆勤手当の反映をミスなく「One人事」資料を無料ダウンロード
 目次[表示]
目次[表示]
皆勤手当とは?
皆勤手当とは、一般的には一定期間中に1日も欠勤せず出勤した従業員に対して支給される手当です。主に月単位で支給されることが多く、給与明細では基本給とは別に記載されます。
皆勤手当は法律で支給が義務付けられているものではなく、企業が独自に導入する「法定外手当」に分類されます。
皆勤手当制度の主な目的は、従業員の遅刻や欠勤を減らし、出勤率を向上させることです。無遅刻・無欠勤を達成した社員へのインセンティブとして、モチベーションアップや離職率の低下も期待されています。
しかし近年では、働き方改革や多様な勤務形態の普及により、皆勤手当の意義や必要性を見直す企業も増えてきました。「全日出勤を評価する」という考え方が現状にそぐわない場面もあるようです。
皆勤手当の支給条件
皆勤手当の支給は、一般的に「1か月間、1日も欠勤・遅刻・早退がないこと」を条件とするケースが多いようです。会社の規定によりますが、月ごとに勤務状況を確認し、条件を満たせば皆勤手当が支給されます。
自社の支給条件は、就業規則や給与規程で確認しておきましょう。とくに欠勤や遅刻・早退の扱いは企業ごとにルールが異なり、病気や災害など、やむを得ない場合は柔軟に対応するケースもあります。
よく疑問に思われがちですが、年次有給休暇と欠勤は異なるため、有給を取得しても皆勤手当は支給されるケースが一般的です。
精勤手当との違い
皆勤手当に似た制度として「精勤手当」があり、両者は支給基準が異なります。
皆勤手当は、無遅刻・無早退・無欠勤という厳格な条件を満たした場合にのみ支給されます。一方で、精勤手当は「欠勤が少ない」「勤務態度が良好」など、より柔軟な基準が設けられるのが一般的です。
たとえば精勤手当の支給条件として、以下のようなルールがあります。
- 月に1日までの欠勤は許容する
- 遅刻や早退が数回までなら支給対象とする
さらに、勤務態度や業務への取り組み姿勢といった定性的な評価を加味されることも少なくありません。
つまり、皆勤手当は出勤率を100%に保つことが求められるのに対し、精勤手当は「ほぼ皆勤」であれば支給対象となるのです。
▼精勤手当も基本も確認しておきたいなら、以下の記事をご覧ください。
皆勤手当を導入するメリット
皆勤手当を導入することで、企業にはさまざまなメリットがあります。従業員の出勤率向上や遅刻・早退の抑制、生産性の向上や離職防止、従業員満足度の向上など、組織全体によい影響をもたらします。
- 出勤率が高まる
- 遅刻や早退を抑制できる
- 生産性の向上につながる
- 離職を防ぎやすくなる
- 従業員満足度が高まる
とくに、人員が限られている中小企業や、シフト制を採用している現場では、皆勤手当の効果が出やすいでしょう。導入を検討する際は、まず自社の状況に合っているかを見極めることが大切です。
出勤率が高まる
皆勤手当を導入すると、職場の出勤率が安定し、全体の業務計画を立てやすくなります。
従業員にとって「毎月欠勤せずに出勤すると手当がもらえる」という明確な目標ができるため、体調管理やスケジュール調整への意識が自然と高まるためです。
たとえば、軽い理由での欠勤や無断欠勤が減少する傾向があります。結果として、急な人員不足が起こりにくくなり、シフト調整や業務の割り振りもスムーズに進むでしょう。
皆勤手当は単なる報酬制度にとどまらず、職場全体の安定運営を支える施策の一つといえます。
遅刻や早退を抑制できる
皆勤手当に「遅刻や早退をしないこと」という条件を盛り込むと、職場全体の時間管理が改善されます。
手当の支給に直結するため、従業員は出勤・退勤時刻をこれまで以上に意識し、日々の行動に責任を持つようになるでしょう。
たとえば、交通機関の遅延や体調不良の際にも、早めに行動したり事前に連絡を入れたりする人が増えるようです。その結果、会議や作業の開始時間が守られやすくなり、業務の遅延や混乱を防止できます。
皆勤手当の支給条件に時間厳守を含めることで、規律ある職場環境が実現しやすくなるでしょう。
生産性の向上につながる
皆勤手当の導入は、欠勤や遅刻・早退の減少を通じて職場の生産性を高めます。
欠員が出にくくなり、安定した人員配置が可能になるため、業務の流れが滞らず効率的に進むためです。
とくに少人数の部署やシフト制の現場では効果が大きく、5人体制の職場で1人欠勤すれば残りのメンバーに20%の負担が増えます。
皆勤手当があれば、従業員は「手当を得たい」という動機と「自分が休めば同僚に迷惑がかかる」という意識が重なり、責任感を持って業務に取り組むようになるはずです。
もちろん、体調不良などやむを得ない事情の際には無理をする必要はありません。そのうえで欠勤や遅刻が減れば、現場の人員が安定し、結果として生産性向上につながります。
離職を防ぎやすくなる
皆勤手当の導入は、従業員の離職を防ぎ、定着率向上にもメリットが期待できます。
欠勤や遅刻・早退が減ることで、急な欠員によるしわ寄せがなくなり、メンバー同士の摩擦が起こりにくくなるからです。
勤怠不良が続くと、一部のメンバーに業務が集中して不公平感が生まれ、職場の雰囲気が悪化する傾向があります。皆勤手当はこうした不満を抑えることに、ある程度の効果が期待できます。
職場の人間関係が安定すれば、従業員は職場への愛着や満足感を持ちやすくなり、結果として離職防止につながります。
従業員満足度が高まる
皆勤手当は、従業員満足度の向上にも寄与しやすい制度です。
日々の勤怠や努力が正当に評価され、金銭的に還元されることで、従業員は会社への信頼感や安心感を持ちやすくなります。
給与に上乗せされる皆勤手当は、「自分の勤勉さや誠実な勤務態度が会社にきちんと見てもらえている」という実感につながります。
皆勤手当は単なる報酬にとどまらず、従業員のモチベーションや会社との信頼関係を高める効果も期待できるでしょう。
皆勤手当の相場
皆勤手当は企業が独自に設定できる任意の手当であり、金額や支給率も会社ごとに大きく異なります。
精勤手当や出勤手当とまとめて支給されることも多く目安となりますが、厚生労働省が行った「令和2年就労条件総合調査」によると、皆勤手当の全国平均額は月額約9,000円です。
従業員規模で見ると、規模が小さいほど欠勤による業務への影響が大きくなるため、手当額を高めに設定する傾向があります。
| 【企業規模別】皆勤手当の相場 |
|---|
| ・1,000人以上の大企業:平均6,400円 ・300〜999人規模の企業:平均7,600円 ・100〜299人規模の企業:平均7,900円 ・30〜99人規模の中小企業:平均11,200円 |
皆勤手当の金額は、ほかの諸手当と比べると、やや低めです。ほかの手当の全国平均額は以下のとおりです。
- 通勤手当:11,700円
- 住宅手当:17,800円
- 家族手当:17,600円
- 勤務地手当:22,800円
- 単身赴任手当:47,600円
月額約9,000円という皆勤手当の相場は、各種手当のなかでも比較的少額であることがわかります。
▼ミスができない手当の反映。給与計算でミスしやすいポイントをおさえることで、万一のリスクに備えませんか。給与計算のミスを防ぐ対策ガイドは、以下より無料ダウンロードできます。
皆勤手当について知っておきたいポイント
皆勤手当は、「無欠勤であれば支給される手当」という単純な制度に見えます。ただし給与計算や労務管理の実務では、考慮したい複数のポイントがあります。
基本給や残業代、有給休暇との関係は、企業の担当者が正しく理解しておかなければなりません。
ここでは、皆勤手当とほかの給与項目との関係について解説します。
皆勤手当と基本給の関係
皆勤手当は、基本給とは別に支給されるのが一般的です。基本給に皆勤手当を含めてしまうと、出勤状況によって毎月の基本給額が変動し、給与計算が煩雑になります。
基本給は労働者の生活の安定を目的としており、毎月の変動は望ましくありません。多くの企業では皆勤手当を「法定外手当」として基本給とは区別し、給与明細にも別項目で記載します。
また、皆勤手当は所得税の課税対象であり、どのような名目であっても課税される点も覚えておきましょう。
皆勤手当と残業単価の関係
皆勤手当は、毎月支給される手当として、残業代(割増賃金)の計算基礎に必ず含める必要があります。労働基準法で割増賃金の基礎から除外できる手当は限られており、皆勤手当は除外対象ではありません。
残業単価を算出する際には、基本給に皆勤手当を加えた金額を基礎賃金とします。月給制であれば「(基本給+皆勤手当)÷月の所定労働時間数」で1時間あたりの単価を求め、割増率をかけて残業代を計算します。
家族手当や通勤手当などは基礎賃金から除外できますが、皆勤手当は必ず含めましょう。
皆勤手当と有給休暇の関係
一般的には、有給休暇を取得しても皆勤手当の支給対象になります。
法律上、有給休暇を取得したことを理由に賃金を減額したり、不利益な取り扱いをしたりはできません。
多くの企業では「有給休暇は欠勤扱いにしない」と定めており、有給取得による手当カットは行っていません。
ただし、企業によっては就業規則に特別な定めを置いている場合もあるため、自社の規定を確認しましょう。
有給取得による皆勤手当の不支給は、原則として違法とされています。
皆勤手当と遅刻・早退の関係
皆勤手当の支給において、遅刻や早退があった場合の扱いは企業ごとに異なります。基本的に1回でも遅刻や早退があると皆勤手当を支給しないのが原則です。
一方、遅刻や早退の回数や時間に応じて柔軟に対応する企業もあります。たとえば、月に2回までの遅刻・早退は支給対象とする、あるいは遅刻・早退の合計時間が一定以内であれば支給する、といったルールです。
皆勤手当の支給基準は就業規則や賃金規程に明記し、従業員に周知することが大切です。基準があいまいで、精勤手当との違いがはっきりしないと、不公平感やトラブルの原因となります。
電車遅延や災害などのやむを得ない事情による遅刻・早退の扱いも決めておきましょう。
皆勤手当と最低賃金の関係
皆勤手当は、最低賃金法により最低賃金の計算には含められません。毎月必ず支払われる基本的な賃金や一部の諸手当だけが最低賃金の対象です。
皆勤手当は、欠勤や遅刻・早退がなければ支給されるという条件つきの手当です。毎月必ず支給されるものではないため、算定から外れます。
基本給や最低賃金に含められる職務手当や住宅手当などだけで、地域ごとに定められた最低賃金を上回っていなければなりません。
仮に皆勤手当を含めて最低賃金を満たしている場合でも、欠勤や遅刻が発生して皆勤手当が支給されなかった月は、最低賃金を下回るリスクがあるため注意しましょう。
皆勤手当と税金・社会保険料の関係
皆勤手当は、原則として課税対象です。給与所得として扱われ、所得税や住民税の計算に含まれ、源泉徴収の対象となります。また、社会保険料や労働保険料の算定基礎となる標準報酬月額にも含まれます。
健康保険や厚生年金保険の保険料は、基本給や各種手当(皆勤手当を含む)の合計額をもとに計算します。労働保険料も、皆勤手当を含む賃金総額に保険料率をかけて求めます。
通勤手当や出張手当などは一定条件を満たすと非課税になりますが、皆勤手当は対象外です。支給を行う場合は、税金や社会保険料の負担も踏まえて制度や規程を整備しましょう。
皆勤手当を導入する際の注意点
皆勤手当の導入を検討する際には、制度設計や運用方法に細心の注意が必要です。支給条件や金額の明確化、同一労働同一賃金への配慮、廃止時のリスク管理など、担当者がおさえたいポイントは多岐にわたります。
- 支給条件や金額を明確にする
- 同一労働同一賃金のルールを守る
- 廃止は違法ではないが不利益変更に注意する
実務上とくに重要な注意点を、以下で詳しく紹介します。
支給条件や金額を明確にする
皆勤手当を導入する場合は、「無遅刻・無欠勤・無早退」などの条件や支給金額を具体的に定め、就業規則や賃金規程に記載したうえで従業員に周知することが不可欠です。
条件があいまいだと、支給の可否をめぐってトラブルや不公平感が生じやすくなります。金額設定についても、業種や企業規模の相場を参考にし、納得感のある水準に調整しましょう。
同一労働同一賃金のルールを守る
同じ業務内容や責任を持つ労働者には、雇用形態にかかわらず、同じ金額の皆勤手当を支給する必要があります。
正社員だけに皆勤手当を支給し、パートや契約社員には支給しない場合、不合理な待遇差とみなされ、違法となる可能性が高いです。
厚生労働省のガイドラインでも、均等待遇・均衡待遇の原則に基づき、職務内容や配置転換の有無などを踏まえて、合理的な支給基準を設けることが推奨されています。
社内ルールを見直し、全従業員に公平な制度となるように整備しましょう。
廃止は違法ではないが不利益変更に注意する
一度導入した皆勤手当を廃止・減額を検討する場合は注意が必要です。手当の廃止自体は違法ではありませんが、従業員にとって不利益な変更となる場合、合理的な理由や手続きがないと無効と判断されるリスクがあります。
廃止によって賃金が実質的に減額される場合は、従業員の同意や十分な説明が求められます。廃止や見直しを行う際は、ほかの賃金項目で補填する、十分な周知期間を設けるなど、慎重に対応しなければなりません。導入前から将来的な見直しも想定し、制度設計や規程整備を行いましょう。
皆勤手当は時代遅れ?
近年、皆勤手当を「時代遅れ」とみなす声が強まっています。背景には、働き方改革や同一労働同一賃金の適用、テレワークやフレックスタイム制の普及など、労働環境の大きな変化があります。
従来は、全日出勤を奨励し、勤怠のよい従業員を評価する目的で、企業は皆勤手当を導入してきました。現代では意義や必要性が見直されています。
有給休暇取得の義務化により、従業員が有給を利用しやすくなりました。有給以外で欠勤するケースが減り、「出勤日に出勤すること」が特別な評価対象ではなくなっています。
さらに同一労働同一賃金の考え方が広がり、正社員だけでなく、パートや契約社員にも同様の皆勤手当を支給しなければならない状況が生まれています。
皆勤手当の設計や運用が複雑化し、制度そのものの見直しや廃止に踏み切る企業が増加しているのが現状です。
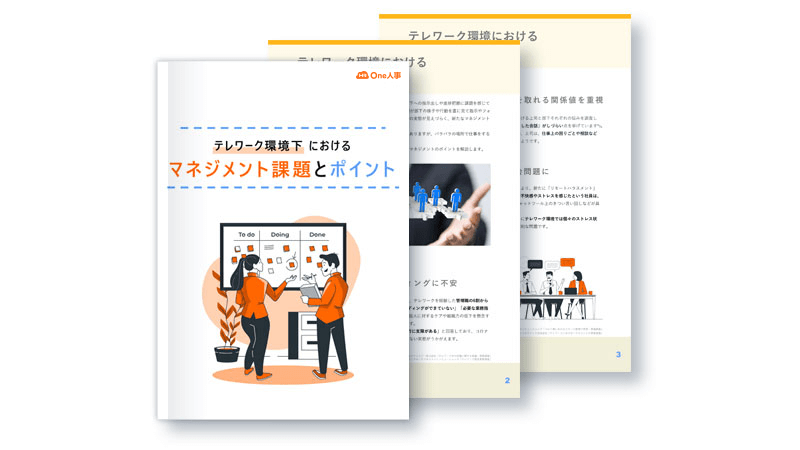
皆勤手当の導入がおすすめな業種
皆勤手当はすべての業種に適しているわけではありませんが、特定の業種では効果を実感しやすい制度です。
従業員の欠勤が業務やサービスの質に直結する現場では、皆勤手当が従業員の出勤意欲やモチベーション向上につながります。
次の業種では、1人の急な欠勤で、配送スケジュールや生産ラインが乱れたり、同僚に負担がかかったりするでしょう。
- 運送業(ドライバー)
- サービス業
- 製造業
- 建設業
現場の人員配置やサービスの安定性が重要な業種では、皆勤手当が職場全体のパフォーマンス維持に貢献するといえます。
まとめ
皆勤手当は、出勤率や勤怠意識の向上、離職防止などのメリットがある制度です。一方で、同一労働同一賃金や働き方改革など、社会の変化に合わせた見直しも必要になっています。
皆勤手当の導入や運用にあたっては、自社の業務実態にあった支給条件と金額を設定し、就業規則や賃金規程で明確にしましょう。
皆勤手当の支給条件の判定に欠かせない、出勤日数を正確に反映するため、勤怠管理システムや給与計算システムを活用するのもおすすめです。
制度の目的と現状の効果を定期的に確認し、必要に応じて改善や廃止も検討していきましょう。
皆勤手当の反映もラクに|One人事[給与]
One人事[給与]は、自社独自の皆勤手当ルールも、柔軟に設定できるクラウド型給与計算システムです。見やすく迷いがない操作画面で、ミスなく簡単に設定が完了します。
また勤怠管理システムOne人事[勤怠]と連携すると、勤怠データの取り込みがスムーズになり、給与計算に欠かせない労働時間の集計が自動化できます。
One人事[給与]の初期費用や気になる使い心地については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門スタッフが、貴社の課題をていねいにお聞きしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、給与計算をはじめ人事労務の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。給与計算をシンプルにして「本来やりたい業務」に集中したい企業は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |