高度プロフェッショナル制度とは? 職種・メリットや裁量労働との違いをわかりやすく解説

高度プロフェッショナル制度の導入を検討するなかで、「裁量労働制と何が違うのか」「本当に自社にメリットがあるのか」と悩んでいませんか。
高度プロフェッショナル制度は、働き方改革の流れのなかで、専門性の高い職種に新たな選択肢として注目されている制度です。
本記事では、高度プロフェッショナル制度の概要や対象となる職種、導入によるメリット・デメリット、裁量労働制との違いまでをわかりやすく解説します。自社への導入を判断するヒントとして、ご活用ください。

 目次[表示]
目次[表示]
高度プロフェッショナル制度をわかりやすく解説
高度プロフェッショナル制度(高プロ)は、2019年4月に働き方改革関連法の一環として導入された新しい労働制度です。対象となるのは、高度な専門知識や技術を持ち、一定の収入要件を満たす労働者です。
高度プロフェッショナル制度の目的は、従来の労働時間の規制から解放し、より自由で創造的な働き方を実現することにあります。時間ではなく成果で働くという趣旨です。
導入された背景
高度プロフェッショナル制度は、なぜ導入されたのでしょうか。
背景には、グローバル競争の激化やイノベーションの加速があります。専門性の高い人材には、時間に縛られない柔軟な働き方が求められており、企業としても優秀な人材の確保・定着に活かせる手段として注目が高まっているのです。
高度プロフェッショナル制度の対象者に対しては、労働基準法で定められた労働時間や休憩、休日や深夜の割増賃金に関する規定が適用されません。
企業側にとっては、労務管理の負担軽減や優秀な人材の確保につながるメリットがあります。一方で、労働者の健康管理や制度の適正な運用が、重要な課題として取り組まなければならなくなるでしょう。
高度プロフェッショナル制度の導入条件・対象者
高度プロフェッショナル制度を導入する企業には、以下のような厳格な要件が設けられています。
- 労使委員会の決議
- 労働者本人の同意
- 年間104日以上の休日確保
- 健康管理時間の把握と健康確保措置
条件を満たしていない場合、高度プロフェッショナル制度は適用できません。
また、高度プロフェッショナル制度の対象は、年収1,075万円以上で、特定の専門業務に従事している労働者に限られます。
導入にあたっては、制度の趣旨を正しく理解したうえで、慎重な判断が求められます。条件を詳しく確認していきましょう。
年収要件
高度プロフェッショナル制度の対象者は、年収1,075万円以上という高い基準を満たさなければなりません。厚生労働省令で「基準年間平均給与額の3倍を相当程度上回る水準で厚⽣労働省令で定める額以上」として定められており、一般的な給与水準と比べてもかなり高額です。
年収の算定には、以下の項目が含まれます。
- 基本給
- 一定額が保証された各種手当
- 最低保証額がある賞与
一方で、業績連動のインセンティブや変動するボーナスなど、確定していない報酬は含まれません。
対象はごく一部のスペシャリストに限定されるため、適用できる人材が社内にどれだけいるかを見極めることがポイントです。
高度プロフェッショナル制度の厳しい年収要件には、「自由な働き方を保障する代わりに、対象者を限定し、制度の乱用を防ぐ」という狙いがあります。

対象の業務(職種)
高度プロフェッショナル制度の対象となる業務は、専門的な知識や経験を必要とし、労働時間と成果の関連性が弱い業務に限られます。
厚生労働省は、制度の適用対象として以下のような代表業務を例示しています。
- 金融商品の開発業務(例:アクチュアリー)
- 資産運用・有価証券売買業務(例:ファンドマネージャー、アセットマネージャー)
- 市場動向分析・投資助言業務(例:証券アナリスト)
- 事業コンサルティング業務(例:経営コンサルタント)
- 研究開発業務(例:企業の研究職)
業務の共通点としては、「時間で縛れない」「裁量的に仕事を進める」という特徴があります。上司からの細かい指示ではなく、自律的に成果を出すことが期待されています。
なお、よく混同されがちですが、「19業務」という数値は、以前の専門業務型裁量労働制の対象職種数です(現在は20業務)。
高度プロフェッショナル制度に明確に「19業務」と定めた法令上の区分はありません。あくまでも厚労省が例示する対象になり得る業務群であり、職種名よりも実際の業務内容・裁量性が重視されます。
対象労働者の範囲
高度プロフェッショナル制度を適用するには、労働者が日常的に対象業務に専念していることが条件です。対象業務に一部携わっていても、その他の業務と兼務している場合は制度の対象にはなりません。制度の適用を進めるうえでは、以下の点を事前に明確に定める必要があります。
- 担当する業務の内容
- 責任の範囲
- 成果の基準
高度プロフェッショナル制度の対象者は企業と労働者との間で書面で合意を交わすことが必須です。合意内容は記録として保管し、本人の自由意思による同意を得なければなりません。また、企業が一方的に業務内容を変更したり、本人の同意なく過大な業務量を課したりすることは法律で禁止されています。
高度プロフェッショナル制度の運用では、労働者の権利を尊重するようにしましょう。
参照:『高度プロフェッショナル制度|わかりやすい解説』厚生労働省
高度プロフェッショナル制度と裁量労働制の違い
高度プロフェッショナル制度(高プロ)と裁量労働制は、どちらも労働時間の柔軟な運用を可能にする制度ですが、適用対象や法的な扱いには違いがあります。主な違いは以下のとおりです。
| 項目 | 高度プロフェッショナル制度 | 裁量労働制 |
|---|---|---|
| 年収要件 | 1,075万円以上 | なし |
| 労働基準法の適用 | 労働時間・休憩・休日・割増賃金に関する規定が適用されない | 多くの規定が適用される |
| 時間外手当 | 不要 | みなし残業代の設定が必要な場合あり |
| 休日出勤手当 | 不要 | 必要 |
| 深夜手当 | 不要 | 必要 |
| 対象業務 | 5業務に限定 | 専門業務型20業務、企画業務型 |
| 導入手続き | 労使委員会の5分の4以上の決議+本人同意 | 労使協定または労使委員会決議 |
労働基準法の適用範囲の違い
最大の違いは、労働基準法のどこまでが適用されるかです。
裁量労働制では、労働時間の算定が「みなし」となるだけで、休憩・休日・深夜手当などは原則として適用されます。
一方、高度プロフェッショナル制度では、労働時間、休憩、休日、深夜の割増賃金といった規定が原則すべて適用されなくなります。
そのため、企業側が労務管理を誤ると、労働時間の「野放し」状態になりかねず、健康管理や制度の適正運用が重要な課題となります。

年収要件の違い
高度プロフェッショナル制度は、年収1,075万円以上という非常に高い基準があるため、対象者はかなり限定的です。裁量労働制には年収要件がありません。適用の可否は職種と制度設計によって判断されます。
対象業務の違い
高度プロフェッショナル制度では、金融商品開発、コンサルティング、研究開発など、高度な専門性をもつ業務に限られます。
裁量労働制は専門業務型と企画業務型に分かれます。専門業務型は、研究開発業務、情報処理システムの分析・設計、記事の取材・編集など20業務が対象です。企画業務型は本社などでの企画・立案業務が該当します。
高度プロフェッショナル制度のメリット
高度プロフェッショナル(高プロ)は、企業と労働者の双方にとって、柔軟な働き方と生産性向上を実現できる制度で、多くのメリットがあります。最大の特徴は、「時間」ではなく「成果」で働き方と評価を設計できる点です。
実務の視点から見た、高度プロフェッショナル制度の主なメリットを3つに整理して紹介していきます。
- 従業員の生産性が向上する
- ワークライフバランスを実現しやすくなる
- 評価の不公平感がなくなる
従業員の生産性が向上する
高度プロフェッショナル制度では、評価基準が「労働時間の長さ」ではなく「業務の成果」に置かれます。従業員は、より短時間で質の高いアウトプットを出す意識が高まり、生産性が高まるでしょう。
時間給型の制度では、長時間労働にインセンティブが働いてしまい、成果と報酬が結びつきにくいケースもありました。高プロでは、無駄な残業や非効率な業務が見直され、労働者が効率的に働く意欲も向上しやすくなります。
高度プロフェッショナル制度は、成果主義を正しく設計できれば、従業員と企業の双方の成長を後押しする制度です。
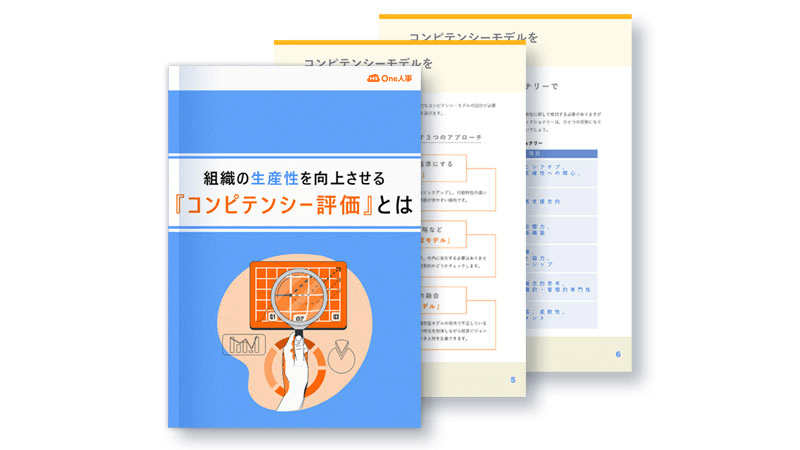
ワークライフバランスを実現しやすくなる
高度プロフェッショナル制度の対象者には、働く時間や場所に大きな裁量が与えられるメリットがあります。
労働時間の上限規制や割増賃金のルールが適用されないため、たとえば以下のような働き方も可能です。
- 子どもの帰宅時間に合わせて早めに退勤
- 親の通院に付き添いながら一時的に仕事を中断
- 自宅やカフェなど、場所を選ばないリモートワーク
時間に縛られずに、個人の事情にあわせて働けたり休暇を取得できたりするため、育児・介護と仕事の両立も現実的になります。
企業側としても、時間管理型の働き方では離職せざるを得なかった優秀な人材を継続して雇用できるメリットが期待できます。

評価の不公平感がなくなる
高度プロフェッショナル制度では、成果そのものを評価対象とするため、公平性の高い評価制度が構築しやすくなります。
日本企業では長らく、残業時間や在席時間が長い人が評価される傾向があり、「効率よく働いているのに評価されない」といった不満が生じることもありました。
高プロ制度のもとでは、スピードや質の高い成果を出す従業員が正当に評価されやすくなります。結果として、評価への納得度が高まり、モチベーションやエンゲージメントの向上にもつながります。
公正な評価制度は、人材の定着と企業競争力の強化につながるメリットです。
▼評価制度の公平性に課題があるなら、運用の見直しを検討してみてもよいでしょう。評価制度の参考になる評価シートは以下よりダウンロードしていただけます。
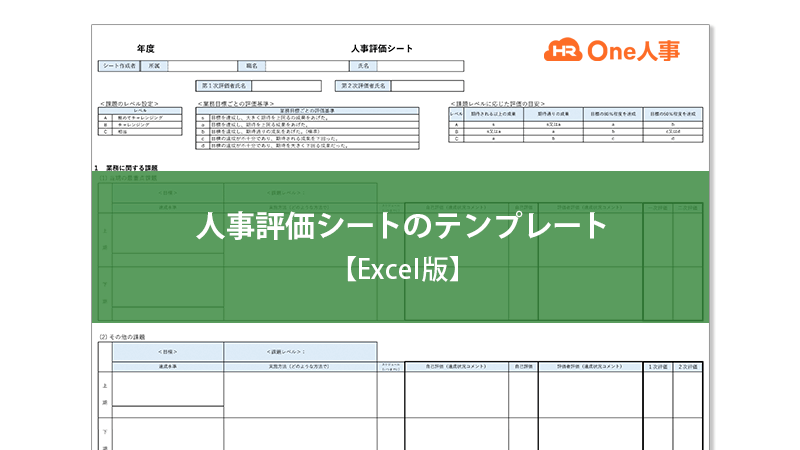
高度プロフェッショナル制度のデメリット
成果で評価され、時間に縛られない、高度プロフェッショナル制度に魅力を感じる方も多いかもしれません。一方で制度の運用を誤ると、労働者の負担が増し、企業にとっても大きなリスクとなる可能性があります。
- 労働時間の上限がなくなることによる長時間労働のリスク
- 成果主義ゆえの評価基準のあいまいさ
制度の趣旨に沿わない運用では、「働き方の自由」を目指すどころか、逆に管理が行き届かないブラックボックス化を招くおそれもあります。適切なリスク管理と評価制度の整備に向けて、もう少し具体的に見ていきましょう。
長時間労働のリスクが高まる
高度プロフェッショナル制度の最大のデメリットは、長時間労働を招きやすい点です。労働基準法による労働者の保護規定が適用されないため、従業員が際限なく働いてしまうリスクが生まれます。
とくに成果が思うように出ない場合、「もっと働けば結果が出るはず」と考え、労働者自身が自発的に長時間労働に陥るケースも少なくありません。法律上は問題がなくても、過度な労働が続くと心身の健康を損なうおそれがあります。
企業には、年間104日以上の休日確保や健康管理時間の把握など、健康確保措置を講じる義務があります。
高度プロフェッショナル制度の運用次第では、これらの措置だけでは長時間労働を十分に防げないかもしれません。制度導入後も長時間労働が常態化しているケースも報告されています。

評価基準が一面的になりやすい
高度プロフェッショナル制度では、労働時間ではなく成果で評価するため、一見するとシンプルで明快な評価が可能に見えます。
しかし、すべての業務が「短期的に成果が明確に出る」とは限りません。たとえば研究開発や新規事業開発のように、長いスパンで取り組む仕事では、数年単位で成果が出ることもあります。
こうした業務では、成果だけに頼った評価では不十分になりがちで、過程や中間目標の達成度をどう扱うかが重要です。評価基準が不明瞭なまま運用されれば、納得感を欠き、モチベーションや定着率の低下につながるおそれもあります。
企業には、成果だけでなく業務プロセスや貢献度も含めた多面的な評価制度を構築することが求められます。
高度プロフェッショナル制度の導入手順
高度プロフェッショナル制度は、対象者に大きな裁量と柔軟な働き方をもたらす一方、導入にあたっては法律で定められた厳しい手順を踏む必要があります。
導入トラブルは避けたいという担当者向けに、導入に必要な5つのステップをわかりやすく解説します。
- 労使委員会を設置する
- 労使委員会で決議をし、労働基準監督署長に届け出る
- 書面で対象労働者の同意をとる
- 対象労働者が業務を開始する
- 定期報告をする
労使委員会を設置する
高度プロフェッショナル制度導入の第一歩は、労使委員会の設置です。労使委員会は、賃金や労働時間、そのほかの労働条件について調査・審議し、事業主に意見を述べる役割を担います。
労使委員会は、使用者と労働者の代表で構成され、最低3名以上でなければなりません。
また、委員の過半数は労働者側の代表である必要があり、その代表は過半数組合または過半数代表者から任期を定めて指名されます。
設置にあたっては、委員会の招集方法・議事の進め方・決議方法などを明記した運営規程を整備することが求められます。
労使委員会で決議をし、労働基準監督署長に届け出る
労使委員会が設置されたら、高度プロフェッショナル制度の適用に関する10項目の決議を行います。
- 対象業務
- 対象労働者の範囲
- 健康管理時間の把握および把握方法
- 休日の確保(年間104日以上かつ4週間を通じ4日以上)
- 選択的措置
- 健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置
- 同意の撤回に関する手続き
- 苦情処理措置およびその具体的内容
- 不利益取扱いの禁止
- その他厚生労働省令で定める事項
決議には委員の5分の4以上の賛成が必要です。決議後は、所定の様式を事業場を管轄する労働基準監督署へ提出しなければなりません。
不備があると制度が無効になる可能性もあるため注意しましょう。「高度プロフェッショナル制度に関する決議届(様式第14号の2)」を用いた、正確な提出が求められます。
参考:『高度プロフェッショナル制度に関する決議届』e-GOV電子申請
書面で対象労働者の同意をとる
労基署への届け出後、実際に高度プロフェッショナル制度を適用する従業員一人ひとりから書面で同意を得る必要があります。
同意は自由意思であることが大前提です。企業側が一方的に進めることはできません。具体的には以下の対応が必要です。
- 同意書には対象業務、賃金、期間、成果条件などを記載
- 職務記述書を用いて、責任範囲や期待される成果を明示
- 労働者が十分理解し納得したうえでの署名をもらう
一方的な説明や不十分な情報で同意を取ると、のちに無効を主張されるおそれもあるため、ていねいな対話を心がけましょう。
対象労働者が業務を開始する
すべての手続きが完了したら、対象労働者は制度の適用を受けて業務を開始します。
高度プロフェッショナル制度の適用期間は、労使委員会の決議で定めた期間内に限って有効です。
継続して運用する場合は、再度の決議・届け出が必要であるため、注意しましょう。
継続的に管理し、定期報告をする
高度プロフェッショナル制度では、企業には継続的な運用管理の責任があります。たとえば、以下のような対応が求められます。
- 年間104日以上の休日を確保する
- 健康管理時間を適切に把握し、健康・福祉措置を実施する
- 労働者から同意の撤回があった場合の手続きを遵守する
また、制度の適正な運用状況を報告する義務として、年2回、所轄の労働基準監督署に対して定期報告を行わなければなりません。報告には、制度適用者の人数や健康管理措置の実施状況などが含まれます。
定期報告を怠ると、制度の停止や是正指導につながる可能性があるため、確実に対応しましょう。

高度プロフェッショナル制度を導入する際の注意点
高度プロフェッショナル制度は、成果重視・時間に縛られない働き方を実現する一方で、慎重な設計と運用が求められる制度です。
決められた導入手順を踏むだけでなく、法律により規制がゆるいため、従業員の健康管理や労務管理において、企業の責任はより重くなります。
制度導入時に、企業がおさえておきたい4つの注意点を紹介します。
- 従業員の健康に配慮する
- 労働基準監督署長への定期報告を怠らない
- 関連事項の記録を作成し、3年間保存する
- 人事評価制度の見直しも検討する
従業員の健康に配慮する
高度プロフェッショナル制度は、労働時間の上限がなくなるため、企業には従業員の健康と福祉を守るための措置が求められます。通常の勤務体系以上に、一人ひとりの健康維持に注意を払わなければなりません。
主な対応は以下のとおりです。
- 健康管理時間の把握
- 年間104日以上かつ4週4休以上の休日確保
- 選択的健康措置(いずれか1つの実施が必須)
- 健康管理時間の状況に応じた健康・福祉確保措置(決議したもの)
健康管理時間とは、事業場内にいた時間と事業場外で労働した時間の合計です。タイムカードやパソコンの使用時間などにより、客観的に記録する必要があります。
休日確保については、法定どおり、年間104日以上かつ4週間を通じ4日以上の休日を与えられているかチェックします。
▼休日に関する法定基準を知るには、以下の記事をご確認ください。
また、選択的健康措置は、以下のいずれかを選択して実施する必要があります。
- 勤務間インターバル11時間以上の確保と月4回以内の深夜業務制限
- 健康管理時間の上限(月100時間または3か月240時間以内)設定
- 年1回以上の連続2週間休日付与
- 臨時健康診断の実施
さらに、健康・福祉確保措置は、以下のうちから決議して実施します。
- 医師による面接指導
- 代償休日または特別な休暇の付与
- 相談窓口の設置
- 適切な部署への配置転換
- 産業医による保健指導
そのほか規定の労働時間を超えた対象者については、本人の希望にかかわらず、医師による面接指導を行います。
高度プロフェッショナル制度の自由度を活かすには、まず健康管理体制を固めることが大切です。
労働基準監督署長への定期報告を怠らない
高度プロフェッショナル制度を導入した企業は、労働基準監督署への定期報告義務を負います。
使用者は労使委員会の決議が行われた日から起算して6か月以内ごとに1回、所定の様式により、管轄の労働基準監督署に報告しなければなりません。
報告内容には、以下が含まれます。
- 対象労働者に適用される評価制度・賃金制度・対象業務の具体的内容
- 健康管理時間の状況
- 休日確保措置・選択的措置・健康福祉確保措置および苦情処理措置の実施状況
対象の労働者が0人であっても、労使委員会で決議を行った時点で、定期報告義務が発生することに注意が必要です。
報告を怠ると、制度の適用停止や是正勧告を受けるリスクもあるため、運用体制に定期報告のフローを組み込みましょう。
関連事項の記録を作成し、3年間保存する
高度プロフェッショナル制度では、書面管理も法令で義務づけられています。労働基準法第109条により、以下の書類は3年間保存しましょう。
- 対象者との同意書・撤回届
- 対象業務・職務内容・賃金額などの書類
- 健康管理時間・休日の記録
- 選択的健康措置の実施記録
- 労使委員会の議事録
書類は、労基署の調査や監査で提示を求められる可能性があるものです。記録の不備や紛失は法令違反となり、制度の継続に支障をきたすおそれもあります。担当者を明確にし、保存ルールやチェック体制を整備しましょう。
人事評価制度の見直しも検討する
高度プロフェッショナル制度では、時間ではなく成果で評価する人事制度が必要です。成果基準に基づいた抜本的な見直しが必要になる場合もあるでしょう。
人事評価制度の見直し時のポイントは以下のとおりです。
- 成果・業績を定量的に測る指標の設計
- 評価基準・プロセスの透明化
- 労働者との合意形成・定期的なフィードバック
評価制度が不適切だと、労働者が正当な評価を受けられず、モチベーション低下や離職につながるリスクがあります。
高度プロフェッショナル制度の導入を成功させるには、対象者が納得できる評価軸の明確化と公正な運用が求められます。
高度プロフェッショナル制度の導入状況
高度プロフェッショナル制度は2019年4月の施行から約6年が経過しました。
導入企業数は非常に限定的な状況が続いています。厚生労働省の最新データによると、2025年3月末時点で制度を導入している企業は34社(36事業場)、対象労働者数は1,390人にとどまっています。
制度の対象となる5つの業務分野のうち、コンサルタント業務が圧倒的な割合となっており、ほかの業務分野での活用は極めて少ない状況です。
年収1,075万円以上という高い要件や複雑な導入手続きが影響し、制度の普及はゆるやかなペースで推移しています。
参照:「高度プロフェッショナル制度に関する報告の状況(令和7年3月末時点)」
まとめ
高度プロフェッショナル制度は、高度な専門知識を持つ労働者に対して柔軟な働き方を提供し、従業員と企業の双方にメリットがある制度です。
労働時間ではなく成果で評価される仕組みにより、生産性向上やワークライフバランスの実現が期待できます。年収1,075万円以上という厳格な要件や限定された業務分野など、適用には厳しい条件があります。
高度プロフェッショナル制度の導入には労使委員会の設置や労働基準監督署への届け出など複雑な手続きが必要です。継続的な健康管理や定期報告の義務も発生します。長時間労働のリスクや、健康管理の重要性を十分に理解し、適切な運用体制を構築していきましょう。
労働時間の客観的な管理に|One人事[勤怠]
One人事[勤怠]は、多様な働き方に対応するクラウド型の勤怠管理システムです。柔軟な働き方を支援する機能も随時アップデートされています。
「自社の勤怠ルールが適用できるだろうか」と気になった方は、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門スタッフが課題をていねいにお聞きしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、勤怠管理の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。勤怠管理をラクにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |
