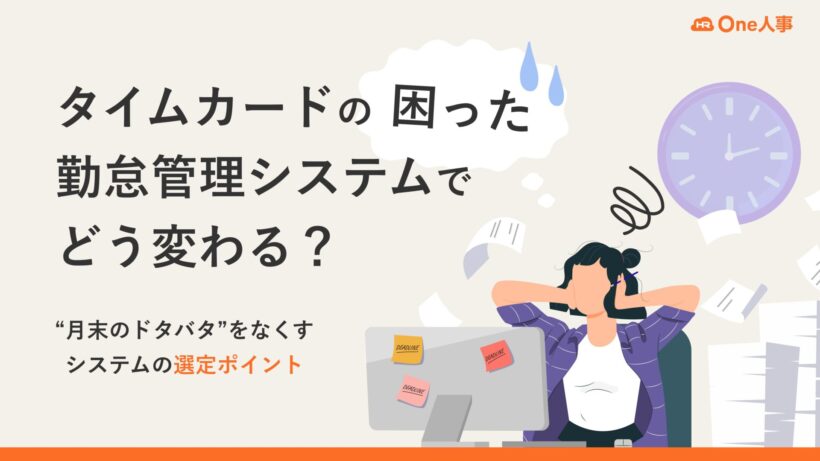勤怠打刻をする意味とは? 必要性や管理不十分のリスク、打刻漏れの対策を解説
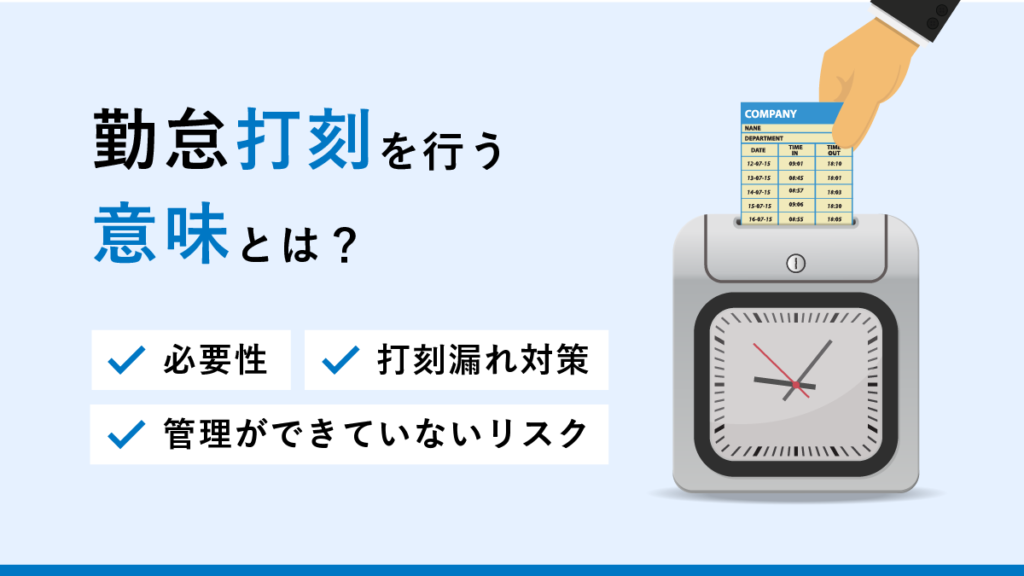
打刻には2つの意味があるのをご存じでしょうか。
- 数字や記号を金属などの硬いものに刻みつけること
- 出退勤の時間を刻んで管理すること
多くの社会人やアルバイトにとって、「打刻」といえば勤怠管理システムを使用して出退勤を記録することを指すのが一般的です。
勤怠打刻を適切に行えないと、給与を正しく計算できず会社と労働者の双方で困った事態に発展します。勤怠打刻を忘れないようにする仕組みは進化しており、ICカードやチャットアプリ、GPS情報などを使用した打刻ツールも増えてきました。
何気なく「勤怠打刻は重要です」といわれますが、必要性や管理できない場合のリスクを詳しく解説していきます。
【勤怠打刻漏れの修正対応に追われている場合は】
→打刻や管理のストレスを軽減|勤怠打刻システム「One人事」資料をダウンロード
 目次[表示]
目次[表示]
勤怠における打刻とは? 3つの必要な理由をもとに解説
勤怠管理における打刻とは、従業員が出勤や退勤のときに自身の勤務開始・終了時間を記録する行為を指します。
企業が従業員の労働時間を適切に把握して、給与計算や残業管理をするうえで重要な役割です。
近年は、技術の進歩によりさまざまな打刻方法が登場し、効率的な勤怠管理が可能となっています。
労働時間を適正に記録するため
労働時間を適正に記録することは、打刻が果たす役割としてもっとも基本的で重要な役割です。
打刻により、従業員がどの時間帯にどれだけ働いたかを記録し、労働基準法に基づいて適切に勤怠管理ができます。
たとえば従業員が予定以上に残業をしている場合や、休憩時間が不足している場合に、早期発見につながり、改善策を行う手立てとなるでしょう。
客観的な方法での労働時間の管理は企業の果たすべき責任の一つです。打刻を徹底することは、働きやすい職場づくりへの第一歩といえます。

残業時間を把握するため
勤怠打刻は、法令に基づく残業時間の管理を徹底し、従業員の労働負荷を緩和させるためにも重要です。
2019年4月の労働基準法改正では、月45時間・年間360時間を超える時間外労働が原則として禁止されました。
従業員の打刻に基づいて、担当者が月の途中で現在の残業実績を確認することで、過重労働や過労を抑制できます。また打刻データは、適切な残業代の支払いにつながり、未払い残業代のような法的リスクを回避します。
打刻による残業時間の把握は、従業員の健康を守るだけでなく、企業のコンプライアンスを確保するうえでも大切な業務です。
給与計算を正しく行うため
従業員が働いた時間に基づいて、残業代や各種手当などが計算されるため、打刻が間違っていると、給与が正しく計算できません。
たとえば、打刻漏れや不正記録があると、正しい残業手当が支給されず、従業員とのトラブルに発展する可能性があります。また反対に、実際には働いていない時間に対して報酬が支払われ、企業にとって不利益な結果を招くこともあるでしょう。
正確な打刻に基づいて給与を払うことで、従業員に安心感を与え、公正な労働環境を提供できます。
打刻管理が不十分な場合に生じるリスク
打刻管理ができていないと、従業員とのトラブルや法的な論争に発展するリスクがあります。
未払い賃金が発生している場合は、労働基準監督署から改善命令が出されるだけでなく、最悪の場合には懲役や罰金を科される可能性があるので注意が必要です。
以下の3つは、打刻管理ができていない場合に生じる代表的なリスクです。
| 打刻管理ができない場合に生じるリスク | |
|---|---|
| 1.未払いの残業代を請求される | 適切な残業代を払えていないことでの従業員とのトラブルに発展する |
| 2.法律違反により罰則を科されるおそれがある | 労働時間が正確に記録されておらず未払い賃金が発生している場合、企業は労働基準法違反として罰則を科されるリスクがある。 |
| 3.勤怠担当者の業務負担が増える | 打刻管理ができていないと、訂正や確認の作業が必要となり、労務担当者の負担が増加する結果になる。 |

適切な打刻管理はとても重要です。
従業員に安心感を与え、法的なトラブルを回避するだけではなく、労務担当者に無駄な業務の発生も防げます。
もし労働基準監督署の調査が入ると、過去の従業員の勤怠データや賃金台帳などの提出を求められ、派生してさまざまな煩雑な業務が発生するでしょう。
勤怠管理を徹底することで、無駄な業務の発生を少なくできるため、管理体制が不十分な企業はすぐに見直すことをおすすめします。
打刻方法の種類とメリット・デメリット
勤怠の打刻方法には主に以下の5つがあり、それぞれ特有のメリット・デメリットがあります。
| 打刻方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| エクセル | 低コストで始められる | 入力でミスが起こりやすい |
| タイムカード | シンプルで使いやすい | 管理が煩雑になりやすい |
| ICカード | データ管理が容易 | 初期コストがかかる |
| 生体認証 | 不正打刻を防止できる | 導入コストが高い |
| 勤怠管理システム | 効率的な管理が可能 | 導入コストがかかる |
どの打刻方法を採用するかは、企業規模や従業員の働き方などを総合的に考慮しなければなりません。また運用・維持コストや操作性も大事なポイントです。
複数の打刻方法を併用することで、リモートワークやフレックスタイム制といった柔軟な働き方にも対応しやすくなる場合があります。
5つの打刻方法について、具体的な特徴を以下で解説していきます。
エクセル
エクセルを使った打刻管理は、初期費用がほとんどかからず、柔軟にカスタマイズできる点が大きな特徴です。特に、小規模な企業や勤怠管理の導入コストを抑えたい場合に適しています。たとえば、マイクロソフトOfficeをすでに使用している企業であれば、追加のソフトウェアを購入する必要がありません。
一方で、エクセルを用いる勤怠管理には課題も多く、特に手動入力によるミスが起こりやすい点がデメリットです。打刻漏れや不正なデータ改ざんを防ぐには、入力の制限や改ざん防止策をとる必要があります。また、従業員数が多くデータが増加する場合、管理の負担が大きくなり効率が低下します。専門的なエクセルスキルを持つ担当者の存在が重要となるでしょう。
タイムカード
タイムカードは、紙のカードに出退勤時間を打刻する方法で、昔から広く利用されています。操作が非常にシンプルで、特別なトレーニングが不要な点は大きなメリットです。特に、従業員数が少なく、日常的にオフィスに出勤する労働者が多い職場で適しています。
しかし、紙でのタイムカード管理には限界があります。打刻忘れが発生しやすく、また不正行為を防ぐためには管理体制を強化する必要があります。さらに、データの集計作業が手作業となるため、時間がかかり、ミスのリスクも伴います。リモートワークやフレックスタイム制には対応しにくいため、近年ではほかのデジタルツールへ移行する企業も増えています。
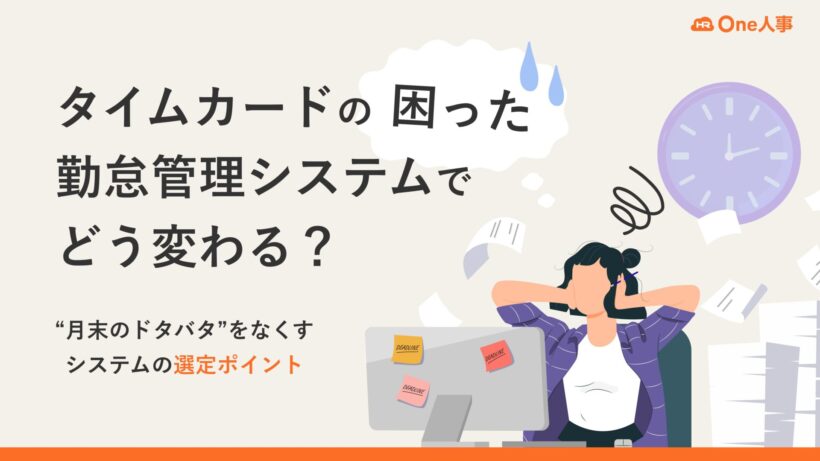
ICカード
ICカードを利用した勤怠管理は、打刻時に専用のICレコーダーにカードをかざすだけで簡単に出退勤時間を記録できる便利な方法です。カードには個別の情報が登録されているため、なりすましや代理打刻を防ぎ、不正行為のリスクを減らします。また、打刻データが自動的にシステムに連携されるため、リアルタイムでの勤怠管理が可能です。
一方で、ICカードを導入するには初期コストがかかり、スキャナーやシステムインフラの整備が必要です。また、カードの紛失や破損が発生した場合の対応策を用意しておくことが求められます。このような課題を考慮しつつ、デジタル化による効率化を重視する企業に適しています。
生体認証
生体認証を用いた打刻方法は、指紋や顔認証などの個人の身体的特徴を利用して勤怠を記録する最先端の方法です。カードや紙などの物理的な媒体が不要で、不正打刻や改ざんを防ぐ高いセキュリティ性がメリットです。たとえば、オフィスの入口に設置された顔認証システムを利用すれば、出退勤時に専用機器に顔を向けるだけで記録が完了します。
しかし、導入には高額なコストがかかり、システムの設定や運用には専門知識が必要です。また、認証エラーが発生する場合や、従業員の認証データを適切に保管するためのセキュリティ体制も整備しなければなりません。課題に対処できれば、精度の高い勤怠管理を実現できる有効な手段といえます。
勤怠管理システム
勤怠管理システムは、クラウド上で勤怠データを一元管理できる高度な打刻ツールです。従業員の打刻情報をリアルタイムで収集し、残業時間や休暇管理などを自動化する機能が備わっています。不正打刻を防ぐアラート機能や、異常な打刻データを通知する機能を持つシステムもあり、効率的な管理が可能です。
しかし、高機能である分、導入や運用コストがかかる点がデメリットです。また、システムトラブルが発生した場合には勤怠データの記録が一時的に止まるリスクがあるため、バックアップ体制を整える必要があります。導入を検討する際は、従業員数や予算、既存の業務フローに適するかを十分に検討しましょう。
→打刻管理を効率化|勤怠管理システムOne人事[勤怠]の特長を見てみる
打刻漏れが起きる原因
打刻漏れが起きる原因を明確にし、事前に対策を講じることは、担当者の修正工数を減らし、法令違反のリスクを回避するためにも重要です。
ではなぜ、さまざまな打刻ツールが増えているにもかかわらず、従業員の打刻の漏れがあとを立たないのでしょうか。
職場で打刻漏れが発生する主な原因は、以下の3つが挙げられます。
| 打刻漏れが起きる主な原因 | |
|---|---|
| 1.打刻する場所や装置に問題がある | 打刻機の不具合・老朽化。打刻場所がオフィスの入口から離れたところにある |
| 2.従業員に打刻が習慣づいていない | 打刻習慣がなく、繁忙期や忙しい時間帯に打刻を忘れてしまう。出張や直行直帰が多い |
| 3.テレワークにより労働環境が変化している | 在宅での打刻の仕組みが整っていない。在宅勤務者が出退勤時刻を不正に調整している |
打刻装置が原因の場合は、すぐに点検して必要に応じて新しいシステムへの切り替えを検討しましょう。打刻機の場所がわかりにくい場合は、職場の入口やロッカーエリアなど、従業員が出退勤時に必ず通る場所に設置するようにします。
またとくに繁忙期は、打刻を忘れる従業員が増える傾向にあります。リマインダーを出したり、ワンクリックで手軽に打刻可能なツールを採用したりすることで、忙しい状況でも打刻が可能です。
テレワークでの打刻に課題がある場合は、位置情報が取得できる勤怠管理システムの導入をおすすめします。
→インターネット環境が整ってさえいれば、スマートフォンからも手軽に打刻できるクラウド型勤怠管理システム「One人事」の資料は【こちら】
打刻漏れの原因は複合的に重なっており、長期的に悪い習慣が定着してしまうのは望ましくありません。
いずれの原因であっても、従業員へ打刻の重要性を周知し、運用ルールを明確にしましょう。
打刻漏れを防止するための対策
打刻漏れの3つの原因を踏まえて、明日からできる4つの対策を紹介します。
| 対策 | |
|---|---|
| 打刻ルールの設定・周知 | 明確なルールを作成し、繰り返し従業員に周知する。リマインダーで意識づけを強化する |
| 打刻の重要性を説明 | 給与計算や法的リスク回避のために打刻が重要であることを教育し、習慣化を促す |
| 打刻機の設置場所を変更 | 通行頻度の高い場所や出入口付近に設置して、打刻の手間を軽減し、忘れにくくする |
| 勤怠管理システムの導入 | クラウドシステムにより、PCやスマホでの打刻を可能にし、自動集計とリアルタイム管理で漏れを防止する |
打刻漏れは勤怠管理の信頼性を低下させ、法的リスクや従業員とのトラブルにつながる可能性があります。以上の対策を実施することで、打刻漏れの防止につながるでしょう。
打刻ルールを設定・周知する
労働時間の記録を正確に行うためには、ルールの設定と周知が欠かせません。同時に従業員がルールを守りやすい仕組みを作ることがポイントです。
たとえば、ルールの周知にはメールだけでなく、定期的な社内ミーティングでの説明やポスター掲示、リマインダーなどの手段を組み合わせると効果的です。さらに、違反が発生した場合の対応ルールも決め、従業員が「自分に関係のあること」と捉えられるようにしましょう。
従業員に勤怠打刻の重要性を周知する
特に新入社員や若手社員には、勤怠打刻が給与計算や残業管理に直結していること、また法的トラブルの回避に重要な役割を果たしていることを説明する必要があります。
従業員が打刻の重要性を理解するには、実例を交えた説明が有効です。たとえば「打刻漏れによって給与計算にミスが生じる」「企業に罰則が科される可能性がある」といった具体例を挙げるのも一案です。
また、勤怠打刻の役割が従業員の権利を守ることであるとを強調すれば、打刻を単なる「義務」ではなく「自分を守る行動」として意識できるかもしれません。
打刻機の設置場所を変更する
打刻機の場所がわかりにくく不便な場合、従業員は意識的にも無意識的にも打刻を忘れてしまいがちです。打刻機の設置場所は、従業員の動線を確認することが重要です。出入口付近やロッカールームに設置すると、目につきやすく、出退勤時に自然に打刻ができるでしょう。
勤怠管理システムを導入する
勤怠管理システムの導入は、単に打刻漏れを防止するだけでなく、勤怠データを活用した生産性向上にもつながります。たとえば、リアルタイムでの勤怠データ分析を通じて、部署ごとの労働時間の偏りや過剰残業を早期に把握し、労務管理の改善に役立てられます。
クラウド勤怠管理システムなら、PCやスマートフォンから簡単に打刻が可能です。また、自動でデータを集計することで、ミスを大幅に削減できるでしょう。リモートワークにも対応できる点も大きなメリットです。
勤怠管理システムの導入をはじめ、打刻漏れの対策を組み合わせることで、企業全体の勤怠管理体制をより効率的で信頼性の高いものにできるでしょう。担当者は現状の課題を把握し、最適な方法を選択して取り入れていく必要があります。
→打刻ミス防止もサポート|One人事[勤怠]の特長を見てみる
打刻漏れを防止するために運用方法の見直しを(まとめ)
勤怠管理における打刻は、企業と従業員にとって非常に重要な役割を担っています。正確な労働時間の記録を行うことで、給与計算の適正化や残業管理の効率化がはかられ、法律違反のリスクも低減します。
打刻管理が不十分だと、企業は法的なリスクや未払い賃金の請求といったトラブルを抱えることになりかねません。従業員に勤怠打刻の重要性を周知して、適切な方法を選び、勤怠管理システムの導入などで打刻漏れを防ぐことが重要です。
勤怠管理システムの大きなメリットは以下の2点です。。
- 勤怠データの自動集計で給与計算が効率化する
- 勤怠実績をリアルタイムで一元管理できる
- 不正打刻や漏れを防ぐ機能がある
勤怠の打刻漏れを防止して従業員の労働時間を正確に把握するために、勤怠管理システムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
正確な勤怠打刻に|One人事[勤怠]
One人事[勤怠]は、正確な打刻管理にお役立ていただける勤怠管理システムです。
- 勤怠の入力・打刻漏れが多い
- 月末の集計をラクにしたい
- 労働時間や残業時間を正確に把握できていない
打刻の管理に課題がある企業を支援しております。
One人事[勤怠]の初期費用や操作性については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門のスタッフが貴社の課題をていねいにヒアリングしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、勤怠管理の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。勤怠管理をラクにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |