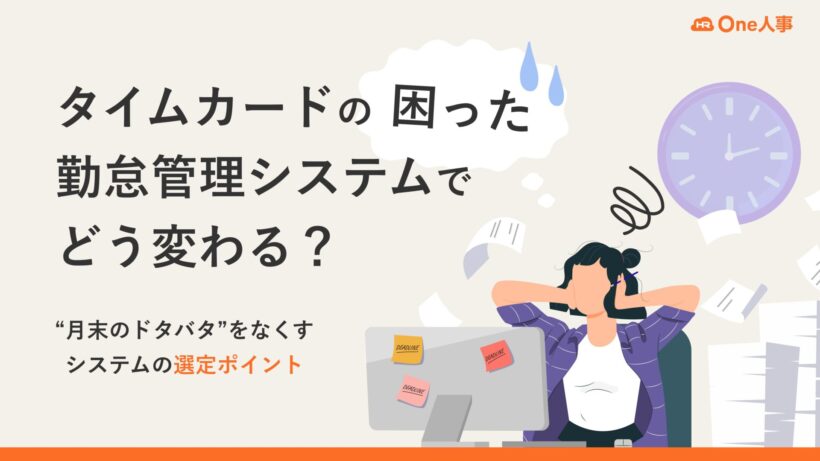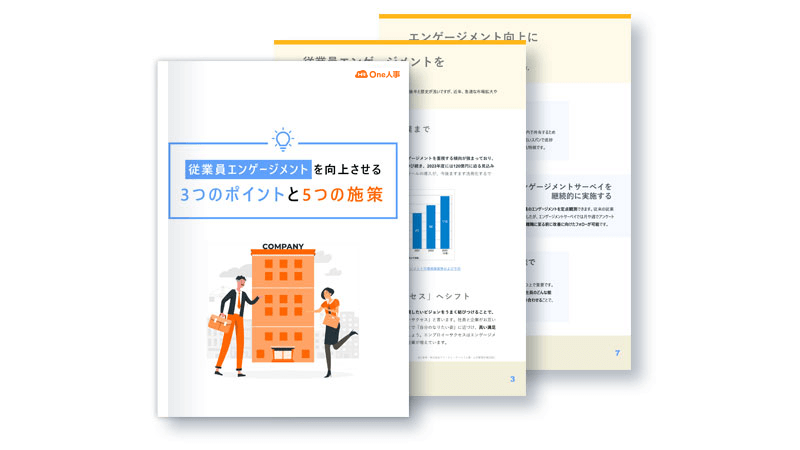タイムカードでの休憩時間の管理方法とは? 押さなくてもいい? 打刻ルールや計算のポイント
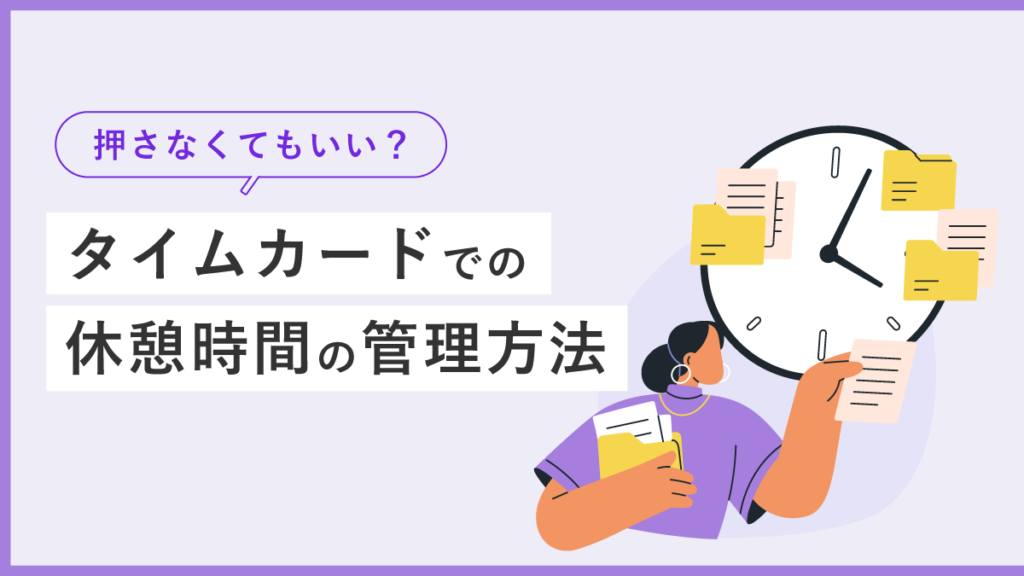
タイムカードは勤怠管理の基本ツールとして多くの職場で利用されています。なかでも「休憩時間もタイムカードを押すべきか」「休憩時間の記録をタイムカードで正確に管理するにはどうすればよいのか」と疑問を持つ人もいるでしょう。
休憩時間の打刻ルールは、労働基準法や会社のルールによって異なり、運用次第で給与計算や労務管理に影響を与えます。
本記事では、タイムカードによる休憩の管理方法やルールの決め方、給与計算のポイントを解説します。
休憩だけでなく労働時間の管理方法についても課題がある場合は以下の資料もご覧ください。
 目次[表示]
目次[表示]
休憩時間におけるタイムカードの打刻|押さなくても違法ではない?
休憩時間の始まりと終わりを、タイムカードに打刻しなければらないという法的決まりはありません。
厚生労働省が公表するガイドラインによると、「労働日ごとに始業と終業の時間を記録すること」と定められています。したがって、休憩時間の打刻は義務づけられておらず、打刻していなくても違法ではありません。給与計算においては、所定労働時間から所定の休憩時間を差し引いて対応するのが一般的です。
労働基準法では、休憩取得のルールや原則が定められており、事業主は休憩時間をどのくらい取得したのか、把握する責任があります。
タイムカードへの休憩打刻は必須ではありませんが、従業員が適切に休憩を取れているか、把握できる仕組みを整えましょう。
参照:『労働時間の適正な把握のために使用者が講ずるべき措置に関するガイドライン』厚生労働省
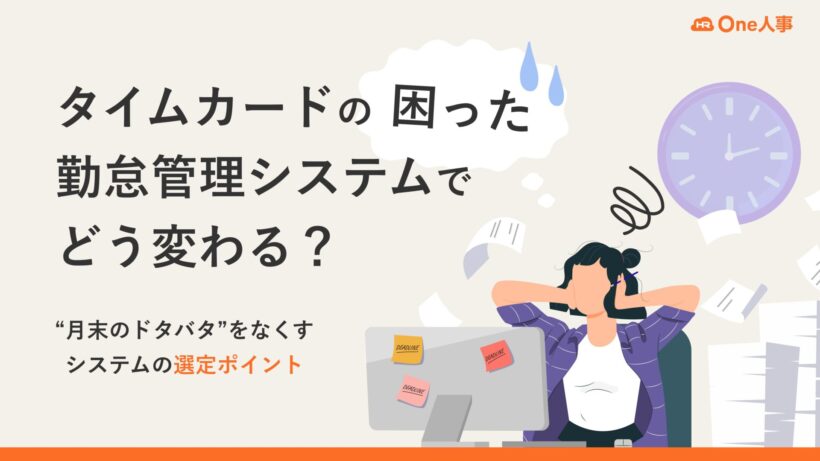
休憩時間の取り扱い方をおさらい
休憩時間は労働者にとって心身をリフレッシュするための大切な時間です。従業員の給与計算にもかかわるため、労働基準法における定義や基本原則を理解しておきましょう。
労働基準法における定義
労働基準法第34条では、休憩時間について、以下のとおり定められています。
第三十四条 使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
引用:『労働基準法第34条』e-GOV法令検索
法律を踏まえると、労働時間ごとの休憩時間は、以下のとおりです。
| 勤務時間 | 休憩時間 |
|---|---|
| 6時間未満 | なし |
| 6時間〜8時間未満 | 45分 |
| 8時間以上 | 60分 |
従業員の健康や生産性を保つために、事業主は休憩時間の厳守を促し、管理を徹底する必要があります。
労働基準法における休憩ルールをさらに詳しく知るには以下の記事もご確認ください。
3原則
労働基準法第34条では、休憩時間を「途中に」「一斉に」「自由に」与えなければならないという「休憩の3原則」が定められています。
- 途中付与の原則
- 一斉付与の原則
- 自由利用の原則
ただし例外もあるため、それぞれの原則について解説します。
原則1.途中付与
途中付与の原則は、休憩時間は労働の途中で付与されなければならないとするルールです。
勤務終了後にまとめて休憩を取るのは、従業員の同意があっても認められません。業務の途中で一定の時間、仕事から離れることで、従業員の健康と安全が確保されます。
原則2.一斉付与
一斉付与の原則は、同じ職場で働く全従業員に対して、休憩を同じタイミングで与えるという基本ルールです。
原則に沿って運用することで、休憩時間の公平性が確保され、業務効率の向上が期待できます。
ただし以下の2つの例外もあり、個別の休憩時間を設定することも可能です。
- 労使協定が結ばれている場合
- 務の都合上、一斉付与が難しいとして労働基準法が定める一定の業種(運送業やサービス業等)
原則3.自由利用
自由利用の原則とは、従業員が休憩時間を自由に利用できる権利を保障するものです。
休憩時間中は、会社が業務のために従業員を拘束することは認められません。従業員は休憩の間、食事やリラックス、個人的な用事を済ませるなど、仕事以外の活動が許されています。
ただし、坑内労働者や児童養護施設の職員など、一定の労働者には、自由利用の原則が適用されません。
また、休憩中の外出許可制は、事業場内で自由に休息が取れるのであれば、認められています。
タイムカードほか、休憩時間の管理方法
休憩時間の打刻は法律上の義務ではありませんが、タイムカードで休憩打刻を管理したい場合もあるでしょう。
休憩時間の管理の方法には、タイムカードのほか出勤簿やエクセル、勤怠管理システムを利用したやり方があります。
とくにシフト制や変形労働時間制を採用している企業では、休憩時間が従業員ごとに異なる場合が多いため、正確な記録が必要です。
休憩時間の4つの管理方法を、メリット・デメリットを踏まえて解説します。
| 管理方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 出勤簿 | ・わかりやすい ・ 初期費用がほとんどかからない | ・記録を変更されてしまう可能性 |
| タイムカード | ・操作が簡単 ・導入コストが比較的低い | ・データの手動集計が必要 ・記録の改ざんや紛失リスク |
| エクセル | ・手軽に始められる ・関数やマクロ使用で自動集計が可能 | ・手動入力によるミスの発生 ・人数が多いとデータ処理が煩雑 |
| 勤怠管理システム | ・記録や集計が自動化 ・柔軟な勤務体系に対応 | ・導入コストがかかる |
各方法の選択は、職場の規模や勤務形態、予算に応じて適切に判断しましょう。

出勤簿で管理する場合
出勤簿を使った休憩時間の管理は、手書きで行うため、特別な機能や操作方法を覚える必要がありません。小規模な職場や従業員数が少ない職場では適した方法です。用紙と筆記具だけで始められるため、初期費用がほとんどかからない点も魅力です。
ただし、記録が手書きであるため、簡単に修正されてしまうリスクがあり、適切な管理体制が求められます。出勤簿はシンプルな方法であるからこそ、運用には注意が必要です。
タイムカードで休憩を管理する場合
タイムカードを使った休憩管理は、カードを挿入するだけで簡単に出退勤を記録できる仕組みのため、操作が直感的で分かりやすい方法です。カードを挿入するだけで打刻が可能で、導入コストも比較的抑えられ、中小規模の事業所でよく採用されています。
しかしタイムカードは、手動でデータを集計する必要があり、とくに従業員数が多い企業は管理が煩雑になります。タイムカード自体の紛失や記録の改ざんリスクもあり、フレックスタイム制やリモートワークなどの多様な働き方に対応できないのがデメリットです。
エクセルで休憩を管理する場合
エクセルを活用した休憩時間の管理は、手軽に始められる方法といえます。シートに関数や数式をあらかじめ設定したうえで、休憩の開始と終了時間を入力することで、自動で月末に集計できます。マクロを活用すると、入力エラーのチェックも可能です。
しかし、エクセルで管理すると手動入力ミスが起こりやすいのがデメリットです。従業員数が多い場合や変動的な休憩時間の場合、データの管理が難しくなります。。
エクセル管理が煩雑と感じているなら、勤怠管理システムの活用も視野に入れましょう。
勤怠管理システムで管理する場合
勤怠管理システムを活用すると、タイムカードなど従来の方法に比べて、休憩時間の管理がシンプルになります。
休憩時間の開始と終了時に、ボタンを1つ押すだけで、記録と集計までできます。休憩時間の一斉付与や、フレックスタイム制など変則的な勤務体系にも柔軟に対応できるため、管理が簡単です。
勤怠管理システムの導入や切り替えには、一定の費用がかかる点さえ解決できれば、タイムカードを使用するより、休憩時間の管理を効率化できる方法といえます。
勤怠管理システムの新規導入や乗り換えをお考えの場合は以下の資料もご覧ください。

休憩管理の管理効率化におすすめなのが、クラウド勤怠管理システムOne人事[勤怠]です。企業独自の勤務ルールに合わせた柔軟な設定が可能で、自社に適した管理と運用が実現します。One人事[勤怠]で実現できることは、当サイトよりお気軽にお問い合わせください。
→人事領域で30年の実績|「One人事」サービス資料はこちら
タイムカードで休憩時間を管理・計算する際の注意点
タイムカードを使って休憩時間を管理する場合、前提として正確な休憩時間の開始と終了の打刻が必要です。正しく記録されないと、実際の労働時間と相違が発生し、給与や残業代の計算にも影響します。以下の6つの注意点に気をつけながら休憩管理を運用しましょう。
- 集計ミスを防ぐ
- 休憩時間を切り捨てない
- 休憩は分割できる
- 基準を越えなければ残業中に休憩を与える必要はない
- 6時間以下の短時間勤務者には休憩を与えなくてよい
- 仕事から完全に離れる
集計ミスを防ぐ
タイムカードで休憩を管理する場合、ミスを防ぐための具体的な対策を準備する必要があります。
手作業ではミスが発生しやすいため、定期的に確認し、ダブルチェックをすることが重要です。
打刻漏れを早期に発見するために、データを自動で集計する勤怠管理システムの導入も検討しましょう。
休憩時間を切り捨てない
休憩時間を短縮して切り捨てる行為は、労働基準法違反となる可能性があります。同法の規定に基づくと、休憩時間は分単位で管理することが原則です。労働時間と同じように、休憩時間も丸めはできません。
休憩時間は分割も認められているものの、極端に短い数分程度の休憩では、労働から解放された時間とはみなされないため注意が必要です。
休憩は分割できる
労働基準法では、休憩時間の分割取得が認められています。 たとえば、1時間の休憩を30分ずつ2回に分けて取ることも可能です。
休憩を分割した場合、休憩時間が不足しないように正しく労働時間を管理する必要があります。
基準を越えなければ残業中に休憩を与える必要はない
労働基準法では、一定の労働時間を超えた場合に、休憩時間を付与することが義務づけられています。
残業になった場合であっても、残業時間の途中に追加で休憩を取らせる義務はありません。
しかし、従業員の体調や集中力を維持するには、状況に応じた適度な休憩が必要です。
長時間の残業が続いている場合、短い休憩を挟むことで、本人がリフレッシュできて作業効率が上がりやすくなります。
全体の生産性を上げるためにも、事業主が配慮して適度な休憩を促しましょう。
残業中の適切な休憩の設定については以下の記事もご確認ください。
6時間以下の短時間勤務者には休憩を与えなくてよい
勤務時間が6時間以下の場合、休憩時間の付与は労働基準法上、義務づけられていません。 ただし、短時間勤務であっても従業員の疲労を軽減し、業務効率を向上させるためには、適度な休憩が必要です。
業務内容が肉体的または精神的に負担が大きい場合は、6時間以下の勤務でも短時間の休憩を設けるとよいでしょう。
従業員の健康やパフォーマンスを維持するためには、業務状況や負担を考慮し、柔軟に対応することが、働きやすい職場環境の構築につながります。
仕事から完全に離れる
休憩の自由付与の原則にもあるように、休憩時間中は、従業員が業務から完全に離れ、自由に使える時間である必要があります。
休憩時間中は業務の指示を出したり、仕事を強制したりすることは認められていません。食事や自由な活動ができる状態を確保し、従業員が適切に休憩できる環境を整えましょう。

休憩の管理を怠るリスク
企業が休憩の管理を怠ってしまうと、法律違反や残業代未払いなど、さまざまな労務リスクにつながります。企業が休憩管理を怠るリスクについて4つ取り上げて解説します。
| 4つのリスク | |
|---|---|
| 労働基準法違反 | 違反時には指導・是正勧告、罰則を受ける |
| 労務トラブル・残業代未払い | 管理ミスは未払い残業代の発生に直結する |
| 労働災害 | 休憩不足で疲労・ストレスが蓄積してミスにもつながる |
| 従業員のエンゲージメント低下 | 休憩不足で個々のモチベーション低下が全体の生産性低下につながる |
適切な休憩管理は、法令遵守や従業員満足の向上だけでなく、企業の信用を守るためにも重要です。
労働基準法違反
労働基準法では、一定の労働時間を超えた場合に休憩時間の付与が義務づけられています。
法律に規定された休憩のルールが守られていないと、労働基準監督署から指導や是正勧告を受け、最悪の場合、法律違反により罰せられる可能性があります。
企業の信用が損なわれる結果にならないよう、従業員に適切に休憩を付与しましょう。
労務トラブル・残業代未払い
休憩時間の不適切な管理や記録ミスは、残業代未払いなどの労務トラブルにつながります。
従業員が実際に取った休憩時間が記録と異なる場合、正しい額の残業代が支払われず、未払い残業代が発生してしまいます。
休憩時間の切り捨てや未付与は、法律上認められません。正確な労働時間の記録と透明性のある管理が必要です。
労働災害
休憩時間が十分に取れないと、従業員の疲労やストレスが蓄積して集中力を失い、ささいなミスによる労働災害のリスクが高まります。
とくに、長時間労働が常態化している職場では深刻な問題です。職場の安全を確保するために、確実に休憩時間を確保してもらいましょう。
従業員のエンゲージメント低下
適切な休憩に入れない状況が続くと、従業員エンゲージメントが低下します。
休憩時間は疲労を回復し、モチベーションを維持して集中力を高めるための時間です。
休憩が不十分な場合、個々のパフォーマンスが悪化するだけでなく、職場全体の生産性にも悪影響を与えます。
適切な休憩管理に勤怠管理システムの活用も(まとめ)
タイムカードで休憩時間を管理する際は、適切な打刻ルールを設定し、集計ミスを防ぐ仕組みの整備が重要です。
タイムカードに休憩時間を記録すること自体は法的に決められていませんが、労働時間の管理と給与計算の正確な運用のために、法の原則を理解する必要があります。
タイムカードを基本に休憩時間の手作業で集計する場合は、ミスが発生しやすいため、勤怠管理システムの活用をおすすめします。
→クラウド勤怠管理システムOne人事[勤怠]の特長を見てみる
休憩管理もサポートするOne人事[勤怠]
One人事[勤怠]は、休憩管理にもお役立ていただける勤怠管理システムです。
- タイムカードでの管理を効率化したい
- タイムカードでの打刻漏れ・集計ミスが多い
- 法改正への対応に不安がある
タイムカードでの勤怠・休憩管理に限界を感じている企業は検討をおすすめします。
One人事[給与]と連携すれば、給与計算に自動で紐づけられるため、より速くより正確に業務を進められるでしょう。
One人事[勤怠]の初期費用や操作性については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門のスタッフが貴社の課題をていねいにお聞きしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、勤怠管理の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。勤怠管理をラクにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |