労働時間の変更手続きとは? 違法回避のポイントや必要書類、会社都合・自己都合の違いも解説
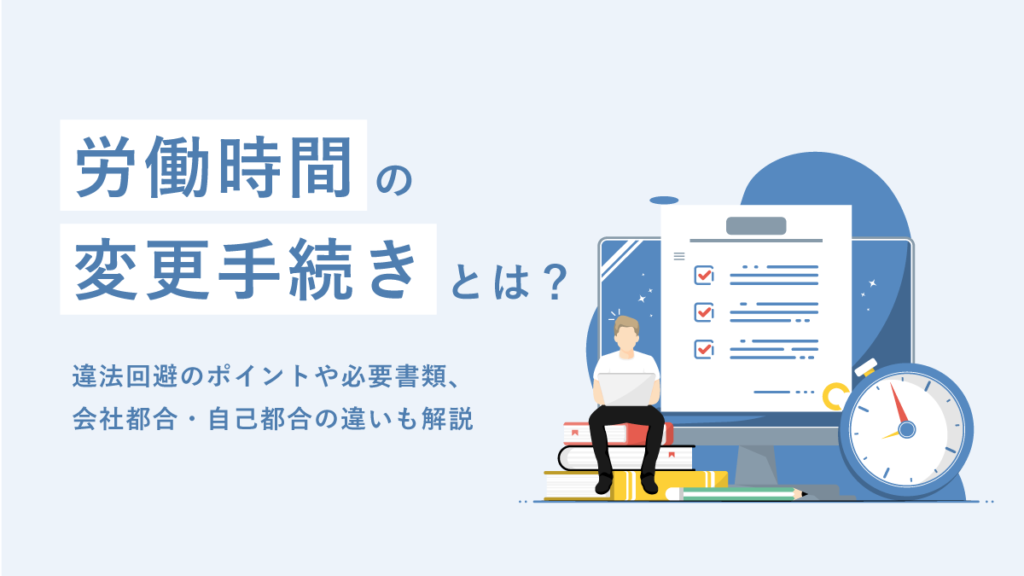
労働時間の変更手続きにおける適切な対応方法や法的リスクについて、懸念を持っている方も多いのではないでしょうか。誤った認識で進めると労働基準法に違反する可能性もあるため、正しい方法を理解して準備を進めることが必要です。
本記事では、労働時間の変更手続きの流れや違法状態にならないための注意点について解説しています。労働時間の変更に必要な書類やよくある疑問点のほか、会社都合と自己都合の場合における違いについても紹介していますので、参考にしてください。
▼労働時間の管理方法に不安がある方は次の資料もぜひお役立てください。

 目次[表示]
目次[表示]
労働時間は変更できる?
まず「そもそも従業員の労働時間は変更できるのか」について確認しましょう。基本的に、労働者と使用者間で合意ができれば、労働時間の変更は可能です。
労働契約法第3条第1項では、契約変更について以下のとおり決められています。
労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする
引用:『労働契約法』e-Gov 法令検索
ただし、変更内容は労働基準法で決められた内容に違反しない範囲でなければなりません。
労働者が不利にならないよう、従業員と適切にコミュニケーションをとり、双方合意のうえで変更することが大切です。
あらかじめ就業規則に労働時間が変更になると記載がある場合も同様に配慮が必要です。
労働時間の変更手続きを進めるためには、変更履歴の記録や従業員との合意管理が欠かせません。
労務管理システムOne人事[労務]を活用すれば、変更内容の記録や本人への通知などを一元管理できます。労働契約関係の管理と透明性を確保するため、システムの導入を検討するのも検討してみてはいかがでしょうか。
→One人事[労務]で実現できることも紹介|「One人事」サービス資料を見てみる

雇用形態に限らずパート・アルバイトにも適用される
労働時間の変更は、正社員に限らずパート・アルバイトにも適用されます。本人から合意を得られたのであれば、労働時間を変更することも可能です。
ただし、労働時間の短縮によって、雇用保険などの被保険者資格を喪失する可能性があることに注意しなければなりません。
社会保険の被保険者資格から外れる場合は、喪失手続きが別途必要になります。誤って資格喪失後も保険料が給与から天引きされてしまう事態にならないように注意しましょう。
会社都合による不利益な労働時間の変更は違法?
会社都合による労働者に不利益な労働時間の変更は、労働契約法に違反し、違法となる可能性があります。
労働時間の変更が可能といっても、会社が勝手に従業員の同意を得ないまま突然労働時間を変えることは認められません。
従業員の不利益となる変更例は以下のとおりです。
- 労働時間の短縮によって支払われる賃金大幅に減ってしまう
- 労働時間が増えたにもかかわらず賃金が変わらない
このような状況を防ぐためにも従業員とよく話し合い、本人の意向を考慮しない労働時間の変更は避けましょう。
会社都合の変更は休業手当の支払い対象になることも
もし会社都合で労働時間を変更すれば、別途、休業手当を支払わなければならないこともあります。
労働基準法第26条では賃金が平均の60%未満となる場合、休業手当の支払いが必要と定められています。
第二十六条使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
引用:『労働基準法』e-Gov 法令検索
どのような例が考えられるか気になりますよね。具体的には以下のケースが代表例として挙げられます。
- 業務縮小によって、一定期間店舗を休業するように命じられた
- 売り上げが悪化し、想定していた労働時間での勤務が難しくなった
ただし、自然災害をはじめ不可抗力のアクシデントによる休業では、会社に休業手当の支払い義務はありません。
実際に休業手当を支給して労働時間を変更する際も、従業員との話し合いは必須です。合意を得られるように、ていねいな説明を心がけましょう。
▼休業手当の計算方法をシミュレーションするには以下の記事もお役立てください。
労働時間の変更手続きと手順・必要書類
実際に従業員の労働時間を変更するにはどのような手続きを踏めばいいのでしょうか。
大前提として「なぜ労働時間を変更するのか」 を明確にしたうえで手続きを進めましょう。会社都合であっても、業務上の必要性など納得感があるものを整理することが重要です。
労働時間の変更には就業規則の変更をともなうため、公的な届け出も必要です。手続きに不備があり、のちの労務トラブルにつながらないよう、以下の流れに沿って慎重に進めましょう。
- 就業規則の項目を修正する
- 労働者代表の意見を尋ねる
- 「就業規則(変更)届」を作成する
- 労働基準監督署へ書類を提出する
- 変更後の就業規則を従業員に周知する
順を追って注意点を確認していきます。
就業規則の項目修正する
就業規則の所定の労働時間(就業時間)の欄を、変更後の労働時間に合わせて修正します。条文は誰が読んでも内容を理解できるように、対象者や時間、変更日をはっきりと明示することがポイントです。
労働者代表に意見を聴く
次に作成した新しい条文を労働者代表に確認してもらい、意見書を作成してもらいます。労働基準法第90条に基づき、就業規則の変更には「過半数労働組合、過半数労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者」の意見を聴取する義務があります。
第九十条使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
引用:『労働基準法』e-Gov 法令検索
労働者代表は監督または管理の立場にない人でなければなりません。使用者側から目的を明らかにしたうえで、挙手や投票で選ばれた人を選出します。
労働者代表から反対意見があっても、意見を聞くことが義務であり、同意が必要なわけではありません。ただし繰り返しになりますが、変更が従業員に著しく不利益を与えると判断された場合は、労務トラブルや裁判に発展する可能性があるため再検討が必要です。
就業規則(変更)届を作成する
続いて、就業規則を変更するために「就業規則(変更)届」を作成します。
就業規則(変更)届には、改正前と改正後の変更事項、事業場名と所在地、業種と労働者数などを記載します。労働者代表の意見書も添付しましょう。
作成後は、必要な書類を2部ずつ印刷するのを忘れずに対応します。
書類を労働基準監督署に提出する
就業規則(変更)届書を記載したら、管轄となる労働基準監督署に以下3種類の書類を提出します。
【必要な書類】(各2部ずつ準備)
| 変更後の就業規則 | ・就業規則の「所定労働時間」に関する項目を変更し、最新の労働条件を反映した規定を明記 |
| 意見書 | ・労働者代表に新しい条文を確認してもらった際に作成する書類 ・変更内容に対する意見(賛成・反対など)を記載 ・特に意見がない場合は「意見なし」と記載 |
| 就業規則(変更)届 | 厚生労働省が提供するフォーマットを使うと便利 |
提出は「書面提出」「郵送提出」「電子申請」のいずれかで可能です。変更届は2部のうち1部は返却されるため、なくさないよう会社で厳重に保管しておきましょう。
変更後の就業規則を従業員に周知する
労働基準監督署の手続きが完了したら、従業員に変更内容を周知します。主な周知の方法は以下の3つです。
- 全従業員が見やすい場所に記載すること
- 印刷して従業員に配布できる状態であること
- 電子媒体に記録し常時画面等で確認できること
不明点の問い合わせ先も明記するようにしましょう。
労働時間を変更する際のポイント・注意点
労働時間を変更する際には、従業員との合意形成・法令遵守・公平な対応が欠かせません。
ここでは手続きにおいて意外と見落としがちなポイントを整理し、実務担当者が確実におさえておきたい注意点を解説します。
話し合いのうえ、従業員の事情も考慮する
労働時間の変更は、従業員にとって大きな影響を与える可能性があるため、事前に十分な話し合いを行い、納得を得ることが重要です。
面談では従業員側の事情も考慮する必要があります。
- 変更による収入への影響(所得制限・扶養控除の適用可否)
- 家庭の事情(育児・介護・通勤時間など)
- 変更後の働き方についての希望
ヒアリングしたうえで、意見を反映させる対応も視野に入れましょう。
一方的な通達にならないよう、変更が会社の都合だけにならないよう、従業員の意見を尊重することも大切です。一部の従業員だけが不利益を受ける変更にならないよう配慮しましょう。
万一、従業員にとって不利益な時間変更をしなければならない場合、変更に合理性があり、変更後の就業規則が労働者に周知されていなければなりません。慎重に対応しましょう。
労働基準法などに準拠しているか確認する
労働時間の変更は、労働基準法を遵守する範囲内で行わなければならず、違反があれば無効 となります。主に以下の点をチェックします。
- 1日 8時間・週40時間の法定労働時間を超えていないか
- 変更により 休憩時間が適切に確保されているか
- 少なくとも毎週1日か4週間に4日以上の休日を与えているか
労働代表者の意見を求める前に、違法性について法的チェックを行います。
同一労働同一賃金の原則に反しない
パート・アルバイトの労働時間を変更する際は、正社員と同じ業務をしているのに待遇差が生じないかを確認しましょう。
「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」第8条で、禁止されている行為だからです。
参照:『短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律』e-Gov 法令検索
【チェックポイント】
- 同じ業務・責任があるのに、労働条件に不合理な差があるのは違法
- 勤務時間の変更が、待遇の差別につながらないよう配慮が必要
待遇差が不合理な場合、あとから労務トラブルになる可能性が高いため、変更前に確認が必要です。
不利益な変更でも合理性があれば認められる場合がある
たとえ従業員にとって不利益な変更だとしても、合理性がある変更だと認められるケースがあります
具体的には業績や経営状況を踏まえて、就業規則を変更する必要性があると感じられたケースです。
- 業績悪化による労働時間変更
- 働き方改革推進にともなう全社的な就業時間の見直し
- 従業員にとってのメリット(例:長時間労働の抑制)をともなう変更
- 法改正などにともなう変更
- 合併による労働条件を同一にするための変更
ただし「合理性があるから変更OK」と一方的に進めず、必ず対象者への説明が必要です。納得してもらえるように説明したり、必要に応じて代替案を検討したりしましょう。
「不利益変更」とは、労働時間の変更により、従業員が何らかの不利益を被ること です
同意しない従業員にも不利益変更は適用される
就業規則で変更が完了してしまうと、同意がなかった従業員にも変更後のルールは適用されます。突然の適用ではトラブルのもとになるため、事前に十分な説明が必要です。
周知を怠ると「そんな話は聞いていない」とトラブルに発展しやすくなります。一定の期間を設けて事前に告知し、必要に応じて個別対応の時間を確保しましょう。
労働時間の変更に関する疑問
労働時間の変更に関しては、企業・従業員のどちらの立場でも、「どこまで変更が許されるのか?」 「拒否された場合はどう対応すればいいのか?」など、さまざまな疑問が生じるものです。
最後に、変更に関するよくある疑問・質問と回答をわかりやすく解説します。
従業員の自己都合による労働時間の変更はできる?
従業員側から労働時間の変更について申し出があった場合は、話し合いを踏まえたうえで適切な判断をします。必ずしもすべてを企業側が応じる義務はありません。
企業側が変更を受け入れるかどうかは、業務への影響を考慮して判断するのが一般的です。要望をかなえることで、職場全体に支障が出るなら、企業側は断ることが可能です。
【主な拒否理由】
- 業務シフトが成り立たなくなる場合
- 他の従業員に負担がかかる場合
- 企業の生産性や業務効率に悪影響がある場合
ただし会社が申し出を断った場合、従業員は退職の道か、現在の労働時間で働くか、選択を迫られるでしょう。一方的に拒否するのではなく、代替案を調整するのも一案です。
変形労働時間制の労働時間変更は違法?
変形労働時間制を導入している企業では、基本的に労働時間の変更はできません。違法性が疑われます。
変形労働時間制では、事前に決められた労働時間で運用することが前提になっているためです。労働基準法にその旨が記載されています。
ただし例外として、地震・台風などの災害発生時や正当な理由がある場合は認められる可能性もあります。労務管理の専門家や社会保険労務士に相談しながら慎重に対応を検討しましょう。
労働時間の変更を強制できる?
企業側が従業員に対して、労働時間の変更を強制できません。労働条件の変更は、労働者の納得に基づいて行われるべきものです。
労働時間の変更手続きは、基本的に従業員と企業で双方合意が必要です。拒否しているのに強引に進めたり、突然変更通知したりすることはできません。
労働時間の変更を拒否されたらどうする?
企業側が労働時間の変更を提案しても、従業員が拒否するケースもあります。
考えられる拒否の理由は「家庭の事情(育児・介護など)」「通勤時間の都合」「収入への影響」です。
労働時間の変更を従業員から拒否された場合は従業員からの合意が得られないため、変更をすることは難しいでしょう。
拒否されたらまず「なぜ変更が必要なのか?」を具体的に説明し、本人の意見を聞きます。代替案を提示するのも一案です。双方が納得できるのが大切なので、無理に押し通さず、調整方法を探るのが賢明な対応といえるでしょう。
まとめ|労働時間の変更手続きのポイントは双方の合意と合理性
労働時間の変更は、基本的に従業員を含めた双方の合意が必要です。
万一、従業員にとって不利益な変更内容だったとしても、内容に合理性があれば認められる可能性がある点もポイントです。
本記事で紹介した内容を参考にして、労働時間の変更をする場合は、従業員と対話を重ね、双方が納得したうえで進めるようにしましょう。
労働契約の管理を電子化|One人事[労務]
One人事[労務]は、煩雑な労務管理をクラウド上で完結させる労務管理システムです。
- 【行政手続き】転記・参照ミスが多い
- 【年末調整】記入漏れ・修正対応に追われている
- 【退職手続き】離職証明書の作成が面倒
担当者の業務効率化を助けて手間を軽減。ペーパーレス化や工数削減、コア業務への注力を支援しております。
One人事[労務]の初期費用や気になる操作性については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門スタッフが、貴社の課題をていねいにお聞きしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、労務管理の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードしていただけます。労務管理をシンプルにして「本来やりたい業務」に集中したい企業は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |
