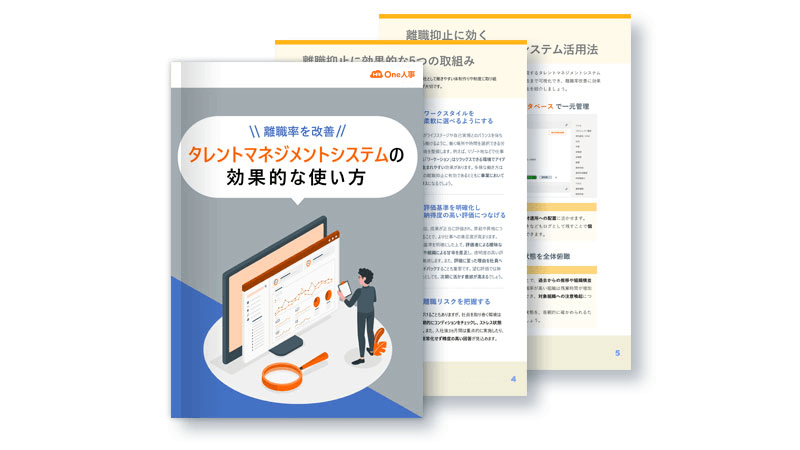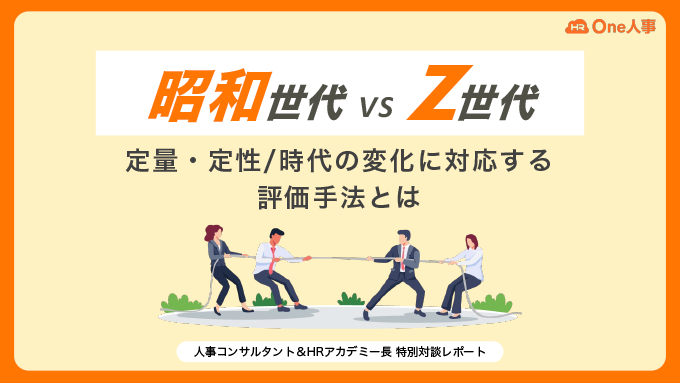びっくり退職とは? 優秀な人材や中堅が突然辞める理由や対策方法を解説

ある日突然、優秀な社員が辞めて驚いたという経験はありませんか。 何の前触れもなく退職を切り出され、引き継ぎもできず現場が混乱するのが「びっくり退職」です。残されたメンバーの士気まで下がってしまい、「次に辞めるのは誰か」という不安も広がります。
本記事では、びっくり退職の背景や主な原因、見逃しやすい兆候、未然に防ぐための対策をわかりやすく解説します。従業員が安心して働き続けられる組織づくりに、お役立てください。
 目次[表示]
目次[表示]
びっくり退職とは?
びっくり退職とは、従業員が突然、退職を申し出ることを指します。とくに周囲からは問題なく見えていた社員が、ある日いきなり「辞めます」と伝えてくるのです。
たとえば「明日から来られません」「今月で辞めさせてください」と、引き継ぎの猶予もなく退職を申し出るケースも少なくありません。結果として、業務調整や人員確保に追われ、企業運営に大きな影響を与えてしまいます。
優秀な人材や中堅が突然辞めるリスク
びっくり退職で優秀な人材や中堅社員が、突然会社を去るインパクトは、決して小さくないでしょう。とくに重要なポジションを担っていた場合、業務の停滞が停滞し、残された社員の負担も一気に増します。
さらに厄介なのは、びっくり退職が連鎖することです。「自分も辞めたいと思っていた」「あの人が辞めたなら自分も」と、不安や焦りが広がり、次々と退職者が出るケースもめずらしくありません。
最近では、SNSで社外のネットワークを使い、気軽に転職相談ができるため、社内では兆候を察知しづらくなっています。「相談されて気づく」ケースは少ないのではないでしょうか。
びっくり退職は、組織の成長を止めて、従業員のモチベーションを下げる要因となります。企業には、一人ひとりに対する日頃のコミュニケーションと、退職のサインを見逃さない管理体制が求められています。
▼離職防止のヒントを知るなら、以下の資料をご活用ください。
びっくり退職の主な原因
表面上はびっくり退職の原因は通常の退職とそれほど大きく変わりませんが、表面化するタイミングが突然である点が異なります。びっくり退職を引き起こす主な原因について詳しく見ていきましょう。
給与に対する不満
給与への不満は、びっくり退職を招く理由として上位に挙げられます。単に「給料が安い」だけでなく、「努力や成果が正当に評価されていない」と感じたとき、不満はより深刻に感じられるでしょう。
たとえば、サービス残業や昇進による手当カット、待遇に見合わない役職責任などです。評価面談が形骸化していれば、従業員は「頑張っても報われない」と感じ、外へ目を向け始めます。
生活に直結する給与への不満は、転職を即決する引き金になりやすいのです。
給与以外の労働条件に対する不満
長時間労働や業務過多など、労働環境への不満も「びっくり退職」の大きな要因です。
とに「改善の見込みがない」と感じたとき、突然退職を決断するケースが多く見られます。
有休が取りにくい、常にギリギリの人数で回している、休んでも仕事が減らないという状態が続けば、従業員は限界を迎えます。
職場環境が変わらないと判断されると、ある日を境に退職の決意が固まってしまっても無理はありません。
業務内容とのミスマッチ
入社前に描いていた仕事と、現実の業務がかけ離れている。そんなミスマッチが、びっくり退職のきっかけになることもあります。
自分の志向やスキル・経験に合わない仕事を任され続けると、不満が募っていきます。
また、 ミスをした新入社員が「報告したら怒られてしまう」「自分には適性がなかった」と感じて相談もできないまま退職を決意するケースもあるようです。
とくに若手ほど、職務内容への納得感を大事にする価値観が広がっています。
▼コロナ化以降、Z世代の転職志向は高まっているといわれています。Z世代に向けた評価手法を検討するなら、以下の資料もご活用ください。
▼採用ミスマッチ防止には、以下の資料をご活用ください。
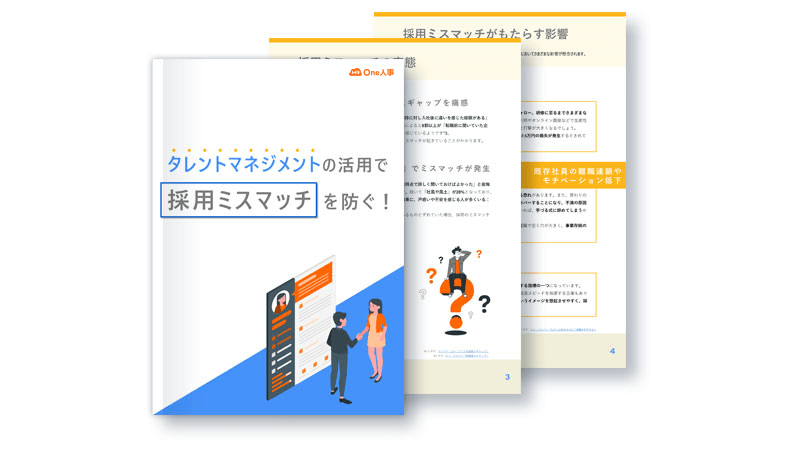
人間関係のトラブルやストレス
職場の人間関係も、びっくり退職につながる代表的な原因の一つです。とくに、苦手な上司の存在やハラスメントがあると、限界を迎えた社員は突然退職を申し出ます。
表面上はうまくやっていても、じつは誰にも相談できず孤立していたというケースも少なくありません。また、業務分担の不公平感や、チームとの温度差もストレスを蓄積させます。
当事者が一人で抱え込んでしまわないように、1on1など定期的な対話の場が必要です。
▼on1ミーティングの進め方に困っているなら、以下の資料もぜひご活用ください。
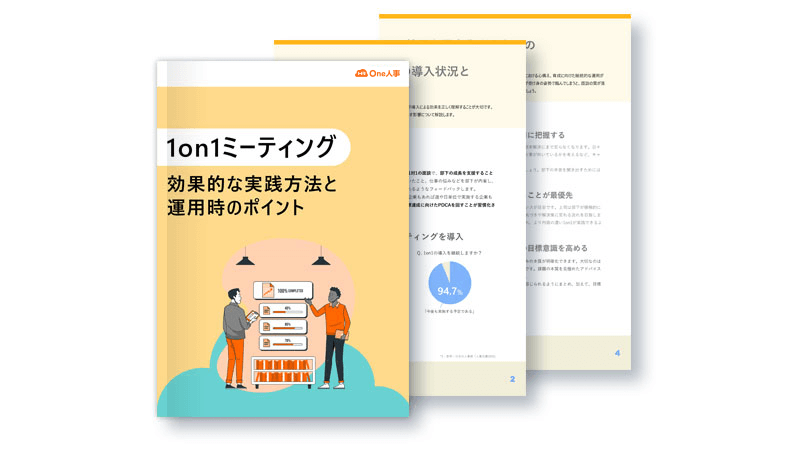
キャリアに対する不安や停滞感
「ここにいても成長できない」と感じたとき、従業員は市場価値を高めるために、職場を離れます。
- 昇進の機会がない
- 挑戦できる仕事が回ってこない
- 自分の能力や価値が認められない
- 将来が見えない
- 専門性が極められない
以上のような不安は、やがてびっくり退職へとつながります。
成長意欲の強い人材ほど、現状維持には耐えられません。 適切なフィードバックやキャリア支援が不十分な場合、成長とキャリア安全性を求め、転職を検討するようになるでしょう。
びっくり退職を防ぐには、日常のなかでキャリアの手応えを持たせることが重要です。
▼退職防止のヒントを知るなら、以下の資料をご活用ください。
ヘッドハンティング
優秀な中堅社員に多いびっくり退職の理由が、他社からのヘッドハンティングです。市場価値の高い人材ほど、他社から魅力的な待遇でのオファーを受けるのは当然のことです。
なかでも競合他社からの直接オファーは、会社には切り出しにくいため、結果的に突然の退職表明につながりやすくなります。
終身雇用が当たり前ではなくなった今、優秀な人材は常に他社から声がかかる存在です。企業は人材が引き抜かれるリスクを認識し、流出を防ぐ対策を講じなければなりません。
過度なプレッシャーやストレス
知らず知らずのうちに、業務のしわ寄せが一部の従業員に集中していませんか。
責任感の強い人ほど、過度なプレッシャーを抱え、無理をしてしまいます。人に頼るのが苦手で、「NOと言えない」タイプの社員は、表面上は問題なく働いていても、内側でストレスをため込みがちです。
どんなに疲れていても仕事を断らず、しかし完璧主義のため、ミスを恐れて自分を責める。そうして限界が来たとき、静かに突然辞めていきます。
問題がなさそうに見える真面目で誠実な人ほど、注意深くフォローすることが大切です。
びっくり退職のよくある兆候
びっくり退職は突然に見えても、じつは何らかのサインを発しているものです。予兆を早期にキャッチし、適切に対応することで、突然の退職を防げる可能性もあります。見逃しやすい代表的な兆候を紹介します。
新しい業務へのモチベーションが低下する
新しい業務への関心や意欲が急に薄れるのは、びっくり退職の初期サインとしてよく見られます。
たとえば、これまで前向きだった社員が、新規プロジェクトの話に乗り気でなくなったり、会議での発言や提案が目に見えて減ったりします。
仕事の進め方にも変化があらわれ、ミスが増える、納期ギリギリまで動かないなど、長期的な関与を避ける行動が目立つこともあるでしょう。
数か月先を見据えた案件に対し、消極的な様子が見られたら、すでに気持ちは外を向いているかもしれません。
遅刻や早退などが増加する
勤怠の乱れは、行動であらわれるわかりやすい変化の一つです。とくに、普段は時間にきちんとしていた社員の遅刻・早退が続くようになったら注意しましょう。
たとえば、以下のような変化が見られます。
- 定時退社が増える(以前は残業していた人が急にぴったり帰る)
- あいまいな理由の遅刻が増える
- 突然の早退・半休が目立つようになる
- 単発の休暇取得が続く
以上のびっくり退職の兆候は、転職活動のスケジュール調整や、メンタル面での負荷が高まっている可能性を示唆しているかもしれません。背景に目を向けてみるのも一案です。
身だしなみに気を使わなくなる
外見の変化も、びっくり退職に向けた気持ちの変化を反映します。従業員の身だしなみに、次のような変化が見られたら注意が必要です。
- 以前より服装がラフになった、乱れが目立つ
- 髪型や化粧を気にしなくなった、清潔感が下がった
- 反対に、普段よりきちんとした格好で出社してくることが増えた
急に身なりが整うのは、面接に行く途中、もしくは帰りであるかもしれないサインです。髪を暗く染め直すなど、ちょっとした変化にも目を配りたいところです。
周囲とのコミュニケーションが減少する
コミュニケーションパターンの変化は、びっくり退職の兆候の一つです。周囲と話さなくなった人は、何かを抱えているかもしれません。
- 会議での発言が減った
- 雑談に加わらなくなった
- ランチを一人で取るようになった
同僚との心理的な距離は、退職を決意した人が無意識に職場から離れようとする行動です。
また、1on1ミーティングを避ける、上司への報告が減るなど、上司との接点を減らす傾向も見られます。
反対に、急に明るくなったり、前向きになったり積極性が高まるケースもあります。退職への気持ちが固まって「吹っ切れた」状態かもしれません。
▼退職防止のヒントを知るなら、以下の資料をご活用ください。
びっくり退職を防ぐための対策
仮に兆候をキャッチできたとして、どのように対応すればびっくり退職は防げるのでしょうか。未然に防ぐため、日頃から取り組みたい基本的な離職対策を7つ紹介します。
- 個別ヒアリングの機会を設ける
- 適切なフィードバックや評価を実施する
- 業務負荷の偏りをなくす
- 理想のキャリアの実現をサポートする
- 従業員のメンタルヘルスをケアする
- 社内コミュニケーションを促進する
- タレントマネジメントシステムを活用する
現場で今日から実践できるヒントとして、ぜひ参考にしてください。
個別ヒアリングの機会を設ける
びっくり退職につながる従業員の小さな変化に気づくには、定期的に個別でじっくり話す機会を設けましょう。
1on1ミーティングを通じて、業務の悩みやキャリアの不安、人間関係のモヤモヤなど、部下の本音に近い部分を引き出していくことがポイントです。
とくに大切なのは、相談しやすい関係性の土台づくりです。単に「困ってることある?」だけでは本音は出てこないため、日頃から安心して話せる雰囲気づくりを意識します。
対話を継続することで、本人すら言語化できていない違和感に気づき、サポートを提案できるかもしれません。
適切なフィードバックや評価を実施する
日常的なフィードバックと公正な評価の仕組みが、びっくり退職の防止にも欠かせません。
評価のタイミングだけでなく、業務のなかでこまめに声をかけ、「〇〇の対応は助かったよ」「次回こうするともっと良くなるね」といった具体的な言葉で、本人の貢献や成長を認識しているとを伝えることが大切です。
また、全社的に評価の軸があいまいだと不信感が募ります。納得感のある基準を提示し、評価結果は一方的に伝えるのではなく、振り返りと今後の期待も含めてていねいにフィードバックしましょう。
業務負荷の偏りをなくす
びっくり退職を防ぐためには、業務量を可視化し、偏りを平準化する工夫が必要です。勤怠管理データや日報などを通じて、労働時間や残業の状況を定期的にチェックし、過重労働の兆しを見逃さないようにしましょう。
忙しい人ほど「頼めばやってくれる」存在になりがちです。マネージャーが意識的に業務配分を見直し、必要であれば業務フローの改善や人員の補充を検討することも重要です。日頃から、休みやすさも含めた働きやすい環境づくりを意識しましょう。
理想のキャリアの実現をサポートする
びっくり退職を防ぐためには、従業員一人ひとりの理想のキャリア像を把握し、応援する姿勢を明確に示すことが重要です。
たとえば定期的な1on1で将来の希望や悩みを聞き、社内でのキャリアパスやスキルアップの機会を提示しましょう。企業には「頑張り続ける理由」を提示する取り組みが求められます。
「ここにいれば成長できる」「挑戦できることがある」と思ってもらえる環境づくりが、びっくり退職の防止につながります。
従業員のメンタルヘルスをケアする
びっくり退職の理由のなかには、表に出にくいメンタル不調が隠れていることもあります。 とくに真面目で責任感が強い従業員ほど、限界まで頑張ってしまい、ある日突然「もう無理です」と退職を申し出るケースが少なくありません。
事態を防ぐには、日ごろから従業員の心理的な変化に気を配り、必要に応じてケアの機会を設けることが重要です。
ストレスチェックや産業医との面談、外部カウンセラーの利用など、心の健康を支える仕組みを整え、従業員が孤立せずにいられる環境を整えましょう。
「一人で抱え込まなくていい」と感じられる職場は、びっくり退職のリスクを下げてくれます。
▼メンタルヘルスケアの具体的な方法を知るには、以下の記事もご確認ください。
社内コミュニケーションを促進する
社内コミュニケーションが希薄な職場では、一人ひとりの悩みが見えにくいため、びっくり退職防止には、日常的な対話と情報共有の活性化が重要です。
上司と部下が業務以外でも気軽に話せる関係性を築いておくことは、ちょっとした違和感や悩みを拾い上げるうえで意味を持ちます。部署間交流を促すイベントや雑談を交えたミーティングも有用でしょう。
また、匿名の提案制度など従業員の声が届く仕組みを整えることも大切です。経営層からも積極的に発信し、企業運営の透明性を高めることで、会社に対する帰属意識の向上にもつながります。
タレントマネジメントシステムを活用する
タレントマネジメントシステムの活用も、びっくり退職を防ぐうえで効果的な手段の一つです。
たとえば、残業時間の急増、評価の低下、エンゲージメントスコアの悪化といった傾向を複合的に把握することで、「離職の予兆」に気づきやすくなります。また、過去の退職者データを分析することで、退職リスクの高いパターンをあらかじめ把握することも可能です。
個人単位だけでなく、部署やチームごとの傾向も可視化できるため、組織全体の状態を客観的に捉えられ、的確な対策につなげられるでしょう。
▼離職防止策を詳しく知るには、以下の資料もご活用ください。
タレントマネジメントシステム|One人事[タレントマネジメント]
One人事[タレントマネジメント]は、従業員一人ひとりの情報を一元管理・分析することで、退職リスクの高い従業員の早期発見にも役立つ、タレントマネジメントシステムです。
勤怠状況や人事評価、1on1の記録、アンケート結果などのデータを集約して管理し、可視化します。蓄積したデータにより退職傾向の分析も可能で、離職対策の検討にもお役立ていただけます。
→離職防止に役立つタレントマネジメントシステムの活用例は【こちら】
▼One人事[タレントマネジメント]で実現できることもわかる。サービス紹介資料は以下よりご確認ください。

従業員から突然退職を切り出された場合の対処法
ある日突然退職の意向を告げられた場合、つい反射的に引き止めたくなるかもしれません。しかしまずは、冷静に耳を傾けることが大切です。
退職の申し出があったとき、最初にやるべきことは、相手の話をしっかり聞くこと。会社の事情を伝えるのは後回しで構いません。まずは「どうして今、退職を考えているのか」をていねいに聴く姿勢が求められます。
例として、忙しすぎるといった理由の裏には、業務への適性に対する不安が隠れていることもあります。「給与に不満がある」と言いつつ、本音は「努力が正当に評価されていない」と感じているのかもしれません。
本音を引き出すためには、次のような姿勢を意識しましょう。
- 感情的にならず、落ち着いて対応する
- 話を途中でさえぎらず、最後まで聞く
- 相づちやうなずきで、傾聴の姿勢で臨む
- 必要に応じて質問を挟み、背景を深掘りする
相手の気持ちや状況を正しく理解できれば、「もう少し頑張ってみよう」と思い直してくれることもまったくないわけではありません。仮に引き止めが難しくても、円満退職や今後の改善策の検討につなげられるはずです。
▼傾聴力を高めるには、以下の記事もご確認ください。
まとめ|予兆をキャッチしてびっくり退職を回避
びっくり退職は、業務の混乱だけでなく、職場全体の士気や信頼関係にも深刻な影響を与えます。 しかし、日々のコミュニケーションや従業員データの活用によって、予兆をキャッチし、未然に防ぐことは十分に可能です。
大切なのは、退職の意志表明より前のサインを見逃さないことです。 日頃の対話やヒアリング、タレントマネジメントシステムによるデータ分析を通じて、従業員の小さな変化を拾い、早期に対応していく姿勢が求められます。
それでも突然の申し出があった場合には、冷静に理由を聞き、必要に応じて引き留めも検討しましょう。
びっくり退職をゼロにできなくても、信頼と対話を積み重ねることでリスクは下げられます。従業員が「ここで働き続けたい」と思える環境づくりが、最大の離職対策です。
びっくり退職であわてる前にできること
びっくり退職の防止には、タレントマネジメントシステムの活用もおすすめです。
One人事[タレントマネジメント]は、社内の人材情報を一元管理し、一人ひとりに適した育成や配置をサポートするサービスです。1on1の記録管理やエンゲージメントサーベイの実施、退職傾向の分析など、多岐にわたる離職対策にもお役立ていただけます。
One人事[タレントマネジメント]の初期費用や気になる操作性については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門スタッフが、自社の課題をていねいにヒアリングしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、人事労務の効率化のヒントが詰まったお役立ち資料を無料でダウンロードしていただけます。入社から退社まで人の情報管理をシームレスに行いたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |