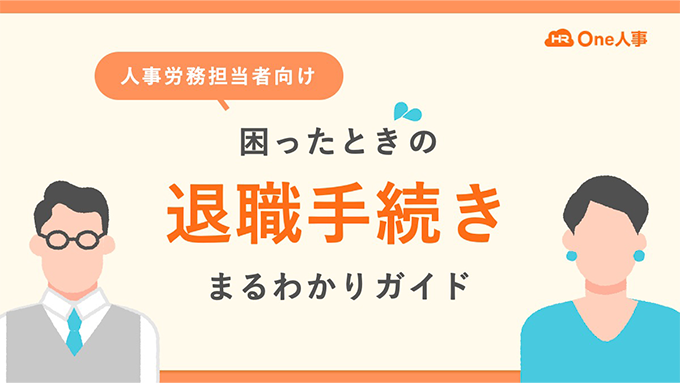労働基準法の解雇ルールについて実務に影響する条文を解説
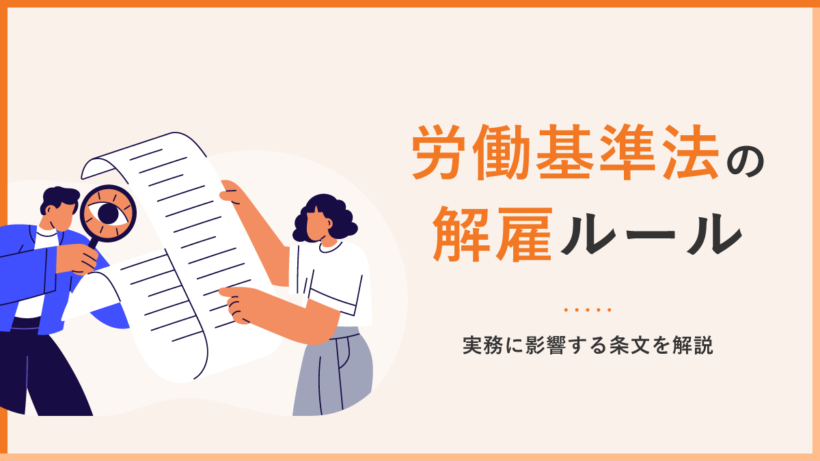
労働基準法には解雇について厳格なルールが定められ、企業が守らなければ不当解雇としてリスクが発生します。
- この社員を解雇にしてもよいのか?
- 手続きを間違えると労務トラブルになるのでは?
そんな不安を抱えて本記事にたどり着いた方もいるでしょう。人事担当者や経営層にとって、「どの理由なら解雇できるのか」「手続きで何に気をつけるべきか」は、状況によって迷いが生じやすいテーマです。
本記事では、労働基準法と関連法規に基づく解雇のルールをわかりやすく解説します。解雇リスクを最小限にし、万一の事態に対応するためのガイドとしてお役立てください。
→退職手続きを効率化|「One人事」の資料を無料ダウンロード
▼退職手続きに全般に不安がある方は、いつでも見返せるように、以下の資料もぜひご活用ください。
 目次[表示]
目次[表示]
解雇と法律
解雇とは、使用者が労働者と結んだ雇用契約を一方的に終わらせることです。しかし、企業が「辞めてもらいたい」と思っただけでは、当然すぐに解雇はできません。
労働契約法第16条では、正当な理由がなければ解雇は無効と定められています。
加えて労働基準法第19条では、解雇にあたって30日前までに予告する義務が定められています。
つまり、企業が従業員を解雇するには「理由」と「手続き」の両方が法律に適合していなければならないのです。
参照:『労働契約法第16条』e-Gov法令検索
参照:『労働基準法第19条』e-Gov法令検索
解雇の種類
解雇を大きく分類すると、普通解雇と懲戒解雇、整理解雇と3つの種類があります。それぞれの解雇の特徴を解説します。
| 解雇の種類 | 特徴 |
|---|---|
| 普通解雇 | 労務提供という債務の不履行 |
| 懲戒解雇 | もっとも重い制裁処分 |
| 整理解雇 | 経営悪化などによる人員削減 |
普通解雇
普通解雇とは、従業員が労働の提供義務を果たせない場合にする解雇です。労務提供とは「決められた仕事を、一定の基準で遂行すること」を意味します。
具体的には以下のケースです。
- 能力不足:期待された水準の業務遂行ができない
- 健康上の問題:病気やケガにより長期間労務提供が困難
- 勤務態度不良:繰り返す遅刻や欠勤、業務命令違反
従業員は、企業に労働力の提供を約束して雇用契約を結んでいます。何らかの理由で従業員が業務遂行できていないと、企業との契約内容を満たしておらず、債務不履行と判断されて解雇に至ることがあります。
懲戒解雇
懲戒解雇とは、従業員の問題行動を理由とした解雇です。従業員による重大な犯罪行為や極めて悪質な行為が、企業側に大きな損害を生じさせたケースが該当します。
従業員が企業の秩序に著しく違反した場合、該当の従業員に対して、企業はもっとも重い処分である懲戒解雇を実行できます。
具体的には以下の行為が該当します。
- 横領・窃盗などの犯罪行為
- 重大なセクハラ・パワハラ
- 企業機密の漏えい
- 無断欠勤の常習
懲戒解雇を決定するには、就業規則や労働条件通知書に懲戒事由を規定しておかなければなりません。問題行動が本当に懲戒解雇に該当するか否かは、慎重な検討と証拠が必要な点にも注意しましょう。
整理解雇
整理解雇とは、経営不振など企業側の事情で人員削減を実施する解雇です。整理解雇は、企業が経営を継続させるためにやむを得ない対応です。従業員に非がないため、とくに厳しい条件が求められています。具体的には原則として以下の4要件をすべて満たさなければなりません。
人員削減の必要性
整理解雇では、人員削減を正当化する理由が必要です。業績悪化や財務状況など、客観的な数字に基づき、人員削減の必要性を示さなければなりません。単純に「人件費を減らしたい」や「業績が去年より下がった」といった理由だけでは認められない点に注意しましょう。
解雇回避努力の実施
整理解雇を実施する前に、企業が十分な解雇回避努力をしたことが問われます。たとえば配置転換の実施や希望退職者の募集、役員の報酬削減です。企業は可能な限り、人員削減を避けるための手を尽くす必要があります。
人選の合理性
解雇対象者の選定では、客観的で合理的な基準に基づく判断が必要です。年齢や勤続年数、成績、会社への貢献度など明確な基準を設けましょう。主観的な人選は認められません。
解雇手続きの妥当性
整理解雇を実施する企業は、人員削減をしなければならない状況や経緯について、従業員や労働組合に十分に説明しなければなりません。具体的な解雇対象者の基準や時期、規模についても説明し、理解を得られるよう努めましょう。
労働基準法の解雇に関する条文
労働基準法には、解雇に関する条文がいくつもあり、内容が複雑だと感じる方も多いのではないでしょうか。そこで以下では、実務に関係の深い条文に絞って、ポイントをわかりやすく解説していきます。
- 労働基準法第15条1項:労働条件の明示
- 労働基準法第19条:解雇の制限
- 労働基準法第20条:解雇予告と手当
- 労働基準法第22条:退職時の証明
- 労働基準法第89条:就業規則の作成・届出
- 労働基準法第104条:通報者の保護
- 労働基準法第3条:均等待遇
「どの場面でどんな対応にかかわるのか」確認していきましょう。
労働基準法第15条1項:労働条件の明示
労働基準法第15条1項では、解雇事由を含めた労働条件の明示について定めています。採用時は解雇の事由を含む労働条件を明示しなければなりません。
なお、労働条件の明示は書面が原則です。雇用契約書や労働条件通知書に解雇事由について記載して交付しましょう。あいまいな表現は見直しが必要です。
労働基準法第19条:解雇の制限
労働基準法第19条では、解雇制限について定めています。次のような状況にある従業員は、一定の期間において原則として解雇はできません。
- 業務上の傷病による休業期間中と、その後30日間
- 産前産後休業中と、その後30日間
天災など企業経営が著しく困難な事情がある場合は例外です。
労働基準法第20条:解雇予告と手当
労働基準法第20条では、解雇予告の義務と解雇予告手当の支払いについて定めています。企業が従業員を解雇する際は、30日以上前に解雇予告をしなければなりません。30日を下回る場合は、不足日数分の平均賃金を「解雇予告手当」として支払う必要があります。
第20条の規定は、「予告する」「手当を支払う」のいずれかが必須であるという原則です。
労働基準法第22条:解雇の証明
労働基準法第22条では、解雇を含む退職時に、従業員から請求があった場合、企業は退職証明書をすみやかに交付しなければならないと定めています。
とくに解雇理由について求められた場合には、客観的な事実に基づいた内容を記載する必要があります。
あらかじめ社内でフォーマットを整備しておけば、対応もスムーズになるでしょう。
なお、解雇通知書や解雇予告通知書に具体的な解雇理由を記載していれば、それをもって証明とすることも可能です。
労働基準法第89条:就業規則の作成・届出
労働基準法第89条では、就業規則の作成と届け出の義務を定めています。
常時10人以上の従業員がいる企業は、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督署長に届け出なければなりません。
解雇事由が社内でどこにも記載がなく、あいまいなままでは、あとで有効性が争点となる可能性があります。第89条の規定に沿って、ケースや基準を定めましょう。
労働基準法第104条:通報者の保護
労働基準法第104条では、労働基準法に関係する内部告発をした労働者(通報者)が、不利益な扱いを受けないよう保護されています。通報を理由に従業員を解雇するのは、「報復解雇」とみなされ、法令違反となる禁止行為です。また、公益通報者保護法第3条でも、公益通報を理由とする解雇は無効とされています。通報しただけで職を奪われるような事態は、許されません。
たとえ通報した従業員に、別件で何らかの問題行動があったとしても、企業は正当な手続きに沿って、公正に処遇を判断する必要があります。安易な解雇や不利益な対応は、重大な労務トラブルに発展するおそれがあるため、慎重に対応しましょう。
労働基準法3条:均等待遇
労働基準法第3条では、解雇事由を含む「均等待遇」の原則が定められています。従業員の国籍・信条・社会的身分を理由として、差別的な扱いをすることは禁止事項です。
条文には「賃金・労働時間その他の労働条件について差別的取扱いをしてはならない」と明記されており、「その他の労働条件」に解雇事由も含まれています。企業は、すべての従業員に対して公正に対応しなければなりません。
解雇が認められる条件
解雇は企業にとって重大な決定です。だからこそ「今回の解雇は労働基準法上、本当に問題ないのか」と不安になるのも無理はありません。
労働基準法および関連法令に照らし、解雇が有効と判断されるための主な条件は、以下のとおりです。
- 解雇予告を実施する
- 解雇予告手当を支払う
- 法律の解雇禁止事項に該当しない
- 就業規則の規定に沿っている
- 解雇に相当性がある
- 解雇手順が適切である
以上の条件を満たさなければ、不当解雇とみなされ、損害賠償請求などの法的紛争に発展するおそれがあります。まずは該当者の就業状況や指導履歴、就業規則との整合性を確認しましょう。
社内判断が難しい場合は、顧問社労士や弁護士と相談しながら進めることをおすすめします。
解雇が無効(不当解雇)と判断される条件
企業が正当な理由なく従業員を解雇した場合、解雇は法的に「無効」とされ、不当解雇にあたります。
不当解雇と認定されると、企業には以下のようなリスクや負担が生じます。
- 労働基準法違反として、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金
- 過去にさかのぼった賃金の支払い義務
- 従業員からの職場復帰請求への対応
では、どのような解雇が「不当」と判断されるのでしょうか。主な条件は以下の3つです。
- 解雇制限に該当する場合
- 相当性がないない場合
- 特定理由に該当する場合
以上の条件を満たしていない解雇は、企業にとって大きなリスクとなります。以下で一つずつ解説するため、条件や判断基準を確認していきましょう。
解雇制限に該当する場合
労働基準法第19条で紹介したように、特定の状況にある従業員について、一定期間の解雇が制限されています。
次のいずれかに該当する期間中は、たとえ従業員側に問題があっても、原則として解雇はできません。
- 業務中の病気や怪我による休業期間中とその後30日間
- 女性の産前産後における休業期間とその後30日間
ただし、以下の例外が認められています。
- 打切補償を支払った場合
- 天災などにより事業の継続が困難になった場合
たとえば、地震や火災により事業所が全壊したようなケースは、事業の継続が困難と判断されます。
参照:『労働条件:解雇、退職(解雇制限、解雇の予告、退職時の証明)』厚生労働省徳島労働局
相当性がない場合
労働契約法第16条では、次のように定められています。
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当でない場合は、解雇は無効とする
つまり、合理的な理由と社会的に納得できる状況がそろっていない限り、企業は解雇できません。以下は、解雇の相当性が認められないケースです。
- 従業員の問題行動などに対して、注意指導など回避努力をしてこなかった
- 経営不振を理由とする整理解雇において、客観的証拠がない
- 解雇を回避するために、配置転換などの十分な対策を検討していない
解雇は「社会常識として妥当」と認められる必要があります。安易な判断で進めると、大きな法的トラブルを招くため慎重に対応しましょう。
特定理由に該当する場合
法律では、次のような特定の理由による解雇を禁止しています。
- 差別に基づく解雇:労働基準法第3条
- 会社の法令違反を通報したことに対する解雇:労働基準法第104条など
- 法律で認められた権利行使に対する解雇:労働組合法、労働契約法など
以上の理由に基づく解雇は「報復的」「差別的」とされ、不当解雇として厳しく取り扱われます。どんな理由で解雇しようとしているのかが、法律上認められるのかを必ず確認しましょう。
参照:『労働契約の終了に関するルール』総務省統計局厚生労働省
労働基準法における解雇のポイント
企業が従業員を解雇するとき、労働基準法に沿った正当な手続きが求められます。以下では、解雇をめぐる実務上の3つの基本ルールについて解説します。
- 就業規則に解雇事由を定める
- 解雇を通知する際は30日前に予告する
- 解雇予告手当を支払う
就業規則に解雇事由を定める
労働基準法第89条で紹介したように、解雇事由も具体的かつ客観的な基準で明記する必要があります。
就業規則は作成して終わりにせず、定期的な見直しも欠かせません。常時、見直しをして、必要に応じて変更手続きが求められます。
▼就業規則の変更対応については以下の記事でご確認ください。
また、全従業員への周知徹底もリスク管理として重要です。
就業規則への書き方が古いままだったり、従業員に周知されていなかったりする場合も、不当解雇になる可能性があるため注意しましょう。
解雇を通知する際は30日前に予告する
労働基準法第20条で紹介したように、解雇を実施する場合は、少なくとも30日前までに予告する義務があると定められています。
具体的には、解雇の予定日から逆算して30日前までに、口頭または書面で解雇の旨を伝える必要があります。
実務では、将来のトラブルを防ぐために「解雇予告通知書」などの書面で通知することが一般的です。通知書には「予告日」や「手当支払額」を明記しましょう。
解雇予告手当を支払う
30日前の予告を行わずに解雇する場合は、解雇予告手当の支払いが必要です。解雇予告と同じく、労働基準法第20条に定められています。たとえば、10日前に予告して解雇する場合は、残りの20日分の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければなりません。平均賃金は直近3か月の賃金をもとに計算します。
法律に基づいた解雇でトラブルを避けるためのポイント
たとえ労働基準法などの法律に沿った解雇であっても、従業員との間でトラブルに発展する可能性は十分にあります。解雇は、従業員にとって生活やキャリアに直結する重大なできごとであり、納得が得られない場合は裁判に発展するリスクもあるでしょう。トラブルを未然に防ぐために、企業が意識したいポイントを解説します。
- 企業と従業員で協議する
- 就業規則などの解雇規定内容を見直す
企業と従業員で協議する
突然の通告や一方的な説明は、従業員の不信感を招き、トラブルの引き金になります。解雇を検討する際は、解雇理由をていねいに説明し、従業員の言い分にもきちんと耳を傾ける姿勢が重要です。双方の立場や事情を尊重した対話が、早期の解決につながります。相互理解を深めることで、円満な退職や納得感のある対応につながりやすくなります。
就業規則などの解雇規定内容を見直す
解雇の基準が就業規則に明記されていなかったり、あいまいな表現になっていたりすると、あとになって「聞いていない」といった認識の相違が起こります。
トラブルを防ぐためには、誰が見ても明確に理解できる内容に整備しておくことが必要です。
あわせて、就業規則の変更や追加を行った際は、従業員全体への周知徹底も忘れずに実施しましょう。

まとめ
労働基準法を中心に、法律では解雇に関するさまざまなルールがあります。条文が多岐にわたり混乱することもあるかもしれませんが、まずは次の3点をチェックしましょう。
- 解雇理由は就業規則に明記されているか
- 解雇予告や手当の対応は適切か
- 解雇制限や禁止理由に該当していないか
就業規則の整備や予告の方法、証拠の記録など、一つひとつの対応が不当解雇の判断を左右します。
万が一に備え、問題がないといえる状態をつくっておくことが、企業にとってのリスク回避につながります。少しでも判断に迷う場合は、社労士や法務部門と連携しながら進めましょう。
退職手続きも効率化|One人事[労務]
One人事[労務]は、煩雑な労務管理をクラウド上で完結させる労務管理システムです。各種行政手続きや事務対応を簡略化し、担当者の負担軽減を期待できます。退職手続きにも、お役立ていただけます。
One人事[労務]の初期費用や気になる操作性については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門スタッフが、貴社の課題をていねいにお聞きしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、労務管理の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードしていただけます。労務管理をシンプルにして「本来やりたい業務」に集中したい企業は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |