管理監督者とは【法律の定義・要件】管理職との違いや設置の注意点もわかりやすく解説
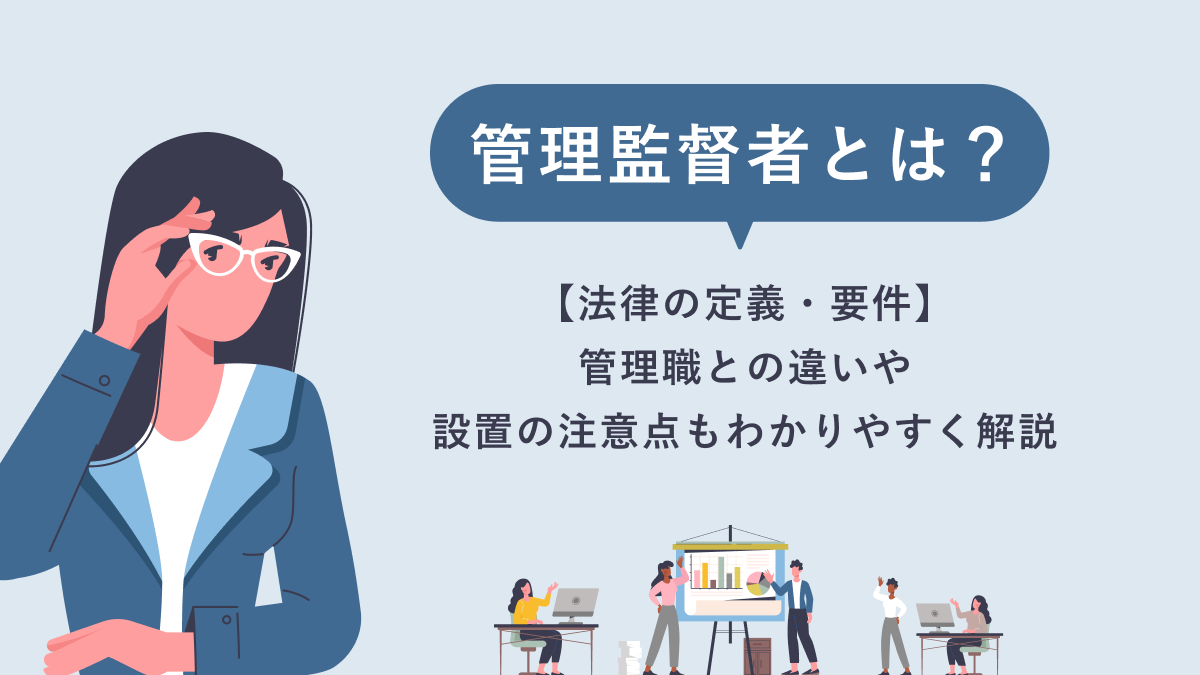
管理監督者=管理職ではありません。
管理監督者とは、労働条件の決定や労務管理について経営者と一体的な立場にある人を指し、労働基準法上の特別な扱いを受けます。
本記事では、管理監督者の法的な定義や要件、単なる管理職との違い、企業が管理監督者を設置する際の注意点までわかりやすく解説します。

 目次[表示]
目次[表示]
管理監督者とは? 定義や役割をわかりやすく解説
管理監督者とは、企業内で相応の地位と権限を持ち、経営者と一体的な立場にある人を指します。単に役職や肩書きで決まるものではありません。
法律上の管理監督者であるかどうかは、職務内容や権限、勤務実態などから総合的に判断されます。
「部長や課長に残業代を払っていないけれど、本当に大丈夫なのか?」「うちの管理職は、法律上の管理監督者に該当するのか?」と不安を感じたことはありませんか。
管理監督者の判断を誤ると「名ばかり管理職」とみなされ、未払い残業代の請求や労働基準監督署の是正指導といったリスクにつながるおそれがあります。
ここでは、管理監督者の定義や役割、一般的な管理職との違いについて詳しく解説します。
▼そもそも役職とは何なのでしょうか。詳しく知るには以下の記事をご確認ください。
労働基準法における管理監督者の定義
管理監督者は、労働基準法第41条第2号により「事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者」と定義されています。条文だけでは、具体的にどのような人があてはまるのか判断が難しいですよね。
厚生労働省の行政解釈では、労働条件の決定や労務管理を担い、経営者と一体的な立場にある人が該当するとされています。
管理監督者の判断基準は肩書きではなく、実際の職務内容や権限、勤務の実態です。権限を持たない「名ばかり管理職」は、法的に管理監督者とは認められません。

管理監督者の役割
管理監督者の役割は、経営者と同じような目線を持ちながら、重要な責任と権限を持って職務を遂行することです。例として以下のような役割が挙げられます。
- 経営方針や経営戦略の決定ににかかわる(経営会議の出席など)
- 部下の採用や人事評価など、部下の管理を担う
- 予算の編成・執行に責任を持ち、部門業績の達成を主導する
- 経営の意向を現場に伝え、部下に浸透させる
管理監督者は、予算の編成・執行に関する権限を持ち、部門の業績目標達成に向けた取り組みを主導します。
以上の要素が備わって初めて、経営者と一体的と評価されるのです。
管理監督者と管理職の違い
「管理職=管理監督者」と思われがちですが、両者は明確に区別されています。
管理監督者は労働基準法で定められた法的な地位です。役職名だけでは判断しきれず、実際の働き方や責任の重さなどをもとに、以下要素から総合的に判断されます。
- 職務の重要性
- 責任と権限
- 裁量ある働き方
- 相応の待遇
一方の管理職は、企業が独自に定めた役職を指し、厳密な定義はありません。たとえば課長や部長という肩書きがあっても、実態がなければ、管理監督者とは認められないでしょう。
管理監督者と管理職の違いを理解することは、労働時間や休憩・休日の法規制が適用されるか否かという点で重要です。
管理監督者は、労働基準法で定める労働者の保護規定の対象から外れます。管理職と呼ばれていても、管理監督者にあてはまらなければ、一般の従業員と同様に規制が適用され、企業は残業代を支払う必要があります。
▼労働時間の管理は徹底できていますか。管理方法に不安があるなら以下の資料をご活用ください。

管理監督者として認められるための4つの要件
管理監督者として認められるには、単に「部長」や「課長」といった肩書きを持っているだけでは不十分です。労働基準法上の管理監督者は、以下の4つの要件をすべて満たしている必要があります。
- 重要な職務内容を有している
- 重要な責任と権限を有している
- 労働時間などの規制になじまない勤務態様で働いている
- 管理監督者として、ふさわしい待遇を受けている
管理監督者として認められる4要件について、詳しく見ていきましょう。
重要な職務内容を有している
管理監督者は、経営者と一体的な立場で、労働時間や休憩・休日の規制を超えて対応せざるを得ない重要な職務を担っています。経営方針や組織運営にかかわる高度な職務内容の遂行が求められます。
たとえば管理監督者は、以下のような業務を担当している人です。
- 経営会議への参加と発言権を持っている
- 経営方針や取引方針の決定に影響を与えられる
- 経営方針に基づき、部門の方針を決定できる
- 部門全体を統括する立場にある
- 経営戦略の企画・立案にかかわっている
- 昇格や昇給、賞与といった労働条件の決定に関与している
- 採用や解雇などの人事権を持っている
以上のような職務に就いていることで、経営者と一体的な立場として判断されやすくなります。
管理監督者は、単に日々の業務を遂行するだけでなく、会社の運営に直接影響を及ぼす役割を担っています。

重要な責任と権限を有している
管理監督者として認められるには、経営者から重要な「責任と権限」を与えられている必要があります。形式的な役職や職務では足りず、実質的に組織の運営において意思決定できる立場でなければなりません。
管理監督者が持つ、重要な「責任と権限」の具体例としては、以下のようなものが挙げられます。
- 従業員の採用・配置・解雇の関する人事権
- 部下の労働条件(労働時間、休日、賃金など)の決定権
- 予算の編成・執行に関する権限
- 取引先との交渉権限
- 部門の業績に対する責任
- 経営方針の実行責任
とくに重要なのは、「提案権」ではなく「決定権」を持っているかどうかです。みずからの裁量で判断し、実行までできる立場でなければ、実質的な権限があるとはいえません。「決定できる」と「提案できる/担当している」では、大きな違いがあるのです。
たとえば、経営会議に参加していてもオブザーバーにすぎなかったり、発言が制限されていたりするなら、管理監督者とは認められないでしょう。昇進して肩書きが変わっても、業務範囲や影響力が以前と変わらないままでは、名ばかりの役職にとどまっていると判断される可能性があります。
労働時間などの規制になじまない勤務態様で働いている
管理監督者は、職務上の責任が大きく、時間にとらわれず業務に従事する必要があるため、労働時間などの規制を受けません。労働基準法の労働時間・休憩・休日の規定から除外され、みずからの裁量で働いています。
そのため、次のように労働時間に関して実質的な裁量を持っていることが求められます。
- 始業・終業時刻をみずから決定できる
- 休憩時間を自由に取れる
- 休日出勤の有無をみずから判断できる
- 業務の進め方や優先順位をみずから決定できる裁量がある
- 始業・終業時刻を自分で決められる
タイムカードで勤怠管理をされていたり、上司の許可がないと退社できなかったりするのであれば、管理監督者の要件を満たしません。
なお、管理監督者に裁量があるからといって、企業が無制限に働かせることは禁止されています。 過重労働によるリスクを避けるため、管理監督者であっても、労働時間の把握や産業医の面談などは必要です。
▼勤怠管理がずさんだと、企業にはさまざまなリスクがあります。リスクとその対応を確認するなら、以下の資料をご活用ください。

管理監督者として、ふさわしい待遇を受けている
管理監督者の地位にふさわしい待遇を受けていることも要件の一つです。管理監督者は労働時間の規制を受けず、残業代が支払われないため、補填するような賃金体系が望ましいとされています。
管理監督者は、一般的に次のような処遇が適用されています。
- 一般労働者と比較して十分に高い基本給
- 役職手当や管理職手当の支給
- 賞与や退職金における優遇措置
- 成果や業績に基づいた評価と報酬
単に「管理職」という肩書きだけで、残業代を支払わないのは法的に問題です。時間外労働が多くても、それを補う給与や手当が支給されている必要があります。「責任だけが重く、給料は一般社員とほぼ同じ」では、「名ばかり管理職」に該当してしまうでしょう。
管理監督者の評価基準も、労働時間ではなく、業績や改善実績、マネジメントの成果といった指標で判断されます。
管理監督者には労働時間・休憩・休日の規定が適用されない
管理監督者は、労働基準法における労働時間・休憩・休日の規定が適用除外となる立場です。経営者と一体的な立場にあり、みずからの裁量で労働時間や業務量を調整できるためです。
一般の労働者であれば、1日8時間・週40時間という法定労働時間や、休憩時間の確保、週1日以上の休日付与が義務づけられています。管理監督者は規制から除外され、残業代の支払い義務も基本的にはありません。
管理監督者が適用除外となる労基法のルールを確認していきましょう。
「労働時間」のルール
管理監督者には、次の労働時間に関する規定が適用されません。
- 法定労働時間(1日8時間・週40時間)の上限規制
- 時間外労働の上限(月45時間・年360時間など)
- 36協定の締結と届出義務
- 時間外・休日労働に対する割増賃金(25%〜35%以上)
以上はすべて、一般の労働者に対して義務づけられた規定です。管理監督者には適用されず、会社としても割増賃金の支払い義務はありません。
ただし、管理監督者は好きな時間に出退勤できるという誤解も見受けられますが、間違いです。管理監督者であっても労働契約に基づく労働義務があり、企業との合意にしたがって勤務する必要があります。
「休憩」のルール
管理監督者は、労働基準法第34条に定める休憩の付与義務からも除外されます。具体的には次のルールが、管理監督者には適用されません。
- 6時間超勤務の場合:45分以上の休憩
- 8時間超勤務の場合:60分以上の休憩
- 休憩は労働時間の途中に与える
- 休憩は原則一斉に与える
- 休憩は従業員が自由に利用できる
法律上は管理監督者に休憩を与えなくても違法ではありません。極端にいえば、1日中連続で働かせることも可能だという解釈になります。
とはいえ現実的に考えると、長時間労働は生産性の低下や健康リスクを招きます。企業には安全配慮義務があり、実際は適切な休憩を確保することが重要です。
▼労働基準法における休憩のルールを詳しく知るには、以下の記事をご確認ください。
「休日」のルール
休日についても、管理監督者には労働基準法第35条の規定が適用されません。
一般の労働者であれば、週1日の法定休日、あるいは4週4日の休日を確保する必要があります。しかし、管理監督者は対象外とされており、休日を与えなくても法律違反とはなりません。
休日労働に対する割増賃金も同様です。法定休日に働かせた場合、一般労働者には35%以上の割増賃金が必要ですが、管理監督者には手当の支払い義務はありません。
ただし、就業規則で定められた「所定休日」は管理監督者にも適用されるため、まったくの無休というわけではありません。また、健康管理や働き方改革の観点からも、休日の確保は必要です。
▼労働基準法における休日のルールを詳しく知るには、以下の記事をご確認ください。
管理監督者にも適用される労働基準法の規定
管理監督者であっても、すべての労働基準法の規定から除外されるわけではありません。
「深夜労働」や「年次有給休暇」に関する規定は、管理監督者にも適用されます。健康維持の観点から必要な規定であり、管理監督者であっても一労働者として基本的な権利が保障されているためです。
ここでは、管理監督者にも適用される労働法上のルールについて、詳しく見ていきましょう。
「深夜労働」のルール
管理監督者であっても、午後10時から午前5時までの深夜時間帯に労働した場合は、深夜割増賃金の支払いが必要です。労働基準法第37条第4項に基づき、通常の賃金に対して25%以上の割増が義務づけられています。
深夜労働のルールが管理監督者にも適用されるのは、深夜労働が健康に与える影響が誰にとっても同じであるという考え方にあります。深夜労働は、心身に負担がかかるため、役職に関係なく保護が必要とされているのです。
たとえば、管理監督者が午後10時から午前0時まで働いた場合、2時間分の深夜割増賃金を支払う必要があります。なお、午後10時以降の労働が所定労働時間を超えていても、管理監督者に支払うのは「深夜割増」のみであり、時間外労働に対する割増賃金は不要です。
「有給休暇」のルール
管理監督者も、年次有給休暇の付与対象です。労働基準法第39条の規定は、管理監督者にも適用され、以下の条件を満たす場合は有給休暇を付与しなければなりません。
- 雇い入れの日から6カ月間、継続して勤務している
- その間の全労働日のうち、出勤率が80%以上である
条件を満たした管理監督者には、勤続年数に応じて10日〜20日の年次有給休暇が付与されます。また、2019年4月施行の「年5日の有給休暇取得義務」も適用されます。
年10日以上の有給が付与される管理監督者に対しては、会社が5日以上の有給休暇を取得させなければならないということです。
有給は労働者のリフレッシュと健康維持のために不可欠な制度です。たとえ経営者に近い立場であっても、管理監督者は労働者であることに変わりありません。そのため、休む権利はしっかりと守られているのです。

【トラブル防止】管理監督者を設置する際の注意点
管理監督者を設置する際には、法的リスクを回避し、適切な労務管理を実現するために注意したい点があります。
- 管理監督者の労働時間も管理する
- 「名ばかり管理職」のトラブルに注意する
- 就業規則に明記する
- 欠勤控除は適用する
- 管理監督者は過半数代表者になれない
管理監督者を設置する際の注意点について詳しく見ていきましょう。
管理監督者の労働時間も管理する
管理監督者には労働時間の規制が適用されませんが、だからといって長時間労働が無制限に許されるわけではありません。健康管理の観点からも、労働時間の実態を正確に把握することが重要です。
2019年の「働き方改革関連法」により、管理監督者を含むすべての労働者について、客観的な方法で労働時間を把握することが義務づけられました。「残業代は不要でも、労働時間の記録は必要」なのです。
とくに長時間労働が続く場合は、産業医による面接指導の対象となることもあります。月80時間を超える時間外・休日労働を行った管理監督者から申し出があれば、医師による面談を実施しなければなりません。
→使いやすい勤怠管理システムOne人事[勤怠]の特長はこちら

「名ばかり管理職」のトラブルに注意する
管理監督者を形式的に設置して「名ばかり管理職」を生まないように注意しましょう。
要件を満たしていないにもかかわらず、肩書きだけで管理監督者と扱い、残業代を支払わない運用を「名ばかり管理職」といいます。
実際に裁判となった「日本マクドナルド事件」(2008年)の事例では、店長が管理監督者に該当しないと判断され、裁判所は未払い残業代の支払いを命じました。
ポイントは、業務に裁量がなく本社の指示に従っていたこと、労働時間が厳しく管理されていたこと、賃金が一般従業員と大差なかったことです。
管理監督者かどうかは、役職名ではなく実態で判断されます。設置する際は、責任・権限・勤務実態・待遇といった要素を客観的に確認し、制度上の正当性を持たせる必要があります。
就業規則に明記する
管理監督者を設置する際は、位置づけを就業規則に明記しておくことが重要です。定義や適用除外の範囲をあらかじめ示しておけば、従業員との間で解釈の違いによるトラブルを防げます。
管理監督者について、就業規則には以下のような内容を盛り込むとよいでしょう。
- 管理監督者の定義(どの職位の人が管理監督者に該当するか)
- 労働時間、休憩、休日の規定が適用されないこと
- 管理職手当などの支給に関する事項
| 例文 |
|---|
| 第○条(管理監督者)本規則における管理監督者とは、○○部長以上の職位にある者をいい、第○条(労働時間)、第○条(休憩時間)および第○条(休日)の規定は適用しない |
| 第○条(管理職手当)管理監督者には、職責に応じて、別表に定める管理職手当を支給する。手当には時間外労働、休日労働に対する割増賃金が含まれるものとする。 |
注意したいのは「部長以上」と職位だけで定義するのではなく、職務内容や権限も含めることです。実態に紐づく規定により、法的リスクを回避できるでしょう。
▼就業規則の変更が必要なら、以下の記事をご確認ください。
欠勤控除は適用する
管理監督者は労働時間の規制から除外されていますが、欠勤控除は適用されます。欠勤した日数に応じて、一般の従業員と同様に給与を日割りで控除することが可能です。
一方で、遅刻や早退に対する控除は行わないのが一般的です。管理監督者は自己の裁量で勤務時間を管理しているという前提要件があるため、細かく管理すると「実態としては一般労働者と同じ」とみなされかねません。
欠勤控除のルールも、就業規則に明記しておくことが重要です。
| 例文 |
|---|
| 第○条(欠勤控除)管理監督者が欠勤した場合には、月額給与を当該月の所定労働日数で除した額に欠勤日数を乗じた金額を控除する |
ルールを明文化しておくことで、労務トラブルの防止につながります。
▼欠勤控除の計算方法を知るなら、以下の記事をご確認ください。
管理監督者は過半数代表者になれない
管理監督者は、労働基準法施行規則第6条の2により、労働者のなかの過半数代表者になれません。管理監督者が経営側と一体的な立場にあることが理由です。
過半数代表者とは、労働組合が存在しない企業で、労使協定を締結する際に、労働者を代表する人です。36協定や変形労働時間制の導入、年次有給休暇の計画的付与など、さまざまな労使協定の締結に必要となります。
過半数代表者の要件は以下のとおりです。
- 管理監督者ではない
- 民主的な手続き(投票や挙手)により、代表者を選出する意思が明示されている
- 会社の意向で選ばれた人ではない
労使間の中立性を保つためにも、管理監督者が関与してはいけない役割であることを理解しておきましょう。
まとめ|管理監督者の判定は実態に即した判断を
管理監督者は、労働基準法上で特別な地位を持つ役職者です。判断には、職務・責任・勤務実態・待遇という要素から慎重に見極める必要があります。
管理監督者の適切な設置と運用は、企業の法令遵守と、個人の健康管理の両面で重要です。実態に即した判断で運用し、労務トラブルを防ぎましょう。
管理監督者は基本的に労働基準法が適用されませんが、深夜労働や有給休暇など一部規定は適用されます。管理監督者であっても、客観的な方法での労働時間の把握が欠かせません。
管理監督者の労働時間管理もサポート|One人事[勤怠]
管理監督者の労働時間を適切に把握・管理するには、勤怠管理システムの活用をおすすめします。
One人事[勤怠]は、煩雑な勤怠管理業務をシンプルにするクラウド勤怠管理システムです。管理監督者を含むすべての従業員の勤怠を、客観的かつ正確に記録・管理できます。
勤怠管理に課題がある企業は、検討してみてはいかがでしょうか。自社独自の勤怠ルールがある場合も、まずは当サイトより、お気軽にご相談ください。専門スタッフが、貴社のお困りごとをお聞きしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、勤怠管理の効率化のヒントに役立つ資料を無料でダウンロードしていただけます。勤怠管理をシンプルにして「本来やりたい業務」に集中したい企業は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたしま |
