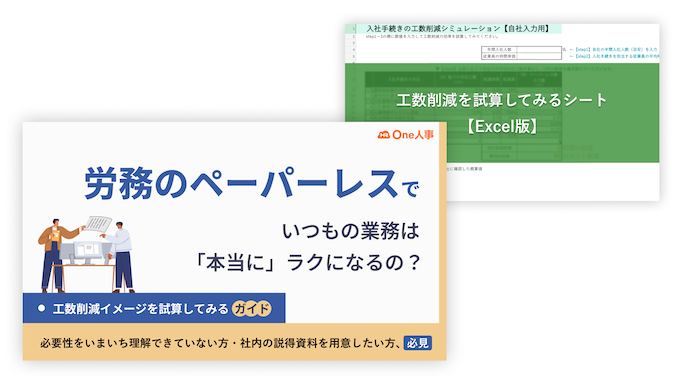人事と労務のDXとは? 求められる背景とつまずく理由、実現へのポイントを解説

「人事労務のDXを進めなければ」と頭ではわかっていても、何から手をつけるべきなのでしょうか。人事労務DXに取り組んだものの、「システムを導入しただけで終わってしまった」というケースがあります。「現場から反発されて頓挫してしまった」という企業も少なくありません。
人事労務DXを適切に進めることで、業務効率化だけでなく、従業員エンゲージメントの向上や、戦略的な人材マネジメントの実現につながります。
本記事では、人事労務DXが求められる背景、よくある課題と解決策、定着に向けた進め方などを、実例を交えながらわかりやすく解説します。
 目次[表示]
目次[表示]
人事と労務のDXとは
人事と労務のDX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を活用して、人材マネジメントを変革する取り組みです。最終的に企業価値の向上を目指します。
人事労務DXを進めようと考えたとき、勤労怠管理や給与計算をシステム化し、業務の手間を減らすことを目的とする企業も多いでしょう。
しかし、デジタルツールの活用はきっかけにすぎません。データを活用して人事の意思決定を、経営と連携しながら戦略的に行うことが重要です。
人事・労務のあり方を根本から見直すことで、企業価値の向上につなげるという視点を持ちましょう。
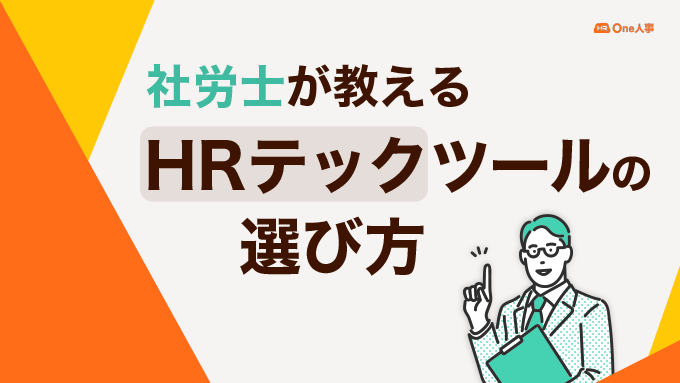
そもそもDXとは
DXは単なるデジタル化とは一線を画す概念で、組織のあり方そのものを変革する取り組みです。
経済産業省によって次のように定義されています。
企業がビジネス環境の激しい変化に対応し、データとデジタル技術を活用して、顧客や社会のニーズをもとに、製品やサービス、ビジネスモデルを変革するとともに、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土を変革し、競争上の優位性を確立すること
引用:『D X 推進指標 (サマリー)』経済産業省
人事労務の分野においては、「業務の効率化」だけでなく、「人材活用の高度化」を目指すことが求められます。
DXは単なるツール導入にとどまらない
DXは単に技術を導入して終わらず、組織全体の変革を通じて、新たな価値を創造する取り組みです。
DXに至るまでには、前段階としてデジタイゼーションとデジタライゼーションがあり、最終的にビジネスモデルを変革する段階へ進みます。
| 段階 | 内容 | 人事労務での具体例 |
|---|---|---|
| デジタイゼーション | アナログ情報のデジタル化 | ・紙の履歴書の電子化 ・押印文書のPDF化 |
| デジタライゼーション | 業務プロセスのデジタル化 | ・勤怠管理システムの導入 ・電子申請の実現 |
| デジタルトランスフォーメーション | ビジネスモデルの変革 | ・AIを活用した採用選考 ・データ分析による戦略的人材配置 ・従業員エンゲージメントの可視化と向上 |
真のDXは、既存の業務から紙をなくし、システムに移行するだけでは不十分です。次のような視点で変革を目指します。
- 従業員の働き方や組織の在り方を根本から見直す
- データに基づく意思決定を実現する
- 新たな価値創造につながる変革を推進する
人事と労務の領域においても、業務効率化を超え、従業員一人ひとりに対する戦略的な成長支援までを視野に入れなければなりません。
人事労務DXが求められる背景
企業がこれから先も持続的に成長するには、現状維持にとどまらず、人事労務DXの推進は避けられないでしょう。
背景には大きな2つの要請があります。
- 非効率な業務を改善すること
- 1を達成したうえで、戦略的な人材マネジメントを実現すること
人事労務DXを進めて課題を解決し、よりよい組織をつくることが必要です。背景を1つずつ確認していきましょう。
人事労務の運用効率化
人事・労務部門は採用、教育、評価、労務管理など幅広い業務を担当しています。
しかし、多くの企業ではアナログ作業が残っており、書類やエクセルでの管理が業務を圧迫しています。
紙を大半とした業務運用は属人化を招き、担当者が不在だと業務が滞るリスクを抱えています。 人事・労務は企業経営の根幹を支える重要な部門であるため、業務のブラックボックス化は避けなければなりません。
とくに中小企業では「ひとり人事」 「2人総務」という状況もめずらしくありません。限られた人員で定型業務をこなさなければいけないのが現状です。
このような課題を解決するには、まずは定型業務の非効率さの解消が必要です。業務プロセスを変革する人事労務DXが求められています。
人事データの蓄積・分析・活用
少子高齢化が加速し、労働力人口の減少するなか、企業は限られた人材を最大限に活用する戦略が必要です。
さらに近年は人事労務業務は単なる事務作業から、経営戦略としての役割分担を要請されるようになってきました。 データを活用した人事戦略が実行できれば、不足する労働力を補いながら、全体のパフォーマンスを高めることが可能です。
しかし、多くの企業では人事データが適切に整理・活用されていないのが現状です。
たとえば、評価データが部署ごとに異なり、昇進基準が属人化しているケースがあります。また、勤続年数やスキルデータが一元化されていないため、適切な人材配置や育成計画の立案ができません。
データ活用の障壁になっている課題を解決するために、人事労務のDX化が求められています。
データドリブンな人事施策を推進できると、離職リスクの予測や人的資本経営の実現にも取り組めるでしょう。
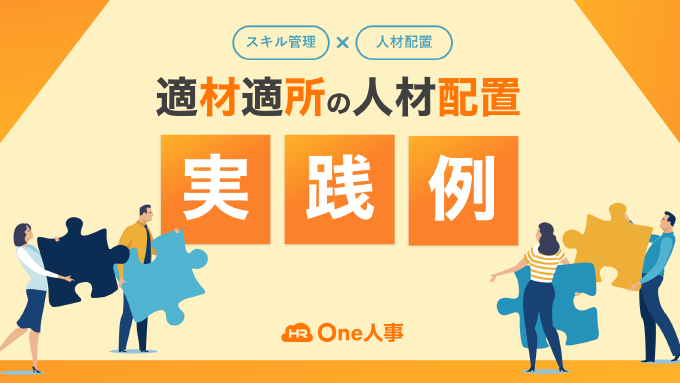
人事労務DXのメリット
人事労務DXの導入は、企業にとって多面的な価値があります。業務効率の向上から人材戦略の高度化まで、組織全体に大きな変革をもたらす可能性を秘めているのです。以下でメリットを詳しく紹介します。
効率化により、工数が削減される
人事労務DXを導入すると、給与計算や勤怠管理、社会保険手続きといった定型業務を自動化でき、工数が削減されます。
- 給与計算の自動処理→ 計算ミスや入力ミスの減少
- 勤怠データの自動集計→ 勤怠実績・残業状況の可視化
- 各種申請・承認作業のワークフロー化→ 処理時間の短縮/タイムロスの削減
人事担当者はより戦略的な業務に集中できるようになります。従業員とのコミュニケーションにも多くの時間を割くことが可能です。
データ活用により、マネジメントが最適化される
人事労務DXでデータをデジタル活用し、分析しやすくなることで、戦略的な人材マネジメントが実行しやすくなります。
- 適性と全体バランスを加味した適材適所の人材配置
- 評価データをもとにした公平な評価制度
- スキル・キャリア履歴、成長度合いの可視化
- 離職リスクの予測
- 希望と適性に合わせた人材育成の計画策定
- 将来的な人材ニーズの予測と採用計画
データドリブンな意思決定によって、組織全体の生産性分析とボトルネックの特定がしやすくなり、組織パフォーマンスの最大化がはかれるでしょう。
ペーパーレス化により、管理コストがなくなる
人事労務DX実現の前段階でペーパーレス化が進み、印刷費用や保管スペースにかかるコストを削減できます。
- 印刷・コピー費用の削減
- 書類管理の効率化、スペース縮小
- 文書管理・運搬にかかる人件費削減
- 情報検索性の向上
- 複数拠点での情報共有
書類の管理がデジタル化され、紛失や情報漏えいのリスクが減り、セキュリティ面での改善が期待できるのもメリットです。
優秀な人材が集まる仕組みが整備される
人事労務のDXを進めることで、企業の魅力が高まり、優秀な人材の獲得と定着につながります。
- AIを活用した候補者選定・スクリーニング
- リモートワーク環境の整備
- 採用データの分析による採用基準の最適化、応募者体験の向上
- 従業員の健康データの活用
- サーベイの実施と分析による組織改善
採用活動にAIデータを活用することで、効率化とともに、より精度の高い候補者選びが可能です。
働き方改革の面では、リモートワーク環境の整備が進み、多様な働き方が実現しやすくなるでしょう。
従業員満足度調査やサーベイの実施で、定期的な測定と改善により、従業員エンゲージメントを高める施策にも取り組みやすくなります。
優秀な人材は、DXを推進する企業を選ぶ傾向にあります。例えば、最新の採用管理システムやAIを活用することで、候補者に対してスムーズな応募体験を提供できます。また、リモートワークやフレックスタイムの導入が進むことで、より多様な働き方を求める人材を促すことができます。
人事労務DXにつまずく理由と解決策
人事労務DXの推進において、多くの企業がさまざまな課題に直面しています。課題を理解し、適切な対策を講じることが重要です。課題や解決策について以下で詳しく紹介します。
データの収集・整理に工数がかかる
人事労務DXを進める際、データ整理が最初の大きな課題となることが多くあります。
既存の人事データの整理と移行作業は、想像以上の時間と労力を必要とします。紙の書類や異なるシステムに散在するデータの統合、フォーマットの統一は、膨大な工数を要する作業です。
長年蓄積された紙の人事記録や、部署ごとに異なるフォーマットで管理されてきた評価データを一元化するのは簡単なことではありません。
解決策としては、優先順位を明確にして、段階的なステップで進めることがポイントです。
- 現状のデータ形式を把握する
- 統一フォーマットを決める
- システムに適したデータ変換を行う
- 移行後のテストを実施する
給与計算や勤怠管理など、基幹業務から着手し、徐々に範囲を広げていくことで、負担を分散できます。データ収集・移行のタスクフォースを編成し、集中的に作業を進めてもよいでしょう。
現場が負担に感じてしまう
新しいシステムや仕組みの導入は、現場の従業員に抵抗感をもたらします。デジタルツールに不慣れな従業員のなかには、運用変更に強くストレスを感じる人もいます。
従来のやり方に愛着を持ち、業務の可視化に不安を感じる中堅・ベテラン社員も少なくありません。日常業務をこなしながら新システムに慣れていくことは、心理的負担も大きいでしょう。
人事労務DXの導入にあたっては、導入の目的や必要性、メリットをていねいに説明することが大切です。従業員の理解と共感を得ることも重要なDX推進のプロセスといえます。
十分な研修期間を設け、段階的な移行計画を立てることで、従業員の不安を軽減できます。選定段階から導入・運用開始後も、伴走型のサポート体制があるサービスなら、定着まで支援してくれるので安心です。
費用対効果を出せていない
変革には投資コストがかかります。しかし、人事労務DXの費用対効果を算出する方法がわからない方も多いのではないでしょうか。上司や経営層に「何の意味があるの?」と理解を得られないケースもありますよね。
【主な導入費用・ランニングコスト】
- システム導入費用
- 保守費用
- 教育費用
投資回収期間が長期化することも課題です。とくに中小企業では、大規模な投資に踏み切れない事情もあります。
解決策として、具体的な数値目標(KPI)を設定し、導入効果を可視化することが必要です。
工数削減効果やペーパーレス化によって、何がどう変わるのか直接的なコスト削減をシミュレーションしてみましょう。
投資対効果を明確に示すことで、経営層の意思決定を促進できます。数値化が可能な人事労務DXの定量効果指標は以下のとおりです。
- 削減される作業時間数、日数
- 削減される金額、人件費
- エラーの改善率
- 紙の枚数、ファイル数
- 保管棚、保管段ボールの減少数
以上のような定量効果は次の資料でシミュレーションしていただけます。ペーパーレスの必要性を感じられていない方、社内の説得材料を準備したい方は、ぜひご活用ください。
人事労務DXの効果は定性的なものもあります。人事評価のDX推進による定性効果は、次の事例記事でご確認ください。
DX人材が不足している
DX技術に精通し、かつ人事労務の知識も持ち合わせた人材の確保は簡単ではありません。
DX推進を企画から運用まで一貫して担える人材はとても少なく、とくに都市部から離れた企業では、人材採用の競争が激化しています。
そのため、既存の人事・労務担当者をDX推進リーダーとして育成し、外部研修やオンライン講座を活用することで、スキルアップを促す方法が現実的な解決策といえます。
また、人事労務DXに関する業務改善の小さなプロジェクトから始め、実践を通じて能力を身につけてもらうのも一案です。
外部のコンサルタントやITベンダーの知見を活用して、不足を補うことも可能でしょう。内部人材の育成と外部の専門家の活用をバランスよく組み合わせるのがおすすめです。
新システムの移行に課題がある
人事労務DXを進めるうえで、業務プロセスの大幅な見直しをともなう移行作業が大きな壁となる企業も少なくありません。
既存のレガシーシステムから新しいクラウドシステムへ移行する際、技術的・運用的な問題が発生することがあります。
とくに、カスタマイズされた既存システムから標準的なクラウドサービスへの移行では、現場が混乱し、負担が大きくなりがちです。
新旧システムで並行して運用期間を設けた場合、負荷はさらに増大し、トラブルへの対応体制も整備しておく必要があります。
解決策として、使いやすさを重視したシステム選定が重要です。トライアル期間で現場の従業員に使用してもらい、本格的な運用を想定して段階的に移行しましょう。
サービス提供会社の導入事例を参考に、実践的な運用準備を行うと、スムーズに移行できます。
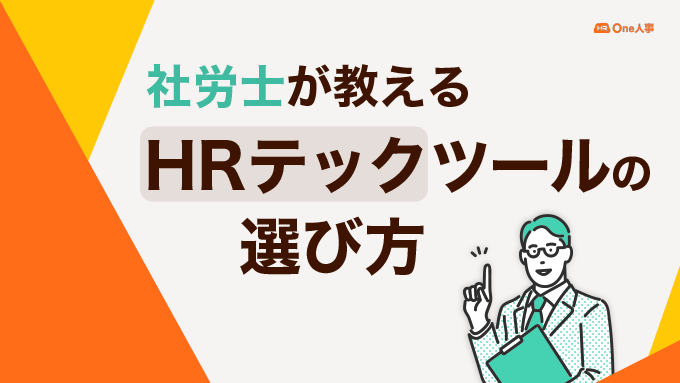
人事労務DXを支えるツール
人事労務DXを実現するためのツールは、大きく3つのタイプに分類できます。
| 種類 | メリット/デメリット | |
|---|---|---|
| ERP型 | 基幹系業務を統合的に管理する大規模なシステム | ・人事・経理・販売など、企業の基幹業務全体を一元管理 ・導入には大きなコストと時間がかかる ・データの一元管理と業務の標準化を実現 |
| 特定業務特化型 | 勤怠管理や給与計算など、特定の業務に特化したシステム | ・必要な機能だけを低コストで導入できる ・特化型システムを業務ごとに導入すると連携の手間が発生 |
| ワンストップ型システム | 人事労務に関する複数の業務をカバーする統合システム | ・採用から評価、給与計算まで一気通貫で管理 ・必要な機能から段階的に導入することも可能 |
現在、多くの企業ではさまざまな業務システムが乱立している状況です。部署ごとに異なるシステムを導入した結果、データの連携作業が新たな負担となり、業務効率が低下するケースも見られます。
全社的なDX推進を目指す場合は、ワンストップ型システムの導入が有効です。データの一元管理により連携の手間を省き、業務効率を向上できます。
また、多くのワンストップ型システムは必要な機能から段階的に導入できるため、企業の状況に応じた柔軟な展開が可能です。
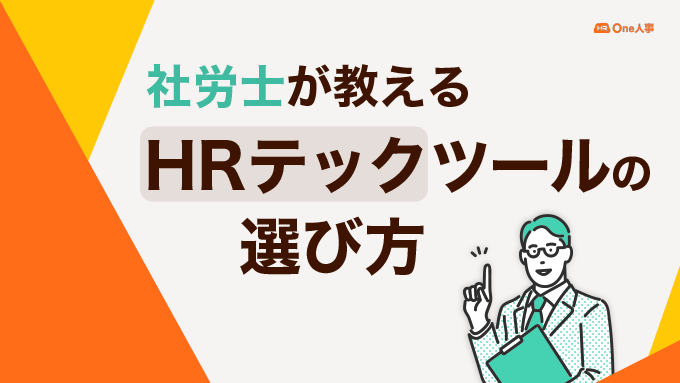
人事労務DX化の進め方・実現へのポイント
人事労務DXを成功させるには、計画的なアプローチと実行が不可欠です。以下に、具体的な進め方を3つのステップに分けて、ポイントとともに解説します。
1.既存業務を洗い出す
人事労務のDXは、現状の業務プロセスと課題を明確にすることから始めましょう。勤怠管理や給与計算、労務管理など、人事労務業務全体を可視化して非効率な部分や改善が必要な点を特定します。
業務の可視化では、手作業による処理が多い工程や、法令遵守の観点で不安のある部分にとくに注目しましょう。同過程で明らかになった課題は、経営層から現場まで広く共有することで、人事労務DX推進への理解と協力を得やすくなります。
2.システムを比較検討・選定する
次に人事労務DXを支える最適なシステムを慎重に選定します。以下の観点から総合的に評価・検討しましょう。
- 機能(自社の導入目的、課題に解決に必要なもの)
- 予算
- 操作性
- カスタマイズ性
- 導入後のサポート体制
トライアルやデモ版を活用して実際の使用感を確認することも重要です。
また、人事労務DXにかかる費用と期待される効果を試算して比較することも欠かせません。サービスごとに以下のポイントを考慮しながら、人事労務DXの進捗を評価する数値目標を事前に決めておくと、導入後の成果検証にも活用できます。
- 短期的な効果:導入直後に削減される人件費や印刷費、書類管理コスト
- 中長期的な効果:作業時間の削減率、エラー発生率の改善、組織の生産性向上
- 投資回収期間の試算:初期投資に対すして何年でコストメリットが出るか
もっとも高い費用対効果が望めるシステムを選定したいところです。
▼作業時間の削減率や削減費用を試算するには以下の資料をご活用ください。
3.継続的に利用する体制を整える
人事労務DXの効果を最大化するには、システムを導入するだけでは不十分です。現場での活用を定着させ、継続的に運用するための仕組みを整えましょう。
人事労務DXは、部分的な導入から始める方法と、一括導入する方法のどちらかを、自社の状況に応じて選択します。
導入後は、DX人材を中心に定着を促進するための教育やサポートを行います。定期的に利用状況を確認するとともに、導入前に試算した効果を検証しましょう。
新しいツールに適応するまでには一定の時間がかかるため、「現場の負担を軽減しながら定着させる」 意識が必要です。
担当者が率先して、明確な成果を示すことで、全社的な理解と協力を得られるはずです。
新たな課題が発見された際は、追加機能の導入や別システムの検討も視野に入れ、継続的な改善を進めていきましょう。
人事労務DX(人事評価DX)の成功事例
大手業務用厨房機器メーカーでは、人事評価システムの導入により、大幅な業務効率化を実現しています。
従来は紙やエクセルによる評価管理を行っており、評価シートの回収に最大5か月を要するなど、効率化に課題がありました。
人事労務DXの推進により、生産性向上が実現し、作業工数は半減する見込みとなっています。
効率化により確保できた時間は、人事制度の見直しにあてる予定です。詳しくは以下の記事もご確認ください。
→同社のほか、年間600時間の評価にかかっていた工数を25%まで削減した事例は【こちら】
人事労務DXの実現に向けて(まとめ)
日本の社会構造は大きく変化し、働き方も多様化が進んでいます。人事労務DXの推進は企業の持続的な成長に不可欠な要素となっています。
人事労務DXは、単なる業務のデジタル化ではありません。従業員一人ひとりの能力を最大限に引き出し、企業の競争力を高める重要な経営戦略です。業務効率化による工数削減、データに基づく戦略的な人材マネジメント、ペーパーレス化によるコスト削減など、効果は多岐にわたります。
データの整理や新システムへの移行、人材育成など、取り組みにはさまざまな課題が存在します。段階的なアプローチと計画的な移行により、課題は着実に克服できるでしょう。
人事労務DXの推進により、企業は活性化し、従業員の働きがいも向上します。優秀な人材が集まる好循環が生まれ、企業の持続的な成長が実現するでしょう。
人事労務DXを推進「One人事」
「One人事」は使いやすいと好評の人事労務システムです。
ワンストップ(オールインワン)型(1つのデータベース管理)が特長ですが、労務・勤怠・給与からタレントマネジメントまで、課題に応じてスモールスタートも可能です。
手厚いサポート体制で、貴社の導入スケジュールにあわせて柔軟に対応できます。まずはお気軽にご相談ください。専門のスタッフが貴社の課題をていねいにお聞きしたうえでご案内いたします。
また操作や社内への定着に不安がある場合は、ぜひ無料トライアルをお申し込みください。