雇用保険料の計算に交通費は含む? 賃金や保険料の計算方法を解説
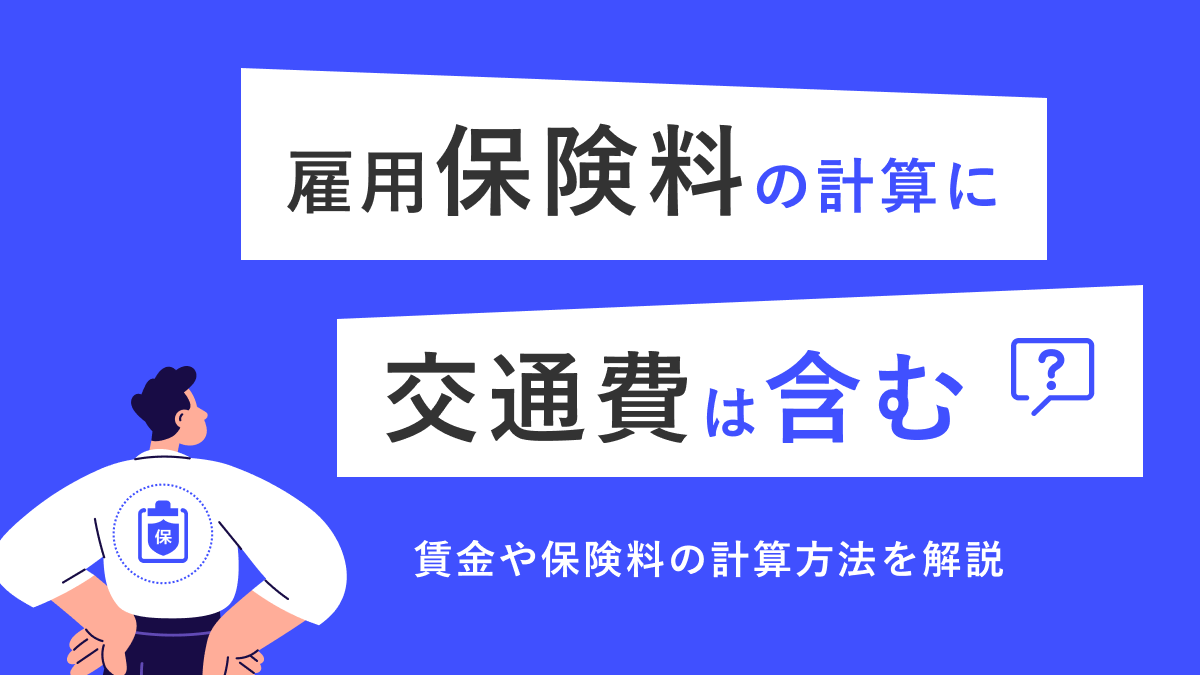
雇用保険料の計算をする際は、給与に関するさまざまな要素を考慮しますが、交通費が対象になるかも知っておかなければなりません。
本記事では、雇用保険法に基づく賃金の定義をはじめ、雇用保険料の計算方法について詳しく解説します。

 目次[表示]
目次[表示]
雇用保険の基礎について解説
雇用保険の基本的な概要について詳しくご紹介します。
雇用保険とは労働者が失業や休業した際に支援する制度
雇用保険とは、労働者が失業や休業をした場合に経済的な支援を行う制度です。企業は雇用保険に加入する義務があり、そのことにより労働者は失業・休業時でも安定した生活を維持する基盤をつくれるのです。
従業員を雇用したら雇用保険の適用事業所となる
企業は、1人でも加入条件を満たす従業員を雇用した場合、雇用保険の「強制適用事業所」とみなされます。
雇用保険は強制加入制度であり、企業は適用事業所の設置申請を行い、雇用保険への加入準備を進めなければなりません。個人事務所も企業と同様に、従業員を雇用している場合は原則として強制適用事業所となります。
また、強制適用事業所以外に「暫定任意適用事業所」も存在します。暫定任意適用事業所とは、以下のすべての条件を満たす事業所を指します。
- 農林水産業であること
- 個人経営であること
- 常時5人未満の労働者を使用すること
暫定任意適用事業所に該当する場合には、雇用保険に加入するかは任意です。ただし、労働者の2分の1以上が希望するときには、事業主は厚生労働大臣に加入の申請を行わなければなりません。
従業員が雇用保険に加入する条件
従業員が雇用保険に加入するためには、次の2つの条件を満たす必要があります。
- 31日以上の雇用が見込まれる
- 1週間の労働時間が20時間以上
しかし、昼間部に通う高校生や大学生などは、雇用保険の加入義務がありません。昼間部の学生は通常の労働時間外で働くことが多いため、このような制度が設けられています。

雇用保険料の基本的な概要
雇用保険料の仕組みとその計算方法を理解することは、企業や従業員にとって非常に重要なポイントです。ここからは、雇用保険料の基本的な概要についてご紹介します。
雇用保険料とは何か
雇用保険料とは、労働保険制度における「雇用保険の掛け金」のことです。労働保険制度には、雇用保険と労災保険の2種類があります。これらの保険料は給付内容が異なるものの、労働基準監督署などに対してまとめて納付されます。
雇用保険料は企業と労働者がともに負担する
雇用保険料は、企業と労働者が共同で負担することで成り立つ制度です。しかし、健康保険や厚生年金保険のように企業と労働者が半分ずつ負担するわけではなく、保険料は「雇用保険法上の賃金」に基づいて算出されます。
「雇用保険法上の賃金」について
雇用保険料の計算をする際の重要な基準の一つが「雇用保険法上の賃金」です。雇用保険法上の賃金の概要についてご紹介します。
労働の対償として労働者に支払う「すべてのもの」
雇用保険法上の賃金とは、労働の対償として事業主から労働者に支払われるすべてのものを指します。
賃金にはさまざまな項目が含まれますが、具体的な手当は次のとおりです。
- 通勤手当(非課税分を含む)
- 定期券代
- 超過勤務手当
- 深夜手当
- 宿直手当
- 家族手当
- 扶養手当
- 技能手当
- 住宅手当など
交通費も「雇用保険法上の賃金」に含まれる
雇用保険法上の賃金に交通費も含まれるか気になる方も多いでしょう。結論からお伝えすると、出社に必要な交通費も雇用保険法上の賃金に含まれます。
企業が従業員に対して毎月交通費を支給している場合、その金額も賃金の一部として考慮され、保険料の計算に反映されるのです。
交通費以外に雇用保険料の計算に関係するもの
交通費以外にも、雇用保険料の計算にかかわる要素は多数あります。たとえば、次のような手当も賃金に含まれるため、保険料の計算をする際に考慮しなければなりません。
- 残業手当
- 扶養手当
- 住宅手当
- 特殊勤務手当など
上記のような手当も雇用保険料の計算に関係する要素であると把握し、正確に雇用保険料を算出する必要があります。
そもそも「交通費」とは
業務をする際に必要な交通費も、雇用保険法上の賃金に大きく影響を与える要素です。交通費の概要や、どのように処理すべき手当なのかを解説します。
交通費とは仕事に必要な移動費
交通費とは、具体的には業務上必要な移動にともなう費用を指します。具体的には、次のようなコストが交通費に該当します。
- 電車やバスの定期券や回数券
- 飛行機や新幹線などでの移動費
- ガソリン代
- 駐車場代
- 有料道路料金 など
交通費と似た手当として通勤手当がありますが、両者の違いは次のとおりです。
| 交通費(出張費) | 業務中の移動で発生する費用 |
|---|---|
| 通勤手当(通勤交通費) | 自宅から会社への通勤で発生する費用 |
交通費は、業務にともなう移動の費用であるため費用は会社が負担します。従業員が立て替えて支払ったあとに、会社に請求するケースが一般的です。
通勤交通費(通勤手当)は「非課税通勤費」として処理できる
給与として所得税の課税対象となる残業手当や扶養手当、住宅手当などとは異なり、通勤のための交通費である通勤手当は非課税限度額までは「非課税通勤費」として処理できます。
つまり、課税所得に含まれないため、所得税が課せられません。
通勤手当の非課税限度額は、ガソリン代・交通費の高騰を理由として、2025年11月に改正されました。
| 区分 | 非課税最高限度額 | |
|---|---|---|
| 公共交通機関を利用する場合 | 15万円 | |
| 自動車や自転車などの交通用具を使用する場合 | 通勤距離が片道55km以上である場合 | 3万8,700円 |
| 通勤距離が片道45km以上55km未満である場合 | 3万2,300円 | |
| 通勤距離が片道35km以上45km未満である場合 | 2万5,900円 | |
| 通勤距離が片道25km以上35km未満である場合 | 1万9,700円 | |
| 通勤距離が片道15km以上25km未満である場合 | 1万3,500円 | |
| 通勤距離が片道10km以上15km未満である場合 | 7,300円 | |
| 通勤距離が片道2km以上10km未満である場合 | 4,200円 | |
| 通勤距離が片道2km未満である場合 | 全額課税 | |
| 通勤用定期乗車券を使って交通機関を利用する場合 | 15万円 | |
| 公共交通機関と車など複数を組みあわせている場合 | 15万円 | |
雇用保険料率について
雇用保険料を計算する際に重要なのが「雇用保険料率」です。ここからは、雇用保険料率の概要について詳しく紹介します。
雇用保険料率は雇用保険料を計算する際に用いられる利率
雇用保険料率とは、雇用保険料を計算するために用いられる利率です。企業と労働者が負担する雇用保険料の金額を、毎月の給与総額に対して雇用保険料率を掛けて算出します。
雇用保険料率は毎年見直しが行われる
雇用保険料率は、失業保険の受給者数や積立金の残高に応じて毎年見直しが行われ、料率に変更がある場合は毎年4月1日から施行されます。近年では、新型コロナウイルスの影響で雇用保険の財源が悪化したことを理由に、2022年に雇用保険料率が引き上げられました。最新の2025年度では、前年より引き下げられています。
| (1)労働者負担 | (2)事業主負担 | (1)+(2)雇用保険料率 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| (2)事業主負担の合計 | 失業等給付・育児休業給付の保険料率 | 雇用保険二事業の保険料率 | |||
| 一般の事業 | 5.5/1,000 | 9/1,000 | 5.5/1,000 | 3.5/1,000 | 14.5/1,000 |
| 農林水産・清酒製造の事業※ | 6.5/1,000 | 10/1,000 | 6.5/1,000 | 3.5/1,000 | 16.5/1,000 |
| 建設の事業 | 6.5/1,000 | 11/1,000 | 6.5/1,000 | 4.5/1,000 | 17.5/1,000 |
出典:『令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内』厚生労働省
雇用保険は「一般の事業」と「農林水産・清酒製造の事業」「建築の事業」の3つに分類されており、それぞれの事業で保険料が異なるため注意しましょう。
雇用保険料の計算方法を解説
雇用保険料を正確に算出するために、正しい計算方法を理解しましょう。
「雇用保険料率 × 賃金」で計算される
雇用保険料の基本的な計算式は、次のとおりです。
▽雇用保険料の計算方法
| 給与額または賞与額 × 雇用保険料率 |
ここでの給与額または賞与額とは「雇用保険法上の賃金」を指し、通勤にかかる交通費や各種手当も含まれます。
雇用保険料を算出する際は、その年度の雇用保険料率とそれぞれの従業員の賃金をもとに計算していくのです。
雇用保険料に端数が出た場合の処理方法
雇用保険料を計算した結果、端数が出る場合があります。その際の基本的な処理方法は、「50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上の場合は切り上げ」です。
ただし、労使ともに納得のうえ、慣習として長いこと続いてきた取り決めとしての特約がある場合、そちらに沿って処理をしても問題ありません。
ボーナスや残業代などによって賃金は変動する点に注意
賃金は、ボーナスや残業代などにより月ごとに変動します。そのため、雇用保険料も同様に変動するものと考え、その都度算出しなければなりません。毎月正確な計算が求められること、毎月定額ではないことを理解したうえで、正確に算出していきましょう。
交通費や雇用保険料の計算にはクラウドサービスの活用がおすすめ
雇用保険は、労働者が失業や休業をした際の生活を支援する重要な制度であり、その適用は1人以上の従業員を雇うすべての企業に対して義務づけられています。
雇用保険料は企業と労働者がともに負担し、「雇用保険法上の賃金」を基準として算出されます。
「雇用保険法上の賃金」には労働の対償として労働者に支払われるすべてのものが該当し、通勤手当(非課税分を含む)や各種手当、そして交通費も含まれます。
したがって、雇用保険の計算時には交通費も考慮しなければなりません。交通費は給与として所得税の課税対象となる残業手当や扶養手当、住宅手当などとは異なり、通勤交通費は非課税限度額までは「非課税通勤費」として処理できます。
通勤手段によって非課税限度額が異なるので、雇用保険料を算出する際は注意しましょう。
「One人事」は人事労務をワンストップで支えるクラウドサービスです。人事労務情報の集約からペーパーレス化まで、一気通貫でご支援いたします。電子申請や年末調整、マイナンバー管理など幅広い業務の効率化を助け、担当者の手間を軽減。費用や気になる使い心地について、お気軽にご相談いただけますので、まずは当サイトよりお問い合わせください。
当サイトでは、サービス紹介資料はもちろん、無料のお役立ち資料をダウンロードいただけます。業務効率化のヒントに、こちらもお気軽にお申し込みください。

