家族手当とは?金額の相場や支給条件、廃止が増えている背景などを解説
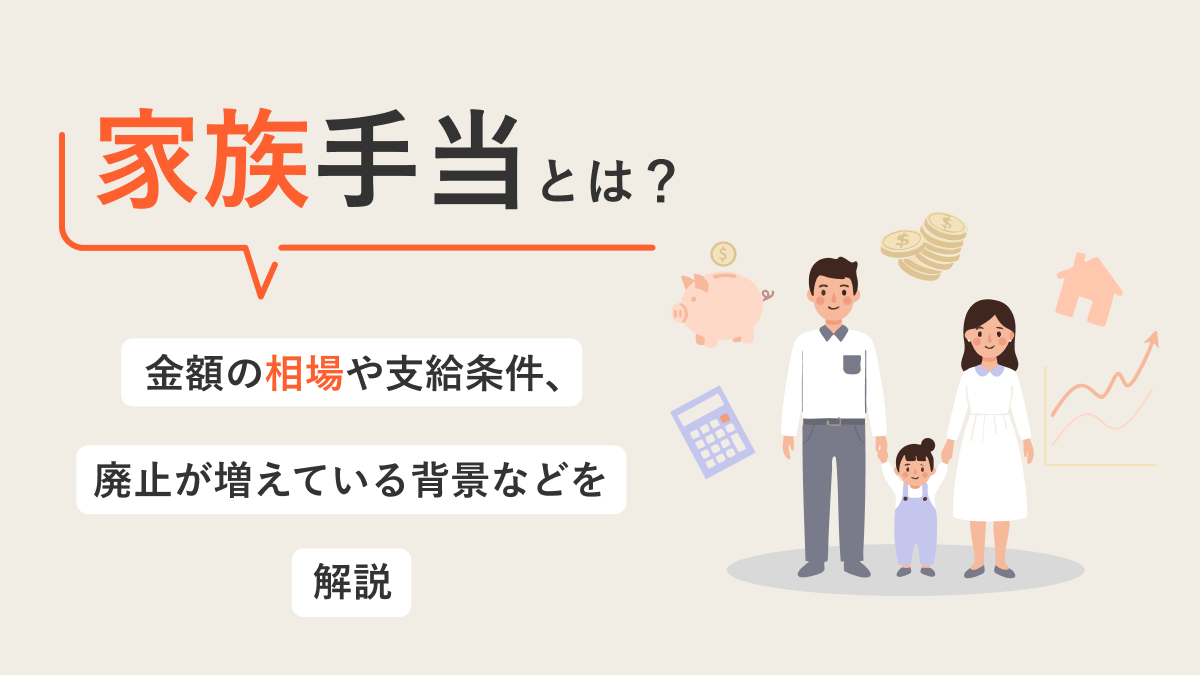
家族手当は、従業員の福利厚生の一環として多くの企業で導入されてきた制度です。社会や働き方の変化を背景に、意義や運用方法が大きく問われています。
経営者や人事担当者にとっては、「自社の家族手当制度は現状に合っているのか」「支給条件や金額の相場はどうなっているのか」など、さまざまな疑問や課題が浮かび上がっているのではないでしょうか。
本記事では家族手当の基本的な仕組みや支給条件、金額の相場、廃止や見直しが進む背景と影響について詳しく解説します。
 目次[表示]
目次[表示]
家族手当とは
家族手当とは、従業員に配偶者や子どもなどの家族がいる場合に支給される福利厚生の一種です。企業が従業員の生活を支援し、経済的な負担を軽減する目的で設けられています。
家族手当は法的に義務づけられた制度ではありません。支給の有無や金額、要件は各企業が就業規則や雇用契約で独自に定めるものです。
企業ごとに内容や支給条件が異なるため、自社の現状や社会的な動向を踏まえて制度設計を行うことが求められます。
扶養手当との相違点
家族手当と扶養手当は似ていますが、支給対象や条件に違いがあります。
家族手当は、配偶者や子どもなどの家族がいる従業員に支給される手当であり、必ずしも扶養していることを条件としない場合もあります。
一方で扶養手当は、扶養している家族が支給の前提です。扶養手当の場合は、家族の収入が一定額を超えると支給対象外となることが一般的です。
企業によっては「配偶者手当」「子ども手当」など名称を分けている場合も多く、扶養手当は家族手当の一種とみなされることもあります。支給条件や対象範囲は企業ごとに異なるため、就業規則をよく確認することが重要です。
育児手当との相違点
育児手当は、子どもを養育する従業員に対して支給される手当です。
家族手当が配偶者や親など幅広い家族を対象とするのに対し、育児手当は主に従業員の子どもを対象としています。
子どもの人数や年齢によって、支給額を変動する場合が多く、保育料の補助や子育て支援を目的とした制度として設けられています。未就学児や小学生までを対象とするケースや、子ども1人ごとに一定額を支給するケースなど、企業によって運用方法はさまざまです。
育児手当は、従業員の子育てと仕事の両立を支援し、働きやすい職場環境づくりや人材の定着にも貢献する福利厚生の一つです。
家族手当の導入状況
家族手当の導入率は、人事院の調査によると、全体で74.5%と高く、大企業ほど導入が進んでいるようです。
企業規模別の家族手当導入率を見ると、従業員500人以上の企業が74.1%、従業員50人以上100人未満の企業が69.9%となっています。
家族手当の金額の相場
家族手当の金額相場は企業規模によって大きく異なり、大企業ほど支給額が高い傾向にあります。経営基盤の安定や福利厚生にかける余裕が大きいためです。
厚生労働省が毎年実施している調査によると、従業員1,000人以上の企業では、令和元年の平均額は22,200円でした。従業員30~99人の企業では平均12,800円と低くなっています。
| 企業規模 | 平均支給額(円) |
|---|---|
| 1,000人以上 | 22,200 |
| 300~999人 | 16,000 |
| 100~299人 | 15,300 |
| 30~99人 | 12,800 |
家族手当は、配偶者や子どもの人数によっても相場が異なります。東京都産業労働局の調査によれば、家族別支給の場合、平均額は以下のように報告されています。
- 配偶者:10,914円
- 第一子:5,884円
- 第二子:5,191円
- 第三子:5,160円
参照:『中小企業の賃金・退職金事情(令和5年版)』東京都産業労働局
家族手当の支給条件
家族手当の支給条件は、企業ごとに細かく設定が可能です。
多くの企業では、従業員の家族構成や家族の収入状況、同居の有無をもとに、次のような基準を設けています。
- 配偶者や子どもの人数
- 配偶者や子どもの年齢
- 家族の収入
- 家族と同居しているか
- 従業員が世帯主か
家族手当の支給は、配偶者や子どもがいることを基本条件とし、人数に応じて支給額を増減させる企業が一般的です。
子どもや親の年齢に上限を設けているケースもあり、「18歳未満」や「大学卒業まで」など、細かく条件を定めることもあります。
家族の収入については、配偶者や扶養家族の年間収入が123万円以下、または130万円未満を要件とする企業が多いようです。これは税法上の扶養控除や社会保険の被扶養者基準に準拠しています。
さらに、家族と同居していることや、従業員本人が世帯主であることを家族手当の支給要件に加える場合もあります。
従業員の経済的負担を軽減する家族手当は、適切な支給条件を設定することで、福利厚生の充実につながるでしょう。
家族手当のメリット
家族手当には、従業員の経済的負担を軽減するだけでなく、企業にとっても多くのメリットがあります。
- 生活費・教育費などの支出をサポートできる
- 従業員満足度の向上・離職率の低下につながる
- 求職者への訴求力が高まり、採用競争力が上がる
- CSR(企業の社会的責任)の観点から評価されやすい
たとえば、結婚や出産などで支出が増えるタイミングに、毎月一定額の手当があることは、従業員にとって大きな安心材料となります。
金銭的な支援があることで、仕事に集中しやすくなり、企業への信頼感や定着率の向上にもつながります。
また、福利厚生が充実している企業は、求職者にとって魅力的に映るでしょう。家族手当は、採用活動においても他社との差別化をはかる有効な制度です。
さらに、家族全体を支援する制度として、企業の社会的責任(CSR)の観点からも評価されやすく、企業イメージの向上も期待できます。
家族手当のデメリット
家族手当には一定のメリットがある一方で、制度の運用次第では不公平感や形骸化(けいがいか)といった課題も生まれやすくなります。
- 家族構成によって給与格差が生まれる可能性がある
- 独身者やDINKS(意識的に子どもの持たないと決めた共働き夫婦)に不公平感が生じる
- 支給条件が共働き世帯にあわず、「働くほど損」になるケースがある
- 時代に合わず、制度の意義が薄れてきている
たとえば、配偶者手当が月1万円、子ども手当が8,000円×2人支給される場合、独身者との間に年間31万2,000円の差が生まれます。
給与格差は若手社員の月給約1か月分に相当する場合もあり、「労働の量や質と関係のない、個人の事情で賃金に差がつくのは不公平だ」と感じる従業員も少なくありません。
また、共働き世帯の増加により、家族手当制度の意義も薄れているのが現状です。多くの企業では、配偶者の年収が税法上の扶養控除や社会保険の被扶養者基準額を超えると支給対象外となるため、フルタイムで働く配偶者がいる家庭では手当を受け取れません。
2018年の配偶者特別控除の改正以降、パート勤務でも勤務時間を延ばして年収が基準を超えるケースが増え、「働けば働くほど損をする」という逆転現象も起きています。
家族手当は「制度そのものが時代にあっていない」といった根本的な見直しも指摘されています。
家族手当を廃止する企業が増加している理由
状況の変化を受けて、家族手当の廃止を検討する企業が増えてきました。背景には、社会構造の変化、法制度の改正、働き方の多様化といった要素が複雑に絡み合っています。
家族手当の主な廃止理由は以下の3つです。
- 生活様式の変容と多様性の拡大
- 配偶者控除制度の変更
- 職務内容に応じた公平な報酬体系の促進(同一労働同一賃金)
それぞれの背景について、詳しく見ていきましょう。
生活様式の変容と多様性の拡大
家族手当の見直しが進む最大の理由は、生活様式と家族形態の変化です。
かつて家族手当制度が広まった高度経済成長期には、「男性が働き、女性が家庭を守る」という性別役割分担が一般的でした。現在では女性の社会進出が進み、共働き世帯が主流になっています。
家族手当の前提である「男性1人が家計を支える」というモデルは、今や現実とは大きくかけ離れています。
また、単身世帯や子どものいない共働き夫婦、事実婚カップルなど、家族のかたちも多様化しています。新しい家族像には、従来の家族手当では対応しきれません。
配偶者控除制度の変更
税制の変化も、家族手当の廃止や見直しを加速させた大きな要因です。
2018年1月に実施された税制改正により、配偶者控除の満額適用上限が103万円から150万円に引き上げられ、さらに201万円までは段階的に控除を受けられるようになりました。
女性の就労を後押しする目的で設計された本改正は、多くの企業の家族手当制度に影響を与えています。
家族手当の支給条件を税制上の扶養範囲に連動させていた企業では、控除の拡大により、家族手当の支給対象者が増加しました。結果として、人件費が膨らみ、制度の見直しを迫られているのです。
さらに2025年には「103万円の壁」が「123万円の壁」に引き上げられました。そのため、配偶者がパートで働く家庭で扶養を外れるケースがさらに増えると見込まれています。家族手当制度についても、再検討の時期に来ているといえるでしょう。
職務内容に応じた公平な報酬体系の促進(同一労働同一賃金)
家族手当の廃止が進む理由には、「同一労働同一賃金」の原則による影響もあります。
2020年4月に施行された「パートタイム・有期雇用労働法」により、正社員と非正規社員の間で不合理な待遇差を設けることが禁止されました。家族手当についても例外ではありません。
たとえば日本郵便事件の最高裁判決では、正社員にのみ扶養手当を支給し、同じ業務を担当する非正規社員に支給しないことが不合理とされました。
判決により、企業は家族手当を正社員のみに支給することの合理性を説明しなければならなくなりました。
しかし、家族構成は職務内容や責任の程度とは無関係であるため、合理的な説明が困難な場合も少なくありません。
多くの企業では非正規社員にも一律で家族手当を支給するか、制度自体を廃止するかという選択を迫られています。
参考:『実務に活かす!「同一労働同一賃金」最高裁判決から考える』厚生労働省
家族手当を廃止(見直し)する場合の手順
家族手当の廃止や見直しは、労働条件の不利益変更にあたる可能性があり、慎重に対応しなければなりません。
労働契約法では、従業員の合意なく労働条件を不利益に変更することを原則として禁止しています。変更の合理性や必要性、従業員への配慮などが総合的に判断されます。
適切な手順を踏まずに制度を変更すると、変更自体が無効とされるリスクもあります。
ここからは、法的リスクを回避しつつ、従業員の理解を得ながら制度を見直すための具体的な進め方について解説します。
1.見直し案の策定
家族手当の見直しは、現状の正確な把握から始めましょう。
対象となる従業員数や家族構成、月額・年間の支給総額をデータで整理し、見直し後の影響を客観的に予測します。
変更案の検討では、以下の選択肢を比較・検討します。
- 完全廃止・段階的縮小・支給条件の変更
- 代替案(基本給への組み入れ、子ども手当、資格手当、成果手当の導入)
- 経過措置(段階的減額、差額補償、移行期間の設定)
従業員の不利益を最小限に抑える視点で、現実的な選択肢を検討していきましょう。
2.従業員との対話
家族手当の見直し案がまとまったら、従業員への説明と意見収集を行います。
説明会の開催や社内イントラネットでの情報公開、部門別のヒアリングなどで情報を共有します。背景や目的、変更点、代替措置、スケジュールまでていねいに伝えましょう。
とくに家族手当を受けている従業員には、アンケートや個別面談、労働組合との協議を通じて、生活への影響や不安の声を受け止めなければなりません。
収集した意見をもとに、家族手当の見直し案を再検討し、変更による個々の従業員への金銭的な影響を具体的に算出します。変更前後のコストも比較し、社内の理解を深めましょう。
3.最終決定
従業員との対話を踏まえて最終案を決定します。変更の必要性や代替措置、経過措置については、納得感を得られるよう、繰り返し説明しましょう。
労働組合がある場合は、労使協議を重ね、合意形成をはかります。労働組合がない場合でも、従業員代表との協議や全体説明会を開催し、透明性を確保することが重要です。
とくに注意したいのは、収入減少が見込まれる従業員への対応方法です。
多くの企業では、労働組合との協議を経て包括的な合意を得る形式が一般的です。
労働組合がない場合は一人ひとりと面談を行い、変更内容をていねいに説明し、同意を得なければなりません。同意が得られない場合は、さらなる経過措置や代替案の提示も検討しましょう。
4.制度化と周知
最終決定後は、家族手当に関する就業規則や関連規程(賃金規程・福利厚生規程など)を見直し、必要な改定手続きを進めます。
変更が完了したら、労働者代表の意見書を添付し、労働基準監督署へ届け出を行いましょう。
改定後の就業規則は、従業員がいつでも閲覧できる状態にします。制度の概要や変更点を全従業員に伝えるとともに、人事部門に相談窓口を設け、疑問や不安に対応できる体制を整えましょう。
変更後も、従業員の声や反応を見ながら、必要に応じて補足説明や追加対応を行うことが大切です。 ていねいなフォローが、制度変更への納得感を高め、労務トラブルの防止につながります。
まとめ
家族手当はこれまで従業員の生活支援や人材確保に貢献してきました。
しかし、共働き世帯の増加やライフスタイルの多様化により、現代の働き方に合わなくなりつつあります。
同一労働同一賃金の法制化や最高裁判決の影響により、正社員のみに支給する制度の継続が難しくなり、多くの企業で家族手当の廃止や見直しが進められています。
今後は、基本給への組み入れや子育て支援の充実など、働き方の多様性に応じた制度設計が必要です。
従業員の理解と納得を得ながら、柔軟かつ慎重に制度を見直していきましょう。
家族手当の給与反映を効率化|One人事[給与]
One人事[給与]は、家族手当をはじめ、自社独自の手当の反映も柔軟に設定できるクラウド型給与計算システムです。見やすく迷いがない操作画面で、ミスなく簡単に設定が完了します。
また勤怠管理システムOne人事[勤怠]と連携すると、勤怠データの取り込みがスムーズになり、給与計算に欠かせない労働時間の集計も自動化できます。
One人事[給与]の初期費用や気になる使い心地については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門スタッフが、貴社の課題をていねいにお聞きしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、給与計算をはじめ人事労務の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。給与計算をシンプルにして「本来やりたい業務」に集中したい企業は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |
