残業代だけ翌月払いできる? 繰越は違法? 適切な支払い時期と退職者・昇給者に対する注意点
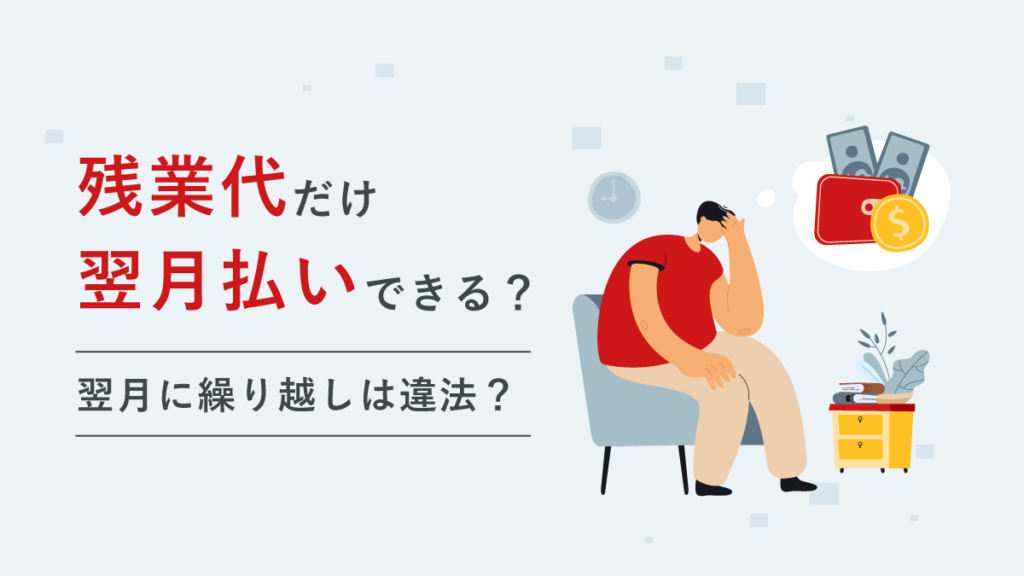
残業代を翌月払いにするのは違法になる可能性をご存じですか。残業代の支払い方法は企業ごとに異なりますが、どのような方法でも認められるわけではありません。従業員に不利な支払い方法を選択してしまうと、法律違反となるため注意が必要です。
では「翌月払い」や「繰越」は法律上、認められるのでしょうか。
本記事では、残業代の適切な支払い時期を確認し、翌月払いの違法性について解説しています。退職者や昇給者に対する実務的な注意点も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
 目次[表示]
目次[表示]
残業代の翌月払いは違法となるおそれがある
残業代を翌月の賃金と合わせて支払うのは、運用次第で違法となるおそれがあります。
とくに従業員にとって、不利益となる支払い方法やタイミングになる場合は注意が必要です。
残業代の翌月払いが法的に許されるケースと許されないケースを、企業が留意したいポイントを交えて解説します。
就業規則で定めていれば違法でない
残業代の支払い時期を、就業規則で翌月に定めてあれば翌月払いは違法ではありません。
たとえば、給与自体が「月末締め翌月払い(=当月働いた分を翌月の指定日に支払う)」を採用している企業では、文字どおり残業代は基本給などと一緒に「翌月払い」が可能です。
事前に定めた支払い時期に給与の一部として残業代を支払えば、賃金の支払いのルールに反しません。
支払い時期を超えて残業代だけ後払い・翌月に繰り越すのは違法
残業代の支払いを、就業規則や賃金規程で定めている時期を超えて行った場合、違法行為とみなされます。労働基準法第24条の「賃金支払いの5原則」に反するためです。
「賃金支払いの5原則」とは、労働の対価である賃金を、労働者が確実に受け取れるように定められたルールです。
| 賃金支払いの5原則 | |
|---|---|
| 通貨払いの原則 | 賃金は通貨で支払う必要があり、現金以外の現物での支払いは認められない |
| 直接払いの原則 | 賃金は労働者本人に直接支払わなければならない |
| 全額払いの原則 | 賃金は全額を支払う必要がある。分割払いや残業代の翌月払いなど、賃金の一部の支払い猶予は認められない |
| 毎月1回以上払いの原則 | 賃金は毎月1回以上支払わなければならない |
| 一定期日払いの原則 | 賃金の支払いについて一定の期日を定め、定められた日に支払わなければならない |
出典:『賃金の支払方法に関する法律上の定めについて教えて下さい。』厚生労働省
事前に支払い時期を定めず、基本給とは別で残業代だけを「翌月に後払い」にしてしまうと、「全額払いの原則」に反します。翌月に繰り越す方法は従業員の不利益となってしまうため、認められていません。
違法な残業代の後払いの例
残業代だけ「翌月繰越」や「別払い」といった後払いが問題になるケースは、ほかにもあります。いずれも「全額払いの原則」に反するため認められていません。
ただし、就業規則や雇用契約書などに残業代だけを翌月に後払いすることが定められている場合は、決められた支払い時期に賃金の支払いをしているため、問題ありません。
| 残業代の後払いが違法になる例 |
|---|
| 就業規則などに定めがなく、毎月の給料とは別に、残業代のみ翌月払いとする |
| 就業規則などに定めがなく、残業代の一部を翌月に繰り越す |
| 複数月の残業代をまとめて払う |
| 残業代をボーナスに含めて払う |
以上のような残業の後払い行為、残業代を含む賃金の未払いが発覚すると、労働基準法違反とみなされるため注意が必要です。
事業主には「懲役6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金」が科せられる可能性があるため理解しておきましょう。
支払い期日を過ぎた残業代には遅延損害金が発生する
残業代支払いが支払い期日を過ぎると、未払い分に対して遅延損害金が発生します。
遅延損害金は、支払い遅延による従業員の損害賠償をするためのもので、強制的に支払いを求める仕組みです。
利率は基本的に民法で年3%と定められ、従業員の退職後は『賃金の支払の確保等に関する法律』に基づいて年14.6%に引き上げられるため、さらに大きな負担となります。
未払い残業代に高い利率が適用されることで、企業は金銭的なダメージを受けるため、支払いスケジュールを管理し、遅延が発生しない体制を整えましょう。
参照:『民法』e-Gov法令検索
参照:『賃金の支払の確保等に関する法律』e-Gov法令検索
残業代の支払いはいつにする?
それでは残業代はいつ支払うのが適切なのでしょうか。原則として毎月の基本給などと一緒に支払われるのが理想です。
しかし状況に応じて例外的な措置も設けられています。いずれにしても雇用契約書などで、あらかじめルールを明確にしておくことが大切です。
残業代の適切な支払い時期を解説します。
原則として毎月の給料日に払う
特別な理由がない限り、残業代も毎月の給料日に、月給や手当などと一緒に支払うのが原則です。
毎月の給料日は、雇用契約書や就業規則に「給料の締め日」や「支払い日」として定められているはずです。
賃金支払いの5原則にある「毎月1回以上払いの原則」「一定期日払いの原則」「全額払いの原則」に沿って、賃金は毎月1回以上、定期的に全額を支払う必要があります。
例外1.就業規則などの定めで当月締め月末日払いとしている場合
当月の給与を月末支給に設定している企業では、就業規則や雇用契約書に明記することで、残業代だけ翌月の給与支給日に精算が可能です。
基本給や家族手当・住宅手当などとは異なり、残業代は実際の時間外労働時間数が定まらない限り、正しい金額を計算できないためです。
当月締め月末日払いの場合、月末まで働いたものとみなして給与を支払います。当月に残業が発生した場合、次回の支払いで調整するしかありません。
当月締め月末日払いに限らず、就業規則や雇用契約で定めることにより、残業代のみを翌月に支給できます。
ただし、残業代を翌月支給にするような就業規則の変更は、不利益変更とみなされます。
就業規則などによらず、何らかの事情で同月の給与と残業代を支払うタイミングがずれてしまった場合は、賃金未払いとなるため、すみやかに対応しましょう。
例外2.給料日が土日祝日の場合
給料日が月によって土日祝日と重なる場合、例外的な処置として、支払い日の調整が認められています。
前倒しで支払ったり、後ろ倒しをして翌営業日に支払ったりする対応であれば問題ありません。
ただし、給料日の翌営業日が翌月になる場合は、労働基準法で定められている「毎月1回以上払いの原則」を守るため、支払いを前倒しするのが一般的です。
残業代を支払う時期は就業規則・雇用契約書で定める
残業代を支払うタイミングは、就業規則や雇用契約書で定めることが大切です。
労働基準法により、賃金の締め日や支払う時期は、就業規則の絶対的必要記載事項とされています。
10名以上の従業員を雇用する事業場は、労働基準監督署長に就業規則を届け出る義務が課せられています。万が一、就業規則が作成・届出されていない場合は違法となるため、注意が必要です。
従業員10名未満の事業場で就業規則を定めない場合は、雇用契約書や労働条件通知書に給料の締め日と支払い期日を記載しましょう。
退職者・昇給者の残業代支払いについて
残業代は適切な時期に支払う必要があり、なかでも退職者や昇給者は、通常とは異なるポイントがあります。
| 退職者の残業代支払い | 退職日と給与日がずれる場合はすみやかに支払う |
| 昇給者 | 昇給前後で日割りする |
対応を誤るとトラブルや法的リスクにつながる可能性があるため慎重に対応しましょう。
退職者
従業員の退職時は、金銭や労働のトラブルが発生しやすいため、特別な規定が設けられています。
退職者から請求があったら、7日以内に賃金を支払わなければなりません。
当月締め月末日払いの企業では、まだ残業代が確定しない時点で、退職従業員が最後の給与日を迎えることになります。
支払い日を過ぎたあとに、予定外の残業代が発生したら、従業員から請求されていなくてもすみやかに支払いましょう。
月の途中の昇給者
月の途中で昇給した従業員は、昇給前と昇給後で日割り計算するのが一般的です。
前後の基本給をもとに、それぞれの残業単価を割り出し、合算した額を月の残業代とします。
たとえば、昇給が15日に行われた場合、1日から14日までは昇給前、15日以降は昇給後の給与として計算します。
未払い残業代を放置するリスク
残業代だけ給与と別にして支払うのは、未払い残業代とみなされるリスクがあります。未払い残業代を放置すると、企業にとって重大な労務トラブルを引き起こしかねません。
未払い残業代を放置した場合の4つのリスクを解説します。
- 従業員からの未払い残業代を請求される
- 会社の評判や企業イメージが悪くなる
- 労働基準監督署から是正勧告を受ける
- 刑事罰を科される
従業員からの未払い残業代を請求される
残業代を正しく支払わないと、従業員から未払い分を請求されるリスクがあります。
請求方法は、内容証明郵便での請求や労働組合を通じた請求などさまざまな手段があり、いずれも対応が必要です。
請求があったにもかかわらず支払わないと、労働審判や民事訴訟などの司法手続きに発展する可能性もあります。
2020年4月の法改正により、残業代の請求期間が従来の2年から5年に延長(経過措置により当面は3年)延長されました。今後の法改正によっては、より長期間にわたる残業代を請求される可能性も否定できません。
参照:『労働者の皆さま 未払賃金が請求できる期間などが延長されています』厚生労働省
会社の評判や企業イメージが悪くなる
未払い残業代を請求され、労働審判や民事訴訟に発展した事実が公になると、悪評につながりネガティブなイメージが広がってしまいます。
たとえ報道されなくても、インターネット上の口コミや掲示板で情報が流出するおそれがあります。
採用活動に支障が出て人材の確保が難しくなったり、消費者による不買運動が起こったりするなど、悪影響が考えられるでしょう。
労働基準監督署から是正勧告を受ける
残業代の未払いは労働基準法第37条違反であり、労働基準監督署による調査の対象となります。調査の結果、違法性が判断されると、是正勧告が出されます。
是正勧告を受けた企業は、定められた期限内に未払い残業代を支払い、労働基準監督署への報告が必要です。
刑事罰を科される
残業代の支払いについて、指摘や是正勧告を受けても改善されない場合や、帳簿やデータの改ざんで悪質性が高いと判断された場合は、刑事処分の対象です。
「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」を科される可能性があります。
会社ぐるみで残業代の未払いを行っていた場合、事業主だけでなく実際に関与した従業員も処罰の対象になるかもしれません。
さらに労働基準監督署によって送検されると、企業名が公表されるため、企業のイメージ低下につながります。
残業代の不適切な支払いを防ぐには?
未払い残業代をはじめ、残業代の不適切な支払い状況を放置しないために、企業としてできる取り組みを3つ取り上げて紹介します。
- 残業代の不適切な支払いがないかを確認する
- 適切な労働時間を把握する
- 弾力的労働時間制度を導入する
残業代の不適切な支払いがないかを確認する
まず、現時点で残業代だけ不適切な支払いを行っていないかを確認しましょう。支払いミスや未払いがないか、就業規則や給与計算の運用をあらためてチェックすることが重要です。
万が一、未払い残業代が発覚した場合は、早急に対処し、従業員に経緯を説明して誠実な対応を心がけます。
残業代の請求期間は法改正により5年(経過措置により当面は3年)に延長されています。5年内であれば、過去の未払い分も従業員から請求される可能性があるため、放置することのないようにしましょう。
適切な労働時間を把握する
残業代を適切に支払うには、従業員の労働時間を正確に把握することが重要です。残業を承認制にしたり、勤怠管理システムを活用したりして、効率的に時間を管理しましょう。
労働時間の管理を効率化するには、クラウド勤怠管理システムOne人事[勤怠]がおすすめです。企業独自の勤務ルールに合わせた柔軟な設定が可能で、自社に適した管理と運用が実現します。One人事[勤怠]で実現できることなど詳しくは、当サイトよりお気軽にお問い合わせください。
→人事領域で30年の実績「One人事」サービス資料はこちら
柔軟な労働時間制度を導入する
労働基準法に定められている「弾力的労働時間制度」の導入も、残業の不適切な支払い防止に役立ちます。主な制度には次のような働き方があります。
- 変形労働時間制
- フレックスタイム制
- 裁量労働制
制度を導入することで、法定労働時間を超えても、割増賃金の支払いが不要となる場合もあります。導入には就業規則の整備や労使協定の締結が必要であり、専門家の助言を受けながら進めるとよいでしょう。
参照:『フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き』厚生労働省
各労働時間制度の概要は以下の記事でもご確認いただけます。
残業代の後払いはルール化が必須(まとめ)
残業代の支払いは、賃金支払の「全額払いの原則」に沿って、給料日と同じ日に支払うのが基本です。就業規則などで定めた場合にのみ、基本給とは別に残業代だけ別に支払うことができます。
残業代の翌月払いは、就業規則等に運用ルールを明確にしていないと、違法になります。
残業代を適切に支払わず未払いが発生すると、従業員からの請求に基づいて、遅延損害金や付加金の発生が考えられるため、注意が必要です。
残業代の支払い時期を就業規則に明記し、未払い残業代が発生しない仕組みを整えましょう。
残業代の支払いをラクに|One人事[給与]
One人事[給与]は、給与計算をミスなくシンプルにできるクラウド型給与計算システムです。
勤怠管理システムOne人事[勤怠]と連携すると、勤怠データの取り込みがスムーズになり、給与計算の基礎となる残業時間の集計が自動化できます。
One人事[給与]の初期費用や気になる使い心地については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門スタッフが、貴社の課題をていねいにお聞きしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、給与計算をはじめ人事労務の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。給与計算をシンプルにして「本来やりたい業務」に集中したい企業は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |
