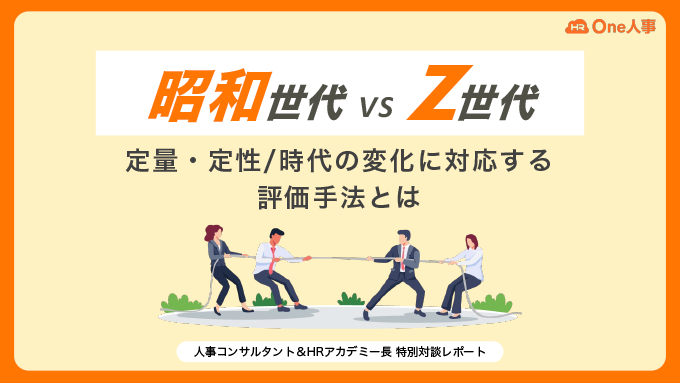飲み会の強制参加は残業扱い?法的なルールや残業代の計算方法などを解説
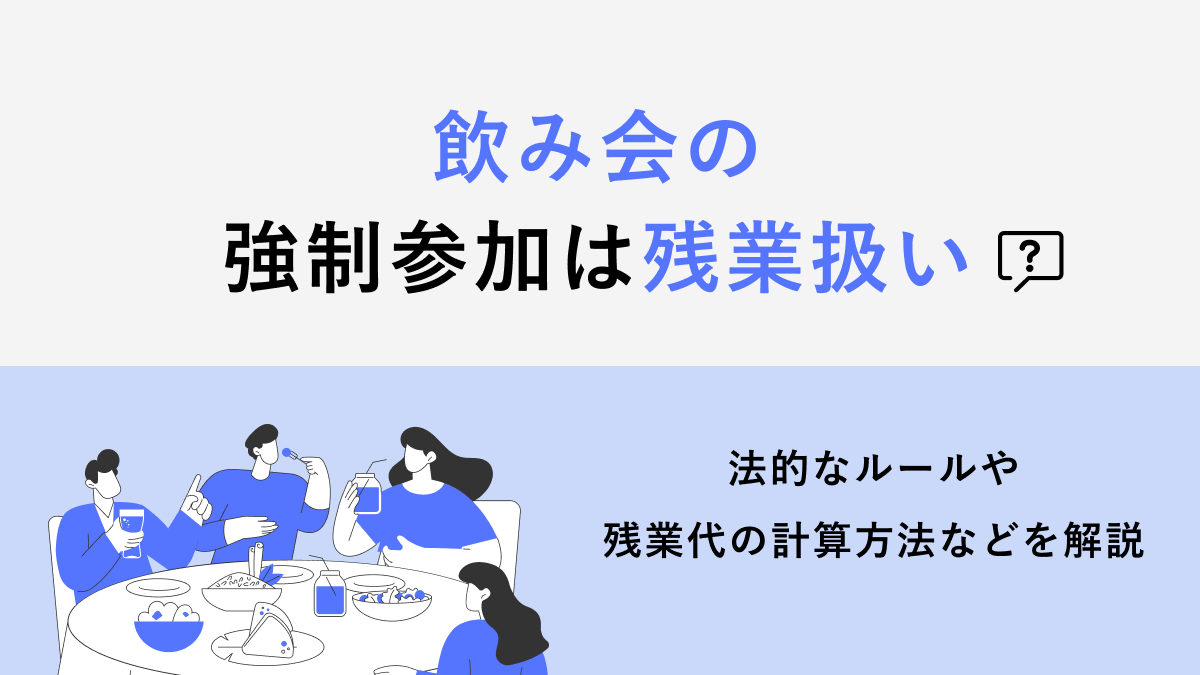
「全員参加の飲み会です」という上司の一言に、断れない空気を感じたことはありませんか。 給与計算担当者ならなおさら、飲み会が残業扱いになるのかと頭を悩ませることもあるでしょう。
業務命令としての飲み会は残業時間に含まれ、残業代の支払い義務が発生します。
本記事では、飲み会が残業になる条件や残業代の計算方法、トラブルを避けるための社内対応策について解説します。
 目次[表示]
目次[表示]
飲み会への強制参加は残業として扱うべき?
会社の飲み会が残業扱いになるか、判断のポイントは、その飲み会が「労働時間」に該当するかどうかです。
労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間のこと。
完全に任意参加の飲み会で、欠席しても評価や業務に影響がない場合は、労働時間つまり残業とはみなされません。
ただし、飲み会中に労働者は指揮命令下にあるのか、単なる親睦行事なのか、線引きは難しいものですよね。
給与担当者や人事担当者は、飲み会の位置づけを正しく理解し、社内での残業扱いを明確にしておく必要があります。
飲み会が残業扱いとなる条件
飲み会が残業として扱われるかどうかは、「労働者が使用者の指揮命令下にあるかどうか」という1点で判断されます。
就業時間外に開催される飲み会であっても、次のいずれかにあてはまる場合は、残業となる可能性があるでしょう。
- 「全員参加」と明示されている
- 不参加の場合に理由を述べる必要がある
- 欠席すると人事評価に影響する可能性がある
- 上司から参加するよう圧力がかかっている
- 業務報告や次期の目標設定など業務に関連する内容を含む
一方で、参加が完全に任意であり、不参加でも人事評価や業務に一切の影響がないと保証されている場合は、指揮命令下ではなく、飲み会は残業にはなりません。
最高裁判所の判例(平成12年3月9日判決)でも、「労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できるか否かにより客観的に定まる」としています。
条件を満たしているのに残業代を支給しないのは違法
飲み会が、労働時間と認められる条件を満たしているにもかかわらず、残業代を支払わない企業は、労働基準法違反です。
残業つまり、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える労働には、労働基準法第37条により、割増賃金の支払いが義務づけられています。
支払いを怠ると、労働者側から残業代が請求される可能性があり、未払い残業代として法的トラブルに発展するリスクも否定できません。
使用者には6か月以下の懲役または30万円以下の罰金といった罰則が科されます。違法となる例は以下のとおりです。
- 強制参加の飲み会を開催しながら、労働時間として扱わず残業代を支給しない場合
- 36協定を締結せずに時間外の飲み会への参加を強制する場合
給与計算や勤怠管理を担う立場であれば、法的リスクを理解し、誤った運用を防がなければなりません。
そもそも「残業」の定義とは?
残業とは一般的に、会社が定めた所定労働時間を超えて働くことを指します。ただし労働基準法の規定から考えると、残業は2つに分けて扱わなければなりません。
- 法定内残業
- 法定外残業
残業の種類によって、割増賃金の計算方法が異なるため、飲み会の残業扱いについて詳しく知るには、2つの区分を正確に理解しておく必要があります。
法定内残業
法定内残業とは、会社が定めた所定労働時間を超えてはいるものの、労働基準法で定める法定労働時間(1日8時間・週40時間)以内に収まっている残業です。別名で「法内残業」や「所定時間外労働」と呼ばれることもあります。
たとえば、所定労働時間が1日7時間の会社で、終業後に1時間の強制参加飲み会があった場合、1時間は法定内残業にあたります。
労働基準法上は、法定内残業に割増賃金を支払う義務はありません。ただし、就業規則や労働契約で割増支払いを定めている場合は、独自ルールにしたがう必要があります。
法定外残業
法定外残業とは、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて働くことを指します。
法定外残業には、労働基準法で定められた割増賃金の支払いが必須です。
たとえば、1日の所定労働時間が8時間の会社で、終業後に2時間の強制参加飲み会があった場合、2時間は法定外残業になります。
また、所定労働時間が7時間の場合でも、終業後に2時間の強制参加飲み会があれば、1時間は法定内残業、残りの1時間は法定外残業という扱いです。
法定外残業では、通常の賃金に25%以上の割増率を加えて支払う必要があります。
▼法定内残業と法定外残業の違いを整理するなら、以下の記事もご確認ください。

割増賃金の種類と割増率
飲み会が労働時間と認められる場合、飲み会時間は残業時間としてカウントされ、割増賃金の支払いが必要です。
支払いが滞ると未払いとなり、あとから労働者に残業代を請求されるケースも否定できません。
割増賃金とは、時間外労働や深夜労働、休日労働に対して、通常の賃金に一定の割合を上乗せして支払うものです。労働者を保護するため、労働基準法で義務づけられています。
| 種類 | 割増率 |
|---|---|
| 時間外手当 | 25%以上 |
| 深夜手当 | 25%以上 |
| 休日手当 | 35%以上 |
たとえば、強制飲み会が夜遅くまで続き、終了が22時を過ぎれば、深夜労働の割増率も適用されます。割増賃金の種類と割増率についてさらに詳しく確認していきましょう。
時間外手当
時間外手当は、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えて労働した場合に支払われる割増賃金です。
強制参加の飲み会が就業時間後に行われれば、時間外労働として時間外手当を支払う必要があります。
時間外労働の割増率は通常の賃金の25%以上です。 時給1,500円の場合、1時間あたり1,875円になります。
| 例 | 所定9時〜18時、終業後の強制飲み会が21時終了(3時間) → 3時間が時間外手当の対象 |
深夜手当
深夜手当は、午後10時から翌午前5時までの間に労働した場合に支払われます。強制参加の飲み会が、深夜時間帯まで延びれば、深夜手当の対象です。
深夜手当の割増率も通常賃金の25%以上です。さらに、時間外労働と深夜労働が重なる場合は、重複して合計50%以上の割増率になります。
| 例 | 所定9時〜18時、18時〜23時まで強制飲み会(5時間) →5時間のうち、18時〜22時の4時間は時間外手当の対象 →5時間のうち、22時〜23時の1時間は時間外手当+深夜手当の対象 |
休日手当
休日手当は、法定休日(週1日または4週4日)に労働した場合に支払われます。 休日に強制参加の飲み会やBBQ大会など社内イベントがあれば、その時間は休日労働となります。
休日手当の割増率は通常賃金の35%以上です。さらに強制イベントが、休日の深夜帯におよんだ場合は、深夜手当と合算され60%以上の割増率になります。
| 例 | 日曜日(法定休日)の21時から23時まで強制参加の飲み会(2時間) →2時間のうち、21時〜22時は、休日手当の対象 →2時間のうち、22時〜23時は、休日手当+深夜手当の対象 |
飲み会が残業にあたる場合の割増賃金の計算例
飲み会が残業として認められた場合、適切な割増賃金を計算して、支払う必要があります。具体的な計算方法を知ることで、給与計算担当者として正確な残業代を支給可能です。ここでは、飲み会が残業として扱われる場合の割増賃金の具体的な計算例を解説します。
飲み会が残業として認められた場合、飲み会参加時間も労働時間に含めて割増賃金を計算します。基本の計算式は次のとおりです。
| 残業代 =1時間あたりの基礎賃金 × 割増率 × 残業時間数 |
1時間あたりの基礎賃金(時給)は、月給制の場合、次のように計算します。
| 1時間あたりの基礎賃金 =1か月の総支給額 ÷ 月平均所定労働時間 |
総支給額には、家族手当や通勤手当などは含まれない点に注意しましょう(労働基準法施行規則第21条)。
月平均所定労働時間の計算は、次のとおりです。
| 月平均所定労働時間 =週所定労働時間 × 52週 ÷ 12か月 |
月給28万円、週の所定労働時間40時間の従業員が、終業時刻18時から21時終了の飲み会に強制参加した場合、次のように計算できます。
| 月平均所定労働時間=40 × 52 ÷ 12 ≒ 173.33時間 1時間あたりの基礎賃金 =28万円 ÷ 173.33時間 ≒ 1,616円残業代=1,616円 × 1.25 × 3時間 ≒ 6,060円 |
▼割増賃金のさまざまな計算パターンを見てみたいなら、次の記事もご確認ください。
飲み会にまつわるトラブルを防ぐための注意点
ビジネスでは「飲みニケーション」という言葉があるように、仕事関係者との飲み会は、社内の親睦や情報共有の場として重視されてきました。
しかし今は、価値観の多様化や働き方改革の影響で、位置づけが大きく変わっています。
飲み会が残業として扱われるリスクだけでなく、ハラスメントや世代間ギャップによるトラブルなどの問題を引き起こしかねません。
ここでは、会社の飲み会にまつわるトラブルを防ぐための注意点について、解説します。
飲み会への参加強要はハラスメントにあたる可能性がある
飲み会への参加を事実上強制することは、パワーハラスメント(パワハラ)に該当する可能性があります。
労働施策総合推進法(パワハラ防止法)では、以下の3つを満たす行為をパワハラと定義しています。
- 職場で優越的な関係を背景にした言動
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えている
- 労働者の就業環境を害する
上司など「優越的」な地位にある者が、業務と直接関係のない飲み会への参加を強制すると2の「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」と判断されるリスクがあるのです。
パワハラに該当する状況の例は、次のとおりです。
- 「飲み会を断ると評価に響く」とほのめかす
- 飲み会中に、あからさまに帰れない雰囲気をつくる
- 飲み会を何度も断っているのに何度も誘う
就業時間内の歓迎会・懇親会などにも賃金は発生する
歓送迎会のような飲み会を、所定の時間内に実施するのであれば、残業にはなりません。ただし、当然ながら、通常勤務と同様に賃金が発生します。
就業時間内に飲み会を行うのは、次のようなメリットがあります。
- 残業代の問題が生じにくい(法定労働時間内であれば割増賃金は不要)
- 参加を促しやすい
- 帰宅時間が遅くならず、プライベートの時間を確保できる
- 飲酒量が抑えられ、トラブルのリスクが低減する
ただし、ランチタイムに実施する場合は、休憩時間の自由利用の原則(労働基準法第34条第3項)に反するおそれがあるため注意が必要です。
また、就業時間内であっても、参加の強制については慎重に検討しなければなりません。アルコールが苦手な社員や健康上の理由で飲酒できない社員も配慮しましょう。
従業員に時代にあわせた意識改革を促す
近年は、若手を中心に飲み会離れが進む一方、飲み会を当然と考える世代もいますよね。世代間ギャップが原因で、意見が衝突したり、雰囲気が悪化したりすることも少なくありません。
トラブルを避けるには、従業員に対して時代にあわせた意識改革を促すことも重要です。
- 飲み会は任意参加であることを明文化する
- 参加・不参加が人事評価に影響しないことを保証する
- 法的知識を交えた研修をする
- 飲み会以外の交流手段(ランチ会、スポーツイベントなど)を用意する
- 多様な価値観を尊重する企業文化を醸成する
自主性・自発性を重んじられ、褒められて育った最近の若者たちにとって、自分の意志を尊重してもらえることは重要です。「参加しなくてもOK」という姿勢を明確にし、無理に誘うことは避けることをおすすめします。
▼Z世代の価値観やZ世代を評価する際のポイントを知るには、以下の資料もご確認ください。
▼1on1ミーティングの場が、よいコミュニケーションの場になっているでしょうか。1on1ミーティングが形骸化している場合は、以下の資料もご活用ください。
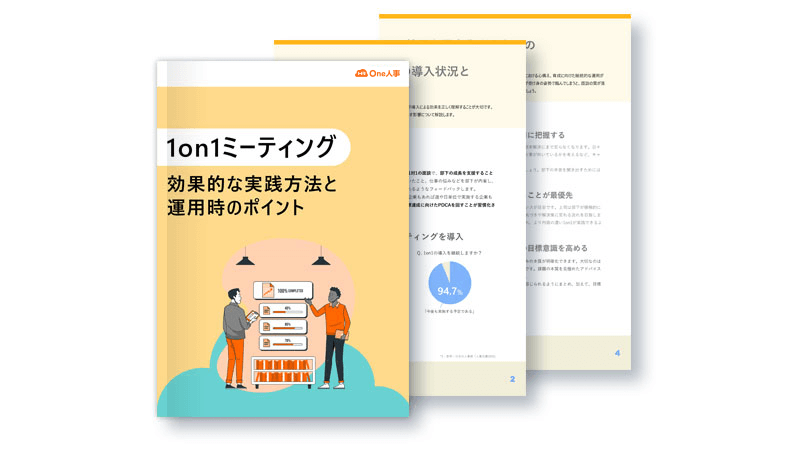
まとめ
就業時間外に開催される強制参加の飲み会は、労働基準法上の「労働時間」として扱われ、割増賃金の支払いが必要です。
任意参加であれば、残業にはなりませんが、参加の強要はパワハラにあたる可能性もあり、注意しなければなりません。
企業は、参加が自由であることを明示するか、業務として行う場合は適切に賃金を支払うなど、ルールを明確にしましょう。
飲み会以外のコミュニケーションの場を充実させることで、時代にあわせた職場文化を構築していく視点も必要です。
適切な残業管理に|One人事[勤怠]
One人事[勤怠]は、残業時間の管理効率化にお役立ていただけるクラウド型の勤怠管理システムです。
One人事[給与]との連携により、実労働時間の集計から割増賃金の計算までをシームレスに運用できます。
One人事[勤怠]の初期費用や操作性については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門のスタッフが貴社の課題をていねいにお聞きしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、勤怠管理の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードしていただけます。勤怠管理をラクにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |