長時間労働の基準とは【5つの目安】違反による罰則や働き方改革の影響も
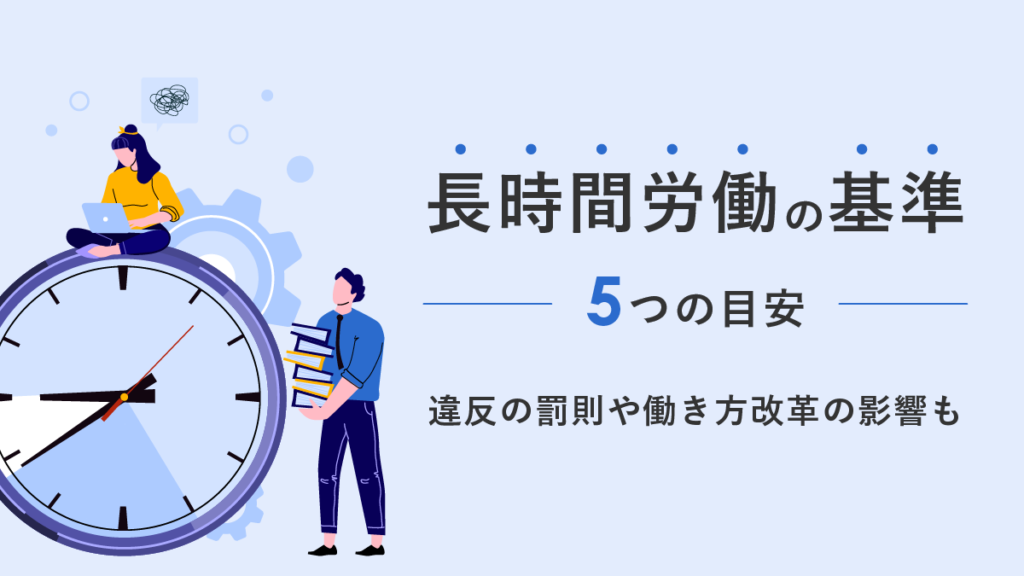
働き方改革や過労死問題が注目されるなか、「長時間労働」への対応に頭を悩ませている企業も多いでしょう。
しかし、長時間労働の基準は、法的に明確な定義はないため、人によってさまざまな認識があります。実務の現場では「何時間働くと違法なのか」「長時間労働をどのように改善すればいいのか」と、疑問に思われるケースも少なくありません。
本記事では、長時間労働の基準を示す【5つの目安】をわかりやすく解説し、違反時の罰則や企業が取り組むべき対応策、働き方改革による影響も紹介します。記事を読むことで、長時間労働のリスクを正しく理解し、自社の労務管理を見直すヒントが得られるでしょう。
労働時間管理の基本をおさらいするには、以下の資料もぜひご確認ください。

 目次[表示]
目次[表示]
長時間労働とは? 目安となる基準・定義を解説
法律では「何時間働いたら長時間労働になるか」という明確な基準や定義は存在しません。しかし目安となる基準が5つあります。
| 基準1.法定労働時間 | 1日8時間以内、1週間に40時間以内 |
| 基準2.36協定の上限 | 月45時間以内、年360時間以内 |
| 基準3.36協定の特別条項の上限 | 年720時間以内 など(詳細下記) |
| 基準4.過労死ライン | 月100時間以上の時間外労働、 または2~6か月平均で80時間以上の時間外労働 |
| 基準5.精神疾患の労災認定 | 疾患の発症直前の1か月に160時間以上 など(詳細下記) |
5つの基準を理解することで、長時間労働のリスクを把握し、法令遵守の対応策を検討できます。それぞれの基準を確認し、自社の労務管理に役立てていきましょう。
基準1.法定労働時間
労働基準法第32条では「1日8時間以内・1週間に40時間以内」と労働時間の基準が定められ、法定労働時間と呼ばれています。
法定労働時間は、長時間労働を判断するうえでの基本的な基準です。
法定労働時間を超えて従業員を働かせる行為は、特別な手続きをしない限り、原則として違法とみなされます。
長時間労働を防ぐためには、まずはこの法定労働時間の考え方を理解し、管理体制を整える必要があります。
参照:『労働時間・休日』厚生労働省
参照:『労働基準法』e-Gov法令検索
基準2.36協定の上限
本来であれば、法定労働時間を超えて労働させることは違法です。しかし、繁忙期がある企業では、どうしても時間内に収めるのが難しいケースもあるでしょう。
労働基準法第36条に基づいて時間外労働を認める36協定を結ぶことで、時間を延長できます。36協定の締結により、法定労働時間を超えて「月45時間以内・年360時間以内」の範囲内で時間外労働を設定することが可能です。
つまり「月45時間以内・年360時間以内」が、長時間労働と判断される2つめ基準といえます。大企業では2019年4月、中小企業では2020年4月から特別な事情がない限り、基準を超えられないこととされています。
参照:『時間外労働の上限規制 わかりやすい解説』厚生労働省
参照:『労働基準法』e-Gov法令検索
36協定についてより深く知るには、以下の記事もご確認ください。
基準3.36協定の特別条項の上限
長時間労働と判断される3つめの基準は、36協定の特別条項です。
繁忙期や突発的な業務が発生した場合、通常の36協定(月45時間・年360時間)では収められないときもあります。特別な事情に対応するために設けられた基準が、特別条項付き36協定です。
36協定の特別条項で定める時間外労働の上限は、次の4つです。
- 年720時間以内(法定休日労働を除く)
- 月100時間未満(法定休日労働を含む)
- 2~6か月の平均が80時間以内(法定休日労働を含む)
- 月45時間を超えられるのは年6回まで
参照:『時間外労働の上限規制 わかりやすい解説』厚生労働省
参照:『労働基準法』e-Gov法令検索
2019年に改正法が施行されるまでは、特別条項付きの36協定さえ締結していれば実質何時間でも長時間労働をさせることが可能でした。長時間労働の温床となる原因を解消するため、特別条項における残業時間にも上限が設けられたのです。
特別条項付きの36協定を利用している場合は、労働時間が上限を超えていないか定期的に確認しましょう。可能であれば繁忙期を見越した人員計画や業務改善を進め、特別条項に頼らない運用を目指すほうが、従業員にとって負担が少なくなります。
36協定の特別条項についてより深く知るには、以下の記事もご確認ください。
基準4.過労死ライン
長時間労働が健康被害を引き起こすかどうかを判断する重要な基準が「過労死ライン」です。
過労死ラインは、月100時間を超える時間外労働、または2~6か月平均で80時間を超える時間外労働を指します。基準を超えると、業務による健康被害のリスクが非常に高いと考えられています。
そもそも過労死とは、仕事での身体的・精神的負担による脳や心臓の疾患、精神障害が原因となって死亡することです。
たとえば、月の時間外労働が100時間を超えると、睡眠不足やストレスにより、脳や心臓の疾患を引き起こす可能性が急激に高まります。
厚生労働省は、長時間労働の削減に向けて、事業主に対し労働時間が週60時間以上の労働者をなくす努力をするよう呼びかけています。
過労死ラインについてより深く知るには、以下の記事もご確認ください。
基準5.精神疾患の労災認定
精神疾患の労災認定基準は、長時間労働が引き起こす深刻さをあらわす重要な基準です。
厚生労働省によって定められており、月160時間以上といった非常に長い時間外労働が行われていたかどうかで適用されます。
具体的には、以下のような過酷な労働状況が続いた場合です。
- 発症直前の1か月に160時間以上の時間外労働を行った
- 発症直前の3週間に120時間以上の時間外労働を行った
- 発症前の2か月間で、連続して月120時間以上の時間外労働を行った
- 発症前の3か月間で、連続して月100時間以上の時間外労働を行った
参照:『精神障害の労災認定』厚生労働省
参照:『stop!過労死』厚生労働省
基準1として紹介した法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える月の時間外労働が160時間を超えた場合、ひと月あたりの総労働時間は328〜336時間程度と計算され、平均しておよそ333時間となります。
つまり、ひと月あたりの総労働時間が333時間分を超えてしまうと精神疾患の発症リスクが高まるとされ、長時間労働を判断する一つの基準となっています。
基準を見て、これほどの労働時間が日常的に発生する状況がいかに厳しいか、想像できるのではないでしょうか。たとえば、月160時間の時間外労働は、通常勤務に加えて1日5~6時間の残業が毎日続く計算になります。
無理な働き方が続くと、心身の健康を損ない、回復が難しくなるケースも少なくありません。水準に達している場合、職場環境を改善する緊急性が高いといえるでしょう。
長時間労働と過重労働の違い
長時間労働の基準が整理できたところで、過重労働とは何が違うのかと思う方もいるのではないでしょうか。どちらも働きすぎをあらわす言葉として使われますが、じつは少し意味が異なります。
| 長時間労働 | 法定労働時間を大きく超えて働いている状態 |
| 過重労働 | 長時間働くことなどを理由に心身の負荷が大きく、 健康被害につながりかねない状態 |
厚生労働省は、過重労働を「時間外・休日労働が100時間を超えること、もしくは2〜6か月平均で80時間を超えること」と定義していますが、一般的に過重労働とは長く働いていることだけを意味するものではありません。
身体的・精神的負荷がかかっているという意味合いも含まれるのが特徴です。過重労働により、脳や心臓疾患、精神障害を発症するリスクが高まります。
一方の長時間労働については、何時間以上が長時間労働といった明確な基準はありません。
しかし、実働時間が法定労働時間を大幅に上回っているようであれば、長時間労働の状態にあるといえるでしょう。
過重労働により、脳や心臓疾患、精神障害などを発症するリスクが高まります。
たとえば、長時間労働の状態であっても、業務に無理がなく、適切な休憩やサポートがあれば負荷が減り健康的に過ごせる人もいます。しかし、業務量が明らかに多く十分な休息が取れないと、過重労働とみなされます。負担が大きいと、従業員が心身ともに限界を迎える危険性があるのです。
参照:『過重労働とは?業務方法を見直し、労働時間の削減につなげる 「働き方改革」に取り組むこと』厚生労働省
長時間労働の基準を超えると労働基準法違反?
本記事で紹介した長時間労働の基準1〜5を超えると、法的なリスクが高まります。
まず36協定を締結していない状況で時間外労働をさせたり、締結していても協定で定めた上限(基準2・基準3)を超えて働かせたりすると、労働基準法違反となります。具体的には「6か月以下の懲役または30万円以下の罰金」が科されるおそれがあるため労働時間の管理徹底が必要です。
また、基準4として紹介した過労死ラインを超えて働かせることは、労働契約法や労働安全衛生法における安全配慮義務違反に該当します。
具体的な罰則は規定されていませんが、訴訟問題に発展した場合は損害賠償を請求されてしまうかもしれません。
実際に、過重労働が原因で従業員が健康を害した事例では、企業に多額の賠償命令が下ったケースもあります。
企業の責任を重く受け止め、勤怠管理を行うことが重要です。
参照:『労働基準法』e-Gov法令検索
参照:『労働契約法』e-Gov法令検索
参照:『労働安全衛生法』e-Gov法令検索
労働基準法の違反事例をさらに知るには、以下の記事もご確認ください。
長時間労働の改善に向けた制度
長時間労働の改善は、従業員の健康を守るだけでなく、企業の生産性向上にも直結します。
課題に対応するため、2019年から改正労働基準法が段階的に施行され、厳格な基準が設けられました。
改正法の施行を受け、多くの企業が制度導入や働き方の見直しを進めていますが「どこから着手すればよいかわからない」と悩む担当者もいるのではないでしょうか。
ここでは、企業が長時間労働の改善に向けて取り組む際におさえておきたい、代表的な3つの制度を紹介します。
月60時間超の時間外労働に対する割増率
2023年4月から、中小企業を含む全企業において、月60時間を超える時間外労働に対する賃金の割増率が50%に引き上げられました。
大企業では2010年4月からすでに適用されていた制度ですが、中小企業は労働現場の実情を踏まえて適用が猶予されていました。改正をきっかけに企業規模を問わず、長時間労働の削減しようとする意識が高まっています。
参照:『2.法定割増賃金率の引上げ』厚生労働省
参照:『月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます』厚生労働省
中小企業の方で残業代規定について詳しく知りたい場合は以下の記事もご確認ください。
勤務間インターバル制度
勤務間インターバル制度とは、1日の勤務終了から翌日の出社時間までの間に一定の休息期間を設ける制度です。従業員の睡眠時間やプライベートの時間を確保する目的があります。
2019年4月以降、企業には制度を導入する努力義務が課されました。たとえば、夜勤がある医療業界では、翌日の勤務開始時間を遅らせることで休息時間を確保している事例があります。
参照:『勤務間インターバル制度をご活用ください』厚生労働省
参考:『医師の勤務間インターバルと代償休息について』厚生労働省
勤務間インターバル制度をより詳しく知るには以下の記事もご確認ください。
産業医・産業保健機能の強化
2019年4月から働き方改革関連法により、産業医・産業保健機能が強化されました。企業には従業員の健康リスクを把握し、適切に対応する役割が求められています。
とくに、長時間労働によるメンタルヘルス不調が懸念される労働者へ、面接指導や健康相談の実施が重要視されています。
企業は産業医と連携し、従業員に対してよりきめ細やかなサポートをするよう努めていきましょう。ストレスチェックの実施と並行して、問題が大きくなる前に早期対応が大切です。
参照:『「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化されます』厚生労働省
産業医制度について詳しく知るには以下の記事もご確認ください。
働き方改革で長時間労働は是正された?
2019年から段階的に施行された改正労働基準法により、長時間労働の是正が進み、全体的な労働時間は年々減少傾向にあります。
しかし「長時間労働が解消された」と言い切るのは難しいのが現状です。
たとえば、パートやアルバイトなどパートタイム労働者の増加により、全労働人口の総労働時間は減少しています。一方で、正社員など一般労働者の労働時間には大きな変化が見られず、依然として長時間労働が常態化している業界もあります。
とくに運送業や建築業では、時間外労働が慢性的に多く、2024年4月から時間外労働の上限規制が適用されているため、人手不足の解消が急務となっています。
管理職や裁量労働制で働く従業員に業務が集中している現状も見逃せません。労働時間が長くなることで、心身への負担が増し、健康リスクの増加や生産性の低下につながるおそれがあります。
また、管理職や裁量労働制で働く従業員に業務が集中していることも、問題点として指摘されています。近年はテレワークの普及にともない、隠れ残業の発生や労働時間が把握しにくくなっていることも新たな課題となっています。
企業は働き方改革を形式化させず、従業員一人ひとりの労働時間を正確に把握する仕組みを整備する必要があります。たとえば、勤怠管理システムを活用した客観的な労働時間の管理や、チーム全体で業務を分担できる体制づくりが必要です。
従業員の健康と生産性を両立させるために、企業全体で取り組みを続けていきましょう。
長時間労働を放置するデメリット
長時間労働を放置することは、企業にも従業員にも以下のデメリットをもたらします。
| 企業側のデメリット | 従業員側のデメリット |
|---|---|
| ・生産性が低下する ・離職率が上昇する ・社会的な信用が低下する ・人件費が増える ・利益が減少する | ・生産性が低下する ・心身の健康リスクが高まる |
それぞれの立場から考え、課題を具体的に確認していきましょう。
企業側のデメリット
長時間労働が基準を超えて慢性化すると、従業員の疲労が蓄積し、仕事への集中力やモチベーションが著しく低下するでしょう。結果として生産性が下がり、企業の業績に直接的に影響します。
従業員が働きすぎる環境に不満を感じ、よりよい条件を求めて離職する状況も考えられます。
離職者が増えれば、採用コストや新人の育成コストがかさみ、在籍する従業員にはさらなる負担がかかるでしょう。悪循環が続けば、企業全体の労働環境が悪化し、組織の成長が停滞する原因となってしまいます。
また、長時間労働が原因で労働災害や健康問題が発生した場合、社会的な信用を失うリスクもあります。取引先や顧客からの信頼が損なわれるだけでなく、法的責任を問われる事態に発展しかねません。
慢性的な残業により人件費が増加し、利益が圧迫される点も大きな課題です。
従業員側のデメリット
長時間労働の基準超えを放置すると、集中力が切れやすくなります。睡眠不足や疲労が蓄積することで業務効率も下がり、生産性が著しく低下してしまうでしょう。
また、適切な休養が取れないと、心身の不調を招くおそれもあります。
なぜ日本の長時間労働は減らない?
さまざまな取り組みが進められているにもかかわらず、日本ではなかなか長時間労働がなくなりません。「働き方改革」という言葉は聞き慣れていても、実際の現場では改善が進んでいないと感じる方も多いのではないでしょうか。
長時間労働が減らないのは、以下の原因が挙げられます。
- 業務量が多い
- 慢性的に人員が不足している
- 長時間労働を評価する企業文化がある
- 管理職のマネジメント力が不足している
業務が多すぎたり、人手不足が続いたりする環境では、勤務時間内に仕事を終わらせるのが難しく、長時間労働が常態化してしまいます。結果として、長時間労働が「当たり前」とされる風潮が生まれます。
「残業している人が頑張っている」と評価する風潮があると、効率的な働き方が軽視され、長時間労働が正当化される悪循環が生まれてしまいかねません。
また、管理職のマネジメント力の不足も、長時間労働がなくならない原因の一つです。管理職が業務量を適切に調整できていないと、業務の偏りや無駄が放置され、従業員の負担が増加し、長時間労働を助長する要因となっているのです。
長時間労働をなくすには、形式的な対策ではなく、実効性のある取り組みが求められます。勤怠管理システムの導入や業務の分担体制の構築、タスクの効率化など、企業全体で労働環境を見直すことが必要です。
長時間労働の改善に向けた社内の取り組み
長時間労働を改善するためには、企業全体で取り組みを進めることが不可欠です。以下のような社内での取り組みが、長時間労働の解消に効果的とされています。
| 働き方や業務配分の見直し | 従業員に過度な負担がかからない体制を整える |
| 有給休暇の取得推進 | 有給休暇取得率の向上は、従業員の健康維持や モチベーション向上にもつながる |
| 面談や専門家への相談ができる体制を整備 | 従業員が抱える業務の負担やストレスを 把握するために、定期的な面談を実施する |
| 勤怠管理システムの活用 | 残業アラート機能で長時間労働を抑制する |
長時間労働を未然に防ぐために、まずは自社の現状を把握することから始めましょう。
従業員の労働時間や業務量を可視化する取り組みが重要です。とくに勤怠管理システムには、従業員が一定時間勤務し続けているとアラートを出す機能があるため、長時間労働の防止につながります。
シンプルな操作性や導入済みのシステムと連携できる勤怠管理システムを選ぶことで、スムーズに導入が進むでしょう。
長時間労働の基準を超えないために(まとめ)
長時間労働には明確な定義がないものの、労働基準法や厚生労働省のガイドラインを基準とし、企業には従業員の労働時間を適切に管理する責任があります。長時間労働の基準を理解し、法令を遵守することは、企業と従業員の双方を守るうえで重要です。
長時間労働が慢性化すれば、従業員の健康リスクや生産性の低下を招きます。リスクを防ぐためには、労働時間の実態を可視化したうえで、働き方や業務配分を見直す必要があります。
小さな改善からでも着手し、長時間労働を防止する仕組みを構築していきましょう。
適切な労働時間の管理に|One人事[勤怠]
One人事[勤怠]は、煩雑な労働時間の管理をシンプルにする勤怠管理システムです。
- 打刻漏れ・集計ミスが多い
- 勤怠管理がアナログで煩雑になっている
- 法改正への対応に不安がある
労働時間の管理に課題を感じている企業をご支援しております。
One人事[給与]と連携すれば、給与計算に自動で紐づけられるため、より速くより正確に業務を進められるでしょう。また、有休の付与・失効アラート機能や、労働基準法などの改正にも対応しております。
One人事[勤怠]の初期費用や気になる操作性については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門のスタッフが貴社の課題をていねいにヒアリングしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、勤怠管理の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。勤怠管理をラクにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |
