有給休暇の時間単位付与はどんな制度? 時間休の導入方法や労使協定の例、休憩と繰越の扱いも解説
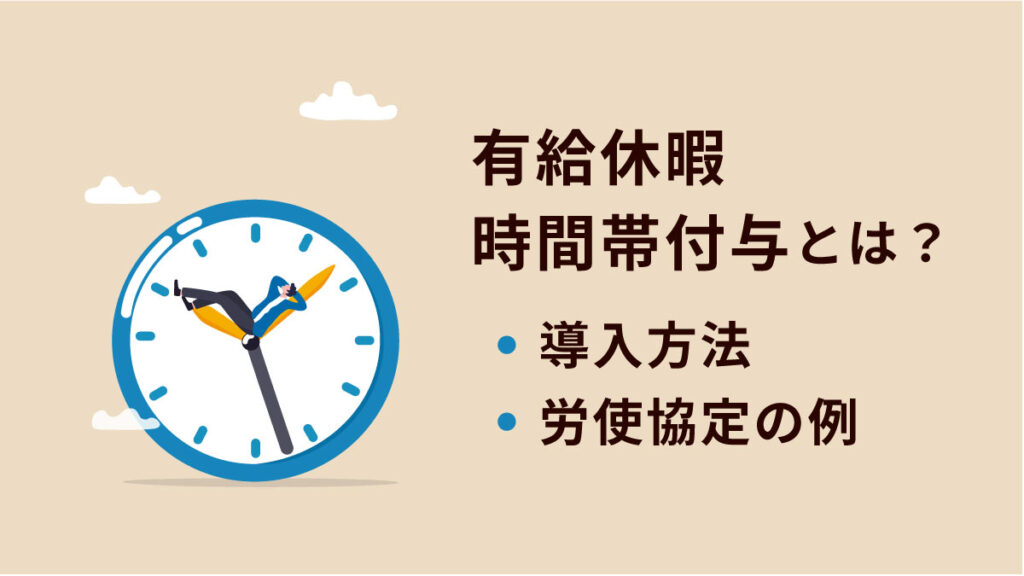
「有給休暇の時間単位付与」は、数時間単位で休暇が取れる柔軟な働き方を支援する制度です。導入により従業員のワークライフバランスの向上が期待できます。
本記事では、有給休暇の時間単位付与について、導入方法や労使協定の例、休憩と繰越の扱いなどをご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
▼有休管理のコツを確認したい方は、以下の資料もぜひご活用ください。

 目次[表示]
目次[表示]
有給休暇の時間単位付与とは
「有給休暇の時間単位付与」という制度は、従業員が1日単位ではなく、数時間単位で有給休暇を取得できるようにするものです。日本での有給休暇の取得率が低い状況を踏まえ、2010年の労働基準法の改正によって設けられました。
時間単位の有給休暇は、労働基準法第三十九条(年次有給休暇)によって定められています。ただし企業が導入する場合は、労働協定の締結や就業規則への記載が必要です。
参照:『年次有給休暇の時間単位付与』 改正労働基準法
参照:『労働基準法』e-GOV 法令検索
制度の目的
労働基準法第39条の趣旨は、働く従業員の疲労を回復させ、労働力の維持・向上をはかり、ゆとりのある生活を実現することです。これを踏まえて、有給休暇の時間単位付与制度の目的は、年次有給休暇を有効に活用することとされています。
ただし、時間単位で付与できる上限時間は、1年間に5日分までです。従業員の心身の回復が有給休暇の本来の目的であるためです。付与日数のすべてを時間単位で消化することはできないため、注意しましょう。

有給休暇の時間単位付与の仕組み
有給休暇の時間単位付与の仕組みを5つの観点から解説します。
1年に5日分取得できる
労使協定を締結すれば、1年に5日を限度として、年次有給休暇が時間単位で取得できます。5日を超える場合は、1日や半日単位での有給休暇を利用する必要があります。
30分ずつは取れない
時間単位での有休は、1時間単位での取得です。30分や10分、15分というように、時間未満の分単位で取得するのは認められません。
年5日の取得義務には含まれない
2019年からの働き方改革関連法施行により、企業は年5日の有給休暇を従業員に取得させることが義務づけられています。
しかし、時間単位で取得した休暇は、この年5日の有給休暇には含まれません。そのため、通常の有給休暇と時間単位での有給休暇は別々に管理することが重要です。
企業は時季変更権を行使できる
時間単位での有休も年次有給休暇のため、事業の正常な運営を妨げる可能性がある場合は使用者による「時季変更権」が認められます。
ただし、日単位での請求を時間単位に変えたり、時間単位での請求を日単位に変えたりすることはできません。
計画年休では付与できない
有休の年間付与日数のうち5日を除いた部分は、労使協定を結ぶことで企業側が計画的に時季を決めて有給休暇を付与できます。
しかし、時間単位での有休は従業員から請求されて付与するものという認識のため、このような計画年休での付与は認められていません。

有給休暇の時間単位付与における労働時間の数え方
有給休暇の時間単位付与における労働時間は、何時間を有休1日分とするかを労使協定で決めてから数える必要があります。
1日の年次有給休暇に相当する具体的な時間数は、下記のとおりです。
- 所定労働時間が5時間以上6時間以下:6時間
- 所定労働時間が6時間以上7時間以下:7時間
- 所定労働時間が7時間以上8時間以下:8時間
参照:『時間単位の年次有給休暇制度を導入しましょう!』 厚生労働省
所定労働時間が日で異なる場合は?
業務によっては、日ごとに所定労働時間数が異なることもあるでしょう。その場合、1年間の1日平均所定労働時間を基準とします。
また、従業員によって所定労働時間が異なるケースでは、労働時間ごとにグループに分け、それを基準としても問題ありません。
所定労働時間が変更になったら?
年の途中で所定労働時間が変更になったら、残っているのが「日単位」なのか「時間単位」なのかで対応が異なるので確認しておきましょう。
日単位で残っている部分は、変更後の所定労働時間によって1日が何時間に該当するかが決まります。日単位に満たず時間単位で保有している部分は、所定労働時間の変動にあわせて時間数が決まります。
有給休暇の時間単位付与における賃金の計算方法
時間単位有休1時間分の賃金額は、下記の3つの中でいずれかを、その日の所定労働時間数で割った額です。
- 平均賃金
- 所定労働時間働いた場合に支払われる通常の賃金
- 標準報酬日額(労使協定が必要)
どの計算方法を最小するかは、日単位での取得と同様にし、就業規則に定める必要があります。
有給休暇の時間単位付与を導入するメリット
企業が「有給休暇の時間単位付与制度」を取り入れることで、得られる3つのメリットについて解説します。
有休の取得率が向上する
有休の取得率が向上することがメリットの一つです。
従来、有給休暇は1日単位で付与されており、1日単位で有休を取得するのが難しい場合、有休を消化できずに余ってしまうことが少なくありませんでした。また、有休消化に罪悪感があったり、休みづらい空気を感じたりする従業員もいるでしょう。
しかし、時間単位付与を導入することで、1時間単位でも有休が取得でき、抵抗感なく少しずつでも有休を取得しやすくなります。
企業イメージが向上する
企業が有休の時間単位付与制度を取り入れることで、社外的に「従業員のワークライフバランスを重視している前進的な企業」と見なされます。そのため、イメージの向上につながるでしょう。
柔軟な働き方を好む人たちにも魅力的と感じてもらえ、将来的な人手不足の解消にも期待できます。
従業員のワークライフバランスを維持できる
時間単位付与の制度を導入すると、従業員は有休を取得しやすくなり、ワークライフバランスを保ちやすくなります。
たとえば、公的機関での手続きや通院など数時間だけの用事や、仕事がたまっているので1日の休みは取れないという場合に便利です。
有給休暇の時間単位付与を導入するデメリット
有給休暇の時間単位付与を導入するとメリットがある一方、デメリットもあります。主な3つのデメリットを紹介します。
管理が煩雑になる
時間単位の有休が加わり、管理が煩雑になることがデメリットの一つです。とくに、勤務時間が従業員によってバラバラな場合は煩雑さが増すため、慎重に対応する必要があります。管理を効率化することが重要です。
本来の趣旨から逸れる
制度の導入によって、時間単位で有休が取りやすくなる一方、1日単位での有休が取りにくくなるかもしれません。休暇をまとめて取得し、休養してもらうという有給休暇本来の趣旨から逸れる可能性があるため、注意が必要です。
時季変更権を行使しにくい
「時季変更権」を行使しにくくなることもデメリットといえます。時間単位での有給休暇取得は事業への影響が少ないためです。企業側は配慮が必要でしょう。
有給休暇の時間単位付与の導入手順・労使協定の定め方
時間単位での有休を導入するには、労使協定の締結と就業規則の変更が必要です。有給休暇の時間単位付与の導入手順と、労使協定の定め方について紹介します。
就業規則の変更
まずは就業規則の変更を行います。就業規則に時間単位の有休を導入する旨や取得の条件などを記載します。
就業規則への記載項目と例
記載が必要となる事項はとくに決まっていませんが、下記のような事項を取り入れるとよいでしょう。
- 時間単位の有給休暇が使える旨とその日数
- 対象となる従業員
- 時間単位の有給休暇取得で1日の年次有給休暇に相当する時間数(例:所定労働時間が6時間を超え7時間の人は7時間)
- 時間単位付与の最低単位(例:1時間単位から付与)
- 時間単位で有給休暇を取得した場合の賃金
労使協定の締結
労働者の過半数で組織している労働組合、または労働者の過半数を代表する人と労使協定を締結します。書面が必要ですが、労働基準監督署へ届出は不要です。
労使協定への記載項目と例
労使協定への記載項目は下記のとおりです。
- 対象となる従業員の範囲
(例:事業の正常な運営が妨げられる場合、工場のラインで働く従業員を対象外としても可) - 時間単位での有給休暇の日数
- 時間単位での有給休暇1日の時間数
- 1時間以外の時間を単位とする際はその時間数
有給休暇の時間単位付与にまつわる疑問
有給休暇の時間単位付与について、よくある疑問とその回答を紹介します。
休憩時間をまたぐ場合どうなる?
有給休暇は、労働義務のない休憩時間に取得することはできません。そのため、休憩時間をまたぐ申請があった際は、休憩時間分を除いた時間単位年休とする必要があります。
時間単位年休は繰越できる? 端数は処理の方法は?
時間単位年休は有給休暇の繰越の対象ですが、次年度分の時間単位年休の日数は、繰越分を含めて5日以内です。
たとえば、所定労働時間が8時間の場合、通常の有休を3日分、時間単位年休を4時間分、次年度に繰り越すケースでは、次年度付与日数が12日とすると最終的に付与される有休は15日と4時間です。
この中で時間単位年休として取得できるのは、5日分(40時間)分までです。繰り越した4時間分を加算した44時間分を取得できるわけではないことに注意しましょう。
時間単位年休を使って中抜けできる?
時間単位年休は、取得する時間帯を制限できません。 そのため、所定労働時間の途中に時間単位年休を取得する、いわゆる「中抜け」として取得することも可能です。
半休と併用できる?
時間単位年休と半日単位年休(半休)の制度は、併用できます。
また、労働基準法に定められている時間単位年休と、法律上の定めがない半日単位年休は扱いが異なります。法改正による時間単位年休を導入した場合も、半日単位年休には影響がありません。
時短のパート・アルバイトも利用できる?
改正労基法では、時間単位の年休制度を導入する場合の対象となる従業員の範囲は、労使協定の締結事項とされています。
そのため、パート・アルバイトなど、すべての従業員が制度の適用対象とはならず、利用できるかどうかは企業によって異なります。
1日に何回取れる取れる?
1日に取得できる時間単位年休の回数に制限はありません。 「1日において取得することができる時間単位年休の時間数を制限すること等は認められない」と定められているためです。
フレックスタイム制ではいつ時間単位年休を取れる?
労働時間の範囲内で始業、終業時刻を自由に決められる制度が「フレックスタイム制」です。
フレックスタイム制には、必ず働かなければならない「コアタイム」と、自分で労働時間を設定できる「フレキシブルタイム」があります。
フレキシブルタイムは従業員に委ねられている時間のため、時間単位年休はコアタイムのみ取得可能なのが一般的です。
早退や遅刻と振り替えできる?
従業員の遅刻や早退を時間単位年休で振り替えできるかは企業によって対応が異なります。
事故や災害などの特別な理由に限って、振替を認める場合もありますが、企業が勝手に振り替えることはできません。時間単位年休を含め、有給休暇の取得は、従業員からの申請があることが前提です。
所定労働時間が変更されたら?
時間単位年休として取得できる範囲のうち、日単位で残っている部分については、1日が何時間になるかは変更後の所定労働時間によります。
日単位に満たず時間単位で保有している部分については、所定労働時間の変動に比例して時間数が変更されます。

時間単位の有給休暇の管理を効率化するには?
時間単位の有給休暇の管理を効率化するには、有給休暇の管理機能が備わった勤怠管理システム導入がおすすめです。
One人事[勤怠]は、有休管理を自動化する勤怠管理システムです。
簡単な設定により、有給休暇の付与日、取得日数、残日数など自動計算ができ、従業員へのリマインド機能もついているため、担当者の負担が軽減されます。
また、有休管理を怠ると、罰金・罰則の適用の恐れや信用の低下につながるため、適切に行う必要があります。
有給休暇の取得率が低い企業は、ぜひご検討ください。

有給休暇の時間帯付与を取り入れて多様な働き方に対応を(まとめ)
時間単位年休とは、1時間単位で有給休暇が取れる制度で、導入には就業規則の変更と労使協定の締結が必要です。
有休の取得率や企業イメージの向上、従業員のワークライフバランスの維持というメリットが期待できます。ただし、管理が煩雑になるというデメリットも把握しておくことが重要です。
勤怠管理システムでシンプルに有給休暇を管理し、有休の消化率を上げて、従業員の心身の健康を守るように取り組んでいきましょう。
