有給休暇義務化の罰則とは? 違反のペナルティや取得促進の対策も
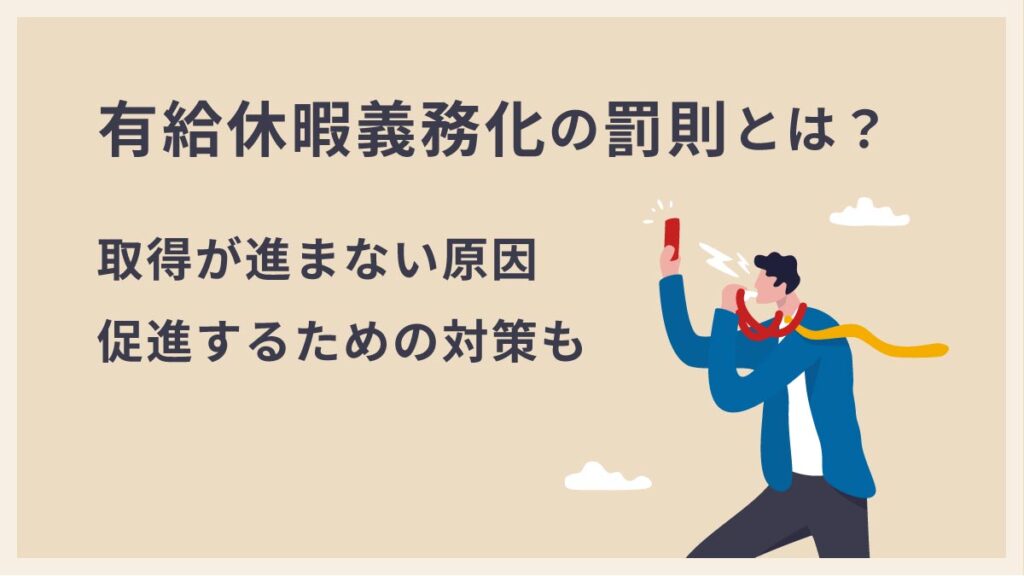
有給休暇に関する罰則として、一定の条件を満たす労働者に対して1年に5日間の有給休暇を取得させないと、企業にペナルティが科される可能性があります。
そのため、有給休暇そのものだけでなく罰則についても正しく理解しておかなければなりません。
そこで本記事では、有給休暇に関する罰則や義務化の内容について解説します。罰則が課されないようにするための対策もご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。
▼有給休暇のルールについて基本から確認したい方は、次の資料もぜひご活用ください。

 目次[表示]
目次[表示]
有給休暇に関する罰則
有給休暇の取得義務化や取得に関する罰則には、どのようなものがあるのでしょうか。具体的なケースや罰則内容を解説します。
- 年5日の有給を取得させていない
- 時季指定が就業規則に明記されていない
- 時季変更権の不当行使
年5日の有給を取得させていない
有給休暇の取得義務化によって、対象者に年5日を取得させなかった場合、労働基準法違反となり、違反者1人につき30万円以下の罰金が科される可能性があります。
違反者が多ければ多いほど罰金額も多くなってしまうため、会社全体として徹底して取得させなければなりません。
時季指定が就業規則に明記されていない
有給休暇の時季指定を行う場合も、罰則対象になることがあるため注意が必要です。
有給休暇の時季指定とは、年間10日以上の有給休暇が付与される労働者に対して、企業側が5日分の時季を指定して有給休暇を取得させるものです。
ただし有給休暇の時季指定を行う場合、あらかじめ就業規則に明記していなければなりません。就業規則に明記されていない状態で時季指定を行うと、労働基準法違反として1件につき30万円以下の罰金が科される可能性があります。
時季変更権の不当行使
有給休暇の取得について、労働者が取得したい日(時季)に、やむを得ない理由なく取得させないと罰則の対象です。この場合、6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金を科される可能性があるため注意が必要です。
「やむを得ない理由」とは、事業の正常な運営を妨げる場合です。たとえば、同一期間に多数の従業員が有給休暇の取得を希望していて、事業運営に支障が生じるようなケースが挙げられます。
有給休暇の義務化内容
働き方改革関連法の施行によって、企業はその雇用する従業員に有給休暇を取得させる義務が課せられました。具体的には、年10日以上の有給休暇を付与している従業員に、基準日から1年以内に5日以上を取得させなければならないという内容です。
参照:『「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」概要』厚生労働省
有給休暇の義務化対象
有給休暇の義務化対象者には、年に10日以上の有給休暇が付与されているすべての労働者が該当します。正社員だけでなく、パートタイマーやアルバイトなども対象とされていますので、注意しましょう。
有給休暇が年10日以上付与されるケースは以下のとおりです。
- 入社後6か月経過、6か月間の全労働日の8割以上出勤したフルタイム労働者
- 入社後6か月経過し、6か月間の全労働日の8割以上出勤した週30時間以上のパート・アルバイト
- 入社後6か月経過し、6か月間の全労働日の8割以上出勤した週5日出勤のパート・アルバイト
- 入社後3年半以上経過し、週4日出勤のパート・アルバイト
- 入社後5年半以上経過し、週3日出勤のパート・アルバイト
労働時間が週30時間未満のパートタイマーやアルバイトについては所定労働日数に応じた「比例付与」が行われるという点を覚えておきましょう。
参照:『年次有給休暇の付与日数は法律で決まっています』厚生労働省
有給休暇の付与タイミング
有給休暇の取得義務化以降、基準日から1年で5日間を取得しなければなりません。基準日とは、有給休暇の付与日です。
一般的なフルタイムの労働者の場合、有給休暇は入社して6か月経過のタイミングで10日間付与されます。そのため、付与される日が基準日となる点を理解しておきましょう。
ただし、企業によっては有給休暇の管理を効率化させるために、基準日を統一している場合もあります。これを有給休暇の「斉一的付与」といい、たとえば斉一的付与日を4月1日とする場合、毎年4月1日が有給休暇の基準日となります。
斉一的付与については企業ごとのルールを決めて運用する必要がありますが、労働者の不利益になるような内容で運用してはいけません。
労働基準法違反になる可能性もあるため、斉一的付与により不利益が生じる労働者には、前倒しで有給休暇を付与するなど、慎重に検討する必要があるでしょう。
有給休暇の取得が進まない要因

有給休暇を取得させたいと考えていても、なかなか取得が進まない場合もあります。有給休暇の取得が進まない要因についてご紹介します。
- 有給休暇の取得状況が管理できていない
- 業務過多や人材不足によって有給休暇が取得しにくい
- 有給休暇を取得しにくい風土や環境
有給休暇の取得状況が管理できていない
有給休暇の取得が進まない要因の一つに、具体的な取得状況を管理・可視化できていないことが挙げられます。従業員本人が現在、何日間有給休暇を持っていて、いつからいつまでに何日取得しなければならないかを把握できていないのです。
また、企業側も一人ひとりの有給休暇を適切に管理出来ていないため、リマインドができず、取得漏れが発生してしまうのでしょう。
業務過多や人材不足によって有給休暇が取得しにくい
多くの業務を抱えて人材が不足している場合は、そもそも有給休暇が取得できない状況にあります。部署や人材によって抱える業務量に差があるため、状況に応じて業務整理や分担を行ったり、人材採用を強化したりするなどの対応が必要です。
有給休暇を取得しにくい風土や環境
企業全体や部署の風土として有給休暇を取得する人が少ないと、有給休暇を取得しにくいという心理的な要因もあるでしょう。
有給休暇の取得が義務化された背景には、企業が労働者の働きやすさを支援したり、労働生産性を向上させたりすることが挙げられます。職場全体で有給休暇に対する理解を深めましょう。
有給休暇の取得を促進する対策
有給休暇の取得促進について、より効果的な対策をご紹介します。
- 有給休暇について社内の理解を深める
- 計画的付与制度を導入する
- 有給休暇取得計画表を作成する
- 半日や時間単位の有給休暇取得を認める
- 有給休暇を管理できるサービスを活用する
有給休暇について社内の理解を深める
有給休暇の取得を進めるためには、社内全体に有給休暇に対する理解を深めることが大切です。全社員を対象に、義務化された背景を解説するなどして、企業として有給休暇の取得促進を行っていることを示しましょう。
また部署の責任者やリーダーを対象に、有給休暇の取得促進を伝えることも有効です。職場の雰囲気として有給休暇を取りにくい場合は、責任者が積極的に取得を呼びかけましょう。
計画的付与制度を導入する
有給休暇の取得促進対策として、計画的付与制度を導入するのも効果的です。計画的付与制度とは、全従業員が保有する年次有給休暇の5日を超える部分について、あらかじめ取得する日にちを決めるものです。計画的付与制度を採用する場合、年5日は従業員の自由な意思で取得できるようにしなくてはなりません。
計画的付与制度は、企業全体(もしくはグループ別・個人別)で指定日に年次有給休暇を取得することになるため、管理の手間が省けるでしょう。
ただし、計画的付与で年次有給休暇を取得させるには、就業規則への明記と労使協定の締結が必要です。
有給休暇取得計画表を作成する
有給休暇取得計画表とは、組織全体で有給休暇の取得予定を立てたものです。半年単位や年単位で作成すれば長期的な見通しを立てられるでしょう。
また、ほかの従業員の有給休暇の予定を確認できることで、自分だけでなくほかの人も有給休暇を取得しているという安心感から、気兼ねなく取得できるようになるはずです。
計画表は手動でも作成できますが、システムなどを使用するとより効率的に作成できます。
半日や時間単位の有給休暇取得を認める
半日単位の有給休暇取得を認めることも、有給休暇の取得促進につながるでしょう。半日単位による有給休暇は、取得義務である年5日から差し引くことができます。ただし、時間単位の有給休暇は取得が義務化された5日から控除できません。
また、時間単位の有給休暇取得を導入するためには、労使協定の締結と就業規則への明記が必要です。時間単位で取得できる有給休暇は1年につき5日分までが上限とされているという点も理解しておきましょう。
有給休暇を管理できるサービスを活用する
有給休暇の取得を促進するためには、有給休暇の管理を自動化することが重要です。有給休暇の取得が進んでいない企業の多くは、取得状況を正確に把握できていないケースがあります。
有給休暇の管理を効率化するサービスには、勤怠管理システムや専用ソフトなどがあります。取得状況を可視化してすぐに確認できたり、アラート機能があったりすると、所得漏れを防げるでしょう。

勤怠管理をラクにするなら|One人事[勤怠]
One人事[勤怠]は、勤怠管理をクラウド上で管理できるシステムです。管理を効率化することで、残業状況の把握や労働時間の集計作業におけるミス防止にも役立ちます。有給の付与・失効アラート機能や、労働基準法などの改正にも対応しているため、有休管理としてもお使いいただけます。
また、給与計算の際も自動で紐づけができるOne人事[給与]との連携で、人事労務領域の業務をより効率化できるでしょう。
One人事[勤怠]の初期費用や気になる使い心地については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門のスタッフが貴社の課題をていねいにヒアリングしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、勤怠管理の効率化のヒントが詰まったお役立ち資料を無料でダウンロードいただけます。勤怠管理をラクにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。
まとめ
有給休暇の義務化に関する罰則を回避するためにも、年5日を確実に取得させることが大切です。
本記事で紹介した、有給休暇の取得が進まない要因や有給休暇の取得を促進する対策を参考にしたうえで、自社に適したものを実行しましょう。
また、有給休暇の取得を適切に進めるには、勤怠管理システムや有給休暇管理システムなどの活用により現状をリアルタイムで可視化し、対応することが重要です。
