有給休暇の消化を促すには? 義務化や退職時の対応、注意点を解説!
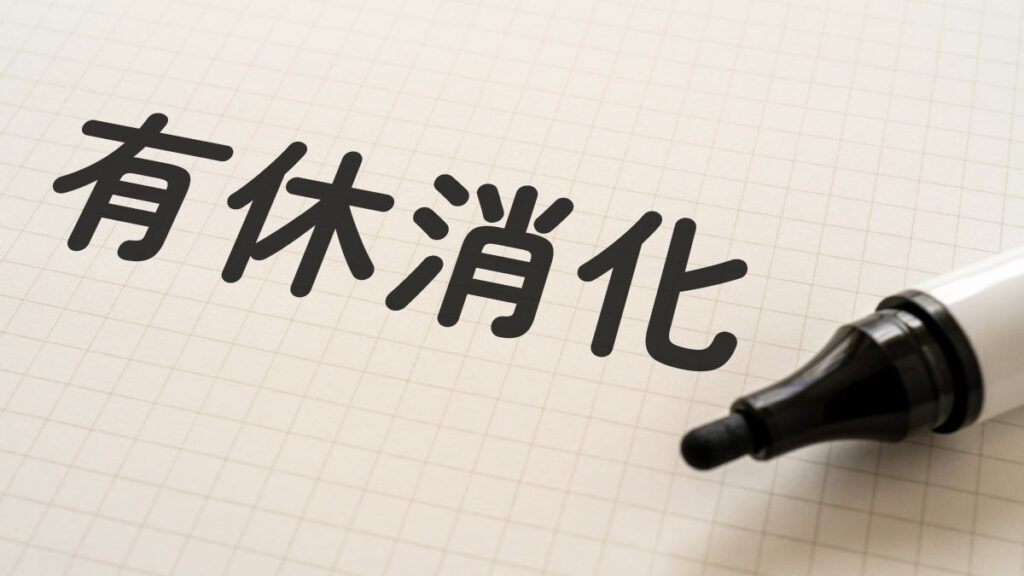
有給(年次有給休暇)の消化は、従業員の働きやすさや体調管理、生産性向上などの点においてさまざまなメリットがもたらされます。2019年の労働基準法改正で、有給取得が義務化されたこともあり、企業ではよりスムーズでトラブルのない有給管理が求められています。
そこで本記事では、有給消化について総合的に解説しながら、有給取得の義務化に関する内容や有給消化の注意点や促進方法などもご紹介します。
▼有給休暇のルールについて基本から確認したい方は、次の資料もぜひご活用ください。

 目次[表示]
目次[表示]
有給(年次有給休暇)の消化とは?
有給(年次有給休暇)消化とは、企業から労働者に対して付与される有給休暇を消化することです。
一定の条件をもとに、企業側は労働者に対して有給を付与しなければならず、さらに有休の一部を消化することが法律で義務化されています。
有給消化は在職中のみに取得できるものであるため、当然ながら退職後に取得することはできません。
有給(年次有給休暇)とは
有給とは、企業が一定の条件を満たした労働者に対して付与する休日です。
また、有給は本来労働者が労働するはずである日にのみ取得し、消化することになっているため、雇用契約で定められている休日に取得することはできません。
たとえば、土日を休日としている企業の場合、有給を土日に取得し消化することはできないということです。
有給休暇の取得条件
有給休暇の取得条件は、
- 雇用開始の日から6か月が経過していること
- 全労働日の8割以上の出勤がなされていること
とされています。
また、最初の有給付与日(基準日)から1年が経過した以降、勤続年数によって付与される有給日数が増えていきます。
| 勤続年数 | 6か月 | 1年 6か月 | 2年 6か月 | 3年 6か月 | 4年 6か月 | 5年 6か月 | 6年 6か月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有給付与日数 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
しかし、6年半以上の勤続では同じ日数(20日)が付与されることになっているため、正しく理解しておきましょう。
参照:『しっかりマスター労働基準法ー有給休暇編ー』厚生労働省
有給付与日(基準日)
有給付与日は、労働者の入社日によって異なります。中途入社などを積極的に行っている企業の場合は、労働者によって有給取得日(基準日)が異なるため、管理を徹底しなければなりません。

有給消化が義務化
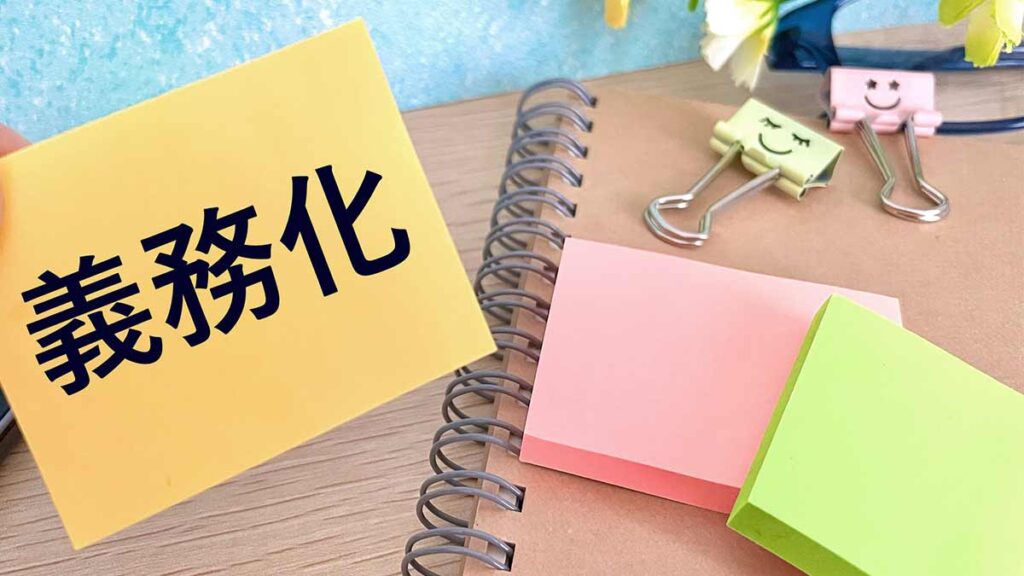
有給消化は、2019年4月に義務化されました。義務化にともない、変更点があったり罰則規定が定められたりと、企業は正しい理解と徹底した管理が必要とされています。
そこで、有給消化の義務化についてわかりやすく解説します。
有給消化が義務化された背景
有給消化が義務化された背景には、労働者の心身の健康を守る目的や働き方改革の推進、労働生産性の向上などが挙げられます。もともと義務化される前にも有給という仕組みはあったものの、企業によっては消化しにくい場合がありました。
また、長時間労働が好ましいとされるような時代もあったものの、近年インターネットの普及や技術革新が進んだことで、生産性が向上しやすくなり、長時間労働のメリットが薄れています。
むしろ長時間労働や少ない休日のなか働き続けることで、労働者の心身の健康が損なわれやすくなり、生産性が低下しかねないという意見が出始めました。
こうした背景を踏まえ、労働者がより働きやすくリフレッシュできることや、労働生産性の向上を目指し、有給消化の義務化につながったといえるでしょう。
義務化の内容や変更点
有給消化の義務化における内容は、有給付与日から1年以内に、新たに付与された付与日数のうち5日を取得させなければならないということです。
義務化によって漏れなく有給を消化させるために、企業側は労働者に有給消化を促したり労働者の有給取得状況を適切に管理したりする必要があるのです。
義務化に違反した場合
有給消化の義務化は、労働基準法で定められているため、違反した場合は労働基準法違反として処分され、違反した労働者1人につき、30万円以下の罰金が企業側に科せられるため、注意しなければなりません。
参照:『労働基準法 第39条、第120条』e-GOV法令検索

有給消化のメリット
有給消化のメリットにはどのような点が挙げられるでしょうか。具体的なメリットをご紹介します。
生産性の向上
有給を消化することで、労働者はリフレッシュできるようになり、仕事の生産性向上につながりやすくなるでしょう。
長時間労働や休日が極端に少ない状態で働き続けると、体調を崩す危険性もあります。疲労からミスが増えてしまったり、よいアイデアが生まれにくくなったりと、生産性が低下しかねません。
有給消化によって十分な休息を取りつつ、仕事やプライベートを充実させられれば、パフォーマンスが向上し、成果にも結び付きやすくなるでしょう。
企業イメージの向上
有給消化を促進している企業ということが伝われば、外部へよい印象を与えられます。
労働者を大切にしていることにもつながるため、採用活動における求職者からのイメージが向上し、人材を確保しやすくなるでしょう。優秀な人材を確保できれば、さらなる会社の成長や成果につながるはずです。
離職防止
有給消化がしやすい環境では、労働者の離職も防止しやすくなるでしょう。働くうえでの条件として、労働時間や休日の日数などを1つのポイントにしている人は少なくありません。
有給消化ができることで、休息が取りやすく働きやすい環境にもつながるため、離職防止効果も期待できそうです。
有給消化のデメリット
有給消化のデメリットにはどのような点があるのでしょうか。メリットが目立ちがちな有給消化ですが、デメリットもゼロではありません。
具体的なデメリットについてチェックしてみましょう。
有給管理が必要
有給消化が義務化されたことで、年10日以上の有給が付与される労働者には年間5日を消化させなければなりません。労働者に確実に有給を取得させるためには、適切な有給管理が必要です。
一人ひとりの有給取得状況を正しく把握し管理しなければならない点は、手間や労力になり、デメリットの一つとして否めません。
罰則規定がある
有給消化は労働基準法により義務化されているため、違反すると罰則対象になってしまいます。具体的な罰則は、違反者1人につき30万円以下の罰金です。
仮にずさんな有給管理によって複数人の違反者を出してしまった場合は、罰金として負担する金額も大きくなってしまうでしょう。
有給消化の注意点
有給消化を行う際には、いくつかの注意点があります。具体的にどのような点に注意すればよいのかをご紹介します。あらかじめ注意点を把握しておくことで、リスクを抑えることにもつながるため、ぜひ参考にしてください。
有給休暇の買取
有給を退職時に取得するケースでは、企業側と退職者側のスケジュールが合わず、どうしても引き継ぎがスムーズに行えない場合もあるためトラブルになりかねません。その場合、企業側による有給休暇の買取も検討してみましょう。
ただし、原則として有休の買取は一部のケースに限って認められるものであるため、通常は認められない点を理解しておきましょう。
有給消化の管理
有給消化は義務化されているため、労働者の有給取得状況を正しく把握しなければなりません。ずさんな管理をしていると、義務化された年間5日の有給取得ができない労働者も出てきてしまう可能性もあります。
労働者が有給を問題なく消化できているかを確認したり、取得できていない労働者に対してどのように取得させるかなどを検討したりして、取得漏れのないよう徹底した管理を行いましょう。
有給消化の拒否
労働者が有休の取得申請を行っているにもかかわらず、拒否してしまうことのないよう企業側は注意しなければなりません。労働者の権利でもある有給取得を拒否することは、労働基準法違反に該当する可能性もあります。
義務化対象の有給を消化させられなかった場合
有給取得の義務化では、年10日以上付与された有休のうち、1年以内に5日間の取得ができない場合は違反とされています。実際に5日間を消化できなかった場合は、労働基準法違反として罰則対象となるリスクがあるため、注意しなければなりません。
退職時に有給消化する場合
有給消化を退職時に行う場合、早めに有給申請を行ってもらうよう、労働者に伝えなければなりません。退職に際して、業務の引き継ぎに時間がかかる場合があり、想定していた有給消化ができなかったというケースも少なくありません。
有給や退職に関しては、トラブルにつながりやすいため、企業や上司と連携しながらスムーズな対応を目指しましょう。
有給消化を促す方法
有給消化が義務化されたことで、企業側は労働者に対して有給消化を促進しなければなりません。期日ギリギリになって慌てないためにも、有給消化を事前に促すことが大切です。
そこで、有給消化を促進する方法をご紹介します。
半日単位での年休消化を認める
有給消化を促進するためには、半日単位の有給取得を認めるという方法が挙げられます。
業務が忙しくて有給が取りにくい状況でも、半日なら取りやすい場合もあるでしょう。義務化された5日分をすべて半日単位で取得する場合、10回取得することになります。
会社や部署の状況にもよりますが、従業員ができるだけ有給を取得しやすいよう、柔軟な対応を検討してみましょう。
時季指定を導入する
有給消化を促進する方法として、あらかじめ有給を取得する日にちを指定する、時季指定を行う方法もあります。
ただし、有給は原則労働者の希望日に取得するものであるため、時季指定を行う場合には、事前に就業規則に記載し、希望や意見があった場合には耳を傾ける必要があるでしょう。
計画年休でまとめて消化する
有給消化の促進として、計画年休(計画的付与制度)を活用する方法もおすすめです。
計画年休とは、労使協定を締結したうえで、企業側が労働者の有給取得日をあらかじめ決められるものです。計画年休では、付与された有休のうち5日間を除いた日数が対象となります。
たとえば、会社全体で同じ日に取得する方法や部署やチームごとの取得、大型休暇の前後などで個別に取得する方法が挙げられます。
計画年休は、条件を満たしたすべての労働者が計画的に有給を取得することになるため、抵抗なく有給を消化しやすいというメリットもあります。
有給消化の仕組みをつくる
有給消化を促進するためには、企業として有給を消化しやすい環境を整えることが大切です。有給消化ができなかった労働者がいた場合、労働基準法違反になってしまうため、有給管理は怠れません。
とくに有効なのは、有休の取得状況を正確に把握したり、すぐに確認できるシステムを活用したりすることが挙げられるでしょう。システムによっては、有給日数が残っている労働者にアラートを出してくれる機能を搭載しているものもあります。
またスムーズな有給取得を行うために、有給を申請する際には「事前に〇日前に申請すること」と期限を就業規則に盛り込んだり、労働者にこまめに周知したりすることも効果的でしょう。
まとめ
有給消化については、2019年4月から労働基準法により「年5日間の取得」が義務化されたことで、取得しなければならないものとなっています。
違反してしまうと罰則が科せられる可能性があるため、企業側は徹底した有給管理と取得促進が求められます。
スムーズでトラブルのない有給消化を行うためにも、事前に労働者へ周知したり、システムを活用したりするなどして、工夫した管理を行いましょう。
有給管理を効率化するなら|One人事[勤怠]
One人事[勤怠]は、煩雑な勤怠管理をクラウド上で完結させる勤怠管理システムです。
- 勤怠の入力・打刻漏れが多い
- 月末の集計をラクにしたい
- 労働時間や残業時間を正確に把握できていない
というお悩みを持つ企業をご支援しております。
One人事[給与]と連携すれば、給与計算に自動で紐づけられるため、より速くより正確に業務を進められるでしょう。また、有休の付与・失効アラート機能や、労働基準法などの改正にも順次対応してまいります。
One人事[勤怠]の初期費用や気になる使い心地については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門のスタッフが貴社の課題をていねいにヒアリングしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、勤怠管理の効率化のヒントが詰まったお役立ち資料を無料でダウンロードしていただけます。勤怠管理をラクにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |
