なぜ付き合い残業はなくならない? 原因と対策や放置のデメリットを紹介
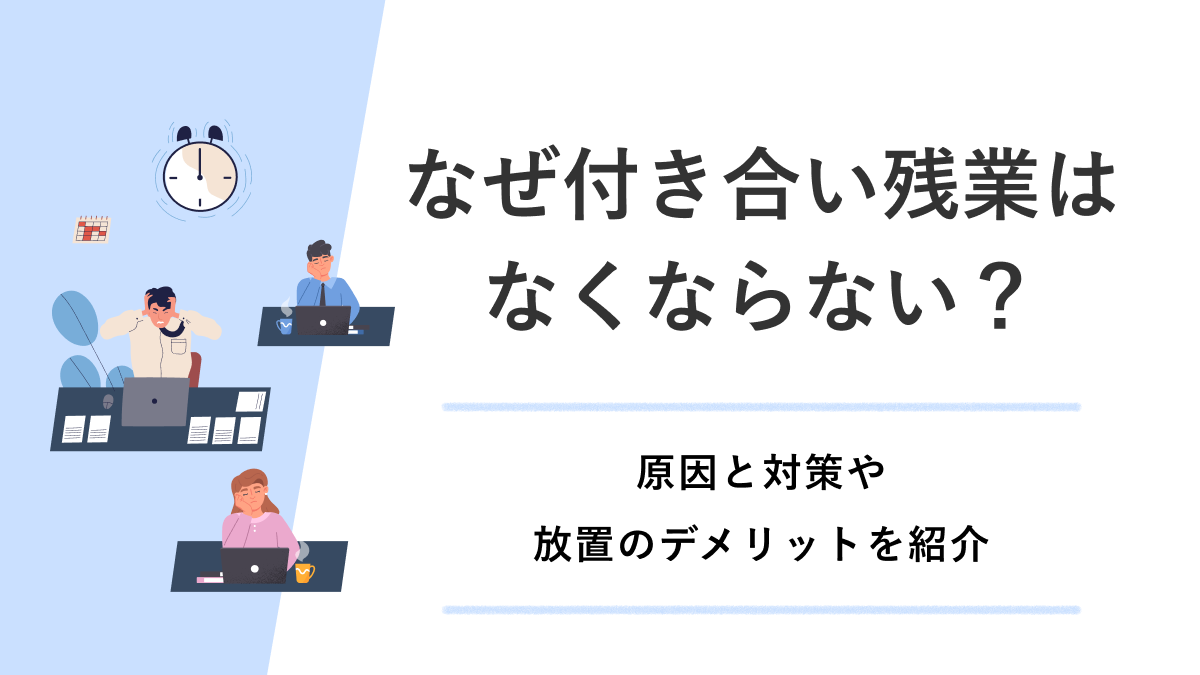
付き合い残業とは、個人では業務が完了しているにもかかわらず、同僚や上司に遠慮して帰れずにいることです。
「自分の仕事は終わっているのに、周りが帰らないから帰れない……」という経験をしたことはありませんか。
本記事では、なぜ付き合い残業がなくならないのか、背景にある原因を整理し、放置するデメリットや対策を解説します。付き合い残業という課題にどう向き合ったらいいか、参考にしてください。

 目次[表示]
目次[表示]
付き合い残業とは?
付き合い残業とは、自分の業務は終わっていても、上司や同僚にあわせて会社に残る現象を指します。
「帰りたいけれど、先に帰るのは気まずい」
「上司より早く帰ると評価が下がるのではないか」
そんな心理的なプレッシャーから発生するのが特徴です。
一部の企業で根強く残っている付き合い残業は、一見すると小さなことに思えるかもしれません。しかし、毎日の積み重ねが従業員の心身に負担を与え、やがては組織全体のパフォーマンス低下を招きます。企業としては適切な対策を講じなければなりません。
サービス残業との違い
サービス残業とは、残業代の全部または一部が支払われないまま、法定労働時間を超えて従業員を働かせることを指します。本来であれば支払うべき賃金を、正当な理由なく支払わないのは、労働基準法違反です。
一方で付き合い残業は、残業代が支払われるケースもあれば、そうでない場合もあります。付き合い残業の問題点は、本人の意思とは関係なく「周囲にあわせて残る」という不合理さです。
もし付き合い残業がサービス残業と重なれば、無駄な時間を過ごすだけでなく、正当な対価も得られないため、精神的・肉体的な疲労がさらに蓄積されるでしょう。早急に解消しなければならない問題といえます。
▼労働時間を客観的に把握できていますか。労働時間の管理方法に少しでも不安があるなら、以下の資料もご活用ください。

付き合い残業が発生する主な原因
付き合い残業は、単なる個人の意思の問題ではなく、企業文化や職場の人間関係に深く根ざしています。代表的な3つの原因を見ていきましょう。
- 周囲が残業していて帰りにくい
- ほかの人から業務を引き受けている
- 残業を認める社内風土がある
周囲が残業していて帰りにくい
付き合い残業の原因で、もっともよくあるのは、上司や同僚が残業しているなかで自分だけ先に帰るのは気まずいと感じているケースです。「周りがまだ働いているのに、自分だけ帰るのは申し訳ない」という心理が働くからです。
この問題は、単なる心理的な圧力にとどまりません。上司が暗に「残るのが当然」という態度を示すと、パワーハラスメントに該当する可能性があります。
労働基準法では、労働時間は1日8時間、1週40時間が上限と定められています。上限を超える労働を強要するのは、法律違反となるため注意が必要です。
ほかの人から業務を引き受けている
自分の仕事は終わっているのに、同僚や部下の仕事を手伝ったり、引き受けたりして付き合い残業になるケースも少なくありません。
チームワークや協力はもちろん大切です。ただし、業務の偏りや人員配置の不備が背景にある場合、特定の人に負担が集中し、残業が常態化してしまいます。
付き合い残業は個人の問題として考えるのではなく、組織全体の業務配分や人員配置から見直す必要があります。
残業を認める社内風土がある
一部の企業では、遅くまで残っている人ほど努力しているとみなす風土が残っているのではないでしょうか。
「先に帰ると評価に響くのではないか」と不安になる社員も少なくありません。
とくに上司が残っていると、部下は必要のない残業をしてしまいます。
定時で帰る人が「手を抜いている」と誤解されるのは望ましくありません。本来なら効率的に仕事を終える人こそ評価されるはずなのに、逆の基準が働いています。
残業が当たり前という風潮は、会社にとって、次のような問題を引き起こします。
- 「時間をかければよい」という誤った認識が広がる
- 長時間労働によって疲労が蓄積し、ストレスが増加する
- 優秀な人材ほど効率性を重視し、転職を検討する
付き合い残業は、組織の評価制度や文化にも起因しているのです。
▼社員の残業実態を適切に把握できていますか。管理方法に少しでも不安があるなら、以下の資料もご活用ください。

付き合い残業を放置するデメリット
付き合い残業は、一見「少しの我慢」で済んでいるように見えても、積み重なると組織全体にも深刻なダメージを与えます。
職場全体に長時間労働が広がり、やがては生産性の低下・人材流出・コスト増大といった課題に直面するでしょう。
ここでは、付き合い残業を放置したときに生じる4つのリスクを整理していきます。
- 長時間残業が常態化しやすくなる
- 生産性が低下する
- 人材が定着しづらくなる
- 人件費が増加する
長時間残業が常態化しやすくなる
付き合い残業を放置すると、職場全体に長時間労働が根づいてしまいます。
「周りが残っているから自分も帰れない」という状況が繰り返されると、社員全体に「残業するのが当たり前」という空気が生まれます。
本来は仕事が終わっているのに、暗黙の了解で1〜2時間の居残りが常態化すれば、疲労やストレスは蓄積し、最悪の場合、労災やメンタル不調のリスクも否定できません。
残業が多い企業は「ブラック企業」というレッテルを貼られ、採用や企業イメージに悪影響を与えるでしょう。
生産性が低下する
付き合い残業は業務効率を著しく低下させます。不要な残業時間で、従業員は時間を持て余し、結果として時間あたりの成果が下がってしまうからです。
たとえば、2時間で終わる作業を4時間かけて行うようになれば、業務効率は半分以下です。しかも夜遅くまで働けば翌日の判断力や集中力も鈍り、ミスの増加や顧客対応の質の低下といった問題も発生するでしょう。
チーム全体の士気を下げ、創造的なアイデアも生まれにくくなってしまいます。
「だらだら残る」文化は、組織全体のパフォーマンスを低下させます。付き合い残業は時間の浪費ではなく、経営資源の損失といえるのです。
人材が定着しづらくなる
付き合い残業が常態化している職場では、優秀な人材ほど職場を去ってしまいます。
効率的に働きたい人にとって、付き合い残業は「自分の時間が理不尽に奪われる」という大きなストレス要因となるからです。
効率よく終わらせても、結局は帰れないのであれば、不満が募るのも当然です。スキルアップや家庭との時間を確保できない、正当に評価されにくいと感じ、転職を選択するケースも少なくありません。
結果的に、企業に残るのは「ただ長く残業できる人」となります。付き合い残業は、人材流出の引き金となる深刻なリスクです。
人件費が増加する
付き合い残業は、人件費というコスト面でも企業にとって大きな損失です。
業務が終わっているのに残業代を支払い続けなければならないため、生産性に見合わない支出が増えることになるでしょう。
1人の従業員が一日1時間の付き合い残業をした場合、月に20時間もの無駄なコストが発生します。時給換算で2,000円とすると、月額4万円の無駄な支出です。
年間では48万円、10人の職場なら480万円もの損失となります。決して、軽視できない金額でしょう。
付き合い残業は「見えにくいコスト」として経営を圧迫するかもしれません。放置は未来への投資機会を失うことと同じです。
本来であれば研修費用や福利厚生の充実、業務効率化システムの導入など、生産性向上につながる投資に回せた資金が失われているのです。
付き合い残業を防ぐための対策
付き合い残業は、生産性の低下や健康リスクなど多くの問題を引き起こします。放置すれば、優秀な人材の退職やコストの増加にもつながりかねません。だからこそ、組織として仕組みを整えることが必要です。
解消に向けた効果的な6つの対策を紹介します。
- 残業を事前承認制とする
- 「定時退社が当たり前」という風土をつくる
- 業務量の配分を見直す
- 人事評価の仕組みを見直す
- 多様な働き方に対応する
- 勤怠管理システムで労働時間を正確に把握する
残業を事前承認制とする
残業を事前承認制にすることで、不必要な付き合い残業を減らせます。
あらかじめ残業理由と所要時間を上司に申請・承認させるルールを徹底すれば、「なんとなく残っている」という状況を排除できるからです。
承認制は「残業が必要かどうか」を可視化する仕組みです。余分な残業を排除し、付き合い残業を根本から防ぎましょう。
「定時退社が当たり前」という風土をつくる
職場の文化として「定時で帰るのが普通」という空気をつくることが、付き合い残業の予防につながります。
職場の雰囲気が変わらない限り、社員は「帰りにくさ」を感じ続けてしまうからです。
たとえば 管理職が率先して定時で帰ると、部下も帰りやすくなります。ほかにも次のような取り組みを継続して行うことで、帰宅しやすい空気にに変わっていくでしょう。
- 終業時に音楽を流す
- 照明を落とす
- 毎週「ノー残業デー」を設定する
風土を変えることは一朝一夕ではありませんが、経営層や管理職がまずはお手本を示し、社員が安心して帰れる環境を整備することが重要です。
業務量の配分を見直す
特定の従業員に業務量が偏っている場合、業務量の配分見直しも付き合い残業をなくすために必要な方法です。
「いつも残業している人」が1人でも少なくなれば、定時退社することに気まずさを覚えていた社員も、気持ちよく帰宅できるようになります。
業務プロセスを見直し、簡略化できる点や無駄な点を洗い出し、改善や削減を行いましょう。従業員の業務負担を軽減するような効率化ツールの導入も一案です。
業務標準化に取り組むと、残業が減っていくでしょう。
業務配分の見直しは、付き合い残業の解消だけでなく、組織全体の生産性向上にもつながります。
人事評価の仕組みを見直す
「残業をしている=頑張っている」という評価基準を改めなければ、付き合い残業はなくなりません。
定時で帰る人が「手を抜いている」と見られてしまう環境では、社員は安心して早く帰れません。
業務を効率的に終えた社員を「時間管理が優秀」として積極的に評価しましょう。早く帰るのはよいこと」というメッセージを全社で共有する取り組みが、社員の意識を変えていきます。
効率や成果をきちんと評価する仕組みがあってこそ、付き合い残業のない健全な職場が実現します。
多様な働き方に対応する
テレワークや時短勤務、フレックスタイム制などを取り入れると、付き合い残業は起きにくくなります。
勤務形態が柔軟になると、そもそも「周囲に合わせて残る」という同調圧力が発生しにくいからです。
テレワークでは周囲の残業を気にせずに済み、業務が終わればすぐ終了できます。時短勤務は「時間内に終わらせる」意識を強め、フレックスタイムは自分のペースで働けるため無理に残業する必要がありません。
多様な働き方は、付き合い残業の予防策であると同時に、従業員のワークライフバランスを支える施策の一つです。
勤怠管理システムで労働時間を正確に把握する
勤怠管理システムを活用すれば、付き合い残業を可視化し、抑制につなげられます。
残業申請や労働時間の実績をリアルタイムで把握できるため、理由のない残業に歯止めをかけられるからです。
勤怠管理システムは、 退勤の打刻や残業申請・承認、シフト作成、労働時間の集計まで一元管理できます。必要性の低い残業基準を設定し、アラートが出る仕組みを取り入れるなどの活用方法もあります。
「どの部署で付き合い残業が多そうか」が特定できるようになれば、具体的な改善に踏み出せるでしょう。

まとめ
付き合い残業が常態化すると、長時間労働の常態化や生産性の低下、人材流出やコスト増大など、企業にとって大きな損失を招きます。
解消には「残業の事前承認制」「定時退社の文化づくり」「評価制度の見直し」といった組織的な取り組みが欠かせません。勤怠管理システムの導入も有効です。
勤怠管理システムを導入すれば、残業の事前承認や労働時間の可視化が可能になり、不必要な付き合い残業防止にもお役立ていただけます。組織全体で「定時退社が当たり前」の文化を根づかせるためにも、まずはシステムから改善を始めてみませんか。
付き合い残業を生まない管理体制を整備|One人事[勤怠]
One人事[勤怠]は、残業時間の管理効率化にお役立ていただけるクラウド型の勤怠管理システムです。
One人事[給与]との連携により、実労働時間の集計から割増賃金の計算までをシームレスに運用できます。
One人事[勤怠]の初期費用や操作性については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門のスタッフが貴社の課題をていねいにお聞きしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、勤怠管理の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードしていただけます。勤怠管理をラクにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |
