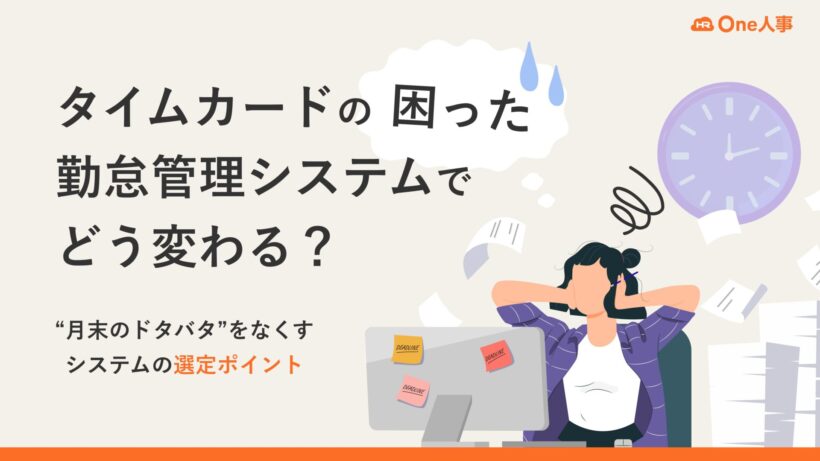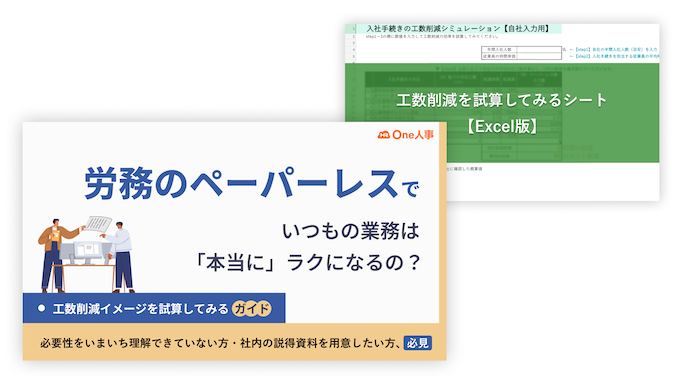タイムカードを廃止すべき理由は? 違法リスクと管理システムの選び方も解説
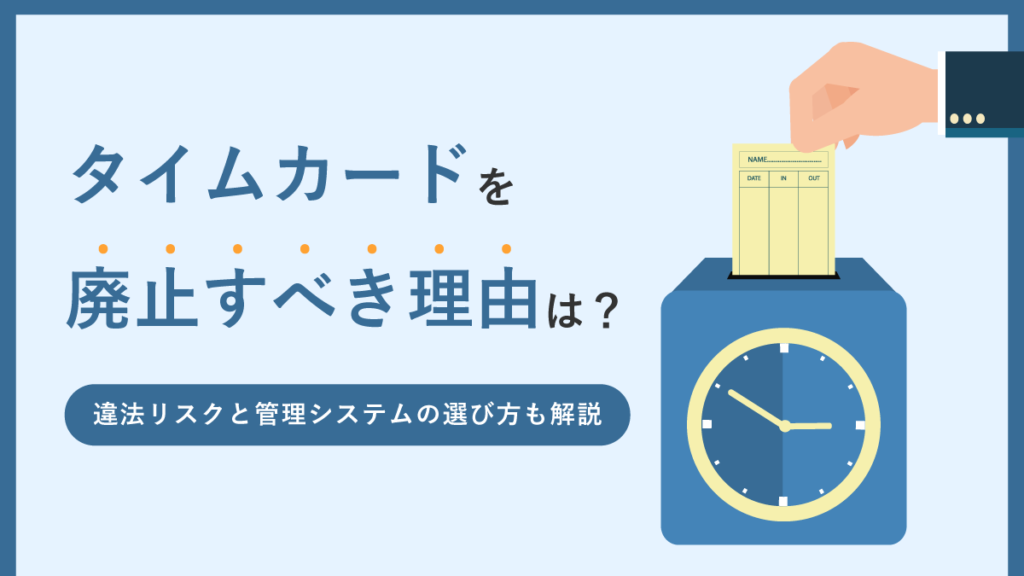
タイムカードの集計作業に毎月何時間もかかっていませんか。 手作業での集計はミスも増え、負担が大きくなりがちです。最近では多くの企業が課題解決のために、タイムカードを廃止し、デジタル化を進めています。
本記事では、タイムカードを廃止するメリットと注意点、代替となる勤怠管理システムの選び方を中心に解説します。
→タイムカードを廃止して管理を効率化|「One人事」サービス資料を無料ダウンロード
 目次[表示]
目次[表示]
タイムカードを廃止すべき理由
労働環境の変化や法改正により、タイムカードによる勤怠管理では対応が難しくなっているのが現状です。
自社でタイムカードを使用している場合、毎月どれくらいの時間を取られているでしょうか。タイムカードを使った勤怠管理では以下のような課題が発生し、人事担当者の負担が大きくなっています。
- 打刻ミスの修正に時間がかかる
- 不正打刻のリスクがある
- 有給休暇の取得状況を一覧で把握できない
- 毎月の集計・確認作業が大きな負担になる
とくに働き方改革関連法の施行後は、より厳密な労働時間管理が求められ、タイムカードを廃止する動きもあります。
タイムカードを廃止すべき3つの理由について、以下で詳しく紹介します。
従業員の労働時間を正確に把握するため
タイムカードでは正確な労働時間の管理が難しく、法律に沿った運用ができないため、廃止が検討されています。
近年の法改正により、以前にも増して、企業には厳密な労働時間の管理が必要になりました。とくに2019年の労働安全衛生法改正では、従業員の労働時間を客観的に記録し、適正に管理することが求められています。
さらに2023年4月からは、中小企業でも「月60時間を超える時間外労働」に対し1.5倍の割増賃金を支払うことが義務化されました。
しかし、タイムカードが客観的な記録といえるかどうかは判断が分かれます。タイムカードでは打刻漏れや不正打刻のリスクを完全になくせず、労働時間の正確性を保つことが難しいからです。
労務トラブルを防ぐためにも、タイムカードを廃止し、客観的な勤怠管理が可能なデジタルへの移行が検討されています。
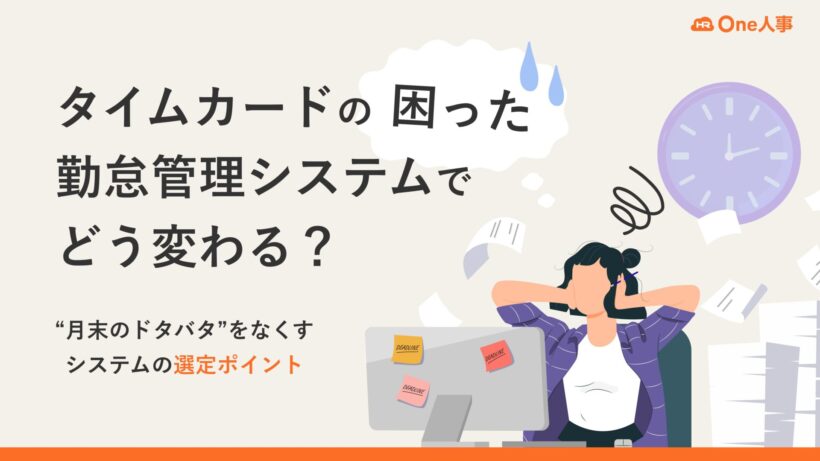
有給休暇の取得状況を把握するため
タイムカードでは有給休暇の取得状況を把握しきれず、法定義務違反のリスクがあるため、廃止の動きがあります。
2019年の法改正により、年間10日以上の有給休暇が付与される従業員には、年5日以上の取得義務が課されました。
企業には「従業員が確実に有給を取得できるよう、取得状況を管理する義務」があり、怠ると労働基準監督署の指導や罰則を受ける可能性があります。
タイムカードは「出退勤の記録」を目的としたものであり、有給休暇の管理には適していません。有休管理にはタイムカードとは別のソフトやツールを使わないと、休暇の取得義務が果たせなくなってしまいます。
管理工数を削減するため
タイムカードでは回収や集計の手作業が必要となり、毎月の締め日前には人事・総務の負担が大きくなります。また、労働時間の集計ミスが発生しやすく、給与計算への影響も否定できません。
企業の勤怠管理業務を効率化し、より重要な業務にリソースを割くためにも、タイムカードを廃止してシステム化が推進されています。
タイムカードを廃止するのは違法?
タイムカードの廃止自体は違法ではありません。労働時間を適切に記録・管理できるタイムカード代替手段があれば、廃止しても問題ないでしょう。
企業には従業員の労働時間を把握する責任があります。労働安全衛生法では、労働者の始業・終業時刻を客観的な記録に基づいて確認し、適正に記録することを規定しています。
以下のような運用が発覚すると、法的な責任が問われるため注意しましょう。
- 適切な勤怠管理方法を導入せずにタイムカードを廃止
- 出勤簿やタイムカードなどの勤怠データを法定保存期間の5年間(当面の間は3年間)保管していない
- 残業時間の記録を改ざんする
従業員の勤怠記録は重要な法定書類です。3年間の保管義務があり、違反した場合は30万円以下の罰金が科されます。
2020年4月の労働基準法改正により、保管期間は5年間に延長されていますが、いつ猶予期間が終わるかはまだ決まっていません。
タイムカードに代わる勤怠管理方法にはICカードやPCログ、勤怠管理システムがあります。デジタルツールは、タイムカードよりも不正やミスが少なく運用できるため、移行の手段として検討してみてもよいでしょう。
タイムカードによる勤怠管理の課題
従来のタイムカードによる勤怠管理には、さまざまな問題点があります。とくに労働環境の変化や法改正の影響により、現代の働き方に対応できないことが企業の生産性を妨げる要因です。
タイムカードを使い続けることで生じる主な課題を解説します。
労働時間の正確な把握が難しい
タイムカードでは自己申告による打刻が基本となるため、実際の労働時間と記録にズレが生じ、正確な勤怠管理が難しくなります。
| 課題・問題点 |
|---|
| ・打刻忘れや打刻ミスにより、実際の労働時間と誤差が生じる可能性がある ・外出・出張時の労働時間を正確に記録できない ・休憩時間の管理があいまいになりがち |
企業には「労働時間の客観的な記録」が義務づけられており、不正確な勤怠管理は未払い残業の発生や労基署の指導につながります。
多様な働き方に対応できない
タイムカードは出社を前提とした仕組みのため、テレワークなどの柔軟な働き方や、外出が多い営業職の働き方に対応できません。スマートフォンやクラウドを活用した勤怠管理システムなら、出社していなくても打刻が可能ですが、打刻機から離れていると勤務時間を記録できない点がタイムカードの課題です。
不正打刻や改ざんのおそれがある
タイムカードには、打刻の不正やあとからの修正が容易であるという問題があります。
| 課題・問題点 |
|---|
| ・代理で打刻してもらう ・遅刻・早退を隠す ・残業時間の水増し |
不正打刻が常態化すると、労働時間の記録の信頼性が低下し、企業のコンプライアンスリスクが高まります。
勤怠データの集計や給与計算に工数がかかる
タイムカードのデータを給与計算に反映させるには、手作業での集計が必要であり、ミスが発生しやすい点が課題です。
| 課題・問題点 |
|---|
| ・給与計算前の集計作業が煩雑 ・転記ミスや計算ミスが発生しやすい ・締め日前の業務負担が増大 |
転記ミスによる給与計算の誤りは、未払い賃金や従業員からのクレームにつながるリスクがあります。
保管場所を確保する必要がある
タイムカードは紙の媒体であるため、長期保管にスペースと管理コストがかかります。勤怠データは5年間保管しなければなりません(当面3年間)。紙は劣化や紛失のリスクがあるうえ、必要なときに探す手間がかかり、業務の非効率につながっています。
タイムカードを廃止してシステム導入をするメリット
勤怠管理システムは、単なるタイムカードの電子化にとどまらず、業務効率の向上や労働時間の適正管理を実現するツールです。労働基準法の遵守や長時間労働の是正など、働き方改革を推進するための役割も果たします。

タイムカードを廃止し、勤怠管理システムを導入する5つのメリットを以下で詳しく紹介します。
集計業務を効率化できる
勤怠管理システムを導入すれば、出退勤時間や残業時間、有給休暇の取得状況を自動集計できるため、手作業での計算ミスや転記ミスを防いで効率化できます。給与計算システムと連携すれば、残業代や控除の計算も自動化され、処理の正確性が向上します。
また、CSVやPDF形式で勤怠データを出力できるため、給与計算システムや人事評価システムと簡単に連携が可能です。雇用形態や勤務体系ごとに異なる計算方法にも対応でき、企業ごとの運用に合わせた設定ができます。
不正打刻や改ざんを防止できる
タイムカードは代理打刻やあとからの手書き修正が可能なため、不正が起こるリスクがあります。一方、勤怠管理システムでは、ICカードや生体認証(指紋・顔認証)を活用することで、本人以外の打刻を防止できます。
打刻データの修正は上長の承認が必要となり、修正履歴がすべてシステムに記録されるため、勤怠データの信頼性が向上します。企業のコンプライアンス強化にもつながるメリットです。
多様な働き方に対応できる
テレワークやフレックスタイム制、直行直帰など、柔軟な働き方を導入している企業にとって、タイムカードの管理は非効率になりがちです。
勤怠管理システムなら、スマートフォンやPCを使ってどこからでも打刻できるため、出社しなくても正確な勤務時間の記録が可能です。GPS機能を搭載したシステムなら、外出先や出張先からの打刻も正確に管理できるため、労務管理の透明性が向上します。
One人事[勤怠]は、多様な働き方の勤怠管理をサポートする勤怠管理システムです。シンプルな操作画面で使いやすく、タイムカードから初めてシステムに移行する企業にも定着しやすくなっております。
→One人事[勤怠]もご紹介|「One人事」総合サービス資料のダウンロードはこちら

コストを削減できる
タイムカードを廃止することで、用紙代やインク代、タイムレコーダーのメンテナンス費用が不要になります。手作業による勤怠集計が不要になるため、労務担当者の作業時間が短縮され、人件費の削減にもつながります。
初期導入費用は発生するものの、長期的に見れば大幅なコスト削減が期待できるでしょう。勤怠管理システムのなかには、給与計算やシフト管理などの機能を備えたものもあり、一元化できれば複数のツールを契約する必要がなくなり、システム全体のコストも抑えられます。
法律にのっとった勤怠管理ができる
勤怠管理システムは、最新の法改正に自動で対応するため、専門知識がなくても適切な労務管理が可能です。
たとえば、残業時間の上限規制や有給休暇の取得状況を自動でチェックし、法定を超えそうな場合にはアラートを出す機能を備えたシステムもあります。また、労働基準法に基づき、企業は勤怠データを一定期間保管する義務がありますが、クラウド上でデータ管理ができるため、長期間の保管も容易です。

タイムカードを廃止してシステム導入をするデメリット
タイムカードの廃止には多くのメリットがある一方で、考慮したい課題もあります。システム導入時の費用負担から運用時のトラブル対応まで、事前に把握しておきたい2つのポイントを紹介します。
導入時に費用や設計工数がかかる
タイムカードを廃止し、システムを導入するには、初期費用や月額費用が発生するケースが多い点がデメリットです。企業の規模や必要な機能によってコストが変わります。無料のシステムもありますが、機能が制限され、就業規則やシフト制に柔軟に対応できません。
また、従業員に対してシステムの使い方を周知し、運用ルールを策定する工数もかかります。タイムカードのようなシンプルな打刻方式からシステム管理へ移行する場合、従業員の慣れや設定調整に時間がかかるため、導入計画を立てたほうがスムーズに移行できるでしょう。
トラブルが発生する可能性がある
勤怠管理システムはインターネット環境に依存するため、ネットワークのトラブルが発生すると、一時的に打刻できなくなります。クラウド型ではとくに、通信環境の整備が不十分だと、アクセスが遅くなったり、打刻の反映に時間がかかったりします。
生体認証では認識エラーで打刻ができないケースや、ICカード・交通系カードを用いた打刻ではカード忘れや紛失のリスクも考えられます。
導入前に「オフラインでも利用できるか」「トラブル時のバックアップ手段があるか」を確認し、サポート体制が整っているかを確認したうえで、タイムカードの廃止を決定するとよいでしょう。
One人事[勤怠]は、運用開始前から定着支援まで、伴走型でシステムの活用を支援している勤怠管理システムです。初めての導入もまずはお気軽にご相談ください。
→One人事[勤怠]もご紹介|「One人事」総合サービス資料のダウンロードはこちら

タイムカード廃止時のシステム検討ポイント
タイムカードから勤怠管理システムへの移行を検討する際は、複数の視点から比較検討が必要です。自社の規模や業務形態に合わせて、以下の7つのポイントを確認しましょう。
- システム形態が自社に合っているか
- 自社の就業規則に対応できるか
- 法改正に対応しているか
- 従業員が使いやすいか
- セキュリティ対策やサポート体制は十分か
- 費用対効果が合うか
- ほかのシステムと連携できるか
システム形態が自社に合っているか
勤怠管理システムには「オンプレミス型」と「クラウド型」があり、それぞれ特徴が異なります。どちらが自社に適しているか、以下の表を参考に選びましょう。
| 項目 | オンプレミス型 | クラウド型 |
|---|---|---|
| 初期費用 | 高額 | 低額 |
| カスタマイズ性 | 高い | 限定的 |
| 導入期間 | 数か月以上 | 即日~数週間 |
| セキュリティ | 自社でカスタマイズ可能 | ベンダー依存 |
| 運用保守 | 自社で対応 | ベンダーが対応 |
社内にシステム運用の専門部署がある場合や、高度なセキュリティ対策が必要な場合はオンプレミスが適しています。できるだけ早く、低コストで導入したい企業はクラウド型がおすすめです。
自社の就業規則に対応できるか
企業ごとに就業規則は異なり、労働時間の管理方法もそれぞれ独自のルールがある場合があります。また、フレックスタイム制や変形労働時間制、シフト制を導入している場合、システムが勤務形態に対応できるか確認する必要があります。
【比較ポイントの例】
- フレックスタイム制や裁量労働制に適応できるか
- シフト作成・管理機能があるか
- 休暇管理や残業アラート機能があるか
法改正に対応しているか
労働基準法をはじめとする労働関連の法律は頻繁に改正されています。 例を挙げると、2019年の働き方改革関連法では「時間外労働の上限規制」や「有給休暇の取得義務化」が強化されました。 2024年には、建設業・運送業などにおける時間外労働の上限規制が適用されています。
担当者の手を煩わせることなく、法改正に対応できるかを確認し、将来的なリスクを軽減しましょう。

従業員が使いやすいか
高機能なシステムでも、従業員が使いにくく勤怠管理の精度が下がり、タイムカードを廃止する意味がありません。打刻方法が複雑すぎると、打刻漏れやミスが多く、管理者負担が増加します。PCやスマートフォンを利用したWeb打刻、ICカードや生体認証など、従業員にとっての負担の少ない方法を選ぶことがポイントです。また、操作画面が直感的かどうか、導入前にデモ版を試して確認しましょう。
セキュリティ対策やサポート体制は十分か
従業員の勤務データや個人情報が保存される勤怠管理システムには、強固なセキュリティ対策が求められます。
タイムカードを廃止してクラウド型を選択する場合、データの暗号化やアクセス制御、二段階認証などのセキュリティ機能が確実にあるか確認することが重要です。システムトラブルが発生した際に、迅速に対応できるサポート体制が整っているかもチェックしましょう。
費用対効果が合うか
タイムカードに代わるシステムの費用は、初期費用だけでなく月額利用料や保守費用を含めた総コストを考慮しなければなりません。
従業員数や利用期間によっても選択肢が変わってきます。大規模な企業では、カスタマイズしないと運用が回らない場合もあります。
▼コストと導入効果が見合うか、事前にシミュレーションしておくとよいでしょう。
ほかのシステムと連携できるか
勤怠管理システムが、給与計算や人事管理システムと連携できることを確認することも重要です。連携が可能であれば、勤怠データを自動で給与計算に反映でき、作業を簡略化できます。人事管理システムと連携できれば、従業員の働き方に関する分析や人材配置の最適化にも利用できるため、活用の幅が広がるでしょう。
タイムカードを廃止したとしても、複数のシステムで運用していると、結果的に業務負荷がかかってしまうため注意が必要です。
タイムカードを廃止し、勤怠管理システムで集計を効率化
タイムカードの廃止は、企業の働き方改革を加速させる大きな一歩です。法改正でより一層、企業には従業員の労働時間を正確に把握・管理する責任が生まれました。
タイムカードの管理を続けると、不正打刻のリスクや集計作業の煩雑さなどの課題に対処する必要があります。廃止を検討しているなら、勤怠管理システムの導入を検討してみてはいかがでしょうか。管理の効率化を実現し、テレワークやフレックスタイム制などの柔軟な働き方にも対応しやすい運用が可能です。
人事・労務担当者の業務負担を軽減し、戦略的な人材管理を実現するためにも、タイムカードの廃止を前向きに検討してみましょう。
正確な労働時間の管理に|One人事[勤怠]
One人事[勤怠]は、煩雑な労働時間の管理をシンプルにする勤怠管理システムです。
- 打刻漏れ・集計ミスが多い
- 勤怠管理がアナログで煩雑になっている
- 法改正への対応に不安がある
というお悩みを持つ企業をご支援しております。
One人事[給与]と連携すれば、給与計算に自動で紐づけられるため、より速くより正確に業務を進められるでしょう。また、有休の付与・失効アラート機能や、労働基準法などの改正にも対応しております。 One人事[勤怠]の費用や操作性については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門スタッフが課題をていねいにヒアリングしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、勤怠管理の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。勤怠管理をラクにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |