人事と労務の業務の違いとは?おすすめの資格や効率化をはかる方法を徹底解説

人事と労務の業務は一見似ているようで、じつは大きな違いがあるのをご存知ですか。
本記事では、人事と労務の違いを整理し、それぞれの業務範囲や役割を明確に解説します。さらに、実務で役立つ資格や、業務を効率化するための方法も紹介します。
「自分の仕事の全体像を把握したい」「もっと効率よく進めたい」という方は、ぜひお役立てください。

 目次[表示]
目次[表示]
人事労務とは?
人事労務とは、企業における人材に関する管理業務全般を指す言葉です。
人事と労務はどちらも従業員を対象とした業務であり、目的は共通しています。どちらも、従業員が安心して働ける環境を整え、組織全体の生産性向上に貢献することが役割です。
人事と労務、そして関連する総務との違いは以下のとおりです。
| 人事と労務の違い | 直接的か、間接的か |
| 労務と総務の違い | 従業員を見るか、会社全体を見るか |
人事と労務の違い
人事と労務は、どちらも組織の人にかかわる仕事ですが、対象とする範囲や業務の性質は少し異なります。
- 人事=社員一人ひとりと直接的にかかわりを持ち、成長や活躍を促すため個別に対応する
- 労務=制度や労働環境を整備する。社員へのかかわりは間接的
たとえば、新しい人材を採用し、育成し、適切な部署に配置するのは人事部門の仕事です。従業員のスキル向上やキャリア開発のための研修プログラムを考案する仕事も含まれます。
一方で労務部門は、バックオフィスとして人が働く環境を整えます。勤怠管理や給与計算、福利厚生の整備、就業規則の作成や労働安全衛生を管理する仕事です。労働基準法をはじめとする労働関連法令を遵守し、コンプライアンスを徹底することで、法的リスクを防ぐ役割も担っています。
人事が「攻めの人材管理」なら、労務は「守りの人材管理」といえるかもしれません。
労務と総務の違い
労務と総務も、混同されやすい業務領域です。しかし、それぞれの対象範囲と役割に違いがあります。
- 労務=従業員の働く環境の整備
- 総務=会社全体の事務・管理業務
労務は、従業員が安全かつ快適に働けるよう、労働環境や制度を整える役割を担います。
一方で、総務は「会社全体がうまくまわるようにする」ことが役割です。対象は従業員個人ではなく、組織運営そのものといえます。総務は「何でも屋」といわれることもありますが、従業員と経営陣をつなぐ、全社の調整役を担うポジションです。
中小企業では、労務と総務を1人の担当者が兼務することも少なくありません。そのため、自分の業務範囲があいまいな方もいるのではないでしょうか。迷う場面があるなら、一度自社の業務を棚卸ししてみてもよいでしょう。

人事業務とは
人事業務とは、組織の目標達成に向けて「人材の力をどう引き出すか」を考える仕事を指します。目的は、従業員の能力や意欲を引き出し、組織全体のパフォーマンスを高めることです。
近年は、人材不足や働き方改革、グローバル化への対応が求められるなかで、人事業務は単なる管理から戦略的な人材マネジメントへと移行しています。
主な人事業務内容
人事業務は多岐にわたり、大きく分けると以下の5つの業務に分かれています。人事の主な業務内容は以下のとおりです。
- 人材採用
- 人材育成
- 人事配置
- 人事制度の策定
- 職場環境の改善
1. 人材採用
人材採用は、組織に必要な人材を確保するための業務です。採用計画の立案にはじまり求人票の作成や面接、内定者フォローまでを担当します。近年はSNSを活用しソーシャルリクルーティングやリファラル採用など手法が多様化しています。
企業の文化に合う人材像を明確にしたうえで採用基準を設定し、ミスマッチを防ぐことが重要です。採用後の定着・活躍を見据えて進めなければなりません。
2. 人材育成
人材育成は、従業員のスキルや能力を高め、組織力を強化する取り組みです。新入社員研修や階層別研修、OJTや自己啓発支援などが含まれます。
最近ではキャリア開発支援やメンター制度を取り入れる企業も増えています。人材育成の効果を高めるには、一人ひとりのスキルを可視化し、パーソナライズ化した育成プランの作成が欠かせません。中長期的な視点で研修の効果を測定し、PDCAをまわすことが重要です。
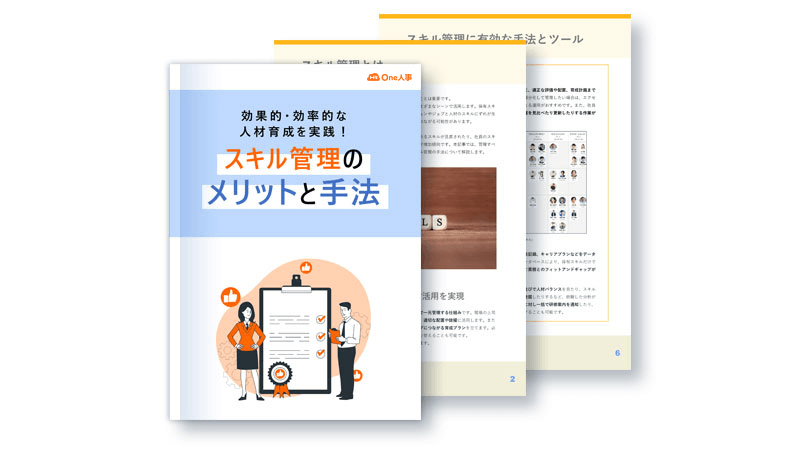
3. 人材配置
人材配置は、人材を適材適所に配置し、組織内でバランスをとりながら、全体のパフォーマンスを最大化する業務です。
個人の適性や希望を考慮しながら、部署間の異動や昇進、降格を実施します。組織の再編や新規事業の立ち上げにともなう人員配置の検討も重要な役割です。
人事異動では本人の意向を尊重しつつ、自律的なキャリア形成も視野に入れることがポイントです。人材配置は一人ひとりのモチベーションや定着率に影響します。
4. 人事制度の策定
人事制度の策定は、評価・報酬・昇進といった各種制度を整える業務です。制度は戦略や文化に合った設計が必要で、公平性や透明性を確保し、納得度の高いものでなければなりません。制度の導入後も定期的に検証し、見直す必要があります。
最近の評価制度では、能力や成果に加えて、行動やバリューも含めて多面的な評価を取り入れる企業も増えています。
5. 職場環境の改善
職場環境の改善は、従業員が安心して快適に働ける環境を整える業務です。ITツールの導入などハード面の整備に加え、ハラスメント防止やメンタルヘルス支援、多様な働き方への対応も含まれます。いずれにしても従業員の声に耳を傾け、現場の課題を把握することが出発点となります。良好な職場環境は従業員の満足度や生産性にも影響するため、継続的な改善活動が必要です。

人事業務に役立つ資格・検定
人事業務の専門性を高め、キャリアの幅を広げるには資格取得も一つの方法です。ここでは、実務で活かしやすい代表的な人事に関する資格を3つ紹介します。
- キャリアコンサルタント
- コーチング検定
- ビジネス・キャリア検定
キャリアコンサルタント
キャリアコンサルタントは、個人の適性や希望に応じてキャリア支援をする国家資格です。個人の適性や経験、希望を踏まえてキャリアパスの選択や能力開発について助言します。
人事部門でこの資格を持つと、従業員のキャリア面談に活かせるでしょう。キャリアコンサルタントの資格取得には、学科試験と実技試験があり、一定の実務経験や養成講座の受講が必要です。
参考:『キャリアコンサルティング・キャリアコンサルタント』厚生労働省
参考:『CC協議会 キャリアコンサルタント試験(国家資格)』厚生労働省
コーチング検定
コーチング検定は、対話を通じて自発的な行動を引き出すスキルを証明する民間資格です。国際コーチ連盟(ICF)や日本コーチ協会(JCA)など複数の団体が認定しており、試験内容やレベルは団体によって異なります。
人事業務では、人材育成や1on1ミーティングで役立つでしょう。理論と実践を学び、認定試験への合格が必要です。
参考:『ICF Japan Chapter』一般社団法人国際コーチング連盟
参考:『JCA日本コーチ協会』
ビジネス・キャリア検定
ビジネス・キャリア検定は、人事や労務の実務知識を体系的に学べる公的資格です。厚生労働省が創設し、中央職業能力開発協会(JAVADA)が運営しています。
2級・3級では、「人事・人材開発」「労務管理」の2つの区分にわかれ、実務経験に応じた知識とスキルがマークシート方式で問われます。
1級では、2級レベルの専門知識と部長相当職として必要な能力が論述式で問われます。
人事・労務管理の専門知識を体系的に習得し、実務に活かしたい担当者に適しているでしょう。
労務業務とは
労務業務とは従業員が安心して働けるように、法令を遵守しながら、就業環境や制度を整える業務です。勤怠管理、給与計算や社会保険処理、安全衛生の管理などを通じて、従業員を支えます。
主な労務業務内容
労務業務も人事業務と同様に多岐にわたる領域を含みます。主な労務の業務内容は以下のとおりです。
- 就業規則の作成と管理
- 勤怠管理(労働時間・残業・休暇・休憩の管理)
- 給与計算(年末調整)
- 労務トラブル発生時の対応
- 安全・衛生管管理
就業規則の作成と管理
就業規則の作成と管理は、労務業務の基本となる大切な仕事です。就業規則は法律に基づいて作られるもので、会社の都合だけで勝手に決めることはできません。就業規則に記載する内容には以下のような項目があります。
- 始業・終業時刻や休憩時間
- 休日・休暇
- 賃金
- 退職のルール
- 災害時の対応
- 表彰や処分の基準
- 制服の貸与
法律の改正や会社方針の変更があれば、就業規則も定期的に見直して更新する必要があります。変更内容は書面やメール、社内掲示などで従業員にきちんと周知しましょう。とくに給料の減額など不利益になる変更をする場合は、必ず労働組合などと交渉し、一方的な変更とならないよう注意が必要です。
勤怠管理
勤怠管理とは、従業員の労働時間や休暇の取得状況を正確に把握・記録する業務です。いつ出勤して何時に退勤したか、残業や有休の取得状況などを勤怠管理システムやタイムカードを活用して日々記録していきます。
労働基準法では、1日8時間・週40時間を超える労働には割増賃金の支払いが義務づけられており、勤怠データの正確性は法令遵守において欠かせません。
働き方改革の流れもあり、勤怠管理は企業にとって欠かせない業務となっています。
給与計算
給与計算とは、従業員の働きに対して支払う金額を正しく計算し、実際に支給するための業務です。単に基本給を計算するだけでなく、時間外手当や通勤手当、家族手当などの各種手当も含めて金額を算出します。そこから社会保険料や所得税、住民税などの控除もしなければなりません。
給与計算には、従業員ごとの勤務時間や役職、どの手当が対象になるかを正確に把握する必要があります。そのうえで、会社の給与規程や雇用契約に基づいて給与や賞与を算出し、必要な控除も反映させます。
金額に誤りがあると信頼を損なうため、ミスが許されない重要な業務です。
労務トラブル発生時の対応
労務トラブル発生時の対応とは、トラブルの事実確認を行い、就業規則や過去の事例をもとに適切な対応をとる一連の労務業務です。
パワハラや賃金未払いといった労務トラブルは、当事者だけでなく職場全体にも悪影響を与えるため、慎重な対応が求められます。
必要に応じて、社労士や弁護士に意見を仰ぐことも重要です。早期に適切な対応をとることで、従業員の信頼を得られ、エンゲージメントの向上や離職防止にも効果が期待できます。
安全・衛生管理
安全・衛生管理とは、従業員が心身ともに健康で安全に働ける職場環境を整えるための労務業務です。労働安全衛生法により、事業者は従業員の安全と健康を守るための措置を講じなければなりません。
労務担当者は法律に基づき、例として以下のような実務を主導します。
- 年1回以上の定期健康診断の実施・手配
- 健診結果の管理
- 産業医との面談調整
- ストレスチェックの年1回実施・管理(従業員50人以上の事業場で義務)
また、建設業や運送業のように安全・衛生に関する規制が厳しい業種では、より厳格な対応が求められています。
さらに、ハラスメント防止も精神的な安全を守るうえで重要です。パワハラ・セクハラに加え、マタハラやモラハラなど多様なハラスメントに備え、相談窓口の設置や再発防止策の整備も労務における安全衛生管理業務の一つです。
労務業務に役立つ資格
労務分野で専門性を高め、実務に役立てるためには資格取得も有用です。ここでは、実務で活かせる代表的な労務に関する資格を4つ紹介します。
- 社会保険労務士
- 労務管理士
- メンタルヘルス・マネジメント検定
- 衛生管理者
社会保険労務士
社会保険労務士(社労士)は、労働や社会保険に関する法制度の専門家で、厚生労働省所管の国家資格です。企業の人事労務管理を支援し、労働時間や賃金、就業規則の整備などに法的な観点から助言をします。また、年金や医療保険に関する相談にも対応しています。
行政機関に提出する書類の作成や手続き代行は社労士の独占業務とされており、企業実務において重要です。独立を目指す人にも有用な資格といえるでしょう。
労務管理士
労務管理士は、労働基準法などの労働関連法を専門的に学び、企業内の労働環境改善や人事・労務管理を支援する民間資格です。日本人材育成協会が認定しており、採用・配置・教育・労働時間管理・退職まで、就業全体の管理に携わります。資格の取得により、法令を遵守しつつ、従業員対応を適切に行う知識・スキルがあると評価されます。ただし、社会保険労務士の独占業務である手続き代行や帳簿作成はできないため、注意が必要です。
メンタルヘルス・マネジメント検定
メンタルヘルス・マネジメント検定は、職場における心の健康管理に関する知識や対応力を問う公的資格です。メンタルヘルス不調の予防や早期対応を目的に、役割別に3つのコースが用意されています。Ⅰ種(マスターコース)は経営幹部や人事労務担当者向け、Ⅱ種(ラインケアコース)は管理職向け、Ⅲ種(セルフケアコース)は一般社員向けで、それぞれに応じた知識を学べます。従業員のメンタルヘルス対策を推進し、健康で活力ある職場づくりに貢献するための資格です。
衛生管理者
衛生管理者は、職場の安全衛生を確保し、労働災害や健康障害を未然に防ぐ役割を担う国家資格です。労働安全衛生法に基づき、常時50人以上の労働者を使用する事業場では、専任の衛生管理者を選任することが義務づけられています。
衛生管理者には「第一種」と「第二種」があり、第一種はすべての業種に対応でき、有害業務にかかわる職場でも衛生管理者として働くことが可能です。一方、第二種は比較的リスクの低い情報通信業、金融業などに限って従事できます。
衛生管理者は、職場の安全衛生体制を技術的に支える重要な専門職です。
参考:『第一種・第二種衛生管理者のご紹介』公益財団法人安全衛生技術試験協会
人事労務業務を効率化する方法
人事労務業務は、採用から退職までの人材管理、勤怠・給与計算、法令対応など、幅広い業務を含みます。企業運営に不可欠である一方で、業務量が多く、担当者の負担も大きくなりがちです。そのため、効率化は避けて通れない課題となっています。
人事と労務の無駄を省いて効率化するには、次のような方法が効果的です。
- 効率化すべき業務を検討する
- ペーパーレス化を推進する
- アウトソーシングを活用する
- ITツール・システムを導入する
効率化すべき業務を検討する
人事労務業務を効率化するには、まず現状の業務を洗い出し、誰がどの作業をどれくらいの時間で行っているかを可視化することが大切です。そのうえで、属人化している業務や繰り返し発生する定型業務を中心に、マニュアル化やシステム化の優先順位を検討します。
たとえば、毎月発生する給与計算は、効率化の効果が大きい分野です。業務フローを見直して無駄を省くことで、本来注力すべき戦略的な業務に時間を使えるようになるでしょう。
ペーパーレス化を推進する
人事労務では履歴書や雇用契約書、給与明細など多くの書類が存在しますが、紙のままでは検索や共有に時間がかかり、保管や廃棄にも手間がかかります。
ペーパーレス化を実現すれば、必要な情報に素早くアクセスでき、作業効率が大きく向上します。たとえば、勤怠管理システムの導入や社会保険手続きのオンライン化は欠かせません。
紙をなくしたほうが、リモートワークにも柔軟に対応できるため、働き方改革の観点からも求められています。
アウトソーシングを活用する
人事労務業務の一部をアウトソーシングすることで、業務効率化をはかれます。給与計算や社会保険手続きなど、専門性が高く時間もかかる業務を外部に委託することで、社内リソースをコア業務に集中させられるでしょう。制度改正への対応や規程の見直しといった分野でも、専門知識を持つ外部の力を活かせます。
一方で、自社にノウハウが蓄積されにくい、個人情報管理が不安、柔軟な対応が難しいといったデメリットもあります。費用対効果を見極めたうえで委託範囲を決めることが大切です。
ITツール・システムを導入する
人事労務業務の効率化には、業務内容にあったITツールやシステムの導入がおすすめです。
勤怠管理や給与計算、社会保険手続きなど、手作業の多い業務を自動化することで、作業時間を大幅に削減できます。
たとえば、労務管理システムを導入すれば、入退社手続きや社会保険・税の処理をWeb上で半自動化でき、ミスの防止と業務の標準化につながります。導入にあたっては、費用や既存システムとの連携、サポート体制を確認し、自社の業務に適したツールを選定することが重要です。
→人事も労務もワンストップで効率化「One人事」の資料を無料ダウンロード

人事労務業務を効率的に運用するためにはシステム導入
人事労務業務は企業運営を支える重要な領域です。しかし、業務の多様性と煩雑さから担当者の負担が大きく、効率化が課題の一つという企業は多いのではないでしょうか。
効率化において欠かせないのは、システムの導入です。
人事管理や労務管理における定型業務をシステム化することで、手作業によるミスを減らし、効率化が実現します。
クラウド型の人事労務システムであれば、テレワークなど多様な働き方への対応が可能です。
人事労務システムの導入・入れ替えを検討しているなら、まず業務の棚卸しを行い、優先順位を決めて、段階的に見直すのがおすすめです。
人事労務の情報管理や手続きといった業務はシステムに任せ、より戦略的な業務に注力できるようにしましょう。
人事労務管理を効率化するシステム「One人事」
「One人事」は、社内に分散する人事と労務の情報を集約して管理し、業務の効率化を助ける人事労務システムです。
初期費用や操作性については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門のスタッフが貴社の課題をお聞きしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、人事労務の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードしていただけます。人事労務をラクにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |
