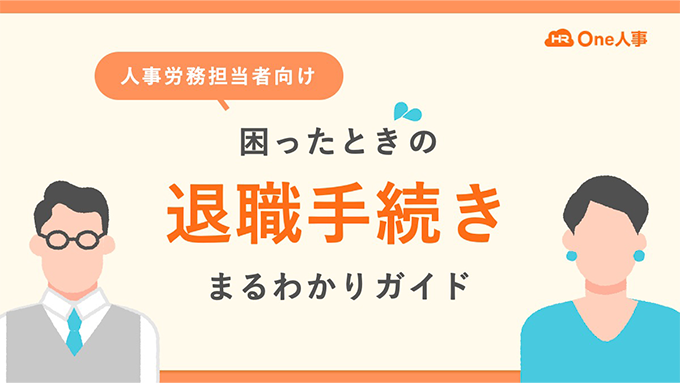離職票やその他書類の保管期間はいつまで? 書類を保管する流れや方法、破棄までを徹底解説

退職者に発行した離職票は、いつまで保管すればよいのでしょうか。離職票は、退職した従業員が失業給付を受けるとき必要になる公的な文書です。企業は、従業員や退職者にかかわる書類を期間を守って保管し、時期を見て適切に破棄しなければなりません。離職票をはじめとする人事書類には、法律で明示された保管期間があります。
本記事では、離職票をはじめとする雇用保険にかかわる書類や、労災保険にかかわる書類などの保管期間をご紹介します。保管や破棄の適切な方法についても触れているため、人事労務担当者はぜひお役立てください。
 目次
目次
離職票の保管期間はいつまで?
離職票はそもそも従業員、つまり雇用保険の被保険者に関する書類に該当します。被保険者が雇用保険の給付申請をする際に提出するものです。雇用保険に関する書類の保管期間は、2年または4年と定められています。根拠となる条文は、以下のとおりです。
事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業又は能力開発事業に関する書類及び徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。)をその完結の日から二年間(被保険者に関する書類にあつては、四年間)保管しなければならない。
引用:『雇用保険法施行規則』e-Gov法令検索
離職票と似ている書類として挙げられる離職証明書も、同様に4年間保管しなければなりません。
離職票の再発行の期限はいつまで?
離職票には発行期限がなく、再発行の期限についての法定規則はありません。
しかし、会社が離職票を保管する期間は4年間と定められているため、再発行の申請期限は事実上「4年」が目安とされることがあります。ただし、離職票の発行は会社の義務です。原則的には、退職者から請求があれば4年目以降も対応する必要があります。
なお、退職証明書の発行義務は「退職から2年間」と明確に定められています。もちろん2年以降も発行自体は可能ですが「義務が課されるのは退職から2年間」とおぼえておきましょう。
退職者の書類を保管する理由は?
退職者の書類を一定期間保管しておくのは、以下の3つの理由からです。
- 法律の側面からの理由
- 訴訟対策の側面からの理由
- 個人情報保護の側面からの理由
それぞれの理由について、詳しく解説します。
法律の側面からの理由
退職者の書類を保管しておく理由として「法律に定められているから」というのが挙げられます。従業員および退職者関連の書類の取り扱いについては、各種法律を根拠とした厳しい決まりが設けられています。
もちろん、書類の保管についても例外ではありません。労働基準法や労働安全衛生法、雇用保険法、消費税法など、さまざまな法律で法定保存期間が定められています。
たとえば、労働基準法によると、労働関係に関する重要書類の保管期間は5年間です。ただし、経過措置により当分の間は、3年間の保存で足りるとされています。
使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入れ、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を五年間保存しなければならない。
引用:『労働基準法』 e-Gov法令検索
訴訟対策の側面からの理由
従業員の退職時には、さまざまなトラブルが発生することがあります。双方が納得する着地点が見つけられない場合は、訴訟に発展する可能性も捨てきれません。
| 退職時のトラブル例 | |
|---|---|
| 会社側が 訴える場合 | ・従業員が引き継ぎをせず、突然やめてしまった ・退職前にほかの従業員に対して引き抜き行為を行っていた ・従業員がトラブルを起こしたあと、そのまま行方をくらましてしまった |
| 従業員側が 訴える場合 | ・離職票の発行を延滞されたせいで、失業手当の受給が遅れてしまった |
※訴えが認められるかどうかは、裁判所の判断によります。
万が一、訴訟に発展した場合、「証拠がない」という状況は避けたいものです。離職票や退職証明書などは退職時のトラブルにおける重大な証拠となりえるので、できる限り長期間保管するのが望ましいでしょう。
しかし、書類を長期間保管するためには、それだけ多くの保管スペースや人的リソースが必要です。実際には、債務不履行による損害賠償請求の時効である「10年」を目安に、保管期間を超えた書類は処分するケースが大半です。
個人情報保護の側面からの理由
人事労務部門で扱う書類には、退職者の氏名・住所やマイナンバーなど個人を特定する重大な情報が数多く記載されています。個人情報保護の観点から考えても、会社は退職者の書類を適切に管理しなければなりません。
しかし、会社が書類を保有している期間が長ければ長いほど、個人情報の流失・紛失のリスクが高まるという側面もあります。そのため、退職者の情報が記載された書類はしかるべきタイミングで処分すべきです。
保管期間を定めることは、すなわち処分するタイミングを定めることでもあります。「保管すべき書類」と「破棄すべき書類」の線引きを明確にし、従業員や退職者の個人情報を適切に管理しましょう。
退職者に関する書類の保管期間はいつまで?
続いて、退職者に関する書類の保管期間を種類別に解説します。
雇用保険に関する書類の保管期間
雇用保険法施行規則第143条で、雇用保険に関する書類の保管期間について定められています。
事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類はその完結の日から二年間(被保険者に関する書類にあつては、四年間)保管しなければならない。
引用:『雇用保険法施行規則』e-Gov法令検索
つまり、雇用保険に関する書類は、従業員の退職・解雇日や、死亡した日から2年間は保管する義務があるのです。なお、同施行規則では、被保険者の書類については4年間の保管が必要と定められています。
| 保管期間4年の書類例 |
|---|
| ・資格取得等確認通知書 ・離職票離職証明書 ・休業開始時賃金月額証明書 など |
労働保険に関する書類の保管期間
労働保険に関する書類の保管期間は5年間と、労働基準法第109条に定められています。労働保険にかかわる書類で代表的なものは、労働者名簿や賃金台帳でしょう。ほかにも「解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する書類」と、同法律では明文化されています。
ただし、書類ごとに起算日が異なる点に注意しましょう。主な書類の起算日は、以下のとおりです。
| 雇用契約書 | 退職・解雇・死亡から5年 |
|---|---|
| 出勤簿 | |
| 労働者名簿 | |
| タイムカード | 最後の記入日から5年 |
| 賃金台帳 |
また、当該記録にかかる賃金の支払期日が以下の期日より遅い場合には、当該支払期日が起算日となります。また、保存期間は5年とされていますが、経過措置により当分の間は3年間の保存で足りるとされています。
労働保険の徴収・納付に関する書類の保管期間
主な労働保険の徴収・納付に関する書類の保存期間は、完結の日から3年間です。労働保険の徴収・納付に関する書類とは具体的に、保険関係成立届や概算保険料申告書などを指し、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第72条に定められています。
これにより、労働保険の徴収・納付に関する書類である成立届や概算保険料申告書などは、3年間保管することが必要です。
参考:『労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則』e-Gov法令検索
労災保険に関する書類の保管期間
労災保険に関する書類として、療養補償給付たる療養の給付請求書などは、完結の日から3年間保管しなければなりません。これは、労働者災害補償保険法施行規則第51条に定められています。
社会保険に関する書類の保管期間
社会保険に関する書類の保管期間は「完結の日から2年間」とされています。つまり、企業は従業員の退職・解雇日や死亡した日から2年間は、保管する義務があるのです。これは健康保険法施行規則第34条や厚生年金保険法施行規則第28条に定められています。
参考:『健康保険法施行規則』e-Gov法令検索
参考:『厚生年金保険法施行規則』e-Gov法令検索
年末調整に関する書類の保管期間
年末調整に関する書類の保管期間は、提出期限の翌年1月10日の次の日から7年間保管する必要があると定められています。これは、所得税法施行規則第76条に定められた「給与所得者の源泉徴収に関する申告書の保存」を根拠としています。
書類を保管する流れ
従業員や退職者に関する書類は、以下の流れで保管するのが一般的です。
1.書類を分類する
まずは、書類を種類ごとに分けるところから始めましょう。雇用保険に関する書類、労災保険に関する書類というように、書類の種類ごとに仕分けして保管するとわかりやすいです。
さらに、賃金台帳なら賃金台帳、源泉徴収票なら源泉徴収票ごとにまとめたり、発行日順に整理したりすると、あとから探しやすくなります。
2.書類をフォルダやファイルに入れる
分類した書類は、フォルダやファイルに入れて収納しましょう。書類の種類ごとにファイルの色を変える、背表紙に書類名を記載しておくなど、ひと目で中身がわかるような工夫をしておくと便利です。
3.書類の保管場所を決定する
すべての書類をまとめたら、決められた保管場所に収納します。その際、適切な環境で保管することが重要です。紙は繊細で、紫外線や温度、湿度などの影響を受けやすい性質があります。5年、10年と保管しても劣化しないよう、直射日光や高温多湿を避けて保管場所を選びましょう。
4.取り出しやすいよう工夫して保管する
フォルダやファイルの背表紙が見えるように収納すると、書類を探しやすくなります。書類の種類や発行日順でまとめるのもおすすめです。また、その年の年末調整に必要な書類など、使用する予定があるものはすぐに取り出せる場所に保管するとよいでしょう。
反対に、長期間保管する書類や一定期間後に破棄する書類は、倉庫やトランクルームなどに保管するほうが無難です。書類はかさばりやすいので、すべての書類を会社に保管するとスペースが圧迫されてしまいます。
書類保管を効率化する方法
本記事でご紹介したような書類は、従業員の数が増えると膨大な量になります。書類を長期間保管する場所がない場合は、保管サービスなどを活用するのも手段の一つです。
保管サービスを利用する
法人向けの書類保管サービスなら、重要書類を安全に保管してもらえます。保管から破棄まで一貫して任せられるサービスも多く、書類の機密を保持したまま適切に処分が可能です。
保管サービスの多くはインターネット上から依頼でき、入出庫の手続きまでオフィスにいながら完結できます。個人情報が記載された重要な書類を保管するので、セキュリティ面も考慮してサービスを比較・検討しましょう。もちろん、立地や利便性も大切です。
クラウド上で書類を保管する
デジタル化した書類をクラウド管理すれば、保管スペースに悩まされる心配がありません。また、検索機能を使って目当ての書類を簡単に探せるため、社内共有もスムーズにできます。
人的・時間的コストの削減や、業務効率化にも役立つでしょう。なお、国税関連の書類については、電子帳簿保存法の要件を満たした書類のみクラウド管理が可能です。
参考:『電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律』e-Gov法令検索
レンタル収納スペースで保管する
紙の書類として保管する場合は、レンタル収納スペースを活用するのもよいでしょう。
レンタル収納スペースは、主に以下の3種類に分けられます。
- トランクルーム
- 倉庫
- コンテナ
なかでもおすすめなのが、トランクルームです。トランクルームとは、定額制で収納スペースを借りるサービスのこと。倉庫やコンテナと比べてセキュリティ性が高く、重要書類の保管に適しています。
期限切れの書類を破棄する方法
保管期限を過ぎた書類は、適切に破棄することが重要です。会社の重要情報や従業員の個人情報が漏えいしないよう、的確な処分方法を検討しましょう。
シュレッダーで破棄する
シュレッダーのメリットは、書類をその場ですぐに処分できる点です。数枚の書類であれば手間もかからず、手軽かつスピーディに書類を処分できます。
また、担当者がみずから裁断するため「確実に処分できた」という安心感を得られるでしょう。ただし、シュレッダーは一度に大量の書類を処分したいときには不向きです。
焼却で処分する
紙を燃やして処分する「焼却処理」は、重要書類を確実に抹消できるというメリットがあります。箱詰めした書類を業者に渡すだけでよいので、大量の書類の処分も容易です。
また紙の書類だけでなく、CD-ROMやUSBなどのデータが入った媒体も同時に処理できます。ただし、焼却処分によりCO2が排出されるため、環境への悪影響が懸念されます。
溶解で処理する
溶解処理は、環境への影響に配慮した廃棄方法です。書類を水と混ぜながら粉砕し、液状化させることで処分します。方式によっては、ファイルやフォルダから書類を抜き取ったり、ホチキスを外したりする必要もありません。
担当者の手間もかからず、環境にも優しいとあって、近年注目を集めている処分方法です。ただし、溶解処理には専用設備が必要です。専門業者に処分を委託する必要があるため「自社内で完結させたい」というケースには不向きといえるでしょう。
離職票やその他書類は、法定保存期間を守って適切に保管しましょう
離職票や離職証明書などの書類には、各種法律によって保管期間が定められています。法定保存期間は書類の種類によって異なるため、それぞれどの規則に該当するか把握しておきましょう。
従業員や退職者の個人情報が含まれるため、保管期間中は適切に管理することが重要です。今回ご紹介した内容を参考に、重要書類の保管方法を見直してみてください。
重要書類の管理・破棄など、人事労務の業務負担を軽減するなら「One人事」がおすすめです。
「One人事」は、人事労務をワンストップで支えるクラウドサービスです。従業員の入退社手続きや年末調整の効率化を実現し、担当者の負担を軽減することで、人材活用の基盤をつくります。気になる費用や操作性は、お気軽にご相談いただけますので、まずは当サイトよりお問い合わせください。
当サイトでは、サービス紹介資料はもちろん、無料のお役立ち資料をダウンロードいただけます。業務効率化のヒントに、こちらもお気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |