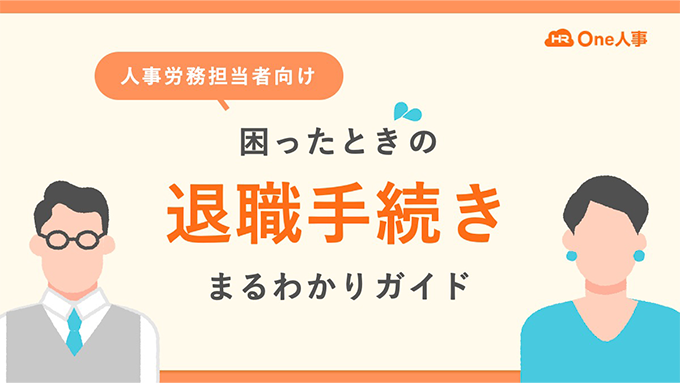退職勧奨による退職は会社都合か自己都合か? 離職票手続きや注意点も解説

退職勧奨による退職が「会社都合」か「自己都合」か、疑問に感じていませんか。会社都合退職と自己都合退職では、離職票の記載内容や退職後の保険給付が大きく異なるため、担当者として正確に理解しておかなければなりません。
本記事では、退職勧奨が会社都合か自己都合か判断する基準と、離職票を記載する際の注意点について解説します。退職後のトラブルを防ぐためにも参考にしてください。
 目次[表示]
目次[表示]
退職勧奨とは
退職勧奨とは、企業が従業員に自らの意思で退職を申し出るようすすめることです。
雇用契約を強制的に解消する解雇とは異なり、退職勧奨は従業員の意思で退職させる意味合いがあります。企業が強制するものではありません。あくまでも従業員の意思で退職を選択するため、法律による厳しい制限も受けません。
退職勧奨による退職は会社都合退職か自己都合退職か
退職勧奨によって従業員を退職させる場合、基本的には会社都合として扱われます。しかし退職勧奨をした結果、別の理由で自己都合退職として扱われるケースも考えられます。
自社の状況がどちらに当てはまるのか確認してみましょう。
| 会社都合になる場合 | 自己都合になる場合 |
|---|---|
退職勧奨による退職 ※パート・アルバイト・試用期間中であっても同様 | 退職勧奨の結果、従業員の納得が得られず別の理由を適用する |
退職勧奨による退職は会社都合退職
退職勧奨による退職は、原則として会社都合退職として扱われます。退職勧奨は、企業が従業員に退職を働きかけているためです。
従業員本人が退職届を出したかどうかは関係なく、会社都合による退職とするのが基本です。
企業から退職勧奨を受けた場合は、雇用保険法施行規則第36条の厚生労働省令で定める理由に該当するため、特定受給資格者として扱われます。
アルバイトやパート、試用期間中も退職勧奨なら会社都合退職
退職勧奨によってアルバイトやパートなどの有期雇用契約を結ぶ従業員が退職した場合も、会社都合による退職として扱われます。
同様に試用期間中の従業員が、退職勧奨によって退職する場合も会社都合退職です。
雇用形態や雇用状態にかかわらず、基本的にすべての労働者が会社都合になると覚えておきましょう。
退職勧奨で自己都合退職になるケース
退職勧奨は基本的に会社都合の退職になりますが、従業員が企業の退職勧奨に納得しておらず拒否することもあります。その結果、退職勧奨以外によって退職することになった場合は、自己都合退職として扱いを変更するケースも考えられます。
会社都合退職と自己都合退職
会社都合退職とは、会社側の経営上の理由や業務上の必要性により、従業員が自主的な希望以外の退職を指します。 具体的には事業縮小や災害による事業の継続が困難な状況が挙げられます。
一方で自己都合退職とは、従業員みずからの希望による退職や、本人の責任によって懲戒解雇になった場合の退職を指します。
会社都合退職と自己都合退職では、退職後の雇用保険における基本手当の給付に違いがあります。
会社都合退職と自己都合退職の違い
会社都合による退職をした場合、雇用保険上では「特定受給資格者」となります。
一方、自己都合による退職をした従業員は、雇用保険上で原則として「一般受給離職者」です。特定受給資格者と一般受給離職者では、給付金が支給されるまでの期間や給付日数が異なり、特定受給資格者のほうがよりよい条件が設定されています。
失業保険給付の時期
失業保険給付の中で、基本手当の部分が、支給時期に影響します。基本手当とは、退職した従業員が失業期間中に受け取れる給付金です。
基本手当の受給は会社都合退職でも自己都合退職でも受け取れますが、給付される時期や日数が異なります。
基本手当が支給されるまでの待期期間は、原則として7日間です。ただし、自己都合退職の場合はさらに2か月間の給付制限を待たなければなりません。
会社都合退職の場合は、給付制限期間はないため、待機期間を過ぎれば、従業員はすぐに基本手当を受け取れます。
失業保険給付の支給期間
会社都合と自己都合では、失業保険給付における基本手当を受給できる期間にも違いがあります。
会社都合退職(特定受給資格者)は、90日から最大330日です。対して自己都合退職(一般受給離職者)は90日から最大150日と決められています。
被保険者によって基本手当を受給できる期間が異なると覚えておきましょう。
退職金の扱いが異なることもある
退職金も会社都合退職か自己都合退職かによって、扱いが異なる場合があります。
会社都合による退職では、退職金が全額支給されるのが一般的です。自己都合による退職では退職金が一部のみ支給されたり、支給されなかったり会社の判断に左右されることが多いでしょう。
具体的な支給要件は企業が定める就業規則に規定されています。詳しい対応や扱いは企業ごとに決められているため、まずは自社の規定を確認しましょう。
退職勧奨のメリット
退職勧奨における企業側のメリットには以下の2点が挙げられます。
- 解雇によるリスクを回避できる
- 人員削減を合理的に実施できる
企業が問題のある従業員や人員整理のための解雇を検討する場合、正当な理由が必要です。
解雇は簡単に認められるわけではありません。そのため、退職勧奨により退職を促進できれば、解雇無効のリスクを抑えられます。
会社都合退職のデメリット
会社都合退職における企業側のデメリットには以下の2点が挙げられます。
- 国による雇用関係の助成金受給を制限される
- 特定技能外国人の雇用を制限される
会社都合の退職者を出していると、国の助成金制度を一部受けられなくなったり、人材不足の解消をしにくくなったりする可能性があります。しかし、企業が会社都合の退職者を出したからといって、永久的に制限されるわけではありません。
退職勧奨で退職をした場合における離職票
退職勧奨による退職をした場合の離職票について解説します。
離職票とは、退職者が雇用保険の失業保険を受給するために提出する『雇用保険被保険者離職票』を指します。厳密には、離職票は企業の作成する離職証明書をもとに、ハローワークが交付します。
離職票の発行手続きについて
離職票の交付に必要な『離職証明書』をハローワークから入手します。企業は、従業員が退職した日の翌々日から10日以内に、必要事項を記載し、ハローワークに提出しなければなりません。ハローワークでは、離職証明書の記載内容から、会社都合退職か自己都合退職かを判断されます。
ハローワークで重視するのは離職理由
離職証明書のなかで、とくに重視されるのが「離職理由欄」です。
退職勧奨による退職の場合、「事業主からの働きかけによるもの」を選び、さらに「希望退職の募集又は退職勧奨」を選択しましょう。
退職勧奨と退職届
退職勧奨によって退職する場合も、退職届を提出してもらうか、退職合意書を作成します。
退職合意書とは、従業員と会社が退職に関する条件や手続きを解決したことを明文化、双方の署名や捺印を施したうえで、正式な合意を確認する書面です。
退職勧奨で退職について合意を得られても、証拠がない限りくつがえされる可能性もあるため用意されます。
企業は従業員に、できるだけすみやかに退職届を提出してもらうか、退職合意書を作成するように促しましょう。
退職届の書き方
退職届の書き方について解説します。従業員みずからの希望で退職する場合、退職届には以下の文章を記載するのが一般的です。
| 「一身上の都合により、退職致します」 |
退職勧奨による退職の場合は、あくまでも会社の意思による退職であるため、一身上の都合ではなく、会社の意思による退職であることを示します。具体的には、以下の文章にします。
| 「会社からの退職勧奨を受け入れるため、退職致します」 |
退職勧奨によって、企業が従業員に退職届を提出させる際は、書き方や文章についても説明しましょう。
退職合意書も作成
退職勧奨による従業員の退職では、退職合意書も作成するのがおすすめです。
退職合意書とは、退職について企業と従業員の両者が合意や納得していることを証明する書類です。退職合意書の記載内容として、具体的には以下のような点を記載しましょう。
- 退職に関する合意
- 退職条件
- 退職理由が会社都合退職であること
- 清算条項(支給日が到来していない賃金以外に、会社及び退職者に債権債務がないことの確認)
以上の点を書類に明記しておくことで、トラブル防止に役立ちます。
退職勧奨時に注意すべきこと
退職勧奨を進めるうえで避けるべき行為や、トラブルを防ぐための心構えを4つ紹介します。
- 退職を強制しない
- 従業員が拒否したら深追いしない
- 面談の記録を残す
- 退職勧奨時に会社都合であることを説明する
企業が慎重に対応しなければ、労働者から「不当な圧力」と受け止められ、労働トラブルに発展するリスクもあるためです。それぞれを確認し、円満に収めるため注意点をおさえましょう。
退職を強制しない
退職勧奨は、あくまでも企業が「退職をすすめる」ものであり、強制力はありません。退職勧奨を行う企業は、無理に退職させてはならないのです。
退職するかどうかを決めるのは、従業員自身です。企業の退職勧奨に納得したうえで退職の意思を固めてもらいます。企業が何度も面談を迫ったり、「退職勧奨に応じなければ懲戒解雇になる」とおどしたりすることは、退職の強要にあたり、許されません。
従業員が拒否したら深追いしない
退職勧奨に強制力はないため、対象従業員が明確に拒否したら、企業はそれ以上の持ちかけはしないようにします。企業があまりにしつこくすると、パワハラや退職強要などと判断されてしまうおそれがあります。退職勧奨を行う企業は、退職を強制するのではなく、「すすめる」にとどめましょう。
面談の記録を残す
退職勧奨では、面談の内容を記録して残しましょう。たとえば、面談で従業員が退職に応じる意思を示したことなどを記録します。退職勧奨による退職に合意したにもかかわらず、あとから考えが変わったり、退職を強要されたと主張されたりした場合、記録した内容を証拠にすることが可能です。
退職勧奨時に会社都合であることを説明する
退職勧奨をする際は、「会社都合の退職」として扱えることを、わかりやすく説明しましょう。会社都合の退職であれば、雇用保険における基本手当の受給で、条件が有利になり、従業員にとってメリットがあります。
対象従業員にとって有利な条件を提示することで、納得を得やすくなり、スムーズに話を進められる可能性もあります。

まとめ
退職勧奨は、原則として「会社都合の退職」として扱う重要な手続きです。企業には慎重かつ適切な対応が求められます。
従業員との円満な解決を目指す際には、即日解雇をするのではなく、まずはていねいな説明とともに退職勧奨を検討しましょう。おどしたり強要したりすると、労働トラブルに発展することも否定できません。
退職勧奨を行う場合、以下の注意点を心がけることが大切です。
- 本人が納得できるよう、十分な説明を行う
- 強制しないよう、慎重にコミュニケーションをとる
- 退職合意書など、法的に有効な書類を作成する
退職勧奨は、慎重に対応すれば従業員と企業双方にとって最善の選択肢となる場合もあります。適切な手順を踏み、従業員の権利を尊重しながら円満な退職を目指しましょう。