超過勤務手当とは? 残業手当との違いと種類、計算方法を解説
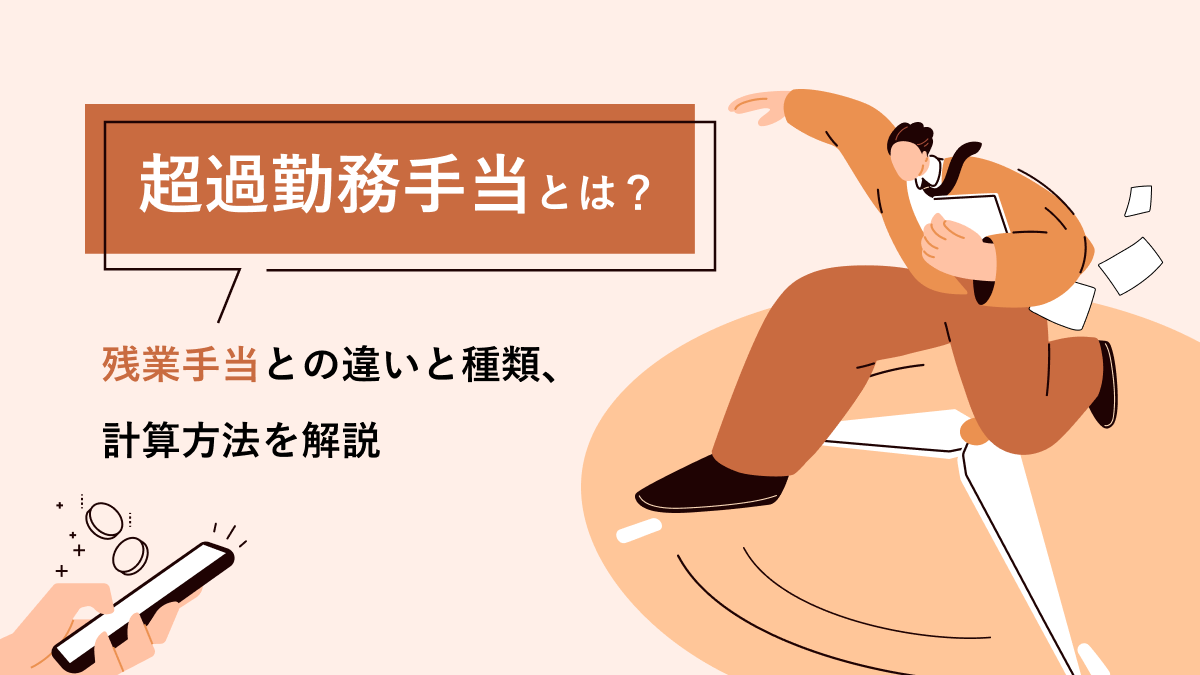
従業員の決められた労働時間を超えて働いた場合、いわゆる超過勤務手当を支払うのは、人事・労務担当者にとってごく日常的な業務です。しかし「超過勤務手当」という言葉、意味や使い方をきちんと説明できますか。
超過勤務手当には、法的な定義があるわけではないため、企業によって運用方法が異なることもあります。一方で、労働基準法が定める「時間外労働に対する割増賃金」のルールは明確で、違反すれば法的リスクも否定できません。
本記事では超過勤務手当の基本や計算方法を、残業手当との違いも交えてわかりやすく解説します。
→給与計算をミスなく速く|「One人事」の資料を無料ダウンロード
 目次[表示]
目次[表示]
超過勤務手当とは?
超過勤務手当とは、労働者が所定労働時間や法定労働時間を超えて、働いたときに支払う割増賃金です。
一般的には「残業代」や「時間外手当」と同じ意味で使われることが多く、一部企業の就業規則にも見られる表現です。
「超過勤務手当」という言葉は法律上の正式な用語ではありません。企業によっては運用ルールや対象範囲が少しずつ異なる場合もあります。
本来は国家公務員の賃金に適用される言葉
もともと「超過勤務手当」は、国家公務員や地方公務員の給与制度で使われる用語です。民間企業でも慣習的に使われることがありますが、国家公務員における超過勤務手当は、『人事院規則15-14』で制度として明確に定義されており、支給基準も明文化されています。
国家公務員の基本の所定勤務時間は、月曜から金曜の週5日間・1日7時間45分で、週38時間45分が基準です。所定時間を超えて勤務した場合や、週休日・休日に勤務した場合に、超過勤務手当が支給されます。
参照:『人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)』e-GOV法令検索
労働基準法に超過勤務手当を定義する条文はない
民間企業に適用される労働基準法には、「超過勤務手当」や「超過勤務」という言葉の定義は出てきません。超過勤務手当はあくまで実務上の呼称であり、使う人や文脈によって意味が異なります。
労働基準法で定義されているのは「時間外労働」と「割増賃金」です。法定労働時間を超えた時間外労働に対して、25%以上の割増賃金を支払う義務があります。
超過勤務手当と割増賃金はほぼ同じ意味
民間企業で使われている「超過勤務手当」は、労働基準法における「時間外労働に対する割増賃金」とほぼ同義と考えてよいでしょう。
割増賃金(超過勤務手当)支払いの有無は、企業の法的責任にもかかわる重要なポイントです。従業員の労働時間を正確に把握し、適切な形式で賃金を支払うことは、労働者の権利を守るうえでも、企業のコンプライアンスを守るうえでも欠かせません。
※本記事では、「所定労働時間を超える労働」と「法定労働時間を超える労働」を両方とも超過勤務手当の対象として、解説を進めていきます。
超過勤務手当と時間外勤務手当、残業手当との違い
超過勤務手当は定義があいまいなため、「時間外勤務手当」や「残業手当」との違いがわからないという方もいるのではないでしょうか。超過勤務手当との違いは以下のとおりです。
| 用語 | 定義 | 割増 | 補足 |
|---|---|---|---|
| 超過勤務手当 | 所定労働時間・法定労働時間いずれかを超えた労働 | 割増賃金の有無は超過時間、企業の運用による | 公務員制度では正式用語だが、民間では定義されていない |
| 時間外勤務手当 | 法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えた労働 | 割増賃金あり | 労働基準法第37条に基づく |
| 残業手当 | 所定労働時間を超えたが、法定労働時間内の労働(法定労働時間を超えた労働も残業手当と呼ぶケースあり) | 割増賃金なし(法定労働時間を超えた場合は割増賃金あり) | 企業独自の就業時間を超えたぶんへの手当 |
▼所定労働時間・法定労働時間について詳しく知るには、以下の記事をご確認ください。
どの時間を基準にしているかによって、同じ超過勤務でも支払い条件や割増率が異なります。
また、「残業」や「残業手当」も、日常的にはよく使われていますが、労働基準法における正式な用語ではありません。
企業によっては、「超過勤務手当」や「残業手当」という法定用語以外を使っている就業規則もありますが、意味や運用が統一されていない場合は、社内での定義を明確にしておくことが重要です。
超過勤務手当の種類
超過勤務手当のなかでも、複数の種類があり、働いた時間帯や労働時間の長さによって、支給の条件や割増率が異なります。
- 法定内残業手当
- 時間外労働手当(時間外勤務手当)
- 深夜手当
- 休日手当
人事・労務担当者としては、「どの勤務に、どの超過勤務手当が発生するのか」を理解しておくことが大切です。
超過勤務手当の主な4種類について、それぞれの特徴と注意点を解説します。
法定内残業手当
法定内残業手当は、所定労働時間を超えて働いたものの、法定労働時間以内に収まっている労働に対して支払われる超過勤務手当です。
たとえば、1日7時間30分が所定労働時間の会社で、8時間勤務した場合、30分が法定内残業にあたります。
法定内残業では、基本的な時給や月給をそのまま適用し、通常の賃金を支給します。
割増率は適用されませんが、未払いは違法となるおそれがあるため注意が必要です。
なお、法定内残業は時間外労働には該当しないため、36協定の締結や届出は必要ありません。
時間外労働手当(時間外勤務手当)
時間外労働手当は、法定労働時間を超えた労働に対して支払う割増賃金です。労働基準法第37条により、時間外労働手当として、25%以上の割増率での支払いが義務づけられています。
月60時間を超える時間外労働が発生した場合は、超過時間に対して50%以上の割増率が適用されます。
また、時間外労働を命じるためには、あらかじめ36協定の締結と労働基準監督署への届出が必要です。
時間外労働の上限時間は原則として月45時間・年360時間までです。特別条項つきでも、以下の範囲内に収めなければなりません。
- 月100時間未満(時間外労働+休日労働)
- 2か月〜6か月のどの月をとっても平均80時間以内(時間外労働+休日労働)
- 年720時間以内
深夜手当
深夜手当は、午後10時から翌5時までの時間帯に働いた場合に支払われる割増賃金です。
労働基準法では通常の賃金に25%以上を上乗せすることが義務とされています。
深夜手当はほかの超過勤務手当と重複して適用される点が特徴です。
たとえば、時間外労働が深夜に及んだ場合は、「基礎賃金(100%)+ 時間外手当(25%)+ 深夜手当(25%)= 150%」の超過勤務手当です。
時給1,000円の労働者が深夜時間帯に時間外労働を1時間行った場合、1,500円の手当が支給されます。
休日手当
休日手当は、休日に働いた場合に支払われる手当ですが、法定休日か所定休日かによって取り扱いが異なります。
法定休日とは、労働基準法第35条で定められた週1日または4週間を通じて4日以上の休日です。一方で、所定休日とは企業が独自に設定した法定休日以外の休日を指します。
所定休日の場合
所定休日に労働した場合、基本的には割増なしで通常の賃金と計算は同じ方法です。ただし、週40時間を超過した時間については、超過勤務手当として25%以上の割増率を適用する必要があります。
月曜から金曜まで1日8時間ずつ働いた労働者が土曜日(所定休日)に出勤した場合、週40時間を超えるため、土曜日の労働時間すべてに対して適用されるのは25%の割増率です。
1日7時間×週5日勤務の企業では、所定休日に5時間働いても週40時間を超えないため、通常賃金での支払いとなります。
法定休日の場合
法定休日に労働した場合は、労働時間の長さにかかわらず、35%以上の超過勤務手当が発生します。
法定休日かつ深夜帯の勤務に該当する場合は、休日手当と深夜手当が重複して支払われるため、合計60%以上の割増率となるケースもあります。
法定休日労働を行わせる場合も、36協定の締結と届出が必要です。
所定休日と法定休日の区別を就業規則で明確にしておくと、適切な休日管理と割増賃金の計算につながり、実務上の混乱を防げるでしょう。
注意!超過勤務手当は重複する
超過勤務手当は、労働の時間帯や曜日によって、複数の手当が重複して支給される場合があります。
基本的な考え方として、まず深夜手当は、常にほかの手当と重複して適用される点がポイントです。深夜手当は「時間帯」に対する規制であるからです。
一方で、時間外手当や休日手当は、労働時間の長さに対する手当であり、重複せずに通常は独立して数えます。
超過勤務手当の主な重複パターンを理解し、ミスのない超過勤務手当の計算につなげましょう。
時間外+深夜労働の場合
時間外労働が深夜22時以降にもおよんだ場合、時間外手当と深夜手当の両方が適用されます。
| 時間外手当(25%)+深夜手当(25%)=50% |
時給2,000円の労働者が深夜に2時間働いた場合、超過勤務は以下のとおりです。
| 2,000円 × 1.5 × 2時間 = 6,000円 |
月60時間を超えた時間外労働は割増率が上がるため、深夜労働も発生すると、さらに高い割増率が適用されます。
| 時間外手当(50%)+ 深夜手当(25%)=75% |
所定休日+深夜労働の場合
所定休日に深夜労働が重なる場合でも、1週間の総労働時間が40時間を超えるかどうかによって、割増率が異なるため労働時間の集計が重要です。
所定休日の労働によって週40時間を超える場合、超過ぶんには時間外手当(25%)が発生します。さらに、労働が深夜時間帯におよぶ場合は、深夜手当(25%)も加算されます。つまり、時間外手当と深夜手当が重複して適用されるのです。
所定休日と深夜労働が重複し、かつ週40時間を超えた場合の超過勤務手当には、以下の割増率が適用されます。
| 時間外手当(25%)+深夜手当(25%)=50% |
一方、週40時間を超えない場合は、時間外手当が発生しません。深夜割増の適用のみとなります。
法定休日+深夜労働の場合
法定休日に働いた場合、休日手当が無条件で発生し、休日労働が22時~翌5時の深夜帯なら、さらに深夜手当も加算されます。超過勤務手当の割増率は以下のとおりです。
| 休日手当(35%)+ 深夜手当(25%)= 60% |
注意点として、休日は暦日単位(0~24時)で数えることです。深夜と休日が重なるのは、法定休日の0~5時、もしくは22時~24時までとなります。
「日曜の22時〜翌1時」に働いた場合、22〜24時は休日+深夜手当、0〜1時は深夜手当のみが適用されると理解しましょう。
ただし、法定休日の深夜労働は、労働者の健康に与える影響が大きいため、企業は慎重な労働時間管理が求められます。
超過勤務手当は分単位で計算!方法は?
超過勤務手当は、労働基準法に基づき、1分単位で正確に計算しなければなりません。
わずか1分であっても、法定時間を超えれば、超過勤務手当の支払い対象です。企業が労働時間を切り捨てて計算することは法律違反です。
超過勤務手当の基本的な計算式は、以下のとおりです。
| 1時間あたりの基礎賃金×割増率×超過勤務時間 |
超過勤務手当の計算は次の3ステップで行います。
- 賃金を時給換算する
- 超過勤務時間を集計する
- 超過勤務手当を計算する
具体例を交え順を追って解説していきます。
1.賃金を時給換算する
超過勤務手当の計算では、まず1時間あたりの基礎賃金を求める必要があります。
月給制の場合は、以下の式で基礎時給と月平均所定労働時間を出します。
| 時給 = 月給 ÷ 月平均所定労働時間 月平均所定労働時間 = (年間暦日数 - 年間休日)× 所定労働時間 ÷ 12 |
基礎賃金に含まれるのは、基本給や役職手当、資格手当など労務提供を前提とした手当です。家族手当・通勤手当・住宅手当・賞与など、個人的事情による手当は基本的に含めません。
月給30万円、月平均160時間を例に挙げると、基礎時給は以下のとおり計算できます。
| 基礎時給=30万円 ÷ 160時間 = 1,875円 |
2.超過勤務時間を集計する
超過勤務時間を、次のような労働の種類ごとに正確に分類して集計していきます。
| 時間外労働 | 1日8時間・週40時間を超えた労働 | 25%以上(月60時間超は50%以上) |
| 休日労働 | 法定休日の労働 | 35%以上 |
| 深夜労働 | 22時~翌5時の労働 | 25%以上 |
複数の労働が重なる場合は、割増を加算して支給します。深夜労働は、そのほかの手当と基本的に重複することになる点に注意が必要です。
3.超過勤務手当を計算する
最後に、1で算出した基礎時給に、2の割増率を掛けて計算します。
たとえば、時間外と深夜の場合、 1,875円 ×(1.25 + 0.25)= 2,343円(150%)です。また、休日と深夜の場合、 1,875円 ×(1.35 + 0.25)= 3,000円(160%)と割増率が高くなります。
超過勤務手当の計算例
所定労働時間は午前9時から午後6時まで(休憩1時間)で、1日8時間勤務、月平均所定労働時間は168時間(21日×8時間)とします。
まず、1時間あたりの基礎賃金を算出します。
- 月給20万円 ÷ 168時間 = 1,190円(基礎時給)
次に、残業時間ごとに割増賃金を計算します。時間外労働は、午後6時~午後10時の4時間です。
- 1,190円 × 1.25 = 1,488円(割増単価)
- 1,488円 × 4時間 = 5,952円
午後10時~午前0時の2時間は深夜の時間外労働となります。
- 1,190円 × 1.50 = 1,785円(割増単価)
- 1,785円 × 2時間 = 3,570円
最後に、それぞれの金額を合算すると、1日あたりの超過勤務手当は以下のとおりです。
- 5,952円(時間外)+ 3,570円(深夜+時間外)= 合計9,522円
以上のように、超過勤務手当は基礎賃金と割増率をもとに、時間帯ごとに分けて正確に計算する必要があります。
超過勤務手当の端数処理
超過勤務手当を計算する際、1時間あたりの賃金や割増賃金に1円未満の端数が出ることがあります。端数は次のように処理することが認められています。
- 50銭未満 → 切り捨て
- 50銭以上1円未満 → 1円に切り上げ
たとえば、1時間あたりの超過勤務手当が「1,234.49円」だった場合は「1,234円」、
「1,234.50円」だった場合は「1,235円」として計算します。
最終的な支給額にも同様の端数処理を適用して構いません。一貫したルールで処理しましょう。
超過勤務手当の計算からは除外する手当
超過勤務手当(いわゆる残業代)を計算する際の基礎賃金には、すべての手当が含まれるわけではありません。なかには、計算対象から除外できる手当もあります。
除外される手当は、労働そのものと直接的な関係が薄く、労働者の個人的な事情に基づいて支給される性質のためです。以下に、代表的な超過勤務手当から外れる手当と、判断ポイントを解説します。
家族手当
家族手当は、労働者の扶養家族数に応じて支給される手当です。配偶者や子どもの人数に応じて金額が変動する家族手当なら、超過勤務手当の基礎から除外できます。たとえば以下のような支給ルールです。
- 配偶者1人+扶養家族2人 → 2万円支給
- 扶養家族1人 → 1万円支給
名称が「配偶者手当」「子ども手当」であっても、家族構成に応じて金額が変わるなら、家族手当として同様に扱います。
ただし、扶養家族の人数にかかわらず、家族手当と称して、労働者全員に一律で支給しているなら、超過勤務手当の基礎賃金から除外できません。
通勤手当
通勤手当は、実費相当額を基準に支給されている場合は、超過勤務手当の基礎賃金から除外可能です。通勤手当は、労働者の通勤交通費の補助として支給されるものです。
一方で、距離や交通手段に関係なく従業員に一律で支給している場合は、実費を超える金額は、割増賃金の算定基礎に含まれます。
たとえば、実費が5,000円なのに一律1万円支給なら、差額5,000円は基礎賃金に含めなければなりません。
住宅手当
住宅手当は、賃貸・持ち家や住宅ローンの有無など、個人の住宅事情に応じて金額が決まるため、超過勤務手当の計算から除外されます。
住宅手当は、住居費を補助する目的で支給されるものです。
個人の状況に応じた支給であれば除外可能ですが、全員に一律支給される住宅手当は対象外となります。
超過勤務手当の計算に含めるかの判断で重要なのは、手当の名称ではなく「支給基準」や「支給実態」です。
臨時賃金
突発的な事由によって、一時的・不定期に支給される賃金は臨時賃金として、超過勤務手当の計算除外対象になります。
臨時賃金の具体例は以下のとおりです。
- 結婚祝い金
- 出産祝い金
- 病気見舞金
- 災害見舞金
- 創業記念品の支給
臨時賃金は予定されていない私的・突発的な支出への対応として支給されるため、超過勤務手当の基礎に含める必要はありません。
ただし、毎年一定の時期に支給される賞与(ボーナス)や業績手当は、定期支給扱いとなり、除外されないため注意しましょう。
別居手当
別居手当は、労働者の個人的事情によって支給の可否が決まるため、超過勤務手当の基礎から除外できます。
別居手当は、会社都合の転勤などで家族と別居せざるを得ない労働者に対して支給される制度です。単身赴任手当や帰省手当と呼ばれることもあります。生活費の増加を補う目的があり、扶養家族の有無などで変動します。
転勤により、家族と離れて生活することになった労働者の特別な事情に基づく手当であり、労働の内容や量とは直接的な関係がないため、超過勤務の計算に含めないのです。
手当が超過勤務手当の計算から除外できるかどうかは、名称ではなく、支給の基準や内容が重要です。個人的な事情に基づいて金額が決まるものは除外対象ですが、全員一律に支給される場合は、基本的に基礎賃金に含める必要があります。
管理職に対する超過勤務手当
管理職への超過勤務手当の支給が必要かどうかは、労働基準法上の「管理監督者」に該当するかどうかによって異なります。
労働基準法では、管理監督者に該当する場合、労働時間・休憩・休日に関する規定の適用が除外されるため、原則として超過勤務手当を支給する義務はありません。
ただし、注意したいのは「管理職」という肩書きがあるだけでは足りないという点です。
管理監督者に該当するかどうかは、以下のような観点から実態を総合的に判断する必要があります。
- 経営方針の決定などに関与する権限を持っているか
- 労働時間の裁量が与えられているか
- 一般社員と比べて待遇面で優遇されているか
以上をを満たしていない場合、たとえ「課長」「マネージャー」といった肩書きがあっても、管理監督者とは認められず、通常の労働者として扱われます。そのため、超過勤務手当を支給しなければなりません。
また、管理監督者であっても、深夜労働(午後10時〜午前5時)に対する割増賃金の支払いは必要です。
従業員に超過勤務を依頼する場合の注意点
従業員に時間外労働や休日労働を依頼する際には、法的な手続きを踏むことはもちろん、健康と安全への十分な配慮も欠かせません。とくに、労働基準法第36条に基づく「36協定」の締結と届け出が必要となります。
時間外労働をさせるためには36協定の締結が必要
法定労働時間を超える労働や、法定休日の勤務を命じるには、まず労使間で36協定を締結し、所轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります。
36協定には、以下の内容を明記しなければなりません。
- 時間外・休日労働を命じる具体的な業務の事由
- 対象となる労働者の範囲
- 延長できる労働時間の上限(1日・1か月・1年)
- 協定の有効期間
通常の36協定で認められる時間外労働の限度は、月45時間・年360時間です。基準を超過して労働させるには、「特別条項つき36協定」の締結が必要となります。
なお、36協定を締結・届出せずに時間外労働や休日労働をさせた場合は、労働基準法第32条(労働時間)および第35条(休日)違反となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があるため注意しましょう。
従業員の健康や安全に配慮する
36協定の範囲内であっても、企業には労働契約法第5条に基づく「安全配慮義務」があります。
超過勤務が増えれば増えるほど、過労死や健康障害のリスクが高まることが指摘されており、企業は従業員の健康を守るための措置を講じる必要があります。
とくに次のような労働時間は「過労死ライン」として注意が必要です。
- 発症前1か月間に100時間超の時間外労働
- 発症前2~6か月間にわたり、月平均80時間超の時間外労働
以上のような労働状況が続くと、脳・心疾患の発症リスクが顕著に高まるとされます。過重労働への対策として、企業には、以下のような取り組みが求められます。
- 労働時間の正確な把握と上限管理
- 勤務間インターバル制度の導入
- 長時間労働者への健康診断・面談
- 適切な人員配置と業務分担の見直し
- 従業員が相談しやすい環境づくり
企業には、法令を守るだけでなく、従業員の健康を守る視点からの時間管理と労務管理が求められます。

まとめ|正しい超過勤務手当の運用が、健全な職場づくりに
超過勤務手当は、労働者の権利を守り、企業が法令を遵守するうえで重要な制度です。
法定内残業手当や時間外手当、深夜手当、休日手当など複数の種類があり、それぞれ割増率や支給要件が異なります。
超過勤務手当を正しく支給するためには、基礎賃金の算出や労働時間の正確な把握が欠かせません。
管理職であっても「管理監督者」に該当しない場合は手当が必要となり、時間外労働には36協定の締結も求められます。
勤怠管理の徹底や健康への配慮も含め、制度を正しく運用することが、健全な職場と企業の信頼性向上につながります。
超過勤務手当の反映をミスなく|One人事[給与]
One人事[給与]は、ミスができない超過勤務手当の反映も、オンライン半自動化できるクラウドツールです。
- 【給与計算】毎月ミスがないか不安
- 【給与明細】紙の発行が面倒
- 【勤怠との照合】勤怠データと一括管理したい
給与計算における課題解決を支援し、担当者の負担を軽減します。さらに勤怠管理システムOne人事[勤怠]と連携すると、勤怠データの取り込みがスムーズになり集計が自動化できます。
One人事[給与]の初期費用や気になる使い心地については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門スタッフが、貴社の課題をていねいにお聞きしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、給与計算をはじめ人事労務の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードいただけます。給与計算をシンプルにして「本来やりたい業務」に集中したい企業は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |
