年間の労働時間の上限・計算方法は? 法改正後のポイントを解説
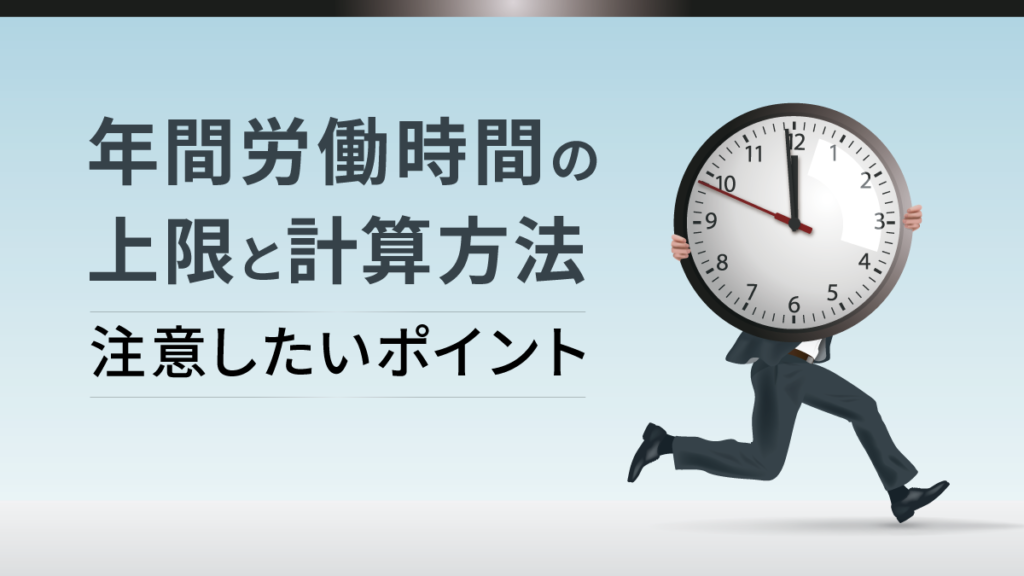
働き方改革や法改正により、年間の労働時間の管理がますます重要になっています。 法定労働時間や時間外労働の上限を理解し、年間の労働時間を正確に計算することが必要です。
本記事では、年間の労働時間の上限や計算方法を具体例と一緒に解説します。計算を効率化するためのツールや、時間外労働の上限規制に対応するポイントも紹介します。
→労働時間の正確な管理に「One人事」製品資料をダウンロード

 目次[表示]
目次[表示]
年間の労働時間を求めるための基礎知識
年間の労働時間を正確に算出するには、法定労働時間や年間休日数、時間外労働の上限など、基本的な要素を理解する必要があります。まずは年間の労働時間を求めるために必要な基礎知識をおさらいします。
労働時間とは
労働時間とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれた時間」であり、「勤務時間-休憩時間」で求められます。
勤務時間とは、従業員が始業してから終業するまでの時間です。勤務時間は休憩時間を含みますが、労働時間は休憩時間を含みません。
| 勤務時間と労働時間の違い | |
|---|---|
| 勤務時間 | 9時間(8時30分〜17時30分) |
| 労働時間 | 勤務時間(9時間)-休憩時間(1時間)=8時間 |
法定労働時間と所定労働時間の違い
労働時間には、「法定労働時間」と「所定労働時間」の2種類があります。
| 労働時間の種類 | |
|---|---|
| 法定労働時間 | 労働基準法によって定められた労働時間の上限 |
| 所定労働時間 | 企業の就業規則によって定められた労働時間 |
法定労働時間とは、労働基準法第32条において定められた労働時間の上限であり、「1日8時間・週40時間」までと定められています。法定労働時間の上限を超えて働くことを「時間外労働」といい、時間外労働をさせる場合は36協定の締結が必要です。
所定労働時間とは、雇用契約書や就業規則などで会社が独自に定める労働時間です。法定労働時間の範囲内で定めなければなりません。
年間労働時間=法定労働時間+時間外労働
年間の労働時間は、1年間の「法定労働時間」と「時間外労働時間」を合算することで計算できます。
| 年間労働時間=1年間の法定労働時間+1年間で発生した時間外労働の時間数 |
週の法定労働時間40時間あるため、1年間の法定労働時間は、およそ「2,085時間」です。
| 1年間の週数 | 365日÷7日=52.14週 |
| 1年間の法定労働時間 | 週40時間×52.14週=2,085時間 |
「2,085時間」に、各月で発生した時間外労働時間を足し算した結果が、年間の労働時間です。

年間の労働時間の上限規制とは? 法改正後に気をつけること
2019年4月より施行された『働き方改革関連法』によって、労働基準法が改正され、長時間労働の是正を目的とした時間外労働の上限規制が適用されています。
法改正後の年間労働時間の上限規制において気をつけたいポイントを解説します。
年間の労働時間=法定労働時間+360時間が上限
年間の労働時間の上限は、年間の法定労働時間と時間外労働の上限時間を足し算することで、算出できます。
| 年間労働時間の上限=1年間の法定労働時間+時間外労働の上限時間 |
従業員に時間外労働をさせる場合、36協定の締結が必要です。ただし、36協定を締結したとしても、時間外労働には「月45時間・年360時間」という上限があります。
つまり、年間の労働時間の上限は、「2,445時間」となります。
| 年間の労働時間の上限(36協定を締結している場合) | |
|---|---|
| 1年間の法定労働時間 | 2,085時間 |
| 時間外労働の上限 | 月45時間・年360時間 |
| 年間労働時間の上限 | 2,085時間+360時間=2,445時間 |
特別条項付きの36協定を締結すると最大年720時間まで延長可能
特別条項付きの36協定を締結すると、年間の時間外労働の上限「360時間」を、最大で「720時間」まで延長できます。
特別条項付きの36協定とは、繁忙期やトラブル対応など臨時的でかつ特別な事情がある場合に、労使間の合意のもと締結できる協定です。締結している場合は、年間の労働時間の上限は「2,805時間」となります。
| 年間の労働時間の上限(36協定の特別条項を締結している場合) | |
| 1年間の法定労働時間 | 2,085時間 |
| 時間外労働の上限時間 | 年720時間 |
| 年間労働時間の上限 | 2,085時間+720時間=2,805時間 |
特別条項付きの36協定には「年間720時間以内」という上限に加えて、以下の制限が定められています。
- 時間外労働が年間720時間以内である
- 時間外労働と休日労働の合計が月に100時間未満である
- 2〜6か月の時間外労働と休日労働の平均時間が1か月あたり80時間以内である
- 時間外労働が月45時間を超えられるのは年に6回まで
上限規制に違反した場合は、労働基準法により6か月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。罰則に加えて、労働基準法や労働安全衛生法に基づいて労働基準監督署の監査が入り、最悪の場合は行政処分の対象となるため注意が必要です。
年間の労働時間の上限内でも適用できる柔軟な働き方
年間の労働時間の範囲内で、従業員に効率よく働いてもらうために、柔軟な働き方の導入を検討しましょう。法定労働時間の弾力的な運用が認められている労働形態を3つ紹介します。
- 変形労働時間制
- フレックスタイム制
- みなし労働時間制
変形労働時間制
変形労働時間制とは、一定期間内の労働時間を平均して「1週間あたり40時間以内」に調整する働き方です。繁忙期には労働時間が長くなり、閑散期に短くなるなど、業務の繁閑や特殊性に応じて柔軟に労働時間を配分できます。
一定期間内(1週間・1か月・1年)の平均労働時間が「週40時間」に収まるのであれば、ある特定の時期は、法定労働時間を超えて働けるのが特徴です。
フレックスタイム制
フレックスタイム制とは、一定期間内の労働時間を設定し、その範囲内で従業員が始業・終業時間、労働時間を自由に決められる制度です。
設定した期間内の平均労働時間が「週40時間」以内である必要があります。仕事と私生活のバランスをとりながら効率的に働けるのが特徴です。
フレックスタイム制は自由度が高いですが、企業(使用者)には従業員の労働時間を正確に管理する義務があります。
参照:『フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き』厚生労働省
みなし労働時間制
みなし労働時間制とは、実際働いた時間に関係なく、事前に労使間で決めた労働時間を働いたとみなして賃金を支払う制度です。
主に「事業場外みなし労働時間制」と「裁量労働制」の2種類があり、裁量労働制はさらに「専門業務型裁量労働制」と「企画業務型裁量労働制」に分けられます。
制度別の働き方の特徴や対象となる職種・業種は、以下のとおりです。
| みなし労働時間制の種類 | 対象職種・業種の例(一部抜粋) | ||
|---|---|---|---|
| 事業場外みなし労働時間制 | 事業場外で労働し労働時間の算定が難しい場合に、原則として所定労働時間分働いたとみなす制度 | ・外回りが多い営業職 ・旅行添乗員 ・在宅勤務/テレワーク | |
| 裁量労働制 | 専門業務型裁量労働制 | 業務の進め方や時間配分を労働者の裁量にゆだねる20の業務について、実労働時間数に関係なく、労使協定で定めた労働時間数を働いたとみなす制度 | ・新商品の研究開発または人文・自然科学の研究 ・記事の取材・編集 ・M&Aアドバイザー ・弁護士 |
| 企画業務型裁量労働制 | 労働者が主体的に技術や企画能力を発揮できる働き方として導入された制度 | ・人事・労務 ・財務・経理 ・広報 | |
参照:『労働時間・休日』厚生労働省
参照:『専門業務型裁量労働制について』厚生労働省
参照:『企画業務型裁量労働制の解説』厚生労働省
年間の労働時間計算に重要な年間休日について
年間の労働時間を正確に計算するには、年間休日の把握が必要です。休日と休暇の違いや年間休日の計算方法を解説します。
休日と休暇の違い
「休日」は労働義務がない日、「休暇」は労働義務が免除された日を指す言葉です。休日はもともと休みであった日であり、休暇は本来労働日であった日を意味します。
法定休日と所定休日の違い
休日には、大きく分けて「法定休日」と「所定休日」の2種類があります。
| 休日の種類 | |
|---|---|
| 法定休日 | 労働基準法第35条で定められた休日 |
| 所定休日 | 法律では規定されていない、企業が独自に設定する休日 |
法定休日とは、労働基準法によって定められた休日です。企業は週に1回もしくは4週に4回の法定休日を設定する必要があります。
所定休日は、法律での規定はなく、企業が独自に設定できる休日です。
1年間を52週とすると、最低でも52日の法定休日の設定をしなければなりません。しかし、52日では法定要件を満たせないため、所定休日を設定します。
年間休日数の決め方
年間の法定労働時間はおよそ2,085時間です。法定労働時間は1日8時間であり、年間労働日数の上限はおよそ「260日」と計算できます。
| 2,085時間 ÷ 8時間 = 260.625日 |
1年の総日数を365日とすると、年間休日の最低ラインは105日です。
| 年間最低休日数=365日−260日= 105日 |
年間休日の日数による休日の設定方法は、以下のパターンが考えられます。
| 年間の休日数 | 年間休日に含まれる休暇 |
|---|---|
| 125日 | 週2日の休み+祝日+夏季休暇や年末年始休暇など |
| 120日 | 週2日の休み+祝日 |
| 110日 | ・週2日の休み+夏季休暇や年末年始休暇など(完全週休2日制) ・日曜日、土曜隔週休み+祝日+夏季休暇や年末年始休暇など(週休2日制) |
| 105日 | 月8〜9日程度の休日(シフト制) |

年間の労働時間計算を効率化するツール
最後に年間の労働時間の計算を効率化するツールを3つ紹介します。
- エクセル
- WEBの計算ツール
- 勤怠管理システム
効率化ツールを利用することで、負担を軽減しつつ、ミスを防げます。正確な労働時間の管理を実現するために、効率化ツールの活用を検討してみましょう。
エクセル
多くの企業が導入している表計算ソフト・エクセルは、コストもかからず導入しやすいツールです。ただし、手入力や計算式の間違いによるミスが発生する懸念があります。
WEBの計算ツール
インターネット上で公開されている年間労働時間や年間休日数を計算できるツールも、労働時間の算出に活用できます。無料で利用できるツールも多く、手軽に導入できるのがメリットです。
ただし入力データをWeb上に保管できないため、別のツールに移す必要があります。移行作業中に、データ形式の不一致や入力ミスが発生するリスクがあります。
勤怠管理システム
勤怠管理システムは、従業員の労働状況を把握し、管理を半自動化するツールです。手作業によるミスを減らし、データが蓄積されていくため、手間が省けます。
アラート機能を活用すれば、年間の労働時間を超える前に、働き方の見直しを促すことができます。
クラウド型の勤怠管理システムなら、スマートフォンでの打刻が可能で、リモートワークや外回り、出張など多様な働き方に適しています。

年間の労働時間の上限を超えないためには?
年間の労働時間の上限規制を意図せず超えないようにするには、管理の半自動化が欠かせません。
勤怠管理システムOne人事[勤怠]は、労働時間の超過アラートを出すなど、法律に沿った労働時間の管理を助けるツールです。
One人事[勤怠]の初期費用や操作性については、当サイトより、お気軽にご相談ください。専門のスタッフが貴社の課題をていねいにヒアリングしたうえでご案内いたします。
当サイトでは、勤怠管理の効率化に役立つ資料を無料でダウンロードしていただけます。勤怠管理をラクにしたい企業の担当者は、お気軽にお申し込みください。
| 「One人事」とは? |
|---|
| 人事労務をワンストップで支えるクラウドサービス。分散する人材情報を集約し、転記ミスや最新データの紛失など労務リスクを軽減することで、経営者や担当者が「本来やりたい業務」に集中できるようにサポートいたします。 |
上限規制を意識して年間の労働時間を正しく計算
年間の労働時間を正確に把握することは、労働基準法に違反するリスクを減らすだけでなく、従業員にとって働きやすい環境づくりにつながります。年間の労働時間の上限規制を正しく理解し、従業員が安心して働ける環境を整備しましょう。
